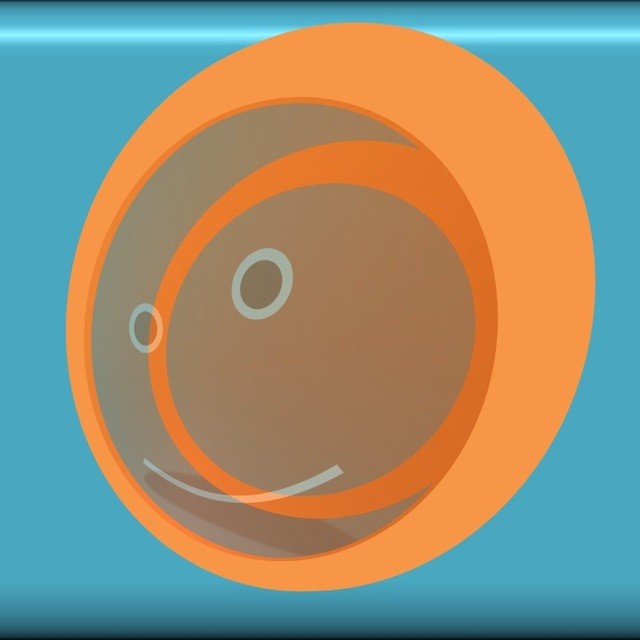第5話:赤い工具箱。
文字数 4,788文字
ミザリイの家から一歩踏み出した先には、鬱蒼 とした森が広がっていた。
おれはつい先日、この森の中から、彼女の家にやって来たと言うのに、圧倒的な森の息吹に今更ながら驚いてしまった。
中々足が前へと進まない。一歩進んで止まり、また一歩進んで止まり周囲を茫然と見渡す。
その様子を、ミザリイはおれよりも少し進んだところで見ていた。
家の周りは切り拓かれ、花壇や小さな小屋、古びた井戸などが点在している。
森の木々は数多の種類が競い合い茂っており、一見ひとつとして同じ種類が無い様にも見えた。
そして、何より目を引かれるのは、恐らく魔獣や幻獣と呼ばれる存在。
人よりも一回り二回り程の巨体を揺らしながら悠然と歩いている獣や、羽も無いのに空中をふわふわと浮かんでいるそれらは、聞くまでも無くそう言った存在なのだろう。
おれに全く関心を抱かないものが多いが、明らかに殺気と感じれる様な威圧感を差し向けてくるものもいて、迂闊に歩みを進める事が出来ない心境でもあった。
この地はミザリイ・アート・ココレイトの支配域なのだから、恐らく全ての魔獣や幻獣は彼女の支配下にあるのだと思う。
そうすると、このおれも、彼女から魔紋を刻まれているのだから、同じ支配下の一員……の筈なのだが、やはり魔が付こうが幻が付こうが獣は獣ということなのだろうか?
力比べとか喧嘩とかをしないと認められない、みたいな少年漫画風の風習があると厄介だと思いつつ、縋る様にミザリイの顔を見た。
「――どうした?やはり、まだ気分が優れんのか?」
彼女はそう言い、おれの方へと歩み寄ってきた。
小さなリスの様なしっぽの長い獣が二匹、彼女の足元をぐるぐると走り回っている。
「いや、気分や体調は大丈夫だと思う。ただ、これは、情けないけれど、おれはビビってるんだ。この世界の現実を目の当たりにして。獣や鳥や魚はおれの世界にも沢山いたけれど、魔獣や幻獣の様な存在は、それこそお伽噺や妄想の世界だけの存在だったからね」
おれがそう言うと、ミザリイは右手を上げ、広げた手を二度三度振る。
すると、すぐにおれに対し威圧的な獣たちは森の中へと消えてしまった。
それらは大型の猪や熊の様にも見えたが、大きな角が生えていたり脚が六本あったりと、何処か普通では無いフォルムをしていた。元居た世界では普通でないと言った方が良いのか。
それこそゲームの中のモンスターの様な、と形容するのが分かりやすいだろうか。
「あやつらは魔獣だ。私が魔紋を刻んでおるから、貴様に対し威嚇はしても危害は加えられん」
「やはり、あれが魔獣なのか。そのミザリイの足元を駆け回ってる小さいやつは?」
「ああ、これは只の獣だ。今はまだな」
「只の獣が、その内、魔獣化するってこと?」
「この地で長く生きておれば、魔獣化するかもしれん。しかし、それはそうなってみねば分からん。さて、どうする?動く気にならんのなら、私ひとりで探索に赴くが?」
彼女からそう言われ、おれは小さくひとつ息を吐いた。
これからこの世界で生きて行かなければならないのに、こんな最初の一歩で躓いていては先が思いやられると、苦い笑みが零れる。
「いや、ついて行くよ。追い払ってくれた魔獣たちとも、その内仲良くならないとな。それで、その辺をふわふわと浮いてる不定形のやつらが幻獣かい?この地に転生して来た時は気が付かなかったけどな」
おれは話ながら、幻獣とおぼしきものへと手を伸ばした。
触れると、特に感触も無く形を変えふたつに分かれて、暫くするとまたひとつへと戻った。
宙を浮くスライムの様な印象だった。
「幻獣を目視出来る様になったのは、魔紋の影響だろうな。しかし、貴様の場合、人間にしては基礎魔力が高い故に、その内見える様にはなっておったと思う。それらが幻獣か魔獣か、只の獣かという見分けも、その内に自ずと出来る様になるだろう。では、行くぞ?」
そう言うとミザリイはきゅっと踵を返し森の方へと歩いて行った。
おれはその後を小走りで追いかける。
魔紋を刻まれて、恐らく基礎魔力が向上した、ということなのだろう。
身体の抵抗力も向上しているだろうから、森への同行も許可してくれているのだろうし。
しかし、漫画やアニメの様にチート的な能力は付与されて無い様に感じる。
異世界転移をする時に、例えば神様的な存在が関与していれば、たとえこの世界で死んでしまっても、何等かまた救いの手が差し伸べられるかもしれないが、おれの場合はどちらかと言えば異世界召喚だから、ご都合主義の神様は関与してくれないだろう。
要するに、極力死の危険からは遠ざかなければならないということだ。
そんな事は元の世界でも当然なのだけれど、それを改めて認識させられると言うか、肝に銘じなければならない。より一層。
ミザリイは、細い獣道へと進んで行った。
おれはこの道を通って来た筈なのだが、あまり記憶に無い。
そうだ、あの時は目の前を行く金髪の魔女に見惚れて周囲を余り見て無かった。
彼女は深い森をするすると進んで行く。
そんな彼女のあとを時折小走りになりつつ、おれは追いかけた。
とにかくペースが速い。普通に歩いていてはすぐに置いていかれてしまう。
朝と夕、毎日森を散策していると言っていたから、森歩きに慣れているのは分かるが、それにしても足が速い。
走っている様には見えないが、その動作に無駄がなく茂みにも躊躇なく踏み込んで行くので、一動作毎に比較的都会人のおれは遅れてしまうのだ。
それでも懸命に、蔓草や枝葉を払いながら進んで行くと、突然目の前が拓けた。
おれは勢い良く、その拓けた場所へと踊り出る。
小さな空き地だった。
半径三十メートルくらいか。直線で五十メートルあるか無いか程度の空き地だ。
ミザリイはその概ね中央辺りで、地面を眺めつつぶつぶつと呟いている。
地面に生えている雑草が所々焦げて灰化していた。
おれを転移、もしくは召喚させた時の名残りだろうか?
ゆっくりと歩き、彼女へと近づく。そして声を掛けた。
「――ここに魔法陣を描いて、それでおれが転移された、ってこと?」
緩やかな風が吹き、頬を撫でてゆく。
ミザリイの真っ黒なローブもはたはたと靡いていた。
「うむ、ここに魔法陣を描いた。他に類を見ぬ程難解な魔法陣でな、描き始めから丸々三日も要した。今考えてみると、その異常性に何故気が付かなかったのか?と、思うてな……。あの古文書自体に、何やらその手の呪いの様な術が仕込まれていた可能性は拭えんなあ、と。そうであれば、貴様の異世界転移は仕組まれていた可能性も出てくる。そうで無い事を願うが、調べてみる価値はあるかもな」
少し険しい表情で、彼女はそう言った。
正義感の強い人だから、そう言った悪巧みは許せないのだろう。そして、恐らくそれに乗せられてしまった自分の事も。
「まあ、確かに、誰かに仕組まれていたのなら、ちょっとタチが悪いね。で、恐らく赤い工具箱もこの辺りに落ちてるってこと、だよな?」
おれは嫌な空気を払拭すべく、明るく大きな声を発していた。
偶然にせよ必然にせよ、今ここにおれがいるのは、キミのせいでは無いから、と思いを込めて。
「ああ、そうだな。いや、もう大体の当たりはついておる。魔獣どもからの情報でな。貴様の持ち物故、貴様同伴で拾いに来た方が良いだろうと思っておったのだ」
「へえ、そうなんだ?それってさ、やっぱり、ミザリイは魔獣とか幻獣と会話が出来るってこと?」
「会話と言うか、意思の疎通だな。今貴様としておる魔力疎通となんら変わらんよ。あと、それと、魔紋を刻んだ相手の五感を共有することが出来る」
そう言うと、ミザリイは歩き出した。今度はゆっくりとしたペースで。
「五感を共有って、要するにおれが見てる映像をさ、全く同じものをミザリイも観れるってこと?」
「簡単に言うと、そう言うことだ。やはり、貴様は飲み込みが早いな。ひとつ言えばふたつ、みっつと理解しよる」
「いや、だからさ、そう言う設定ってよくあるんだよ。今更ながら我が世界の空想作家には感動するなあ。作家さんたち、こっちの世界に来たら歓喜のあまり号泣しちゃうんだろうなあ」
「ふむ、その件に関しても一応マグナラタンと報告しておかなければならんかもな。貴様の世界の空想や妄想とやらは、この世界に通じすぎておる。こちらからあちらへと転移した者がおらんとは断言出来んからな。貴様と同様に何等かの事情で、意に反して異世界転生が繰り返されておるのなら、マグナラタンどころか全ての英知を結集してでも解決せねばならん問題だ。と、まあ、それはさて置き。ほれ、その大樹のうねった根のところに赤い工具箱があるであろう?」
ミザリイはぴたりと足を止め、指差していた。
確かに、太い木の根に隠れる様に赤い工具箱が置いてある。
転生の瞬間に弾き飛ばされてここまで飛んで来たのだろうか?それとも魔獣か幻獣が運んでここまで持って来た?
いやいや、兎に角、おれは同じ世界からやって来た赤い工具箱を見て涙が出る程歓喜した訳だ。
そして、木の根を飛び跳ねる様に近づき手を伸ばした。
「お、おい?迂闊に触れるなよ?いや、やはり待て、先に私が……」
ミザリイの声は確かに耳に入っていた。いや、魔力疎通だから脳に響いていたと言うべきか。
しかし、おれは伸ばした手を止める事が出来なかった。
だって触れて拾わないと持って帰れないから、そう思って。
安易に伸ばした手が、赤い工具箱に触れる。
その刹那!
工具箱はばちばちと大きな火花をあげ、そして轟々と音を立て強烈な赤い光を発した。
そして、触れても無い鍵が外れ、ばっかりと開いた工具箱から業火が噴き出してきた。
一瞬にして辺り一面は炎の海となる。
間近で業火噴出に巻き込まれたおれは、火だるまとなり後方へと吹き飛んだ。
頭の中が真っ白になった。
火に焼かれてる熱さよりも、自分の身体が燃えていると言う事実に驚き、恐怖のあまり絶叫を上げていた。
地面をごろごろと転がるが全く火が消える気配が無い。
それどころか、動けば動くほど火の勢いが増している様に見えた。
これは、もう駄目だと思った。
死の危険から出来るだけ遠ざからなければ、と肝に銘じたばかりなのに……と、悔やんでも悔やみきれない思いがこみ上げて来る。
ミザリイはどうなった?彼女は無事か?と思うが、立ち上がる事も、目を開ける事も出来なかった。
自身の血肉が焼ける音と匂いに絶望を感じ、死を覚悟する。
ばたばたと暴れるのを止めると、脱力感に包まれた。
「――ヨウスケ!しっかりしろ!今助けてやる!」
ミザリイの声が聞こえた様な感覚があった。
多分、彼女は魔女だから、なんとかなったのだろう。
いや、自分の過ちに彼女が巻き込まれて死ぬ様な事だけは避けたかった。
それだけは、絶対に、駄目だと。
そして。
意識が薄れゆく、その間際、左肩の魔紋から冷たい水が噴き出している様な感覚があった。
もう既に虫の息なのだと思う。
生きているのか死んでいるのか、分からない様な虚ろな感覚。
しかし、左肩の魔紋は徐々にその存在感を強めてゆく。
それを感じつつ、もしかしたら、ミザリイが、何とかしてくれるのかもしれないなあ、と思っていた。
おれは藁にも縋る思いで、淡い希望の光へと手を伸ばした。
けれど、そこで意識は、暗い闇へと落ちていった。
第2章
この世界の現在。
END
おれはつい先日、この森の中から、彼女の家にやって来たと言うのに、圧倒的な森の息吹に今更ながら驚いてしまった。
中々足が前へと進まない。一歩進んで止まり、また一歩進んで止まり周囲を茫然と見渡す。
その様子を、ミザリイはおれよりも少し進んだところで見ていた。
家の周りは切り拓かれ、花壇や小さな小屋、古びた井戸などが点在している。
森の木々は数多の種類が競い合い茂っており、一見ひとつとして同じ種類が無い様にも見えた。
そして、何より目を引かれるのは、恐らく魔獣や幻獣と呼ばれる存在。
人よりも一回り二回り程の巨体を揺らしながら悠然と歩いている獣や、羽も無いのに空中をふわふわと浮かんでいるそれらは、聞くまでも無くそう言った存在なのだろう。
おれに全く関心を抱かないものが多いが、明らかに殺気と感じれる様な威圧感を差し向けてくるものもいて、迂闊に歩みを進める事が出来ない心境でもあった。
この地はミザリイ・アート・ココレイトの支配域なのだから、恐らく全ての魔獣や幻獣は彼女の支配下にあるのだと思う。
そうすると、このおれも、彼女から魔紋を刻まれているのだから、同じ支配下の一員……の筈なのだが、やはり魔が付こうが幻が付こうが獣は獣ということなのだろうか?
力比べとか喧嘩とかをしないと認められない、みたいな少年漫画風の風習があると厄介だと思いつつ、縋る様にミザリイの顔を見た。
「――どうした?やはり、まだ気分が優れんのか?」
彼女はそう言い、おれの方へと歩み寄ってきた。
小さなリスの様なしっぽの長い獣が二匹、彼女の足元をぐるぐると走り回っている。
「いや、気分や体調は大丈夫だと思う。ただ、これは、情けないけれど、おれはビビってるんだ。この世界の現実を目の当たりにして。獣や鳥や魚はおれの世界にも沢山いたけれど、魔獣や幻獣の様な存在は、それこそお伽噺や妄想の世界だけの存在だったからね」
おれがそう言うと、ミザリイは右手を上げ、広げた手を二度三度振る。
すると、すぐにおれに対し威圧的な獣たちは森の中へと消えてしまった。
それらは大型の猪や熊の様にも見えたが、大きな角が生えていたり脚が六本あったりと、何処か普通では無いフォルムをしていた。元居た世界では普通でないと言った方が良いのか。
それこそゲームの中のモンスターの様な、と形容するのが分かりやすいだろうか。
「あやつらは魔獣だ。私が魔紋を刻んでおるから、貴様に対し威嚇はしても危害は加えられん」
「やはり、あれが魔獣なのか。そのミザリイの足元を駆け回ってる小さいやつは?」
「ああ、これは只の獣だ。今はまだな」
「只の獣が、その内、魔獣化するってこと?」
「この地で長く生きておれば、魔獣化するかもしれん。しかし、それはそうなってみねば分からん。さて、どうする?動く気にならんのなら、私ひとりで探索に赴くが?」
彼女からそう言われ、おれは小さくひとつ息を吐いた。
これからこの世界で生きて行かなければならないのに、こんな最初の一歩で躓いていては先が思いやられると、苦い笑みが零れる。
「いや、ついて行くよ。追い払ってくれた魔獣たちとも、その内仲良くならないとな。それで、その辺をふわふわと浮いてる不定形のやつらが幻獣かい?この地に転生して来た時は気が付かなかったけどな」
おれは話ながら、幻獣とおぼしきものへと手を伸ばした。
触れると、特に感触も無く形を変えふたつに分かれて、暫くするとまたひとつへと戻った。
宙を浮くスライムの様な印象だった。
「幻獣を目視出来る様になったのは、魔紋の影響だろうな。しかし、貴様の場合、人間にしては基礎魔力が高い故に、その内見える様にはなっておったと思う。それらが幻獣か魔獣か、只の獣かという見分けも、その内に自ずと出来る様になるだろう。では、行くぞ?」
そう言うとミザリイはきゅっと踵を返し森の方へと歩いて行った。
おれはその後を小走りで追いかける。
魔紋を刻まれて、恐らく基礎魔力が向上した、ということなのだろう。
身体の抵抗力も向上しているだろうから、森への同行も許可してくれているのだろうし。
しかし、漫画やアニメの様にチート的な能力は付与されて無い様に感じる。
異世界転移をする時に、例えば神様的な存在が関与していれば、たとえこの世界で死んでしまっても、何等かまた救いの手が差し伸べられるかもしれないが、おれの場合はどちらかと言えば異世界召喚だから、ご都合主義の神様は関与してくれないだろう。
要するに、極力死の危険からは遠ざかなければならないということだ。
そんな事は元の世界でも当然なのだけれど、それを改めて認識させられると言うか、肝に銘じなければならない。より一層。
ミザリイは、細い獣道へと進んで行った。
おれはこの道を通って来た筈なのだが、あまり記憶に無い。
そうだ、あの時は目の前を行く金髪の魔女に見惚れて周囲を余り見て無かった。
彼女は深い森をするすると進んで行く。
そんな彼女のあとを時折小走りになりつつ、おれは追いかけた。
とにかくペースが速い。普通に歩いていてはすぐに置いていかれてしまう。
朝と夕、毎日森を散策していると言っていたから、森歩きに慣れているのは分かるが、それにしても足が速い。
走っている様には見えないが、その動作に無駄がなく茂みにも躊躇なく踏み込んで行くので、一動作毎に比較的都会人のおれは遅れてしまうのだ。
それでも懸命に、蔓草や枝葉を払いながら進んで行くと、突然目の前が拓けた。
おれは勢い良く、その拓けた場所へと踊り出る。
小さな空き地だった。
半径三十メートルくらいか。直線で五十メートルあるか無いか程度の空き地だ。
ミザリイはその概ね中央辺りで、地面を眺めつつぶつぶつと呟いている。
地面に生えている雑草が所々焦げて灰化していた。
おれを転移、もしくは召喚させた時の名残りだろうか?
ゆっくりと歩き、彼女へと近づく。そして声を掛けた。
「――ここに魔法陣を描いて、それでおれが転移された、ってこと?」
緩やかな風が吹き、頬を撫でてゆく。
ミザリイの真っ黒なローブもはたはたと靡いていた。
「うむ、ここに魔法陣を描いた。他に類を見ぬ程難解な魔法陣でな、描き始めから丸々三日も要した。今考えてみると、その異常性に何故気が付かなかったのか?と、思うてな……。あの古文書自体に、何やらその手の呪いの様な術が仕込まれていた可能性は拭えんなあ、と。そうであれば、貴様の異世界転移は仕組まれていた可能性も出てくる。そうで無い事を願うが、調べてみる価値はあるかもな」
少し険しい表情で、彼女はそう言った。
正義感の強い人だから、そう言った悪巧みは許せないのだろう。そして、恐らくそれに乗せられてしまった自分の事も。
「まあ、確かに、誰かに仕組まれていたのなら、ちょっとタチが悪いね。で、恐らく赤い工具箱もこの辺りに落ちてるってこと、だよな?」
おれは嫌な空気を払拭すべく、明るく大きな声を発していた。
偶然にせよ必然にせよ、今ここにおれがいるのは、キミのせいでは無いから、と思いを込めて。
「ああ、そうだな。いや、もう大体の当たりはついておる。魔獣どもからの情報でな。貴様の持ち物故、貴様同伴で拾いに来た方が良いだろうと思っておったのだ」
「へえ、そうなんだ?それってさ、やっぱり、ミザリイは魔獣とか幻獣と会話が出来るってこと?」
「会話と言うか、意思の疎通だな。今貴様としておる魔力疎通となんら変わらんよ。あと、それと、魔紋を刻んだ相手の五感を共有することが出来る」
そう言うと、ミザリイは歩き出した。今度はゆっくりとしたペースで。
「五感を共有って、要するにおれが見てる映像をさ、全く同じものをミザリイも観れるってこと?」
「簡単に言うと、そう言うことだ。やはり、貴様は飲み込みが早いな。ひとつ言えばふたつ、みっつと理解しよる」
「いや、だからさ、そう言う設定ってよくあるんだよ。今更ながら我が世界の空想作家には感動するなあ。作家さんたち、こっちの世界に来たら歓喜のあまり号泣しちゃうんだろうなあ」
「ふむ、その件に関しても一応マグナラタンと報告しておかなければならんかもな。貴様の世界の空想や妄想とやらは、この世界に通じすぎておる。こちらからあちらへと転移した者がおらんとは断言出来んからな。貴様と同様に何等かの事情で、意に反して異世界転生が繰り返されておるのなら、マグナラタンどころか全ての英知を結集してでも解決せねばならん問題だ。と、まあ、それはさて置き。ほれ、その大樹のうねった根のところに赤い工具箱があるであろう?」
ミザリイはぴたりと足を止め、指差していた。
確かに、太い木の根に隠れる様に赤い工具箱が置いてある。
転生の瞬間に弾き飛ばされてここまで飛んで来たのだろうか?それとも魔獣か幻獣が運んでここまで持って来た?
いやいや、兎に角、おれは同じ世界からやって来た赤い工具箱を見て涙が出る程歓喜した訳だ。
そして、木の根を飛び跳ねる様に近づき手を伸ばした。
「お、おい?迂闊に触れるなよ?いや、やはり待て、先に私が……」
ミザリイの声は確かに耳に入っていた。いや、魔力疎通だから脳に響いていたと言うべきか。
しかし、おれは伸ばした手を止める事が出来なかった。
だって触れて拾わないと持って帰れないから、そう思って。
安易に伸ばした手が、赤い工具箱に触れる。
その刹那!
工具箱はばちばちと大きな火花をあげ、そして轟々と音を立て強烈な赤い光を発した。
そして、触れても無い鍵が外れ、ばっかりと開いた工具箱から業火が噴き出してきた。
一瞬にして辺り一面は炎の海となる。
間近で業火噴出に巻き込まれたおれは、火だるまとなり後方へと吹き飛んだ。
頭の中が真っ白になった。
火に焼かれてる熱さよりも、自分の身体が燃えていると言う事実に驚き、恐怖のあまり絶叫を上げていた。
地面をごろごろと転がるが全く火が消える気配が無い。
それどころか、動けば動くほど火の勢いが増している様に見えた。
これは、もう駄目だと思った。
死の危険から出来るだけ遠ざからなければ、と肝に銘じたばかりなのに……と、悔やんでも悔やみきれない思いがこみ上げて来る。
ミザリイはどうなった?彼女は無事か?と思うが、立ち上がる事も、目を開ける事も出来なかった。
自身の血肉が焼ける音と匂いに絶望を感じ、死を覚悟する。
ばたばたと暴れるのを止めると、脱力感に包まれた。
「――ヨウスケ!しっかりしろ!今助けてやる!」
ミザリイの声が聞こえた様な感覚があった。
多分、彼女は魔女だから、なんとかなったのだろう。
いや、自分の過ちに彼女が巻き込まれて死ぬ様な事だけは避けたかった。
それだけは、絶対に、駄目だと。
そして。
意識が薄れゆく、その間際、左肩の魔紋から冷たい水が噴き出している様な感覚があった。
もう既に虫の息なのだと思う。
生きているのか死んでいるのか、分からない様な虚ろな感覚。
しかし、左肩の魔紋は徐々にその存在感を強めてゆく。
それを感じつつ、もしかしたら、ミザリイが、何とかしてくれるのかもしれないなあ、と思っていた。
おれは藁にも縋る思いで、淡い希望の光へと手を伸ばした。
けれど、そこで意識は、暗い闇へと落ちていった。
第2章
この世界の現在。
END