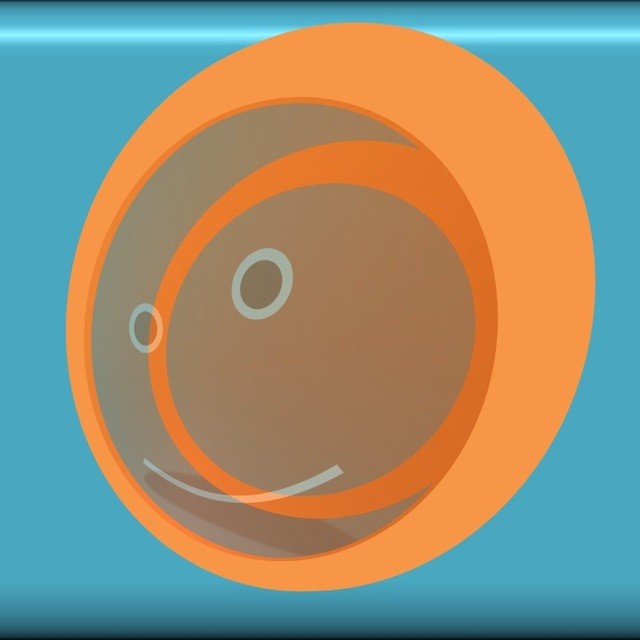第4話:緋色の魔女と漆黒の魔女。
文字数 4,989文字
緋色の魔女、と呼ぶべきだろうか。
おれがこの世界で二番目に会った人物は、暫く微動だにせずにこちらへと視線を向けていた。
頭の先から足元まで、値踏みをする様に見ている。
そして、何やら聞き慣れない言語でミザリイに語り掛けていた。
この世界の言語なのだろう。当然一言一句たりとも理解出来なかった。
何となく、そわそわとしてしまう。
街中で、いきなり外国人二人組に話しかけられた時の様な、と表現するのが妥当だろうか。
これが例えば英語であれば、流暢な会話は出来なくとも単語だけでそれなりに乗り切れるかもしれない。
相手が中国人であればメモ帳に筆談でそれなりに意思疎通が図れるかもしれない。
しかし、相手がアラビア語やスワヒリ語の様な聞くにも書くにも全く馴染みの無い言語の国の出身だと、身振り手振りでコミュニケーションをとるしかない。
言わばお手上げに近い状態だ。
同じ地球に住んでいても、そうなってしまうのだ。これが、異世界に来て目の前で繰り広げられているのだから、お手上げ以上にどうしようもない状況だった。
異世界人とは言え、美しい女性二人を相手にもじもじと時を過ごすのは、正直性分では無いが、訳も分からずにお茶らけてドン滑りするのも、これまた性分でない。
そうして、暫く居心地の悪い空気に晒されて、漸くミザリイがおれへと視線を向けてくれた。
「――ああ、すまない。カーリーよ、魔力疎通を使ってくれ。この者はこの世界の言語を全く理解しておらんのだ。と、その前に、部屋に入ったのだから、まずは帽子とローブを取らんか、この無礼者めが」とミザリイ。
おれを相手に話す時よりも随分とキツイ口調で、カーリーと呼んだ魔女へ言い放っていた。
「へえ、この世界の言語は分からないのに、魔力疎通は使えるのかい?それは中々面白い存在だねえ。ミザリイが人間に魔紋を刻んだと言うから、どんな奴かと思って駆けつけた訳だけど」
カーリーは、ミザリイからの叱責を受けてもも悪びれる事無く、飄々とした態度で語り、緋色の帽子とローブを脱ぎ去った。
そしてそのまま床へと投げ捨てる。
それを見て、ミザリイは溜息をひとつ零して帽子とローブを拾い上げていた。
それぞれの人間性が垣間見える瞬間だった。
優等生と不良だけど幼馴染みで仲が良いみたいな、そういう関係性なのかもしれない。
「それで、アンタ、名前はなんてんだい?」と、カーリーは腕組みをしてそう言った。
ミザリイと同じくローブの下は黒いワンピースだけと言う格好だった。
しかし、彼女の場合少女の様な身体付きでは無く、鍛え上げられたアスリートの様な体型だった。
魔女と言うよりか、女戦士や海賊の様と表現した方がしっくりと来る。
「アダチ、ヨウスケだ。貴女のことは、カーリーと呼べばいいのかな?」
「ああ、それでいいよ。魔女名はカーリー・ラーク・フュールってんだけどね。それにしても――」
カーリーはそこで言葉を止め、改めておれの事を観ていた。そして続ける。
「私とミザリイを目の前にして、全く怯む感じが無いね。普通の人間が、こんな密室に閉じ込められてたら、魔女の魔力で頭がおかしくなっても不思議じゃあ無いってのにさ。如何に魔紋刻んだとは言え、昨日の今日なんだろう?」
彼女はおれの事を見詰めながら話していたが、文脈からミザリイに向けた発言だと思った。
「ふむ、それに関しては、私も魔紋を刻み繋がって漸く分かったのだが、この者は魔力耐性が極めて高い。あと、魔導具無しで魔力疎通が出来るのか、と思っておったのだが、どうやら左腕の時計とやらが魔導具として作用しておるようだ」
ミザリイはそう言って、腕時計を指さした。
そんなこと初耳だぞ、と思いつつおれは左手を上げて魔導具化したと言う腕時計を眺め見た。
どこか様子が変わっている訳では無い。チクタクと異世界でも変わらずに時を刻んでくれている。
「よ、要するに、異世界転移をした時に、普通の道具から魔導具化した、ってこと?」
「その可能性はある。が、異世界転移は関係無く、貴様の世界にある道具の全てが、こちらの世界では魔導具として使えるのかもしれん。それは定かでは無いし、現状それを追及する術も無い。いや、しかし、どちらにせよ、その時計が魔導具である事には変わらん」
おれとミザリイのやり取りをカーリーは大人しく聞いていたが、ふと何かを思いついたのか「あ!」と大きな声を上げた。
そして、大股でおれへと近づきべたべたと遠慮の無い手つきで作業着に触れてきた。
「じゃあさ、この薄汚れた服も魔導具ってことかい?」
カーリーからそう言われ、おれはミザリイの顔を見た。
この金髪の魔女が全てを把握してる訳で無い事は承知しているが、それでも何かそれなりの答えや案を出してくれるとおれはいつの間にやら信頼してしまっているのだ。
「恐らく、そうであろう。しかし、その効果や作用の程は今すぐには分からん。魔導具とは、基本的に用途を明確にして作成する物故にな、得体の知れぬ魔導具にいきなり魔力を注ぐのは愚の骨頂。貴様が異世界から持ち込んだ物は、古代遺跡から発掘された魔導具と同じ様な調査や鑑定をする必要があるだろう……なっ!」
ミザリイはそう言いつつ、手を伸ばしカーリーの左耳を抓り引っ張った。
「い、痛い、痛い。分かったから、余計なことはしないから」
カーリーは情けない声を上げ、おれから引き摺り離される。
恐らく、作業着に魔力を注ぎ込もうとしていたのだろう。
調査とか鑑定とか面倒くさいだろう?的な安易な考えで。
「本当に、油断も隙もあったものでは無い。貴様の火の魔力を注ぎ込んで、万が一この作業着とやらが魔力増幅の魔導具であったらどうするつもりなのだ?辺り一面火の海に包まれる可能性があると、考えが付かんのか?浅はかにも程がある。ほれ、もう用が無ければとっと立ち去れ。そして他の魔女にも伝えておけ。当分は誰も私の支配域には立ち寄るな、とな。この男の心身の安全確保と魔導具の調査鑑定が済むまでは、マグナラタンに連れて行く気も無いからな」
そう言うと、ミザリイは抱えていた緋色の帽子とローブをカーリーへと押し付け、扉の外へと追い出してしまった。
そして、そのままミザリイ諸共外へ出て行ってしまう。
あからさまに、扉の外で何やら密談していると分かる状況。
何だかんだ言いつつも魔女同士でおれには聞かれたく無い事もあるのだろう。
しかし、別に外に出て行かなくとも、この世界の言葉で会話されたらおれには何も分からないのだけれど、と思うと笑みが零れてくる。
暫くして、ミザリイはするりと音も無く戻ってきた。
おれは立ったまま待ち惚けるのも馬鹿らしいと思い、椅子に座って腕時計をつぶさに観察していた。
じっくりと見れば何処かに変化を見つけれるかもしれない、と思ったのだが、そもそもそこまでじっくりと観察したことが無いので、それらしい何かを見つける事は出来なかった。
「――おかえり。カーリーは大人しく帰ってくれたかい?」
そう声を掛けると、ミザリイは薄らと苦い笑みを浮かべていた。
そして、まるで決められた作業の様に湯を沸かし茶の準備をする。
「あやつにしたら、大人しく帰ってくれた方だと思う。恐らくあのまま追い返したら今後も色々とちょっかいを出して来るのは分かり切っておったのでな、貴様の心身の安全が確保出来た時点でマグナラタンより先にカーリーの支配域へと貴様を連れて行くと、約束をしておいた」
多分、それは嘘ではないのだろう、と思った。
他にも色々と算段はしているのかもしれないが、それを根掘り葉掘り探りを入れるべきではない、今は。
「あのさ、ミザリイ?さっきは言わなかったんだけど――」
「ああ、いや、貴様の言いたい事は分かっておる。赤い工具箱の事であろう?」
彼女は木の器に茶を注ぎつつそう言う。
やはり、察しもいいし頭もいい。
「おれは別にカーリーの事を悪くは思って無いけど、まだ伏せて置いた方が良いかと思って」
「その判断は間違っておらん。あやつは敵では無いが、調子に乗ると手が付けられんからな。知らんで良い事は知らんで良いのだ。工具箱の中には、何やら色々と道具が入っておる、と言うことなのだろう?」
ふたり同じ様なタイミングで茶を啜りつつ会話をしていた。
お洒落な隠れ家的カフェで優雅に寛いでいる様な気分になってしまう。
「ああ、入ってるよ。おれの世界で言うところの偉大な魔法使いの様な人の工具箱だからさ、年季の入った素晴らしい道具が沢山あると思う」
「それは要するに、貴様の所有物では無い、と言うことか?」
「そうなんだよ。おれの師匠みたいな人の道具箱。ミザリイで言うと図書館の館長の魔導具ってことかな?」
「なるほど、な。それはおいそれとは使えんな。何処かに封印してしまうか?師匠の魔導具を断りも無しに使用するなど、想像しただけで血の気が引く思いがする」
ミザリイのこういう発言を聞くと、何だか癒される心地になってしまう。
間違いなく堅物だけれど、どこか可愛らしい一面もあるのだ。そのギャップは、彼女の大きな魅力のひとつなのだろう。
「いや、元の世界なら、本当においそれとは使えないんだけど、この世界にいるなら使っても怒られないと思う。今考えたら、あのタイミングで工具箱を取りに行かせてくれたのは奇跡だと思うし。いや、まだ実際、手元に無いしさ、あったとてそれが魔導具かどうかも分からない状態だけど、心の拠り所になる事は間違いないだろうし」
おれはそう言いい、茶を飲み干した。
それを見て、ミザリイも同様に器を空ける。
申し合わせた訳では無いが、これが工具箱を探しに出かけるタイミングなのだろうと、感じていた。
「――ヨウスケよ、身体の具合はどうだ?」
ミザリイはおれの目を見詰めながらそう言った。
相変わらず表情は乏しいが、出会った時より若干柔和である様に見える。これも魔紋を刻んだ影響なのだろうか?
「ああ、随分と楽になったよ。今から森で工具箱を探すんだろう」
「うむ、そうだな。いつまでも得体の知れぬ魔導具を支配域に放置しておく事は出来んし。体調が良いなら貴様を連れて行きたいと考えておるが、どうだ?」
「勿論、ついて行くさ。師匠の大切な工具箱だからな、人任せには出来ない。それに、この世界を観てみたいしな。転移して直ぐは、まさか自分が異世界に来てるとは思いもしなかったからさ」
そう言いおれは飲み干した器を逆さにして置いた。
確かお代わり無用とか、飲み干した合図だったはず。
何処の文化か覚えて無いが一時仲間内でそれが流行った事があった。
この時は、何となく気分が高揚して咄嗟にやってしまっただけ、なのだが。
「その、器を逆さにするのは、何か意味があるのか?」と、当然興味心オバケのミザリイは質問を投げかけてくる。
「ああ、これはもう茶はいらないぜってこと。そろそろ帰るとかさ、宴をお開きにしようとか、そう言う感じかな」
それがあってるかどうかなんて今は調べようが無い。
元の世界にいたらスマホで調べたりするのだろうけれど。
「ふむ、なるほど。しかし、やはり貴様のいた世界の風習やら文化は興味深いな。確かに、器をひっくり返せばもう茶は注げん。いちいち帰る旨を告げる必要も無いということか」
ミザリイはそう言うと、自分の器もひっくり返して置いていた。
それは彼女の何気ない行動のひとつだった訳だが、おれの心に温かな火を灯してくれたのだ。
異世界に来て、学ぶ事ばかりで圧し潰されそうだと感じていたが、逆におれから教えたり伝えれる事も多くあると、気付かされた一瞬でもあった。
そんなおれの事など気に掛ける事も無く、彼女は森を探索するべく、真っ黒な鍔の広い帽子を目深に被り、丈長のローブを身に纏っていた。
カーリーを緋色の魔女と例えるなら、ミザリイは漆黒の魔女と言ったところか。
「――では、行くぞ、ヨウスケ。着いて参れ」
彼女はそう言うと、扉を開け外へと踏み出した。
おれがこの世界で二番目に会った人物は、暫く微動だにせずにこちらへと視線を向けていた。
頭の先から足元まで、値踏みをする様に見ている。
そして、何やら聞き慣れない言語でミザリイに語り掛けていた。
この世界の言語なのだろう。当然一言一句たりとも理解出来なかった。
何となく、そわそわとしてしまう。
街中で、いきなり外国人二人組に話しかけられた時の様な、と表現するのが妥当だろうか。
これが例えば英語であれば、流暢な会話は出来なくとも単語だけでそれなりに乗り切れるかもしれない。
相手が中国人であればメモ帳に筆談でそれなりに意思疎通が図れるかもしれない。
しかし、相手がアラビア語やスワヒリ語の様な聞くにも書くにも全く馴染みの無い言語の国の出身だと、身振り手振りでコミュニケーションをとるしかない。
言わばお手上げに近い状態だ。
同じ地球に住んでいても、そうなってしまうのだ。これが、異世界に来て目の前で繰り広げられているのだから、お手上げ以上にどうしようもない状況だった。
異世界人とは言え、美しい女性二人を相手にもじもじと時を過ごすのは、正直性分では無いが、訳も分からずにお茶らけてドン滑りするのも、これまた性分でない。
そうして、暫く居心地の悪い空気に晒されて、漸くミザリイがおれへと視線を向けてくれた。
「――ああ、すまない。カーリーよ、魔力疎通を使ってくれ。この者はこの世界の言語を全く理解しておらんのだ。と、その前に、部屋に入ったのだから、まずは帽子とローブを取らんか、この無礼者めが」とミザリイ。
おれを相手に話す時よりも随分とキツイ口調で、カーリーと呼んだ魔女へ言い放っていた。
「へえ、この世界の言語は分からないのに、魔力疎通は使えるのかい?それは中々面白い存在だねえ。ミザリイが人間に魔紋を刻んだと言うから、どんな奴かと思って駆けつけた訳だけど」
カーリーは、ミザリイからの叱責を受けてもも悪びれる事無く、飄々とした態度で語り、緋色の帽子とローブを脱ぎ去った。
そしてそのまま床へと投げ捨てる。
それを見て、ミザリイは溜息をひとつ零して帽子とローブを拾い上げていた。
それぞれの人間性が垣間見える瞬間だった。
優等生と不良だけど幼馴染みで仲が良いみたいな、そういう関係性なのかもしれない。
「それで、アンタ、名前はなんてんだい?」と、カーリーは腕組みをしてそう言った。
ミザリイと同じくローブの下は黒いワンピースだけと言う格好だった。
しかし、彼女の場合少女の様な身体付きでは無く、鍛え上げられたアスリートの様な体型だった。
魔女と言うよりか、女戦士や海賊の様と表現した方がしっくりと来る。
「アダチ、ヨウスケだ。貴女のことは、カーリーと呼べばいいのかな?」
「ああ、それでいいよ。魔女名はカーリー・ラーク・フュールってんだけどね。それにしても――」
カーリーはそこで言葉を止め、改めておれの事を観ていた。そして続ける。
「私とミザリイを目の前にして、全く怯む感じが無いね。普通の人間が、こんな密室に閉じ込められてたら、魔女の魔力で頭がおかしくなっても不思議じゃあ無いってのにさ。如何に魔紋刻んだとは言え、昨日の今日なんだろう?」
彼女はおれの事を見詰めながら話していたが、文脈からミザリイに向けた発言だと思った。
「ふむ、それに関しては、私も魔紋を刻み繋がって漸く分かったのだが、この者は魔力耐性が極めて高い。あと、魔導具無しで魔力疎通が出来るのか、と思っておったのだが、どうやら左腕の時計とやらが魔導具として作用しておるようだ」
ミザリイはそう言って、腕時計を指さした。
そんなこと初耳だぞ、と思いつつおれは左手を上げて魔導具化したと言う腕時計を眺め見た。
どこか様子が変わっている訳では無い。チクタクと異世界でも変わらずに時を刻んでくれている。
「よ、要するに、異世界転移をした時に、普通の道具から魔導具化した、ってこと?」
「その可能性はある。が、異世界転移は関係無く、貴様の世界にある道具の全てが、こちらの世界では魔導具として使えるのかもしれん。それは定かでは無いし、現状それを追及する術も無い。いや、しかし、どちらにせよ、その時計が魔導具である事には変わらん」
おれとミザリイのやり取りをカーリーは大人しく聞いていたが、ふと何かを思いついたのか「あ!」と大きな声を上げた。
そして、大股でおれへと近づきべたべたと遠慮の無い手つきで作業着に触れてきた。
「じゃあさ、この薄汚れた服も魔導具ってことかい?」
カーリーからそう言われ、おれはミザリイの顔を見た。
この金髪の魔女が全てを把握してる訳で無い事は承知しているが、それでも何かそれなりの答えや案を出してくれるとおれはいつの間にやら信頼してしまっているのだ。
「恐らく、そうであろう。しかし、その効果や作用の程は今すぐには分からん。魔導具とは、基本的に用途を明確にして作成する物故にな、得体の知れぬ魔導具にいきなり魔力を注ぐのは愚の骨頂。貴様が異世界から持ち込んだ物は、古代遺跡から発掘された魔導具と同じ様な調査や鑑定をする必要があるだろう……なっ!」
ミザリイはそう言いつつ、手を伸ばしカーリーの左耳を抓り引っ張った。
「い、痛い、痛い。分かったから、余計なことはしないから」
カーリーは情けない声を上げ、おれから引き摺り離される。
恐らく、作業着に魔力を注ぎ込もうとしていたのだろう。
調査とか鑑定とか面倒くさいだろう?的な安易な考えで。
「本当に、油断も隙もあったものでは無い。貴様の火の魔力を注ぎ込んで、万が一この作業着とやらが魔力増幅の魔導具であったらどうするつもりなのだ?辺り一面火の海に包まれる可能性があると、考えが付かんのか?浅はかにも程がある。ほれ、もう用が無ければとっと立ち去れ。そして他の魔女にも伝えておけ。当分は誰も私の支配域には立ち寄るな、とな。この男の心身の安全確保と魔導具の調査鑑定が済むまでは、マグナラタンに連れて行く気も無いからな」
そう言うと、ミザリイは抱えていた緋色の帽子とローブをカーリーへと押し付け、扉の外へと追い出してしまった。
そして、そのままミザリイ諸共外へ出て行ってしまう。
あからさまに、扉の外で何やら密談していると分かる状況。
何だかんだ言いつつも魔女同士でおれには聞かれたく無い事もあるのだろう。
しかし、別に外に出て行かなくとも、この世界の言葉で会話されたらおれには何も分からないのだけれど、と思うと笑みが零れてくる。
暫くして、ミザリイはするりと音も無く戻ってきた。
おれは立ったまま待ち惚けるのも馬鹿らしいと思い、椅子に座って腕時計をつぶさに観察していた。
じっくりと見れば何処かに変化を見つけれるかもしれない、と思ったのだが、そもそもそこまでじっくりと観察したことが無いので、それらしい何かを見つける事は出来なかった。
「――おかえり。カーリーは大人しく帰ってくれたかい?」
そう声を掛けると、ミザリイは薄らと苦い笑みを浮かべていた。
そして、まるで決められた作業の様に湯を沸かし茶の準備をする。
「あやつにしたら、大人しく帰ってくれた方だと思う。恐らくあのまま追い返したら今後も色々とちょっかいを出して来るのは分かり切っておったのでな、貴様の心身の安全が確保出来た時点でマグナラタンより先にカーリーの支配域へと貴様を連れて行くと、約束をしておいた」
多分、それは嘘ではないのだろう、と思った。
他にも色々と算段はしているのかもしれないが、それを根掘り葉掘り探りを入れるべきではない、今は。
「あのさ、ミザリイ?さっきは言わなかったんだけど――」
「ああ、いや、貴様の言いたい事は分かっておる。赤い工具箱の事であろう?」
彼女は木の器に茶を注ぎつつそう言う。
やはり、察しもいいし頭もいい。
「おれは別にカーリーの事を悪くは思って無いけど、まだ伏せて置いた方が良いかと思って」
「その判断は間違っておらん。あやつは敵では無いが、調子に乗ると手が付けられんからな。知らんで良い事は知らんで良いのだ。工具箱の中には、何やら色々と道具が入っておる、と言うことなのだろう?」
ふたり同じ様なタイミングで茶を啜りつつ会話をしていた。
お洒落な隠れ家的カフェで優雅に寛いでいる様な気分になってしまう。
「ああ、入ってるよ。おれの世界で言うところの偉大な魔法使いの様な人の工具箱だからさ、年季の入った素晴らしい道具が沢山あると思う」
「それは要するに、貴様の所有物では無い、と言うことか?」
「そうなんだよ。おれの師匠みたいな人の道具箱。ミザリイで言うと図書館の館長の魔導具ってことかな?」
「なるほど、な。それはおいそれとは使えんな。何処かに封印してしまうか?師匠の魔導具を断りも無しに使用するなど、想像しただけで血の気が引く思いがする」
ミザリイのこういう発言を聞くと、何だか癒される心地になってしまう。
間違いなく堅物だけれど、どこか可愛らしい一面もあるのだ。そのギャップは、彼女の大きな魅力のひとつなのだろう。
「いや、元の世界なら、本当においそれとは使えないんだけど、この世界にいるなら使っても怒られないと思う。今考えたら、あのタイミングで工具箱を取りに行かせてくれたのは奇跡だと思うし。いや、まだ実際、手元に無いしさ、あったとてそれが魔導具かどうかも分からない状態だけど、心の拠り所になる事は間違いないだろうし」
おれはそう言いい、茶を飲み干した。
それを見て、ミザリイも同様に器を空ける。
申し合わせた訳では無いが、これが工具箱を探しに出かけるタイミングなのだろうと、感じていた。
「――ヨウスケよ、身体の具合はどうだ?」
ミザリイはおれの目を見詰めながらそう言った。
相変わらず表情は乏しいが、出会った時より若干柔和である様に見える。これも魔紋を刻んだ影響なのだろうか?
「ああ、随分と楽になったよ。今から森で工具箱を探すんだろう」
「うむ、そうだな。いつまでも得体の知れぬ魔導具を支配域に放置しておく事は出来んし。体調が良いなら貴様を連れて行きたいと考えておるが、どうだ?」
「勿論、ついて行くさ。師匠の大切な工具箱だからな、人任せには出来ない。それに、この世界を観てみたいしな。転移して直ぐは、まさか自分が異世界に来てるとは思いもしなかったからさ」
そう言いおれは飲み干した器を逆さにして置いた。
確かお代わり無用とか、飲み干した合図だったはず。
何処の文化か覚えて無いが一時仲間内でそれが流行った事があった。
この時は、何となく気分が高揚して咄嗟にやってしまっただけ、なのだが。
「その、器を逆さにするのは、何か意味があるのか?」と、当然興味心オバケのミザリイは質問を投げかけてくる。
「ああ、これはもう茶はいらないぜってこと。そろそろ帰るとかさ、宴をお開きにしようとか、そう言う感じかな」
それがあってるかどうかなんて今は調べようが無い。
元の世界にいたらスマホで調べたりするのだろうけれど。
「ふむ、なるほど。しかし、やはり貴様のいた世界の風習やら文化は興味深いな。確かに、器をひっくり返せばもう茶は注げん。いちいち帰る旨を告げる必要も無いということか」
ミザリイはそう言うと、自分の器もひっくり返して置いていた。
それは彼女の何気ない行動のひとつだった訳だが、おれの心に温かな火を灯してくれたのだ。
異世界に来て、学ぶ事ばかりで圧し潰されそうだと感じていたが、逆におれから教えたり伝えれる事も多くあると、気付かされた一瞬でもあった。
そんなおれの事など気に掛ける事も無く、彼女は森を探索するべく、真っ黒な鍔の広い帽子を目深に被り、丈長のローブを身に纏っていた。
カーリーを緋色の魔女と例えるなら、ミザリイは漆黒の魔女と言ったところか。
「――では、行くぞ、ヨウスケ。着いて参れ」
彼女はそう言うと、扉を開け外へと踏み出した。