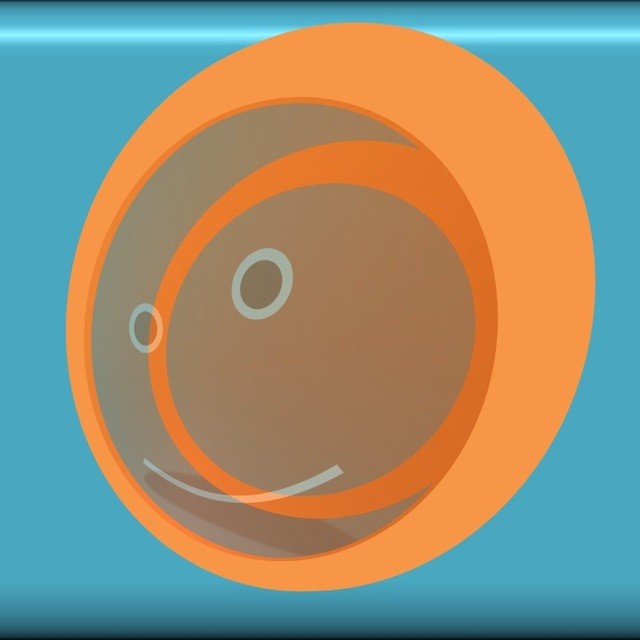第3話:元の世界に戻るのは不可能では無い、かもしれん。
文字数 5,246文字
窓の外へ目をやると、夕闇が落ちていた。
今いる部屋にはそう大きく無い窓がひとつだけあり、カーテンは掛かって無かった。
この世界にカーテンが存在しないのか、ミザリイがカーテンを必要としてないのか。
そう言った細かな事まで考えてみると、彼女に聞かなければならない事は、文字通り山の様にあるのだろう。
しかし、今は……明日の昼までに関しては魔法や魔女のことに関して、話題を絞るべきだろうと思い、視線を目の前の彼女へと戻した。
「魔力圧縮も出来ないおれだが、魔力疎通をしてると言う事は、要するに、おれも魔法が使える様になるかもしれない、と言う事なのだろうか?」と、おれは次の質問を繰り出す。
普段これ程硬い口調では無いが、ミザリイと会話をしていると自然とそうなってしまう。
彼女は、おれの問い掛けを受けると、少し間を空けてから話出した。
「――先ほども述べたが、魔力疎通も立派な魔法のひとつ。それを踏まえると、貴様は既に魔法を使っていると言える。故に、私からの返答は、貴様も魔法が使える様になるだろう……答えるしか無いだろうな。しかし、私が考えるに、注目したいのは貴様が魔法を使える様になるかならないか、では無くて、何故魔導具無しで魔力疎通が使えるのか?という点だ」
そう言うと、ミザリイは茶を一口飲んだ。濡れた艶やかな唇を舌でひと舐めする仕草に目を奪われてしまう。
こんな訳の分からない状況に追い込まれても色気に走ってしまうおれが異常なのでは無くて、彼女の魅力が尋常では無いのだろう、思う事にした。
魔女なのだから、相手を魅了する魔法を使っているか、そう言う能力を有しているのかもしれないし。
「魔力疎通か。直接、頭の中へ語り掛けているって事なのだろう?て、事は、全く魔法を使えない者がおれとミザリイの会話を聞いたら、全く異なる言語で会話してる様に聞こえるって事、だよな?」
「うむ、そうなるな。その辺の村人にしてみたら、異様な光景に見えるであろう。故に、貴様が魔法の使えぬ村人と接したとしたら、貴様の言い分は相手に伝わるが、貴様は相手の言葉を理解出来ん。しかしながら、貴様がこの世界の言葉を理解するのに、そう時は掛からんだろうとは思う。会話に必要な単語さえ理解してしまえば、相手が何を伝えたいのか、凡そは理解出来るだろうし、何よりの強みは貴様が理解してるかして無いかを、貴様自身が相手に事細かに伝える事が可能だと言う点であろうな」
彼女はそう言うと、首を横に向け窓の外へと視線を向けた。
おれも彼女の視線の先へを目を向ける。
「何か、外に気になる事でもあるのか?」おれは何となくそう思い語り掛けていた。
彼女の表情が、少し物憂げである様に見えたのだ。
「ああ、いや、普段は陽が落ちる頃に支配域を散策する事にしておるのだ。使役している魔獣がおる故、万が一侵入者や不審な者が現れたとて、全て駆逐してくれるのだがな。私は、こう見えて用心深い性質なのだよ。不用意に貴様を異世界転移させておいて何を言うかと思われるかもしれんが、な」
そう言うと彼女は視線をおれへと戻した。
おれは彼女から一呼吸遅れて、視線を彼女へと重ねる。
彼女の優美な瞳に、おれは直ぐに心を掴まれてしまう。
見れば見る程、美しい。言動は強く老獪にも感じるが、その容姿は至極魅力的だった。
それでもおれは、テーブルの下で拳を強く握り締め緩みそうな気持ちを戒める。
色気に感けてる場合で無い事は十分承知してる筈なのに、彼女の魅力に心が揺らいでしまっている己を、内心激しく罵倒していた。
「そ、その――」そんな腑抜けた感情を断ち切る様に絞り出した声は恥ずかしいくらい上擦ってしまう。
おれは一旦言葉を切り、茶で喉を潤してから、改めて切り出した。
「その、支配域と言うのは、ミザリイが支配してる土地の事を指しているのか?」
その問い掛けに対して、彼女は即答せずに一呼吸の間を設ける。
それが彼女の会話のテンポと言う事なのだろう。
「支配域とは、魔女が支配する土地の事を指しておる。それに関しては貴様の認識で相違ない。魔女の格は、支配域の広大さと成熟具合で測られる故、一般的に魔女は自身の支配域を広げ成熟させる為に日々を過ごしておると言って過言は無い」
彼女はそう言うと、立ち上がり鍋を手に取った。
そのまま窓際にある大きな甕から鍋に何やら液体を移し、それを火に掛ける。
流れる様な動作だった。動きの中で物音ひとつしない様な、滑らかで無駄の無い動き。
火に掛けた鍋の中に、彼女は乾燥した植物や茸類を大雑把に投げ入れ、香辛料と思しき粉末をぱらぱらと投じる。
室内には、馨しい匂いが立ち込めていた。
彼女は鍋を木の棒で掻き混ぜ、その中に指を入れ味見をすると、おれの対面へと戻って来た。
「今作ってるのは、夕食?」とおれは言った。
匂いに釣られて腹が鳴る。
「私は、基本的に夜食事はとらんが、世間一般では、夕闇が舞い降りる頃に夕食をとるであろう?それは貴様がいた世界でも同じか?」
「そうだな、それは同じだと思う。おれがいた世界にも、夜食事をとらない者はいるけどな。それは比較的少数派かもしれない。普通の人は朝昼晩と一日三回食事をするよ」
「ふむ、そうか。やはり、全く異質な文明で育った訳では無いと言う事だな。で、あれば貴様がこの世界に馴染むのに、そう時は掛からんかもな。食事が口に合う合わないは別にして、朝起きて夜寝て、その都度食事して……と基本的な生活概念が同じであれば、共有共感出来る事象は多くある事だろうし」
その彼女の言葉を聞き、おれはふと思い至った事があった。
彼女は、おれがこの世界に永住する事を念頭に会話を進めている。
しかし、おれとしては、おれなりの異世界転移の概念があって。
要するに、こちら側に転移出来たのだから、元の世界に戻る事も、これまた可能では無いのか?という事。
簡単では無いかもしれないが、絶対に不可能な筈は無い、とそう思っていた。
それでおれは彼女に対して「おれが、元の世界に戻れる可能性って、無いのかな?」と尋ねた。
すると彼女は、一瞬大きく目を見開き、一頻り長く間を取った。
それだけで、元の世界に戻る事が難しいという事を理解せざるを得ない状況。
色々と聞きたい事が口をついて出そうになるが、おれはそれをぐっと堪えて彼女の言葉を待った。
――そして。
「貴様が、元の世界に戻るのは不可能では無い、かもしれん。だが現状、私はその術を有しておらん。今回、貴様を転生させる際に使った魔法陣は、この古文書に描かれてあった」
そう言うと、彼女は一冊の古びた書物を差し出して来た。
おれはそれを手に取り、ぱらぱらと捲った。勿論、それに書かれてある事は全く理解する事は出来ない。
彼女が言う魔法陣は、書物の後半に描かれてあった。
「この魔法陣を使って、おれを転移させたって事?」
「うむ、そうだ。私はこの古文書の解読をマグナラタンから依頼されておったのだが、余りにも難解で、私の手に余る故に、一旦マグナラタンに返却しようと思ったのだ。しかし、そこに描かれておる魔法陣が妙に気になってな、返却前に、一度それを発動させてみたいと言う気持ちに駆られてしまった。今思うと、不用意で不用心過ぎる行いだと思うが、その時はその衝動を抑える事が出来なかったのだ。そして、発動した結果、目の前に貴様が現れた。結果から鑑みて、その古文書が、異世界から人間を転移させる代物である事は間違い無いだろう。しかし、私はその古文書を解読する事が出来なかった。と言う事は、それを私に依頼して来たマグナラタンも解読は出来無いと言う事になる。それに書かれている文字がどの言語体系にも当てはまらんのだ。難解な暗号を解くよりも難しいやもしれん。いつの時代の物かも分からん。そして、貴様に関係する事で一番の問題は、その古文書に描かれている魔法陣がひとつだけ、と言う事だ」と彼女はそこで言葉を切った。
じっと、強い意志を以て見詰めてくる。
おれに現状までの理解を求めているのだろう。
「よ、要するに、ここに描かれている魔法陣は、異世界から人間を呼び寄せるもので、こちらの世界から人間を異世界に送るものでは無いと言う事か?」とおれは、そうと確信しながら、そう問い掛けていた。
彼女は、こくりと頷く。
「そう言う事だ。一人の人間を異世界へと送り戻すという常識を逸脱した行為を、ひとつの同じ魔法陣で行える筈が無い。恐らくだが、これと対となる古文書が何処かに存在するやもしれん。しかし、それを断言する事は、私には出来ん。万が一、存在したとしてもそれを入手出来るかどうかも分からん。その上、ひとつ思う事は、それらしき古文書を入手したとして、それに描かれている魔法陣を発動させたとして、それで貴様が元居た世界へと転移出来るかどうかは、私には分からん、と言う事だ。一緒に転移する訳では無いからな。それを踏まえた上で、貴様に問いたい事がある」
そう言うと、彼女は一口茶を飲んだ。そしておれの事をじいっと見据える。
「問いたい事って?」おれは彼女特有の間を埋めるべく、言葉を発していた。
「貴様は、本心から元居た世界へと戻りたいと思っておるのか?」
彼女の声は、殷々と響いた。
そう問われ、おれは即答出来ずに、口を閉ざすしかなかった。
それを見て、彼女は続けた。
「いや、本心から元居た世界へと戻りたいと思っておるなら、初めからそう訴え掛けて来ても良いだろう、と私的には思うのだ。しかし、貴様は、あからさまにこの世界への興味を示しておる。この世界に早く順応しようとしてる様にも見える。で、あれば、そうすれば良いのでは?と私は思うのだ。例えば、元いた世界へと転移出来そうな古文書を見つけたとして、それを発動して元居た世界へと戻れれば、それで結果良しとなるが、そうで無かった場合、貴様はどうするのだ?その新たに転移した先が、言葉も意思も通じぬ世界だったら、貴様はどう生きる?いや、これは可能性の話でしか無い。だが、しかし、どちらの可能性も確実にある。その様な、無謀な賭けにその身を晒すくらいなら、意思疎通の出来るこの世界に留まった方が良いのでは無いか?と言うのが、私の提案だ。無論、それらの判断決心は、貴様が有しておるがな……」
恐らく、ミザリイは、言葉を選んでおれの事を諭してくれているのだろう。
ここに来て、改めておれは己の置かれている境遇を知るに至った。
確かに、それっぽい古文書や魔法陣を見つけた所で、元の世界へと戻れる確証は全く無い。
それを認識する事が出来ただけでも、彼女との会話は、至極有意義だと思う。
そう思うと、むしろこの世界に転移出来た事を、幸運だったとすら思えてしまう。
いや、勿論異世界転移なんてしないに越した事は無いのだけれど。
おれは、自分の置かれた境遇を理解して、漸く少し落ち着きを取り戻した。
まだ腹を括った、とまでは行かないが……。
「――ミザリイ?」と、取り敢えず呼び掛けてみる。それから問うべき題材を考えた。
「あの、いや、正直な話、完全に現状を理解は出来て無いのかもしれない。理解と言うか覚悟と言うか。でも、それでも、兎に角、おれはこの世界で生きてゆかねばならない、と、それは理解出来た。その上で聞くけれど、要するにおれはミザリイの庇護下に入り、奴隷の様な身分で生活を送る、と言う事なのだろうか?」
そのおれの問い掛けに対し、ミザリイは茶を飲み一呼吸置いた。
「ん?なんだ、貴様は私の奴隷になりたいのか?」
「あ、いや、別に好き好んで奴隷になりたい、とは思わないけど。魔紋を刻むって、そう言う事では無いのかな?」
「ふむ、いや、これは考え方次第だが、魔紋を刻むと言う行為自体が、それ即ち奴隷と言う事では無い。魔紋は奴隷の証では無いからな。しかし、私の庇護下に入る言う概念は間違いでは無いのだ。そうか、それに関しては言葉が足りなかったか。いや、実は、人間に魔紋を刻むのは、貴様が初めてなのだ。魔獣や幻獣にはあるがな。それら獣に関しては、そう言った説明が必要が無い。奴らとの関係性は純然たる力の差で決まるから。奴らは、私の力を認めれば、そもそも魔紋が無くともある程度は従ってくれるからな。しかし、人間相手では、そうはいかんと言う事か。それを考えると、何十人もの人間に魔紋を刻んでる他の魔女たちの気が知れんな」
そこで言葉を切ると、彼女は立ち上がり、煮沸してる鍋の中に、いつの間にか手にしていた干し肉の様な物を投じ、更に香辛料をぱらぱらと入れていた。
その間、おれは特に何を思う事無く、窓の外の夕闇へと目を向けていた。
今いる部屋にはそう大きく無い窓がひとつだけあり、カーテンは掛かって無かった。
この世界にカーテンが存在しないのか、ミザリイがカーテンを必要としてないのか。
そう言った細かな事まで考えてみると、彼女に聞かなければならない事は、文字通り山の様にあるのだろう。
しかし、今は……明日の昼までに関しては魔法や魔女のことに関して、話題を絞るべきだろうと思い、視線を目の前の彼女へと戻した。
「魔力圧縮も出来ないおれだが、魔力疎通をしてると言う事は、要するに、おれも魔法が使える様になるかもしれない、と言う事なのだろうか?」と、おれは次の質問を繰り出す。
普段これ程硬い口調では無いが、ミザリイと会話をしていると自然とそうなってしまう。
彼女は、おれの問い掛けを受けると、少し間を空けてから話出した。
「――先ほども述べたが、魔力疎通も立派な魔法のひとつ。それを踏まえると、貴様は既に魔法を使っていると言える。故に、私からの返答は、貴様も魔法が使える様になるだろう……答えるしか無いだろうな。しかし、私が考えるに、注目したいのは貴様が魔法を使える様になるかならないか、では無くて、何故魔導具無しで魔力疎通が使えるのか?という点だ」
そう言うと、ミザリイは茶を一口飲んだ。濡れた艶やかな唇を舌でひと舐めする仕草に目を奪われてしまう。
こんな訳の分からない状況に追い込まれても色気に走ってしまうおれが異常なのでは無くて、彼女の魅力が尋常では無いのだろう、思う事にした。
魔女なのだから、相手を魅了する魔法を使っているか、そう言う能力を有しているのかもしれないし。
「魔力疎通か。直接、頭の中へ語り掛けているって事なのだろう?て、事は、全く魔法を使えない者がおれとミザリイの会話を聞いたら、全く異なる言語で会話してる様に聞こえるって事、だよな?」
「うむ、そうなるな。その辺の村人にしてみたら、異様な光景に見えるであろう。故に、貴様が魔法の使えぬ村人と接したとしたら、貴様の言い分は相手に伝わるが、貴様は相手の言葉を理解出来ん。しかしながら、貴様がこの世界の言葉を理解するのに、そう時は掛からんだろうとは思う。会話に必要な単語さえ理解してしまえば、相手が何を伝えたいのか、凡そは理解出来るだろうし、何よりの強みは貴様が理解してるかして無いかを、貴様自身が相手に事細かに伝える事が可能だと言う点であろうな」
彼女はそう言うと、首を横に向け窓の外へと視線を向けた。
おれも彼女の視線の先へを目を向ける。
「何か、外に気になる事でもあるのか?」おれは何となくそう思い語り掛けていた。
彼女の表情が、少し物憂げである様に見えたのだ。
「ああ、いや、普段は陽が落ちる頃に支配域を散策する事にしておるのだ。使役している魔獣がおる故、万が一侵入者や不審な者が現れたとて、全て駆逐してくれるのだがな。私は、こう見えて用心深い性質なのだよ。不用意に貴様を異世界転移させておいて何を言うかと思われるかもしれんが、な」
そう言うと彼女は視線をおれへと戻した。
おれは彼女から一呼吸遅れて、視線を彼女へと重ねる。
彼女の優美な瞳に、おれは直ぐに心を掴まれてしまう。
見れば見る程、美しい。言動は強く老獪にも感じるが、その容姿は至極魅力的だった。
それでもおれは、テーブルの下で拳を強く握り締め緩みそうな気持ちを戒める。
色気に感けてる場合で無い事は十分承知してる筈なのに、彼女の魅力に心が揺らいでしまっている己を、内心激しく罵倒していた。
「そ、その――」そんな腑抜けた感情を断ち切る様に絞り出した声は恥ずかしいくらい上擦ってしまう。
おれは一旦言葉を切り、茶で喉を潤してから、改めて切り出した。
「その、支配域と言うのは、ミザリイが支配してる土地の事を指しているのか?」
その問い掛けに対して、彼女は即答せずに一呼吸の間を設ける。
それが彼女の会話のテンポと言う事なのだろう。
「支配域とは、魔女が支配する土地の事を指しておる。それに関しては貴様の認識で相違ない。魔女の格は、支配域の広大さと成熟具合で測られる故、一般的に魔女は自身の支配域を広げ成熟させる為に日々を過ごしておると言って過言は無い」
彼女はそう言うと、立ち上がり鍋を手に取った。
そのまま窓際にある大きな甕から鍋に何やら液体を移し、それを火に掛ける。
流れる様な動作だった。動きの中で物音ひとつしない様な、滑らかで無駄の無い動き。
火に掛けた鍋の中に、彼女は乾燥した植物や茸類を大雑把に投げ入れ、香辛料と思しき粉末をぱらぱらと投じる。
室内には、馨しい匂いが立ち込めていた。
彼女は鍋を木の棒で掻き混ぜ、その中に指を入れ味見をすると、おれの対面へと戻って来た。
「今作ってるのは、夕食?」とおれは言った。
匂いに釣られて腹が鳴る。
「私は、基本的に夜食事はとらんが、世間一般では、夕闇が舞い降りる頃に夕食をとるであろう?それは貴様がいた世界でも同じか?」
「そうだな、それは同じだと思う。おれがいた世界にも、夜食事をとらない者はいるけどな。それは比較的少数派かもしれない。普通の人は朝昼晩と一日三回食事をするよ」
「ふむ、そうか。やはり、全く異質な文明で育った訳では無いと言う事だな。で、あれば貴様がこの世界に馴染むのに、そう時は掛からんかもな。食事が口に合う合わないは別にして、朝起きて夜寝て、その都度食事して……と基本的な生活概念が同じであれば、共有共感出来る事象は多くある事だろうし」
その彼女の言葉を聞き、おれはふと思い至った事があった。
彼女は、おれがこの世界に永住する事を念頭に会話を進めている。
しかし、おれとしては、おれなりの異世界転移の概念があって。
要するに、こちら側に転移出来たのだから、元の世界に戻る事も、これまた可能では無いのか?という事。
簡単では無いかもしれないが、絶対に不可能な筈は無い、とそう思っていた。
それでおれは彼女に対して「おれが、元の世界に戻れる可能性って、無いのかな?」と尋ねた。
すると彼女は、一瞬大きく目を見開き、一頻り長く間を取った。
それだけで、元の世界に戻る事が難しいという事を理解せざるを得ない状況。
色々と聞きたい事が口をついて出そうになるが、おれはそれをぐっと堪えて彼女の言葉を待った。
――そして。
「貴様が、元の世界に戻るのは不可能では無い、かもしれん。だが現状、私はその術を有しておらん。今回、貴様を転生させる際に使った魔法陣は、この古文書に描かれてあった」
そう言うと、彼女は一冊の古びた書物を差し出して来た。
おれはそれを手に取り、ぱらぱらと捲った。勿論、それに書かれてある事は全く理解する事は出来ない。
彼女が言う魔法陣は、書物の後半に描かれてあった。
「この魔法陣を使って、おれを転移させたって事?」
「うむ、そうだ。私はこの古文書の解読をマグナラタンから依頼されておったのだが、余りにも難解で、私の手に余る故に、一旦マグナラタンに返却しようと思ったのだ。しかし、そこに描かれておる魔法陣が妙に気になってな、返却前に、一度それを発動させてみたいと言う気持ちに駆られてしまった。今思うと、不用意で不用心過ぎる行いだと思うが、その時はその衝動を抑える事が出来なかったのだ。そして、発動した結果、目の前に貴様が現れた。結果から鑑みて、その古文書が、異世界から人間を転移させる代物である事は間違い無いだろう。しかし、私はその古文書を解読する事が出来なかった。と言う事は、それを私に依頼して来たマグナラタンも解読は出来無いと言う事になる。それに書かれている文字がどの言語体系にも当てはまらんのだ。難解な暗号を解くよりも難しいやもしれん。いつの時代の物かも分からん。そして、貴様に関係する事で一番の問題は、その古文書に描かれている魔法陣がひとつだけ、と言う事だ」と彼女はそこで言葉を切った。
じっと、強い意志を以て見詰めてくる。
おれに現状までの理解を求めているのだろう。
「よ、要するに、ここに描かれている魔法陣は、異世界から人間を呼び寄せるもので、こちらの世界から人間を異世界に送るものでは無いと言う事か?」とおれは、そうと確信しながら、そう問い掛けていた。
彼女は、こくりと頷く。
「そう言う事だ。一人の人間を異世界へと送り戻すという常識を逸脱した行為を、ひとつの同じ魔法陣で行える筈が無い。恐らくだが、これと対となる古文書が何処かに存在するやもしれん。しかし、それを断言する事は、私には出来ん。万が一、存在したとしてもそれを入手出来るかどうかも分からん。その上、ひとつ思う事は、それらしき古文書を入手したとして、それに描かれている魔法陣を発動させたとして、それで貴様が元居た世界へと転移出来るかどうかは、私には分からん、と言う事だ。一緒に転移する訳では無いからな。それを踏まえた上で、貴様に問いたい事がある」
そう言うと、彼女は一口茶を飲んだ。そしておれの事をじいっと見据える。
「問いたい事って?」おれは彼女特有の間を埋めるべく、言葉を発していた。
「貴様は、本心から元居た世界へと戻りたいと思っておるのか?」
彼女の声は、殷々と響いた。
そう問われ、おれは即答出来ずに、口を閉ざすしかなかった。
それを見て、彼女は続けた。
「いや、本心から元居た世界へと戻りたいと思っておるなら、初めからそう訴え掛けて来ても良いだろう、と私的には思うのだ。しかし、貴様は、あからさまにこの世界への興味を示しておる。この世界に早く順応しようとしてる様にも見える。で、あれば、そうすれば良いのでは?と私は思うのだ。例えば、元いた世界へと転移出来そうな古文書を見つけたとして、それを発動して元居た世界へと戻れれば、それで結果良しとなるが、そうで無かった場合、貴様はどうするのだ?その新たに転移した先が、言葉も意思も通じぬ世界だったら、貴様はどう生きる?いや、これは可能性の話でしか無い。だが、しかし、どちらの可能性も確実にある。その様な、無謀な賭けにその身を晒すくらいなら、意思疎通の出来るこの世界に留まった方が良いのでは無いか?と言うのが、私の提案だ。無論、それらの判断決心は、貴様が有しておるがな……」
恐らく、ミザリイは、言葉を選んでおれの事を諭してくれているのだろう。
ここに来て、改めておれは己の置かれている境遇を知るに至った。
確かに、それっぽい古文書や魔法陣を見つけた所で、元の世界へと戻れる確証は全く無い。
それを認識する事が出来ただけでも、彼女との会話は、至極有意義だと思う。
そう思うと、むしろこの世界に転移出来た事を、幸運だったとすら思えてしまう。
いや、勿論異世界転移なんてしないに越した事は無いのだけれど。
おれは、自分の置かれた境遇を理解して、漸く少し落ち着きを取り戻した。
まだ腹を括った、とまでは行かないが……。
「――ミザリイ?」と、取り敢えず呼び掛けてみる。それから問うべき題材を考えた。
「あの、いや、正直な話、完全に現状を理解は出来て無いのかもしれない。理解と言うか覚悟と言うか。でも、それでも、兎に角、おれはこの世界で生きてゆかねばならない、と、それは理解出来た。その上で聞くけれど、要するにおれはミザリイの庇護下に入り、奴隷の様な身分で生活を送る、と言う事なのだろうか?」
そのおれの問い掛けに対し、ミザリイは茶を飲み一呼吸置いた。
「ん?なんだ、貴様は私の奴隷になりたいのか?」
「あ、いや、別に好き好んで奴隷になりたい、とは思わないけど。魔紋を刻むって、そう言う事では無いのかな?」
「ふむ、いや、これは考え方次第だが、魔紋を刻むと言う行為自体が、それ即ち奴隷と言う事では無い。魔紋は奴隷の証では無いからな。しかし、私の庇護下に入る言う概念は間違いでは無いのだ。そうか、それに関しては言葉が足りなかったか。いや、実は、人間に魔紋を刻むのは、貴様が初めてなのだ。魔獣や幻獣にはあるがな。それら獣に関しては、そう言った説明が必要が無い。奴らとの関係性は純然たる力の差で決まるから。奴らは、私の力を認めれば、そもそも魔紋が無くともある程度は従ってくれるからな。しかし、人間相手では、そうはいかんと言う事か。それを考えると、何十人もの人間に魔紋を刻んでる他の魔女たちの気が知れんな」
そこで言葉を切ると、彼女は立ち上がり、煮沸してる鍋の中に、いつの間にか手にしていた干し肉の様な物を投じ、更に香辛料をぱらぱらと入れていた。
その間、おれは特に何を思う事無く、窓の外の夕闇へと目を向けていた。