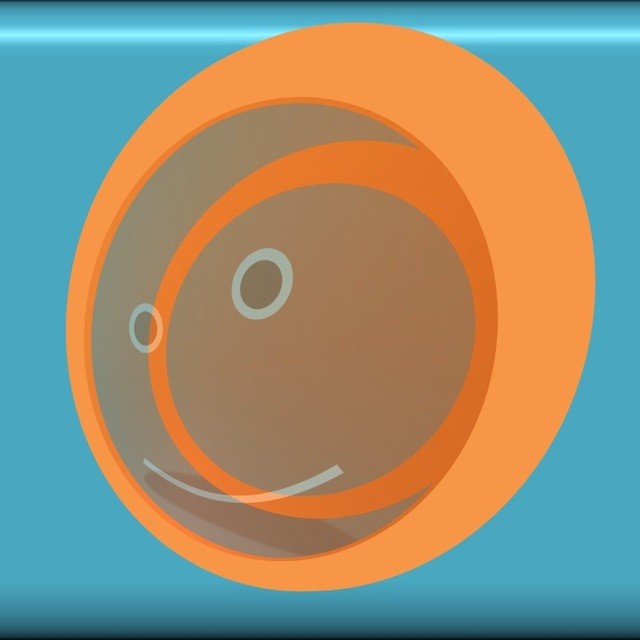第2話:変わり者の魔女。
文字数 4,634文字
茶を飲みつつ、テーブルに並べられた工具類を眺めていた。
ミザリイは、おれの対面に座り何やら分厚い書物を読んでいる。
今までは、おれの為に何かと時間を割いてくれていたが、ある程度の説明責任と身の回りの世話を終えた彼女は、普段の魔女生活へと回帰するという事なのだろう。
魔女道を極めるのが、彼女の仕事なのだから、いつまでもおれ一人の面倒をみていられないのは道理で、それに関しておれは現状を受け入れるしかない。
しかし、このままボケっと茶を飲んで時を過ごすのは時間を無駄にしてる様な感じがするので、必要最低限の問い掛けをしてみることにした。
「ミザリイ?本を読みながらでいいから、いくつか質問してもいいかい?」
それに対し、ミザリイは茶をひと口飲み、ちらりとこちらへ目を向けた。美しい碧眼だ。思わずうっとりと見入ってしまう。
「うむ、全然構わぬ。貴様と会話することにより、私も得られることが多々ある故、遠慮せずに申してみよ」
「まず、この工具だけど、一旦、工具箱の中へ仕舞っても構わないだろうか?」
そう問い掛けると、彼女は即答せずに、工具と工具箱を交互に見つめていた。
そして「――いや、今はまだ止めておけ。後で、魔導具に詳しい者が訪れる故、その者が来てからするべきだ」と言い、再び本へと目を移した。
「と言う事は、今はまだ触れない方がいいってこと?」
「そうするべきだろうな。得体の知れぬ魔導具は専門家に任せた方が安全だ。まあ、既に痛い目にあっている貴様には、それについてくどくどと説明する必要はなかろう」
それはごもっともで。それに関してはこちらから何も言い分は無い。
改めて、整然と並べてある工具へと視線を移した。
それから眼前に腕時計を持ってきた。今までの経緯から、この腕時計が既にチート的な魔導具の可能性がある。
この世界の言葉を全く理解しておらず、その上魔力制御も出来ないおれが、魔女にしか出来ない魔力疎通とやらを難なくしてしまえているのだから、それは間違いなくチートと言えるだろう。
燃えて無くなってしまったが、着ていた作業服も致命傷に至るほどの火傷 を防いでくれたのだから、その効力は大きかったのだと思う。
そうなると、この工具たちにも自ずと期待感が湧いてくる。
これって、ネットゲームのガチャを回す前の感覚に似ているな、と思わず笑みが零れた。
今後の生活がモロに掛かっているから、課金出来るなら全財産注ぎ込んで廃課金者として名を馳せたいくらいだ。
「どうした、何かおもしろいことでもあったか?」とミザリイ。
読書をしていてもなんやかんやで、おれのことを意識してくれてはいる様だ。
「あ、いや、少し思い出し笑い、かな。あのさ?後で来る魔導具に詳しい人って、魔女なのかい?」
「うむ、同じ魔女同盟の者だ。コリンという。貴様の火傷の処置をしたアリアの妹弟子にあたる」
「そうか、火傷の処置をしてくれた魔女もいるって言ってたよな。ぜひ、その人にもお礼を言いたいんだけど」
「アリアなら、明日あたり顔を出すであろう。あの者は自分の患者をずっと放っておくような無責任なことはせぬから」
それを聞き、おれは一旦体重を背もたれに預けた。
考えれば考えるほど、至れり尽くせりで運がいいなと思えてくる。
あれほどの業火に焼かれて、僅か数日でここまで回復しているのだから、これ以上の幸せは現状望むことは出来なかった。
その上、この目の前の工具が全てチート級の魔導具だったとしたら……おれの異世界生活は案外捨てたモノでは無いのかもしれない。
「ミザリイ?あのさ?身体が完全に癒えて、この工具の使い道が判明して、ある程度日常会話が出来る程度に言葉を覚えたら……おれは、それからどういう風に生きて行けばいいかな?」
おれがそう言うと、彼女はぱたりと本を閉じてテーブルの上に置いた。
「取り合えず、私の支配域に属しておる集落にでも行ってみればいい。人口三十数名程度の小さな集落だが、この世界の現実を見るには丁度良いかもしれん」
「それって、おれ一人で行っていいのかい?」
「うむ、構わん。ここで養生してる間に、魔獣か幻獣を手懐けれれば、それらを連れて行っても構わんしな」
彼女はそういうが、六本足の獣や空中をふわふわと浮いている得体の知れないモノを簡単に手懐けれるとは思えなかった。おれは特に動物好きってわけでも無いから。
「けど、ここにいる魔獣とか幻獣ってミザリイが使役してるんだろう?それをおれが手懐けて連れて行ってもいいのかい?」
「支配域にいる全ての獣を私が使役してるわけではない。しかし、別に使役してる獣でも全然連れて行って構わん。その点に関して貴様が気にする必要はない。好きな獣を連れて行けば良い」
そう言うと彼女は「なんだ、もう来おったのか」と言い右手を上げて、ぱちりと指を鳴らした。
あの緋色の魔女が来た時と同じだった。このタイミングなので、恐らく来たのは魔導具に詳しい魔女……という事なのだろう。
ミザリイが指を鳴らしてから、すぐに扉が開く。
黄色いローブに身を包んだ女性がつかつかと足早に入って来た。
まずおれの顔を見て、ミザリイを見て、それからテーブルの上の工具に目を向けると挨拶も無しにテーブルへと近づいた。床へ膝をつき、食い入るように工具を見詰めている。
それを見たミザリイは「はあああ」と深い溜息を漏らした。「コリンよ?魔女であるならば、室内に入った時ははまず帽子を取りローブを脱げ。全く、カーリーといいコリンと言い、どうして我が同盟には礼儀知らずの魔女が多いのか……」ミザリイはそう言って立ち上がり、テーブル前から微動だにしないコリンへと歩み寄った。
そして、彼女から帽子を取りローブを剥ぎ取り丁寧に畳んで棚へと置いていた。
二人の関係性が垣間見える。
コリンは栗色の髪を背中辺りで一つに束ねていた。他の魔女と同じく、極めて露出度の高い黒いワンピースを身に着けている。
ミザリイが誰しもが認めるであろう美少女タイプだとしたら、コリンは知的な美人さんと言ったところか。
コリンが夢中で工具を見詰めている間に、ミザリイは奥の部屋から椅子をひとつ運んで来て、来客の為に茶を淹れていた。
「すまんな、ヨウスケよ。コリンはいつもこうなのだ。未知の魔導具を見ると暫くそれに魅了され動けなくなる。まあ、これだけの品々を目の前にしたらこうなるのは目に見えていたがな。しかし、異世界の者がおってもそれには全く興味を抱かんとは……」
ミザリイはそういい、また溜息をひとつ零した。
しかし、コリンはそれに対して反応を示す。用意された椅子に座らず、工具をじいっと見つめたまま。
「いやいや、異世界人には興味があるよ。しかし、ね、この魔導具たちへの興味がそれを完全に上回ってしまってるんだ。申し送れたね、私の名はコリン・ルール・ジイル。それにしても、これほどの数の未知の魔導具を一度に見るのは、生まれて初めてだよ!ひとつでも凄いことなのにね!」とコリンは依然工具に目を奪われたまま歓喜の声を上げていた。
異世界人に興味はあると言ってはいるが、工具と比べたら百分の一程度しかないのかもしれない。
「で、どうだ?貴様の手に負えそうな代物か?」
ミザリイは普段通り冷静な口調だった。狂喜してるコリンとは至極対照的だ。
「それは……まだ、なんとも言えないねえ。えーっと、異世界人……名前は確か、ヨウスケと言ったかな?」
コリンはこちらに目を向けずに問い掛けてくる。
「ああ、そうだけど……」
「へえ、本当に魔力疎通が出来るのか。魔力制御も出来ない人間がね!まあ、取り合えず、今はそれはさて置き。この道具類には、それぞれ決まった役割とか用途があるんだろう?」
「ああ、そうだね。個々それぞれ使用目的が違う物ばかりだよ」
「それを、キミは全て熟知している?もしくは完璧に使い熟せるかな?」
この全く人間に興味を抱かない魔女は、元の世界で言うところの職人と呼ばれる存在なのだろう。興味がある物に対する集中力が正にそれと同等だと感じた。
「そこにある工具の使い方は熟知してるよ。ほぼ毎日の様に使うものばかりだから」
「へえ、これほど多様な道具をほぼ毎日、ね。では、キミは元居た世界ではそれほど難解な仕事に取り組んでいた、という認識でいいかな?」
そう問われ少し考える。工作機械のエンジニアと言う仕事は、確かに誰しもがすぐに熟せる仕事ではない。長年毎日やっていると、それ程特別な仕事とは段々感じなくなっては来るけれど。それを踏まえておれは「そうだね、それなりに難解な仕事だと思う」と答えた。
それは恐らく、この世界の文明レベルから見れば、どう考えても別次元の技術を取り扱った仕事だと、認識があったから。
「いや、そうだろうね。何となく、使用目的の想像がつく物もあるけれど、コレなんて全く何に使うのか分からないよ、私には……」
そう言い、コリンが指さしたのは、六角レンチセットだった。
六角穴ボルトが無いこの世界では正に無用長物と言える物だろう。想像出来なくて当然だと思う。
第一、この世界にはまだ螺子 自体が無いだろうし。
「その工具は、物と物を繋ぎ合わせる時に使用する螺子を締め込む時に使用するものだよ」
「へえ!物と物を繋ぎ合わせる、ねじ、か。その、ねじはこの中には無いのかな?」
「螺子は無いね」
「そうか、残念だ。その、ねじは様々な大きさがあるのかい?例えば、この道具は八種類の大きさがあるのだけれど、その分、ねじにも種類がある?」
「その通り。だけど、螺子にはもっと多くの種類があって、その工具ももっと多くの種類がある。もっと言えば、このドライバーと、これとこれとこれとかも、螺子を締めたり緩めたりする道具だよ」
おれがそう告げると、コリンは初めてこちらへと顔を向けた。
キラキラと目を輝かせておれのことを見ている。いや、そもそも瞳の色が金色掛かっているのだ。美しい瞳だった。
「ちょ、ちょっと教えて欲しい。一体なぜ、異世界では、物と物を繋ぎ合わせるのに、それ程多種多様な、ねじを創り出す必要があったんだい?」
そう訊ねられ。おれは思わず苦い笑みを零した。
仕事をしていて幾度となくそうそう感じたことがあったから。しかし、それを真面目に答えるとしたら……。
「それは……多種多様な機械があるからかな。大きいものから小さいものまで。精度を要求されるものもあれば、取り合えず固く締まってあればいいってものもあるしね。おれが住んでいた世界では、用途に合わせて突き詰めなければ仕事が貰えないから。突き詰めれば突き詰めるほど……細かい差異が生まれて、日に日に様々な部品が生まれて、それに合わせて工具も生まれる。こんな感じの説明で、いいかな?」
「ああ、説明としては申し分ないね。取り合えず、ひとつ分かったことは、ミザリイ?この異世界人は、私たちの世界よりも遥かな高度な文明を育んだ世界から、こちらの世界にやって来た、と言う事だ。これは凄いことだよ……」
コリンはそういうと、漸くミザリイが用意した椅子に腰かけて、少し冷めたであろう茶をごくごくと飲んでいた。
ミザリイは、おれの対面に座り何やら分厚い書物を読んでいる。
今までは、おれの為に何かと時間を割いてくれていたが、ある程度の説明責任と身の回りの世話を終えた彼女は、普段の魔女生活へと回帰するという事なのだろう。
魔女道を極めるのが、彼女の仕事なのだから、いつまでもおれ一人の面倒をみていられないのは道理で、それに関しておれは現状を受け入れるしかない。
しかし、このままボケっと茶を飲んで時を過ごすのは時間を無駄にしてる様な感じがするので、必要最低限の問い掛けをしてみることにした。
「ミザリイ?本を読みながらでいいから、いくつか質問してもいいかい?」
それに対し、ミザリイは茶をひと口飲み、ちらりとこちらへ目を向けた。美しい碧眼だ。思わずうっとりと見入ってしまう。
「うむ、全然構わぬ。貴様と会話することにより、私も得られることが多々ある故、遠慮せずに申してみよ」
「まず、この工具だけど、一旦、工具箱の中へ仕舞っても構わないだろうか?」
そう問い掛けると、彼女は即答せずに、工具と工具箱を交互に見つめていた。
そして「――いや、今はまだ止めておけ。後で、魔導具に詳しい者が訪れる故、その者が来てからするべきだ」と言い、再び本へと目を移した。
「と言う事は、今はまだ触れない方がいいってこと?」
「そうするべきだろうな。得体の知れぬ魔導具は専門家に任せた方が安全だ。まあ、既に痛い目にあっている貴様には、それについてくどくどと説明する必要はなかろう」
それはごもっともで。それに関してはこちらから何も言い分は無い。
改めて、整然と並べてある工具へと視線を移した。
それから眼前に腕時計を持ってきた。今までの経緯から、この腕時計が既にチート的な魔導具の可能性がある。
この世界の言葉を全く理解しておらず、その上魔力制御も出来ないおれが、魔女にしか出来ない魔力疎通とやらを難なくしてしまえているのだから、それは間違いなくチートと言えるだろう。
燃えて無くなってしまったが、着ていた作業服も致命傷に至るほどの
そうなると、この工具たちにも自ずと期待感が湧いてくる。
これって、ネットゲームのガチャを回す前の感覚に似ているな、と思わず笑みが零れた。
今後の生活がモロに掛かっているから、課金出来るなら全財産注ぎ込んで廃課金者として名を馳せたいくらいだ。
「どうした、何かおもしろいことでもあったか?」とミザリイ。
読書をしていてもなんやかんやで、おれのことを意識してくれてはいる様だ。
「あ、いや、少し思い出し笑い、かな。あのさ?後で来る魔導具に詳しい人って、魔女なのかい?」
「うむ、同じ魔女同盟の者だ。コリンという。貴様の火傷の処置をしたアリアの妹弟子にあたる」
「そうか、火傷の処置をしてくれた魔女もいるって言ってたよな。ぜひ、その人にもお礼を言いたいんだけど」
「アリアなら、明日あたり顔を出すであろう。あの者は自分の患者をずっと放っておくような無責任なことはせぬから」
それを聞き、おれは一旦体重を背もたれに預けた。
考えれば考えるほど、至れり尽くせりで運がいいなと思えてくる。
あれほどの業火に焼かれて、僅か数日でここまで回復しているのだから、これ以上の幸せは現状望むことは出来なかった。
その上、この目の前の工具が全てチート級の魔導具だったとしたら……おれの異世界生活は案外捨てたモノでは無いのかもしれない。
「ミザリイ?あのさ?身体が完全に癒えて、この工具の使い道が判明して、ある程度日常会話が出来る程度に言葉を覚えたら……おれは、それからどういう風に生きて行けばいいかな?」
おれがそう言うと、彼女はぱたりと本を閉じてテーブルの上に置いた。
「取り合えず、私の支配域に属しておる集落にでも行ってみればいい。人口三十数名程度の小さな集落だが、この世界の現実を見るには丁度良いかもしれん」
「それって、おれ一人で行っていいのかい?」
「うむ、構わん。ここで養生してる間に、魔獣か幻獣を手懐けれれば、それらを連れて行っても構わんしな」
彼女はそういうが、六本足の獣や空中をふわふわと浮いている得体の知れないモノを簡単に手懐けれるとは思えなかった。おれは特に動物好きってわけでも無いから。
「けど、ここにいる魔獣とか幻獣ってミザリイが使役してるんだろう?それをおれが手懐けて連れて行ってもいいのかい?」
「支配域にいる全ての獣を私が使役してるわけではない。しかし、別に使役してる獣でも全然連れて行って構わん。その点に関して貴様が気にする必要はない。好きな獣を連れて行けば良い」
そう言うと彼女は「なんだ、もう来おったのか」と言い右手を上げて、ぱちりと指を鳴らした。
あの緋色の魔女が来た時と同じだった。このタイミングなので、恐らく来たのは魔導具に詳しい魔女……という事なのだろう。
ミザリイが指を鳴らしてから、すぐに扉が開く。
黄色いローブに身を包んだ女性がつかつかと足早に入って来た。
まずおれの顔を見て、ミザリイを見て、それからテーブルの上の工具に目を向けると挨拶も無しにテーブルへと近づいた。床へ膝をつき、食い入るように工具を見詰めている。
それを見たミザリイは「はあああ」と深い溜息を漏らした。「コリンよ?魔女であるならば、室内に入った時ははまず帽子を取りローブを脱げ。全く、カーリーといいコリンと言い、どうして我が同盟には礼儀知らずの魔女が多いのか……」ミザリイはそう言って立ち上がり、テーブル前から微動だにしないコリンへと歩み寄った。
そして、彼女から帽子を取りローブを剥ぎ取り丁寧に畳んで棚へと置いていた。
二人の関係性が垣間見える。
コリンは栗色の髪を背中辺りで一つに束ねていた。他の魔女と同じく、極めて露出度の高い黒いワンピースを身に着けている。
ミザリイが誰しもが認めるであろう美少女タイプだとしたら、コリンは知的な美人さんと言ったところか。
コリンが夢中で工具を見詰めている間に、ミザリイは奥の部屋から椅子をひとつ運んで来て、来客の為に茶を淹れていた。
「すまんな、ヨウスケよ。コリンはいつもこうなのだ。未知の魔導具を見ると暫くそれに魅了され動けなくなる。まあ、これだけの品々を目の前にしたらこうなるのは目に見えていたがな。しかし、異世界の者がおってもそれには全く興味を抱かんとは……」
ミザリイはそういい、また溜息をひとつ零した。
しかし、コリンはそれに対して反応を示す。用意された椅子に座らず、工具をじいっと見つめたまま。
「いやいや、異世界人には興味があるよ。しかし、ね、この魔導具たちへの興味がそれを完全に上回ってしまってるんだ。申し送れたね、私の名はコリン・ルール・ジイル。それにしても、これほどの数の未知の魔導具を一度に見るのは、生まれて初めてだよ!ひとつでも凄いことなのにね!」とコリンは依然工具に目を奪われたまま歓喜の声を上げていた。
異世界人に興味はあると言ってはいるが、工具と比べたら百分の一程度しかないのかもしれない。
「で、どうだ?貴様の手に負えそうな代物か?」
ミザリイは普段通り冷静な口調だった。狂喜してるコリンとは至極対照的だ。
「それは……まだ、なんとも言えないねえ。えーっと、異世界人……名前は確か、ヨウスケと言ったかな?」
コリンはこちらに目を向けずに問い掛けてくる。
「ああ、そうだけど……」
「へえ、本当に魔力疎通が出来るのか。魔力制御も出来ない人間がね!まあ、取り合えず、今はそれはさて置き。この道具類には、それぞれ決まった役割とか用途があるんだろう?」
「ああ、そうだね。個々それぞれ使用目的が違う物ばかりだよ」
「それを、キミは全て熟知している?もしくは完璧に使い熟せるかな?」
この全く人間に興味を抱かない魔女は、元の世界で言うところの職人と呼ばれる存在なのだろう。興味がある物に対する集中力が正にそれと同等だと感じた。
「そこにある工具の使い方は熟知してるよ。ほぼ毎日の様に使うものばかりだから」
「へえ、これほど多様な道具をほぼ毎日、ね。では、キミは元居た世界ではそれほど難解な仕事に取り組んでいた、という認識でいいかな?」
そう問われ少し考える。工作機械のエンジニアと言う仕事は、確かに誰しもがすぐに熟せる仕事ではない。長年毎日やっていると、それ程特別な仕事とは段々感じなくなっては来るけれど。それを踏まえておれは「そうだね、それなりに難解な仕事だと思う」と答えた。
それは恐らく、この世界の文明レベルから見れば、どう考えても別次元の技術を取り扱った仕事だと、認識があったから。
「いや、そうだろうね。何となく、使用目的の想像がつく物もあるけれど、コレなんて全く何に使うのか分からないよ、私には……」
そう言い、コリンが指さしたのは、六角レンチセットだった。
六角穴ボルトが無いこの世界では正に無用長物と言える物だろう。想像出来なくて当然だと思う。
第一、この世界にはまだ
「その工具は、物と物を繋ぎ合わせる時に使用する螺子を締め込む時に使用するものだよ」
「へえ!物と物を繋ぎ合わせる、ねじ、か。その、ねじはこの中には無いのかな?」
「螺子は無いね」
「そうか、残念だ。その、ねじは様々な大きさがあるのかい?例えば、この道具は八種類の大きさがあるのだけれど、その分、ねじにも種類がある?」
「その通り。だけど、螺子にはもっと多くの種類があって、その工具ももっと多くの種類がある。もっと言えば、このドライバーと、これとこれとこれとかも、螺子を締めたり緩めたりする道具だよ」
おれがそう告げると、コリンは初めてこちらへと顔を向けた。
キラキラと目を輝かせておれのことを見ている。いや、そもそも瞳の色が金色掛かっているのだ。美しい瞳だった。
「ちょ、ちょっと教えて欲しい。一体なぜ、異世界では、物と物を繋ぎ合わせるのに、それ程多種多様な、ねじを創り出す必要があったんだい?」
そう訊ねられ。おれは思わず苦い笑みを零した。
仕事をしていて幾度となくそうそう感じたことがあったから。しかし、それを真面目に答えるとしたら……。
「それは……多種多様な機械があるからかな。大きいものから小さいものまで。精度を要求されるものもあれば、取り合えず固く締まってあればいいってものもあるしね。おれが住んでいた世界では、用途に合わせて突き詰めなければ仕事が貰えないから。突き詰めれば突き詰めるほど……細かい差異が生まれて、日に日に様々な部品が生まれて、それに合わせて工具も生まれる。こんな感じの説明で、いいかな?」
「ああ、説明としては申し分ないね。取り合えず、ひとつ分かったことは、ミザリイ?この異世界人は、私たちの世界よりも遥かな高度な文明を育んだ世界から、こちらの世界にやって来た、と言う事だ。これは凄いことだよ……」
コリンはそういうと、漸くミザリイが用意した椅子に腰かけて、少し冷めたであろう茶をごくごくと飲んでいた。