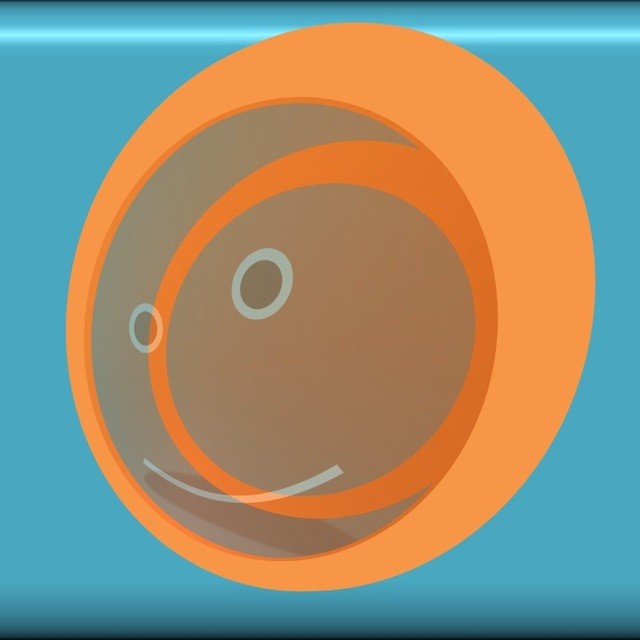第1話:それは言い得て妙だな。
文字数 5,725文字
――今、おれの目の前には一人の少女がいる。
その淡い碧色の双眸で、こちらをじいっと見詰めていた。
時折、長く美しい金髪を掻き上げる仕草に目を引かれる。
とても美しい少女だ。少々性格はきつそうだが、モデルや女優としても通用しそうな顔立ちでスタイルだった。
しかし彼女は自分の事を「私は、魔女だ」という。
それに対しておれは一度天を仰ぎ、それから今一度彼女と視線を重ねて「その魔女ってのは、魔法が使える女の子って言う意味の魔女かい?」と問い掛けてみた。
すると彼女は「その認識で概ね間違いでは無い。魔女とは精霊魔法と召喚魔法を体得し、錬金術や薬学にも長け、自らの版図として支配域を有している女性の事を指す呼称だ」と、少し冷たく少し早い口調でそう言った。
出逢った時から、彼女の表情は硬い。
こちらに敵対心は抱いてなさそうだが、警戒はしている様に見える。
おれは、森の中で彼女と出会い、それからすぐに家に招き入れられていた。
そこは森の中の開けた土地に、一軒だけある家だった。
色褪せた煉瓦造りで、濃い赤色の瓦葺き屋根には所々苔が生え、壁には蔓草が絡まり伸びていた。
魔女、と聞きおれは今一度室内をぐるりと見まわす。平屋で外から見た感じよりも広い部屋だった。
おれが今いるのはダイニングと言ったところだろうか。奥に視線を向けると、別の部屋がありベッドが置いてあるのが見えた。
その他の特徴は、大きな本棚が幾つかあり、その全てに分厚い本が綺麗に並べられている。
茸類や野草などと、石や金属などが大雑把に仕分けされてそうな木の箱が幾つかあり、理科の実験に使いそうな小道具もそこかしこに散見される。
それらを踏まえて、おれは自称魔女へと視線を戻した。
彼女は森の中では、真っ黒な鍔の広い帽子を目深に被り、丈長のローブを身に纏っていたが、室内に入ると黒いワンピースだけの姿となっていた。
身体のラインが露わとなり、目のやり場に困ってしまう格好だった。
如何にも魔女らしいとは言えるのだろうけど。
いや、彼女が魔女かどうかはさて置き、肝が据わっているのは確かだ。
あの森の空き地でテンパっていた、見ず知らずおれを「落ち着け、馬鹿者!」と一喝して部屋に招き入れてくれたのだから。
そして、今は物怖じする様子無く、おれの言葉をじいっと待ってくれている。
それは中々出来る事では無いと思った。
冷静沈着な彼女の様子を見て、おれは漸く落ち着きを取り戻せた訳だから、その言葉に多少冷たさを感じたとしても感謝しなけらばならないだろう。
「――では、幾つか、質問をしてもいいかな?」とおれは声を掛けた。
彼女はおれの目を見据えたまま頷き「構わん。貴様にはその権利がある」と言う。
「権利がある?おれに?」
「うむ、それに関しては後で説明してやろう。今は、貴様が問いたい事を問いたいだけ問うが良い。そうする事で、私は貴様が何を知り何を知らぬか把握出来るし、貴様に対する認識も深まるからな」
森の中で、彼女と出会ってから三十分程度過ぎただろうか。
金髪で淡い青色の瞳、透き通る様な白い肌。どう見ても西洋人だけれど、彼女は実に上手く日本語を使っていた。
その口調は容姿に見合わない堅苦しい感じ。タメ口をつかうハーフタレントの様な雰囲気も無くはない。
「えーっと、では、まず初めに……そうだな、おれは、今日と言うか、ついさっきまで得意先の工場で先輩と工作機のメンテナンスをしてた、筈なんだ。その証拠に、今着てるこれ――」
おれはそう言って、その場に立ち上がった。
今更その必要は無かったかも知れないが、少しでも彼女に今の置かれてる現状を理解して欲しいという思いが強かった。
「この作業着さ、メンテナンスをする時に油まみれになるから、その時にしか着ない作業着なんだよ。作業帽被ってるし、安全靴を履いてる。そう、そうだ、確か、田中さんから、赤い工具箱を取ってきてくれって言われて、それで……」
自身の記憶を辿りつつ、おれはそう呟く様に言っていた。そして遅ればせながら作業帽を取り手に握り締めた。
ぽつりぽつりと吐いた言葉は質問と言うよりか、只の独り言でしか無く、それに対して彼女が口を開く事は無かった。
おれは頭の中で何度も何度も同じ記憶をなぞる。
朝早く起きて、コンビニで朝食を買い、運転しながら朝食を食べ、ラジオから流れる音楽を口ずさみ、得意先の工場で田中さんと落ち合って、それから設備診断に入り、工具箱を取りに行って、落雷の様な音がして、真っ黒な球体があって、それに触れて、視界と意識が閉じて……気が付くと森の中。
あの真っ黒な球体が現れるまで、何か特別な事は一切無かった筈だ。
朝早いのは毎度の事で、ほぼ毎日寄るコンビニで買い物し、毎日乗る車を運転し、お決まりのFMで、過去何度も訪れている得意先の工場で、いつもしてる仕事を、おれはいつも通りにしていただけ。
思考の深みに嵌ると、パニックに陥りそうになってしまう。
いつもの日常と、自称魔女の金髪美少女と向き合って会話してる現状が、全く繋がらない。
記憶に明らかな空白があるのだ。それが堪らなく不安だった。もう三十五になるいい大人だが、情緒が保てず目に涙が浮かんでしまった。
「どうした、質問はしないのか?」と、彼女は先ほどよりも幾分穏やかな口調でそう語り掛けてくれた。
こちらの心境を少しは察してくれているのかもしれない。
「すまない、取り乱してしまった。あの、質問の前に、キミの名前を教えてくれるかい?」
「ふむ、私の名は、ミザリイ・アート・ココレイトだ。ミザリイと呼ぶがよい。で、貴様の名は?」
「おれの名は安達、陽介。陽介で、いいよ」
「ふむ、アダチ・ヨウスケとは、また聞き慣れない名だな。国は何処だ?顔立ちからして、遥か東南域に住む民族の様にも見えるが」
ミザリイの表情は相変わらず硬いままだが、お互い名を知り会話が進展し始めた事に、おれは幾許かの安堵を手にしていた。
「国は、日本だよ。ミザリイだって日本語喋ってるんだから、それは分かるだろう?お父さんかお母さんが日本人なのかな?それとも日本在住が長い?いや、最近は日本のアニメとかドラマが流行ってるからそれで日本語覚える外国人も多いって聞くからなあ。あ、ごめん、国ってもしかして故郷の事だった?」気持ちにゆとりが出来たからか、おれはついつい多弁となってしまう。
記憶の空白は解消されて無いが、落ち着いて話を聞いてくれる人がいるのは何より心強い。
しかし、おれの話を聞きつつミザリイは眉を顰 めていた。
漸く崩れた表情が困り顔なのは、残念でしかない。折角の美しい顔なのに。
「あの、ごめん、おれ、調子に乗って喋り過ぎたかな?」とおれは声のトーンを戻しそう言った。
「ああ、いや、構わん、気にするな。実に愚かな事だが、私は、事の重大さに今し方気が付いてしまったのだ。ちなみに、先ほどの貴様の言葉に対し、幾つか返答しておくと、私の父と母はニホン人では無いし、ニホン語も話して無いし、ここはニホン国では無いし、そもそも私の知る限りニホンと言う名の国家は歴史上存在してない。有史前の人類黎明期に興った国家であれば、或いは存在するのかもしれないが……」と彼女は日本語で、そう言う。
おれの耳には十分全うで流暢な日本語にしか聞こえない。
日本語を知らない者が「有史前の人類黎明期」なんて普通の日本人でもあまり使わない言葉をすらすらと使える筈が無い訳だし。
「いや、あの、ミザリイは十分に日本語を喋れてるよ?そんなに謙遜する必要は無いと思うけど?おれ、何人か外国人と一緒に働いたことあるけど、ここまで流暢に喋れるやつは一人もいないしな」
おれの言葉を受け、彼女はまた眉を顰めていた。
「ん?もしや、貴様、自分が魔力疎通で会話してる事に気が付いておらんのか?」
「へ?魔力、疎通?いや、ごめん、多分、気が付いて無いと、思うけど」
「自身の思考をマナに変換して直接相手の思考へと語り掛ける、所謂これも立派な魔法だ。いきなり私に対して断りも無く魔力疎通を仕掛けてくるから、無礼なヤツだと思っておったのだが。そうか、魔力疎通を知らずにそれを行使しておったと言う訳か。成程……いや、しかし、それならば尚更奇怪と言える。要するに恐らく貴様は魔導師でも無いのであろう?何かの作業に従事しておるのか?それは魔法を扱う職では無いのだな?」
「えーっと、魔法とかとは、全く無関係の仕事だよ。真逆と言った方がいいかもしれない。兎に角、おれは魔法も超能力も使えないし、霊能力もからっきしだから」
「いやいや、だからこそ分からんと言っておるのだ。レイノウリョクやらチョウノウリョクやらは一体どの様なモノか知らんが、魔法を使えん者が魔力疎通するなど、我々の常識ではあり得んからな。ある程度経験を積んだ魔女か魔導師しか行使出来ん術だぞ?恐らく、魔法に無知な貴様に言っても理解出来んだろうけどな」
彼女とここまで噛み合わないながらも会話して、今漸くおれは、事の重大さに気が付き始めていた。
あれ、もしかして、これって……と、今更ながら、ある現象が脳裏に過る。
「あ、あの、ミザリイ?また、少し、質問があるのだけれど……」おれはそう言い、ごくりと生唾を飲み込んだ。
「ふむ、良かろう、聞きたい事は全て吐き出せ」
「えーっと、これが例えば大掛かりなドッキリとかでは無い限り、何となくだけれど、ここは、おれが元々住んでいた世界とは、違う世界の様な気がする。例えば、ミザリイはさ、アメリカとかイギリスとか中国とかロシアとかって国、知ってる?」
その問い掛けに対し彼女は首を横に振り「それは知らん。が、貴様の言いたい事は分かる」と言った。
そして彼女は言葉を続ける。
「今口にした、アメリカやらイギリスやらは、貴様の世界の有名な国なのであろう?それを知らぬ者は世の中にはいないであろう国々の名、なのであろうな。要するに、私の世界で言うところのパルティアやエニグマ、トロイデンと言ったところか。いや、似たような地名や単語はあるやもしれんな。しかし、双方の世界で共通する超大国は無いという事か。まだ断定するには尚早かもしれんが、これで貴様の置かれた状況は概ね掌握出来た」
ミザリイはそこで言葉を切ると、ふうと息を吐き、若干緊張を解いた様な雰囲気を醸し出す。
その反面、おれは自身の境遇に驚愕し、頭の中が真っ白になっていた。
暫く茫然としていると、ミザリイは席を立ち、鍋で湯を沸かし陶磁器の器に茶を入れて出してくれた。
それが何茶なのか詮索する余裕は無かったが、おれは兎に角、何とか冷静になろうと思い、一口飲み喉を潤す。
薄味だが、匂いが良く後味のすっきりとした美味い茶だった。
おれが落ち着きを取り戻すのを、彼女は自身の茶をゆっくりと堪能しつつ待ってくれていた。
彼女のその姿勢に、おれは度々救われる。あれやこれやと問い質されたら、恐らく何かが判明する度にパニックを引き起こしてしまっていただろうから。
おれは、茶をもう一口飲んでから、語り始めた。
「要するに、おれは、別の世界から、この世界へと転生……いや転移か?一回死んで別の人物になってたら転生だけど、どうやらおれはおれのままだから転移ってことでいいのか?えーっと、それってさ、おれの世界では、異世界転移って言うんだけど……」
「ほう、異世界転移とな。それは言い得て妙だな。今後は私もそう言う様にしよう。それにしても、そう言う言葉があるくらいだから、貴様の世界では、その異世界転移とやらが頻繁に起こっている、という事なのだな?」
「あ、いや、頻繁って言うか、そう言う現象を描いた創作物が多いと言うか、そう言う現象に憧れている人が結構いる、と言うか……」
「異世界転移が憧れ?では、貴様も今置かれてる境遇は、好ましく感じているのか?満更でも無いと?」
「いやいや、好ましくは、無い、かな。そう言った創作物を観たり読んだりするのは好きだったけど、いざ自分がそうなってみると、これからどうすればいいか全然分からないし、全く別の世界に来て無事に生きて行ける自信は無いし、さ。あの、ミザリイ?」
「うむ、どうした?」
「ミザリイは魔女なんだろう?」
「うむ、そうだな。魔女であり、今は貴様を召喚した召喚主だ」
「ん?おれを召喚した?ミザリイが?おれを?なんで?」
「なんで、と問われても、それは分からん。解読中の古文書にあった魔法陣を描いて発動させた結果、貴様をこの世界に召喚してしまった、だけだからな。貴様の世界で言うところの異世界転移か。別に私は、貴様を狙って魔法陣を発動させた訳では無いから。しかし、経緯はどうあれ、召喚主として貴様を見捨てる事は出来んからな、こうして親身に相談に乗っておる次第だ。他に何か問いたい事はあるか?」
そう言うとミザリイは茶を一気に飲み干し、立ち上がった。
立っても、座っているおれより少し高い程度の身長だった。
「他に質問は……多分、沢山あるんだけど、今は頭が混乱してて……」
「そうか、では今から貴様の身体に魔紋を刻む故、その場で服を脱げ」
そう言うと彼女はテーブルの対面側から、歩み寄って来る。
おれは状況が飲み込めず、立ち上がり後退って彼女と距離を取った。
「え、ちょっと待って、ミザリイ?身体に刻むって、何を?」
「魔紋だ。私が、貴様の召喚主として、所有者としての証。本来は魔獣や幻獣か奴隷に刻むのだがな、貴様は現状取り扱いが不明だから取り合えず刻んでおく。万が一他の魔女に目を付けられて横取りされるのは胸糞悪いからな。ほれ、さっさと服を脱げ。暴れるでないぞ?じっとしておれば、然程痛みは感じんはずだ……」
そう言うと、ミザリイはじわりじわりと、おれを壁際にまで追い込んできた。
その淡い碧色の双眸で、こちらをじいっと見詰めていた。
時折、長く美しい金髪を掻き上げる仕草に目を引かれる。
とても美しい少女だ。少々性格はきつそうだが、モデルや女優としても通用しそうな顔立ちでスタイルだった。
しかし彼女は自分の事を「私は、魔女だ」という。
それに対しておれは一度天を仰ぎ、それから今一度彼女と視線を重ねて「その魔女ってのは、魔法が使える女の子って言う意味の魔女かい?」と問い掛けてみた。
すると彼女は「その認識で概ね間違いでは無い。魔女とは精霊魔法と召喚魔法を体得し、錬金術や薬学にも長け、自らの版図として支配域を有している女性の事を指す呼称だ」と、少し冷たく少し早い口調でそう言った。
出逢った時から、彼女の表情は硬い。
こちらに敵対心は抱いてなさそうだが、警戒はしている様に見える。
おれは、森の中で彼女と出会い、それからすぐに家に招き入れられていた。
そこは森の中の開けた土地に、一軒だけある家だった。
色褪せた煉瓦造りで、濃い赤色の瓦葺き屋根には所々苔が生え、壁には蔓草が絡まり伸びていた。
魔女、と聞きおれは今一度室内をぐるりと見まわす。平屋で外から見た感じよりも広い部屋だった。
おれが今いるのはダイニングと言ったところだろうか。奥に視線を向けると、別の部屋がありベッドが置いてあるのが見えた。
その他の特徴は、大きな本棚が幾つかあり、その全てに分厚い本が綺麗に並べられている。
茸類や野草などと、石や金属などが大雑把に仕分けされてそうな木の箱が幾つかあり、理科の実験に使いそうな小道具もそこかしこに散見される。
それらを踏まえて、おれは自称魔女へと視線を戻した。
彼女は森の中では、真っ黒な鍔の広い帽子を目深に被り、丈長のローブを身に纏っていたが、室内に入ると黒いワンピースだけの姿となっていた。
身体のラインが露わとなり、目のやり場に困ってしまう格好だった。
如何にも魔女らしいとは言えるのだろうけど。
いや、彼女が魔女かどうかはさて置き、肝が据わっているのは確かだ。
あの森の空き地でテンパっていた、見ず知らずおれを「落ち着け、馬鹿者!」と一喝して部屋に招き入れてくれたのだから。
そして、今は物怖じする様子無く、おれの言葉をじいっと待ってくれている。
それは中々出来る事では無いと思った。
冷静沈着な彼女の様子を見て、おれは漸く落ち着きを取り戻せた訳だから、その言葉に多少冷たさを感じたとしても感謝しなけらばならないだろう。
「――では、幾つか、質問をしてもいいかな?」とおれは声を掛けた。
彼女はおれの目を見据えたまま頷き「構わん。貴様にはその権利がある」と言う。
「権利がある?おれに?」
「うむ、それに関しては後で説明してやろう。今は、貴様が問いたい事を問いたいだけ問うが良い。そうする事で、私は貴様が何を知り何を知らぬか把握出来るし、貴様に対する認識も深まるからな」
森の中で、彼女と出会ってから三十分程度過ぎただろうか。
金髪で淡い青色の瞳、透き通る様な白い肌。どう見ても西洋人だけれど、彼女は実に上手く日本語を使っていた。
その口調は容姿に見合わない堅苦しい感じ。タメ口をつかうハーフタレントの様な雰囲気も無くはない。
「えーっと、では、まず初めに……そうだな、おれは、今日と言うか、ついさっきまで得意先の工場で先輩と工作機のメンテナンスをしてた、筈なんだ。その証拠に、今着てるこれ――」
おれはそう言って、その場に立ち上がった。
今更その必要は無かったかも知れないが、少しでも彼女に今の置かれてる現状を理解して欲しいという思いが強かった。
「この作業着さ、メンテナンスをする時に油まみれになるから、その時にしか着ない作業着なんだよ。作業帽被ってるし、安全靴を履いてる。そう、そうだ、確か、田中さんから、赤い工具箱を取ってきてくれって言われて、それで……」
自身の記憶を辿りつつ、おれはそう呟く様に言っていた。そして遅ればせながら作業帽を取り手に握り締めた。
ぽつりぽつりと吐いた言葉は質問と言うよりか、只の独り言でしか無く、それに対して彼女が口を開く事は無かった。
おれは頭の中で何度も何度も同じ記憶をなぞる。
朝早く起きて、コンビニで朝食を買い、運転しながら朝食を食べ、ラジオから流れる音楽を口ずさみ、得意先の工場で田中さんと落ち合って、それから設備診断に入り、工具箱を取りに行って、落雷の様な音がして、真っ黒な球体があって、それに触れて、視界と意識が閉じて……気が付くと森の中。
あの真っ黒な球体が現れるまで、何か特別な事は一切無かった筈だ。
朝早いのは毎度の事で、ほぼ毎日寄るコンビニで買い物し、毎日乗る車を運転し、お決まりのFMで、過去何度も訪れている得意先の工場で、いつもしてる仕事を、おれはいつも通りにしていただけ。
思考の深みに嵌ると、パニックに陥りそうになってしまう。
いつもの日常と、自称魔女の金髪美少女と向き合って会話してる現状が、全く繋がらない。
記憶に明らかな空白があるのだ。それが堪らなく不安だった。もう三十五になるいい大人だが、情緒が保てず目に涙が浮かんでしまった。
「どうした、質問はしないのか?」と、彼女は先ほどよりも幾分穏やかな口調でそう語り掛けてくれた。
こちらの心境を少しは察してくれているのかもしれない。
「すまない、取り乱してしまった。あの、質問の前に、キミの名前を教えてくれるかい?」
「ふむ、私の名は、ミザリイ・アート・ココレイトだ。ミザリイと呼ぶがよい。で、貴様の名は?」
「おれの名は安達、陽介。陽介で、いいよ」
「ふむ、アダチ・ヨウスケとは、また聞き慣れない名だな。国は何処だ?顔立ちからして、遥か東南域に住む民族の様にも見えるが」
ミザリイの表情は相変わらず硬いままだが、お互い名を知り会話が進展し始めた事に、おれは幾許かの安堵を手にしていた。
「国は、日本だよ。ミザリイだって日本語喋ってるんだから、それは分かるだろう?お父さんかお母さんが日本人なのかな?それとも日本在住が長い?いや、最近は日本のアニメとかドラマが流行ってるからそれで日本語覚える外国人も多いって聞くからなあ。あ、ごめん、国ってもしかして故郷の事だった?」気持ちにゆとりが出来たからか、おれはついつい多弁となってしまう。
記憶の空白は解消されて無いが、落ち着いて話を聞いてくれる人がいるのは何より心強い。
しかし、おれの話を聞きつつミザリイは眉を
漸く崩れた表情が困り顔なのは、残念でしかない。折角の美しい顔なのに。
「あの、ごめん、おれ、調子に乗って喋り過ぎたかな?」とおれは声のトーンを戻しそう言った。
「ああ、いや、構わん、気にするな。実に愚かな事だが、私は、事の重大さに今し方気が付いてしまったのだ。ちなみに、先ほどの貴様の言葉に対し、幾つか返答しておくと、私の父と母はニホン人では無いし、ニホン語も話して無いし、ここはニホン国では無いし、そもそも私の知る限りニホンと言う名の国家は歴史上存在してない。有史前の人類黎明期に興った国家であれば、或いは存在するのかもしれないが……」と彼女は日本語で、そう言う。
おれの耳には十分全うで流暢な日本語にしか聞こえない。
日本語を知らない者が「有史前の人類黎明期」なんて普通の日本人でもあまり使わない言葉をすらすらと使える筈が無い訳だし。
「いや、あの、ミザリイは十分に日本語を喋れてるよ?そんなに謙遜する必要は無いと思うけど?おれ、何人か外国人と一緒に働いたことあるけど、ここまで流暢に喋れるやつは一人もいないしな」
おれの言葉を受け、彼女はまた眉を顰めていた。
「ん?もしや、貴様、自分が魔力疎通で会話してる事に気が付いておらんのか?」
「へ?魔力、疎通?いや、ごめん、多分、気が付いて無いと、思うけど」
「自身の思考をマナに変換して直接相手の思考へと語り掛ける、所謂これも立派な魔法だ。いきなり私に対して断りも無く魔力疎通を仕掛けてくるから、無礼なヤツだと思っておったのだが。そうか、魔力疎通を知らずにそれを行使しておったと言う訳か。成程……いや、しかし、それならば尚更奇怪と言える。要するに恐らく貴様は魔導師でも無いのであろう?何かの作業に従事しておるのか?それは魔法を扱う職では無いのだな?」
「えーっと、魔法とかとは、全く無関係の仕事だよ。真逆と言った方がいいかもしれない。兎に角、おれは魔法も超能力も使えないし、霊能力もからっきしだから」
「いやいや、だからこそ分からんと言っておるのだ。レイノウリョクやらチョウノウリョクやらは一体どの様なモノか知らんが、魔法を使えん者が魔力疎通するなど、我々の常識ではあり得んからな。ある程度経験を積んだ魔女か魔導師しか行使出来ん術だぞ?恐らく、魔法に無知な貴様に言っても理解出来んだろうけどな」
彼女とここまで噛み合わないながらも会話して、今漸くおれは、事の重大さに気が付き始めていた。
あれ、もしかして、これって……と、今更ながら、ある現象が脳裏に過る。
「あ、あの、ミザリイ?また、少し、質問があるのだけれど……」おれはそう言い、ごくりと生唾を飲み込んだ。
「ふむ、良かろう、聞きたい事は全て吐き出せ」
「えーっと、これが例えば大掛かりなドッキリとかでは無い限り、何となくだけれど、ここは、おれが元々住んでいた世界とは、違う世界の様な気がする。例えば、ミザリイはさ、アメリカとかイギリスとか中国とかロシアとかって国、知ってる?」
その問い掛けに対し彼女は首を横に振り「それは知らん。が、貴様の言いたい事は分かる」と言った。
そして彼女は言葉を続ける。
「今口にした、アメリカやらイギリスやらは、貴様の世界の有名な国なのであろう?それを知らぬ者は世の中にはいないであろう国々の名、なのであろうな。要するに、私の世界で言うところのパルティアやエニグマ、トロイデンと言ったところか。いや、似たような地名や単語はあるやもしれんな。しかし、双方の世界で共通する超大国は無いという事か。まだ断定するには尚早かもしれんが、これで貴様の置かれた状況は概ね掌握出来た」
ミザリイはそこで言葉を切ると、ふうと息を吐き、若干緊張を解いた様な雰囲気を醸し出す。
その反面、おれは自身の境遇に驚愕し、頭の中が真っ白になっていた。
暫く茫然としていると、ミザリイは席を立ち、鍋で湯を沸かし陶磁器の器に茶を入れて出してくれた。
それが何茶なのか詮索する余裕は無かったが、おれは兎に角、何とか冷静になろうと思い、一口飲み喉を潤す。
薄味だが、匂いが良く後味のすっきりとした美味い茶だった。
おれが落ち着きを取り戻すのを、彼女は自身の茶をゆっくりと堪能しつつ待ってくれていた。
彼女のその姿勢に、おれは度々救われる。あれやこれやと問い質されたら、恐らく何かが判明する度にパニックを引き起こしてしまっていただろうから。
おれは、茶をもう一口飲んでから、語り始めた。
「要するに、おれは、別の世界から、この世界へと転生……いや転移か?一回死んで別の人物になってたら転生だけど、どうやらおれはおれのままだから転移ってことでいいのか?えーっと、それってさ、おれの世界では、異世界転移って言うんだけど……」
「ほう、異世界転移とな。それは言い得て妙だな。今後は私もそう言う様にしよう。それにしても、そう言う言葉があるくらいだから、貴様の世界では、その異世界転移とやらが頻繁に起こっている、という事なのだな?」
「あ、いや、頻繁って言うか、そう言う現象を描いた創作物が多いと言うか、そう言う現象に憧れている人が結構いる、と言うか……」
「異世界転移が憧れ?では、貴様も今置かれてる境遇は、好ましく感じているのか?満更でも無いと?」
「いやいや、好ましくは、無い、かな。そう言った創作物を観たり読んだりするのは好きだったけど、いざ自分がそうなってみると、これからどうすればいいか全然分からないし、全く別の世界に来て無事に生きて行ける自信は無いし、さ。あの、ミザリイ?」
「うむ、どうした?」
「ミザリイは魔女なんだろう?」
「うむ、そうだな。魔女であり、今は貴様を召喚した召喚主だ」
「ん?おれを召喚した?ミザリイが?おれを?なんで?」
「なんで、と問われても、それは分からん。解読中の古文書にあった魔法陣を描いて発動させた結果、貴様をこの世界に召喚してしまった、だけだからな。貴様の世界で言うところの異世界転移か。別に私は、貴様を狙って魔法陣を発動させた訳では無いから。しかし、経緯はどうあれ、召喚主として貴様を見捨てる事は出来んからな、こうして親身に相談に乗っておる次第だ。他に何か問いたい事はあるか?」
そう言うとミザリイは茶を一気に飲み干し、立ち上がった。
立っても、座っているおれより少し高い程度の身長だった。
「他に質問は……多分、沢山あるんだけど、今は頭が混乱してて……」
「そうか、では今から貴様の身体に魔紋を刻む故、その場で服を脱げ」
そう言うと彼女はテーブルの対面側から、歩み寄って来る。
おれは状況が飲み込めず、立ち上がり後退って彼女と距離を取った。
「え、ちょっと待って、ミザリイ?身体に刻むって、何を?」
「魔紋だ。私が、貴様の召喚主として、所有者としての証。本来は魔獣や幻獣か奴隷に刻むのだがな、貴様は現状取り扱いが不明だから取り合えず刻んでおく。万が一他の魔女に目を付けられて横取りされるのは胸糞悪いからな。ほれ、さっさと服を脱げ。暴れるでないぞ?じっとしておれば、然程痛みは感じんはずだ……」
そう言うと、ミザリイはじわりじわりと、おれを壁際にまで追い込んできた。