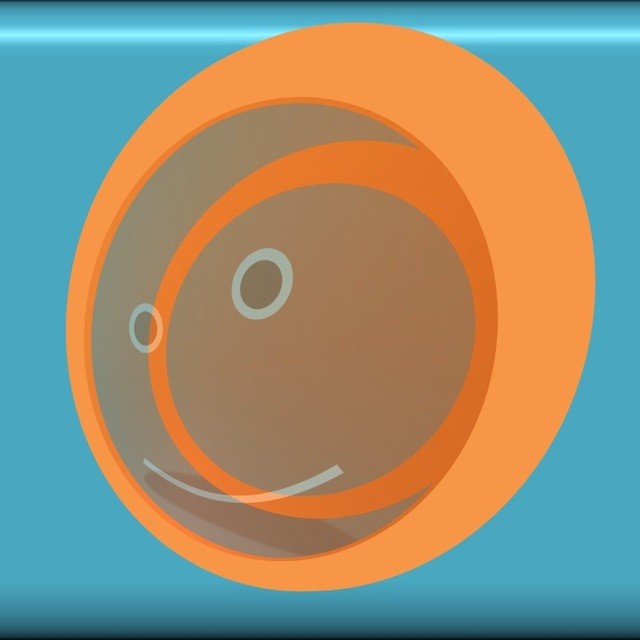第2話:鹿肉とキノコの煮込み。
文字数 4,802文字
他人に振る舞える程、料理が得意というわけでは無い。
ただ元の世界では一人暮らしで、コンビニ弁当や外食ばかりでは飽きてしまうから、仕事が定時で終わった時や、週末予定が無い時などは自炊をするようにしていた。
野菜炒めやカレーくらいなら自分好みの味に作れる程度の腕前はある。
しかし、その程度の腕前しかないおれが、異世界に来て美しい魔女二人に料理を振る舞うことになるのだから、世の中って本当にどう転ぶか分かったものでは無い。
さて、で、問題の食材。
まずはカッチカチの鹿の干し肉。もはやジャーキーと言った感じ。酒のアテには最高だと思う。支配域の集落に住む猟師がたまに持って来るらしい。
そして、色取り取りのキノコ類。乾燥してるのから生っぽいのまで色々。匂いは良いが、色味は紫系とか赤と緑とか……ヤバいのばかりが目に映る。ピンク色のエノキみたいなのって食べて平気なのだろうか?
あとは、何かしらのハーブの葉、木の実、小さな芋っぽいモノなど。
一体この食材で何が作れるのか、今のところさっぱり分からない。
次は調味料。
岩塩の塊。少しピンク色をしてるが、元の世界でもそういう色した岩塩はあったよな、と思い込み問題視するのは止めた。
あとは、黒とか緑とか赤の粉末。目を凝らして見ると、木の実か種の様な物を磨り潰している様に見えた。
依然、ミザリイが料理を作ってくれた時に、これらの粉末を鍋の中へと投じていた記憶がある。
粉末に関しては、ひとつずつ味見をするしか無い。いや、本来なら全ての食材をひとつずつ味見をするべきなのだろうけど……。
おれが食材や調味料をあれこれと手に取り調べてる間、ミザリイは茶を飲みながらおれの様子を黙って見ていた。
暇なのかと思い、調理を始める前に幾つか確認しておこうと、声を掛けた。
「――あのさ、ミザリイ、ちょっといいかな?」
「うむ、どうかしたか?」とミザリイ。普段通り、落ち着いた語り口調だ。
「おれって、魔紋刻まれてるから、少々の毒なら食べても問題無いんだろう?」
「そうだな。少々の毒なら問題無い。しかし、今、貴様が手にしておる、紫色の茸は問題有りだな。それは魔女殺しという名の茸でな、魔女でも食したら三日間腹が下るという猛毒の茸だ」
それを聞き、おれは思わず魔女殺しを手から落としてしまった。
「ちょ、ちょっと待ってくれ。他には?今テーブルの上にある食材で、食べたら問題有りなヤツはもう無い?」
何故、魔女殺しの存在を先に教えてくれなかったのか追及したかったけれど、今は押し問答をするよりも、今は自分の身を護ることに集中した方がいい、はずだ。
「――あとは、集落の者たちが持って来た食材ばかりゆえ、問題は無い筈だ。やはり、魔紋を刻んでおいて正解だったな。全ての食材の毒見なんてしておったら、先に貴様が衰弱して死んでおったであろう」
「それはそうだけど……。明らかに問題有りそうな物を食べようとしてる時は、ちゃんと止めてくれよ?それとも、人間に魔紋刻んだの初めてだから、色々様子を見てみたいって思いもあったりするのか?」
その問いに対して、ミザリイは答えずに澄ました顔で茶を啜っていた。真面目で堅物の様だが、こういう狡さは持ち合わせていると言ったところか。これに関してはおれが慣れる他ない。
「うーん、じゃあ、穀物は無いのかな?小麦とか米とか……豆とか蕎麦とかトウモロコシとか……。芋もさ、こんな痩せっぽちのじゃなくて、握り拳くらいの大きさのは無い?」
「穀物か……。集落に行けば、クロムギがあるぞ。豆もある。たまに持って来てくれるが、貴重な食糧ゆえ、私は受け取らずに持ち帰らせておるのだ。魔女は、直接的な食事は殆ど摂らんからな。芋も、集落に行けばもう少しマシなものがある、と思うが貴様の握り拳ほど大きな芋は、集落の畑では見た事が無い」
そうか、それはそうだ。おれがいた世界の農作物と同じ基準で見ていい筈がない。
どの様な畑でどんな感じで農作業をしてるか分からないけれど、そこまで高水準では無い可能性の方が高いだろう。
しかも、クロムギってなんなんだ?豆もおれが想像してるのとは全然別物の可能性がある。この世界の食文化とか、魔女と一緒にいるだけでは皆目見当がつかない。
「なあ、ミザリイ?おれさ、例えばだけど、明日とか、その集落に行ってもいいのかな?」
「明日……か?アリアが貴様の治療に来てくれることになっておるのだが……」
「あ、いや、別に、集落で長時間滞在しようとは考えてない。アリアが午前中にくるなら午後からとか……」
ミザリイは、少し間を取っていた。難しい顔はしてない。ただ真剣に考えてくれてはいるみたいだ。
「――構わん。私も明日は支配域を色々と回るつもりだから、集落まで送り届けてやろう。ついでに、貴様の紹介もしておいた方が良いだろうしな」
「お!いいんだ?紹介もしてくれるのは助かるね。けど、集落の人は魔力疎通が出来ないから、会話が一方通行になるってことだよな?」
要するに、おれは意志を伝えられるけれど、相手が喋ってる内容は理解が出来ないのだ。
「集落には図書館の職員が駐在しておるから、そやつを共に着けよう。帰って来る時も、そやつに案内を頼めばいい」
「まじか!なんか、滅茶苦茶テンション上がってきたんだけど!よし、じゃあ、ちょっと気合入れて料理作るわ!」
と、息まいて見せるが、食材が食材なだけに他人様に振る舞えるほど格好の良い料理は作れない。
しかし、集落で食材を手に入れれば、それなりの料理が作れるだろう。
今日のところはあり合わせで何とかするしかない。
で、何を作るのかと言うと、煮込み料理しか思いつかないワケで。スマホかパソコンで料理サイトとか見れれば、もう少しマシなアイデアが拾えると思うが、この世界で無い物ねだりはこの上なく無駄なので、諦めるしかない。
まず、鍋に水を入れ、ミザリイに火を点けて貰った。その中に鹿の干し肉を千切って投入する。
三人分なので、ある分は全部入れてしまった。まず、これで出汁を取る。
干し肉ってことは旨味が凝縮してる筈だから、そこそこ出汁が出るだろうと、思っていた。そして、出汁をとるならキノコも一緒にいれてしまえと、色取り取りのキノコたちを千切っては投げ千切っては投げ……。
それから暫く煮立つのを待った。じわじわと浮いてくるアクを、丁寧に取り除きつつ……。
ここでミザリイからの問い掛けがあった。
「貴様、その白い泡を器に移してどうするのだ?味見をするのか?」
「泡?ああ、これ?味見じゃなくてさ、アクっていうんだけど、これはさ、おれも詳しくは分かんないけど、白い泡は無い方が、雑味が無くなるんだと思う」
「ふむ。で、その雑味とは?」
「えーっと、食べた時のエグ味っていうか……。んんー、なんて言えばいいんだろう?美味しさには必要の無い味って感じかなあ」
ただ何となく、母親の見様見真似で料理をしているだけのおれは、理論的なことを何も知らないと言って過言無い。要するに、ミザリイの知識欲を満たせるほどの知識がおれには無いのだ。
しかし、その拙い説明で満足してくれたのか、ミザリイは再び静観状態になってくれた。
大体、アクをとり終えたおれは、岩塩を細かく砕いて、少しづつ鍋の中へと投じた。しっかりと出汁が出てれば、塩だけでもそこそこの味が出るだろうと思い……。
塩を入れ味見をし、塩を入れ味見をし。
思いの他、悪くは無い味わいだった。極度の空腹の為、何を食べても美味いと感じる状態だったのは否め無いが。
ある程度味が整ってから、何かしらのハーブの葉っぱを山盛り投じた。木の実や痩せた芋は、今回は使用しないことにした。あと、謎の粉末も。緑色の粉末は、舌にぴりりとして山椒っぽいが、それを使い熟せるスキルがおれにはない。
ただ、鹿の干し肉と色取り取りのキノコの出汁と岩塩の相性がかなり良く、奇跡的に適当に入れたハーブも見事功を奏して、当初の想定よりもいい感じの鹿肉汁が完成した。
室内には、食欲をそそる良い匂いが漂っている。
「――ミザリイ?そろそろ、火を消してくれるかな?」
おれがそう告げると、彼女は鍋の下の火に手を翳 し、すぐに消火してくれた。
「もう完成したのか?では、コリンを起こすぞ?」
「ああ、いいよ。じゃあ、三人分、器によそっておくよ……」
そう言い、おれが木の器に手を伸ばすと、ミザリイは驚く程大きな音で指を鳴らした。すると、奥の部屋のベッドで寝ていたコリンが、びくんっと飛び跳ね起き上がる。手で目を擦り眠そうだが、何も言葉を発することなく、ベッドから下りて歩き部屋を移って来た。
「――ああ、ミザリイ帰って来たんだ?ねえ?なんだかイイ匂いするけど、これ、なに?」とコリン。眠そうな顔は一瞬で消えてしまった。ついさっきまで昏睡状態だったのに、信じられない寝起きの良さだった。
「ヨウスケが食事を作ってくれたのだ。コリンの分もあるぞ」
コリンはおれの隣りの椅子に座り、ミザリイからは茶を出され、おれは鹿肉とキノコの煮込みを器によそい差し出した。
「へえ、これって、異世界の料理なのかい?」コリンは目を輝かせてそう言った。
次にミザリイの分をよそい、最後に自分を分をよそう。
「知っておるか、コリン?異世界では食事を摂る前に、頂きますと言うのだ。食材の命に感謝の気持ちを伝えるらしいぞ」ミザリイはそういうと、手を合わせて「いただきます」と言っていた。
どうやら彼女は、その考え方が気に入ったみたいだ。
コリンは特に興味を示したわけでは無かったが、ミザリイを真似て「いただきます」と言っていた。それに続きおれも同じく。
極限の空腹状態なので今すぐにでも食べたかったが、魔女たちの反応が気になり、先に手をつけることが出来なかった。
ミザリイもコリンも、木製の小さなスプーンを使い煮込み料理を掻き混ぜたり、匂いを嗅いだり……さながら理科の実験の様だった。
「あの、二人とも?冷めない内に食べて欲しいんだけど。温かい方が美味しいから」とおれは堪らず催促してしまった。
適当に作った煮込み料理を、有難そうに調査されると、なんだか気恥ずかしい気分になる。
「――ああ、そうだな。では、コリン、頂こう」
ミザリイがそういうと、コリンは躊躇わず料理を口に入れた。静かに、もぐもぐと頬を動かしている。
おれはともかく、ミザリイもコリンの様子を見詰めていた。要するに……ミザリイは料理の毒見をコリンにさせたかっただけなのでは無いだろうか?と疑念が生まれたが、今まで色々世話になっているので、目を瞑ることにした。
と、それよりコリンの反応は……「あ、ミザリイ?これ、美味しいよ。食べてみて」とかなりの好評。
それを受けて漸く、ミザリイもスプーンを口へと運んでくれた。
「ほう、確かに、美味い。薄味の様だが、味わい深くもあるな」
ミザリイの評価も上々だった。それから漸く、おれも食事を始める。
若干薬膳鍋の様な風味があるが、悪くない味わいだった。鹿肉の獣臭さを、ハーブが消してくれているのだろうか。
確かに味付けは薄いが、空腹には丁度良かったのかもしれない。けれどワガママを言えば、七味とかネギとか薬味が欲しい。っていうか、大盛のゴハンが欲しい。米が無いならクロムギで作ったパスタとか。なんでもいいから炭水化物が食べたいんだ、おれは、とにかく……。
それからおれたちは、黙々と食事を続けた。
ミザリイは静かに、コリンはぶつぶつと呟き、おれは脇目も振らずがつがつと。
ただ元の世界では一人暮らしで、コンビニ弁当や外食ばかりでは飽きてしまうから、仕事が定時で終わった時や、週末予定が無い時などは自炊をするようにしていた。
野菜炒めやカレーくらいなら自分好みの味に作れる程度の腕前はある。
しかし、その程度の腕前しかないおれが、異世界に来て美しい魔女二人に料理を振る舞うことになるのだから、世の中って本当にどう転ぶか分かったものでは無い。
さて、で、問題の食材。
まずはカッチカチの鹿の干し肉。もはやジャーキーと言った感じ。酒のアテには最高だと思う。支配域の集落に住む猟師がたまに持って来るらしい。
そして、色取り取りのキノコ類。乾燥してるのから生っぽいのまで色々。匂いは良いが、色味は紫系とか赤と緑とか……ヤバいのばかりが目に映る。ピンク色のエノキみたいなのって食べて平気なのだろうか?
あとは、何かしらのハーブの葉、木の実、小さな芋っぽいモノなど。
一体この食材で何が作れるのか、今のところさっぱり分からない。
次は調味料。
岩塩の塊。少しピンク色をしてるが、元の世界でもそういう色した岩塩はあったよな、と思い込み問題視するのは止めた。
あとは、黒とか緑とか赤の粉末。目を凝らして見ると、木の実か種の様な物を磨り潰している様に見えた。
依然、ミザリイが料理を作ってくれた時に、これらの粉末を鍋の中へと投じていた記憶がある。
粉末に関しては、ひとつずつ味見をするしか無い。いや、本来なら全ての食材をひとつずつ味見をするべきなのだろうけど……。
おれが食材や調味料をあれこれと手に取り調べてる間、ミザリイは茶を飲みながらおれの様子を黙って見ていた。
暇なのかと思い、調理を始める前に幾つか確認しておこうと、声を掛けた。
「――あのさ、ミザリイ、ちょっといいかな?」
「うむ、どうかしたか?」とミザリイ。普段通り、落ち着いた語り口調だ。
「おれって、魔紋刻まれてるから、少々の毒なら食べても問題無いんだろう?」
「そうだな。少々の毒なら問題無い。しかし、今、貴様が手にしておる、紫色の茸は問題有りだな。それは魔女殺しという名の茸でな、魔女でも食したら三日間腹が下るという猛毒の茸だ」
それを聞き、おれは思わず魔女殺しを手から落としてしまった。
「ちょ、ちょっと待ってくれ。他には?今テーブルの上にある食材で、食べたら問題有りなヤツはもう無い?」
何故、魔女殺しの存在を先に教えてくれなかったのか追及したかったけれど、今は押し問答をするよりも、今は自分の身を護ることに集中した方がいい、はずだ。
「――あとは、集落の者たちが持って来た食材ばかりゆえ、問題は無い筈だ。やはり、魔紋を刻んでおいて正解だったな。全ての食材の毒見なんてしておったら、先に貴様が衰弱して死んでおったであろう」
「それはそうだけど……。明らかに問題有りそうな物を食べようとしてる時は、ちゃんと止めてくれよ?それとも、人間に魔紋刻んだの初めてだから、色々様子を見てみたいって思いもあったりするのか?」
その問いに対して、ミザリイは答えずに澄ました顔で茶を啜っていた。真面目で堅物の様だが、こういう狡さは持ち合わせていると言ったところか。これに関してはおれが慣れる他ない。
「うーん、じゃあ、穀物は無いのかな?小麦とか米とか……豆とか蕎麦とかトウモロコシとか……。芋もさ、こんな痩せっぽちのじゃなくて、握り拳くらいの大きさのは無い?」
「穀物か……。集落に行けば、クロムギがあるぞ。豆もある。たまに持って来てくれるが、貴重な食糧ゆえ、私は受け取らずに持ち帰らせておるのだ。魔女は、直接的な食事は殆ど摂らんからな。芋も、集落に行けばもう少しマシなものがある、と思うが貴様の握り拳ほど大きな芋は、集落の畑では見た事が無い」
そうか、それはそうだ。おれがいた世界の農作物と同じ基準で見ていい筈がない。
どの様な畑でどんな感じで農作業をしてるか分からないけれど、そこまで高水準では無い可能性の方が高いだろう。
しかも、クロムギってなんなんだ?豆もおれが想像してるのとは全然別物の可能性がある。この世界の食文化とか、魔女と一緒にいるだけでは皆目見当がつかない。
「なあ、ミザリイ?おれさ、例えばだけど、明日とか、その集落に行ってもいいのかな?」
「明日……か?アリアが貴様の治療に来てくれることになっておるのだが……」
「あ、いや、別に、集落で長時間滞在しようとは考えてない。アリアが午前中にくるなら午後からとか……」
ミザリイは、少し間を取っていた。難しい顔はしてない。ただ真剣に考えてくれてはいるみたいだ。
「――構わん。私も明日は支配域を色々と回るつもりだから、集落まで送り届けてやろう。ついでに、貴様の紹介もしておいた方が良いだろうしな」
「お!いいんだ?紹介もしてくれるのは助かるね。けど、集落の人は魔力疎通が出来ないから、会話が一方通行になるってことだよな?」
要するに、おれは意志を伝えられるけれど、相手が喋ってる内容は理解が出来ないのだ。
「集落には図書館の職員が駐在しておるから、そやつを共に着けよう。帰って来る時も、そやつに案内を頼めばいい」
「まじか!なんか、滅茶苦茶テンション上がってきたんだけど!よし、じゃあ、ちょっと気合入れて料理作るわ!」
と、息まいて見せるが、食材が食材なだけに他人様に振る舞えるほど格好の良い料理は作れない。
しかし、集落で食材を手に入れれば、それなりの料理が作れるだろう。
今日のところはあり合わせで何とかするしかない。
で、何を作るのかと言うと、煮込み料理しか思いつかないワケで。スマホかパソコンで料理サイトとか見れれば、もう少しマシなアイデアが拾えると思うが、この世界で無い物ねだりはこの上なく無駄なので、諦めるしかない。
まず、鍋に水を入れ、ミザリイに火を点けて貰った。その中に鹿の干し肉を千切って投入する。
三人分なので、ある分は全部入れてしまった。まず、これで出汁を取る。
干し肉ってことは旨味が凝縮してる筈だから、そこそこ出汁が出るだろうと、思っていた。そして、出汁をとるならキノコも一緒にいれてしまえと、色取り取りのキノコたちを千切っては投げ千切っては投げ……。
それから暫く煮立つのを待った。じわじわと浮いてくるアクを、丁寧に取り除きつつ……。
ここでミザリイからの問い掛けがあった。
「貴様、その白い泡を器に移してどうするのだ?味見をするのか?」
「泡?ああ、これ?味見じゃなくてさ、アクっていうんだけど、これはさ、おれも詳しくは分かんないけど、白い泡は無い方が、雑味が無くなるんだと思う」
「ふむ。で、その雑味とは?」
「えーっと、食べた時のエグ味っていうか……。んんー、なんて言えばいいんだろう?美味しさには必要の無い味って感じかなあ」
ただ何となく、母親の見様見真似で料理をしているだけのおれは、理論的なことを何も知らないと言って過言無い。要するに、ミザリイの知識欲を満たせるほどの知識がおれには無いのだ。
しかし、その拙い説明で満足してくれたのか、ミザリイは再び静観状態になってくれた。
大体、アクをとり終えたおれは、岩塩を細かく砕いて、少しづつ鍋の中へと投じた。しっかりと出汁が出てれば、塩だけでもそこそこの味が出るだろうと思い……。
塩を入れ味見をし、塩を入れ味見をし。
思いの他、悪くは無い味わいだった。極度の空腹の為、何を食べても美味いと感じる状態だったのは否め無いが。
ある程度味が整ってから、何かしらのハーブの葉っぱを山盛り投じた。木の実や痩せた芋は、今回は使用しないことにした。あと、謎の粉末も。緑色の粉末は、舌にぴりりとして山椒っぽいが、それを使い熟せるスキルがおれにはない。
ただ、鹿の干し肉と色取り取りのキノコの出汁と岩塩の相性がかなり良く、奇跡的に適当に入れたハーブも見事功を奏して、当初の想定よりもいい感じの鹿肉汁が完成した。
室内には、食欲をそそる良い匂いが漂っている。
「――ミザリイ?そろそろ、火を消してくれるかな?」
おれがそう告げると、彼女は鍋の下の火に手を
「もう完成したのか?では、コリンを起こすぞ?」
「ああ、いいよ。じゃあ、三人分、器によそっておくよ……」
そう言い、おれが木の器に手を伸ばすと、ミザリイは驚く程大きな音で指を鳴らした。すると、奥の部屋のベッドで寝ていたコリンが、びくんっと飛び跳ね起き上がる。手で目を擦り眠そうだが、何も言葉を発することなく、ベッドから下りて歩き部屋を移って来た。
「――ああ、ミザリイ帰って来たんだ?ねえ?なんだかイイ匂いするけど、これ、なに?」とコリン。眠そうな顔は一瞬で消えてしまった。ついさっきまで昏睡状態だったのに、信じられない寝起きの良さだった。
「ヨウスケが食事を作ってくれたのだ。コリンの分もあるぞ」
コリンはおれの隣りの椅子に座り、ミザリイからは茶を出され、おれは鹿肉とキノコの煮込みを器によそい差し出した。
「へえ、これって、異世界の料理なのかい?」コリンは目を輝かせてそう言った。
次にミザリイの分をよそい、最後に自分を分をよそう。
「知っておるか、コリン?異世界では食事を摂る前に、頂きますと言うのだ。食材の命に感謝の気持ちを伝えるらしいぞ」ミザリイはそういうと、手を合わせて「いただきます」と言っていた。
どうやら彼女は、その考え方が気に入ったみたいだ。
コリンは特に興味を示したわけでは無かったが、ミザリイを真似て「いただきます」と言っていた。それに続きおれも同じく。
極限の空腹状態なので今すぐにでも食べたかったが、魔女たちの反応が気になり、先に手をつけることが出来なかった。
ミザリイもコリンも、木製の小さなスプーンを使い煮込み料理を掻き混ぜたり、匂いを嗅いだり……さながら理科の実験の様だった。
「あの、二人とも?冷めない内に食べて欲しいんだけど。温かい方が美味しいから」とおれは堪らず催促してしまった。
適当に作った煮込み料理を、有難そうに調査されると、なんだか気恥ずかしい気分になる。
「――ああ、そうだな。では、コリン、頂こう」
ミザリイがそういうと、コリンは躊躇わず料理を口に入れた。静かに、もぐもぐと頬を動かしている。
おれはともかく、ミザリイもコリンの様子を見詰めていた。要するに……ミザリイは料理の毒見をコリンにさせたかっただけなのでは無いだろうか?と疑念が生まれたが、今まで色々世話になっているので、目を瞑ることにした。
と、それよりコリンの反応は……「あ、ミザリイ?これ、美味しいよ。食べてみて」とかなりの好評。
それを受けて漸く、ミザリイもスプーンを口へと運んでくれた。
「ほう、確かに、美味い。薄味の様だが、味わい深くもあるな」
ミザリイの評価も上々だった。それから漸く、おれも食事を始める。
若干薬膳鍋の様な風味があるが、悪くない味わいだった。鹿肉の獣臭さを、ハーブが消してくれているのだろうか。
確かに味付けは薄いが、空腹には丁度良かったのかもしれない。けれどワガママを言えば、七味とかネギとか薬味が欲しい。っていうか、大盛のゴハンが欲しい。米が無いならクロムギで作ったパスタとか。なんでもいいから炭水化物が食べたいんだ、おれは、とにかく……。
それからおれたちは、黙々と食事を続けた。
ミザリイは静かに、コリンはぶつぶつと呟き、おれは脇目も振らずがつがつと。