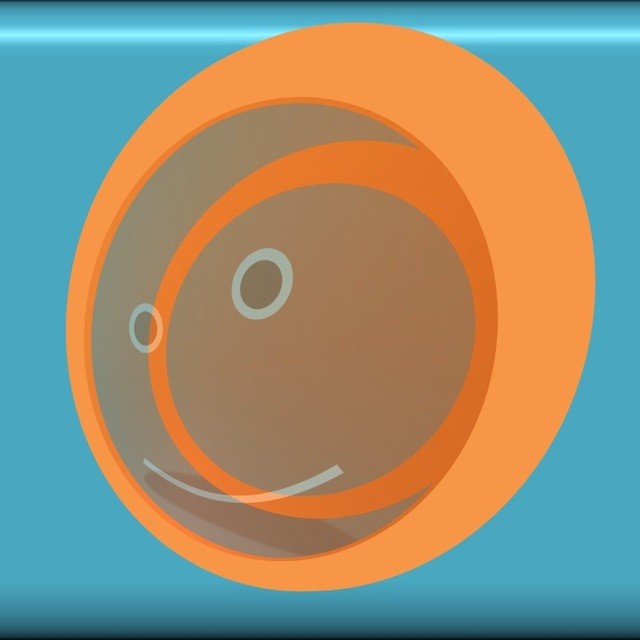第4話:そう考えると、全てが虚しく思えて来る
文字数 5,106文字
ミザリイは味見も無しに、香辛料や調味料らしき粉末を次々と鍋の中へと投じていた。
コトコトと煮立つ音が響き、室内には少々刺激的な匂いが立ち込めている。
それがこの世界の一般的な料理の仕方で、今彼女が作っているものが持成しの料理であるのなら、おれは嫌な顔ひとつせずに出されたもの全てを平らげるべきなのだろう。
調理の最終段階に入ったのか、彼女は口を閉ざし鍋と向き合っている。
おれはその様子を、茶を飲みながら見詰め物思いに耽っていた。
先ほど鍋へと投じていた肉は、一体どの様な獣のものなのだろう?
聞くべきか聞かざるべきか、静かに悩んでいたが食事前に聞くのは止める事にした。
余計な先入観があると、味覚が鈍ってしまう可能性がある。折角、異世界の料理を堪能出来るのだから、極力フラットな心持ちで事に臨むべきだろう。
しかし、改めて思うのは、今のこの現状は不幸中の幸いだと言う事。
過去に視聴してきた異世界転生や転移ものの創作物だと、いきなり戦いに巻き込まれるとか不幸のどん底に陥るとか、大抵ネガティブな事象に巻き込まれるのが一般的だけれど、おれの異世界転生は今のところ至って平和だ。
平和どころか、幸福だと言ってもいいくらいか。
静かな森の中の趣深い煉瓦造りの家で、金髪の美しい魔女と茶を飲みながら会話をしていられるのだから。
その上、彼女の手料理までご馳走になろうとしてる訳で。
これが例えばリザードマンの集落とかに転生していたら、生の川魚とか血生臭い獣の肉とかを出されてたかもしれない。
ゴブリンとか言葉も意思疎通も交わせない相手だったら、出逢った瞬間に殺されていた可能性だってある。
それを考えると、やはり、現状の幸せを噛みしめるべきなのだろう。
今のところ元の世界に戻る術が無いのだから、そう思う他無いし、そう思う事が精神的にも健全なのだと、思う。
だから、要するにおれはこれから、この世界で生きて行くと腹を括るしか無い、と言う事か。
確かに、それらしい古文書を手に入れて、限りなく信頼度の高い元の世界へと戻れる魔法陣を描けたとしても、日本の何処かに戻れるという保証は無い。
元の世界でも紛争地域とか太平洋のど真ん中とか、訳の分からないところに転移してしまったら、それこそ一巻の終わりだ。
その上、時間軸のズレも発生する可能性もある。
一日二日やせめて二年三年程度なら許容範囲だが、恐竜がいる様な過去とか、人類が滅んでしまっている未来とかに転移してしまったら、泣くに泣けない。
そんなギャンブルめいた異世界転移をするくらいなら、おれは、この世界で、目の前の金髪魔女の奴隷だろうが使用人だろうが何でもいいから、兎に角生きた方が良いに決まっている。
――よし、決めた。おれはこの世界で生きてゆく。
と、ある程度の決心がついた時、ミザリイは鍋から木製の皿へと料理をよそう。
見た感じ、シチューとか肉の煮込み的な雰囲気を醸し出していた。
「すまないな、この程度の粗末な食事しか出せなくて。普段、私は殆ど料理をせんのだ」
そう言うと、彼女は湯気の立つ皿とスプーンをおれの前に出してくれた。
正直、色味は悪い。濁った汁に肉が何切れか浮いている感じ。全然美味そうには見えない。
しかしおれは「いやいや、とんでもないよ。食事を与えて貰えるだけで有難いから。いただきます……」と手を合わせてから、勢いよくスプーンを握り締め、一切の躊躇いを捨て、兎に角一口ソレを口の中へと入れてみた。
その様子を彼女は興味深そうに見ている。
彼女からしてみれば、彼氏に初めて手料理を出す女の子的な気持ち……では無くて、飼い犬に初めて餌を与える時みたいな心境なのだと思う。
そして、問題の味。
美味くも不味くも無い。あれほど様々な香辛料的なものを投入していたのにこの味の無さは奇跡と言えるだろう。
肉はスジが多く噛み切れないし、室内に茸や山菜があるのに全く入れてくれてない。
つい先刻、この世界で生きてゆくと腹を括ったところなのだが、この料理を毎日食うくらいならイチかバチかで異世界転移した方が良いと思うくらいの代物だった。
「どうだ?口に合わんか?」と、彼女はそう尋ねてきた。
「ああ、うん、あ、いや、なんと言うか、おれのいた世界の料理とは、若干赴きが違うと言うか。いや、でも、こうして鍋で食材を煮て、それを皿によそってスプーンで食べるのはさ、全く同じだよ。味云々より、おれはそれに驚いた」
おれは苦し紛れだが、そう答えた。我ながら無難で良い返答だと思った。
「そうか、では、明日は貴様が料理を作ってみろ。食材は、ここに有る物ならどれを使っても良いから。と、それより貴様、食前に祈りを捧げておっただろう?それは要するに、己が信ずる神への祈りか?」
彼女からそう言われおれは噛み切れない肉を咀嚼しつつ「祈り?」と呟いた。
神様に祈りなんてしたっけ?と一瞬思ったが直ぐに「ああ、いただきますの事か」と言った。
そして噛み切れない肉をごくりと飲み込み、続けた。
「――あれはさ、祈りに見えるけど、そんなに深い想いは込めて無いんだ。けど、おれのいた世界では、食べる前に、いただきますと手を合わせて、食べた後にごちそうさまでしたと手を合わせなさいって、親から教えられるんだよ。中には、ちゃんと神様にお祈りを捧げる人もいるけどな。おれの家はそう言う風では無かった。確か、でも、その意味は誰かから聞いた事があったな。えーっと、いただきますは、命を頂きますって感謝をすることで、ごちそうさまでしたは料理を提供してくれた人を労う言葉だったと思う。おれが育った世界はさ、そう言う昔からの習わしみたいなのが、結構あるんだよ。皆、深い意味も知らずに、子供の頃に教わったからやってるだけって感じで、それを死ぬまでやるんだ」
おれの話を、ミザリイは真剣な眼差しで聞いてくれていた。
誰かの受け売りの受け売りみたいな話を、真面目に聞かれると何だか気恥ずかしい気持ちが湧いて出てくる。
「ふむ、そうか。いただきます、ごちそうさまでした。成程、興味深い。獣の肉を食らって、その獣に感謝するとは、その様な宗教や思想は聞いた事が無い。しかし、料理を提供した者に労いの言葉を掛けると言うのは、感心だな。それを考えると、恐らく貴様のいた世界は、この世界より成熟した文明なのだと思う。ひとつ、問いたいのは、その様な素晴らしい文明でも、争いはあるのか?人と人が殺し合う様な戦争、と言う意味でだが」そう言って、ミザリイは茶を一口飲む。
彼女は、おれがこの世界の事を知るのが優先だと言っていたけれど、その知識欲や興味心には抗えないと言う事なのだろう。
「戦争は、あるよ。おれの育った国は、七十年以上戦争をしてないけど、おれのいた世界は、戦争とか紛争だらけだよ。今、改めて思うと、滅茶苦茶な世界だ。同じ世界でも平和な国と、危険な国の差が異常にあるから。って言う、おれの国もさ、七十年前には世界を相手に大きな戦争をしたんだ。確か、おれの国だけで三百万人くらい死んだんじゃ無かったっけな?」とおれがそう言うと、彼女は目を大きく見開いた。
そして「三百万人だと?」と声を荒げる。それは出逢ってから一番大きな声だった。
そのまま彼女は続ける。
「戦争で、三百万もの人の命が奪われた、と言う事か?」
「ああ、うん、確かそれくらいだと記憶にある。でもそれはおれの育った国だけの死者だから。全世界でみたら、何千万人も死んだんだと思う」
「ちょっと待て。そもそも貴様のいた世界には、一体どれほどの人間がいたのだ?何千万もの命を失って、それでも尚文明や社会が成り立つのか?」
「うーん、その当時の世界人口は流石に分からないなあ。スマホでもあれば調べれたけど。あ、いやスマホあってもネットに繋がらないから調べれないか。でも、今現在は、確か七十億くらいじゃない?」
「な、七十億だと?人間がか?」
「七十億以上は確実にいると思う。そう遠くない将来は百億超えるらしいし」
「それは虚勢では……いや、無いな。魔力疎通で会話をして嘘をつくなど、そうそう出来る事では無い。お互い直接頭の中に語り掛けているのだから。しかし、流石に七十億以上の人間が生活してる世界など想像する事も出来ん。それこそ、食事はどうしておるのだ?七十億からそう遠くない将来百億に達すると言う事は、食糧は満ち足りてあるという事か?」
この話題に彼女がここまで食いついて来るとは思いもして無かった。
しかし、自分で語りつつも、その数の異常さに異世界の地でおれは気が付かされるのだ。皮肉なものだけれど。
「いずれ七十億から百億になるけれど、全ての人が満たされている訳では無いんだ。格差は、それこそ虫けらと神様程の開きがある。それを考えると、本当に幸せな人なんて、七十億いても、その十分の一もいないんじゃないかな。いやもっと少ないか。ほんの一握り裕福で幸せな人がいて、その一握りの神様の様な人たちを、その他大勢の虫けらたちが支えている、そう言う世界だよ、おれがいた世界は。でも、それって、多分、この世界でも似た様なものじゃない?一般庶民はさ、王様とか皇帝や貴族みたいのに支配されてるんだろう?」
この時、おれは漸く出された料理を、殆ど平らげるに至っていた。
量的にも満足感的にも全く満たされては無かったが、取り敢えず手を合わせ「ごちそうさまでした」と言う。
それを見て聞いてミザリイは少し破顔して「お、おう……」とつぶやいていた。
やはり、この魔女は悪いヤツでは無い。
それを確信した瞬間だった。
彼女は、食事を終えたおれに茶を注いでくれた。
そして、そのまま自分の器にも注ぐと、すぐに言葉を紡ぎだした。
「私はな?今、この世界に格差があるのは、文明や文化、社会が発展途上にあるからだと思っていた。発展するための必要悪というか、そうでなければ人間社会は発展し成熟せぬのだろう、と。しかしながら、貴様の話を聞くに、人間は何処まで繁栄しようとも、その格差は埋まらんと言う事に気が付かされた訳だ。いや、恐らく、格差は広がる一方なのかもしれん。それを考えると、人間とは一体、何の為に存在しておるのだろうか?いつの日にか、皆平等に生き幸せを享受する事を目指しておるのだと思っていたが、恐らくそうでは無い様だな。一握りの富裕層の為にその他大勢が存在している?そう考えると、全てが虚しく思えて来る……」
彼女はひと口茶を飲んだ。一度、嘆息し再び口を開く。
「――七十億の現在より百億の将来の方が、より不幸な人間が増えるのを、指を咥えてみるしかない貴様の世界の施政者に、私は強烈な嫌悪感を抱いてしまうよ。この世界が、貴様のいた世界と同じ道を歩まなければ良いと素直に思う。が、それもまた難しい事なのかもな。実際、現状、確かにこの世界には王侯貴族が乱立していて、命の重い者と軽い者の線引きが明確にあるのだから。その線引きが、ある日突然消える事など、決して無い。いやいや、それに関しては、貴様と言う存在が現れなくとも、分かってはいたのだ。見て見ぬふりをして来ただけの話。しかし……。しかし、いざ自身の盲目を解かれると、これ程まで胸糞悪くなるものか。腹立たしい、実に腹立たしい。この件に関しては魔女同盟とマグナラタンに提起してみよう。他の魔女とも語り合いたい」
彼女は怒りに打ち震えている様に見えた。
これは演技では無い。彼女の本心なのだろう。
最初に魔女と聞いたから、少し色眼鏡で見てしまっていたけれど、彼女は実直で清廉な人物なのだろう、と今は思う。
そして、ここまで彼女と話して分かったことが幾つかあった。
まず、この世界はおれのいた世界より文明が成熟してない。
恐らく中世ヨーロッパ……いや、その前の暗黒時代くらいの文明なのかもしれない。
魔法はあるけれど、基本的な生活は随分と遅れているという認識で良いだろう。
あと、それともうひとつ。
それは、彼女が正義の心を有している魔女であると言う事。これも恐らく間違い無いだろう。
世の中に置いて、正義の全てが正しいとは言い難いけれど、それが明確であれば付き合いやすいし信用も出来る。
何より、おれは、彼女の人間性を知って魔紋とやらを、彼女になら刻まれてもいいかも、と思う様になっていた。
コトコトと煮立つ音が響き、室内には少々刺激的な匂いが立ち込めている。
それがこの世界の一般的な料理の仕方で、今彼女が作っているものが持成しの料理であるのなら、おれは嫌な顔ひとつせずに出されたもの全てを平らげるべきなのだろう。
調理の最終段階に入ったのか、彼女は口を閉ざし鍋と向き合っている。
おれはその様子を、茶を飲みながら見詰め物思いに耽っていた。
先ほど鍋へと投じていた肉は、一体どの様な獣のものなのだろう?
聞くべきか聞かざるべきか、静かに悩んでいたが食事前に聞くのは止める事にした。
余計な先入観があると、味覚が鈍ってしまう可能性がある。折角、異世界の料理を堪能出来るのだから、極力フラットな心持ちで事に臨むべきだろう。
しかし、改めて思うのは、今のこの現状は不幸中の幸いだと言う事。
過去に視聴してきた異世界転生や転移ものの創作物だと、いきなり戦いに巻き込まれるとか不幸のどん底に陥るとか、大抵ネガティブな事象に巻き込まれるのが一般的だけれど、おれの異世界転生は今のところ至って平和だ。
平和どころか、幸福だと言ってもいいくらいか。
静かな森の中の趣深い煉瓦造りの家で、金髪の美しい魔女と茶を飲みながら会話をしていられるのだから。
その上、彼女の手料理までご馳走になろうとしてる訳で。
これが例えばリザードマンの集落とかに転生していたら、生の川魚とか血生臭い獣の肉とかを出されてたかもしれない。
ゴブリンとか言葉も意思疎通も交わせない相手だったら、出逢った瞬間に殺されていた可能性だってある。
それを考えると、やはり、現状の幸せを噛みしめるべきなのだろう。
今のところ元の世界に戻る術が無いのだから、そう思う他無いし、そう思う事が精神的にも健全なのだと、思う。
だから、要するにおれはこれから、この世界で生きて行くと腹を括るしか無い、と言う事か。
確かに、それらしい古文書を手に入れて、限りなく信頼度の高い元の世界へと戻れる魔法陣を描けたとしても、日本の何処かに戻れるという保証は無い。
元の世界でも紛争地域とか太平洋のど真ん中とか、訳の分からないところに転移してしまったら、それこそ一巻の終わりだ。
その上、時間軸のズレも発生する可能性もある。
一日二日やせめて二年三年程度なら許容範囲だが、恐竜がいる様な過去とか、人類が滅んでしまっている未来とかに転移してしまったら、泣くに泣けない。
そんなギャンブルめいた異世界転移をするくらいなら、おれは、この世界で、目の前の金髪魔女の奴隷だろうが使用人だろうが何でもいいから、兎に角生きた方が良いに決まっている。
――よし、決めた。おれはこの世界で生きてゆく。
と、ある程度の決心がついた時、ミザリイは鍋から木製の皿へと料理をよそう。
見た感じ、シチューとか肉の煮込み的な雰囲気を醸し出していた。
「すまないな、この程度の粗末な食事しか出せなくて。普段、私は殆ど料理をせんのだ」
そう言うと、彼女は湯気の立つ皿とスプーンをおれの前に出してくれた。
正直、色味は悪い。濁った汁に肉が何切れか浮いている感じ。全然美味そうには見えない。
しかしおれは「いやいや、とんでもないよ。食事を与えて貰えるだけで有難いから。いただきます……」と手を合わせてから、勢いよくスプーンを握り締め、一切の躊躇いを捨て、兎に角一口ソレを口の中へと入れてみた。
その様子を彼女は興味深そうに見ている。
彼女からしてみれば、彼氏に初めて手料理を出す女の子的な気持ち……では無くて、飼い犬に初めて餌を与える時みたいな心境なのだと思う。
そして、問題の味。
美味くも不味くも無い。あれほど様々な香辛料的なものを投入していたのにこの味の無さは奇跡と言えるだろう。
肉はスジが多く噛み切れないし、室内に茸や山菜があるのに全く入れてくれてない。
つい先刻、この世界で生きてゆくと腹を括ったところなのだが、この料理を毎日食うくらいならイチかバチかで異世界転移した方が良いと思うくらいの代物だった。
「どうだ?口に合わんか?」と、彼女はそう尋ねてきた。
「ああ、うん、あ、いや、なんと言うか、おれのいた世界の料理とは、若干赴きが違うと言うか。いや、でも、こうして鍋で食材を煮て、それを皿によそってスプーンで食べるのはさ、全く同じだよ。味云々より、おれはそれに驚いた」
おれは苦し紛れだが、そう答えた。我ながら無難で良い返答だと思った。
「そうか、では、明日は貴様が料理を作ってみろ。食材は、ここに有る物ならどれを使っても良いから。と、それより貴様、食前に祈りを捧げておっただろう?それは要するに、己が信ずる神への祈りか?」
彼女からそう言われおれは噛み切れない肉を咀嚼しつつ「祈り?」と呟いた。
神様に祈りなんてしたっけ?と一瞬思ったが直ぐに「ああ、いただきますの事か」と言った。
そして噛み切れない肉をごくりと飲み込み、続けた。
「――あれはさ、祈りに見えるけど、そんなに深い想いは込めて無いんだ。けど、おれのいた世界では、食べる前に、いただきますと手を合わせて、食べた後にごちそうさまでしたと手を合わせなさいって、親から教えられるんだよ。中には、ちゃんと神様にお祈りを捧げる人もいるけどな。おれの家はそう言う風では無かった。確か、でも、その意味は誰かから聞いた事があったな。えーっと、いただきますは、命を頂きますって感謝をすることで、ごちそうさまでしたは料理を提供してくれた人を労う言葉だったと思う。おれが育った世界はさ、そう言う昔からの習わしみたいなのが、結構あるんだよ。皆、深い意味も知らずに、子供の頃に教わったからやってるだけって感じで、それを死ぬまでやるんだ」
おれの話を、ミザリイは真剣な眼差しで聞いてくれていた。
誰かの受け売りの受け売りみたいな話を、真面目に聞かれると何だか気恥ずかしい気持ちが湧いて出てくる。
「ふむ、そうか。いただきます、ごちそうさまでした。成程、興味深い。獣の肉を食らって、その獣に感謝するとは、その様な宗教や思想は聞いた事が無い。しかし、料理を提供した者に労いの言葉を掛けると言うのは、感心だな。それを考えると、恐らく貴様のいた世界は、この世界より成熟した文明なのだと思う。ひとつ、問いたいのは、その様な素晴らしい文明でも、争いはあるのか?人と人が殺し合う様な戦争、と言う意味でだが」そう言って、ミザリイは茶を一口飲む。
彼女は、おれがこの世界の事を知るのが優先だと言っていたけれど、その知識欲や興味心には抗えないと言う事なのだろう。
「戦争は、あるよ。おれの育った国は、七十年以上戦争をしてないけど、おれのいた世界は、戦争とか紛争だらけだよ。今、改めて思うと、滅茶苦茶な世界だ。同じ世界でも平和な国と、危険な国の差が異常にあるから。って言う、おれの国もさ、七十年前には世界を相手に大きな戦争をしたんだ。確か、おれの国だけで三百万人くらい死んだんじゃ無かったっけな?」とおれがそう言うと、彼女は目を大きく見開いた。
そして「三百万人だと?」と声を荒げる。それは出逢ってから一番大きな声だった。
そのまま彼女は続ける。
「戦争で、三百万もの人の命が奪われた、と言う事か?」
「ああ、うん、確かそれくらいだと記憶にある。でもそれはおれの育った国だけの死者だから。全世界でみたら、何千万人も死んだんだと思う」
「ちょっと待て。そもそも貴様のいた世界には、一体どれほどの人間がいたのだ?何千万もの命を失って、それでも尚文明や社会が成り立つのか?」
「うーん、その当時の世界人口は流石に分からないなあ。スマホでもあれば調べれたけど。あ、いやスマホあってもネットに繋がらないから調べれないか。でも、今現在は、確か七十億くらいじゃない?」
「な、七十億だと?人間がか?」
「七十億以上は確実にいると思う。そう遠くない将来は百億超えるらしいし」
「それは虚勢では……いや、無いな。魔力疎通で会話をして嘘をつくなど、そうそう出来る事では無い。お互い直接頭の中に語り掛けているのだから。しかし、流石に七十億以上の人間が生活してる世界など想像する事も出来ん。それこそ、食事はどうしておるのだ?七十億からそう遠くない将来百億に達すると言う事は、食糧は満ち足りてあるという事か?」
この話題に彼女がここまで食いついて来るとは思いもして無かった。
しかし、自分で語りつつも、その数の異常さに異世界の地でおれは気が付かされるのだ。皮肉なものだけれど。
「いずれ七十億から百億になるけれど、全ての人が満たされている訳では無いんだ。格差は、それこそ虫けらと神様程の開きがある。それを考えると、本当に幸せな人なんて、七十億いても、その十分の一もいないんじゃないかな。いやもっと少ないか。ほんの一握り裕福で幸せな人がいて、その一握りの神様の様な人たちを、その他大勢の虫けらたちが支えている、そう言う世界だよ、おれがいた世界は。でも、それって、多分、この世界でも似た様なものじゃない?一般庶民はさ、王様とか皇帝や貴族みたいのに支配されてるんだろう?」
この時、おれは漸く出された料理を、殆ど平らげるに至っていた。
量的にも満足感的にも全く満たされては無かったが、取り敢えず手を合わせ「ごちそうさまでした」と言う。
それを見て聞いてミザリイは少し破顔して「お、おう……」とつぶやいていた。
やはり、この魔女は悪いヤツでは無い。
それを確信した瞬間だった。
彼女は、食事を終えたおれに茶を注いでくれた。
そして、そのまま自分の器にも注ぐと、すぐに言葉を紡ぎだした。
「私はな?今、この世界に格差があるのは、文明や文化、社会が発展途上にあるからだと思っていた。発展するための必要悪というか、そうでなければ人間社会は発展し成熟せぬのだろう、と。しかしながら、貴様の話を聞くに、人間は何処まで繁栄しようとも、その格差は埋まらんと言う事に気が付かされた訳だ。いや、恐らく、格差は広がる一方なのかもしれん。それを考えると、人間とは一体、何の為に存在しておるのだろうか?いつの日にか、皆平等に生き幸せを享受する事を目指しておるのだと思っていたが、恐らくそうでは無い様だな。一握りの富裕層の為にその他大勢が存在している?そう考えると、全てが虚しく思えて来る……」
彼女はひと口茶を飲んだ。一度、嘆息し再び口を開く。
「――七十億の現在より百億の将来の方が、より不幸な人間が増えるのを、指を咥えてみるしかない貴様の世界の施政者に、私は強烈な嫌悪感を抱いてしまうよ。この世界が、貴様のいた世界と同じ道を歩まなければ良いと素直に思う。が、それもまた難しい事なのかもな。実際、現状、確かにこの世界には王侯貴族が乱立していて、命の重い者と軽い者の線引きが明確にあるのだから。その線引きが、ある日突然消える事など、決して無い。いやいや、それに関しては、貴様と言う存在が現れなくとも、分かってはいたのだ。見て見ぬふりをして来ただけの話。しかし……。しかし、いざ自身の盲目を解かれると、これ程まで胸糞悪くなるものか。腹立たしい、実に腹立たしい。この件に関しては魔女同盟とマグナラタンに提起してみよう。他の魔女とも語り合いたい」
彼女は怒りに打ち震えている様に見えた。
これは演技では無い。彼女の本心なのだろう。
最初に魔女と聞いたから、少し色眼鏡で見てしまっていたけれど、彼女は実直で清廉な人物なのだろう、と今は思う。
そして、ここまで彼女と話して分かったことが幾つかあった。
まず、この世界はおれのいた世界より文明が成熟してない。
恐らく中世ヨーロッパ……いや、その前の暗黒時代くらいの文明なのかもしれない。
魔法はあるけれど、基本的な生活は随分と遅れているという認識で良いだろう。
あと、それともうひとつ。
それは、彼女が正義の心を有している魔女であると言う事。これも恐らく間違い無いだろう。
世の中に置いて、正義の全てが正しいとは言い難いけれど、それが明確であれば付き合いやすいし信用も出来る。
何より、おれは、彼女の人間性を知って魔紋とやらを、彼女になら刻まれてもいいかも、と思う様になっていた。