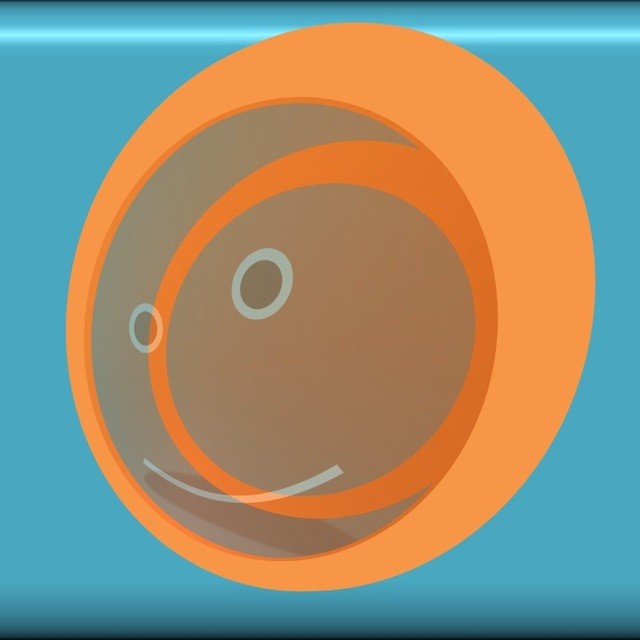第3話:マグナラタンの図書館長の命令。
文字数 5,503文字
もしも、自分がファンタジー世界やゲームの中に転移もしくは転生したらどうなるだろう?と考えた事は、何度かあった。
それは、例えば宝くじで三億円当たったらどうする?とか、好きなアイドルと密室で二人きりになったらどうする?みたいな願望妄想と同じレベルのもしもシリーズだ。
三億円当たったら、一億円は親にあげて一億円で家を建てて残りの一億円で優雅に暮らすとか、資産運用の勉強をして投資家になるとか、誰にも言わないでライフスタイルを崩さずに老後の為に貯蓄しておくとか、人それぞれ十人十色の使い道を、ああだこうだと言い合う、不毛な時間潰し。
おれ的には、もしも、自分がファンタジー世界へと来てしまったら、そこには凶悪な魔王がいて滅びかけている人類がいて、古えの神々から啓示を受け勇者として巨悪に立ち向かうみたいな……単純明快で分かりやすい方が良かったなあ、と思う。
まさか、飲み水とか食べ物とか疫病感染とかに悩まされて、身動き取れない状況に追い込まれるとは思いもして無かった訳だ。
これがオンラインゲームの世界だったら、低評価でクソゲーと罵られすぐにアンインストールされてしまうだろう。
しかし、これはゲームの世界ではない。
そして、おれは今、異世界で本物の魔女や魔法が存在するファンタジー世界で、妙に現実的な問題に直面してしまっている。
いや、不都合なことばかりではない。
都合の良い事もたしかにある。
転移して初めて出会った第一異世界人が金髪の美しい魔女だったこと。
そしてその魔女と意思疎通が出来て会話が成立すること。
あと、人は家に住みベッドで寝て器を使って食事を摂るという元居た世界との共通点も割かし多くある点も都合が良いと言えるだろう。
しかし元居た世界で、異世界転移したらどうする?という話題になった時、取り敢えず安全な空気や水や食料の調達からだ!なんて真面目ぶった発言をしたって場がシラケるだけだから、その状況を真剣に考えた事が無かった。
もしも無人島に漂着してしまったら?なら、水や食料の調達の仕方で盛り上がるのだろうけれど、無人島漂着と異世界転移では盛り上がりたい話題の方向性が違ってくるのだ。
異世界転移研究会とかテーブルトークRPGの経験者なら、今おれが直面している状況を想定して様々な打開策や対応策について語り合ってるのかもしれないが、おれの様な一般人に毛が生えた程度のファンタジー好き程度には、そこまでの妄想力は無い。
「――で、だから、おれは、この世界で生き延びるために、金髪の魔女から魔紋を刻まれて、取り敢えずの難を逃れた訳だ。そして、施術の際の昏睡魔法で眠って、起きて、喉が渇いてたから甕の水を二杯飲んで、椅子に座って、そろそろ一時間が過ぎる。ミザリイは何処に行ったんだ?」
少し大きな声で、独り言を発していた。
それまでは静かに時を過ごしていた。水を飲んで、椅子に座って、魔女ミザリイの帰りを大人しく待っていたのだ。
現状、唯一と言っていい文明の利器の腕時計の針を見詰めつつ。
その間様々な事を考えていた。前述したもしもシリーズの事や、ミザリイと語り合った事を思い返したりして。
そして一時間静かに過ごしてから、声を発した。自分の存在確認をする為の発生だったと言っていいかもしれない。
ふいに、生きてこの場に存在してると言う証明が欲しくなったのだ。
このまま、ずっとひとりかもしれない……なんてネガティブな思考が湧いてきてしまう。
しかし、なにか行動を起こそう!と考える前に、ミザリイは帰って来てくれた。
鍔の広いとんがり帽子と、真っ黒なローブに身を包み如何にも魔女的な服装で。
彼女は扉を閉めると、帽子を取りするするとローブを脱ぎ、目のやり場に困ってしまう程露出度の高い黒いタイトなワンピース姿となる。
「――起きていたか。どうだ気分は?魔紋を刻んだ箇所が痛むとか、吐き気や頭痛がするとか身体に違和感は無いか?」
そう言い、彼女は水を汲んだ鍋に火を掛ける。流れる様な動作だ。
一片の淀みも無く見える。
「気分は悪くない。少し頭がぼーっとしているかもしれない。魔紋を刻まれた箇所は痛く無いが、ひんやりとしていて何だか妙な感覚だ」とおれは答え、それから「また散歩に出掛けてたのかい?」と尋ねた。
すると彼女は首を横に振った。おれの対面へと腰掛け、短く小さく息を吐いた。
「いや、実は、貴様が寝ておる間にマグナラタンへと行っておった。ほら、言ったであろう?私は、人間に魔紋を刻むのは貴様が初めてだと。それ故にな、当面その予定が無かったから、人間に魔紋を刻む際の規則や条例があるかもしれんと思い、それを問い合わせに行っておったのだ」と、彼女は平然とそう言った。
しかしそれは、おれとしては少し聞き捨てならない内容だった。
「え?ちょっと待ってくれ。それって、本来なら魔紋を刻む前に確認しておくべき事なんじゃあ無いのか?」
「うむ、そうだな。本来ならそうすべきだった。しかし、それに気が付いたのが魔紋を刻んだ後だった故に、もはや手遅れだった。私は、時を戻す魔法は使えんからな」
彼女は明らかな失態を悪びれる事無く、堂々と言ってのける。これがこの世界の風習なのだろうか?元居た世界にも絶対に謝らない人種はいたけれど。
「あの、それで、何か規則や条例はあったのかい?って言うか、ミザリイはさ、百五十年も生きてる魔女なのに、その件に関しては知らなかったって事?」
「ふむ、知らなかった、と言うのは正しい表現では無い。忘れていた、と言うのが正しいだろうな。なにせ、私がそれを学んだのは百三十年以上前の事だから。その間、人間に魔紋を刻む気が無かった故に、記憶の深層に沈み込んでしまったのであろう。こればかりは私が如何に魔女であろうともどうにもならん。魔女として生きておる限り学ぶ事が膨大にあるのでな、必要無い知識は自然と薄れてゆくのだ」
そう言うと、彼女は例の魔力回復を促進させる茶を淹れてくれた。
ここまで会話して分かった事は、この件に関して彼女は全く謝るつもりが無いという事。
おれに対して申し訳無いと言う気持ちは微塵も無い様に感じる。
その事に、正直苛立ちは否めない。
しかし、声を荒げ癇癪を起す気にはならなかった。
一瞬、心に火が灯る様な感覚はあったが、それがすぐに鎮火してしまった様な、そう言う感覚は確かにあった。
「――それで、例えばどう言う規則や条例があったんだい?」
おれはそう言い、茶を一口飲んだ。昨夜よりも深く身体へと染み込んでいく様な味わいだった。
「まず、マグナラタンに対し事前報告が必要だった。遅くても十日前までに報告し、戸籍や身元を証明するものを用意せねばならん。それから施術の際はマグナラタンの職員の立ち合いが必要だった。魔紋を刻む際に禁忌に触れる紋様を刻まぬ様に見張りを立てるのだ。後、貴様の様な大人には基本的に魔紋を刻んではならんらしい。拒否反応を起こして発狂して廃人になる場合が殆どだそうだ。それを考えると、貴様はまだまともそうだし、廃人にはならずに済んだ様で何よりだ」
おれは思わず、手にしていた器をテーブルに落としてしまった。
開いた口が塞がらないとは正にこの事だ。
事前報告や職員立ち合いはまだしも、発狂して廃人になる恐れある事を忘れてしまっていたのは流石に肝が冷える。
「あ、あのさ?万が一、おれが発狂して廃人になってしまったらさ、ミザリイの魔法で何とか回復出来たのかな?」
怒りを上回る恐怖の為、声が震えてしまっていた。
「それは、何とも言えんな。私は発狂して廃人になった人間を治してやろうと思った事が一度も無い故。勿論、貴様がそうなっておったら、何かしら手を考えて回復させてやろうとはするだろうが、確実に治してやるとは断言出来ん。しかしな?それらの規則やら条例やらは、全てこの国と協定を結んだ周辺国内の人間に施術する場合の取り決めなのだ。それを考慮すると、貴様の場合、異世界人であるからそれらの規則や条例には当て嵌まらん。故に、事前報告も職員の立ち合いも必要ない、と言ったのだが……」
ミザリイは珍しく言葉を濁した。表情は、少し拗ねているようにも見える。
「言ったのだが……?」
「ふむ、いや、簡単に申せば、私の訴えは退けられた。そして、明日、貴様をマグナラタンへと出向させよと命ぜられた。マグナラタンの図書館長直々にな」
「と、図書館長って、図書館の一番偉い人って事か?」
「うむ、そうだ」
正直、拍子抜けの回答だった。高々図書館の長ごときが魔女に命令出来るのも驚きで、おれは思わず「百五十年を生きた魔女が、図書館の館長に逆らえないんだ?」と問い掛けていた。
「本来なら逆らえんな。マグナラタンは世界最古の図書館だ。歴代館長は、その時代最高の魔女が務めて来た。任期は百年。現館長は三期目。要するに二百年以上最高の魔女であり続けておる、という事だ。私が生まれる前から最高の魔女なのだからな、その様な相手に逆らう魔女など、気が触れておると思われても仕方ない。しかも、その上――」
「その上……?」
おれがおうむ返しで尋ねると、彼女はひとつ溜息を零した。
どう言う意図の溜息かは分りかねたが、感情の起伏が乏しい彼女には珍しい反応だった。
「――その上、現マグナラタン図書館長アート・ココレイト・コーリンは、私の師匠だ。魔女の師弟関係は絶対的。実の親兄弟よりも師弟関係の方が強力な結びつきがあるのだ。言うまでも無く、魔力の差も歴然。私なんぞ師匠に掛かれば一息で消滅させられるであろう。故に絶対に抗う事も逆らう事も出来ん。しかし、案ずることは無い。私はこれまで真面目にマグナラタンと師匠の命令に忠実に働いてきたからな、発言権が全く無い訳では無いのだ。それ故、この度、貴様がマグナラタンへと赴く件に関しては、暫くの猶予を貰った。今すぐ外に出しては色々と危険が伴うかもしれんと、理由をこじつけてな」と彼女は淡々と語る。
平然とおれの目を見詰め、悠々と茶を口にしていた。
そして、おれ自身も何故かそこまでの不安を感じて無いと言う、この事実。
まだ昏睡魔法が抜け切れて無くて精神的に不感症になっているのかもしれない。
要するに、おれはその師匠のところに、取り敢えずは赴かなくて良い、ということだ。たぶん、きっと。
と、それより。おれは「ん?あれ?」思わず声を漏らした。
ミザリイの師匠の名を聞き、ふと思ったのだ。
「ん?どうかしたか?」
「ああ、いや、確かミザリイってさ、ミザリイ・アート・ココレイト、だったよな?」
「うむ、そうだ。ミザリイとは師匠から与えられた名だ。魔女は名乗る際に、師匠と大師匠の名も名乗るのだ。故に、私の姉弟子はマーリン・アート・ココレイトと名乗っておる。大師匠のココレイト・コーリン・ラアラは弟子を多く持たれたお方で、それ故にココレイト・コーリンを名乗る魔女は師匠を含め八名もおられる。その全てが各分野で大成されておる方々ばかりなのでな、私は名乗るだけでそれなりに由緒正しき魔女だと認識されるのだ。師匠が違っても大師匠が同じであれば同じ一門として交流もしやすい。まあ、そうは言っても私は大師匠には会ったことも見たことも無いのだけれどな」
そう言うと彼女は静かに天井を見上げた。
要するに、大師匠は既に天に召された、と言う事なのだろうか?死者に対して想いを馳せる仕草は元居た世界と変わらないのかと思うと何だか感慨深い。
「現代最高の魔女を育てた大師匠も今はもう亡くなっていないってこと?」
おれは天井へと向けていた顔を下ろした彼女へと、そう尋ねた。
「いやいや、それは無い。大師匠ほどの魔女は肉体は滅したとしても膨大な魔力と融合した魂は残り、神の如き存在となられるのだ。一般的には神化と呼ばれるがな。神化した魔女は、基本的に人間界から離れ自然の中で悠久なる時を過ごされる」
「それって、全ての魔女が神化にはならないってこと?」
「神化出来るのは一握りの偉大な魔女だけだ。現代で言う所のアート・ココレイト・コーリンだな。勿論、他にも偉大な魔女はおるし、神化せずに人間界に関与し続ける魔女もいなくは無い」
ここでまた彼女は天井を見詰めた。どうやら死者に想いを馳せている訳では無いらしい。
おれも彼女と同じポイントを見詰める。
「天井に、何かあるのかい?」
「いや、天井のその先だ。どうやら来客ありだ。珍しい。連絡も寄こさずに訪れるとは……。ああ、さてはマグナラタンから貴様の情報が漏れたのだな。私が魔紋を刻んだ人間を見に来たのか……」
「え、それって、他の魔女ってこと?」
「うむ、近くに支配域を持つ魔女だ。同じ魔女同盟に所属しておる仲間、と言った所か。いやしかし案ずるな。少々荒っぽいが悪い魔女では無い」
そう言うと彼女は、ぱちんっと指を鳴らした。
するとすぐに家の扉が勢い良く開いた。おれと然程背丈の変わらない女性が大股で上がり込んで来る。
燃える様な緋色のとんがり帽子とローブ。その大柄さから存在感だけで言うとミザリイよりも強烈で強大だった。
要するにこれで魔女にも色々いる、という事が分かった。
兎に角、面倒くさい奴でなければいい……と思いつつ、おれは息を飲み大柄で派手な魔女の事を見詰めていた。
それは、例えば宝くじで三億円当たったらどうする?とか、好きなアイドルと密室で二人きりになったらどうする?みたいな願望妄想と同じレベルのもしもシリーズだ。
三億円当たったら、一億円は親にあげて一億円で家を建てて残りの一億円で優雅に暮らすとか、資産運用の勉強をして投資家になるとか、誰にも言わないでライフスタイルを崩さずに老後の為に貯蓄しておくとか、人それぞれ十人十色の使い道を、ああだこうだと言い合う、不毛な時間潰し。
おれ的には、もしも、自分がファンタジー世界へと来てしまったら、そこには凶悪な魔王がいて滅びかけている人類がいて、古えの神々から啓示を受け勇者として巨悪に立ち向かうみたいな……単純明快で分かりやすい方が良かったなあ、と思う。
まさか、飲み水とか食べ物とか疫病感染とかに悩まされて、身動き取れない状況に追い込まれるとは思いもして無かった訳だ。
これがオンラインゲームの世界だったら、低評価でクソゲーと罵られすぐにアンインストールされてしまうだろう。
しかし、これはゲームの世界ではない。
そして、おれは今、異世界で本物の魔女や魔法が存在するファンタジー世界で、妙に現実的な問題に直面してしまっている。
いや、不都合なことばかりではない。
都合の良い事もたしかにある。
転移して初めて出会った第一異世界人が金髪の美しい魔女だったこと。
そしてその魔女と意思疎通が出来て会話が成立すること。
あと、人は家に住みベッドで寝て器を使って食事を摂るという元居た世界との共通点も割かし多くある点も都合が良いと言えるだろう。
しかし元居た世界で、異世界転移したらどうする?という話題になった時、取り敢えず安全な空気や水や食料の調達からだ!なんて真面目ぶった発言をしたって場がシラケるだけだから、その状況を真剣に考えた事が無かった。
もしも無人島に漂着してしまったら?なら、水や食料の調達の仕方で盛り上がるのだろうけれど、無人島漂着と異世界転移では盛り上がりたい話題の方向性が違ってくるのだ。
異世界転移研究会とかテーブルトークRPGの経験者なら、今おれが直面している状況を想定して様々な打開策や対応策について語り合ってるのかもしれないが、おれの様な一般人に毛が生えた程度のファンタジー好き程度には、そこまでの妄想力は無い。
「――で、だから、おれは、この世界で生き延びるために、金髪の魔女から魔紋を刻まれて、取り敢えずの難を逃れた訳だ。そして、施術の際の昏睡魔法で眠って、起きて、喉が渇いてたから甕の水を二杯飲んで、椅子に座って、そろそろ一時間が過ぎる。ミザリイは何処に行ったんだ?」
少し大きな声で、独り言を発していた。
それまでは静かに時を過ごしていた。水を飲んで、椅子に座って、魔女ミザリイの帰りを大人しく待っていたのだ。
現状、唯一と言っていい文明の利器の腕時計の針を見詰めつつ。
その間様々な事を考えていた。前述したもしもシリーズの事や、ミザリイと語り合った事を思い返したりして。
そして一時間静かに過ごしてから、声を発した。自分の存在確認をする為の発生だったと言っていいかもしれない。
ふいに、生きてこの場に存在してると言う証明が欲しくなったのだ。
このまま、ずっとひとりかもしれない……なんてネガティブな思考が湧いてきてしまう。
しかし、なにか行動を起こそう!と考える前に、ミザリイは帰って来てくれた。
鍔の広いとんがり帽子と、真っ黒なローブに身を包み如何にも魔女的な服装で。
彼女は扉を閉めると、帽子を取りするするとローブを脱ぎ、目のやり場に困ってしまう程露出度の高い黒いタイトなワンピース姿となる。
「――起きていたか。どうだ気分は?魔紋を刻んだ箇所が痛むとか、吐き気や頭痛がするとか身体に違和感は無いか?」
そう言い、彼女は水を汲んだ鍋に火を掛ける。流れる様な動作だ。
一片の淀みも無く見える。
「気分は悪くない。少し頭がぼーっとしているかもしれない。魔紋を刻まれた箇所は痛く無いが、ひんやりとしていて何だか妙な感覚だ」とおれは答え、それから「また散歩に出掛けてたのかい?」と尋ねた。
すると彼女は首を横に振った。おれの対面へと腰掛け、短く小さく息を吐いた。
「いや、実は、貴様が寝ておる間にマグナラタンへと行っておった。ほら、言ったであろう?私は、人間に魔紋を刻むのは貴様が初めてだと。それ故にな、当面その予定が無かったから、人間に魔紋を刻む際の規則や条例があるかもしれんと思い、それを問い合わせに行っておったのだ」と、彼女は平然とそう言った。
しかしそれは、おれとしては少し聞き捨てならない内容だった。
「え?ちょっと待ってくれ。それって、本来なら魔紋を刻む前に確認しておくべき事なんじゃあ無いのか?」
「うむ、そうだな。本来ならそうすべきだった。しかし、それに気が付いたのが魔紋を刻んだ後だった故に、もはや手遅れだった。私は、時を戻す魔法は使えんからな」
彼女は明らかな失態を悪びれる事無く、堂々と言ってのける。これがこの世界の風習なのだろうか?元居た世界にも絶対に謝らない人種はいたけれど。
「あの、それで、何か規則や条例はあったのかい?って言うか、ミザリイはさ、百五十年も生きてる魔女なのに、その件に関しては知らなかったって事?」
「ふむ、知らなかった、と言うのは正しい表現では無い。忘れていた、と言うのが正しいだろうな。なにせ、私がそれを学んだのは百三十年以上前の事だから。その間、人間に魔紋を刻む気が無かった故に、記憶の深層に沈み込んでしまったのであろう。こればかりは私が如何に魔女であろうともどうにもならん。魔女として生きておる限り学ぶ事が膨大にあるのでな、必要無い知識は自然と薄れてゆくのだ」
そう言うと、彼女は例の魔力回復を促進させる茶を淹れてくれた。
ここまで会話して分かった事は、この件に関して彼女は全く謝るつもりが無いという事。
おれに対して申し訳無いと言う気持ちは微塵も無い様に感じる。
その事に、正直苛立ちは否めない。
しかし、声を荒げ癇癪を起す気にはならなかった。
一瞬、心に火が灯る様な感覚はあったが、それがすぐに鎮火してしまった様な、そう言う感覚は確かにあった。
「――それで、例えばどう言う規則や条例があったんだい?」
おれはそう言い、茶を一口飲んだ。昨夜よりも深く身体へと染み込んでいく様な味わいだった。
「まず、マグナラタンに対し事前報告が必要だった。遅くても十日前までに報告し、戸籍や身元を証明するものを用意せねばならん。それから施術の際はマグナラタンの職員の立ち合いが必要だった。魔紋を刻む際に禁忌に触れる紋様を刻まぬ様に見張りを立てるのだ。後、貴様の様な大人には基本的に魔紋を刻んではならんらしい。拒否反応を起こして発狂して廃人になる場合が殆どだそうだ。それを考えると、貴様はまだまともそうだし、廃人にはならずに済んだ様で何よりだ」
おれは思わず、手にしていた器をテーブルに落としてしまった。
開いた口が塞がらないとは正にこの事だ。
事前報告や職員立ち合いはまだしも、発狂して廃人になる恐れある事を忘れてしまっていたのは流石に肝が冷える。
「あ、あのさ?万が一、おれが発狂して廃人になってしまったらさ、ミザリイの魔法で何とか回復出来たのかな?」
怒りを上回る恐怖の為、声が震えてしまっていた。
「それは、何とも言えんな。私は発狂して廃人になった人間を治してやろうと思った事が一度も無い故。勿論、貴様がそうなっておったら、何かしら手を考えて回復させてやろうとはするだろうが、確実に治してやるとは断言出来ん。しかしな?それらの規則やら条例やらは、全てこの国と協定を結んだ周辺国内の人間に施術する場合の取り決めなのだ。それを考慮すると、貴様の場合、異世界人であるからそれらの規則や条例には当て嵌まらん。故に、事前報告も職員の立ち合いも必要ない、と言ったのだが……」
ミザリイは珍しく言葉を濁した。表情は、少し拗ねているようにも見える。
「言ったのだが……?」
「ふむ、いや、簡単に申せば、私の訴えは退けられた。そして、明日、貴様をマグナラタンへと出向させよと命ぜられた。マグナラタンの図書館長直々にな」
「と、図書館長って、図書館の一番偉い人って事か?」
「うむ、そうだ」
正直、拍子抜けの回答だった。高々図書館の長ごときが魔女に命令出来るのも驚きで、おれは思わず「百五十年を生きた魔女が、図書館の館長に逆らえないんだ?」と問い掛けていた。
「本来なら逆らえんな。マグナラタンは世界最古の図書館だ。歴代館長は、その時代最高の魔女が務めて来た。任期は百年。現館長は三期目。要するに二百年以上最高の魔女であり続けておる、という事だ。私が生まれる前から最高の魔女なのだからな、その様な相手に逆らう魔女など、気が触れておると思われても仕方ない。しかも、その上――」
「その上……?」
おれがおうむ返しで尋ねると、彼女はひとつ溜息を零した。
どう言う意図の溜息かは分りかねたが、感情の起伏が乏しい彼女には珍しい反応だった。
「――その上、現マグナラタン図書館長アート・ココレイト・コーリンは、私の師匠だ。魔女の師弟関係は絶対的。実の親兄弟よりも師弟関係の方が強力な結びつきがあるのだ。言うまでも無く、魔力の差も歴然。私なんぞ師匠に掛かれば一息で消滅させられるであろう。故に絶対に抗う事も逆らう事も出来ん。しかし、案ずることは無い。私はこれまで真面目にマグナラタンと師匠の命令に忠実に働いてきたからな、発言権が全く無い訳では無いのだ。それ故、この度、貴様がマグナラタンへと赴く件に関しては、暫くの猶予を貰った。今すぐ外に出しては色々と危険が伴うかもしれんと、理由をこじつけてな」と彼女は淡々と語る。
平然とおれの目を見詰め、悠々と茶を口にしていた。
そして、おれ自身も何故かそこまでの不安を感じて無いと言う、この事実。
まだ昏睡魔法が抜け切れて無くて精神的に不感症になっているのかもしれない。
要するに、おれはその師匠のところに、取り敢えずは赴かなくて良い、ということだ。たぶん、きっと。
と、それより。おれは「ん?あれ?」思わず声を漏らした。
ミザリイの師匠の名を聞き、ふと思ったのだ。
「ん?どうかしたか?」
「ああ、いや、確かミザリイってさ、ミザリイ・アート・ココレイト、だったよな?」
「うむ、そうだ。ミザリイとは師匠から与えられた名だ。魔女は名乗る際に、師匠と大師匠の名も名乗るのだ。故に、私の姉弟子はマーリン・アート・ココレイトと名乗っておる。大師匠のココレイト・コーリン・ラアラは弟子を多く持たれたお方で、それ故にココレイト・コーリンを名乗る魔女は師匠を含め八名もおられる。その全てが各分野で大成されておる方々ばかりなのでな、私は名乗るだけでそれなりに由緒正しき魔女だと認識されるのだ。師匠が違っても大師匠が同じであれば同じ一門として交流もしやすい。まあ、そうは言っても私は大師匠には会ったことも見たことも無いのだけれどな」
そう言うと彼女は静かに天井を見上げた。
要するに、大師匠は既に天に召された、と言う事なのだろうか?死者に対して想いを馳せる仕草は元居た世界と変わらないのかと思うと何だか感慨深い。
「現代最高の魔女を育てた大師匠も今はもう亡くなっていないってこと?」
おれは天井へと向けていた顔を下ろした彼女へと、そう尋ねた。
「いやいや、それは無い。大師匠ほどの魔女は肉体は滅したとしても膨大な魔力と融合した魂は残り、神の如き存在となられるのだ。一般的には神化と呼ばれるがな。神化した魔女は、基本的に人間界から離れ自然の中で悠久なる時を過ごされる」
「それって、全ての魔女が神化にはならないってこと?」
「神化出来るのは一握りの偉大な魔女だけだ。現代で言う所のアート・ココレイト・コーリンだな。勿論、他にも偉大な魔女はおるし、神化せずに人間界に関与し続ける魔女もいなくは無い」
ここでまた彼女は天井を見詰めた。どうやら死者に想いを馳せている訳では無いらしい。
おれも彼女と同じポイントを見詰める。
「天井に、何かあるのかい?」
「いや、天井のその先だ。どうやら来客ありだ。珍しい。連絡も寄こさずに訪れるとは……。ああ、さてはマグナラタンから貴様の情報が漏れたのだな。私が魔紋を刻んだ人間を見に来たのか……」
「え、それって、他の魔女ってこと?」
「うむ、近くに支配域を持つ魔女だ。同じ魔女同盟に所属しておる仲間、と言った所か。いやしかし案ずるな。少々荒っぽいが悪い魔女では無い」
そう言うと彼女は、ぱちんっと指を鳴らした。
するとすぐに家の扉が勢い良く開いた。おれと然程背丈の変わらない女性が大股で上がり込んで来る。
燃える様な緋色のとんがり帽子とローブ。その大柄さから存在感だけで言うとミザリイよりも強烈で強大だった。
要するにこれで魔女にも色々いる、という事が分かった。
兎に角、面倒くさい奴でなければいい……と思いつつ、おれは息を飲み大柄で派手な魔女の事を見詰めていた。