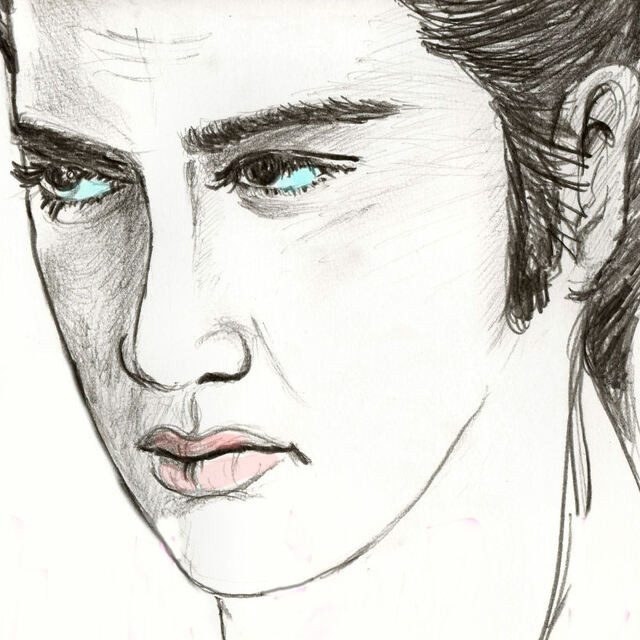侍の言い分
文字数 2,666文字
奉行の淡路肥後の守は、涙を浮かべ肩を振るわせ、白砂に伏している罪人の播磨に言った。
「武士として、どのような理由があろうとも、妹の義父を殺害するとはもってのほかである。しかし、お主が義父を殺したもっともなる理由があると聞いておる、その理由を思いの丈を言うてみよ。お主の地獄へ行く餞 として聞いてつかわそうほどにのう、気の向くままに述べてみよ。その殺したいほどの理由とやらをな……」
「は、はい、お奉行様、格別のお計らい、拙者は涙が出る思いにござりまする……」
そう言って縄に打たれた罪人の播磨は、その思いを白砂で告げることになった。
「そこなる役人よ、今から罪人がことのいきさつを話すのじゃ、も少し楽にさせてよいぞ」
「ははっ!」
侍を拘束している役人は、肩からきつく袈裟懸けにしている荒縄を解いて播磨を楽にさせた。侍の手は相変わらず後ろで重ねられ、縛られている。その若者を見てか知らずか、遠くの梅の木に停まりながら、この世の謳歌とばかりに相変わらずホーホケキョとばかりに囀る鶯の声だけが、その真っ白な白砂の庭で冴え渡っていた。
しかし、他の数人の役人は少し距離を置いて槍を携えていた。いくら奉行の許しがあったとて、役人の身としては注意を怠ってはならないのだ。いくらかの戒めを緩くしたとて、相手が藩一番の剣の使い手とあれば致し方ない。
「では、播磨、義父殺しに至った動機を述べてみよ」
「はい、ありがたきご配慮、播磨、嬉しく思いまする。では……」
播磨と言われた若者は恭しく頭を垂れ一礼すると、目を開けジロリと辺りを見渡した。その目の先には、もうこれからは抱くことも、声すら掛けることもままならない妻の顔が見えた。眼で心を送ると、それを眼で返す妻の心が伝わってきた。
(あなた、さようなら、短い間でしたが……でももうお別れですね)
播磨には、妻の心が空気を伝って、自分の心に伝わるのである。この心境を以心伝心というのだろうか。
(これでいい、これで良いのだ。たとえこの首を刎ねられようとも、青山家で培われてきた武士としての生き様を、身を以て証とせねばならぬ、妹を陵辱されて、この先、男として自分の生きる道など在りはしない、在るとすれば本懐を遂げた今のこの清々しさがあるのみ……)
こうして、義父殺しの罪で囚われの身になった若侍の告白が始まったのである。
下手人の青山播磨という若者は希に見る美男子であり、妹と共に十代の物心が付き始めた頃、病気で両親が病で死別した為に、それぞれに引き取られていった。彼の元の名は山崎真之介と言った。
彼等の身の上を案じた親戚の青山家に真之介は引き取られたのである。そして同じように妹の佳代は、娘のいない遠い親戚の山越家に引き取られていった。お互いの兄弟が同じ所に引き取られるということは、その時の事情が許さなかったからだ。
二人は涙を溜めて別れを告げたが、あれから大分合っていない。青山家は父の弟の繋がりで立派な武家であり、真之介は次第に才覚もあり凛々しく育っていった。
しかし、 真之介は、佳代が引き取られたという山越家という家柄を知らされていないし、聞かされてはいなかった。
青山家では、播磨となった兄と、妹の佳代が引き取られた山越家とは面識がなかったことも、一因と言える。それ以外に、山越家には極端に親戚が少ないという或る事情が絡んでいたからである。
成人した真之介は、播磨と名乗ってからも、いつも妹のことを案じていた。彼は青山家で幸せを享受しながらも、元気に育ってくれていればいいが、と妹のことを常に気に掛けている優しい兄だった。
しかし、実際には兄の切なる思い通りには、妹はなっていなかった。
妹が引き取られた山越家の当主の与左衛門という男は、いわゆる不埒な男だった。元々の家柄はあるのだが、与左衛門の時代になってから、どうやらおかしくなっていったようである。
彼は変な癖があり、妻となった女はついに愛想が尽きて、出ていってしまった。何人かいた召使いの女達には手を出し、それを嫌った女はいつのまにかいなくなった。後に残った女と言えば、賄いや掃除などをする為に雇った色気の無い女ばかりである。
しかし、その中でも、一人だけ前から居残っていた希有な女がいた。その名前をお佐和と言ったが、以前は女中の出身であり、居残ったのは女の家の事情によるからである。
貧しいが故に、実家に帰ることが出来ず、与左衛門の言いなりになっていさえすれば、実家が潤うという打算が働いていたからで、そこで貰う手当を貧しい実家に送るという優しい心がけの女ではあったが。
今では、与左衛門の妾のような存在であり、彼の言いなりになり、その身に甘んじていれば安泰であることに身を任せていた。
始めに奉公に来ていた頃は気の優しい女だったが、今はその面影も無い。与左衛門の性癖は、女を手籠めにし、それを部下の侍達に見せつけることで快感を得ていたのだ。
お佐和は始めは、それが死ぬほど辛かった 、出来ればこんなことはされたくなかった。
着物をはだけて、その姿を家来達に見られているという羞恥と恐怖があるからだ。
「それ、お佐和、もっと狂え、もっと悶えろ」
「いやです、ご主人様、許して下さい」
「ダメだ」
「あぁ……」
来る日も、来る日もそんな責めに合い、お佐和の心と身体は次第に変わっていった。馴れとは怖ろしいもので、それが次第に慣らされていく。家来達は始めはその行為に嫌がり驚いたが、それも毎度のことでありいつしか彼等も慣れていった。
世の習わしとして長い物には巻かれろという諺がある。
今更、主人を替えられないという事情がある者達はそれを傍観するか、無視するしか無いのだ。そうなると、与左衛門としては面白くない。それに物珍しがり屋の与左衛門としても、そろそろ年増になってきたこのお佐和にも飽きてきたからである。
始めの頃はピチピチとしていた身体も、腰が太くなり腹も出てきたお佐和にはなんの興味も示さなくなっていた。いつの時代でも、こういう強欲で好色な男はいるものである。
与左衛門は、お佐和にそのような女を捜させてくるのだ。
「お佐和、お前の知り合いや、近くの者で良い女を見つけてこい」
「は、はい。そうは言いましても中々そのような女子は……」
「馬鹿野郎、それが今のお前の仕事なんだ、わしを満足出来ないのなら、自分で見つけてこい、そうでもしなけりゃ、お前を放り出すか、又は手当が無くなっても良いんだな」
「い、いえっ、それは困ります、はい、では何とか……」
「武士として、どのような理由があろうとも、妹の義父を殺害するとはもってのほかである。しかし、お主が義父を殺したもっともなる理由があると聞いておる、その理由を思いの丈を言うてみよ。お主の地獄へ行く
「は、はい、お奉行様、格別のお計らい、拙者は涙が出る思いにござりまする……」
そう言って縄に打たれた罪人の播磨は、その思いを白砂で告げることになった。
「そこなる役人よ、今から罪人がことのいきさつを話すのじゃ、も少し楽にさせてよいぞ」
「ははっ!」
侍を拘束している役人は、肩からきつく袈裟懸けにしている荒縄を解いて播磨を楽にさせた。侍の手は相変わらず後ろで重ねられ、縛られている。その若者を見てか知らずか、遠くの梅の木に停まりながら、この世の謳歌とばかりに相変わらずホーホケキョとばかりに囀る鶯の声だけが、その真っ白な白砂の庭で冴え渡っていた。
しかし、他の数人の役人は少し距離を置いて槍を携えていた。いくら奉行の許しがあったとて、役人の身としては注意を怠ってはならないのだ。いくらかの戒めを緩くしたとて、相手が藩一番の剣の使い手とあれば致し方ない。
「では、播磨、義父殺しに至った動機を述べてみよ」
「はい、ありがたきご配慮、播磨、嬉しく思いまする。では……」
播磨と言われた若者は恭しく頭を垂れ一礼すると、目を開けジロリと辺りを見渡した。その目の先には、もうこれからは抱くことも、声すら掛けることもままならない妻の顔が見えた。眼で心を送ると、それを眼で返す妻の心が伝わってきた。
(あなた、さようなら、短い間でしたが……でももうお別れですね)
播磨には、妻の心が空気を伝って、自分の心に伝わるのである。この心境を以心伝心というのだろうか。
(これでいい、これで良いのだ。たとえこの首を刎ねられようとも、青山家で培われてきた武士としての生き様を、身を以て証とせねばならぬ、妹を陵辱されて、この先、男として自分の生きる道など在りはしない、在るとすれば本懐を遂げた今のこの清々しさがあるのみ……)
こうして、義父殺しの罪で囚われの身になった若侍の告白が始まったのである。
下手人の青山播磨という若者は希に見る美男子であり、妹と共に十代の物心が付き始めた頃、病気で両親が病で死別した為に、それぞれに引き取られていった。彼の元の名は山崎真之介と言った。
彼等の身の上を案じた親戚の青山家に真之介は引き取られたのである。そして同じように妹の佳代は、娘のいない遠い親戚の山越家に引き取られていった。お互いの兄弟が同じ所に引き取られるということは、その時の事情が許さなかったからだ。
二人は涙を溜めて別れを告げたが、あれから大分合っていない。青山家は父の弟の繋がりで立派な武家であり、真之介は次第に才覚もあり凛々しく育っていった。
しかし、 真之介は、佳代が引き取られたという山越家という家柄を知らされていないし、聞かされてはいなかった。
青山家では、播磨となった兄と、妹の佳代が引き取られた山越家とは面識がなかったことも、一因と言える。それ以外に、山越家には極端に親戚が少ないという或る事情が絡んでいたからである。
成人した真之介は、播磨と名乗ってからも、いつも妹のことを案じていた。彼は青山家で幸せを享受しながらも、元気に育ってくれていればいいが、と妹のことを常に気に掛けている優しい兄だった。
しかし、実際には兄の切なる思い通りには、妹はなっていなかった。
妹が引き取られた山越家の当主の与左衛門という男は、いわゆる不埒な男だった。元々の家柄はあるのだが、与左衛門の時代になってから、どうやらおかしくなっていったようである。
彼は変な癖があり、妻となった女はついに愛想が尽きて、出ていってしまった。何人かいた召使いの女達には手を出し、それを嫌った女はいつのまにかいなくなった。後に残った女と言えば、賄いや掃除などをする為に雇った色気の無い女ばかりである。
しかし、その中でも、一人だけ前から居残っていた希有な女がいた。その名前をお佐和と言ったが、以前は女中の出身であり、居残ったのは女の家の事情によるからである。
貧しいが故に、実家に帰ることが出来ず、与左衛門の言いなりになっていさえすれば、実家が潤うという打算が働いていたからで、そこで貰う手当を貧しい実家に送るという優しい心がけの女ではあったが。
今では、与左衛門の妾のような存在であり、彼の言いなりになり、その身に甘んじていれば安泰であることに身を任せていた。
始めに奉公に来ていた頃は気の優しい女だったが、今はその面影も無い。与左衛門の性癖は、女を手籠めにし、それを部下の侍達に見せつけることで快感を得ていたのだ。
お佐和は始めは、それが死ぬほど辛かった 、出来ればこんなことはされたくなかった。
着物をはだけて、その姿を家来達に見られているという羞恥と恐怖があるからだ。
「それ、お佐和、もっと狂え、もっと悶えろ」
「いやです、ご主人様、許して下さい」
「ダメだ」
「あぁ……」
来る日も、来る日もそんな責めに合い、お佐和の心と身体は次第に変わっていった。馴れとは怖ろしいもので、それが次第に慣らされていく。家来達は始めはその行為に嫌がり驚いたが、それも毎度のことでありいつしか彼等も慣れていった。
世の習わしとして長い物には巻かれろという諺がある。
今更、主人を替えられないという事情がある者達はそれを傍観するか、無視するしか無いのだ。そうなると、与左衛門としては面白くない。それに物珍しがり屋の与左衛門としても、そろそろ年増になってきたこのお佐和にも飽きてきたからである。
始めの頃はピチピチとしていた身体も、腰が太くなり腹も出てきたお佐和にはなんの興味も示さなくなっていた。いつの時代でも、こういう強欲で好色な男はいるものである。
与左衛門は、お佐和にそのような女を捜させてくるのだ。
「お佐和、お前の知り合いや、近くの者で良い女を見つけてこい」
「は、はい。そうは言いましても中々そのような女子は……」
「馬鹿野郎、それが今のお前の仕事なんだ、わしを満足出来ないのなら、自分で見つけてこい、そうでもしなけりゃ、お前を放り出すか、又は手当が無くなっても良いんだな」
「い、いえっ、それは困ります、はい、では何とか……」