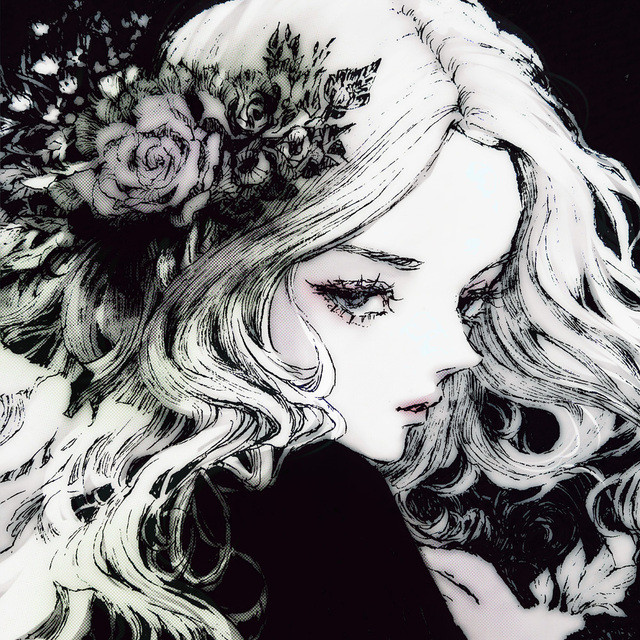第202話 ミリテアの決意
文字数 2,462文字
手渡された小さな箱を開けると、そこにはオモチャのような小さな指輪。
子供の時の、小さな約束。
『ゼブリスとあたしは、きっと結婚するのよ。そしてね、可愛い子供に囲まれて、小さなお城に住むの。
きっとよ?約束よ?』
ミリテアが家に来る細工師に、こっそり作ってもらった二人のイニシャルが刻んである飾りの無い小さなリング。
生まれた時から婚約して、それは当たり前のように大好きだった。
きっと、結婚するのだと、それが当たり前のように思っていたのに。
だがその約束は、あっと言う間に崩れて婚約は兄へと移り、彼女は手の中から消えていった。
「これは、確か母に頼んで処分したはず……」
父に勝手に未来を変更されても抗えず、見るのも辛いからと頼んだのに、処分していなかったのか。
「それと、こちらの書状を。」
手紙を受け取り、暗い階段の小さな窓から差し込む一筋の光に照らしてそれを読む。
それは、忘れもしないミリテアの優しい文字。
ゼブリスルーンレイアは、その短い手紙を読むと手がガタガタと震えた。
「な、なぜ!なぜこんな……彼女は、何を考えている!」
「確かにお届けいたしました。では、私はまた消えまする。
ご入り用なときはいつでもお使い下さい。
今の私はあなたの為におります。」
ただ、手紙を凝視する彼を置いて、ミスリルはまた闇に消える。
ゼブリスルーンレイアは、手紙の文字を何度も繰り返し読みながら、知らずあふれ出る涙を拭うことも忘れてその場に立ち尽くした。
『ゼブリス、勝手なことをしてごめんなさい。
でも、私はどうしても消せないこの思いをあなたに伝えたい。
あなたが好き。
このままでは心が壊れてしまいそう。
私の隣にはあなたが、どうかあなたがいて欲しい。
だからお願い、この指輪を受け取って。
そうしたら、私はほんの少し強くなれるから。』
なんてことだろう。
彼女は自分の家に、そしてレナパルド家に泥を塗ってでも家を出る気だ。
父がそれを許すはずが無い。
彼女の家も名家で知られていると言っても、一貴族でしか無いのに。
震える指で指輪を取る。
あの頃は大きすぎると感じていたのに、それはもう小さくて小指にしか入らない。
それほどの時間が過ぎ去ってしまった。
指輪を返せば、彼女は諦めて何事も無く兄との結婚式は終わるだろう。
返さなければ、彼女は……彼女の家は、父の、貴族院の長の怒りを買って名も知れぬ田舎の領主などへと落ちぶれるかもしれない。
すべてが壊れてしまうかもしれないのに。
それでも、
彼女はそこまでの覚悟があるというのか。
私に、それを選べというのか。
馬鹿げている。
大きく何度も首を振り、小指の指輪を握りしめる。
私に、そんな……そんな勇気など、家に逆らう意気など無い。
一緒に貴族を捨てるなど、出来るはずも無いではないか。
ミリテアは、上流階級で生きてきた貴族の子女だ。
彼女が貧乏に耐えられるわけが無い。
息を吐き、うなだれて力なく笑う。
小指の指輪をはずし、箱に戻そうとしてふと思い止まり、指にとった。
小さな指輪、彼女の決意。
明かり取りの窓に、その指輪を照らしリングの中から差し込む日の光を浴びて、まぶしさに目を細めた。
“お前の、愛する者はおらぬのか?
お前を、求め愛する者はおらぬのか?
お前はその短い生を、諦めだけで満たして終わって、それでよいのか?”
フレアゴートの言葉が、遠くから自分に問いかける。
ああ、
ああ、
私は…………
フレアゴートよ、希望の光の精霊よ、
私は、自分のために生きてもいいのだろうか。
ああ、でもなぜ、私が自分のために生きるには、沢山の犠牲が必要なのだろう。
でも、それでも……彼女は、それでもと………
目を閉じ、唇を噛み締める。
大きく深呼吸して、顔を上げ心に決めた。
涙をふき、ゼブリスルーンレイアは指輪をギュッと握りしめ、そして胸に押しつけると左手の小指にしっかりと通した。
「まだいるか?」
「ここに」
暗闇から先ほどのミスリルがまた現れる。
ゼブリスルーンレイアは指輪の入っていた空の小箱を差し出し、すうっと深呼吸した。
「これを渡してくれ、これが答えだと。」
「は、……よろしいので?」
「……そうだな、父に知られると命を狙われるかもしれぬな…………
だが、彼女がそう望むのだ。
ならば、それに答えることも、私の道であって良いはずだ。
なれば、答えようと思う。」
「はい、承知致しました。』
「力に……なって、くれぬか?」
「私は、あなたにお仕えせよと命令されてここにおります。どうぞ心置きなく。」
膝を付くミスリルに、目を閉じる。
父に知れたら、お前も同罪になってしまうのだ。それでもと……
「お前の命を賭けることになるかもしれない。」
「承知しております。どうぞご命令を。」
「わかった、だがこれは命令とは言うまい。これはそなたへの頼みだ。
今、私は彼女と共にいることが出来ない。そなたが彼女の力になってくれ。
これからしばし私は、王子に最後のお力添えをしなくてはならない。」
「そ、それは……
もったいなきお言葉にございますが……」
「良いのだ、これで私の気持ちもはっきりとした。
あと、もしや命の危険に及ぶことがあるやも知れん、彼女をどこかにかくまうことは出来るか?」
「はい、お任せを、安全な所にお連れします。
聡明な方ゆえ、我らミスリルにもご理解のある御方です。」
「そうか、では任せたぞ。
……そなたにも、迷惑をかける。名は?」
「は、ガイラと申します。」
「良い名だ。すまぬ、ガイラ頼むぞ。」
「はっ!この命に替えましても、お守り致します!」
ガイラが、一礼して階下へと降りて行く。
その後ろ姿に、心の中で手を合わせた。
自分はずっと城中暮らしで、ずっと張り詰めるばかりで誰も信用してこなかった。
それがこう言う時、頼れる者が誰も浮かばないという事になるとは……
彼だけが、ガイラだけが今は頼りだ。
自分や彼女が、貴族を捨てて生きていけるかわからない。
でも、それでも……
前途多難だが、すべてが落ちついて、それから考えよう。
今は、王子の事を考えるのみ。
ゼブリスルーンレイアは、指にある指輪を見て口づけすると、顔を引き締め王子の部屋へと急いだ。
子供の時の、小さな約束。
『ゼブリスとあたしは、きっと結婚するのよ。そしてね、可愛い子供に囲まれて、小さなお城に住むの。
きっとよ?約束よ?』
ミリテアが家に来る細工師に、こっそり作ってもらった二人のイニシャルが刻んである飾りの無い小さなリング。
生まれた時から婚約して、それは当たり前のように大好きだった。
きっと、結婚するのだと、それが当たり前のように思っていたのに。
だがその約束は、あっと言う間に崩れて婚約は兄へと移り、彼女は手の中から消えていった。
「これは、確か母に頼んで処分したはず……」
父に勝手に未来を変更されても抗えず、見るのも辛いからと頼んだのに、処分していなかったのか。
「それと、こちらの書状を。」
手紙を受け取り、暗い階段の小さな窓から差し込む一筋の光に照らしてそれを読む。
それは、忘れもしないミリテアの優しい文字。
ゼブリスルーンレイアは、その短い手紙を読むと手がガタガタと震えた。
「な、なぜ!なぜこんな……彼女は、何を考えている!」
「確かにお届けいたしました。では、私はまた消えまする。
ご入り用なときはいつでもお使い下さい。
今の私はあなたの為におります。」
ただ、手紙を凝視する彼を置いて、ミスリルはまた闇に消える。
ゼブリスルーンレイアは、手紙の文字を何度も繰り返し読みながら、知らずあふれ出る涙を拭うことも忘れてその場に立ち尽くした。
『ゼブリス、勝手なことをしてごめんなさい。
でも、私はどうしても消せないこの思いをあなたに伝えたい。
あなたが好き。
このままでは心が壊れてしまいそう。
私の隣にはあなたが、どうかあなたがいて欲しい。
だからお願い、この指輪を受け取って。
そうしたら、私はほんの少し強くなれるから。』
なんてことだろう。
彼女は自分の家に、そしてレナパルド家に泥を塗ってでも家を出る気だ。
父がそれを許すはずが無い。
彼女の家も名家で知られていると言っても、一貴族でしか無いのに。
震える指で指輪を取る。
あの頃は大きすぎると感じていたのに、それはもう小さくて小指にしか入らない。
それほどの時間が過ぎ去ってしまった。
指輪を返せば、彼女は諦めて何事も無く兄との結婚式は終わるだろう。
返さなければ、彼女は……彼女の家は、父の、貴族院の長の怒りを買って名も知れぬ田舎の領主などへと落ちぶれるかもしれない。
すべてが壊れてしまうかもしれないのに。
それでも、
彼女はそこまでの覚悟があるというのか。
私に、それを選べというのか。
馬鹿げている。
大きく何度も首を振り、小指の指輪を握りしめる。
私に、そんな……そんな勇気など、家に逆らう意気など無い。
一緒に貴族を捨てるなど、出来るはずも無いではないか。
ミリテアは、上流階級で生きてきた貴族の子女だ。
彼女が貧乏に耐えられるわけが無い。
息を吐き、うなだれて力なく笑う。
小指の指輪をはずし、箱に戻そうとしてふと思い止まり、指にとった。
小さな指輪、彼女の決意。
明かり取りの窓に、その指輪を照らしリングの中から差し込む日の光を浴びて、まぶしさに目を細めた。
“お前の、愛する者はおらぬのか?
お前を、求め愛する者はおらぬのか?
お前はその短い生を、諦めだけで満たして終わって、それでよいのか?”
フレアゴートの言葉が、遠くから自分に問いかける。
ああ、
ああ、
私は…………
フレアゴートよ、希望の光の精霊よ、
私は、自分のために生きてもいいのだろうか。
ああ、でもなぜ、私が自分のために生きるには、沢山の犠牲が必要なのだろう。
でも、それでも……彼女は、それでもと………
目を閉じ、唇を噛み締める。
大きく深呼吸して、顔を上げ心に決めた。
涙をふき、ゼブリスルーンレイアは指輪をギュッと握りしめ、そして胸に押しつけると左手の小指にしっかりと通した。
「まだいるか?」
「ここに」
暗闇から先ほどのミスリルがまた現れる。
ゼブリスルーンレイアは指輪の入っていた空の小箱を差し出し、すうっと深呼吸した。
「これを渡してくれ、これが答えだと。」
「は、……よろしいので?」
「……そうだな、父に知られると命を狙われるかもしれぬな…………
だが、彼女がそう望むのだ。
ならば、それに答えることも、私の道であって良いはずだ。
なれば、答えようと思う。」
「はい、承知致しました。』
「力に……なって、くれぬか?」
「私は、あなたにお仕えせよと命令されてここにおります。どうぞ心置きなく。」
膝を付くミスリルに、目を閉じる。
父に知れたら、お前も同罪になってしまうのだ。それでもと……
「お前の命を賭けることになるかもしれない。」
「承知しております。どうぞご命令を。」
「わかった、だがこれは命令とは言うまい。これはそなたへの頼みだ。
今、私は彼女と共にいることが出来ない。そなたが彼女の力になってくれ。
これからしばし私は、王子に最後のお力添えをしなくてはならない。」
「そ、それは……
もったいなきお言葉にございますが……」
「良いのだ、これで私の気持ちもはっきりとした。
あと、もしや命の危険に及ぶことがあるやも知れん、彼女をどこかにかくまうことは出来るか?」
「はい、お任せを、安全な所にお連れします。
聡明な方ゆえ、我らミスリルにもご理解のある御方です。」
「そうか、では任せたぞ。
……そなたにも、迷惑をかける。名は?」
「は、ガイラと申します。」
「良い名だ。すまぬ、ガイラ頼むぞ。」
「はっ!この命に替えましても、お守り致します!」
ガイラが、一礼して階下へと降りて行く。
その後ろ姿に、心の中で手を合わせた。
自分はずっと城中暮らしで、ずっと張り詰めるばかりで誰も信用してこなかった。
それがこう言う時、頼れる者が誰も浮かばないという事になるとは……
彼だけが、ガイラだけが今は頼りだ。
自分や彼女が、貴族を捨てて生きていけるかわからない。
でも、それでも……
前途多難だが、すべてが落ちついて、それから考えよう。
今は、王子の事を考えるのみ。
ゼブリスルーンレイアは、指にある指輪を見て口づけすると、顔を引き締め王子の部屋へと急いだ。