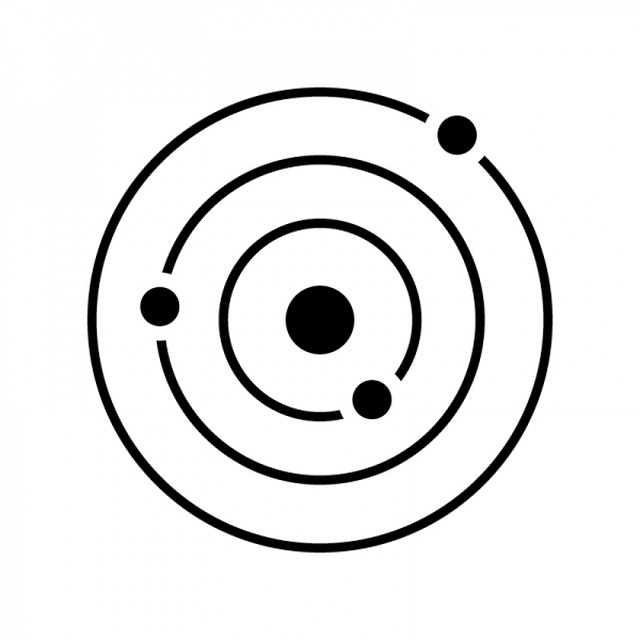第33話 日々
文字数 814文字
二つの原子爆弾が日本に落ちて、戦争は終わった。
電波が運んだ終戦の知らせを、月子は夢現 に聞いているようだと思った。きっと今まで、こんな光景を目にしたことがなかったせいだ。
家族全員が同じ方向に身体を向けたまま、同じような角度で俯いていた。
月子はその時、じっと畳目を凝視していた。雑音の混ざった音声は、段々別の言語のように聞こえてくる。
畳の目の中に、小さな砂粒をひとつふたつ、見つけていた。
月子はその後、数年経った後でも、あの時聞いた『玉音放送』を頭の中で諳んじることができた。放送のどの部分で大きなノイズが入ったのか、そんなことまで鮮明に記憶している。
戦争は終わったのだった。
弟の一人が、
「月子姉 だから言うけど」
と神妙な顔で打ち明けた。
「いつ兵隊にならなきゃいけないんだろうって、怖かった……行かずに終わったんだ。俺は、生き延びたんだ」
***
とはいえ、その後は戦時中と変わらない、いや、それ以上に空腹と疲労に苦しむ日々が待っていた。
W村ではどの家でも食糧を作っていたが、自分たちで食べる分を残しつつ、他所の人間に分けてやる余剰はそれほど多くなかった。はじめのうちは「家財と食べ物を交換しにやってくる人を、断るのが心苦しい」と辛そうだった母も、次第に溜息すらつかずに首を振ることを躊躇しなくなった。
子供たちが虫の蛹 を見つけてくるのも、以前は純粋なただの遊びだったはずだ。しかし今では、それは彼らの真剣な「狩り」だった。煎って食べれば、味はわりと気にならない。そんなことを最初に発見したのは、一体誰なのだろう。
月子は一人になる時間を見つけては、龍の鱗を袋から取り出した。肌身離さず身につけているので、触れるといつも温かい。
相変わらず黄金色に輝いて、根本には乾かないままの血が付いている。
月子は艷やかに光るその場所に、口付けるのだ。
――鉄の味がする
そして月子は自分も確かに生きていることを、実感するのだった。
電波が運んだ終戦の知らせを、月子は
家族全員が同じ方向に身体を向けたまま、同じような角度で俯いていた。
月子はその時、じっと畳目を凝視していた。雑音の混ざった音声は、段々別の言語のように聞こえてくる。
畳の目の中に、小さな砂粒をひとつふたつ、見つけていた。
月子はその後、数年経った後でも、あの時聞いた『玉音放送』を頭の中で諳んじることができた。放送のどの部分で大きなノイズが入ったのか、そんなことまで鮮明に記憶している。
戦争は終わったのだった。
弟の一人が、
「月子
と神妙な顔で打ち明けた。
「いつ兵隊にならなきゃいけないんだろうって、怖かった……行かずに終わったんだ。俺は、生き延びたんだ」
***
とはいえ、その後は戦時中と変わらない、いや、それ以上に空腹と疲労に苦しむ日々が待っていた。
W村ではどの家でも食糧を作っていたが、自分たちで食べる分を残しつつ、他所の人間に分けてやる余剰はそれほど多くなかった。はじめのうちは「家財と食べ物を交換しにやってくる人を、断るのが心苦しい」と辛そうだった母も、次第に溜息すらつかずに首を振ることを躊躇しなくなった。
子供たちが虫の
月子は一人になる時間を見つけては、龍の鱗を袋から取り出した。肌身離さず身につけているので、触れるといつも温かい。
相変わらず黄金色に輝いて、根本には乾かないままの血が付いている。
月子は艷やかに光るその場所に、口付けるのだ。
――鉄の味がする
そして月子は自分も確かに生きていることを、実感するのだった。