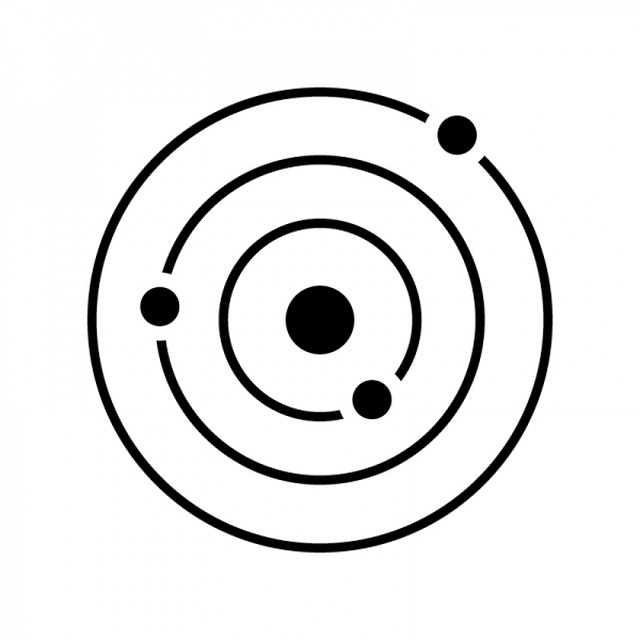第1話 上がる手
文字数 1,340文字
痺れるような強烈な臭気が、辺りに立ち込めている。
――もっと風が吹けば、匂いなどすぐに気にならなくなるのに
生憎今日の風は緩かった。ほとんど無風と言ってもいいほどに、穏やかに晴れた春の日だ。
――燃やすには、確かにちょうどいい日だ
風が強い日に大きな炎を熾すのは、危険なのだ。田畑に燃え移っては大惨事である。
月子は燃え盛る炎から視線を外し、足元を見た。土で汚れた草履を履いた自分の足と、ハコベやスミレの小さな花が目に入る。手を伸ばして届く範囲のものを全て摘み取って、彼女は立ち上がった。
「お別れするのにも、良い日だね」
炎の中に、小さな野花を放り投げる。
パチパチと爆ぜる音を聞きながら、月子は赤い炎の中央、黒い塊を静かに見つめた。
――そろそろかな
初めてではない。
何度目かは、数え忘れているので定かではない。けれど月子はこういう炎を見守ることに、慣れている。正確に計算しなくとも、火の大きさ、爆ぜる音の間隔や大きさ、匂いの強さ諸々の感覚で、頃合いが分かるようになっていた。
――もうすぐ
バン! と大きな破裂音と共に、火の中から二本の人の腕が立ち上がった。
「出てきた」
熱気でこれ以上近づくことは出来ない。目を細めながら、月子は炎の中央を観察する。
そこで彼女のよく知る人物の身体が、燃えていた。
大柄な人だった。用意した棺代わりの木箱には案の定入り切らなくて、手足を折り曲げて押し込めるしかなかった。大人の男ではありがちなことである。
村の衆は木箱に身体を入れながら、
『ごめんなぁ。身体痛いよなぁ』
『すぐに楽になるからな』
口々にそんな言葉をかけていた。これも毎度のことである。
――燃やすと、なぜ手足は伸びるのかしら
月子には原理は分からなかったが、そういうものなのだろう。棺に屈曲させて押し込んだ遺体は、燃やされて一定の時間が経過すると、ピンと身体を伸ばすのだ。燃え朽ちて弱った棺の板を、内側から破壊できるほどの力が生まれる。
――もう死んでいるはずなのに。不思議
九歳の月子は、不思議を感じても恐怖とは思わなかった。
同じ年頃の子供や、月子よりも年長の子供たち、大人でさえも怖がる現象なのだが。
村で誰かが亡くなって、火葬を行う時、炎の番が必要となる。その役目を率先して引き受けたがる者はいない。
――役得だと思うんだけどな。確かに臭いはきついけど
月子は炎の中に向かって、手を振った。
黒く焼けただれていく腕は、天に向って五本の指を広げながら、ゆらゆらと揺れている。
――一番最後まで、一緒にいられるのだから
立ち上がった二本の腕は、やがてゆっくりと落ちていく。今度こそ力尽きたとでも言うように。
「さよなら」
なんまいだぶ、と唱えるべきところなのだろう。しかし月子は、何となく「さようなら」と別れの挨拶を口にしたくなるのだ。
もう少し経ったら、炎の奥に手足の形を確認できなくなるだろう。日が暮れるころまでかかるだろうか。暗くなる前には、きっと次の人と交代になるはずだ。
「もうすぐお骨拾ってもらえるからね。皆やってくるよ。寂しくないからね。大丈夫」
炎の奥から聞こえてくるパチパチという音が、どこか切なげに聞こえて、月子はそんな言葉を祖父の遺体に向かってかけていた。