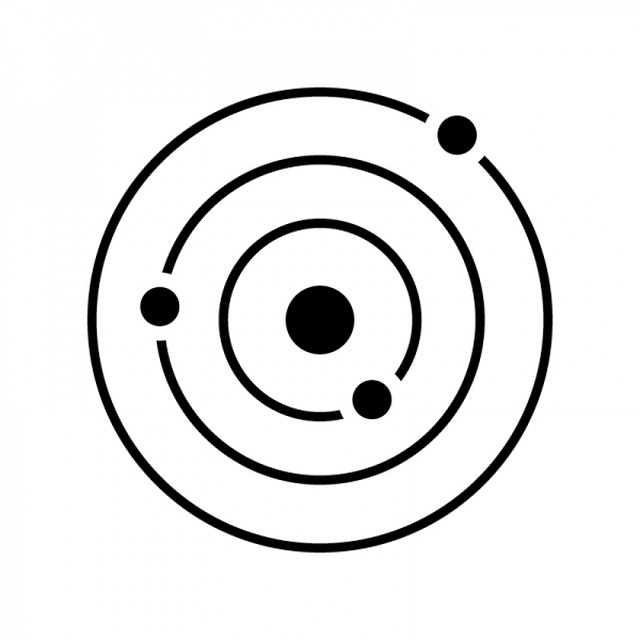最終話 面影
文字数 1,326文字
数十年後。
あの日々を生きた人が、ほとんどいなくなりかけた頃。
自分もそろそろあちら側に行く頃合いだと、克輝は強く感じるようになっていた。
両親は勿論、妻も、兄も、友人たちも既に殆どが鬼籍に入っている。
高齢者は真夏の暑さを乗り切れない事が多い――誰かから聞いたそんな言葉が、現実味を帯びてきた。
蒸し暑い日だった。
「じいちゃん!」
よく通る声は、一番下の孫のものだ。十八になったばかりの雄二の声は、特別大きい。すっかり遠くなってしまった耳にも、彼の声はいつもよく聞こえた。聞き返す手間がないので、克輝は雄二との会話が好きだった。
「じいちゃん! 起きてる?」
座椅子にもたれて、ウトウトしていた。夏も近い。汗ばむ陽気だと皆言うが、克輝にはその感覚もよく分からなくなっていた。暑さを煩わしく感じないのなら、老衰も悪くないかもしれない。
「雄二。どうした」
「じいちゃん、大ニュース!」
孫は六人いるが、雄二は幼い頃から特に克輝に懐いていた。気質が似ていて、よく遊び相手をしていたからかも知れない。幼児の頃から続けていたスイミングスクールの送迎も、免許を返納するまで務めていたのは克輝だった。
「俺、インターハイ決まった!」
「本当か」
急に立ち上がることはできない。膝もすっかり悪くなってしまったし、立位を取れても全身の震えが止むことはなかった。
本当は大声で喜びを表現したくても、喉も口も言うことを聞いてはくれない。
――やはり、老衰はもどかしいものだ
衰えきった身体のせいで、大会の応援にも繰り出せなかった。せめてすぐに朗報を受け取れるようにと、携帯電話を握りしめながら待っていたはずなのに。いつの間にか目的も忘れて、眠りこけている始末である。
「おめでとう。よかったなぁ雄二」
「ありがとう。今日は寿司取ってくれるって、母さんが」
克輝の側まで近寄った雄二は、スマートフォンを操作した。画面に映し出されたのは、水の中を泳ぐ高校生たちだった。
「別の学校の選手だよ。気を緩めないで予習しとけって、コーチが動画送ってくれたんだ」
泳ぎ終えた選手達が、水泳帽とゴーグルを外している場面になっていた。画面がアップになり、彼ら一人ひとりの表情がよく見えるようになる。
そこで、克輝は静かに息を飲んだ。おもむろにテーブルの方へと動いた祖父の手に、雄二が眼鏡を握らせる。
いくらか明瞭になった視界に、見覚えのある色が映った。
「……彼は?」
数人の選手を順番に映していた映像は、最後の方で一人にフォーカスしていた。先程のレースで、抜きん出た早さで泳ぎきった選手である。
「東京の代表だって。めちゃくちゃ早いよな……俺、あんな化け物と戦うのかあ。大丈夫かな、自信なくなってくる」
説明する孫の声が、遠くなっていった。
『化け物』という単語だけが、遥な意識の中で反芻されている。
克輝は小さな画面の向こうに自分が見たものを、ほんの一瞬だけ、耄碌 した脳が見せた幻覚かと疑った。
――……月子
遠い昔の初恋の人を呼んだ。
脳裏に浮かんだ彼女の顔は、炎を前に赤く煌やいていた。人の肉体が焼ける臭いが蘇る。
彼女を攫っていった、不思議な少年。
知らない高校生の顔の上に、克輝はその面影を感じたのだった。
あの日々を生きた人が、ほとんどいなくなりかけた頃。
自分もそろそろあちら側に行く頃合いだと、克輝は強く感じるようになっていた。
両親は勿論、妻も、兄も、友人たちも既に殆どが鬼籍に入っている。
高齢者は真夏の暑さを乗り切れない事が多い――誰かから聞いたそんな言葉が、現実味を帯びてきた。
蒸し暑い日だった。
「じいちゃん!」
よく通る声は、一番下の孫のものだ。十八になったばかりの雄二の声は、特別大きい。すっかり遠くなってしまった耳にも、彼の声はいつもよく聞こえた。聞き返す手間がないので、克輝は雄二との会話が好きだった。
「じいちゃん! 起きてる?」
座椅子にもたれて、ウトウトしていた。夏も近い。汗ばむ陽気だと皆言うが、克輝にはその感覚もよく分からなくなっていた。暑さを煩わしく感じないのなら、老衰も悪くないかもしれない。
「雄二。どうした」
「じいちゃん、大ニュース!」
孫は六人いるが、雄二は幼い頃から特に克輝に懐いていた。気質が似ていて、よく遊び相手をしていたからかも知れない。幼児の頃から続けていたスイミングスクールの送迎も、免許を返納するまで務めていたのは克輝だった。
「俺、インターハイ決まった!」
「本当か」
急に立ち上がることはできない。膝もすっかり悪くなってしまったし、立位を取れても全身の震えが止むことはなかった。
本当は大声で喜びを表現したくても、喉も口も言うことを聞いてはくれない。
――やはり、老衰はもどかしいものだ
衰えきった身体のせいで、大会の応援にも繰り出せなかった。せめてすぐに朗報を受け取れるようにと、携帯電話を握りしめながら待っていたはずなのに。いつの間にか目的も忘れて、眠りこけている始末である。
「おめでとう。よかったなぁ雄二」
「ありがとう。今日は寿司取ってくれるって、母さんが」
克輝の側まで近寄った雄二は、スマートフォンを操作した。画面に映し出されたのは、水の中を泳ぐ高校生たちだった。
「別の学校の選手だよ。気を緩めないで予習しとけって、コーチが動画送ってくれたんだ」
泳ぎ終えた選手達が、水泳帽とゴーグルを外している場面になっていた。画面がアップになり、彼ら一人ひとりの表情がよく見えるようになる。
そこで、克輝は静かに息を飲んだ。おもむろにテーブルの方へと動いた祖父の手に、雄二が眼鏡を握らせる。
いくらか明瞭になった視界に、見覚えのある色が映った。
「……彼は?」
数人の選手を順番に映していた映像は、最後の方で一人にフォーカスしていた。先程のレースで、抜きん出た早さで泳ぎきった選手である。
「東京の代表だって。めちゃくちゃ早いよな……俺、あんな化け物と戦うのかあ。大丈夫かな、自信なくなってくる」
説明する孫の声が、遠くなっていった。
『化け物』という単語だけが、遥な意識の中で反芻されている。
克輝は小さな画面の向こうに自分が見たものを、ほんの一瞬だけ、
――……月子
遠い昔の初恋の人を呼んだ。
脳裏に浮かんだ彼女の顔は、炎を前に赤く煌やいていた。人の肉体が焼ける臭いが蘇る。
彼女を攫っていった、不思議な少年。
知らない高校生の顔の上に、克輝はその面影を感じたのだった。