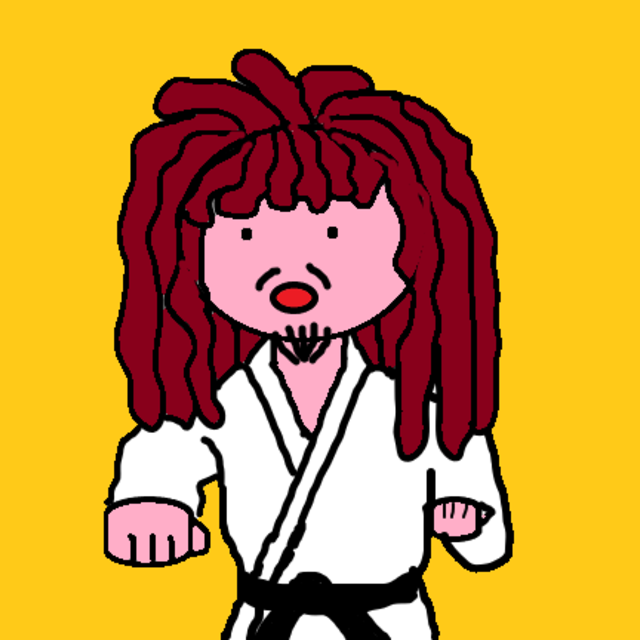第22話 秘奥技炸裂する
文字数 3,090文字
北海道のヒグマの前手での一撃は、馬の頭部を吹き飛ばすほどの威力があるという。
武樽の奥技・熊の手はそのような熊の戦闘スタイルを模したもので、両手を振り回すように使うことで威力を増大させている。
もちろんただ形を真似ただけでは大した威力にはならないが、武樽はこの三年の間、最初は大鍋で炒った豆に両手の指先を突き入れる訓練をし、二年目には砂、三年目には砂利を突いて指を鍛えた。最終的に幼児の拳大ほどの鉄球で満たした鍋を突くようになったころには、その指先は畳を貫き、板塀や湯呑に穴を開けるほどになっていた。まさに人間凶器の完成である。
そのように凶器と化した両手で挟み込むような攻撃がチルーを襲った。
熊の手の危険な威力を本能的に察知したチルーは、虎の手の構えを崩さぬままで大きく跳び退った。
胸元をかすめた武樽の熊の手は、チルーの着物を切り裂いた。あらわになったチルーの白い胸元には五筋の剃刀が走ったような傷が付き、血が滲んでいる。その様子を見た武樽が言った。
「チルー、お前の美しい身体に傷をつけるのは俺も胸が痛むぞ。どうだ、もう降参して早く俺たちの祝言を上げないか」
そんな武樽の提案は聞き流して、チルーは考えていた。
(威力に脅えて跳び退ったんじゃだめだ。危険を承知で内懐に飛び込まなくては)
覚悟を決めたチルーは、武樽に言った。
「武樽、あたしたちは腑抜けた今どきの琉球武士とは違うはずよ。決着が付くまで戦わなきゃ」
その言葉を聞いた武樽はうれしそうに微笑んだ。『あたしたち』という主語が気に入ったのであろう。
「わかったチルー、俺の奥技のすべてをお前に打ち込んでやる。たのむから死なないでくれ」
武樽はふたたび熊の手の構えを取った。
熊の手と虎の手。お互いの呼吸を読みあう緊迫の時間を破ったのは武樽であった。
驚くべきスピードと凄まじい破壊力を秘めた熊の手が、左右からチルーを襲った。
(武樽の攻撃は無視!とにかく中に入って虎の手を打つ)
左脇に構えていたチルーの両拳が、楕円軌道を描いて武樽の顔面めがけて飛んだ。
左拳は武樽の右コメカミ、右拳は下昆(唇と顎の中間の凹んだ部分)を正確に捕らえる。人差し指の第二関節のみを当てる、一本拳(コーサー)での当てなので、急所にピンポイントで食い込ませることができるのだ。
しかし最終奥技、虎の手の真の極意は当てた後にある。チルーは両手を、あたかも自動車のハンドルを急激に右に切るような動作で回した。
ボクシングでは、グローブを着けた拳がアゴの先端を軽くかすめただけでノックアウトしてしまう現象がままある。これは瞬間的に脳が大きく揺すられるため、脳震盪を起こしてしまうからだ。しかしボクシングにおいては、この現象は偶発的に起きることがほとんどである。
虎の手の極意とは両手の一本拳を用いて、上記のような現象を意図的に起こすことなのだ。
武樽の熊の手の軌道はチルーの身体をわずかに外れ、空を切った。
この時の武樽の視界に映る世界は、大きく歪んでいたのだ。
「うわ・・地面が溶けてきた・・俺は地獄に墜ちるのか?チルー・・どこだ・・助けてくれ」
そのまま武樽は尻もちをつくように、地面に座り込んだ。その目は虚ろであり魂が抜けたようであった。
虎の手の効果は単純な脳震盪だけではない。コメカミ(霞)と下昆という、いずれも死に至らせる可能性のある急所を一本拳で貫いているのである。
「勝負あった、与那嶺チルーの勝ち」
ここでチルーの父親が試合終了を宣言した。
これまで息を呑んで静まり返っていた見物人たちが、一斉に歓声を上げる。
「チルー、医者を呼んでいる。あちらの木陰で休め」
父親に言われるまでも無く、全身がひどく痛むのでもう立っていられない。
「筑佐事(現在の警察官)も呼びにやらせている。誰か人殺しの武樽に縄をかけてくれ」
チルーは武樽の様子を見た。
さきほどから武樽は壊れたカラクリ人形のように動かずじっと座っている。魂の抜けた目を見開いたままだ。
気になったチルーは武樽に近寄り、手を鼻の前にかざして呼吸を確かめた。
(息が無い!)
チルーがそう思った次の瞬間である。
静止していた武樽の両腕が素早く伸びて、チルーの両の乳房を熊の手で掴んだ。
指先が食い込み激痛が走る。
「ううっ・・武樽・・っ」
チルーは痛みに耐えながら己の油断を恥じていた。
「チルー、降参してくれ。これは肉千切りの秘術だ。このままでは俺はお前の乳を千切り取ってしまう。俺たちの子供に乳がやれなくなってしまうじゃないか」
武樽が懇願するように言った。
「離れろ武樽。チルーとの勝負はもう終わったのだ」
慌てたチルーの父が言うと、周りの男たち数名が武樽に組み付き、チルーから引き離そうとした。
しかしビクとも動かない。
これ以上無理に引き離そうとすれば、武樽の熊の手はチルーの乳房を本当に千切り取ってしまうであろう。
そのときふと、武樽の熊の手の握力が緩んだ。理由はわからないが、とにかくチルーは熊の手から逃れた。
距離を取ってから武樽の様子を見ると、武樽に組み付いている数名に混じって、武樽の両手首を掴んでいる男が居る。
それは先ほどまで見物人に混じっていた、松村宗棍であった。
松村宗棍は八加二帰八握力法 の秘術を用いて、武樽の両手を制していたのである。
この握力法は世上よく、非常に強力な握力を発揮する秘術であると誤解されがちであるが事実は逆で、握った相手に十分な力を出させなくする術なのだ。この秘術は高度な心理戦術を用いた非常に難度の高い技である。
やがて武樽の目に完全に力が戻り、松村宗棍を睨みつけた。
「なんだお前は。ん?お前、見たことがあるぞ。いつぞやチルーと一緒に歩いていた男だな。お前、チルーに岡惚れしているのか」
そう言うと武樽は、数名の男たちに組み付かれたままゆっくりと立ち上がった。
驚異的な回復を見せた武樽に恐怖した男たちは、武樽の身体から手を離し蜘蛛の子を散らすように逃げ去った。
「武樽、勝負は終わったのだ。これ以上悪あがきするのなら、この松村宗棍が相手するぞ」
その言葉を聞いた武樽は、松村宗棍を憐れむような目で見た。
「松村宗棍とやら。チルーに惚れているのはわかるが、お前は傍観者だろう。最初からお前は蚊帳の外なのだ。これは俺とチルーの問題だ。今さらしゃしゃり出ないでくれ」
「なに?」
「武樽の言うとおりよ」
松村宗棍が振り返ると、そこに立っていた満身創痍のチルーがそう言った。
「あんたはただの見物人。これは私と武樽の問題なの。下がって」
「チルー、君はもう戦える身体じゃない。君こそ下がっていたまえ」
「聞こえなかったの?そこをどきなさい」
足を引きずり肩で息をしながら、こちらに向かって歩いてくるチルーを見た松村宗棍は心を決めた。
「チルー、ご免」
素早い水月への当身である。普段のチルーであれば、この当身は効かなかったかもしれない。しかし呼吸の乱れているチルーの吸う息に合わせての当ては、彼女をしばらく眠らせるには十分であった。
チルーがゆっくりと崩れ落ち、それを近くに居た父親が抱き止める。
それを見た武樽が吠えた。
「貴様ああっ!俺の妻に何をしやがるううっ!」
怒りに震える武樽が両手を振り上げ、熊の手の構えをとった。
松村宗棍は、両手の拳を左手下、右手上に重ね合わせ胸前に自然に伸ばして構えた。それはまるで剣を持たない剣術のような構えである。
「ここからは私は傍観者ではない。武樽、同じ女に惚れた、男と男の勝負と心得よ」
魂から振り絞るように、松村宗棍は言った。
武樽の奥技・熊の手はそのような熊の戦闘スタイルを模したもので、両手を振り回すように使うことで威力を増大させている。
もちろんただ形を真似ただけでは大した威力にはならないが、武樽はこの三年の間、最初は大鍋で炒った豆に両手の指先を突き入れる訓練をし、二年目には砂、三年目には砂利を突いて指を鍛えた。最終的に幼児の拳大ほどの鉄球で満たした鍋を突くようになったころには、その指先は畳を貫き、板塀や湯呑に穴を開けるほどになっていた。まさに人間凶器の完成である。
そのように凶器と化した両手で挟み込むような攻撃がチルーを襲った。
熊の手の危険な威力を本能的に察知したチルーは、虎の手の構えを崩さぬままで大きく跳び退った。
胸元をかすめた武樽の熊の手は、チルーの着物を切り裂いた。あらわになったチルーの白い胸元には五筋の剃刀が走ったような傷が付き、血が滲んでいる。その様子を見た武樽が言った。
「チルー、お前の美しい身体に傷をつけるのは俺も胸が痛むぞ。どうだ、もう降参して早く俺たちの祝言を上げないか」
そんな武樽の提案は聞き流して、チルーは考えていた。
(威力に脅えて跳び退ったんじゃだめだ。危険を承知で内懐に飛び込まなくては)
覚悟を決めたチルーは、武樽に言った。
「武樽、あたしたちは腑抜けた今どきの琉球武士とは違うはずよ。決着が付くまで戦わなきゃ」
その言葉を聞いた武樽はうれしそうに微笑んだ。『あたしたち』という主語が気に入ったのであろう。
「わかったチルー、俺の奥技のすべてをお前に打ち込んでやる。たのむから死なないでくれ」
武樽はふたたび熊の手の構えを取った。
熊の手と虎の手。お互いの呼吸を読みあう緊迫の時間を破ったのは武樽であった。
驚くべきスピードと凄まじい破壊力を秘めた熊の手が、左右からチルーを襲った。
(武樽の攻撃は無視!とにかく中に入って虎の手を打つ)
左脇に構えていたチルーの両拳が、楕円軌道を描いて武樽の顔面めがけて飛んだ。
左拳は武樽の右コメカミ、右拳は下昆(唇と顎の中間の凹んだ部分)を正確に捕らえる。人差し指の第二関節のみを当てる、一本拳(コーサー)での当てなので、急所にピンポイントで食い込ませることができるのだ。
しかし最終奥技、虎の手の真の極意は当てた後にある。チルーは両手を、あたかも自動車のハンドルを急激に右に切るような動作で回した。
ボクシングでは、グローブを着けた拳がアゴの先端を軽くかすめただけでノックアウトしてしまう現象がままある。これは瞬間的に脳が大きく揺すられるため、脳震盪を起こしてしまうからだ。しかしボクシングにおいては、この現象は偶発的に起きることがほとんどである。
虎の手の極意とは両手の一本拳を用いて、上記のような現象を意図的に起こすことなのだ。
武樽の熊の手の軌道はチルーの身体をわずかに外れ、空を切った。
この時の武樽の視界に映る世界は、大きく歪んでいたのだ。
「うわ・・地面が溶けてきた・・俺は地獄に墜ちるのか?チルー・・どこだ・・助けてくれ」
そのまま武樽は尻もちをつくように、地面に座り込んだ。その目は虚ろであり魂が抜けたようであった。
虎の手の効果は単純な脳震盪だけではない。コメカミ(霞)と下昆という、いずれも死に至らせる可能性のある急所を一本拳で貫いているのである。
「勝負あった、与那嶺チルーの勝ち」
ここでチルーの父親が試合終了を宣言した。
これまで息を呑んで静まり返っていた見物人たちが、一斉に歓声を上げる。
「チルー、医者を呼んでいる。あちらの木陰で休め」
父親に言われるまでも無く、全身がひどく痛むのでもう立っていられない。
「筑佐事(現在の警察官)も呼びにやらせている。誰か人殺しの武樽に縄をかけてくれ」
チルーは武樽の様子を見た。
さきほどから武樽は壊れたカラクリ人形のように動かずじっと座っている。魂の抜けた目を見開いたままだ。
気になったチルーは武樽に近寄り、手を鼻の前にかざして呼吸を確かめた。
(息が無い!)
チルーがそう思った次の瞬間である。
静止していた武樽の両腕が素早く伸びて、チルーの両の乳房を熊の手で掴んだ。
指先が食い込み激痛が走る。
「ううっ・・武樽・・っ」
チルーは痛みに耐えながら己の油断を恥じていた。
「チルー、降参してくれ。これは肉千切りの秘術だ。このままでは俺はお前の乳を千切り取ってしまう。俺たちの子供に乳がやれなくなってしまうじゃないか」
武樽が懇願するように言った。
「離れろ武樽。チルーとの勝負はもう終わったのだ」
慌てたチルーの父が言うと、周りの男たち数名が武樽に組み付き、チルーから引き離そうとした。
しかしビクとも動かない。
これ以上無理に引き離そうとすれば、武樽の熊の手はチルーの乳房を本当に千切り取ってしまうであろう。
そのときふと、武樽の熊の手の握力が緩んだ。理由はわからないが、とにかくチルーは熊の手から逃れた。
距離を取ってから武樽の様子を見ると、武樽に組み付いている数名に混じって、武樽の両手首を掴んでいる男が居る。
それは先ほどまで見物人に混じっていた、松村宗棍であった。
松村宗棍は
この握力法は世上よく、非常に強力な握力を発揮する秘術であると誤解されがちであるが事実は逆で、握った相手に十分な力を出させなくする術なのだ。この秘術は高度な心理戦術を用いた非常に難度の高い技である。
やがて武樽の目に完全に力が戻り、松村宗棍を睨みつけた。
「なんだお前は。ん?お前、見たことがあるぞ。いつぞやチルーと一緒に歩いていた男だな。お前、チルーに岡惚れしているのか」
そう言うと武樽は、数名の男たちに組み付かれたままゆっくりと立ち上がった。
驚異的な回復を見せた武樽に恐怖した男たちは、武樽の身体から手を離し蜘蛛の子を散らすように逃げ去った。
「武樽、勝負は終わったのだ。これ以上悪あがきするのなら、この松村宗棍が相手するぞ」
その言葉を聞いた武樽は、松村宗棍を憐れむような目で見た。
「松村宗棍とやら。チルーに惚れているのはわかるが、お前は傍観者だろう。最初からお前は蚊帳の外なのだ。これは俺とチルーの問題だ。今さらしゃしゃり出ないでくれ」
「なに?」
「武樽の言うとおりよ」
松村宗棍が振り返ると、そこに立っていた満身創痍のチルーがそう言った。
「あんたはただの見物人。これは私と武樽の問題なの。下がって」
「チルー、君はもう戦える身体じゃない。君こそ下がっていたまえ」
「聞こえなかったの?そこをどきなさい」
足を引きずり肩で息をしながら、こちらに向かって歩いてくるチルーを見た松村宗棍は心を決めた。
「チルー、ご免」
素早い水月への当身である。普段のチルーであれば、この当身は効かなかったかもしれない。しかし呼吸の乱れているチルーの吸う息に合わせての当ては、彼女をしばらく眠らせるには十分であった。
チルーがゆっくりと崩れ落ち、それを近くに居た父親が抱き止める。
それを見た武樽が吠えた。
「貴様ああっ!俺の妻に何をしやがるううっ!」
怒りに震える武樽が両手を振り上げ、熊の手の構えをとった。
松村宗棍は、両手の拳を左手下、右手上に重ね合わせ胸前に自然に伸ばして構えた。それはまるで剣を持たない剣術のような構えである。
「ここからは私は傍観者ではない。武樽、同じ女に惚れた、男と男の勝負と心得よ」
魂から振り絞るように、松村宗棍は言った。