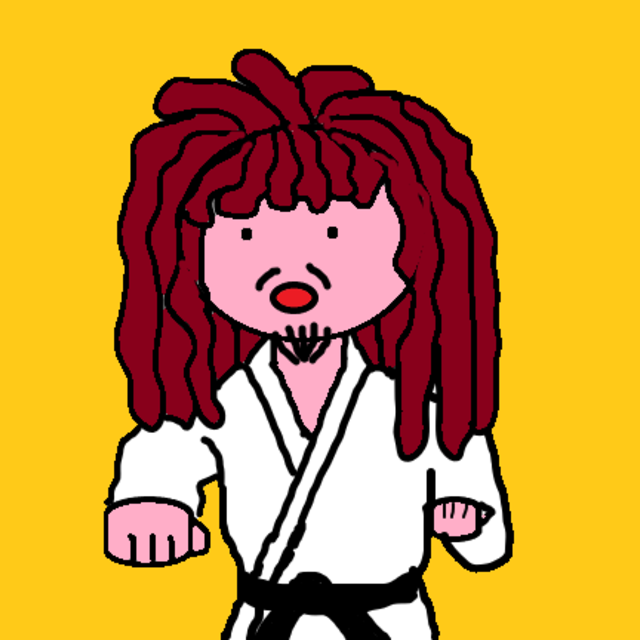第33話 百姓手 対 武士手
文字数 1,717文字
お互いに手首を触れ合った状態から、掛け試しの再スタートである。
ふたりの間に流れる空気は先ほどまでとは異なり、ぴりぴりした緊張感を漂わせていた。
どれ程かの時間が経過した後、ふたりの足元から突然土煙が舞い上がった。と、同時にふたりの身体は反発するように後方に吹っ飛んだ。しかしどちらも倒れずに踏ん張って耐えている。
お互いの前方への発力がぶつかり合っての現象である。しかし飛ばされた距離はチルーの方がやや大きい。
これは体重の差によるもので、こればかりはいかに剛腕のチルーといえど補い切れないのだ。
松村宗棍は右足前で左拳を自然に前方に突き出し、その上に右拳を重ねるように構えた。武樽戦で見せた剣を持たない剣術のような構えである。
このように両手をできるだけ近い位置に構えることを、後に松村宗棍よりカラテを学んだ本部朝基は『夫婦手(メオトーデ)の構え』と称し『この構えが組手に応用さるるを見れば、その効果の偉大なることを悟るであろう』と書き残している。ちなみに本部朝基は五十歳を過ぎてロシア人ボクサーと対戦し、一撃でこれを打ち倒したことで、日本全国にその名を轟かせた大正期~戦前の実戦カラテ家であった。
夫婦手の構えでじっと動かなくなった松村宗棍から発せられる圧力を、チルーは皮膚で感じ取っていた。この構えから繰り出される単純な正拳(テージグン)の一撃を食らえば、そこでチルーの命は尽きるであろう。
(武士手に付き合ってはいけない。私は百姓の娘。マチューさん、私は今こそ百姓手で松村宗棍を倒します)
チルーの脳裏に糸満の浜でウェークを振るうマチューの姿が浮かんだ。
チルーはまるで舞を舞うように、ゆらゆらと手足を動かしながら、摺り足で松村宗棍に近付く。奇妙な動きであるが、これが何らかの撹乱戦法であれば、宗棍には通用しない。無駄な動きはむしろ命取りとすら言えるのだ。
突然、チルーの身体がとんぼ返りのように宙で回った。宗棍の目の前に大きな鶴の絵模様が広がる。チルーの攻撃は今で言うところの胴廻し回転蹴りであろうか。
宗棍は何のためらいも無く、チルーの祭装束の背中にある鶴の絵模様の真ん中に、右拳による一撃必殺の突きを放った。決まればチルーの背骨が砕けるかもしれない無慈悲な一撃だ。
・・・?
しかし松村宗棍の拳には何の手応えも無かった。前方回転していたのはチルーの青い衣装のみだったのだ。
策にはまったことを悟った宗棍は、チルーの身体は下に潜り込んでいると判断した。しかしそこにもチルーの姿は無かった。
「こっちだよ、松村宗棍」
チルーは祭装束のさらに上空に居た。手早くその衣装を宗棍の頭に被せて視界を奪う。さらに宗棍が突き出していた右手首を両手で掴み着地の勢いを借りて、逆に極めた宗棍の右腕を肩に担いだ。ウェークを担いで振り下ろす要領である。
生木をへし折るような音がウガンジュの広場に響いた。
「ぐあああっ!」
その場に居た目撃者すべてが凍り付いた。
あの松村宗棍が苦痛に声を上げて、チルーの足元に倒れたのだ。その腕はあり得ない方向に曲がっている。
(相手を倒すまで決して動きを止めない。これが百姓手の極意)
マチューの教えは見事、松村宗棍の必殺の手に打ち勝ったのである。
「ううう・・」
うめき声を上げながら、松村宗棍は頭に被せられたチルーの青い衣装を左手で剥ぎ取った。
チルーはそんな宗棍を見下ろしながら言った。
「うふふ、百姓手はどうだった?策士のあんたがまんまと策にはまたったね。ちょっと愉快」
松村宗棍は蒼白な顔に脂汗を浮かべてチルーを睨み付けた。
「私はこの勝負はもっと純粋なものだと思っていた。小賢しい策など不要と考えていた。しかしそれは私の甘さだったようだ」
「そうね松村宗棍、あんたは甘い。それでどうするの?降参?」
松村宗棍はチルーの衣装を地面に投げ捨てると、よろよろと立ち上がった。
右腕はだらりと垂れ下がっている。
「降参?まさか。これは本気の勝負なんだろう、チルー」
チルーはまるで菩薩のように慈愛に満ちた微笑みで応えた。
「そうこなくっちゃ松村宗棍。お祭りはまだこれからだよね」
松村宗棍は無言で左手の拳を中段に構えた。
ふたりの間に流れる空気は先ほどまでとは異なり、ぴりぴりした緊張感を漂わせていた。
どれ程かの時間が経過した後、ふたりの足元から突然土煙が舞い上がった。と、同時にふたりの身体は反発するように後方に吹っ飛んだ。しかしどちらも倒れずに踏ん張って耐えている。
お互いの前方への発力がぶつかり合っての現象である。しかし飛ばされた距離はチルーの方がやや大きい。
これは体重の差によるもので、こればかりはいかに剛腕のチルーといえど補い切れないのだ。
松村宗棍は右足前で左拳を自然に前方に突き出し、その上に右拳を重ねるように構えた。武樽戦で見せた剣を持たない剣術のような構えである。
このように両手をできるだけ近い位置に構えることを、後に松村宗棍よりカラテを学んだ本部朝基は『夫婦手(メオトーデ)の構え』と称し『この構えが組手に応用さるるを見れば、その効果の偉大なることを悟るであろう』と書き残している。ちなみに本部朝基は五十歳を過ぎてロシア人ボクサーと対戦し、一撃でこれを打ち倒したことで、日本全国にその名を轟かせた大正期~戦前の実戦カラテ家であった。
夫婦手の構えでじっと動かなくなった松村宗棍から発せられる圧力を、チルーは皮膚で感じ取っていた。この構えから繰り出される単純な正拳(テージグン)の一撃を食らえば、そこでチルーの命は尽きるであろう。
(武士手に付き合ってはいけない。私は百姓の娘。マチューさん、私は今こそ百姓手で松村宗棍を倒します)
チルーの脳裏に糸満の浜でウェークを振るうマチューの姿が浮かんだ。
チルーはまるで舞を舞うように、ゆらゆらと手足を動かしながら、摺り足で松村宗棍に近付く。奇妙な動きであるが、これが何らかの撹乱戦法であれば、宗棍には通用しない。無駄な動きはむしろ命取りとすら言えるのだ。
突然、チルーの身体がとんぼ返りのように宙で回った。宗棍の目の前に大きな鶴の絵模様が広がる。チルーの攻撃は今で言うところの胴廻し回転蹴りであろうか。
宗棍は何のためらいも無く、チルーの祭装束の背中にある鶴の絵模様の真ん中に、右拳による一撃必殺の突きを放った。決まればチルーの背骨が砕けるかもしれない無慈悲な一撃だ。
・・・?
しかし松村宗棍の拳には何の手応えも無かった。前方回転していたのはチルーの青い衣装のみだったのだ。
策にはまったことを悟った宗棍は、チルーの身体は下に潜り込んでいると判断した。しかしそこにもチルーの姿は無かった。
「こっちだよ、松村宗棍」
チルーは祭装束のさらに上空に居た。手早くその衣装を宗棍の頭に被せて視界を奪う。さらに宗棍が突き出していた右手首を両手で掴み着地の勢いを借りて、逆に極めた宗棍の右腕を肩に担いだ。ウェークを担いで振り下ろす要領である。
生木をへし折るような音がウガンジュの広場に響いた。
「ぐあああっ!」
その場に居た目撃者すべてが凍り付いた。
あの松村宗棍が苦痛に声を上げて、チルーの足元に倒れたのだ。その腕はあり得ない方向に曲がっている。
(相手を倒すまで決して動きを止めない。これが百姓手の極意)
マチューの教えは見事、松村宗棍の必殺の手に打ち勝ったのである。
「ううう・・」
うめき声を上げながら、松村宗棍は頭に被せられたチルーの青い衣装を左手で剥ぎ取った。
チルーはそんな宗棍を見下ろしながら言った。
「うふふ、百姓手はどうだった?策士のあんたがまんまと策にはまたったね。ちょっと愉快」
松村宗棍は蒼白な顔に脂汗を浮かべてチルーを睨み付けた。
「私はこの勝負はもっと純粋なものだと思っていた。小賢しい策など不要と考えていた。しかしそれは私の甘さだったようだ」
「そうね松村宗棍、あんたは甘い。それでどうするの?降参?」
松村宗棍はチルーの衣装を地面に投げ捨てると、よろよろと立ち上がった。
右腕はだらりと垂れ下がっている。
「降参?まさか。これは本気の勝負なんだろう、チルー」
チルーはまるで菩薩のように慈愛に満ちた微笑みで応えた。
「そうこなくっちゃ松村宗棍。お祭りはまだこれからだよね」
松村宗棍は無言で左手の拳を中段に構えた。