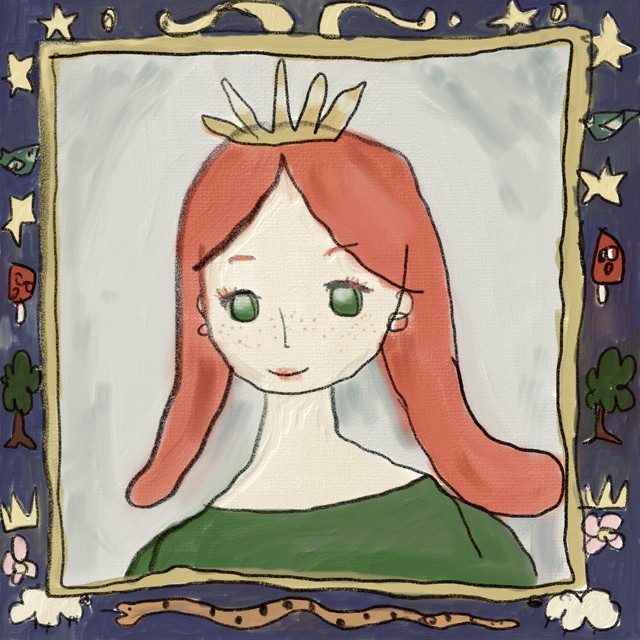手合わせという名の余興
文字数 4,960文字
「ところで、アレックス君は帯剣はしていないようだが、武器は銃かなにかかな?」
王の指摘の通り、アレックスは一目でわかるような武器は携えていない。というか、一目でわからないような武器も携えていない。わかりやすく言うならば、丸腰だ。
「自分は基本的には特定の武器は持ちません。特に今回の任務は護衛であり、魔物と対峙したとしても目的は退治ではないと認識しています。」
アレックスは身軽でいるのを好んだ。戦闘に於いてもそれは同じだ。武器の所有はものによっては重量や質量が気になるし、時には整備が必要だ。アレックスにはどれも煩わしく感じた。
「ほほう、忌避が叶えば殺生の必要はないと?」
アレックスに限ったことではなく、最近の魔物への対処法は討伐だけが主流ではなくなりつつあった。魔物、といえば退治するもの、殲滅するものという価値観が長い間台頭していたが、最近では研究も進み、魔物といっても全てが人間を襲うものではないこと、人間どころか動物も家畜も農作物も襲わない種もいることなどがわかってきている。
未知な部分が多いため、まだまだ大多数の人間が魔物と聞けば震え上がるし忌み嫌ってはいるが、一方で新しい価値観も芽生え始めていた。アレックスもなるべくなら殺生は避けたいと考えていた。
それがアレックスの倫理的な美学というわけでもない。特に大型の魔物を退治したとなれば、場合によっては死体の処理も考えねばならなくなる。時にはそれこそが人間の生活を脅かす可能性さえ出てくるのだ。魔物の生態は未知である。人里から遠い場所で、勝手に寿命で尽きてくれたほうが手間も省けるというものだ。
「…とはいっても、自分は術者でもあるので、いざというときには代替になる物が用意できます。」
襲撃者を遠ざけることができればそれに越したことはないが、魔物の場合は意思疎通ができない相手でもある。相手の襲撃を止めるためには、時には武器となる物も必要であることは否めない。王がほうほう、と感心したように頷く。
「しかし、警戒すべきは魔物だけではあるまい。野盗などの対人間に対しては、武器の携行は威嚇にもなるのではないか?」
最近は魔物の数が以前と比べて増えているという報告があるが、同様に野盗などのならず者も世界的に増えている。こちらは、どの国でも政治や経済の綻びが出始めていることが原因とされた。
「一理あります。ただ、自分は丸腰で相手を油断させておくほうが性に合っているかと。」
他人を襲うタイプのならず者という属性は国の東西を問わず大概が頭がいかれているので、こちらが威嚇しているつもりでも意図が伝わらないことが大半だ、というのがアレックスの見立てである。アレックスの回答に王は大笑いして膝を打つ。
「いいね、アレックス君。面白いね君。ちょっと手合わせしてみてくれない??おい、タルソムどうだ。」
王が上手の入り口を護る兵士に声をかけた。先ほどからずっとアレックスの様子を伺い続けている男だ。一歩前に出て「是非」と応える。この瞬間を待っていました、という闘志を漲らせているのがわかった。
「弊国の一兵卒ではあるが、なかなか強い男だぞ。こいつが君に敵わなかったら、我が国で君に勝てる者はいないということだ。」
どうやら隊長のようだった。タルソムと呼ばれた兵士は、兜の奥から鋭い視線をアレックスに向けた。こんな学生上がりの小僧に姫が護れるものか、という声が聞こえてきそうだった。王と左隣に座る王子が目を輝かせて、これから始まるであろう一戦に期待を寄せているのが分かった。ちょっとした余興のつもりなのだろう。后は不安そうな、不満そうな表情をしている。ソラは結果が見えているのか、興ざめした表情で下がって元いた椅子に腰かけた。早く祭りの準備に取り掛かりたいのだろう。ニナ姫は、状況が分かっていないのかきょろきょろと皆の様子を見比べている。横にニルンが忠実に侍っている。彼女は状況が分かっているかもしれない。少なくとも、ニナ姫よりは。
「模造刀を使います。」
端から脇差しはフェイクのようだった。ソラの正装の中身が普段着なのと同じ理由だろう。確かに魔物の気配もないこの辺境の村で、真剣の常携は無用の長物といえる。
「自分、”騎士道”みたいな戦い方、出来ないかもしれないす。」
相手にとっては卑怯に映るかもしれないが、勝負するにあたっては勝つことしか目的にない、というのがアレックスのスタイルだ。できうる限り最短のルートで、可能なら一撃で。とはいえ、この状況で戦闘慣れしていない観客たちにわかりやすい勝負をするのであれば、ある程度の応戦が必要だろうと思われた。
お互いに一礼すると、タルソムが模造刀の切っ先をアレックスに向けて集中した。広間内に緊張した空気が漂う。注目されるのは苦手だ。
「Yahaaa!」
訓練通りと思われる掛け声とともに、タルソムが剣を振ってくる。軌道から身をかわすとブン、という空気を派手に切り裂く音がする。ブン、ブン、ブン。そんな大振りがそんなに簡単に当たるわけはない。ブン、ブン、ブン。相手は攻撃に多彩さを加えるつもりがないらしい。
「ふん、見事な身のこなしだな。だが、躱してばかりでどうする?もう後がないぞ。」
この隊長は世の多くの隊長がそうであるように、相手を追い詰めることに快感を覚えるタイプかもしれない。初めてその表情に笑みが浮かんだ。後ろに下がって攻撃を避けていたアレックスの背後に広間の側面である石壁が迫っていた。
「Dahaaa!」
止めとも言わんばかりの声を上げて、タルソムは模造刀を水平に振った。横に避けさせないためだ。後ろと横がダメなら、上がある。
「跳んだ!」
身を乗り出して勝負の行方を見守っていた王子が声を上げた。この少年が姉のニナに似ているのは、その表情に一滴も嘘がないところだ。さっきからタルソムの一振り一振りにまるで自分が対戦しているかのような表情を見せている。姉のほうは試合を見慣れていないのか、硬い表情のまま固まっている。表情が豊かなこと以外は姉弟はあまり似ていなかった。というより、一家の中で、いや、この村の中で、王女のニナは若干異質だった。わかりやすいところで髪色がそうだ。同じく雰囲気が異なるソラと血縁だといわれたほうが納得できる。
「くそっ、」
隊長の背後に着地すると、彼はすかさず振り返ってすぐにまた剣を振り始める。焦りが出始めて動きに精細さを欠き始めた。そろそろ終わりにしてもいいだろうか。
模造刀を奪うのも手かもしれないが、この隊の隊訓のうちの一つに”対戦相手に己の魂ともいえる剣を奪われるようなことはあってはならない”というような精神論があるかもしれない、と考えるとそれは避けたいと思った。隊長の尊厳を奪ってしまうのは本意ではない。アレックスは攻撃を避けながら、再び広間の中央へ戻る。隊長の息が上がり始めた。頃合いだろう。
アレックスは視線を天井へ向けた。少し芝居が露骨だったかもしれないが、焦りが出始めている隊長は、簡単に釣られて視線の先の巨大なシャンデリアを確認した。一瞬目を見開いて、瞬時に体を本人の利き手の逆である左手に横跳びさせる。アレックスはそこに右足を伸ばすだけだった。「ぐはっ、」という声と共に勢いのついた隊長の体躯が見事に転倒した。アレックスはそのまま、模造刀を掴んでいる右手と左肩を膝も使って押さえつけた。視界の端で、王子がついに立ち上がったのが見えた。
「続けます?」
隊長の目が見開き一瞬だけ抗いたいような表情をしたが、間もなく模造刀を手から離した。
「降参だ…。」
タルソム隊長は無念そうに目を瞑った。
「見事!」
王が座りなおして、手を叩く。アレックスは息の上がった隊長を立ち上がらせ、模造刀を拾い上げると、手渡した。その際「少しお人が良すぎましたね」と伝えた。ただの手合わせの試合で、さすがに玉座広間のシャンデリアは落とさない。弁償を求められても困る。アレックスはまだ資産を持たない学生上がりの訓練生でしかない。指摘に隊長はハッとした表情でアレックスを見た。この村の人間は皆、素朴で素直なのだろう。つまらない戦術を思いついてしまった自分を恥ずかしく感じる。二人は再び向かい合って、深く礼をした。興奮して立ち上がってしまっていた王子も座りなおした。
「アレックス君がニナに同行することに異存はないな?タルソムよ。」
王は自分の兵が負けたというのに何故か満足そうだ。隊長は「ありません!」と姿勢を正して答えた。
「お前にはこれまで通り隊を率いてもらわねばならぬからな、引き続き精進せよ。」
御意、と隊長は一礼すると、元居た警備位置に戻って行った。彼はもしかしたら、ニナの護衛役を志願していたのかもしれない、とアレックスはその背中を見送りながら考えた。
「いいものを見せてもらった、アレックス。ヴァンサーと言えど訓練生がこれほどの技量を持ち合わせているとは、正直思っていなかった。」
少年のような表情で王が目を輝かせる。隣で王子も同じ目をして何度も頷いた。
「恐れ入ります。」
アレックスは軽く頭を下げる。
「これなら旅も安心だな、なあソラ?」
広間正面口脇の控え椅子に腰かけて事の行方を見守っていたソラに満足げに王が声をかける。訓練生とはいえ、決して安いとは言えないであろう予算を割いているのだから(アレックスに正確な金額は知り得ないが)、雇い主に少しでも納得してもらえたらなら、アレックスも安心だ。すべては評価に繋がる。
「ですねーえ。」
満面の笑みはわざわざ手合わせなんかしなくてもわかるでしょ、とでも言いたげだ。ニナ王女の聖樹巡礼の旅だが、王がソラに同意を求めているところを見ると、この旅の主導はソラだとわかる。ニナは他人事のように大型犬ニルンの頭を撫でていて、王妃に窘められていた。
「困ったことや不満があったら遠慮なくソラに言いなさい。ソラが窓口になってくれるから。ニナはダメだよ、そういうの全く不向き。ホント、手を焼かせるとしたら魔物よりたぶんニナなんだと思ってるけど、どうかよろしく頼むよ。まあ、君はニナの身の安全の確保だけに集中して、後は全部ソラに任せればいい。ニナの扱いは彼が一番知っているから。な、ソラ。」
ソラはあはははは、と乾いた愛想笑いを返すだけだった。実の娘だというのにひどい言いようではあるが、仲の良さの表れなのかもしれない。家族のいないアレックスにはわからない関係性だった。
「キルファ王、そろそろいいですか??お祭の準備しなきゃ。」
ソラは一応遠慮しているフリも醸しつつ切り出した。
「おお、そうだったな。今日はこれくらいにしておこう。ソラ、アレックス、出発前に一度ゆっくり食事でもしよう。麦星祭、大いに楽しむが良い。」
王はご機嫌に立ち上がりながら声をかけた。これが顔合わせ終了の合図になり、二人は再度形式的に礼をした。妃と長男を引き連れてビロードのカーテンの奥へと消える。長男がアレックスに何か言いたげな表情をしていたが、母親に促されて退室した。
ニナは家族にお構いなしでソラとアレックスに近寄る。ニルンは場所を変えずに、ニナを見守っている。
「アレックスが一緒に来てくれる人だったら。私、護衛さんて言うからもっと熊みたいな大きな人が来るんだと思ったさ。」
ニナは愉快そうに笑う。自分も20歳と聞いていたから別の人物だと思っていた、とは言わないでおく。
「それあれでしょ、『最後の旅の物語』のイメージでしょ」
ソラに指摘されてニナは一瞬考えると、あ、そうらーと言って再度笑った。
「さてさて聖歌隊の準備に行くよ。みんなが待ってる。最後軽く合わせなきゃ。」
ソラはすっかり麦星祭に焦点が当たっている。あそっか、と言ってニナはソラと一緒に家族とは異なり正面出口へ向かった。ニルンが腰を上げてニナについていく。
「アレックス、見ててね。みんな、一生懸命練習したから。」
足早に出て行ったソラに置いていかれながらも、ニナは最後アレックスに声をかけてくれる。アレックスが承知したことを伝えると、またねーと言ってソラの後を追った。昨日、どこかから歌声が聴こえたのは聖歌隊の練習だったのかもしれない。
王の指摘の通り、アレックスは一目でわかるような武器は携えていない。というか、一目でわからないような武器も携えていない。わかりやすく言うならば、丸腰だ。
「自分は基本的には特定の武器は持ちません。特に今回の任務は護衛であり、魔物と対峙したとしても目的は退治ではないと認識しています。」
アレックスは身軽でいるのを好んだ。戦闘に於いてもそれは同じだ。武器の所有はものによっては重量や質量が気になるし、時には整備が必要だ。アレックスにはどれも煩わしく感じた。
「ほほう、忌避が叶えば殺生の必要はないと?」
アレックスに限ったことではなく、最近の魔物への対処法は討伐だけが主流ではなくなりつつあった。魔物、といえば退治するもの、殲滅するものという価値観が長い間台頭していたが、最近では研究も進み、魔物といっても全てが人間を襲うものではないこと、人間どころか動物も家畜も農作物も襲わない種もいることなどがわかってきている。
未知な部分が多いため、まだまだ大多数の人間が魔物と聞けば震え上がるし忌み嫌ってはいるが、一方で新しい価値観も芽生え始めていた。アレックスもなるべくなら殺生は避けたいと考えていた。
それがアレックスの倫理的な美学というわけでもない。特に大型の魔物を退治したとなれば、場合によっては死体の処理も考えねばならなくなる。時にはそれこそが人間の生活を脅かす可能性さえ出てくるのだ。魔物の生態は未知である。人里から遠い場所で、勝手に寿命で尽きてくれたほうが手間も省けるというものだ。
「…とはいっても、自分は術者でもあるので、いざというときには代替になる物が用意できます。」
襲撃者を遠ざけることができればそれに越したことはないが、魔物の場合は意思疎通ができない相手でもある。相手の襲撃を止めるためには、時には武器となる物も必要であることは否めない。王がほうほう、と感心したように頷く。
「しかし、警戒すべきは魔物だけではあるまい。野盗などの対人間に対しては、武器の携行は威嚇にもなるのではないか?」
最近は魔物の数が以前と比べて増えているという報告があるが、同様に野盗などのならず者も世界的に増えている。こちらは、どの国でも政治や経済の綻びが出始めていることが原因とされた。
「一理あります。ただ、自分は丸腰で相手を油断させておくほうが性に合っているかと。」
他人を襲うタイプのならず者という属性は国の東西を問わず大概が頭がいかれているので、こちらが威嚇しているつもりでも意図が伝わらないことが大半だ、というのがアレックスの見立てである。アレックスの回答に王は大笑いして膝を打つ。
「いいね、アレックス君。面白いね君。ちょっと手合わせしてみてくれない??おい、タルソムどうだ。」
王が上手の入り口を護る兵士に声をかけた。先ほどからずっとアレックスの様子を伺い続けている男だ。一歩前に出て「是非」と応える。この瞬間を待っていました、という闘志を漲らせているのがわかった。
「弊国の一兵卒ではあるが、なかなか強い男だぞ。こいつが君に敵わなかったら、我が国で君に勝てる者はいないということだ。」
どうやら隊長のようだった。タルソムと呼ばれた兵士は、兜の奥から鋭い視線をアレックスに向けた。こんな学生上がりの小僧に姫が護れるものか、という声が聞こえてきそうだった。王と左隣に座る王子が目を輝かせて、これから始まるであろう一戦に期待を寄せているのが分かった。ちょっとした余興のつもりなのだろう。后は不安そうな、不満そうな表情をしている。ソラは結果が見えているのか、興ざめした表情で下がって元いた椅子に腰かけた。早く祭りの準備に取り掛かりたいのだろう。ニナ姫は、状況が分かっていないのかきょろきょろと皆の様子を見比べている。横にニルンが忠実に侍っている。彼女は状況が分かっているかもしれない。少なくとも、ニナ姫よりは。
「模造刀を使います。」
端から脇差しはフェイクのようだった。ソラの正装の中身が普段着なのと同じ理由だろう。確かに魔物の気配もないこの辺境の村で、真剣の常携は無用の長物といえる。
「自分、”騎士道”みたいな戦い方、出来ないかもしれないす。」
相手にとっては卑怯に映るかもしれないが、勝負するにあたっては勝つことしか目的にない、というのがアレックスのスタイルだ。できうる限り最短のルートで、可能なら一撃で。とはいえ、この状況で戦闘慣れしていない観客たちにわかりやすい勝負をするのであれば、ある程度の応戦が必要だろうと思われた。
お互いに一礼すると、タルソムが模造刀の切っ先をアレックスに向けて集中した。広間内に緊張した空気が漂う。注目されるのは苦手だ。
「Yahaaa!」
訓練通りと思われる掛け声とともに、タルソムが剣を振ってくる。軌道から身をかわすとブン、という空気を派手に切り裂く音がする。ブン、ブン、ブン。そんな大振りがそんなに簡単に当たるわけはない。ブン、ブン、ブン。相手は攻撃に多彩さを加えるつもりがないらしい。
「ふん、見事な身のこなしだな。だが、躱してばかりでどうする?もう後がないぞ。」
この隊長は世の多くの隊長がそうであるように、相手を追い詰めることに快感を覚えるタイプかもしれない。初めてその表情に笑みが浮かんだ。後ろに下がって攻撃を避けていたアレックスの背後に広間の側面である石壁が迫っていた。
「Dahaaa!」
止めとも言わんばかりの声を上げて、タルソムは模造刀を水平に振った。横に避けさせないためだ。後ろと横がダメなら、上がある。
「跳んだ!」
身を乗り出して勝負の行方を見守っていた王子が声を上げた。この少年が姉のニナに似ているのは、その表情に一滴も嘘がないところだ。さっきからタルソムの一振り一振りにまるで自分が対戦しているかのような表情を見せている。姉のほうは試合を見慣れていないのか、硬い表情のまま固まっている。表情が豊かなこと以外は姉弟はあまり似ていなかった。というより、一家の中で、いや、この村の中で、王女のニナは若干異質だった。わかりやすいところで髪色がそうだ。同じく雰囲気が異なるソラと血縁だといわれたほうが納得できる。
「くそっ、」
隊長の背後に着地すると、彼はすかさず振り返ってすぐにまた剣を振り始める。焦りが出始めて動きに精細さを欠き始めた。そろそろ終わりにしてもいいだろうか。
模造刀を奪うのも手かもしれないが、この隊の隊訓のうちの一つに”対戦相手に己の魂ともいえる剣を奪われるようなことはあってはならない”というような精神論があるかもしれない、と考えるとそれは避けたいと思った。隊長の尊厳を奪ってしまうのは本意ではない。アレックスは攻撃を避けながら、再び広間の中央へ戻る。隊長の息が上がり始めた。頃合いだろう。
アレックスは視線を天井へ向けた。少し芝居が露骨だったかもしれないが、焦りが出始めている隊長は、簡単に釣られて視線の先の巨大なシャンデリアを確認した。一瞬目を見開いて、瞬時に体を本人の利き手の逆である左手に横跳びさせる。アレックスはそこに右足を伸ばすだけだった。「ぐはっ、」という声と共に勢いのついた隊長の体躯が見事に転倒した。アレックスはそのまま、模造刀を掴んでいる右手と左肩を膝も使って押さえつけた。視界の端で、王子がついに立ち上がったのが見えた。
「続けます?」
隊長の目が見開き一瞬だけ抗いたいような表情をしたが、間もなく模造刀を手から離した。
「降参だ…。」
タルソム隊長は無念そうに目を瞑った。
「見事!」
王が座りなおして、手を叩く。アレックスは息の上がった隊長を立ち上がらせ、模造刀を拾い上げると、手渡した。その際「少しお人が良すぎましたね」と伝えた。ただの手合わせの試合で、さすがに玉座広間のシャンデリアは落とさない。弁償を求められても困る。アレックスはまだ資産を持たない学生上がりの訓練生でしかない。指摘に隊長はハッとした表情でアレックスを見た。この村の人間は皆、素朴で素直なのだろう。つまらない戦術を思いついてしまった自分を恥ずかしく感じる。二人は再び向かい合って、深く礼をした。興奮して立ち上がってしまっていた王子も座りなおした。
「アレックス君がニナに同行することに異存はないな?タルソムよ。」
王は自分の兵が負けたというのに何故か満足そうだ。隊長は「ありません!」と姿勢を正して答えた。
「お前にはこれまで通り隊を率いてもらわねばならぬからな、引き続き精進せよ。」
御意、と隊長は一礼すると、元居た警備位置に戻って行った。彼はもしかしたら、ニナの護衛役を志願していたのかもしれない、とアレックスはその背中を見送りながら考えた。
「いいものを見せてもらった、アレックス。ヴァンサーと言えど訓練生がこれほどの技量を持ち合わせているとは、正直思っていなかった。」
少年のような表情で王が目を輝かせる。隣で王子も同じ目をして何度も頷いた。
「恐れ入ります。」
アレックスは軽く頭を下げる。
「これなら旅も安心だな、なあソラ?」
広間正面口脇の控え椅子に腰かけて事の行方を見守っていたソラに満足げに王が声をかける。訓練生とはいえ、決して安いとは言えないであろう予算を割いているのだから(アレックスに正確な金額は知り得ないが)、雇い主に少しでも納得してもらえたらなら、アレックスも安心だ。すべては評価に繋がる。
「ですねーえ。」
満面の笑みはわざわざ手合わせなんかしなくてもわかるでしょ、とでも言いたげだ。ニナ王女の聖樹巡礼の旅だが、王がソラに同意を求めているところを見ると、この旅の主導はソラだとわかる。ニナは他人事のように大型犬ニルンの頭を撫でていて、王妃に窘められていた。
「困ったことや不満があったら遠慮なくソラに言いなさい。ソラが窓口になってくれるから。ニナはダメだよ、そういうの全く不向き。ホント、手を焼かせるとしたら魔物よりたぶんニナなんだと思ってるけど、どうかよろしく頼むよ。まあ、君はニナの身の安全の確保だけに集中して、後は全部ソラに任せればいい。ニナの扱いは彼が一番知っているから。な、ソラ。」
ソラはあはははは、と乾いた愛想笑いを返すだけだった。実の娘だというのにひどい言いようではあるが、仲の良さの表れなのかもしれない。家族のいないアレックスにはわからない関係性だった。
「キルファ王、そろそろいいですか??お祭の準備しなきゃ。」
ソラは一応遠慮しているフリも醸しつつ切り出した。
「おお、そうだったな。今日はこれくらいにしておこう。ソラ、アレックス、出発前に一度ゆっくり食事でもしよう。麦星祭、大いに楽しむが良い。」
王はご機嫌に立ち上がりながら声をかけた。これが顔合わせ終了の合図になり、二人は再度形式的に礼をした。妃と長男を引き連れてビロードのカーテンの奥へと消える。長男がアレックスに何か言いたげな表情をしていたが、母親に促されて退室した。
ニナは家族にお構いなしでソラとアレックスに近寄る。ニルンは場所を変えずに、ニナを見守っている。
「アレックスが一緒に来てくれる人だったら。私、護衛さんて言うからもっと熊みたいな大きな人が来るんだと思ったさ。」
ニナは愉快そうに笑う。自分も20歳と聞いていたから別の人物だと思っていた、とは言わないでおく。
「それあれでしょ、『最後の旅の物語』のイメージでしょ」
ソラに指摘されてニナは一瞬考えると、あ、そうらーと言って再度笑った。
「さてさて聖歌隊の準備に行くよ。みんなが待ってる。最後軽く合わせなきゃ。」
ソラはすっかり麦星祭に焦点が当たっている。あそっか、と言ってニナはソラと一緒に家族とは異なり正面出口へ向かった。ニルンが腰を上げてニナについていく。
「アレックス、見ててね。みんな、一生懸命練習したから。」
足早に出て行ったソラに置いていかれながらも、ニナは最後アレックスに声をかけてくれる。アレックスが承知したことを伝えると、またねーと言ってソラの後を追った。昨日、どこかから歌声が聴こえたのは聖歌隊の練習だったのかもしれない。