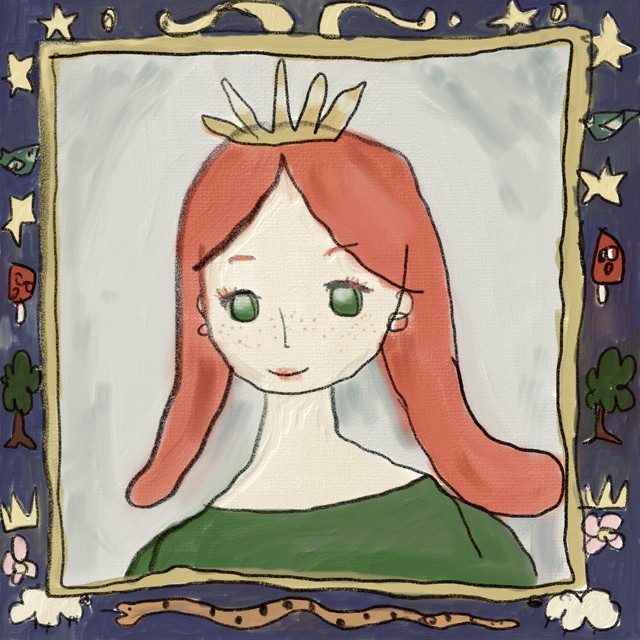麦星祭 第3部
文字数 7,076文字
しばらくの間を置いて、ステージの照明が消えた。また何かが始まる予感で、散らばっていた村人や観光客たちもまたステージ前に集った。
思わせぶりな時間を取らずに、ギターを肩から下げたソラを筆頭に、先程のジョイントロボ、昼間に王の間で接見した王子と似たような年代の若い男、そして最後にニナが現れた。先程親父バンドに混じって場を盛り上げたばかりのソラと、冒頭で衝撃を与えたニナが揃って現れたことに、主に外部の観客たちから期待で歓声を上げる。
ニナは聖歌隊の時の衣装で花冠も被ったままだが、足元はショートブーツを履いていた。歓声に嬉しそうに手を振って応えている。
王子であるニナの弟がドラムにつき、もう一人の腕っぷしの強そうな男がベースを担ぐ。この二人は緊張からか表情は固かった。
「どうもルクノルディアバンドでーす。」
ソラがギターにケーブルを繋ぎながらマイクで名乗る。国名そのままの何の捻りもないバンド名に笑いのような歓声が上がる。
ニナはスタンドマイクの前に立ってもなお緊張感なく、一人一人に手を振っていた。
アレックスの座っている近くテーブルに、先程の親父バンドのメンバーが各々大きなビールジョッキと軽食を持ち寄って、一仕事終えた乾杯をしていた。あとは若手のステージを楽しむだけだ、とでもいうような雰囲気である。
1曲目は意外にも重厚なナンバーだった。ベース音が暗闇から鳴り渡り、夜空の銀河を際立たせた。ニナやソラのこれまでののほほんとした雰囲気が吹き飛ぶ。最初の聖歌隊が纏っていた神聖さが近いが、それにギターとベースに四つ打ちのドラムが観客をかろうじて現代にとどまらせる。
歌はFiol語だった。孤独と祈りの歌だった。ニナの細い体からは発せられているとは思えない力強い声。だが同時に儚げな少女のようでいて、無垢な少年のようでもあった。観客は一気にその世界に惹き込まれていく。親父バンドの最後の陽気さとの落差がすごい。誰から見てもこのバンドのリーダーと思われるソラの思惑通りかもしれない。
まだ固さの残るドラムとベースの上で、ソラだけは自由にしなやかにそのギターを鳴らす。音に没頭しているようで他のメンバーを気遣って見守っているのがわかる。
ニナは他のメンバーが鳴らす音に疑うことなく身を預けて歌い上げる。憑依型とは彼女のようなタイプのことを言うのだろうと思った。先程までステージ上からニコニコと手を振っていた人物と、また昼間に邂逅した人物と、やはり同一人物だとは思えなかった。最初の聖歌隊の錫杖を持っていた彼女ともどこか違うようだ。
アレックスは再び鳥肌が立っているのを自覚した。隣の親父たちもビールのジョッキをテーブルに置いたままステージに見入っている。観客の中には感極まっている女もいた。
その場にいる人間全員の思いを受け止めた歌声は、祈りとなって夜空へ消えていく。
曲が終わっても歓声も拍手の一つも起きなかった。誰もが魂を抜かれたようになっている。そんなことは想定済みだとでも言いたげにソラが次の曲を奏で始めた。
前曲とは打って変わって、軽快でダンサブルなリズムだ。ニナの表情に満面の笑みが戻り、観客に向かって、ところで何をそんなに深刻になっているの?とバンドが問うているようだった。
挑発されて嬉しそうに観客達の体も自然と動き出す。親父達もビールを飲み出す。この瞬間は完全にソラの手の内のようだ。ニナもこれまでと打って変わってポップに表情豊かに体でリズムを取りながら歌い上げる。表情豊かに、足元は軽やかにステップを踏んでいる。観客はとっくに座席の存在を忘れて思い思いに踊ったり、拳を上げたりしている。
最初のサビ終わりでニナが被っていた花冠を客席に投げた。餌を取り合う雛のように、近くの観客がそれに殺到する。それを合図にニナはスタンドからマイクを持ち出し、なおも自由に踊り出した。見事な黄金色の長い髪が、照明を受けて輝きながら波打っている。
ニナに引っ張られて、ドラムとベースの奏でる音がだんだんと柔らかくなっていくのが分かった。彼らの表情にも汗と共に笑顔が生まれ始めた。ソラもそれを感じているのか、自分の演奏に集中し始めたように見えた。これは前持って打ち合わせていたのだろう、ニナとソラが途中で同じステップを踏むと、会場はますます盛り上がった。二人は双子のように同じ髪色で、同じ肌色で、息もぴったりだった。幼馴染とのことで、多くの言葉はいらないように見える。そんな存在がいるというのは、どういう感覚だろう。アレックスは少し羨ましく思ったかもしれなかった。
ニナがセンターの位置とは全く違う場所でひとしきり踊って、2曲目が終わった。今度は、堰を切ったように歓声が上がる。しかしバンドは止まらない。
立て続けにデジタル音のテンポの速いイントロが鳴り始める。瞬時に客席はさら湧き立った。
それはアレックスでさえ耳にしたことがあるイントロだった。数年前に大ヒットした有名な女性歌手の曲だ。毎日街のどこかしらでこのメロディー耳にしていて、音楽に疎いアレックスでもわかった。
観客の興奮に、ソラがしてやったりの笑顔でジャンプしながら観客に手拍子を誘う。観客は漏れなく自分の頭上で手拍子を始めた。彼らはいつしかステージ前に殺到して密集していた。ここは世界の外れにある山の上だが、もはやライブハウス状態だ。
そんな観客に臆することなくニナは歌う。オリジナルの歌手はかなり独特の声をしているが、ニナはそれに寄せていた。今までの声調とは明らかに違う。こんなに自在に声を操れるものなのだろうか。
言語はオリジナルに揃えてEstalia語だ。彼女にとってはFiol語以上に馴染みのない言語らしいことはところどころの発音でわかったが、そんなことは本人も観客もお構いなしだ。サビのキーポイントでニナがマイクを観客へ向けると、観客は応えて皆で大合唱となる。ニナはその反応に嬉しそうに歌い続け、舞った。木綿のドレスが黄金色の髪と一緒にライトを受けて舞い上がり、頬が薔薇色に染まっていた。
誰もが自分のカメラの存在を忘れて目の前のステージに熱中していた。ソラはやはり合間合間で観客を煽り、自分は軽やかにステージ上で跳ねる。
歌詞は現代の都市的なもので、おおよそこの村とは無縁の内容だったが、この瞬間は誰もが空中トラムやチューブの高速道路が血管のように這っている大都会の上を飛んでいるようだった。
曲が終わると、ニナは少し息が上がっていた。それ以上に、観客は自分達の体から湯気を上げて興奮していた。ステージ上のメンバーはそれぞれに目を合わせて、手応えを確認しているようだった。
「改めましたで、ルクノルディアバンドです。楽しんでますかー?」
喋ると嘘みたいに昼間ののほほんとしたニナに戻る。アレックスも観客もまだこの落差に追いつかない。湧き上がる観客の歓声に、ニナはへへへと笑って、用意されたグラスの飲み物で喉を潤す。アレックスが2杯目にありつけなかったスパークリングベリーだ。
「みなさん、遠くから来てくれてありがとうでした。今日は、この村にとっても特別な夜になりました。」
ニナはFiol語で辿々しく、それでも丁寧に言ってから、メンバー紹介をします、と言って照れたように笑った。
「まずはドラムのこの男は私の弟のカイルです。15歳です。」
ニナは脇に立ち位置を変えて、奥に設置しているドラムが見えるようにして紹介する。歓声が起きる。王子はドラムを簡単に鳴らして歓声に応える。嬉し恥ずかしの表情の15歳だ。
「で、ベースをしているのが、えーと漁師さんのサミル君です。」
真面目そうなサミル君の年齢は紹介されなかったが、その腕の太さの理由は推し量れた。サミル君は観客に向かって深々と頭を下げる。皆が温かい拍手を送る。親父バンドの一人が、いいぞサミル!と揶揄うような野次を入れる。父親か、漁師仲間か、そんな感じのこちらも腕っぷしの強そうな親父だった。
「あと、不思議な音とか、照明をつけたり消したりしてくれているロボットのJOYです。それから、前髪が可愛いのが、今日のこのステージの殆どを夜も寝ずに考えたソラですー。」
紹介しているニナ自ら、手を叩く。大きな歓声が上がる。ソラは歓声に応えて、ギターを派手にかき鳴らした。ニナが嬉しそうにソラを見る。
熱狂の中、ソラがマイクを取って「ボクらの歌姫、ニナ!」と紹介する。ニナは少し恥ずかしそうにはにかんで、歓声の中ぺこりとお辞儀をした。そんなニナの様子を見てソラが半分揶揄うように「ニーナ!ニーナ!」とニナコールを誘う。観客が乗ってニナコールを始めると、ソラはそのリズムに合わせて4曲目を演奏し始めた。
これまた世界中でスタンダードだったが一世代前のナンバーだった。異国情緒を誘うサウンドとメロディー。独特でインパクトのあるイントロが、またしても観客を沸かせた。先ほどまでコールを受けて恥ずかしそうにしていたニナはどこへやら、乾いた砂漠の市場を彷徨う旅行者になっていた。旅先での、見知らぬ言葉を喋る男とのひとときの恋を歌っていた。ここは針葉樹が立ち並び、世界のどこよりも一足先に冬を迎えようとしている高地であるのに、観客は一気に灼熱の砂漠へ連れていかれていた。
わかりやすい曲の締めに合わせてニナが良くわからないポーズを決める。観客は自らの体から湯気を発しながら、歓声を上げる。ニナが少し圧倒されて笑っていた。
「今のは、村のおばちゃんたちが好きな歌でした。i yakaite tta?」
ニナは現地語で屋台のおばちゃんたちに向かって何か問いかける。屋台の奥で、村人たちが嬉しそうに声を上げた。
国を封鎖していたとはいえ、諸外国の文化はそれなりに入っていたようだ。城に一日籠っていても飽きなさそうな立派な図書室もある。最新の、とはいかないまでも、それなりの共通のエンターテインメントには触れていたらしいことがわかる。
「では、次が最後です。」
不意の終了の知らせに、悲嘆にも似た声が上がる。歓声の中、今日はありがとうとニナが言うのと同時にソラはギターを鳴らし始めた。
最後は4ピースのロックバンドとして期待を裏切らない、四つ打ちのみずみずしい楽曲だった。これまでの曲のなかでは、この若々しいバンドに一番相応しいような、さわやかで疾走感のある曲だった。ドラムのカイルが力強い一音を鳴らすたびに汗が輝いて飛んでいた。ソラは誰よりも自由でしなやかにその風景を描いた。ニナの伸びやかな素直な歌声が風に乗って駆け抜けていく。ベースのサミル君は、そんな3人を守るようにいつくしむように行くべき道に導いている。
雲一つない晴れた日にあの一本道の農道を、この4人が駆け抜けていくさまが見えるようだった。
最後のサビも超えてアウトロが終わっても、音は止まなかったし、観客の歓声も止まない。ニナはアドリブで歌い終幕を惜しんでいるようだった。
「最後はみんなで飛ぶさー」と観客に向かって言うと、演奏の音量が一段階上がる。ニナは観客を嬉しそうに一度見渡すと、「せーの!」と掛け声をかける。ニナとソラとサミル君と会場が同時に飛んだ。着地とともに最後の一音が鳴らされ、周囲に静寂が訪れた。
と思った瞬間、今夜一番の歓声が起こった。ステージの4人はやり切った表情で歓声を全身で受け、お互いに顔を見合わせて相手を称えていた。ニナが「ありがとう、またね」と言って手を振りながら、鳴り止まない拍手に見送られて4人はステージを後にした。
4人が去っても拍手は鳴り止まず、そのままアンコールが叫ばれた。これで帰ろうとする者は一人もいなかった。特に観光客の若者たちがステージに送る声は熱気そのものだった。もみくちゃになって、汗なのか頭からアルコールを被ったのかよくわからないような状態でバンドを呼んでいる。
アレックスは変わらずテーブル席から様子を眺めていただけだが、気づけば飲み物を飲む手が止まっていた。「すげーな、」こぼれるように一人呟いてみたが、周囲の歓声で誰にも届かない。思い出したようにワインを一口飲んだ。
アンコールはいつの間にかニナコールに変わっていた。3曲目の終わりで、ソラに教えられたやつだ。特にもったいぶることもなく、4人は再度壇上に上がった。歓声の中、ニナはありがとうと言ってから準備をする3人を一人ずつ改めて紹介した。
「アンコールしてもらえてよかったら。」と、素直にソラと顔を見合わせて言うと、どっと笑いが起きた。前提で準備していたのがわかる。アレックスも思わず笑ってしまった。
「最後は、聖歌隊のみんなにも手伝ってもらいます。」
ニナがそういうと、聖歌隊が年長組を先頭に10人皆がステージ上に上がった。最年少の少女は少し上の少女に手を引かれて現れた。冒頭の衝撃を思い出したのか、観客は皆期待から万雷の拍手を送った。少女たちは皆、嬉しいような恥ずかしいような素直な表情をしている。ニナは全員と丁寧に目を合わせてから、スタンドマイクに向かった。
「本当に今日はありがとうございました。みなさんが、今後もずっと幸せであることを願って、ルクノルディアバンドと聖歌隊が心を込めてこの歌を贈ります。」
ニナが再び皆と目を合わせたあと、正面を向いてスタンドマイクに少し身を預けるように構えた。観客は声援を止めて、その時を待った。ドラムのカイルが3拍の拍子をとったのを合図にニナが一音発声したと同時に、聖歌隊のコーラスと重低音と共に最後の曲が始まった。
聖歌隊がいても、サウンドは重厚なロックバンドのものだった。しばらくはギターとニナの歌唱だけのフレーズが続いた。湖面を背後に星空の下、世界はニナとソラだけだった。
ニナはスタンドマイクで体を支え、前後に体を揺らしてリズムをとりながら歌っている。目の前の観客たちの姿が見えなくなったかのように、ソラの鳴らすギターに全身を預けているのがわかる。ソラもそれが分かっているのだろう、もうニナしか見ていなかった。ニナは少し思い詰めているかのようにさえ見えた。曲調がそう見させているのだろうか。
途中からドラムの音が強くなり、ベース音も前に出てくる。と同時に、聖歌隊も控えめにハーモニーを奏でた。そして一瞬、ニナの歌声以外の音が消え去った。ニナの声が星空に響き渡った。その残響が消えきる前に、ドラムが一音鳴らす。
それを合図に、ベースとギターと聖歌隊が怒涛の波のように観客を襲った。あふれる祈りの波に背中を押されて、ニナは前後に体を揺らしたまま、今日の景色を忘れないと歌った。光を受けてその瞳に輝くものが見えるのは、汗だろうか。
あとはすべてを聖歌隊の祈りの歌とベースの音がかき消していった。ニナは聖歌隊の圧倒的な音を浴びてかき消されるのを望んでいるようにさえ見えた。
圧倒的な祈りのうねりが止み、静かなギターとベースとの音が僅かに鳴ったあと、すべては夜空に消えていった。
一瞬の間をおいて、観客が暴発したように沸いた。万雷の拍手の中でソラがギターを掲げると、拍手は一層高まった。
聖歌隊たちは安心したように顔を合わせている。直前まで圧倒的なハーモニーを奏でていた者たちとは思えない、素朴な少女たちがそこにいた。
ソラが自分のギターを背中に回して、ニナに近づく。ニナはマイクスタンドを掴んだまま、動けなくなっていた。
ソラはニナを隠すようにマイクの前に立ち、ありがとうございましたーと満面の笑みで観客に向かって手を振った。再度拍手が起こる。
ニナは泣いているのだろうか。もう声を発せなくなっているようだった。ソラが笑いながら、ニナの頭をくしゃくしゃしている。
聖歌隊の少女たちがニナに近寄り、ソラがニナを託す。少女たちの何人かもつられたのか、顔を真っ赤にして泣きそうになっているのが分かった。皆で抱き合っているのをソラが笑いながら舞台袖に行くように催促している。
カイルとサミル君とソラが、観客に向かって手を振る。サミル君も感極まっているようだった。目が赤くなっている。よくよく見ると熱狂の中、号泣している観客も一人や二人ではなかった。
メンバーを見送って、ソラが一番最後にステージから降りた。マイクを通さずに声を張り上げて、最後にもう一度ありがとうございました!と叫んで大きく手を振ると、万雷の拍手が起きた。興奮冷めやらずに再度のアンコールを試みる者もいたが、無情にもステージの明かりは落とされた。悲嘆の声と共に会場がざわつく。圧倒的な余韻だけがその場に残された。
アレックスは大きく息を吐いてから席を立った。呼吸が止まっていたかもしれない。
会場はまだまだ熱気で溢れていたが、アレックスはそこを後にした。風に打たれ、たった今目撃したものを自分の中で消化させながら、ゆっくりと城に戻る。
会場のざわめきが遠くなっていく。城に人の気配はなく、アレックスは与えられた部屋の近くのバルコニーに出た。少し興奮した体に、冷たい風が心地よかった。
眼下の湖は闇に身を隠し、ほとりの会場の灯りと人々のざわめきだけが漏れ届いた。彼らの夜はまだまだ続きそうだ。
おそらく、アレックスはこれまでの人生で一番印象深い夜を過ごした。一昨日、雪山で一人で迎えた夜に匹敵する夜を、2日後にはもう迎えることになるとは思ってなかった。
今夜も夜空には満天の星が輝いている。
思わせぶりな時間を取らずに、ギターを肩から下げたソラを筆頭に、先程のジョイントロボ、昼間に王の間で接見した王子と似たような年代の若い男、そして最後にニナが現れた。先程親父バンドに混じって場を盛り上げたばかりのソラと、冒頭で衝撃を与えたニナが揃って現れたことに、主に外部の観客たちから期待で歓声を上げる。
ニナは聖歌隊の時の衣装で花冠も被ったままだが、足元はショートブーツを履いていた。歓声に嬉しそうに手を振って応えている。
王子であるニナの弟がドラムにつき、もう一人の腕っぷしの強そうな男がベースを担ぐ。この二人は緊張からか表情は固かった。
「どうもルクノルディアバンドでーす。」
ソラがギターにケーブルを繋ぎながらマイクで名乗る。国名そのままの何の捻りもないバンド名に笑いのような歓声が上がる。
ニナはスタンドマイクの前に立ってもなお緊張感なく、一人一人に手を振っていた。
アレックスの座っている近くテーブルに、先程の親父バンドのメンバーが各々大きなビールジョッキと軽食を持ち寄って、一仕事終えた乾杯をしていた。あとは若手のステージを楽しむだけだ、とでもいうような雰囲気である。
1曲目は意外にも重厚なナンバーだった。ベース音が暗闇から鳴り渡り、夜空の銀河を際立たせた。ニナやソラのこれまでののほほんとした雰囲気が吹き飛ぶ。最初の聖歌隊が纏っていた神聖さが近いが、それにギターとベースに四つ打ちのドラムが観客をかろうじて現代にとどまらせる。
歌はFiol語だった。孤独と祈りの歌だった。ニナの細い体からは発せられているとは思えない力強い声。だが同時に儚げな少女のようでいて、無垢な少年のようでもあった。観客は一気にその世界に惹き込まれていく。親父バンドの最後の陽気さとの落差がすごい。誰から見てもこのバンドのリーダーと思われるソラの思惑通りかもしれない。
まだ固さの残るドラムとベースの上で、ソラだけは自由にしなやかにそのギターを鳴らす。音に没頭しているようで他のメンバーを気遣って見守っているのがわかる。
ニナは他のメンバーが鳴らす音に疑うことなく身を預けて歌い上げる。憑依型とは彼女のようなタイプのことを言うのだろうと思った。先程までステージ上からニコニコと手を振っていた人物と、また昼間に邂逅した人物と、やはり同一人物だとは思えなかった。最初の聖歌隊の錫杖を持っていた彼女ともどこか違うようだ。
アレックスは再び鳥肌が立っているのを自覚した。隣の親父たちもビールのジョッキをテーブルに置いたままステージに見入っている。観客の中には感極まっている女もいた。
その場にいる人間全員の思いを受け止めた歌声は、祈りとなって夜空へ消えていく。
曲が終わっても歓声も拍手の一つも起きなかった。誰もが魂を抜かれたようになっている。そんなことは想定済みだとでも言いたげにソラが次の曲を奏で始めた。
前曲とは打って変わって、軽快でダンサブルなリズムだ。ニナの表情に満面の笑みが戻り、観客に向かって、ところで何をそんなに深刻になっているの?とバンドが問うているようだった。
挑発されて嬉しそうに観客達の体も自然と動き出す。親父達もビールを飲み出す。この瞬間は完全にソラの手の内のようだ。ニナもこれまでと打って変わってポップに表情豊かに体でリズムを取りながら歌い上げる。表情豊かに、足元は軽やかにステップを踏んでいる。観客はとっくに座席の存在を忘れて思い思いに踊ったり、拳を上げたりしている。
最初のサビ終わりでニナが被っていた花冠を客席に投げた。餌を取り合う雛のように、近くの観客がそれに殺到する。それを合図にニナはスタンドからマイクを持ち出し、なおも自由に踊り出した。見事な黄金色の長い髪が、照明を受けて輝きながら波打っている。
ニナに引っ張られて、ドラムとベースの奏でる音がだんだんと柔らかくなっていくのが分かった。彼らの表情にも汗と共に笑顔が生まれ始めた。ソラもそれを感じているのか、自分の演奏に集中し始めたように見えた。これは前持って打ち合わせていたのだろう、ニナとソラが途中で同じステップを踏むと、会場はますます盛り上がった。二人は双子のように同じ髪色で、同じ肌色で、息もぴったりだった。幼馴染とのことで、多くの言葉はいらないように見える。そんな存在がいるというのは、どういう感覚だろう。アレックスは少し羨ましく思ったかもしれなかった。
ニナがセンターの位置とは全く違う場所でひとしきり踊って、2曲目が終わった。今度は、堰を切ったように歓声が上がる。しかしバンドは止まらない。
立て続けにデジタル音のテンポの速いイントロが鳴り始める。瞬時に客席はさら湧き立った。
それはアレックスでさえ耳にしたことがあるイントロだった。数年前に大ヒットした有名な女性歌手の曲だ。毎日街のどこかしらでこのメロディー耳にしていて、音楽に疎いアレックスでもわかった。
観客の興奮に、ソラがしてやったりの笑顔でジャンプしながら観客に手拍子を誘う。観客は漏れなく自分の頭上で手拍子を始めた。彼らはいつしかステージ前に殺到して密集していた。ここは世界の外れにある山の上だが、もはやライブハウス状態だ。
そんな観客に臆することなくニナは歌う。オリジナルの歌手はかなり独特の声をしているが、ニナはそれに寄せていた。今までの声調とは明らかに違う。こんなに自在に声を操れるものなのだろうか。
言語はオリジナルに揃えてEstalia語だ。彼女にとってはFiol語以上に馴染みのない言語らしいことはところどころの発音でわかったが、そんなことは本人も観客もお構いなしだ。サビのキーポイントでニナがマイクを観客へ向けると、観客は応えて皆で大合唱となる。ニナはその反応に嬉しそうに歌い続け、舞った。木綿のドレスが黄金色の髪と一緒にライトを受けて舞い上がり、頬が薔薇色に染まっていた。
誰もが自分のカメラの存在を忘れて目の前のステージに熱中していた。ソラはやはり合間合間で観客を煽り、自分は軽やかにステージ上で跳ねる。
歌詞は現代の都市的なもので、おおよそこの村とは無縁の内容だったが、この瞬間は誰もが空中トラムやチューブの高速道路が血管のように這っている大都会の上を飛んでいるようだった。
曲が終わると、ニナは少し息が上がっていた。それ以上に、観客は自分達の体から湯気を上げて興奮していた。ステージ上のメンバーはそれぞれに目を合わせて、手応えを確認しているようだった。
「改めましたで、ルクノルディアバンドです。楽しんでますかー?」
喋ると嘘みたいに昼間ののほほんとしたニナに戻る。アレックスも観客もまだこの落差に追いつかない。湧き上がる観客の歓声に、ニナはへへへと笑って、用意されたグラスの飲み物で喉を潤す。アレックスが2杯目にありつけなかったスパークリングベリーだ。
「みなさん、遠くから来てくれてありがとうでした。今日は、この村にとっても特別な夜になりました。」
ニナはFiol語で辿々しく、それでも丁寧に言ってから、メンバー紹介をします、と言って照れたように笑った。
「まずはドラムのこの男は私の弟のカイルです。15歳です。」
ニナは脇に立ち位置を変えて、奥に設置しているドラムが見えるようにして紹介する。歓声が起きる。王子はドラムを簡単に鳴らして歓声に応える。嬉し恥ずかしの表情の15歳だ。
「で、ベースをしているのが、えーと漁師さんのサミル君です。」
真面目そうなサミル君の年齢は紹介されなかったが、その腕の太さの理由は推し量れた。サミル君は観客に向かって深々と頭を下げる。皆が温かい拍手を送る。親父バンドの一人が、いいぞサミル!と揶揄うような野次を入れる。父親か、漁師仲間か、そんな感じのこちらも腕っぷしの強そうな親父だった。
「あと、不思議な音とか、照明をつけたり消したりしてくれているロボットのJOYです。それから、前髪が可愛いのが、今日のこのステージの殆どを夜も寝ずに考えたソラですー。」
紹介しているニナ自ら、手を叩く。大きな歓声が上がる。ソラは歓声に応えて、ギターを派手にかき鳴らした。ニナが嬉しそうにソラを見る。
熱狂の中、ソラがマイクを取って「ボクらの歌姫、ニナ!」と紹介する。ニナは少し恥ずかしそうにはにかんで、歓声の中ぺこりとお辞儀をした。そんなニナの様子を見てソラが半分揶揄うように「ニーナ!ニーナ!」とニナコールを誘う。観客が乗ってニナコールを始めると、ソラはそのリズムに合わせて4曲目を演奏し始めた。
これまた世界中でスタンダードだったが一世代前のナンバーだった。異国情緒を誘うサウンドとメロディー。独特でインパクトのあるイントロが、またしても観客を沸かせた。先ほどまでコールを受けて恥ずかしそうにしていたニナはどこへやら、乾いた砂漠の市場を彷徨う旅行者になっていた。旅先での、見知らぬ言葉を喋る男とのひとときの恋を歌っていた。ここは針葉樹が立ち並び、世界のどこよりも一足先に冬を迎えようとしている高地であるのに、観客は一気に灼熱の砂漠へ連れていかれていた。
わかりやすい曲の締めに合わせてニナが良くわからないポーズを決める。観客は自らの体から湯気を発しながら、歓声を上げる。ニナが少し圧倒されて笑っていた。
「今のは、村のおばちゃんたちが好きな歌でした。i yakaite tta?」
ニナは現地語で屋台のおばちゃんたちに向かって何か問いかける。屋台の奥で、村人たちが嬉しそうに声を上げた。
国を封鎖していたとはいえ、諸外国の文化はそれなりに入っていたようだ。城に一日籠っていても飽きなさそうな立派な図書室もある。最新の、とはいかないまでも、それなりの共通のエンターテインメントには触れていたらしいことがわかる。
「では、次が最後です。」
不意の終了の知らせに、悲嘆にも似た声が上がる。歓声の中、今日はありがとうとニナが言うのと同時にソラはギターを鳴らし始めた。
最後は4ピースのロックバンドとして期待を裏切らない、四つ打ちのみずみずしい楽曲だった。これまでの曲のなかでは、この若々しいバンドに一番相応しいような、さわやかで疾走感のある曲だった。ドラムのカイルが力強い一音を鳴らすたびに汗が輝いて飛んでいた。ソラは誰よりも自由でしなやかにその風景を描いた。ニナの伸びやかな素直な歌声が風に乗って駆け抜けていく。ベースのサミル君は、そんな3人を守るようにいつくしむように行くべき道に導いている。
雲一つない晴れた日にあの一本道の農道を、この4人が駆け抜けていくさまが見えるようだった。
最後のサビも超えてアウトロが終わっても、音は止まなかったし、観客の歓声も止まない。ニナはアドリブで歌い終幕を惜しんでいるようだった。
「最後はみんなで飛ぶさー」と観客に向かって言うと、演奏の音量が一段階上がる。ニナは観客を嬉しそうに一度見渡すと、「せーの!」と掛け声をかける。ニナとソラとサミル君と会場が同時に飛んだ。着地とともに最後の一音が鳴らされ、周囲に静寂が訪れた。
と思った瞬間、今夜一番の歓声が起こった。ステージの4人はやり切った表情で歓声を全身で受け、お互いに顔を見合わせて相手を称えていた。ニナが「ありがとう、またね」と言って手を振りながら、鳴り止まない拍手に見送られて4人はステージを後にした。
4人が去っても拍手は鳴り止まず、そのままアンコールが叫ばれた。これで帰ろうとする者は一人もいなかった。特に観光客の若者たちがステージに送る声は熱気そのものだった。もみくちゃになって、汗なのか頭からアルコールを被ったのかよくわからないような状態でバンドを呼んでいる。
アレックスは変わらずテーブル席から様子を眺めていただけだが、気づけば飲み物を飲む手が止まっていた。「すげーな、」こぼれるように一人呟いてみたが、周囲の歓声で誰にも届かない。思い出したようにワインを一口飲んだ。
アンコールはいつの間にかニナコールに変わっていた。3曲目の終わりで、ソラに教えられたやつだ。特にもったいぶることもなく、4人は再度壇上に上がった。歓声の中、ニナはありがとうと言ってから準備をする3人を一人ずつ改めて紹介した。
「アンコールしてもらえてよかったら。」と、素直にソラと顔を見合わせて言うと、どっと笑いが起きた。前提で準備していたのがわかる。アレックスも思わず笑ってしまった。
「最後は、聖歌隊のみんなにも手伝ってもらいます。」
ニナがそういうと、聖歌隊が年長組を先頭に10人皆がステージ上に上がった。最年少の少女は少し上の少女に手を引かれて現れた。冒頭の衝撃を思い出したのか、観客は皆期待から万雷の拍手を送った。少女たちは皆、嬉しいような恥ずかしいような素直な表情をしている。ニナは全員と丁寧に目を合わせてから、スタンドマイクに向かった。
「本当に今日はありがとうございました。みなさんが、今後もずっと幸せであることを願って、ルクノルディアバンドと聖歌隊が心を込めてこの歌を贈ります。」
ニナが再び皆と目を合わせたあと、正面を向いてスタンドマイクに少し身を預けるように構えた。観客は声援を止めて、その時を待った。ドラムのカイルが3拍の拍子をとったのを合図にニナが一音発声したと同時に、聖歌隊のコーラスと重低音と共に最後の曲が始まった。
聖歌隊がいても、サウンドは重厚なロックバンドのものだった。しばらくはギターとニナの歌唱だけのフレーズが続いた。湖面を背後に星空の下、世界はニナとソラだけだった。
ニナはスタンドマイクで体を支え、前後に体を揺らしてリズムをとりながら歌っている。目の前の観客たちの姿が見えなくなったかのように、ソラの鳴らすギターに全身を預けているのがわかる。ソラもそれが分かっているのだろう、もうニナしか見ていなかった。ニナは少し思い詰めているかのようにさえ見えた。曲調がそう見させているのだろうか。
途中からドラムの音が強くなり、ベース音も前に出てくる。と同時に、聖歌隊も控えめにハーモニーを奏でた。そして一瞬、ニナの歌声以外の音が消え去った。ニナの声が星空に響き渡った。その残響が消えきる前に、ドラムが一音鳴らす。
それを合図に、ベースとギターと聖歌隊が怒涛の波のように観客を襲った。あふれる祈りの波に背中を押されて、ニナは前後に体を揺らしたまま、今日の景色を忘れないと歌った。光を受けてその瞳に輝くものが見えるのは、汗だろうか。
あとはすべてを聖歌隊の祈りの歌とベースの音がかき消していった。ニナは聖歌隊の圧倒的な音を浴びてかき消されるのを望んでいるようにさえ見えた。
圧倒的な祈りのうねりが止み、静かなギターとベースとの音が僅かに鳴ったあと、すべては夜空に消えていった。
一瞬の間をおいて、観客が暴発したように沸いた。万雷の拍手の中でソラがギターを掲げると、拍手は一層高まった。
聖歌隊たちは安心したように顔を合わせている。直前まで圧倒的なハーモニーを奏でていた者たちとは思えない、素朴な少女たちがそこにいた。
ソラが自分のギターを背中に回して、ニナに近づく。ニナはマイクスタンドを掴んだまま、動けなくなっていた。
ソラはニナを隠すようにマイクの前に立ち、ありがとうございましたーと満面の笑みで観客に向かって手を振った。再度拍手が起こる。
ニナは泣いているのだろうか。もう声を発せなくなっているようだった。ソラが笑いながら、ニナの頭をくしゃくしゃしている。
聖歌隊の少女たちがニナに近寄り、ソラがニナを託す。少女たちの何人かもつられたのか、顔を真っ赤にして泣きそうになっているのが分かった。皆で抱き合っているのをソラが笑いながら舞台袖に行くように催促している。
カイルとサミル君とソラが、観客に向かって手を振る。サミル君も感極まっているようだった。目が赤くなっている。よくよく見ると熱狂の中、号泣している観客も一人や二人ではなかった。
メンバーを見送って、ソラが一番最後にステージから降りた。マイクを通さずに声を張り上げて、最後にもう一度ありがとうございました!と叫んで大きく手を振ると、万雷の拍手が起きた。興奮冷めやらずに再度のアンコールを試みる者もいたが、無情にもステージの明かりは落とされた。悲嘆の声と共に会場がざわつく。圧倒的な余韻だけがその場に残された。
アレックスは大きく息を吐いてから席を立った。呼吸が止まっていたかもしれない。
会場はまだまだ熱気で溢れていたが、アレックスはそこを後にした。風に打たれ、たった今目撃したものを自分の中で消化させながら、ゆっくりと城に戻る。
会場のざわめきが遠くなっていく。城に人の気配はなく、アレックスは与えられた部屋の近くのバルコニーに出た。少し興奮した体に、冷たい風が心地よかった。
眼下の湖は闇に身を隠し、ほとりの会場の灯りと人々のざわめきだけが漏れ届いた。彼らの夜はまだまだ続きそうだ。
おそらく、アレックスはこれまでの人生で一番印象深い夜を過ごした。一昨日、雪山で一人で迎えた夜に匹敵する夜を、2日後にはもう迎えることになるとは思ってなかった。
今夜も夜空には満天の星が輝いている。