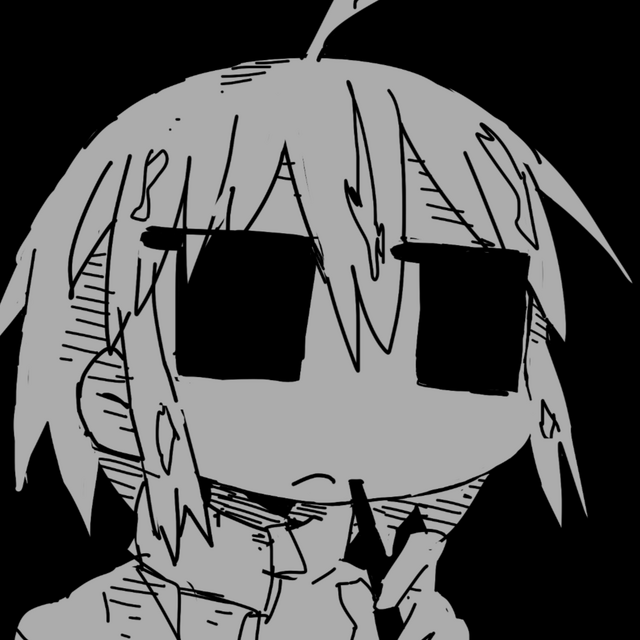第5話
文字数 2,455文字
『――お客さん。起きてください』
タクシードライバーの「着きましたよ」の声で起きる。
「え、ええ。眠りかけていました」
なんて言ったが実際は眠っていた。
〈少し眠ってしまった。不用心だ〉
このタクシードライバーが危険じゃなくて助かった。
タクシーで眠るなんてアルゼンチンでは危険なこと。急いで料金を払おうとしたけれど「いえ、別にいいですよ。一応、出版社からもらっていますのでね」と言われた。そんなことは、今、初めて聞いた。お金に余裕がない私は「取材の協力に感謝します」とお礼を言い、彼の言葉に従い、荷物を手にタクシーを降りた。
私を降ろすと、タクシーは闇夜へと走り去っていく。
「さて。家に帰るとしようか」
そう言って、今、自分がどこに居るのか把握しようと思って、あたりを見回す。すると 「レティーロ駅ではない」ことは確かだ。
「どこだ。ここ?」
郊外にも程がある。道路と標識。街灯。
「え? 一体、どこに私を連れてきたんだ? 適当に走って、レティーロ駅に戻るという会話をしたのに」
まさか、話の途中で眠った私への嫌がらせか?
道に、人も、車も見当たらない。
長く暗い道路の向こうに一軒、大きな家の灯りと思われる灯りが見える、一本道。やたら寂しい風景が「どこか分からない場所に居る」という不安を大きくさせる。スマホで現在地を確認しようとしたけれど「圏外」の文字。
「最悪だ。明日もあるのに」
とにかく人気のない道は危険だ。
とりあえずあの灯りまで歩くことに。歩いていると「どこか見覚えのあるような道だ」と感じたが、思い出せない。そうやって歩いていくとその先に「あの邸」があった。先日、取材で訪れた「あの邸」だ。
でも、何故か廃墟じゃない?
灯りも点いている。
〈そうか。郊外のバス停からこの邸へ行く道だった。でも、この前と景色も空気も違う。何故、あの邸は廃墟ではない? どうして灯りが灯っているんだ? あの灯りは、ライターの炎のように揺らめく妖しい灯りだ〉
「ここは、現実ではないのかもしれない」
その予感はおそらく正しいかもしれない。
しかし、恐怖より好奇心が前に出てくる。
「Occult Writer」の悲しき性質。調べてみよう。あるいは、そうしなければ抜け出せないかもしれないとさえ感じる「鍵」ならある。時間があれば出版社によって返そう返そうと思って鞄に入れて、そのままだ。
私は鞄から「鍵」を取り出す。
まだ、半信半疑で鍵穴に差し込んでみると「ガチャリ」と回った。
〈正直に言うとちょっと怖いが〉
誰かが居るかもしれない、あるいは居ないなら幽霊か。どちらにしても、流石に怖いが、ここで引き返すのも「負けたようで嫌」だ。
「オカルトなら調べて記事にしてやろうか」
それが、私の今のアイデンティティーである。私の「強さ」だ。今、それを失えば心が脆くなる。心の脆さでオカルトは増長する。
「強さはオカルトに負けないために必要だ」
ゆっくりと警戒しながら邸の扉を開いた。
* * * * *
邸の中に入ると玄関から邸の様子が見える。
70’sの豪邸のように見える。
家具等は大きくてゴシック調、色合いは赤と黒のようだ。
その割に「現代の家電製品」はあまり見て取れない。階段横に置かれている電話機はダイアル式で、現代ならアンティークだけどまるで新品のように見える。暖炉、炎が灯っている。邸の空気は不思議な感じだ。
まるで夢を見ているかのようだ。
でも、意識は微睡んでいなくはっきりしている。
そんな感覚は、初めて経験する。
『ようこそ。お客様』
奥から一人の女性が私の前に現れる。
「私は「リリー・ミントフィールド」といいます。この邸の使用人です。一体、どのような用事でこの邸へ? 邸の鍵を持っているのですか?」
女性は「東洋人」のように思えた。
メイド服を着た「チーノ」のように感じる。それと不思議な佇まいがある。もしかすると日本人「マッジーア・ジャポネーゼ」かもしれない。もっとも、その違いは私は区別できないのだが、何となく「彼女は日本人かもしれない」と感じた。
少なくとも「ラティーナには見えない」かな。
まず問われたことに答えようとした。けれど。
「私もこの状況がよく分かっていないのですが」
どう説明していいのか分かっていない。
「どうやら道に迷っているみたいです」
今の状況の全てを話して怪しまれるのも、あれだ。少しずつ、それとなく情報を聞き出してみるのが正解かもしれないと。ペラペラと自分から全てを喋ることは少し避けて、向こうが喋ってくれるかを、待つか。
〈彼女は敵かもしれない〉
分からない。何もかも未確定だ。
私がそう思っていると声がした。
『この時刻に、一体誰だ?』
男性の声だ。階段の上から声が聞こえた。階段を見ると灯りに映された「影」が見える。男性の影で間違いないだろう。
リリーと名乗った使用人は言う。
「そのようです。ご主人」
「私に覚えのない来客だ」
「ですが、外はもう夜です」
リリーのその言葉に少し考えた後、男性は答える。
「それもそうだな。よろしい。武器を持っていないことを確認したら邸へあげなさい。一応「おもてなし」するように。そう、私のコレクションでも楽しんでもらえればいい。折角、集めた絵画を見せないのも寂しいことだ」
「かしこまりました。ご主人」
リリーは振り向いて私に告げる。
「だ、そうです」
「ご厚意、ありがとうございます」
私がそう伝えると「お名前は?」と彼女に聞かれた。
彼らが「オカルト」なら私の本名を名乗るは危険か? そう、こんな時に名乗れる「もう一つの名前」を私は持っている。
「「ボルヘス・K・ジェローム」です」
「男性名のように聞こえますが?」
「そう名付けられたもので。はい」
リリーの表情は疑問に思っているように見えたが「そうですか」と、詮索はしてこなかった。私は、武器を持っていないことを証明した。
リリーは、私を邸の中へと入れた。
「それではジェローム様。邸に飾られている絵画をお見せしましょう」
タクシードライバーの「着きましたよ」の声で起きる。
「え、ええ。眠りかけていました」
なんて言ったが実際は眠っていた。
〈少し眠ってしまった。不用心だ〉
このタクシードライバーが危険じゃなくて助かった。
タクシーで眠るなんてアルゼンチンでは危険なこと。急いで料金を払おうとしたけれど「いえ、別にいいですよ。一応、出版社からもらっていますのでね」と言われた。そんなことは、今、初めて聞いた。お金に余裕がない私は「取材の協力に感謝します」とお礼を言い、彼の言葉に従い、荷物を手にタクシーを降りた。
私を降ろすと、タクシーは闇夜へと走り去っていく。
「さて。家に帰るとしようか」
そう言って、今、自分がどこに居るのか把握しようと思って、あたりを見回す。すると 「レティーロ駅ではない」ことは確かだ。
「どこだ。ここ?」
郊外にも程がある。道路と標識。街灯。
「え? 一体、どこに私を連れてきたんだ? 適当に走って、レティーロ駅に戻るという会話をしたのに」
まさか、話の途中で眠った私への嫌がらせか?
道に、人も、車も見当たらない。
長く暗い道路の向こうに一軒、大きな家の灯りと思われる灯りが見える、一本道。やたら寂しい風景が「どこか分からない場所に居る」という不安を大きくさせる。スマホで現在地を確認しようとしたけれど「圏外」の文字。
「最悪だ。明日もあるのに」
とにかく人気のない道は危険だ。
とりあえずあの灯りまで歩くことに。歩いていると「どこか見覚えのあるような道だ」と感じたが、思い出せない。そうやって歩いていくとその先に「あの邸」があった。先日、取材で訪れた「あの邸」だ。
でも、何故か廃墟じゃない?
灯りも点いている。
〈そうか。郊外のバス停からこの邸へ行く道だった。でも、この前と景色も空気も違う。何故、あの邸は廃墟ではない? どうして灯りが灯っているんだ? あの灯りは、ライターの炎のように揺らめく妖しい灯りだ〉
「ここは、現実ではないのかもしれない」
その予感はおそらく正しいかもしれない。
しかし、恐怖より好奇心が前に出てくる。
「Occult Writer」の悲しき性質。調べてみよう。あるいは、そうしなければ抜け出せないかもしれないとさえ感じる「鍵」ならある。時間があれば出版社によって返そう返そうと思って鞄に入れて、そのままだ。
私は鞄から「鍵」を取り出す。
まだ、半信半疑で鍵穴に差し込んでみると「ガチャリ」と回った。
〈正直に言うとちょっと怖いが〉
誰かが居るかもしれない、あるいは居ないなら幽霊か。どちらにしても、流石に怖いが、ここで引き返すのも「負けたようで嫌」だ。
「オカルトなら調べて記事にしてやろうか」
それが、私の今のアイデンティティーである。私の「強さ」だ。今、それを失えば心が脆くなる。心の脆さでオカルトは増長する。
「強さはオカルトに負けないために必要だ」
ゆっくりと警戒しながら邸の扉を開いた。
* * * * *
邸の中に入ると玄関から邸の様子が見える。
70’sの豪邸のように見える。
家具等は大きくてゴシック調、色合いは赤と黒のようだ。
その割に「現代の家電製品」はあまり見て取れない。階段横に置かれている電話機はダイアル式で、現代ならアンティークだけどまるで新品のように見える。暖炉、炎が灯っている。邸の空気は不思議な感じだ。
まるで夢を見ているかのようだ。
でも、意識は微睡んでいなくはっきりしている。
そんな感覚は、初めて経験する。
『ようこそ。お客様』
奥から一人の女性が私の前に現れる。
「私は「リリー・ミントフィールド」といいます。この邸の使用人です。一体、どのような用事でこの邸へ? 邸の鍵を持っているのですか?」
女性は「東洋人」のように思えた。
メイド服を着た「チーノ」のように感じる。それと不思議な佇まいがある。もしかすると日本人「マッジーア・ジャポネーゼ」かもしれない。もっとも、その違いは私は区別できないのだが、何となく「彼女は日本人かもしれない」と感じた。
少なくとも「ラティーナには見えない」かな。
まず問われたことに答えようとした。けれど。
「私もこの状況がよく分かっていないのですが」
どう説明していいのか分かっていない。
「どうやら道に迷っているみたいです」
今の状況の全てを話して怪しまれるのも、あれだ。少しずつ、それとなく情報を聞き出してみるのが正解かもしれないと。ペラペラと自分から全てを喋ることは少し避けて、向こうが喋ってくれるかを、待つか。
〈彼女は敵かもしれない〉
分からない。何もかも未確定だ。
私がそう思っていると声がした。
『この時刻に、一体誰だ?』
男性の声だ。階段の上から声が聞こえた。階段を見ると灯りに映された「影」が見える。男性の影で間違いないだろう。
リリーと名乗った使用人は言う。
「そのようです。ご主人」
「私に覚えのない来客だ」
「ですが、外はもう夜です」
リリーのその言葉に少し考えた後、男性は答える。
「それもそうだな。よろしい。武器を持っていないことを確認したら邸へあげなさい。一応「おもてなし」するように。そう、私のコレクションでも楽しんでもらえればいい。折角、集めた絵画を見せないのも寂しいことだ」
「かしこまりました。ご主人」
リリーは振り向いて私に告げる。
「だ、そうです」
「ご厚意、ありがとうございます」
私がそう伝えると「お名前は?」と彼女に聞かれた。
彼らが「オカルト」なら私の本名を名乗るは危険か? そう、こんな時に名乗れる「もう一つの名前」を私は持っている。
「「ボルヘス・K・ジェローム」です」
「男性名のように聞こえますが?」
「そう名付けられたもので。はい」
リリーの表情は疑問に思っているように見えたが「そうですか」と、詮索はしてこなかった。私は、武器を持っていないことを証明した。
リリーは、私を邸の中へと入れた。
「それではジェローム様。邸に飾られている絵画をお見せしましょう」