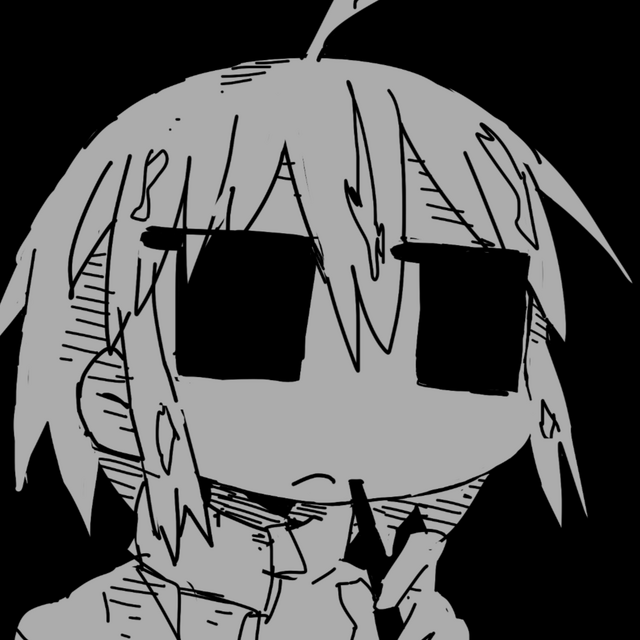第1話
文字数 2,454文字
アルゼンチン。ブエノスアイレスの市バス。
「ボロい」市バスに乗るのは、正直、きつい。
〈金のない国だって分かるよ。安いから、市バスがとにかく混むんだ〉
インフラの老朽化はこの国の社会問題の一つ。
利用者が多いけれど、バスはボロいし、常に満員でも本数は増えない。それも当然のことで「乗車料金が安い」からだ。この料金だと客を乗せようが、儲からないので。でもインフラとして機能しないと国民は不満を爆発させる。それは「国民性」だけど、あまり良いものじゃないと「私」は思う。
さっさと乗り込んで、空いている席へ。
固い緑色のシート席。相席で肩を縮めて座った。
座席に座って安物のイヤホンをして音楽を聴く。
〈Marshallのヘッドフォンが欲しいなあ。でも、金ないからなあ。あれで音楽を聴くのなら、こういう時間も楽しいものになるのかもな〉
バイト増やそうかな、と一瞬考える。
〈いや。勉強の時間はもうこれ以上削れないな〉
いつの世も、金のない人間は苦労するしかないのだ。
市バスの窓の向こう。相変わらず「喧騒」と呼ぶのに相応しいブエノスアイレスの街並みを眺めながら「今日の取材」の内容を確認する。手に持っている「書類」は、取材の内容が書かれたメールを印刷したものだ。
〈〈私たちが信頼する「ボルヘス」よ。
君の怪奇記事にまた一つ素晴らしいものを加える助けになるかと思われる「案件」を持ってきた。私たちも君の仕事に期待している。
今回の案件は郊外にある邸「廃墟」の調査だ。
詳しくは添付したPDFを見てほしい。調査にかかる費用は「公共のものならば」出版社が後日、君に支払おう。何かあればメールしてくれ〉〉
「信頼するボルヘス、ね」
思わず呟く、私は「ルミナ・マリア・ストーン」女子大学生だ。
アルバイトとして「ライター」をしている。
オカルト雑誌「Munew」はオカルト雑誌だ。
今は、ネットにも記事を載せて広告でも収入を得ているらしい。言っちゃあ何だが雑誌「Munew」は「怪しいメディア」だ。でも別にそんなことはいい。私は「Munew」から報酬をもらっている身なので、潰れたら困る。
* * * * *
私のPNは「ボルヘス・K・ジェローム」だ。
編集に勝手に決められたPNだけど、そこそこ気に入っている。
小さい頃から色々な本を読んで育ってきた。
ボルヘスは言わずもしれたアルゼンチンの文豪だ。
「ジェローム・K・ジェローム」も、アルゼンチンには特に関係ないが、まあ、好きだ。でも、何故、私のPNに英国人名の「ジェローム」を入れたのかは疑問だ。私は女だし。でも、聞くタイミングを逸した。
〈今や、立派なオカルトライターだな〉
2年半も出版社にお世話になっている。
まともな「オカルト記事」を書ける記者は希少らしい。
このバイトに不満も愚痴もあるが、まあ、他のバイトより「マシ」ということで「心霊ライター」を続けている。言っちゃうと、変な人間を相手にするよりは、まだオカルト相手の方が割り切れる時がある。
若干、私も浮世離れしてきているのかも。
〈にしたって本当、ボロい市バスだ〉
座っていて体が少し痛くなってきた。
アルゼンチンが先進国だった。みたいな話を年寄りからたまに聞くが、今は発展途上国に落ちている。熱しやすい国民性は、ポピュリズムを拒みきれずに、場当たり的な政策が続くお国柄。
豊かになるどころか年々悪化している。
残念ながら「私は熱くない」冷めている。
本の虫「Bookworm」と呼ばれていた頃もある。
サッカーもそれほど興味もない。この国ではメッシの話をよくされるが、サッカーにそれほど熱を上げていない私は、少し肩身が狭い。代表戦のあった翌日にはあらゆるところから「昨日、観たか?」と話しかけられる。
その度に私は「いや、観てないです」と答える。
大体の場合、彼ら、あるいは彼女たちは「Bookwormめ」と私に失望する。面倒なので、別にそれでいいや、ってなる人間だ。
バス停で止まった市バスを降りる。
市バスは去っていく。
「さて、ここからが仕事だ」
今回も適当にオカルト記事を書かないといけない。
「地図によると徒歩10分くらい」
地図とマップアプリを見ながら目的地に向けて歩き出す。
* * * * *
「ようやく到着だ。何が徒歩10分だ。30分は歩いたぞ」
歩いてたどり着いたのは、無人の邸宅。
ブエノスアイレスの郊外。幸い、スラムではない。
「それも、かなり大きい。美術館よりも大きいんじゃないかって思うくらいだ。よほどの金持ちが建てたんだろうな。庭にプールもあると聞いているけれど、落ちたら抜け出せなさそう、物理的に。雑草とかで」
一つの懸念は「もう夕方」ということ。
午後、思ったより市役所での用事が遅れたツケが回った。
「やばいな。暗くなると幽霊は強くなる」
たまに聞かれる「幽霊なんて居るの?」への私の返答は「居る」だ。
はじめは「否定したかった」けれど、こういう仕事を続けていると「あ、これはもう否定しきれないな」と思う案件をいくつも経験する。それで、居ないよ、と言うことは出来なくなった。自分の目で見たこと、耳で聞いたこと。それを否定してしまえば自分の存在を否定することになるから。
私はそこに居て見て、聞いた。体験したからだ。
それを言えなければ「私が幽霊」だ。
「夜になる前に取材を終わらせよう。中に入るか」
「鍵」をオーナーからもらっている。
銀色の鍵。それを入れて回すと確かに鍵がかかっていたようで「ガチャ」っと感覚がして、その事実に「安堵」する。
「よかった。鍵はかかっていた」
中に人が住み着いている可能性は低い。
この廃墟となっている邸が「今回の取材現場」だ。
当然、心霊「オカルト」の取材になる。が。人が居る可能性が一番怖かった。どうやら、その可能性が低いことに少し安堵する。ギイイ、と鈍い音を立てながら重い玄関の扉を開けて、私は中へ乗り込む。
「さーて。今回のオカルトさんはどんなだろうね?」
「ボロい」市バスに乗るのは、正直、きつい。
〈金のない国だって分かるよ。安いから、市バスがとにかく混むんだ〉
インフラの老朽化はこの国の社会問題の一つ。
利用者が多いけれど、バスはボロいし、常に満員でも本数は増えない。それも当然のことで「乗車料金が安い」からだ。この料金だと客を乗せようが、儲からないので。でもインフラとして機能しないと国民は不満を爆発させる。それは「国民性」だけど、あまり良いものじゃないと「私」は思う。
さっさと乗り込んで、空いている席へ。
固い緑色のシート席。相席で肩を縮めて座った。
座席に座って安物のイヤホンをして音楽を聴く。
〈Marshallのヘッドフォンが欲しいなあ。でも、金ないからなあ。あれで音楽を聴くのなら、こういう時間も楽しいものになるのかもな〉
バイト増やそうかな、と一瞬考える。
〈いや。勉強の時間はもうこれ以上削れないな〉
いつの世も、金のない人間は苦労するしかないのだ。
市バスの窓の向こう。相変わらず「喧騒」と呼ぶのに相応しいブエノスアイレスの街並みを眺めながら「今日の取材」の内容を確認する。手に持っている「書類」は、取材の内容が書かれたメールを印刷したものだ。
〈〈私たちが信頼する「ボルヘス」よ。
君の怪奇記事にまた一つ素晴らしいものを加える助けになるかと思われる「案件」を持ってきた。私たちも君の仕事に期待している。
今回の案件は郊外にある邸「廃墟」の調査だ。
詳しくは添付したPDFを見てほしい。調査にかかる費用は「公共のものならば」出版社が後日、君に支払おう。何かあればメールしてくれ〉〉
「信頼するボルヘス、ね」
思わず呟く、私は「ルミナ・マリア・ストーン」女子大学生だ。
アルバイトとして「ライター」をしている。
オカルト雑誌「Munew」はオカルト雑誌だ。
今は、ネットにも記事を載せて広告でも収入を得ているらしい。言っちゃあ何だが雑誌「Munew」は「怪しいメディア」だ。でも別にそんなことはいい。私は「Munew」から報酬をもらっている身なので、潰れたら困る。
* * * * *
私のPNは「ボルヘス・K・ジェローム」だ。
編集に勝手に決められたPNだけど、そこそこ気に入っている。
小さい頃から色々な本を読んで育ってきた。
ボルヘスは言わずもしれたアルゼンチンの文豪だ。
「ジェローム・K・ジェローム」も、アルゼンチンには特に関係ないが、まあ、好きだ。でも、何故、私のPNに英国人名の「ジェローム」を入れたのかは疑問だ。私は女だし。でも、聞くタイミングを逸した。
〈今や、立派なオカルトライターだな〉
2年半も出版社にお世話になっている。
まともな「オカルト記事」を書ける記者は希少らしい。
このバイトに不満も愚痴もあるが、まあ、他のバイトより「マシ」ということで「心霊ライター」を続けている。言っちゃうと、変な人間を相手にするよりは、まだオカルト相手の方が割り切れる時がある。
若干、私も浮世離れしてきているのかも。
〈にしたって本当、ボロい市バスだ〉
座っていて体が少し痛くなってきた。
アルゼンチンが先進国だった。みたいな話を年寄りからたまに聞くが、今は発展途上国に落ちている。熱しやすい国民性は、ポピュリズムを拒みきれずに、場当たり的な政策が続くお国柄。
豊かになるどころか年々悪化している。
残念ながら「私は熱くない」冷めている。
本の虫「Bookworm」と呼ばれていた頃もある。
サッカーもそれほど興味もない。この国ではメッシの話をよくされるが、サッカーにそれほど熱を上げていない私は、少し肩身が狭い。代表戦のあった翌日にはあらゆるところから「昨日、観たか?」と話しかけられる。
その度に私は「いや、観てないです」と答える。
大体の場合、彼ら、あるいは彼女たちは「Bookwormめ」と私に失望する。面倒なので、別にそれでいいや、ってなる人間だ。
バス停で止まった市バスを降りる。
市バスは去っていく。
「さて、ここからが仕事だ」
今回も適当にオカルト記事を書かないといけない。
「地図によると徒歩10分くらい」
地図とマップアプリを見ながら目的地に向けて歩き出す。
* * * * *
「ようやく到着だ。何が徒歩10分だ。30分は歩いたぞ」
歩いてたどり着いたのは、無人の邸宅。
ブエノスアイレスの郊外。幸い、スラムではない。
「それも、かなり大きい。美術館よりも大きいんじゃないかって思うくらいだ。よほどの金持ちが建てたんだろうな。庭にプールもあると聞いているけれど、落ちたら抜け出せなさそう、物理的に。雑草とかで」
一つの懸念は「もう夕方」ということ。
午後、思ったより市役所での用事が遅れたツケが回った。
「やばいな。暗くなると幽霊は強くなる」
たまに聞かれる「幽霊なんて居るの?」への私の返答は「居る」だ。
はじめは「否定したかった」けれど、こういう仕事を続けていると「あ、これはもう否定しきれないな」と思う案件をいくつも経験する。それで、居ないよ、と言うことは出来なくなった。自分の目で見たこと、耳で聞いたこと。それを否定してしまえば自分の存在を否定することになるから。
私はそこに居て見て、聞いた。体験したからだ。
それを言えなければ「私が幽霊」だ。
「夜になる前に取材を終わらせよう。中に入るか」
「鍵」をオーナーからもらっている。
銀色の鍵。それを入れて回すと確かに鍵がかかっていたようで「ガチャ」っと感覚がして、その事実に「安堵」する。
「よかった。鍵はかかっていた」
中に人が住み着いている可能性は低い。
この廃墟となっている邸が「今回の取材現場」だ。
当然、心霊「オカルト」の取材になる。が。人が居る可能性が一番怖かった。どうやら、その可能性が低いことに少し安堵する。ギイイ、と鈍い音を立てながら重い玄関の扉を開けて、私は中へ乗り込む。
「さーて。今回のオカルトさんはどんなだろうね?」