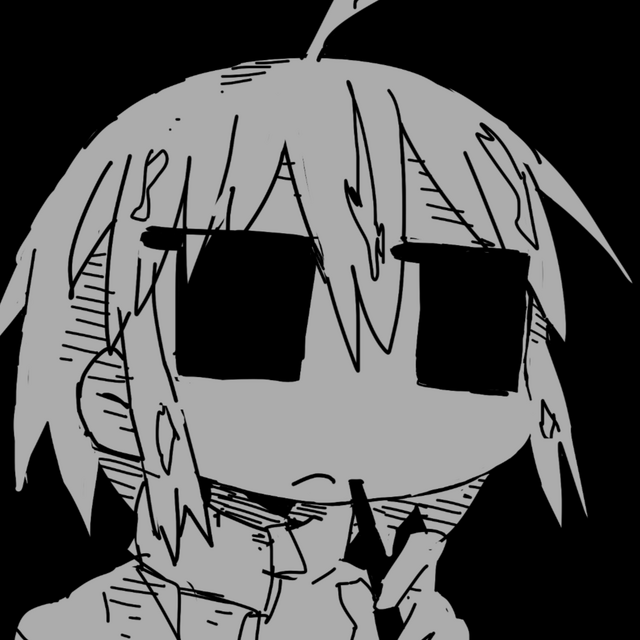第4話
文字数 2,346文字
後日。大学の構内。
研究所。一人で「共同論文」の校正をしている。
これでも「ブエノスアイレス大学」在籍。
大学の講義は割と真面目に聞いている方だと思う。大学での専攻は「民俗学」だ。専門的なことを学んでいるのは、消えゆく中南米の先住民の、口語で伝わっている神話形体を後の世にも残していきたいと思っているからだ。アメリカ大陸に住んでいる私は、それを「意味のある職業」だと考える。
〈少なくとも心霊ライターよりは良い職だ〉
大学の研究チームの一員として残りたい。
ただ「そこ」に就くには、大学で教授の評価を得なければならない。素晴らしい論文を書くか、あるいは、教授の推薦で研究チームに雇われなければならない。狭き門。それをくぐれずに、気が付けば心霊ライターになっている。
〈理想と現実の差に愕然とするよな〉
私は、特に世渡りの術に長けているわけでもない。
こういった論文作業もサポートに回ることが多いが、一度投げ出したなら「そこで終わり」だと分かっている。地道に、それでも自分の出来る限りの最善を尽くしたいと思うのは、それが私の夢への挑戦でもあるから。
「少し、休むか」と席を立つ。
研究所にある無料で飲めるコーヒーメーカーの前へ。
スイッチを押して、紙コップに注がれたコーヒーを飲んだ。
あの後「Munew」に「ボルヘス・K・ジェローム」の記事が掲載された。
〈今夜。また次の取材をする予定がある〉
取材は「出版社」に話を通してから行くことになっている。
向こうがアポを取ってくれる、その内容でかかった出費は出版社持ち、それ以外は自費になる。世知辛くもあり、出版社がある程度機能していることはありがたくもある。おそらく、オカルト雑誌には、もっと酷い出版社もあるだろう。
「流石は国内オカルト雑誌ナンバー1の「Munew」だ」
独り言を言って伸びをする。
「今夜は「タクシードライバーに取材」か」
一つ懸念がある。
「面白いものになるんだろうか?」
* * * * *
オカルトは時に風俗を写し出す。時代性や生活様式、それと価値観や言語特徴を。そういうものが好きだったからこんな仕事を今も続けている。
でも、オカルト雑誌「Munew」は正直、創作みたいな記事も多い。
時には「怪奇小説じみているもの」も。
あるいは「陰謀論じみているもの」も。
オカルト好きはそういうものを含めて「楽しんでいる」から、それでいいらしい。少なくとも、オカルト雑誌の提供するものはエンターテイメントで、真実は二の次だと。楽しければいい。同感だ。ご勝手にするさ。
アルゼンチンには「怪談」が多くある。
1つは「忽然と人が消える」というものが多い。
飛行士が飛行機ごと消えた事件や、行方不明者が全然違う場所で見つかったりなどがそれだ。そういう怪談話を子供の時に聞いているので、思いの外、オカルト好きが多かったりする。怖いもの見たさは人の性だ。
* * * * *
大学での共同論文の作業が終わったのは夜。
〈眠い。最近少しタフな日々が続いているな〉
寝ないようにしないといけない。
ブエノスアイレス、レティーロ駅前。止まっているタクシーに乗り込む「ボルヘス・K・ジェロームです」と挨拶をした。タクシードライバーの顔を後部座席からミラーで見たが、特にこれと言った印象は残らなかった。予め、今夜の取材の内容や事前のやり取りはタクシードライバーと済ませていた、が。
「それで「どこか」へ向かいますか?」
そう言われて少し戸惑った。
「えっと。取材の内容は「話を聞く」ことですが?」
「いえ。運転しながらでも話せるので」
言われて考える。タクシーがずっと止まっていることもリスクがありそうだと。だから「じゃあ、適当に走って1時間後にレティーロ駅前に戻る感じに出来ますか?」と伝える「了解しました」と、タクシーは走り出す。
そして「タクシードライバー」から怪談話を聞くことに。
「自由に話してください」と伝えた。
「ええ。それでは適当に見繕って話していきます」
はじめは、若い新しい同業の話らしい。
「新しく入ってきた同業の話になるんですが、先日、初めて幽霊を乗せたらしくて。雰囲気で、ああ、これは人間じゃないな。そう感じ取れるものなんですよ。それで、車のミラーを見た時、乗客の顔を見てしまった、と。それが、どうしたことか、彼は震えていましてね。聞いてみると、その幽霊は自分の顔をしていた、と。その後、彼は事故で車ごとあの世へ行きましたね」
〈ああ、期待はずれだったかな〉
「ハズレくじ」みたいな気分だ。
〈オカルトに関しては私の方が専門職なんだよな〉
神父に説教、みたいな気分になってきたぞ。
そう思いながらも運転手の話を聞いている。
「このような職業だと乗客が人間でない時や、もしくは「怪しい者」であることもありますね。ただ、運転手としては「そのくらい楽しめるようになったかな」と口元で小さく笑うくらいで丁度いいんですよ」
眠たくなるような話だ。
うとうとしてきた。やばい。寝そうだ。
「私がタクシードライバーになった理由は「車を運転することでお金がもらえたら幸せだろうな」という軽い気持ちでしたね。今では、それは間違いだった、と思うようになりましたが、他の職業へ転職する気力もないんですよ。私はまるで「ゴースト」です。乗せるお客もまた、ゴーストかもしれない。そう思った時に、もはや乗客が人であろうが幽霊であろうが「別に気にするようなことではない」と気付きました。行き先が、現実でも死者の国でも気にすることでもない、と」
今回の取材は完全に失敗だったな。
そう思った時に〈起きてても良いことないな〉と考えた瞬間、疲れと眠い話が相まって抗えきれず意識が遠のいていった。
研究所。一人で「共同論文」の校正をしている。
これでも「ブエノスアイレス大学」在籍。
大学の講義は割と真面目に聞いている方だと思う。大学での専攻は「民俗学」だ。専門的なことを学んでいるのは、消えゆく中南米の先住民の、口語で伝わっている神話形体を後の世にも残していきたいと思っているからだ。アメリカ大陸に住んでいる私は、それを「意味のある職業」だと考える。
〈少なくとも心霊ライターよりは良い職だ〉
大学の研究チームの一員として残りたい。
ただ「そこ」に就くには、大学で教授の評価を得なければならない。素晴らしい論文を書くか、あるいは、教授の推薦で研究チームに雇われなければならない。狭き門。それをくぐれずに、気が付けば心霊ライターになっている。
〈理想と現実の差に愕然とするよな〉
私は、特に世渡りの術に長けているわけでもない。
こういった論文作業もサポートに回ることが多いが、一度投げ出したなら「そこで終わり」だと分かっている。地道に、それでも自分の出来る限りの最善を尽くしたいと思うのは、それが私の夢への挑戦でもあるから。
「少し、休むか」と席を立つ。
研究所にある無料で飲めるコーヒーメーカーの前へ。
スイッチを押して、紙コップに注がれたコーヒーを飲んだ。
あの後「Munew」に「ボルヘス・K・ジェローム」の記事が掲載された。
〈今夜。また次の取材をする予定がある〉
取材は「出版社」に話を通してから行くことになっている。
向こうがアポを取ってくれる、その内容でかかった出費は出版社持ち、それ以外は自費になる。世知辛くもあり、出版社がある程度機能していることはありがたくもある。おそらく、オカルト雑誌には、もっと酷い出版社もあるだろう。
「流石は国内オカルト雑誌ナンバー1の「Munew」だ」
独り言を言って伸びをする。
「今夜は「タクシードライバーに取材」か」
一つ懸念がある。
「面白いものになるんだろうか?」
* * * * *
オカルトは時に風俗を写し出す。時代性や生活様式、それと価値観や言語特徴を。そういうものが好きだったからこんな仕事を今も続けている。
でも、オカルト雑誌「Munew」は正直、創作みたいな記事も多い。
時には「怪奇小説じみているもの」も。
あるいは「陰謀論じみているもの」も。
オカルト好きはそういうものを含めて「楽しんでいる」から、それでいいらしい。少なくとも、オカルト雑誌の提供するものはエンターテイメントで、真実は二の次だと。楽しければいい。同感だ。ご勝手にするさ。
アルゼンチンには「怪談」が多くある。
1つは「忽然と人が消える」というものが多い。
飛行士が飛行機ごと消えた事件や、行方不明者が全然違う場所で見つかったりなどがそれだ。そういう怪談話を子供の時に聞いているので、思いの外、オカルト好きが多かったりする。怖いもの見たさは人の性だ。
* * * * *
大学での共同論文の作業が終わったのは夜。
〈眠い。最近少しタフな日々が続いているな〉
寝ないようにしないといけない。
ブエノスアイレス、レティーロ駅前。止まっているタクシーに乗り込む「ボルヘス・K・ジェロームです」と挨拶をした。タクシードライバーの顔を後部座席からミラーで見たが、特にこれと言った印象は残らなかった。予め、今夜の取材の内容や事前のやり取りはタクシードライバーと済ませていた、が。
「それで「どこか」へ向かいますか?」
そう言われて少し戸惑った。
「えっと。取材の内容は「話を聞く」ことですが?」
「いえ。運転しながらでも話せるので」
言われて考える。タクシーがずっと止まっていることもリスクがありそうだと。だから「じゃあ、適当に走って1時間後にレティーロ駅前に戻る感じに出来ますか?」と伝える「了解しました」と、タクシーは走り出す。
そして「タクシードライバー」から怪談話を聞くことに。
「自由に話してください」と伝えた。
「ええ。それでは適当に見繕って話していきます」
はじめは、若い新しい同業の話らしい。
「新しく入ってきた同業の話になるんですが、先日、初めて幽霊を乗せたらしくて。雰囲気で、ああ、これは人間じゃないな。そう感じ取れるものなんですよ。それで、車のミラーを見た時、乗客の顔を見てしまった、と。それが、どうしたことか、彼は震えていましてね。聞いてみると、その幽霊は自分の顔をしていた、と。その後、彼は事故で車ごとあの世へ行きましたね」
〈ああ、期待はずれだったかな〉
「ハズレくじ」みたいな気分だ。
〈オカルトに関しては私の方が専門職なんだよな〉
神父に説教、みたいな気分になってきたぞ。
そう思いながらも運転手の話を聞いている。
「このような職業だと乗客が人間でない時や、もしくは「怪しい者」であることもありますね。ただ、運転手としては「そのくらい楽しめるようになったかな」と口元で小さく笑うくらいで丁度いいんですよ」
眠たくなるような話だ。
うとうとしてきた。やばい。寝そうだ。
「私がタクシードライバーになった理由は「車を運転することでお金がもらえたら幸せだろうな」という軽い気持ちでしたね。今では、それは間違いだった、と思うようになりましたが、他の職業へ転職する気力もないんですよ。私はまるで「ゴースト」です。乗せるお客もまた、ゴーストかもしれない。そう思った時に、もはや乗客が人であろうが幽霊であろうが「別に気にするようなことではない」と気付きました。行き先が、現実でも死者の国でも気にすることでもない、と」
今回の取材は完全に失敗だったな。
そう思った時に〈起きてても良いことないな〉と考えた瞬間、疲れと眠い話が相まって抗えきれず意識が遠のいていった。