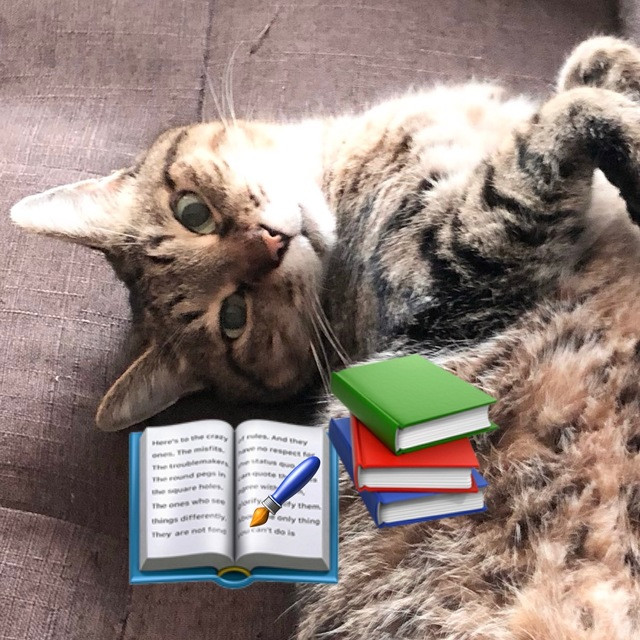第1話 文学賞のゆくえ
文字数 3,356文字

ここは神楽坂の「書籍会館」。多くの版元(出版社)が加盟する組合の更生施設も兼ねる。休日ともなれば出版社社員向けの趣味の講座が開かれる。生け花、写真、版画、油絵など多種多様。交通の便がよいこともあってどの教室もかなりの賑わいを見せる。
ただ、ひと月にいち度、怪しげな会合が開かれることもその筋では名高い。名前は「大手版元懇親会」。名前の通りに日本を代表する出版大手6社が居並ぶ。参加者は社の編集長。しかし執行役員でなければダメ。大手出版社には編集長の肩書を持つ者はゾロゾロ居る。ただし、社の人事運営権を持つ(株式所有)編集局長となるとそうは居ない。
メンツはいつも同じ。年齢的には高齢者に近いので、会の規定により退職した場合のみ入れ替わる。神楽坂との土地柄からどこぞの料亭でと思うのだが、そこは長きの伝統。政治屋さんとはいっ線を画すジャーナリズムの集団。歴史は明治の黎明期に遡る。
ご一新の際の尊王の獅子たちの残党が、長屋のひと部屋に集まり、日本のジャーナリズムの勃興を熱く語り合った。そんな名残が残っているやもしれない。でも現在ここで議論されることは「談合」に他ならない。
まずは今年の幹事、出版社A(以下、出版社B~F)が発言する。
「今年の『獅鷲賞』はE社の番です。何か優秀な作品はありますか? 今は好景気ですから、他の大衆賞とは違ってとりわけ格調高いものにしたいんですが…」
『獅鷲賞』とは日本でいち番権威のある文学賞。いっぱしの作家への登竜門でもある。自称作家は日本に何人いるかはしらねど、目指すところはこの賞。中には10年待ち組などもざらに居る。当初は年に1回だったが、その需要から年に上下半期1回ずつに増えた。
この賞は純文学のみに与えられる。文学とは純文学をさす、と断じて譲らない読書家も多い。
出版社Dが発言する。
「不景気の時は、『透明に近いブルー』『エーゲ海に捧ぐ』『僕って何』とか、あん時は話題を巻くような大衆賞に近いものが尊ばれた。しかし今は書籍の売上も順調。
佳い本とは、売れる本のこと。そんな常識は当たり前なんですが、読書家にはこの理屈は通らない。出版社も商売してるんですがね、、まぁ、ここらで売上げ度外視の獅鷲賞を考えましょうや。それで、おや、やはりジャーナリズムは金満屋とは違うとなる…」
この出版社Dの発言はもっともだ。今や「神武景気(1954~1957年高度成長期の始まりをさす)」以来の好景気と表現される。書籍はどんなジャンルでも押し並べて売れる。ただ、週刊誌などの雑誌類、またコミックマンガは群を抜いて急成長の分野だ。
「たしかに。センセーショナルな作品は数点ありますよ」
順番のEは自信満々だ。
と、出版社Bがしゃしゃり出る。
「ダメだよ。そうじゃなくて。心の奥底までに響き渡る珠玉の名編」
「そうは言っても、読者はやはり時代の先端をゆくものを探してるもんです」
Eは承服しかねる。すると、沈黙していたCが、
「作品はそこそこでも、変わった経歴の著者はいないかな。脱サラ組とか普通の主婦とか、貧乏学生とか。底辺から成りあがって『獅鷲賞』を取ったなんて、今の時代に相応しくないかな? ご存知のように話題性だけあれば、内容の方は校正・校閲のプロ集団がどうとでもしますよ、どうですEさん?」
「だね。ノーベル文学賞だって、ベトナム戦争(1955~1975)以降は政治思想、戦争で命を張った作家にしか与えない。小手先の表現じゃ、相手にされない。小難しい純文表現の英訳には限界があるしね。思想信条で売らなきゃダメだ。平和ボケしてきた日本人作家には当分はムリ…」
このFの発言には皆が同意する。
発言がいっ周まわったところで、議長Aが、
「そんな作家、日本では居ないでしょう。再び中国、北朝鮮、ソビエトから侵略戦争をされない限り現われないんじゃないかな」
この発言にも皆が同意する。
「それじゃ、今年は今の世相を代表するように、作家自体の人生にスポットを当ててみましょうか。云わばアメリカンドリームの日本版みたいな…Japan as No1 でもあるわけですし」
「なるほど、ディスコサウンズみたいにノリノリでゆくわけですね」
若手のCはダメを押した。
「『獅鷲賞』にはまだ時間があるので次回以降また討議しましょう。
今日は別件で話し合う問題があります。それは国会で再販制度に、いちゃもんを付ける革新無所属の議員がいまして、取次各社からも何とか措置せよとの相談が相次いでおります」
Aはここで違う話題にふった。これも出版界に永遠に付き纏う課題。
「そいつは出版業界が我々大手6社と取次から出来てるって知ってるんかいな」
再販制度の話題になると俄然議論が白熱する。再販制度とは製造元である出版社と小売店である書店との間に問屋(取次会社と呼ぶ/大小10社ほどある)を噛ませることを言う。また、価格は絶対に弄れない。書籍には定価が存在する。勝手に安売りするのは法律違反となる。
でもこれは自由な価格競争を唱える規制撤廃論議に反するもの。戦後から幾度となく国会で議論されて来た。それでも規制が撤廃されないのは熱心なロビー活動、政治的癒着が隠れているとあて推量されてもおかしくはない。
そもそも再販制度保持の理由は、全国津々浦々の小売書店に最新の知識を配布するためのもの。地域差による知識の不平等の解消を狙った。憲法にも保証されている権利。確かに先の大戦直後の青森県龍飛崎周辺の小さな書店には「広辞苑」は行き届かなかった。
だが、今は話しが違う。書店のない西表島の住民も版元に電話をすれば「六法全書」も送って貰える。発端の理屈が有名無実化しつつある。だが、これを大っぴらにすれば現行法では罰則はないものの法律違反となる。二律背反が興っている。
また、別の観点から見てみる。書店も商売をしている。厚くて売り場面積の邪魔をする「広辞苑」「六法全書」は置かない。注文を受けてから取次から取り寄せればよい。
はてまた、好景気となれば書店間での競争も激化する。どこで買っても定価があるなら、このご時世ド派手なお洒落な店舗を選ぶし、利便性も考慮される。その最たるものが急速に小売業界に台頭して来たコンビニ。売れ筋の雑誌やコミックマンガはどこのコンビニでも置かれるようになった。
さらに、書店が頭を抱える問題として薄利が挙げられる。つまり再販制度の弊害で版元は取次(問屋)に0.7で卸し、取次は0.1を手数料として取り、書店に輸送する。なので書店の利益は0.2となる。書籍はおしなべて価格が安い。2割の利益じゃ薄利多売が原則となり、ちょっとしたことで経営難に陥る。万引きが横行して書店が潰れたなどのニュースもここに起因する。
ただ今の書店経営はこの再販制度に護られている側面もある。いちいち売れ筋を注文しなくても取次が売れる商品を選り好んで届けてくれる。この制度のことを指定配本と呼ぶ。今や書店で売れる商品と言えば、コミックと雑誌、いち部話題の書籍に限定される。そしてこの手の売れ筋を出版している版元は大手6社なのだ。
大手とは資本力から人気の作家を囲い込める。コミックしかり書籍もそう。また雑誌に至っては記事取材にやはり金がかかる。大手のじゃないと無理だ。それに新聞や雑誌に広告を出さなくてはならない。この理屈から、大手の寡占状態になっても致し方ない。
つまり万事都合の良い状態を長年保って来た。いつまでも競争の原則が入り込む余地がない。割を食うのは末端の購買客となる。未だに定価販売が法律で定められている商品は書籍と新聞、音楽CD以外にはない。いずれも高額ではないので文句が出ないのだろうか。それかジャーナリズムって奴が、自らの利権を保つ為に、異論を封じ込めているやもしれない。
「政府与党の〇先生に頼もうじゃないか。国会議員なんて選挙区の地盤あっての役職。その革新無所属の不満分子はお抱えの右翼や新興宗教〇会に頼んで黙らせてもらう」
早速、Fが反応する。全員が頷く。
「じゃ、〇先生には私の方から頼むことにします」
Aには戦後から固く護られて来た制度への揺るぎない自信があった。
※再販制度は現在でも脈々と維持されています。