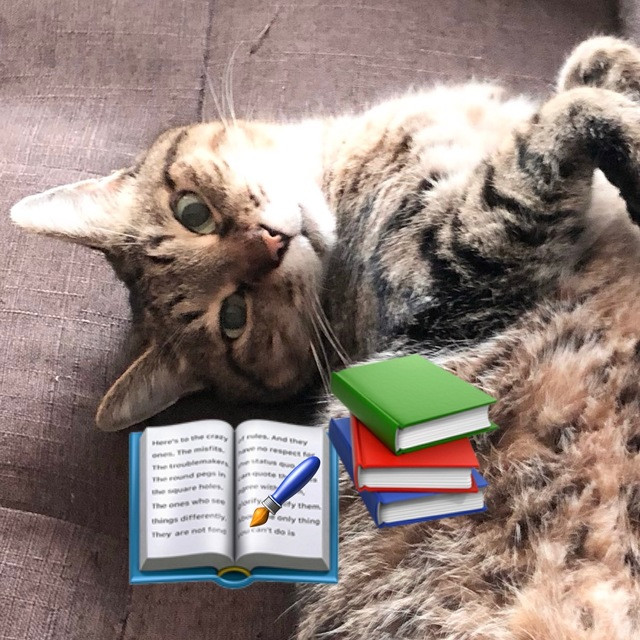第7話 行き場を失うホームレス
文字数 2,723文字
ここんとこ世間では金詰まりが起きていた。株価が1日で1万円近くも暴落し破産する俄か長者が増えた。著名人の中にも現れて来る。聖徳太子を両手で振りかざしていた輩が、まるでモグラ叩きゲームのように沈んでゆくのは観てて気持ちがよい。だけどそれもあまり続けば、あれまたか、となってしまう。従ってもはや特ダネとは呼ばれない。
入れ替わるように社会にはホームレスが溢れた。彼らは好景気のツケのようなもの。仕事が失くなった日雇い労働者たちが路上で暮らす。その中には俄か長者だったも者も含まれた。さらにもうひとパターン、端から狂乱の時代に便乗出来なかった人たち。
吉岡灯はホームレスの取材を始めた。バカげた時代の遺物、残骸、犠牲者との発想からだった。都内の大きな公園やら河川敷には何処にでも見られるが、中でも巨大な一集団は新宿西口の段ボール団地だろう。新宿駅西口から都庁に向う地下通路に一列に段ボールハウスが立てられていた。
ここである悲劇が興る。火災で四名が亡くなったのだ。詳しい原因は不明。段ボール内でのホームレスの火の不始末と片付けられた。だが憶測は拡がる。当時、段ボール団地の撤去を巡って住人と東京都との間でいざこざがあったからだ。
撤去に応じないホームレスへの嫌がらせ、いや殺人行為。噂はまことしやかに流れた。権力ある処には必ず反社との癒着が生じる。新宿の指定暴力団員にめこぼしの見返りに放火をそれとなく仄めかす。ありそうなことだ。
灯は早速、ホームレス団地の聞込みに回った。そこで知り合ったのが「教授」だった。彼の段ボールハウスには最新のコンピューターがあり、プログラムを駆使して集まるホームレスたちのいわば住民票を作っていた。
氏名、年齢、親族への連絡先、資産、飲食物の取得場所…最後には、遺書まで登録されていた。また当時では聞き慣れないアルゴリズム算法を用いて、行政の動きと支援団体の動きを予測していた。そこには嫌がらせ10件ののち強制排除処分、さらにこれに三度(みたび)繰り返し、この負の歴史はなかったものにされる、と結論づけられていた。
灯はこの人物に興味を持った。青白い顔のどこか病的な彼は物静かだった。彼には雄弁な同居人がいて、考えを代弁してくれた。二人とも身なりは薄汚れてはいるものの、何処にでもいそうな三十半ばの若者だった。
こいつは紅林正孝。〇大理学部大学院博士課程修了。研究課題は「アルゴリズム」論。夢は世界中のコンピューター同士を結び繋げること。そのための会社を起業し投資を募ったものの失敗。体調の悪化と共にここで暮らすようになった。因みにオレは株成金で、コイツに投資しようとしていた矢先に大暴落ですってんてんに。ここで偶然出会った。
「じゃ、やはり放火は行政の仕業?」
「そう考えても不思議ではない。ここの住民はたびたび空き缶瓶を投げつけられたり、ゴミを巻き散らかされたり、度重なる罵声にあっている。つまり目障りなんだよ。日本人は規律を重んじ規則正しい。社会にこんなデカいゴミがあっては世界に恥ずかしいと思うんだろうね…」
紹介にあずかった紅林正孝は消え入る様な小さな声で囁いた。
「…ここの住人は日本社会が作り上げた「金塊社会」「狂乱のどつぼ」のツケ、犠牲者たち。これが社会の在り様なんだよ。世界中どこにだってホームレスは居る。その人権を護ってこそ成熟した一流の社会と言える。隠していてはダメだ。認めて皆で救済しなくては…
今回計画されている大掛かりな強制排除は、潤った企業や市民からの所得税10億円で、動く舗道の建設設置を名目にしている。
けれど今にもっと安価な方法でホームレスを排除しようとするだろうね。しかも大衆にはそれと分からない方法で。例えばごつごつした石垣を作るとか、コンクリの針山を作るとか、その場所には住めないようにする…(これは今では「排除アート」と呼ばれる)」

激しく咳き込む正孝。
「アンタは何処かの大手メディアだよね。記事にして貰えないか、この現実を。ここ10年の好景気に現(うつつ)を抜かし奢り高ぶり、技術革新の時代への投資をほったらかしにし、大量のホームレスを産んだ。日本は大罪を犯した。この失態は必ず将来、日本社会の凋落を招く」
「もうその辺でやめとけや。コイツは肺が悪い。支援団体には医師も居るんだが、彼らは信用できないそうだ。支援団体自体も行政側が作ったものだし、また中には、便乗して名を挙げようとする者たちのも居るようだ」
灯も口だけの似非(えせ)正義にうんざりしていた。
ホームレスたちは声などあげない。撤去されれば大人しく出て行き、行政が去ればまた元に戻って来る。だって居場所がないんだから。ここが彼らの生業の場所。替わりにメディアで代弁するのは、口だけが達者な論客。そんな奴に限って1分たりともホームレスたちに話しを聞いたりもしない。
灯は取材に手応えを感じた。早速、社に戻って「週刊〇〇」のデスクに話す。3日後にデスクの上司にあたる編集局長の部屋に招かれた。コイツは書籍会館で談合していた、例のE社の代表。
「そりゃ、いいネタだ。君はその人から何かメモとか記事にする材料を貰ってないかね?」
五十絡みの白髪をオールバックにまとめ、当時流行の肩パット入りツータックパンツのスーツ姿、ダンディな編集局長は満面の笑顔で灯を見つめる。
「はい受け取ってますが、何か?」
灯は、教授こと紅林正孝がここ10年の世情を憂う、渾身の原稿を託されていた。あとはここにシュウさんが撮りためた写真を足せば立派な書物になると考えていた。段ボールハウスのホームレスの実情はマスコミ各社がすでに特集している。いまさら雑誌記事でもない。
「うん、世相を描いた書籍にしようと考えている。名前は『大罪』だ。その人物は〇大理学部出身、経歴も問題ない。印税は普通、出版半年後に支払うものだが、今回は特別にいま支払おうじゃないか? 幾らぐらいなら悦びそうかな?」
灯はざっと計算する。これは印税の先払い。原稿買取と呼ばれる手法。一見受けそうだが何万部のベストセラーとでもなれば損をする。灯はざっと計算してみる。印税で10%貰える人はいっぱしの作家たち。素人同然の作者は安く買い叩かれる。
定価1800円の単行本、印税一冊180円 × 2万部 =360万円。そう返事すると、
「どうだ。300万で手をうとうじゃないか。これでホームレスから脚を洗える。名も売れる。よい条件だと思うが、どうだい? というか君は我が社の立派な社員だ。それでまとめ上げて来るのが君の役割だな」
おっと、執行役員に注文つけられちまった。まぁ、知っちゃぁいないがね…。
入れ替わるように社会にはホームレスが溢れた。彼らは好景気のツケのようなもの。仕事が失くなった日雇い労働者たちが路上で暮らす。その中には俄か長者だったも者も含まれた。さらにもうひとパターン、端から狂乱の時代に便乗出来なかった人たち。
吉岡灯はホームレスの取材を始めた。バカげた時代の遺物、残骸、犠牲者との発想からだった。都内の大きな公園やら河川敷には何処にでも見られるが、中でも巨大な一集団は新宿西口の段ボール団地だろう。新宿駅西口から都庁に向う地下通路に一列に段ボールハウスが立てられていた。
ここである悲劇が興る。火災で四名が亡くなったのだ。詳しい原因は不明。段ボール内でのホームレスの火の不始末と片付けられた。だが憶測は拡がる。当時、段ボール団地の撤去を巡って住人と東京都との間でいざこざがあったからだ。
撤去に応じないホームレスへの嫌がらせ、いや殺人行為。噂はまことしやかに流れた。権力ある処には必ず反社との癒着が生じる。新宿の指定暴力団員にめこぼしの見返りに放火をそれとなく仄めかす。ありそうなことだ。
灯は早速、ホームレス団地の聞込みに回った。そこで知り合ったのが「教授」だった。彼の段ボールハウスには最新のコンピューターがあり、プログラムを駆使して集まるホームレスたちのいわば住民票を作っていた。
氏名、年齢、親族への連絡先、資産、飲食物の取得場所…最後には、遺書まで登録されていた。また当時では聞き慣れないアルゴリズム算法を用いて、行政の動きと支援団体の動きを予測していた。そこには嫌がらせ10件ののち強制排除処分、さらにこれに三度(みたび)繰り返し、この負の歴史はなかったものにされる、と結論づけられていた。
灯はこの人物に興味を持った。青白い顔のどこか病的な彼は物静かだった。彼には雄弁な同居人がいて、考えを代弁してくれた。二人とも身なりは薄汚れてはいるものの、何処にでもいそうな三十半ばの若者だった。
こいつは紅林正孝。〇大理学部大学院博士課程修了。研究課題は「アルゴリズム」論。夢は世界中のコンピューター同士を結び繋げること。そのための会社を起業し投資を募ったものの失敗。体調の悪化と共にここで暮らすようになった。因みにオレは株成金で、コイツに投資しようとしていた矢先に大暴落ですってんてんに。ここで偶然出会った。
「じゃ、やはり放火は行政の仕業?」
「そう考えても不思議ではない。ここの住民はたびたび空き缶瓶を投げつけられたり、ゴミを巻き散らかされたり、度重なる罵声にあっている。つまり目障りなんだよ。日本人は規律を重んじ規則正しい。社会にこんなデカいゴミがあっては世界に恥ずかしいと思うんだろうね…」
紹介にあずかった紅林正孝は消え入る様な小さな声で囁いた。
「…ここの住人は日本社会が作り上げた「金塊社会」「狂乱のどつぼ」のツケ、犠牲者たち。これが社会の在り様なんだよ。世界中どこにだってホームレスは居る。その人権を護ってこそ成熟した一流の社会と言える。隠していてはダメだ。認めて皆で救済しなくては…
今回計画されている大掛かりな強制排除は、潤った企業や市民からの所得税10億円で、動く舗道の建設設置を名目にしている。
けれど今にもっと安価な方法でホームレスを排除しようとするだろうね。しかも大衆にはそれと分からない方法で。例えばごつごつした石垣を作るとか、コンクリの針山を作るとか、その場所には住めないようにする…(これは今では「排除アート」と呼ばれる)」

激しく咳き込む正孝。
「アンタは何処かの大手メディアだよね。記事にして貰えないか、この現実を。ここ10年の好景気に現(うつつ)を抜かし奢り高ぶり、技術革新の時代への投資をほったらかしにし、大量のホームレスを産んだ。日本は大罪を犯した。この失態は必ず将来、日本社会の凋落を招く」
「もうその辺でやめとけや。コイツは肺が悪い。支援団体には医師も居るんだが、彼らは信用できないそうだ。支援団体自体も行政側が作ったものだし、また中には、便乗して名を挙げようとする者たちのも居るようだ」
灯も口だけの似非(えせ)正義にうんざりしていた。
ホームレスたちは声などあげない。撤去されれば大人しく出て行き、行政が去ればまた元に戻って来る。だって居場所がないんだから。ここが彼らの生業の場所。替わりにメディアで代弁するのは、口だけが達者な論客。そんな奴に限って1分たりともホームレスたちに話しを聞いたりもしない。
灯は取材に手応えを感じた。早速、社に戻って「週刊〇〇」のデスクに話す。3日後にデスクの上司にあたる編集局長の部屋に招かれた。コイツは書籍会館で談合していた、例のE社の代表。
「そりゃ、いいネタだ。君はその人から何かメモとか記事にする材料を貰ってないかね?」
五十絡みの白髪をオールバックにまとめ、当時流行の肩パット入りツータックパンツのスーツ姿、ダンディな編集局長は満面の笑顔で灯を見つめる。
「はい受け取ってますが、何か?」
灯は、教授こと紅林正孝がここ10年の世情を憂う、渾身の原稿を託されていた。あとはここにシュウさんが撮りためた写真を足せば立派な書物になると考えていた。段ボールハウスのホームレスの実情はマスコミ各社がすでに特集している。いまさら雑誌記事でもない。
「うん、世相を描いた書籍にしようと考えている。名前は『大罪』だ。その人物は〇大理学部出身、経歴も問題ない。印税は普通、出版半年後に支払うものだが、今回は特別にいま支払おうじゃないか? 幾らぐらいなら悦びそうかな?」
灯はざっと計算する。これは印税の先払い。原稿買取と呼ばれる手法。一見受けそうだが何万部のベストセラーとでもなれば損をする。灯はざっと計算してみる。印税で10%貰える人はいっぱしの作家たち。素人同然の作者は安く買い叩かれる。
定価1800円の単行本、印税一冊180円 × 2万部 =360万円。そう返事すると、
「どうだ。300万で手をうとうじゃないか。これでホームレスから脚を洗える。名も売れる。よい条件だと思うが、どうだい? というか君は我が社の立派な社員だ。それでまとめ上げて来るのが君の役割だな」
おっと、執行役員に注文つけられちまった。まぁ、知っちゃぁいないがね…。