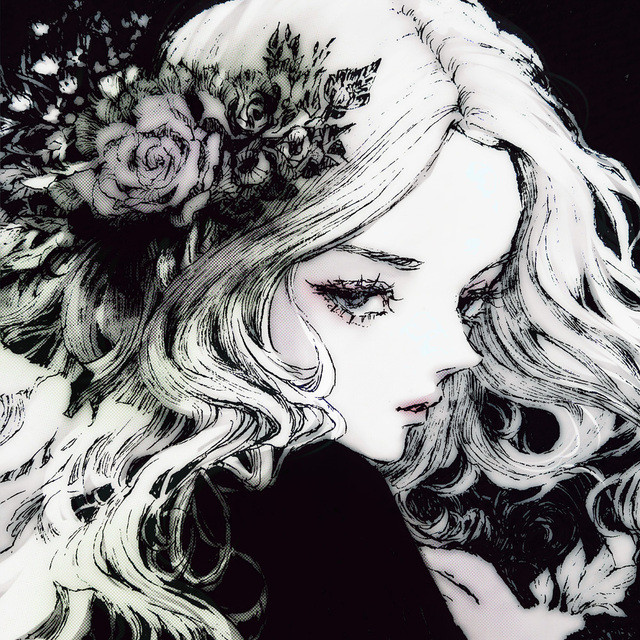第113話 貴族院の長の息子
文字数 2,998文字
その日、貴族院の長レナパルド公の館は、明るい声で包まれていた。
跡継ぎである長男オルセウスの婚約者ミリテアが、婚礼準備に訪れていることもあったが、何より珍しく、幼少のおりに王子の側近となって家を出た、次男のゼブリスルーンレイアが久しぶりに館を訪れたことが大きい。
ゼブリスルーンレイアは家ではゼブリス、城ではゼブラと親しく呼ばれ、家臣たちからも一目置かれて頼りない王子の右腕となってよく勤めている。
レナパルド家の誇りだ。
まだ母が恋しい年頃から家を出されたにもかかわらず、この年まで家には数えるほどしか帰ったことがない。
我慢強く、家のためによく働いているのが貴族院の長でもある父の自慢でもあった。
「ゼブリス、本当にお会い出来て嬉しいわ!
ほら、ご覧になって。小指にあとが残っているでしょう?
覚えておいでかしら?おそろいで作らせた指輪。私、お気に入りでしたのよ?」
「ああ、覚えているよ。子供の時の遊びで作ったね。まだ持ってるのかい?
僕はとうの昔に無くしてしまったよ。」
「まあ!ひどいわ。私は子供たちにゆずるの。決めてるのよ?」
「ははっ、たちって何人作るつもりだい?兄さんは愛されているね。」
機嫌の良い父と母を交え、皆で昼食を共にしたあと居間で兄とミリテアと3人でお茶を楽しんでいると、ゼブリスにミリテアが親しく話しかけてくる。
ミリテアは元々ゼブリスの許嫁で小さな頃はよく一緒に遊んでいた。
しかし、城に上がる予定だった兄は非常に不器用で、精神的にも、また身体も弱かったために、小さい頃からしっかり者で病気もあまりしなかったゼブリスが城に上がることになってしまったのだ。
父にしてみれば長男の急病に面目躍如だっただろうが、てっきり自分は家の跡継ぎだと思っていたゼブリスはそこから自由を失う事となり、たいそうショックだった。
「それでね、リリーナったら騎士のお3方に求婚されましたのよ。それもステキな方ばかり。」
「彼女は美しいからね。君には負けるけど。」
「キャッ!お上手ね、ゼブリス。
あなたも今度、社交の会にいらしたらいいのに。
あなたもステキだから、すぐに女の子が集まりますわよ。」
「それはいいね、考えておこう。」
楽しそうな二人に、傍で見ている兄のオルセウスは少々面白くない。
許嫁と言え、ミリテアはやはり自分よりもゼブリスの方が好きに見えて仕方ないのだ。
「私は仕事があるので失礼するよ。ゼブリス、お前はゆっくりしてゆくががいい。
ミリテア、私の部屋で婚儀の話をしようか。」
兄はカップを置いて立ち上がると、プイと部屋を出て行く。
ゼブリスはカップを置いて立ち上がり、軽く頭を下げた。
「兄上、お時間をいただきありがとうございました。」
「ゼブリス、またお会いしましょう。」
ミリテアは戸惑った様子で、ゼブリスの頬にキスをして慌ててあとを追っていく。
二人が消えて一人、静かな部屋で椅子にもたれて座り、窓から見える庭の景色に一息つく。
小さい頃の自分は、跡継ぎになるためしっかりしなければと一生懸命だった。
それが裏目に出るとは思いもしなかったが、あの頃は自由で毎日が楽しかった……
眼を閉じて、家の香りを胸一杯に吸ってみる。
小さな頃に良く聞いた、母の奏でるハープの音色がどこからか聞こえてくるような錯覚にとらわれ、頭を軽く振って笑った。
「久しぶりに、母上様にねだってみようかな……フフ……」
「ゼブリスルーンレイア様、御館様がお呼びでございます。」
「ああ、わかった。今行こうと思っていたんだ、丁度いい。」
執事に呼ばれて書斎へと向かう。
中へ入ると、部屋の片隅には間者に使っているミスリルのガウズが一人、ひざまずいていた。
「ゼブリス。お前の言うとおりであった。
赤い髪の子は巫子の許しを得に、レナントの騎士とこちらに向かっているそうだ。
お前も良い間者を持っているようだな。」
「はい、父上。私は、この事に大変憂慮しております。
巫子は位の高い者。しかもどんな地位の低い人間でも巫子であることは特殊であり、ドラゴンがそう訴えればたとえ王でも覆すことは難しいことです。
あの者はたいそう精霊に気に入られていると、ゲール殿も仰っておりました。
恐らくはそれを利用し、レナントの人々を丸め込んだのでしょう。」
ふむ、とレナパルド公が腕を組む。
すでに、あの赤い髪の子は自分こそが真の王位継承者だと知っている。
ならば、なんとしても奪還しようとするのは眼に見えているのだ。
使用人の身分に落とされた恨みもあるに違いない。
しかし、キアナルーサの失脚は我が子の失脚にも、そして我が家にも関係してくる。
あってはならないことだ。
「ガウズ、魔導師に敵う手練れを向かわせよ。
相手は15の小柄の少年だが、魔導師としては腕が立つ、しかもレナントの騎士が3人護衛に付いている。」
「15……まだ子供でございますな、ならば良いはぐれミスリルを存じております。
魔導はさておき、下働きの奴隷あがりであれば剣の腕はさっぱりでしょう。
で、見返りはいかほど。」
「そうさな、首と引き替えに金100枚とシリウスの星の指輪はどうか。」
シリウスの星とは、精霊達の好む霊力を持つ宝石だ。
それを持つ者は容易に精霊を配下に収め、魔導師でなくとも簡単な魔導を使える。
だが、力を使うごとに石の容量は減ってゆくので、過去に重宝されて今では非常に貴重な物となって滅多に見る物ではない。
「それは上々。ですが、赤い髪の子は相当の美形と聞き及びます、子供好きゆえ首は欲しがるかもしれません。」
「確かに死んだとわかればよい。
しかし子供好きなれば、よもやほだされる事はあるまいな。」
「くくっ、御館様、好きにも色々ございますので。アレはミスリルでも異端の者。闇落ちした精霊に近いミスリルです。ご期待に添えましょう。では」
後ろ手に窓を開け、ガウズが消える。
気味の悪さにゾッとしながら、公が立ち上がり美しい香水瓶のふたを開けて清めに中の聖水を窓に振りまく。
「汚らわしい物言いだが、下賤の者でも使いようだ。
ゼブリスルーンレイアよ、お前の願いはこの父がなんでも叶えよう。
お前は王子をお守りし、そして側近として地位を確立するのだ。
それがお前のためにも、そして我が家の繁栄にも繋がろう。」
「承知しております、父上。」
「お前は私の誇りだ。お前の働きは王にも覚えめでたい。
何か気にやむことがあれば、いつでも父に相談せよ。
ここはお前の家なのだ、遠慮のう来るがいい。」
公が息子を大きな手で抱きしめる。
まだ成人もしていない息子は、家を背負うには若すぎる。
一人、城で王子に仕えて頑張っている姿を時々見かけると、かけたくなる声をグッと飲み込んでいた。
そしてそれは、もちろんゼブリス自身も同じだったのだ。
父の姿を横目で追いながら、声もかけることも出来ず、わがままな王子にひたすら尽くしてきた。
「父上どうかご安心を。ゼブリスは王子が無事に王位継承なさるその時まで、全力で王子をお守りします。」
王子が王にならなければ、自分がこれまで尽くしてきたことはすべて水泡に帰する。
両親から離れ、許嫁をあきらめ、自由を捨ててひたすらやってきたのは、王子が王位継承者だからなのだ。
それが、まさかあんな下賤な奴隷風情が出てくるとは。
育ちの悪いあのような下卑た者が、なぜ登城を許されたのかわからない。
王の心変わりがあったのかも知れぬ。
許せない
絶対に
王子は、絶対に王にならねばならぬのだ。
跡継ぎである長男オルセウスの婚約者ミリテアが、婚礼準備に訪れていることもあったが、何より珍しく、幼少のおりに王子の側近となって家を出た、次男のゼブリスルーンレイアが久しぶりに館を訪れたことが大きい。
ゼブリスルーンレイアは家ではゼブリス、城ではゼブラと親しく呼ばれ、家臣たちからも一目置かれて頼りない王子の右腕となってよく勤めている。
レナパルド家の誇りだ。
まだ母が恋しい年頃から家を出されたにもかかわらず、この年まで家には数えるほどしか帰ったことがない。
我慢強く、家のためによく働いているのが貴族院の長でもある父の自慢でもあった。
「ゼブリス、本当にお会い出来て嬉しいわ!
ほら、ご覧になって。小指にあとが残っているでしょう?
覚えておいでかしら?おそろいで作らせた指輪。私、お気に入りでしたのよ?」
「ああ、覚えているよ。子供の時の遊びで作ったね。まだ持ってるのかい?
僕はとうの昔に無くしてしまったよ。」
「まあ!ひどいわ。私は子供たちにゆずるの。決めてるのよ?」
「ははっ、たちって何人作るつもりだい?兄さんは愛されているね。」
機嫌の良い父と母を交え、皆で昼食を共にしたあと居間で兄とミリテアと3人でお茶を楽しんでいると、ゼブリスにミリテアが親しく話しかけてくる。
ミリテアは元々ゼブリスの許嫁で小さな頃はよく一緒に遊んでいた。
しかし、城に上がる予定だった兄は非常に不器用で、精神的にも、また身体も弱かったために、小さい頃からしっかり者で病気もあまりしなかったゼブリスが城に上がることになってしまったのだ。
父にしてみれば長男の急病に面目躍如だっただろうが、てっきり自分は家の跡継ぎだと思っていたゼブリスはそこから自由を失う事となり、たいそうショックだった。
「それでね、リリーナったら騎士のお3方に求婚されましたのよ。それもステキな方ばかり。」
「彼女は美しいからね。君には負けるけど。」
「キャッ!お上手ね、ゼブリス。
あなたも今度、社交の会にいらしたらいいのに。
あなたもステキだから、すぐに女の子が集まりますわよ。」
「それはいいね、考えておこう。」
楽しそうな二人に、傍で見ている兄のオルセウスは少々面白くない。
許嫁と言え、ミリテアはやはり自分よりもゼブリスの方が好きに見えて仕方ないのだ。
「私は仕事があるので失礼するよ。ゼブリス、お前はゆっくりしてゆくががいい。
ミリテア、私の部屋で婚儀の話をしようか。」
兄はカップを置いて立ち上がると、プイと部屋を出て行く。
ゼブリスはカップを置いて立ち上がり、軽く頭を下げた。
「兄上、お時間をいただきありがとうございました。」
「ゼブリス、またお会いしましょう。」
ミリテアは戸惑った様子で、ゼブリスの頬にキスをして慌ててあとを追っていく。
二人が消えて一人、静かな部屋で椅子にもたれて座り、窓から見える庭の景色に一息つく。
小さい頃の自分は、跡継ぎになるためしっかりしなければと一生懸命だった。
それが裏目に出るとは思いもしなかったが、あの頃は自由で毎日が楽しかった……
眼を閉じて、家の香りを胸一杯に吸ってみる。
小さな頃に良く聞いた、母の奏でるハープの音色がどこからか聞こえてくるような錯覚にとらわれ、頭を軽く振って笑った。
「久しぶりに、母上様にねだってみようかな……フフ……」
「ゼブリスルーンレイア様、御館様がお呼びでございます。」
「ああ、わかった。今行こうと思っていたんだ、丁度いい。」
執事に呼ばれて書斎へと向かう。
中へ入ると、部屋の片隅には間者に使っているミスリルのガウズが一人、ひざまずいていた。
「ゼブリス。お前の言うとおりであった。
赤い髪の子は巫子の許しを得に、レナントの騎士とこちらに向かっているそうだ。
お前も良い間者を持っているようだな。」
「はい、父上。私は、この事に大変憂慮しております。
巫子は位の高い者。しかもどんな地位の低い人間でも巫子であることは特殊であり、ドラゴンがそう訴えればたとえ王でも覆すことは難しいことです。
あの者はたいそう精霊に気に入られていると、ゲール殿も仰っておりました。
恐らくはそれを利用し、レナントの人々を丸め込んだのでしょう。」
ふむ、とレナパルド公が腕を組む。
すでに、あの赤い髪の子は自分こそが真の王位継承者だと知っている。
ならば、なんとしても奪還しようとするのは眼に見えているのだ。
使用人の身分に落とされた恨みもあるに違いない。
しかし、キアナルーサの失脚は我が子の失脚にも、そして我が家にも関係してくる。
あってはならないことだ。
「ガウズ、魔導師に敵う手練れを向かわせよ。
相手は15の小柄の少年だが、魔導師としては腕が立つ、しかもレナントの騎士が3人護衛に付いている。」
「15……まだ子供でございますな、ならば良いはぐれミスリルを存じております。
魔導はさておき、下働きの奴隷あがりであれば剣の腕はさっぱりでしょう。
で、見返りはいかほど。」
「そうさな、首と引き替えに金100枚とシリウスの星の指輪はどうか。」
シリウスの星とは、精霊達の好む霊力を持つ宝石だ。
それを持つ者は容易に精霊を配下に収め、魔導師でなくとも簡単な魔導を使える。
だが、力を使うごとに石の容量は減ってゆくので、過去に重宝されて今では非常に貴重な物となって滅多に見る物ではない。
「それは上々。ですが、赤い髪の子は相当の美形と聞き及びます、子供好きゆえ首は欲しがるかもしれません。」
「確かに死んだとわかればよい。
しかし子供好きなれば、よもやほだされる事はあるまいな。」
「くくっ、御館様、好きにも色々ございますので。アレはミスリルでも異端の者。闇落ちした精霊に近いミスリルです。ご期待に添えましょう。では」
後ろ手に窓を開け、ガウズが消える。
気味の悪さにゾッとしながら、公が立ち上がり美しい香水瓶のふたを開けて清めに中の聖水を窓に振りまく。
「汚らわしい物言いだが、下賤の者でも使いようだ。
ゼブリスルーンレイアよ、お前の願いはこの父がなんでも叶えよう。
お前は王子をお守りし、そして側近として地位を確立するのだ。
それがお前のためにも、そして我が家の繁栄にも繋がろう。」
「承知しております、父上。」
「お前は私の誇りだ。お前の働きは王にも覚えめでたい。
何か気にやむことがあれば、いつでも父に相談せよ。
ここはお前の家なのだ、遠慮のう来るがいい。」
公が息子を大きな手で抱きしめる。
まだ成人もしていない息子は、家を背負うには若すぎる。
一人、城で王子に仕えて頑張っている姿を時々見かけると、かけたくなる声をグッと飲み込んでいた。
そしてそれは、もちろんゼブリス自身も同じだったのだ。
父の姿を横目で追いながら、声もかけることも出来ず、わがままな王子にひたすら尽くしてきた。
「父上どうかご安心を。ゼブリスは王子が無事に王位継承なさるその時まで、全力で王子をお守りします。」
王子が王にならなければ、自分がこれまで尽くしてきたことはすべて水泡に帰する。
両親から離れ、許嫁をあきらめ、自由を捨ててひたすらやってきたのは、王子が王位継承者だからなのだ。
それが、まさかあんな下賤な奴隷風情が出てくるとは。
育ちの悪いあのような下卑た者が、なぜ登城を許されたのかわからない。
王の心変わりがあったのかも知れぬ。
許せない
絶対に
王子は、絶対に王にならねばならぬのだ。