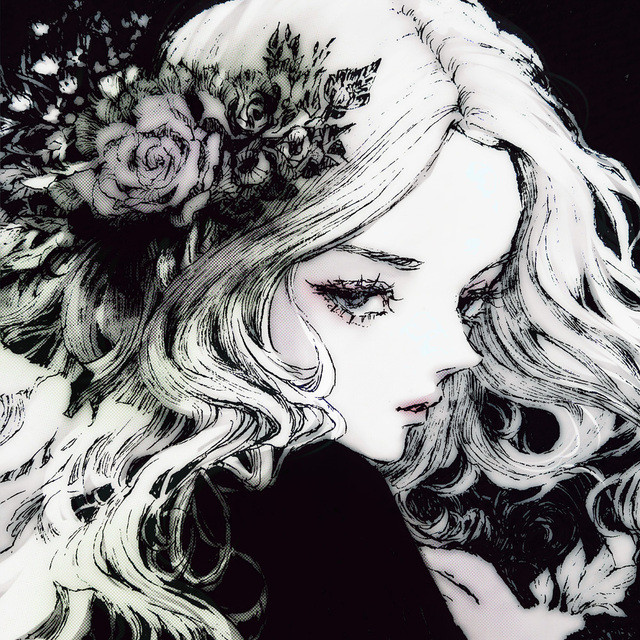第205話 ほこらの中
文字数 2,460文字
「ああああ……」
キアナルーサが、頭を押さえてよろめき地に倒れ込んだ。
「違う、違う、違うんだ、ゼブラ、ゼブラ、違うんだ。
僕じゃない、僕じゃない、許してくれ。」
恐怖に震える身体を小さく丸めて頭をかきむしり、大きく息をつくと顔を上げてようやく這うようにしてほこらにすがりついた。
「ううう……邪魔だ、邪魔だ、軟弱な物などいらぬ。
我は、我は、取り戻すのだ、この城を。
この国を。」
ブツブツつぶやきながら、狂ったようにツタを取り払う。そしてまるで小さな石棺のようなほこらの石を退け始めた。
だが、百合の紋章の入ったフタのような石はビクとも動かない。
確かに石で重いだろうが、1人で動かせない大きさでは無い。なのにガタリともしないのだ。
「おのれ、ヴァシュラムめ。
だがこの身体が誰と血を分けたか忘れたか?」
腰から剣を抜き、腕を一息に切った。
痛みに顔を歪め、したたる血を百合の紋章に落とす。
百合の紋章は血に染まり、なぜか石に刻まれたそれが揺らめいて見えた。
ビシッ!
ビシッ!ビシッ!
紋章が輝き、そこから一斉に石の表面にヒビが入る。
そして次の瞬間、百合の紋章はシュンと小さな音を立てて煙を出して消え、フタになっている石は中にバラバラと音を立て崩れ落ちた。
「くくく、やった、やったぞ。それで無くてはこの身体を手に入れた意味が無い。
結界を破るのは巫子の血が手っ取り早い。
こんな出来損ないでも双子なのだ。
そっくり同じでは無いが、ほんの少しでも気が混じっていればと望みを託したが、やはり思った通りだった。
魔導師が毎日補強していても、巫子でなければ意味が無い。すでに弱った封印など、この身体の血で十分よ。
フフフ……この剣があれば、こんな軟弱な王子の意識など完全に消し去れる。
さあ、忌まわしき火の巫子を殺した剣よ、我が手に帰るがいい!」
首のスカーフで切った腕を縛り、ほこらを覗き込む。
中は外から見るよりなぜか結構深く、ふちから懸命に手を伸ばす。
そして崩れ落ちた石を退け、長い年月ですっかり色の変わった麻の包みを握った。
その重み、手の感触は確かに懐かしささえ覚える自分の剣。
だが、持ち上げようとした瞬間、突然ほこらの中が緑色に輝き、白く華奢な手が伸びてその包みをグッと掴んだ。
「な、なんだ?なんだこの手は?ええい、離せ!」
グイと引いてもビクともしない。
ほこらはなぜか底が抜けたようで、離せば緑の光の中に吸い込まれそうな不安感に襲われる。
そしてその緑の輝きは、濁った彼の魂さえ浄化しそうなほど清浄で彼にとって不快な物だった。
「この手!まさか?地の者か!」
渾身の力で引くと、その腕がズルズルほこらから伸びてくる。
やがて腕の持ち主の顔が揺らめいて、光の中に現れた。
その忘れようも無い、息を飲むほど整った美しい顔。
水の中から現れたように、濡れた金の髪が頬に張り付き、唇が薄く開くとめまいがする。
遙か昔に数回見ただけというのに、心に刻まれるような緑の宝石のような眼差し。
「ま、まさか!ガラリア?!貴様も迷ったか!
い、いや、違う、この手は?この手は実体か?まさか……」
冷や汗を流しながら、苦し紛れにガラリアにニッと不気味に笑う。
手元から石を一つ取り、ガラリアの手にギリギリと押しつけ、そして何度も打ち付けた。
「下賤な花売りが!ヴァシュラムをたらし込んで生き延びたか!
くくく、だがお前に何が出来ようか。
なんの力も無いお前が出来る事は、せいぜい身体を売ることぐらいだ!
汚れた手で触るな、離せ!
それとも、この俺に抱いて欲しいと申すか?
そうか、そうだ思い出したぞ。
あの時は邪魔が入ったのだったな、くくく……
そうか、なれば城に来るがいい。その朽ちぬ身体、どのような物か俺が確かめてやる。くっくっく」
石で何度も叩かれ、包みを掴むガラリアの白い手が血も流さずつぶれていく。
ガラリアは王子の顔をしたその相手を、見開いた目で見つめながら、緑の揺らめきの中で変わらず形の美しい唇を動かした。
『されば、心して待つがよい』
揺らぐ涼やかな声が響き、ガラリアの手が緑のツタになって包みに巻き付いて行く。
「なにっ!馬鹿な!」
慌てて落ちていたキアナルーサの剣を足で引き寄せて取り、包みを引き上げて緑のツタとなったガラリアの腕を、包みの下で何度も切りつけて断ち切った。
切れた瞬間反動で、包みを持ったまま後ろにひっくり返る。
急ぎ身を起こして、ほこらを覗くと光が消えて石の底が見えている。
ツタになったガラリアの手は、一瞬輝くと灰のように白くなり、もろく崩れて一陣の風に吹かれ散っていった。
「くくく、馬鹿め!やった、これは俺の剣だ!
これがあればこの身体完全に手にする事が出来る。
さあ、俺の剣よ、力を貸せ!」
さっそく包みを開き、懐かしい剣を手にする。
ズシンと響く、黒く渦巻くようなこの念。
柄の頭にある大きな毒々しい赤い宝石を、こみ上げる懐かしさに思わずなでた。
心地よさに、ああ……と感嘆の息を漏らしながら、さっそく柄を持ち剣を抜こうと力を入れる。
が、
抜けない。
「くっ、くそっ!くそっ!くそっ!くそっ!くそうっ!」
どんなに力を入れてもビクともしない。
サビでは無い、この呪いの剣からは力を感じる。
だが、どうやっても抜けない。
「まさか……ガラリアは巫子でも無い、ただの飾りだったはずだ。」
血に濡れたスカーフを取り、傷を開いて鞘に血を塗り込む。
だが、今度は血が蒸発して消え、消える瞬間鞘に微かに百合の紋章が輝いて消えた。
「こいつの血では弱い、封印の強さに負ける。
おのれ……ガラリア、長い時の間に力を得たか……だが、たかが偽巫子の付け焼き刃。
すぐに剣を抜いてやるぞ、こちらにはもう一つコマがあるのだ。
お前の子を飲み込んだ聖なる火、試す価値はあろう。いざとなったら巫子を殺して血を手に入れるまで。」
垣根の向こうで兵の気配がする。
見回りが回ってきたのだろう。
王子はキアナルーサの剣と腰にある鞘を抜いて森へ向けて投げ捨てると、ほこらにあった剣を腰に差し、見つからないよう身を潜ませそっと戻っていった。
*花売りとは売春婦のことです。
キアナルーサが、頭を押さえてよろめき地に倒れ込んだ。
「違う、違う、違うんだ、ゼブラ、ゼブラ、違うんだ。
僕じゃない、僕じゃない、許してくれ。」
恐怖に震える身体を小さく丸めて頭をかきむしり、大きく息をつくと顔を上げてようやく這うようにしてほこらにすがりついた。
「ううう……邪魔だ、邪魔だ、軟弱な物などいらぬ。
我は、我は、取り戻すのだ、この城を。
この国を。」
ブツブツつぶやきながら、狂ったようにツタを取り払う。そしてまるで小さな石棺のようなほこらの石を退け始めた。
だが、百合の紋章の入ったフタのような石はビクとも動かない。
確かに石で重いだろうが、1人で動かせない大きさでは無い。なのにガタリともしないのだ。
「おのれ、ヴァシュラムめ。
だがこの身体が誰と血を分けたか忘れたか?」
腰から剣を抜き、腕を一息に切った。
痛みに顔を歪め、したたる血を百合の紋章に落とす。
百合の紋章は血に染まり、なぜか石に刻まれたそれが揺らめいて見えた。
ビシッ!
ビシッ!ビシッ!
紋章が輝き、そこから一斉に石の表面にヒビが入る。
そして次の瞬間、百合の紋章はシュンと小さな音を立てて煙を出して消え、フタになっている石は中にバラバラと音を立て崩れ落ちた。
「くくく、やった、やったぞ。それで無くてはこの身体を手に入れた意味が無い。
結界を破るのは巫子の血が手っ取り早い。
こんな出来損ないでも双子なのだ。
そっくり同じでは無いが、ほんの少しでも気が混じっていればと望みを託したが、やはり思った通りだった。
魔導師が毎日補強していても、巫子でなければ意味が無い。すでに弱った封印など、この身体の血で十分よ。
フフフ……この剣があれば、こんな軟弱な王子の意識など完全に消し去れる。
さあ、忌まわしき火の巫子を殺した剣よ、我が手に帰るがいい!」
首のスカーフで切った腕を縛り、ほこらを覗き込む。
中は外から見るよりなぜか結構深く、ふちから懸命に手を伸ばす。
そして崩れ落ちた石を退け、長い年月ですっかり色の変わった麻の包みを握った。
その重み、手の感触は確かに懐かしささえ覚える自分の剣。
だが、持ち上げようとした瞬間、突然ほこらの中が緑色に輝き、白く華奢な手が伸びてその包みをグッと掴んだ。
「な、なんだ?なんだこの手は?ええい、離せ!」
グイと引いてもビクともしない。
ほこらはなぜか底が抜けたようで、離せば緑の光の中に吸い込まれそうな不安感に襲われる。
そしてその緑の輝きは、濁った彼の魂さえ浄化しそうなほど清浄で彼にとって不快な物だった。
「この手!まさか?地の者か!」
渾身の力で引くと、その腕がズルズルほこらから伸びてくる。
やがて腕の持ち主の顔が揺らめいて、光の中に現れた。
その忘れようも無い、息を飲むほど整った美しい顔。
水の中から現れたように、濡れた金の髪が頬に張り付き、唇が薄く開くとめまいがする。
遙か昔に数回見ただけというのに、心に刻まれるような緑の宝石のような眼差し。
「ま、まさか!ガラリア?!貴様も迷ったか!
い、いや、違う、この手は?この手は実体か?まさか……」
冷や汗を流しながら、苦し紛れにガラリアにニッと不気味に笑う。
手元から石を一つ取り、ガラリアの手にギリギリと押しつけ、そして何度も打ち付けた。
「下賤な花売りが!ヴァシュラムをたらし込んで生き延びたか!
くくく、だがお前に何が出来ようか。
なんの力も無いお前が出来る事は、せいぜい身体を売ることぐらいだ!
汚れた手で触るな、離せ!
それとも、この俺に抱いて欲しいと申すか?
そうか、そうだ思い出したぞ。
あの時は邪魔が入ったのだったな、くくく……
そうか、なれば城に来るがいい。その朽ちぬ身体、どのような物か俺が確かめてやる。くっくっく」
石で何度も叩かれ、包みを掴むガラリアの白い手が血も流さずつぶれていく。
ガラリアは王子の顔をしたその相手を、見開いた目で見つめながら、緑の揺らめきの中で変わらず形の美しい唇を動かした。
『されば、心して待つがよい』
揺らぐ涼やかな声が響き、ガラリアの手が緑のツタになって包みに巻き付いて行く。
「なにっ!馬鹿な!」
慌てて落ちていたキアナルーサの剣を足で引き寄せて取り、包みを引き上げて緑のツタとなったガラリアの腕を、包みの下で何度も切りつけて断ち切った。
切れた瞬間反動で、包みを持ったまま後ろにひっくり返る。
急ぎ身を起こして、ほこらを覗くと光が消えて石の底が見えている。
ツタになったガラリアの手は、一瞬輝くと灰のように白くなり、もろく崩れて一陣の風に吹かれ散っていった。
「くくく、馬鹿め!やった、これは俺の剣だ!
これがあればこの身体完全に手にする事が出来る。
さあ、俺の剣よ、力を貸せ!」
さっそく包みを開き、懐かしい剣を手にする。
ズシンと響く、黒く渦巻くようなこの念。
柄の頭にある大きな毒々しい赤い宝石を、こみ上げる懐かしさに思わずなでた。
心地よさに、ああ……と感嘆の息を漏らしながら、さっそく柄を持ち剣を抜こうと力を入れる。
が、
抜けない。
「くっ、くそっ!くそっ!くそっ!くそっ!くそうっ!」
どんなに力を入れてもビクともしない。
サビでは無い、この呪いの剣からは力を感じる。
だが、どうやっても抜けない。
「まさか……ガラリアは巫子でも無い、ただの飾りだったはずだ。」
血に濡れたスカーフを取り、傷を開いて鞘に血を塗り込む。
だが、今度は血が蒸発して消え、消える瞬間鞘に微かに百合の紋章が輝いて消えた。
「こいつの血では弱い、封印の強さに負ける。
おのれ……ガラリア、長い時の間に力を得たか……だが、たかが偽巫子の付け焼き刃。
すぐに剣を抜いてやるぞ、こちらにはもう一つコマがあるのだ。
お前の子を飲み込んだ聖なる火、試す価値はあろう。いざとなったら巫子を殺して血を手に入れるまで。」
垣根の向こうで兵の気配がする。
見回りが回ってきたのだろう。
王子はキアナルーサの剣と腰にある鞘を抜いて森へ向けて投げ捨てると、ほこらにあった剣を腰に差し、見つからないよう身を潜ませそっと戻っていった。
*花売りとは売春婦のことです。