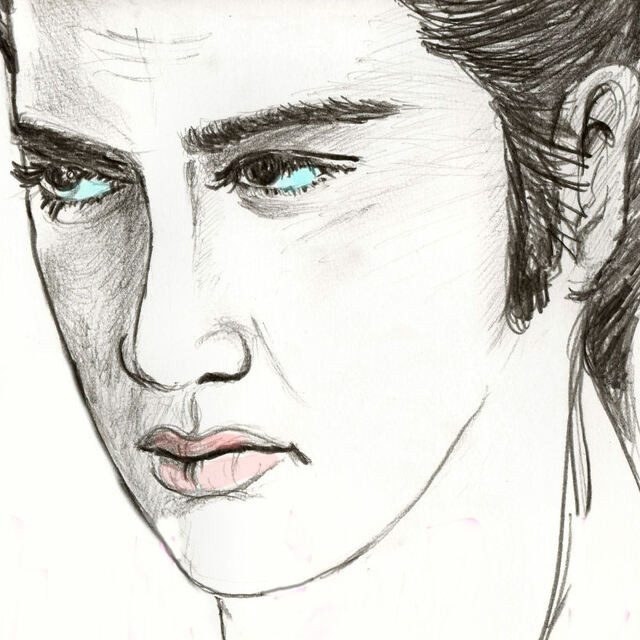第20話 最後の救助
文字数 3,289文字
警備隊のベテランのウイリアムの救難ヘリコプターは、相棒のアダムと共に遭難したローズ・プリンセス号の現場に近づいていた。その時刻は夕方にはなっていたが、幸運にもその日の天候は比較的穏やかだった、普通は船が遭難する時は、その日の天候が荒れていたりと厳しい時が多かった。故に、ウィリアムにはこの穏やかな地中海沖で客船が遭難することは、あまり経験がない。
救難のケースとして今までには、地震による津波の影響だったり、強風が吹いてるときが多かったが、それ意外には大きな事故は起きていない。船自身の故障の場合は比較的起きることがある。その他としては、船が浅瀬に乗り上げたりして座礁する場合が考えられる。
その日の夕刻は、海面に照らされたサーチライトの下で木の葉のように三艘の救命ボートが浮かんでいた。ボートの上では乗客がヘリコプターに向かって大きく手を振っている。早く救助してくれと言うサインだろう。海はもう相当冷え込んでいるはずだ、一刻も猶予はない。
ヘリコプターの中でウィリアムは、操縦桿を握りながら慎重にボートの真上の約二〇メートル程の高さでホバリングを続けていた。余り下に近づき過ぎると、ヘリコプターのブレードによる回転風により波が荒れて、ボートが揺れて危険である。
救命ボートの動きに合わせ、高さを一定にしたホバリングを確保しながら、横揺れに対する微調整をしなければならない、それに無いと言っても風は吹いている、その微調整も必要だ。また地上にいる遭難者を救助する場合と違って標的が揺れ動く。これらの作業は両手足を駆使し、少しの距離を操作しなければならない神業でもある。救助の時にはこの瞬間がいちばん緊張するのだ。
遭難した客船の上空でヘリを慎重に静止させ、その位置からピンポイントで救難員をロープで吊り下げて降ろし、遭難者を抱きかかえて救助をしなければならない。ホバリングは、ロープから吊り下ろした救助隊員の機敏な動きにも影響される、それはパイロットと救助隊員との連携が不可欠なのだ。その時間は夕方で暗闇に包まれており、サーチライトや暗視装置がなければ救助が困難になる、幸いにもこの救難ヘリコプターはそれらを有しているが、安心はできない。
更に問題が一つある。それは一度に救助できる人数に制限あるからだ。この手の救難ヘリの場合には最大一〇名程度であり、もしその中に怪我をした人や横になって運ばなければならない病人がいる場合には更に少なくなる。
この三艘のボートには約全部で三〇〇数一〇名が乗っており、これらの遭難者を一度で救助することは出来ない。目的地で遭難者を降ろし、再び戻ってくると言う気の遠くなるような作業が待っているのだ。その為には大量の動員が必要になる。しかし、既に客船事務所からは、乗員並びに乗客の人数は知らされており、その対策は練られていた。
その遭難場所を目指して次々と救難ヘリコプターは飛んでいった。さらに海上からは何艘かの救難艇が救助に向かっていた。
それは海と空からの大規模な救難活動である。時間とともに、ボートの乗客及び乗員達は次々とヘリコプターや救難艇に救助されて、陸地で待つ救急車で病院に運ばれていった。
実際には救難ヘリコプターで救助される前に、ボートに乗れなかった人物がいた。それはあのローズ・プリンセス号の船長のクラークとマーチン機関長だった、彼等二人は客船が沈没した時に流れてきた板の上にかじりついて助かった。
二人は責任ある立場として最後まで船に残って指揮をしていた。客船を回り取り残された乗客がいないか、 或いはまだ救える乗員はいないかと声を張り上げて見回っていた、それは自分の命さえ顧みない男の宿命でもある。
クラークとマーチンの二人ともその年齢になってみれば、この危機に向かって今更ながら生き延びようとは思っていなかったし、最後まで自分の仕事をすることこそ天命だと思ったからである。マーチン機関長は、秋には子供が産まれる予定の三等機関士のジェームスの骨折した腕を庇いながらボートに乗せたし、機関室の職場を死守しようとしている部下達をいち早く逃がした。
そして最後を見届けた時には、九死に一生を得るほどの危機か迫っていたが、溺れそうになりながら流れ着いてきた板に掴まり何とか助かった。その板で偶然、船長のクラークも助けられて海に浮かんでいた。
「あぁ、クラーク船長も」
「マーチン機関長もよく無事で」
二人はびしょ濡れになりながら海面に浮かぶ小板で再会した。
「申し訳ないマーチン、私の管理が万全ではなかったようだ」
「そんなことはありませんよ、クラーク船長。これは私達がもっと早く気が付いておくべきでした」
「そうだね、お互いがもう少し慎重にならなければ……ということかな」
二人は顔を見合わせて苦笑した。
「もうよそう、この話は、いずれ海難審判で原因が明らかになるでしょう」
「そうですね、船長」
「その罪を償う為に私はもう少し頑張らなければ、乗員達の名誉の為にも」
「私も同罪ですよ、潔く裁判を受け、この歳になって罪を償うつもりです」
「ありがとう、マーチン」
二人の男は海の上で板きれ一枚の上で手を取り合い泣いていた。クラークは、後一日で、晴れて船長を引退し、悠々自適に送る隠退生活を夢見ていたのだが、それは少し遠のいたようである。それはマーチンも同じだった。この二人のお陰で乗員の多くが命拾いをした。その中に食堂の見習い日本人コックの吾妻涼太と、彼を愛するマリアンもいた。
暫くして、その土地の病院に収容された中に佐々木明子がいた。ベッドの中で点滴を受けていたが、その顔は明るかった。彼女の話の相手は及川龍平である。
「ねえ、龍平さん」
「何かな明子?」
「ありがとう、助けて貰って」
「バカだな、当たり前だろう、婚約者だし」
「でも、嬉しいの、命を与えて貰ってこんなに生きることが素晴らしいって思ったこと無いわ」
「そうだね、本当に死ぬかと思ったけれど、僕たち運が良かったね」
「ええ、私もそう思うわ」
「明子、秋の結婚式までには身体を治しておこうね」
「ええ、龍平さんがいれば、心強いわ」
その時に病室のドアをノックする音が聞こえた。
「誰だろう?」
「どうぞ、お入り下さい」
そこに花束を持っていたのは、同じ病院で治療を終えた藤崎夫婦だった。
「あっ、藤崎さん!」
「お邪魔して宜しいですかな」
「ええ、どうぞどうぞ、奥さまお身体は大丈夫ですか?」
「はい、もう何とか元気になりました、これもあなた達のお陰ですよ」
「それは良かったです、ずっと心配していましたから」
「あの、お二人は秋に結婚する予定でしたね」
「はい、憶えてくれていたのですね」
「勿論ですとも、それで一つお願いが……」
「はい、何でしょうか、藤崎さん」
「もし、帰国してからですが、宜しければ、お二人のご結婚式に……」
「えっ? 出て下さる、とか……ですか?」
「ええ、差し出がましいのですが」
「勿論、喜んで、こちらこそお願い致します」
「有り難うございます、こちらで買った花ですが、気晴らしにと思いましてね」
「わぁ、綺麗ですね、素敵です、有り難うございました、藤崎さん」
「良かったね、喜んで頂いて、晴子」
「はい、パパ」
その病室には、地中海の美しい可憐な花を咲かせるスミレの花束があった。何とも良い花の放つ香りが二人の将来を祝福しているようである。
あの日、ローズ・プリンセス号の船長のクラークを待っていた客船船長のブラウンはクラークが死んでいなかったことを知らされた。
(良かったねクラーク、無事で生きていて本当に良かった。君にはこれから色々大変なことが待っているだろうが、私も出来るだけ君を応援するから頑張ってくれたまえ。君にはその覚悟があるはずだ、待っている!)
彼は既に船長を辞職したがクラークと再会することを願っていた。
了
救難のケースとして今までには、地震による津波の影響だったり、強風が吹いてるときが多かったが、それ意外には大きな事故は起きていない。船自身の故障の場合は比較的起きることがある。その他としては、船が浅瀬に乗り上げたりして座礁する場合が考えられる。
その日の夕刻は、海面に照らされたサーチライトの下で木の葉のように三艘の救命ボートが浮かんでいた。ボートの上では乗客がヘリコプターに向かって大きく手を振っている。早く救助してくれと言うサインだろう。海はもう相当冷え込んでいるはずだ、一刻も猶予はない。
ヘリコプターの中でウィリアムは、操縦桿を握りながら慎重にボートの真上の約二〇メートル程の高さでホバリングを続けていた。余り下に近づき過ぎると、ヘリコプターのブレードによる回転風により波が荒れて、ボートが揺れて危険である。
救命ボートの動きに合わせ、高さを一定にしたホバリングを確保しながら、横揺れに対する微調整をしなければならない、それに無いと言っても風は吹いている、その微調整も必要だ。また地上にいる遭難者を救助する場合と違って標的が揺れ動く。これらの作業は両手足を駆使し、少しの距離を操作しなければならない神業でもある。救助の時にはこの瞬間がいちばん緊張するのだ。
遭難した客船の上空でヘリを慎重に静止させ、その位置からピンポイントで救難員をロープで吊り下げて降ろし、遭難者を抱きかかえて救助をしなければならない。ホバリングは、ロープから吊り下ろした救助隊員の機敏な動きにも影響される、それはパイロットと救助隊員との連携が不可欠なのだ。その時間は夕方で暗闇に包まれており、サーチライトや暗視装置がなければ救助が困難になる、幸いにもこの救難ヘリコプターはそれらを有しているが、安心はできない。
更に問題が一つある。それは一度に救助できる人数に制限あるからだ。この手の救難ヘリの場合には最大一〇名程度であり、もしその中に怪我をした人や横になって運ばなければならない病人がいる場合には更に少なくなる。
この三艘のボートには約全部で三〇〇数一〇名が乗っており、これらの遭難者を一度で救助することは出来ない。目的地で遭難者を降ろし、再び戻ってくると言う気の遠くなるような作業が待っているのだ。その為には大量の動員が必要になる。しかし、既に客船事務所からは、乗員並びに乗客の人数は知らされており、その対策は練られていた。
その遭難場所を目指して次々と救難ヘリコプターは飛んでいった。さらに海上からは何艘かの救難艇が救助に向かっていた。
それは海と空からの大規模な救難活動である。時間とともに、ボートの乗客及び乗員達は次々とヘリコプターや救難艇に救助されて、陸地で待つ救急車で病院に運ばれていった。
実際には救難ヘリコプターで救助される前に、ボートに乗れなかった人物がいた。それはあのローズ・プリンセス号の船長のクラークとマーチン機関長だった、彼等二人は客船が沈没した時に流れてきた板の上にかじりついて助かった。
二人は責任ある立場として最後まで船に残って指揮をしていた。客船を回り取り残された乗客がいないか、 或いはまだ救える乗員はいないかと声を張り上げて見回っていた、それは自分の命さえ顧みない男の宿命でもある。
クラークとマーチンの二人ともその年齢になってみれば、この危機に向かって今更ながら生き延びようとは思っていなかったし、最後まで自分の仕事をすることこそ天命だと思ったからである。マーチン機関長は、秋には子供が産まれる予定の三等機関士のジェームスの骨折した腕を庇いながらボートに乗せたし、機関室の職場を死守しようとしている部下達をいち早く逃がした。
そして最後を見届けた時には、九死に一生を得るほどの危機か迫っていたが、溺れそうになりながら流れ着いてきた板に掴まり何とか助かった。その板で偶然、船長のクラークも助けられて海に浮かんでいた。
「あぁ、クラーク船長も」
「マーチン機関長もよく無事で」
二人はびしょ濡れになりながら海面に浮かぶ小板で再会した。
「申し訳ないマーチン、私の管理が万全ではなかったようだ」
「そんなことはありませんよ、クラーク船長。これは私達がもっと早く気が付いておくべきでした」
「そうだね、お互いがもう少し慎重にならなければ……ということかな」
二人は顔を見合わせて苦笑した。
「もうよそう、この話は、いずれ海難審判で原因が明らかになるでしょう」
「そうですね、船長」
「その罪を償う為に私はもう少し頑張らなければ、乗員達の名誉の為にも」
「私も同罪ですよ、潔く裁判を受け、この歳になって罪を償うつもりです」
「ありがとう、マーチン」
二人の男は海の上で板きれ一枚の上で手を取り合い泣いていた。クラークは、後一日で、晴れて船長を引退し、悠々自適に送る隠退生活を夢見ていたのだが、それは少し遠のいたようである。それはマーチンも同じだった。この二人のお陰で乗員の多くが命拾いをした。その中に食堂の見習い日本人コックの吾妻涼太と、彼を愛するマリアンもいた。
暫くして、その土地の病院に収容された中に佐々木明子がいた。ベッドの中で点滴を受けていたが、その顔は明るかった。彼女の話の相手は及川龍平である。
「ねえ、龍平さん」
「何かな明子?」
「ありがとう、助けて貰って」
「バカだな、当たり前だろう、婚約者だし」
「でも、嬉しいの、命を与えて貰ってこんなに生きることが素晴らしいって思ったこと無いわ」
「そうだね、本当に死ぬかと思ったけれど、僕たち運が良かったね」
「ええ、私もそう思うわ」
「明子、秋の結婚式までには身体を治しておこうね」
「ええ、龍平さんがいれば、心強いわ」
その時に病室のドアをノックする音が聞こえた。
「誰だろう?」
「どうぞ、お入り下さい」
そこに花束を持っていたのは、同じ病院で治療を終えた藤崎夫婦だった。
「あっ、藤崎さん!」
「お邪魔して宜しいですかな」
「ええ、どうぞどうぞ、奥さまお身体は大丈夫ですか?」
「はい、もう何とか元気になりました、これもあなた達のお陰ですよ」
「それは良かったです、ずっと心配していましたから」
「あの、お二人は秋に結婚する予定でしたね」
「はい、憶えてくれていたのですね」
「勿論ですとも、それで一つお願いが……」
「はい、何でしょうか、藤崎さん」
「もし、帰国してからですが、宜しければ、お二人のご結婚式に……」
「えっ? 出て下さる、とか……ですか?」
「ええ、差し出がましいのですが」
「勿論、喜んで、こちらこそお願い致します」
「有り難うございます、こちらで買った花ですが、気晴らしにと思いましてね」
「わぁ、綺麗ですね、素敵です、有り難うございました、藤崎さん」
「良かったね、喜んで頂いて、晴子」
「はい、パパ」
その病室には、地中海の美しい可憐な花を咲かせるスミレの花束があった。何とも良い花の放つ香りが二人の将来を祝福しているようである。
あの日、ローズ・プリンセス号の船長のクラークを待っていた客船船長のブラウンはクラークが死んでいなかったことを知らされた。
(良かったねクラーク、無事で生きていて本当に良かった。君にはこれから色々大変なことが待っているだろうが、私も出来るだけ君を応援するから頑張ってくれたまえ。君にはその覚悟があるはずだ、待っている!)
彼は既に船長を辞職したがクラークと再会することを願っていた。
了