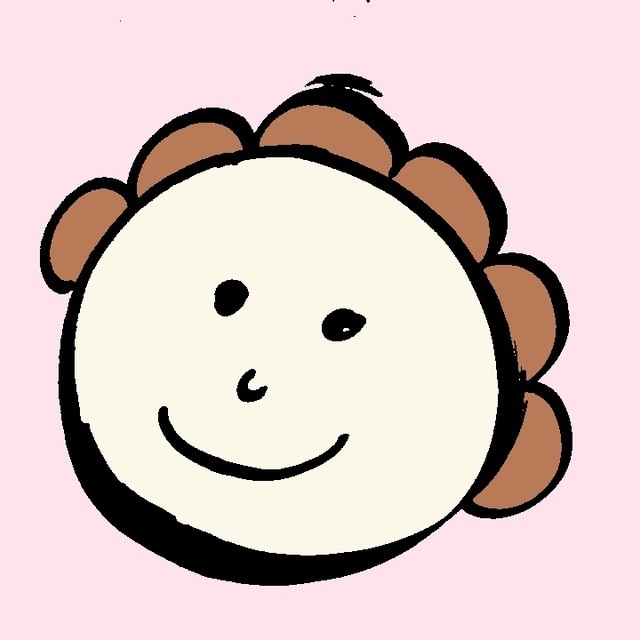3 笑える音
文字数 2,700文字
北浦(きたうら)憲一(けんいち)がピアノのレッスンを始めたのは、物心がついたころ、五歳のころだった。母親は一人っ子の憲一をとてもかわいがっていて、情緒豊かな子になってほしいと思っていた。大枚をはたいてアップライトピアノを買って、レッスンを受けさせることになった。
赤いバイエル。楽譜を読むことを学ぶだけなのだろうが、あまりに単純な楽譜で、先生が弾いたのをすぐ覚えて弾けた。黄色いバイエル。楽譜を読んだり書いたりするのが得意になってきて、ピアノを弾くのも聞くのも好きになってきた。楽譜できれいな曲が表現できることが面白いと思った。
小学校高学年の時、ピアニストになりたいと思うようになった。
高校生になるときに、音楽科ではない普通科に入学する代わりに、ピアノ教室は特選科の週三回のレッスンを開始した。レッスン料は高く、親にとっては経済的な負担はあっただろうが、憲一にとってはピアニストになればすべて許されるものだと思っていた。
「音大のピアノ科に入って、ソロピアニストになる」
全く迷いのない進路を決めていた。母親はとても喜んだ。
小学生の時から教えてくれていた岡本先生はとても厳しかった。
「へたくそ、止めてまえ。才能ない」
憲一は、それを励ましだと思って、むしろ頑張れた。
少なくとも一浪は覚悟していたのに、音大のピアノ科に現役で合格することができた。
しかし大学に入ってから、他の学生のレベルの高さに驚愕する。これまであまり他の学生の演奏をじっくり聴くことがなかった。岡本先生の演奏より深い音がする。メロディーが立体化している。自分がどんなに井の中の蛙で、へたくそだということに気が付き始めた。学校を休みがちとなったが、一緒に住んでいる親には何も言わなかった。
そのころ、大学に近いピアノバー『フォルテ』でバイトを始めた。酒を飲んでいる客の横で大好きなクラシックの曲をそれなりに弾いていたらコンビニのバイトの倍くらいの時給になり、生活に有り余る収入になった。
全く大学には行かなくなった。
「あんた、なにしてんのん。学校へ行ってへんねって。大学から電話きたんやで」
突然、母親がフォルテにやってきて言った。家からつけてこられていたのだった。
「大学、辞める」
母親は泣いていた。
それからもフォルテでバイトをする日が続いていたが、ある日演劇のピアノが弾ける人という条件で客演の依頼が来た。軽い気持ちで行ったのが、子どもの頃に何度か行ったことのある佐飛パラダイスの笑劇場だった。
笑劇場の中のコーナーで、座員がコーラスを歌う。その伴奏を頼まれた。
武田を中心にして、ベテラン座員の松原(まつばら)只男(ただお)たちがボケをする。途中で調子っぱずれになったり、踊りだしたり、曲が変わってしまったりする。客は大笑いしている。座員たちのスキルはすごい。憲一さえ笑いそうになってしまう。
子どもの時にはわからなかったが、笑劇場のアドリブに見えていた笑いが、しっかり作りこまれている。今回はそれが憲一が得意な楽譜の形になっていることに感動した。
武田に直談判して、笑劇場に入団を申し出た。
「食えるほどの仕事はないで」
と言われたが、フォルテでのバイトと並行して入団することになった。
帰宅して、父と母に決意を言った。
「僕はソロピアニストにはなれない。笑劇場で音楽で人を笑わせたい」
母はまだ納得していなかった。
「あんた、なにゆうてんねん。あんなんまともな仕事やあらへん」
「ちゃうで、えらい仕事や。やりたいようにやり。ママももう憲一の選んだ道、認めたろうや」
父が珍しく母に意見して、母は泣きながらも承知した。
その後も憲一の笑劇場の出番は多くはなかった。ピアノを弾かない役も当てられたが、なかなか上手にはできなかった。芝居の基礎を、武田に直接習ったり、舞台を見学しながら裏方を手伝っていた。
憲一が、稽古のない日のがらんとした稽古場で、古びて調律のされていないアップライトピアノを弾いていた。
「北浦君やったな、しばらく使ってへんから変な音やな」
通りがかった松原が笑って言った。
「おはようございます。調律してはらへんのですね」
あまり話したことのない長老座員の松原が急に現れ、緊張して手を止めた。
「いや、弾いててや」
それまで、いかにもピアノの定番である『乙女の祈り』などを引いていた。普通に弾いていても不協和音になるぼろいピアノなので、少し洒落でもともと不協和音のようなこどもの練習曲を弾いてみた。
「なんやそれ?」
松原に問われ、憲一はなんだっけな?と考えないと思い出せなかった。作者は確かプロコフィエフだったと思うが、曲名は覚えていない。
「ソ連の作曲家の、子どもの練習曲です」
「おもろいやん」
装飾音が何度も出てきて、不協和音の繰り返しだけど、シンプルな四拍子。調子の狂ったピアノで弾いても、うまく聞こえた。
小学生の頃のレッスンで、岡本先生はなぜか他の生徒とは違うプロコフィエフの練習曲を、憲一に与えた。当時は自分の個性を見出してくれていると思っていたが、よく考えるとピアニストになるための王道の曲を練習してもセンスのない憲一には意味がないと思われたのかもしれない。
松原が、倉庫からトランペットをもってきて、装飾音の部分をミュートという器具で音を変化させる演奏法で、耳コピーして演奏した。
「笑える音になるやろ」
憲一は、松原のすぐ演奏できる楽器スキルと、笑える音という言葉に驚いた。確かにその音は笑えた。ピアノのレッスンでも、大学でもそんなことを習ったことはなかったが、憲一にはわかった。
「お前、楽譜書けるやろ」
憲一が夢中にその場にあった台本の裏に楽譜を書いた。松原がドラムのパートを書き加えた。
十小節のアタックのようなコミカルな短い曲ができた。ピアノとトランペット、曲が始まる前に松原の声でカウントを入れる。
「ワン・ツー、ワンツー・サンハイ」
ICレコーダーに録音して、松原はそれを内川社長のところに持った。武田も聞いた。
「これ、使おう」
「中村がドラムいけるやろ、スタジオ借りて録音しよう」
ほかに、ギターやベースの弾ける座員も集められた。
翌日公民館のスタジオを借りて録音して、次の週からが、笑劇場の幕開きの音楽になった。
「これから毎日、お前の曲かかるで」
と、松原が憲一に言った。でも、これはプロコフィエフの曲なわけで、ほとんど松原が編曲したわけで、憲一はこっぱずかしかった。 他の座員にも次々と「ええ曲や」「パラダイス名物になるで」と褒められた。憲一は一座員として笑劇場の仲間になれたと実感できた。
赤いバイエル。楽譜を読むことを学ぶだけなのだろうが、あまりに単純な楽譜で、先生が弾いたのをすぐ覚えて弾けた。黄色いバイエル。楽譜を読んだり書いたりするのが得意になってきて、ピアノを弾くのも聞くのも好きになってきた。楽譜できれいな曲が表現できることが面白いと思った。
小学校高学年の時、ピアニストになりたいと思うようになった。
高校生になるときに、音楽科ではない普通科に入学する代わりに、ピアノ教室は特選科の週三回のレッスンを開始した。レッスン料は高く、親にとっては経済的な負担はあっただろうが、憲一にとってはピアニストになればすべて許されるものだと思っていた。
「音大のピアノ科に入って、ソロピアニストになる」
全く迷いのない進路を決めていた。母親はとても喜んだ。
小学生の時から教えてくれていた岡本先生はとても厳しかった。
「へたくそ、止めてまえ。才能ない」
憲一は、それを励ましだと思って、むしろ頑張れた。
少なくとも一浪は覚悟していたのに、音大のピアノ科に現役で合格することができた。
しかし大学に入ってから、他の学生のレベルの高さに驚愕する。これまであまり他の学生の演奏をじっくり聴くことがなかった。岡本先生の演奏より深い音がする。メロディーが立体化している。自分がどんなに井の中の蛙で、へたくそだということに気が付き始めた。学校を休みがちとなったが、一緒に住んでいる親には何も言わなかった。
そのころ、大学に近いピアノバー『フォルテ』でバイトを始めた。酒を飲んでいる客の横で大好きなクラシックの曲をそれなりに弾いていたらコンビニのバイトの倍くらいの時給になり、生活に有り余る収入になった。
全く大学には行かなくなった。
「あんた、なにしてんのん。学校へ行ってへんねって。大学から電話きたんやで」
突然、母親がフォルテにやってきて言った。家からつけてこられていたのだった。
「大学、辞める」
母親は泣いていた。
それからもフォルテでバイトをする日が続いていたが、ある日演劇のピアノが弾ける人という条件で客演の依頼が来た。軽い気持ちで行ったのが、子どもの頃に何度か行ったことのある佐飛パラダイスの笑劇場だった。
笑劇場の中のコーナーで、座員がコーラスを歌う。その伴奏を頼まれた。
武田を中心にして、ベテラン座員の松原(まつばら)只男(ただお)たちがボケをする。途中で調子っぱずれになったり、踊りだしたり、曲が変わってしまったりする。客は大笑いしている。座員たちのスキルはすごい。憲一さえ笑いそうになってしまう。
子どもの時にはわからなかったが、笑劇場のアドリブに見えていた笑いが、しっかり作りこまれている。今回はそれが憲一が得意な楽譜の形になっていることに感動した。
武田に直談判して、笑劇場に入団を申し出た。
「食えるほどの仕事はないで」
と言われたが、フォルテでのバイトと並行して入団することになった。
帰宅して、父と母に決意を言った。
「僕はソロピアニストにはなれない。笑劇場で音楽で人を笑わせたい」
母はまだ納得していなかった。
「あんた、なにゆうてんねん。あんなんまともな仕事やあらへん」
「ちゃうで、えらい仕事や。やりたいようにやり。ママももう憲一の選んだ道、認めたろうや」
父が珍しく母に意見して、母は泣きながらも承知した。
その後も憲一の笑劇場の出番は多くはなかった。ピアノを弾かない役も当てられたが、なかなか上手にはできなかった。芝居の基礎を、武田に直接習ったり、舞台を見学しながら裏方を手伝っていた。
憲一が、稽古のない日のがらんとした稽古場で、古びて調律のされていないアップライトピアノを弾いていた。
「北浦君やったな、しばらく使ってへんから変な音やな」
通りがかった松原が笑って言った。
「おはようございます。調律してはらへんのですね」
あまり話したことのない長老座員の松原が急に現れ、緊張して手を止めた。
「いや、弾いててや」
それまで、いかにもピアノの定番である『乙女の祈り』などを引いていた。普通に弾いていても不協和音になるぼろいピアノなので、少し洒落でもともと不協和音のようなこどもの練習曲を弾いてみた。
「なんやそれ?」
松原に問われ、憲一はなんだっけな?と考えないと思い出せなかった。作者は確かプロコフィエフだったと思うが、曲名は覚えていない。
「ソ連の作曲家の、子どもの練習曲です」
「おもろいやん」
装飾音が何度も出てきて、不協和音の繰り返しだけど、シンプルな四拍子。調子の狂ったピアノで弾いても、うまく聞こえた。
小学生の頃のレッスンで、岡本先生はなぜか他の生徒とは違うプロコフィエフの練習曲を、憲一に与えた。当時は自分の個性を見出してくれていると思っていたが、よく考えるとピアニストになるための王道の曲を練習してもセンスのない憲一には意味がないと思われたのかもしれない。
松原が、倉庫からトランペットをもってきて、装飾音の部分をミュートという器具で音を変化させる演奏法で、耳コピーして演奏した。
「笑える音になるやろ」
憲一は、松原のすぐ演奏できる楽器スキルと、笑える音という言葉に驚いた。確かにその音は笑えた。ピアノのレッスンでも、大学でもそんなことを習ったことはなかったが、憲一にはわかった。
「お前、楽譜書けるやろ」
憲一が夢中にその場にあった台本の裏に楽譜を書いた。松原がドラムのパートを書き加えた。
十小節のアタックのようなコミカルな短い曲ができた。ピアノとトランペット、曲が始まる前に松原の声でカウントを入れる。
「ワン・ツー、ワンツー・サンハイ」
ICレコーダーに録音して、松原はそれを内川社長のところに持った。武田も聞いた。
「これ、使おう」
「中村がドラムいけるやろ、スタジオ借りて録音しよう」
ほかに、ギターやベースの弾ける座員も集められた。
翌日公民館のスタジオを借りて録音して、次の週からが、笑劇場の幕開きの音楽になった。
「これから毎日、お前の曲かかるで」
と、松原が憲一に言った。でも、これはプロコフィエフの曲なわけで、ほとんど松原が編曲したわけで、憲一はこっぱずかしかった。 他の座員にも次々と「ええ曲や」「パラダイス名物になるで」と褒められた。憲一は一座員として笑劇場の仲間になれたと実感できた。