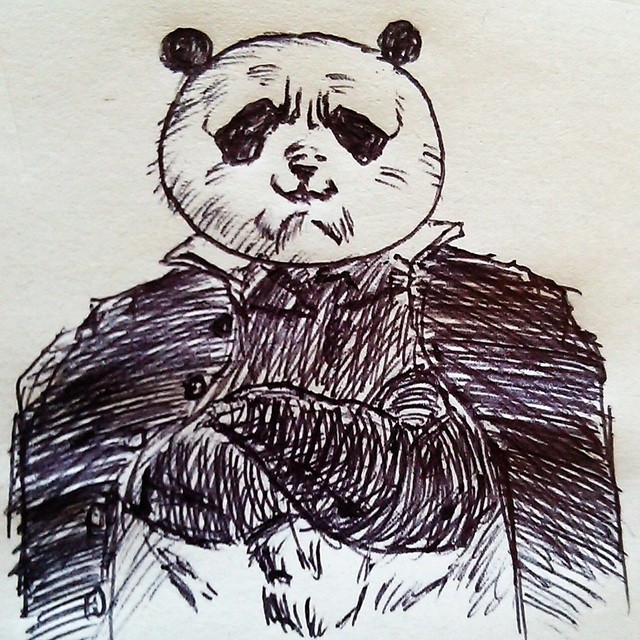#5 魔法との出遭い
文字数 4,942文字
これは人じゃない――ゴブリンだ。
ゴブリンの肌は緑色じゃない。血も赤いし、異臭を漂わせているわけでもない。小憎たらしい顔はしているけれど。
しかもリテルは、ゴブリンに対してそれほど強い嫌悪感を抱いてはいなかった――俺はこの世界のゴブリンについての記憶を思い出してみる。
ゴブリンはいたずら者の妖精だ。
普段は森の中に群れで暮らしていて、果実や木の実、小動物などを食べている。身長は小柄――猿種 の半分くらいで、服装は粗末な布を体に巻いているだけだが、リテルたちの言語からいくつもの単語を覚える知性もある。もっともその単語は、人を罵ったりからかったりするものばかりだから、本当はもっとわかっているはず。
ときどき人里に現れては他愛もないイラズラをして帰ってゆくのだが、そのイタズラも夜中に雨戸を叩いたり、腐った果物を道端に置いて人を転ばそうとしたり、村を囲う柵に糞尿をなすりつけたりという程度。少なくともストウ村では誰かがゴブリンに傷つけられたってのは聞いたことないし、むしろ森の中で迷った村人がゴブリンに遭って食べ物をあげたら森の入口まで連れて行ってくれた話まであるくらい。
この世界のゴブリンは、元の世界のゲームやマンガの中みたいな嫌われ役ではなく、人の周辺に住むれっきとした一種族のようだ。
そのゴブリンが、不意に俺の手をつかんだ。
正確には、つかんだというよりは弱々しくつかまったという感じ。まだ残っている方の手を、力なく震えながらも必死に伸ばしてきたのだ。
え、これ、どうしたらいいんだ?
弟妹くらいの背丈だからか、振り払うのに躊躇 してしまった俺の左手の薬指と小指とを、ゴブリンはぎゅっと握りしめた。
そんな風に頼られても。悪いヤツじゃないにしたって俺には何もできやしないのに。治療だって――いや、見捨てる以外の選択肢、あるんじゃないか?
俺はそのゴブリンを抱えると大キノコを探し、走り出した。
ほどなくして到着したのは、森の中なのにやけに開けた場所。その真ん中に建つ真っ白い円塔。
窓の位置からすると、二階分上がると一回り細くなり、さらにもう二階分上がって細くなり、トータル六階建てだろうか。
一階部分の外側の広さは見た感じ、俺 の学校近くのコンビニくらいはある。
そして、塔の回りには道標にしてきた大キノコが大量に群生している。
ここが魔女様の家で合っているのかな? 家じゃなく塔だけど。
抱えているゴブリンが苦しそうに呻 く。そうだな。そんな悠長なこと言ってる場合じゃない。
俺は大キノコの間を縫うように塔に近づいて質素な扉を見つけ、金属製のドアノッカーを迷わず鳴らした。
「すぐに出る」
中から若い女性の声がして間を開けず、扉が勢いよく開かれる。
内側へ引かれた扉に呼び込まれるように起きた風は、俺の背中から家の中へと吹き込み、中に立っていた少女のショートボブの赤髪をふわりと揺らした。
あの子だ……リテルが会ったことのある、魔女様の使いの子。
「ストウ村の、狩人見習いか?」
「は、はい。リテルと言います」
「どうしてゴブリンを抱えている?」
「あ……こ、ここに来る途中、倒れていて、つい」
「助けるのか?」
「はい」
縁もゆかりもないゴブリンなのに、うっかり「はい」と答えてしまった。
「待っていろ」
赤髪の少女は無表情のまま、部屋の奥に見えるもう一つの扉の向こうへと消える。こちらの玄関扉は開け放ったまま。
入ってすぐの部屋は四畳半くらいだろうか。中央に丸テーブルがあり、椅子が三脚。どれも装飾がないシンプルなもの。
それ以外で目につくのは、真っ青な絨毯。ラピス・ラズリのような鮮やかな青。
――ラピス・ラズリは姉さんの誕生石。
つい、元の世界の家族を思い出してしまった。なんでも完璧にこなす姉さんを。
仕事大好きな父さんは海外出張も多くてめったに帰らないし、母さんに至っては世界をまたにかけるバイオリニストとやらで、長男の誕生日だっていうのに海外で演奏の仕事とか平気で入れちゃう人。
溺愛する姉さんと、俺よりもずっとできのいい弟も一緒に連れて行ったのは、楽器が得意だから。母のコンサートにゲスト出演させるため。
鬱なこと思い出してしまったせいで、その青い絨毯の色を好きになれない。絨毯には罪がないのにな。
「どれ、ゴブリンを見せてみろ」
奥の扉が開く音と共にさっきの少女とは違う女性の声が聞こえ、俺は顔を上げる。
そこには美し過ぎるお姉さんが立っていた。綺麗の最上級を二乗してもいい神々しいレベル。
深い青のストレートロングの髪は膝くらいまであり、猿種 の、二十代くらい――ということは百年以上生きていると噂の魔女様とは違う人なのかな。もしかして魔女様のお弟子さんとか?
いやでもマンガに出てくる魔女ってだいたい外観は若いよね。それにこの格好――絹のように光沢のある真っ白い生地の服は、キャミソールのように肩も胸元も開放感があり、裾もミニスカかってくらい短くて――どうにもエロい。
しかもその薄手の生地は、突き出た胸の頂きから裾までなだらかな曲線をたなびかせ、その曲線に沿って流れる青い髪が、雪の崖を静かに伝う滝のようにも見えて、芸術的な作品のようにさえ見える。
「机の上に置いて構わないのだぞ」
「は、はいっ」
声が裏返ってしまったことも、見とれちゃっていたことも、両方恥ずかしい。
まだ息があるゴブリンを丸テーブルの上へと優しく置き、お姉さんを直視できずに視線を床へと移す。
女神のようなお姉さんは裸足なんだけど、そのつま先からしてもう品がある。生活感のない足。俺なんかとは違う世界の生き物みたい……いや実際、違う世界の人なんだけどさ。
「なんだと?」
「す、すいませんっ」
お姉さんの声に対し、反射的に謝ってしまう。ヤバい。人の心を読んだりできちゃうお方?
とにかくごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
心の中でたくさん謝っている俺を、お姉さんは不思議そうな表情で見つめている。
「なぜ君が謝るのだ?」
「カエルレウム様、この少年はリテルといいます」
いつの間にか赤髪の少女も部屋に戻ってきていた。
よく見たら、この少女の着ている服の生地もお姉さん――カエルレウム様の服と同じっぽい。その服のデザインは、俺やケティとかと同じシャツと膝上短パンなんだけど。
というか、心が読まれては……いない、でいいのかな?
「リテルか……うむ。リテルが謝る必要はない。私がゴブリンにかけていた呪詛が変異していてな。それに驚いただけだ」
喋りながらもカエルレウム様はゴブリンの傷口付近に手を触れる。うわ、傷がみるみる治ってゆく。すげぇ、これが魔法? このお姉さんがやっぱり魔女様?
でもいま呪詛って言ったよな。呪詛って嫌な響きだな。人をカエルとかに変えちゃうやつかな。
「呪詛が変異……ですか?」
興味をうっかり口にしちゃっていた。
「ほほう。魔法に興味があるとは、あの村の者にしては珍しい反応だな」
そう言われてみると、理由はわからないがストウ村では魔法に関する話題が大っぴらになることがないな。
領監さんは魔法の知識があるっぽかったのに……ああ……リテルの記憶から、村の大人たちが積極的に魔法の話題を避けていた空気があったことを思い出す。
とは言え。せっかく異世界に来て、魔法やら魔術やら興味深い話が目の前にあって、スルーなんてできるわけがない。呪詛と魔法が同じなのかってのも気になるし。
「あ、ありますっ! 興味あります!」
「そうか。ではそこに座れ」
「はいっ」
一番近くにあった椅子に座ると、俺の背後で少女が玄関の扉を閉めた。
「リテルは魔法を使ったことがあるか?」
「魔法を?」
え? 使えるの?
まさかストウ村の人たちは全員魔法を使えて、それを隠すために魔法の話題を……?
「どうやらないようだな。魔法について簡単に説明しよう」
「は、はいっ」
「魔法とは思考の具現化だ。理論から言えば、何でもできる。ただし結論から言えば、何でもできるわけではない」
なんだ?
いきなり話が難しくなったぞ。
「理解できるか?」
「何でもできる……けれど……思考を具現化する過程で、何らかの障害が発生する、ということでしょうか?」
「ふむ。リテル、君は素晴らしい。自分でものを考えようとする。それは魔術師にとって最も必要なものだ。魔術師を目指すのであれば、思考を決して手放してはならない」
言われた言葉を反芻すると、とてもドキドキする。
カエルレウム様にほめられることが、どうしてこんなに興奮するのか、その理由へ俺の思考がすぐに辿り着く。
今までずっとリテルの体で、リテルの人間関係で、リテルの築いた実績で、評価されてきたから。今の言葉は、リテルではなく俺 の思考そのものを評価されたから。
俺は今、リテルというガワと全く関係なく、純粋に俺として認識してもらえて、しかも良い評価までされて、嬉しくないわけがない。
「ありがとうございます……え?」
「どうした?」
「魔術師を目指すのであれば、って……目指せるのですか?」
俺でも? 村人でも? 職業クラスとか天から勝手に与えられるとかないの?
あと、魔法と魔術の違いも気になる。
「ああ。魔法は命ある者であれば誰にでも使える。魔法が使える者は魔術師を目指すことができる」
誰にでも!
「魔法と魔術の違いはなんですか?」
「魔術とは、複数の魔法を同時に発動することだ。しかし魔法を使うには自らの命を消費する。魔術ともなれば更に多く。リテルが言及した障害というのがそれだ。魔術の要求する代償を支払えなければ魔術は失敗する。ただ魔術を成功させれば魔術師と呼ばれるかというとそうではない。いかに効率よく命の消費を抑えるか、その制御ができてこその魔術師だ」
魔法を使うには、命を削る必要がある?
「驚くことはない。命ある者は等しく、ただ生きているだけで命を消費しているのだ。魔法を使わない人生は寿命に等しいだけの効果しかもたらさないが、魔法をうまく使えば、本来の寿命ではなし得ぬ効果を生み出すことができる。思考次第だがな」
思考次第で何でもできる……かもしれない。
だとしたら俺はリテルに体を返して、元いたあの世界に戻ることだって――あそこへ戻るかどうかは別として、試す価値は十分にある。
「カエルレウム様っ! 俺に魔法の使い方を教えてください!」
● 主な登場者
・有主 利照 /リテル
猿種 、十五歳。リテルの体と記憶、利照 の自意識と記憶とを持つ。
リテルの想いをケティに伝えた後、盛り上がっている途中で呪詛に感染。寄らずの森の魔女様への報告役に志願した。
・片腕の死にかけゴブリン
小憎たらしい顔ではあるが、獣種の人間に似た外観でイタズラ好きな種族。
魔女様の家へと向かう途中、茂みの中から現れた。弟妹と重ねてしまったリテルは思わず助けるために動いてしまった。。
・利照の家族
仕事大好きな父は海外出張も多くめったに帰らず、母は世界をまたにかけるバイオリニストだが、利照の誕生日よりも仕事を優先する。
姉と弟は利照よりもできが良く、両親の愛情はその二人へとばかり注がれる。
・赤髪の少女
整った顔立ちのクールビューティー。華奢な猿種 。魔女様のお使いの人。
リテルとマクミラ師匠が二人がかりで持ってきた重たい荷物を軽々と持ち上げた。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様のようである。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである猿種 。
魔法や魔術に対して興味を持ったリテルに興味を持ち、魔法について解説し始めた。
■ はみ出しコラム【カエメン】
ストウ村の家屋や寄らずの森の魔女の塔は、白い外観をしている。これはカエメンという素材を使っている。
カエメンは、こちらの世界でいう石灰モルタルに相当する。
カエメン石と呼ばれる石を細かく砕き、一部は窯の中で焼く。砕いただけのカエメン砂と、焼いたカエメン灰と水とを混ぜると、白い煙を出して膨らむので、これを覆うように砂をかけてしばらく放置する。発熱が止まったら、よく混ぜ合わせ、水を加えて練る。
木材や石材、レンガなどで作った家の骨格を、こうして作ったカエメンで補強して建物を建てる。
ゴブリンの肌は緑色じゃない。血も赤いし、異臭を漂わせているわけでもない。小憎たらしい顔はしているけれど。
しかもリテルは、ゴブリンに対してそれほど強い嫌悪感を抱いてはいなかった――俺はこの世界のゴブリンについての記憶を思い出してみる。
ゴブリンはいたずら者の妖精だ。
普段は森の中に群れで暮らしていて、果実や木の実、小動物などを食べている。身長は小柄――
ときどき人里に現れては他愛もないイラズラをして帰ってゆくのだが、そのイタズラも夜中に雨戸を叩いたり、腐った果物を道端に置いて人を転ばそうとしたり、村を囲う柵に糞尿をなすりつけたりという程度。少なくともストウ村では誰かがゴブリンに傷つけられたってのは聞いたことないし、むしろ森の中で迷った村人がゴブリンに遭って食べ物をあげたら森の入口まで連れて行ってくれた話まであるくらい。
この世界のゴブリンは、元の世界のゲームやマンガの中みたいな嫌われ役ではなく、人の周辺に住むれっきとした一種族のようだ。
そのゴブリンが、不意に俺の手をつかんだ。
正確には、つかんだというよりは弱々しくつかまったという感じ。まだ残っている方の手を、力なく震えながらも必死に伸ばしてきたのだ。
え、これ、どうしたらいいんだ?
弟妹くらいの背丈だからか、振り払うのに
そんな風に頼られても。悪いヤツじゃないにしたって俺には何もできやしないのに。治療だって――いや、見捨てる以外の選択肢、あるんじゃないか?
俺はそのゴブリンを抱えると大キノコを探し、走り出した。
ほどなくして到着したのは、森の中なのにやけに開けた場所。その真ん中に建つ真っ白い円塔。
窓の位置からすると、二階分上がると一回り細くなり、さらにもう二階分上がって細くなり、トータル六階建てだろうか。
一階部分の外側の広さは見た感じ、
そして、塔の回りには道標にしてきた大キノコが大量に群生している。
ここが魔女様の家で合っているのかな? 家じゃなく塔だけど。
抱えているゴブリンが苦しそうに
俺は大キノコの間を縫うように塔に近づいて質素な扉を見つけ、金属製のドアノッカーを迷わず鳴らした。
「すぐに出る」
中から若い女性の声がして間を開けず、扉が勢いよく開かれる。
内側へ引かれた扉に呼び込まれるように起きた風は、俺の背中から家の中へと吹き込み、中に立っていた少女のショートボブの赤髪をふわりと揺らした。
あの子だ……リテルが会ったことのある、魔女様の使いの子。
「ストウ村の、狩人見習いか?」
「は、はい。リテルと言います」
「どうしてゴブリンを抱えている?」
「あ……こ、ここに来る途中、倒れていて、つい」
「助けるのか?」
「はい」
縁もゆかりもないゴブリンなのに、うっかり「はい」と答えてしまった。
「待っていろ」
赤髪の少女は無表情のまま、部屋の奥に見えるもう一つの扉の向こうへと消える。こちらの玄関扉は開け放ったまま。
入ってすぐの部屋は四畳半くらいだろうか。中央に丸テーブルがあり、椅子が三脚。どれも装飾がないシンプルなもの。
それ以外で目につくのは、真っ青な絨毯。ラピス・ラズリのような鮮やかな青。
――ラピス・ラズリは姉さんの誕生石。
つい、元の世界の家族を思い出してしまった。なんでも完璧にこなす姉さんを。
仕事大好きな父さんは海外出張も多くてめったに帰らないし、母さんに至っては世界をまたにかけるバイオリニストとやらで、長男の誕生日だっていうのに海外で演奏の仕事とか平気で入れちゃう人。
溺愛する姉さんと、俺よりもずっとできのいい弟も一緒に連れて行ったのは、楽器が得意だから。母のコンサートにゲスト出演させるため。
鬱なこと思い出してしまったせいで、その青い絨毯の色を好きになれない。絨毯には罪がないのにな。
「どれ、ゴブリンを見せてみろ」
奥の扉が開く音と共にさっきの少女とは違う女性の声が聞こえ、俺は顔を上げる。
そこには美し過ぎるお姉さんが立っていた。綺麗の最上級を二乗してもいい神々しいレベル。
深い青のストレートロングの髪は膝くらいまであり、
いやでもマンガに出てくる魔女ってだいたい外観は若いよね。それにこの格好――絹のように光沢のある真っ白い生地の服は、キャミソールのように肩も胸元も開放感があり、裾もミニスカかってくらい短くて――どうにもエロい。
しかもその薄手の生地は、突き出た胸の頂きから裾までなだらかな曲線をたなびかせ、その曲線に沿って流れる青い髪が、雪の崖を静かに伝う滝のようにも見えて、芸術的な作品のようにさえ見える。
「机の上に置いて構わないのだぞ」
「は、はいっ」
声が裏返ってしまったことも、見とれちゃっていたことも、両方恥ずかしい。
まだ息があるゴブリンを丸テーブルの上へと優しく置き、お姉さんを直視できずに視線を床へと移す。
女神のようなお姉さんは裸足なんだけど、そのつま先からしてもう品がある。生活感のない足。俺なんかとは違う世界の生き物みたい……いや実際、違う世界の人なんだけどさ。
「なんだと?」
「す、すいませんっ」
お姉さんの声に対し、反射的に謝ってしまう。ヤバい。人の心を読んだりできちゃうお方?
とにかくごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。
心の中でたくさん謝っている俺を、お姉さんは不思議そうな表情で見つめている。
「なぜ君が謝るのだ?」
「カエルレウム様、この少年はリテルといいます」
いつの間にか赤髪の少女も部屋に戻ってきていた。
よく見たら、この少女の着ている服の生地もお姉さん――カエルレウム様の服と同じっぽい。その服のデザインは、俺やケティとかと同じシャツと膝上短パンなんだけど。
というか、心が読まれては……いない、でいいのかな?
「リテルか……うむ。リテルが謝る必要はない。私がゴブリンにかけていた呪詛が変異していてな。それに驚いただけだ」
喋りながらもカエルレウム様はゴブリンの傷口付近に手を触れる。うわ、傷がみるみる治ってゆく。すげぇ、これが魔法? このお姉さんがやっぱり魔女様?
でもいま呪詛って言ったよな。呪詛って嫌な響きだな。人をカエルとかに変えちゃうやつかな。
「呪詛が変異……ですか?」
興味をうっかり口にしちゃっていた。
「ほほう。魔法に興味があるとは、あの村の者にしては珍しい反応だな」
そう言われてみると、理由はわからないがストウ村では魔法に関する話題が大っぴらになることがないな。
領監さんは魔法の知識があるっぽかったのに……ああ……リテルの記憶から、村の大人たちが積極的に魔法の話題を避けていた空気があったことを思い出す。
とは言え。せっかく異世界に来て、魔法やら魔術やら興味深い話が目の前にあって、スルーなんてできるわけがない。呪詛と魔法が同じなのかってのも気になるし。
「あ、ありますっ! 興味あります!」
「そうか。ではそこに座れ」
「はいっ」
一番近くにあった椅子に座ると、俺の背後で少女が玄関の扉を閉めた。
「リテルは魔法を使ったことがあるか?」
「魔法を?」
え? 使えるの?
まさかストウ村の人たちは全員魔法を使えて、それを隠すために魔法の話題を……?
「どうやらないようだな。魔法について簡単に説明しよう」
「は、はいっ」
「魔法とは思考の具現化だ。理論から言えば、何でもできる。ただし結論から言えば、何でもできるわけではない」
なんだ?
いきなり話が難しくなったぞ。
「理解できるか?」
「何でもできる……けれど……思考を具現化する過程で、何らかの障害が発生する、ということでしょうか?」
「ふむ。リテル、君は素晴らしい。自分でものを考えようとする。それは魔術師にとって最も必要なものだ。魔術師を目指すのであれば、思考を決して手放してはならない」
言われた言葉を反芻すると、とてもドキドキする。
カエルレウム様にほめられることが、どうしてこんなに興奮するのか、その理由へ俺の思考がすぐに辿り着く。
今までずっとリテルの体で、リテルの人間関係で、リテルの築いた実績で、評価されてきたから。今の言葉は、リテルではなく
俺は今、リテルというガワと全く関係なく、純粋に俺として認識してもらえて、しかも良い評価までされて、嬉しくないわけがない。
「ありがとうございます……え?」
「どうした?」
「魔術師を目指すのであれば、って……目指せるのですか?」
俺でも? 村人でも? 職業クラスとか天から勝手に与えられるとかないの?
あと、魔法と魔術の違いも気になる。
「ああ。魔法は命ある者であれば誰にでも使える。魔法が使える者は魔術師を目指すことができる」
誰にでも!
「魔法と魔術の違いはなんですか?」
「魔術とは、複数の魔法を同時に発動することだ。しかし魔法を使うには自らの命を消費する。魔術ともなれば更に多く。リテルが言及した障害というのがそれだ。魔術の要求する代償を支払えなければ魔術は失敗する。ただ魔術を成功させれば魔術師と呼ばれるかというとそうではない。いかに効率よく命の消費を抑えるか、その制御ができてこその魔術師だ」
魔法を使うには、命を削る必要がある?
「驚くことはない。命ある者は等しく、ただ生きているだけで命を消費しているのだ。魔法を使わない人生は寿命に等しいだけの効果しかもたらさないが、魔法をうまく使えば、本来の寿命ではなし得ぬ効果を生み出すことができる。思考次第だがな」
思考次第で何でもできる……かもしれない。
だとしたら俺はリテルに体を返して、元いたあの世界に戻ることだって――あそこへ戻るかどうかは別として、試す価値は十分にある。
「カエルレウム様っ! 俺に魔法の使い方を教えてください!」
● 主な登場者
・
リテルの想いをケティに伝えた後、盛り上がっている途中で呪詛に感染。寄らずの森の魔女様への報告役に志願した。
・片腕の死にかけゴブリン
小憎たらしい顔ではあるが、獣種の人間に似た外観でイタズラ好きな種族。
魔女様の家へと向かう途中、茂みの中から現れた。弟妹と重ねてしまったリテルは思わず助けるために動いてしまった。。
・利照の家族
仕事大好きな父は海外出張も多くめったに帰らず、母は世界をまたにかけるバイオリニストだが、利照の誕生日よりも仕事を優先する。
姉と弟は利照よりもできが良く、両親の愛情はその二人へとばかり注がれる。
・赤髪の少女
整った顔立ちのクールビューティー。華奢な
リテルとマクミラ師匠が二人がかりで持ってきた重たい荷物を軽々と持ち上げた。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様のようである。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである
魔法や魔術に対して興味を持ったリテルに興味を持ち、魔法について解説し始めた。
■ はみ出しコラム【カエメン】
ストウ村の家屋や寄らずの森の魔女の塔は、白い外観をしている。これはカエメンという素材を使っている。
カエメンは、こちらの世界でいう石灰モルタルに相当する。
カエメン石と呼ばれる石を細かく砕き、一部は窯の中で焼く。砕いただけのカエメン砂と、焼いたカエメン灰と水とを混ぜると、白い煙を出して膨らむので、これを覆うように砂をかけてしばらく放置する。発熱が止まったら、よく混ぜ合わせ、水を加えて練る。
木材や石材、レンガなどで作った家の骨格を、こうして作ったカエメンで補強して建物を建てる。