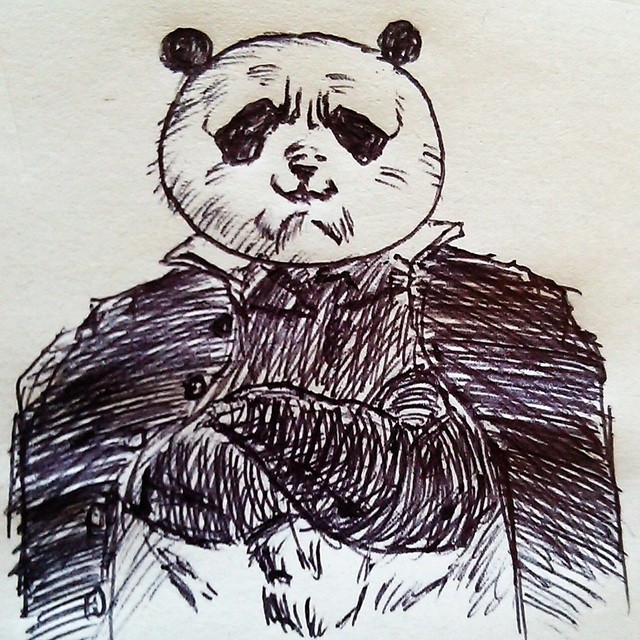#46 哀れハグリーズのおケツが面白痛くなる歌
文字数 8,411文字
「リテル、起きて」
ケティの声で目を覚ます――俺、寝ていたのか?
いつの間に――飛び起きて周囲を確認する。
馬車 は停まっている。
マドハトとルブルムは後方を警戒していて、メリアンは前方を――街道の先の方で馬車 が横転している。
え?
馬車ってそんなコロコロ街道に横転しているもの?
それとも俺は時間を巻き戻す能力でも――いや、そうじゃない。
街道の両側はいつの間にかほぼ森になっているし、馬車 もさっきより一回り大きいし、崩れた部分を含め街道を完全に塞ぐ形に置かれている。
そう、置かれている、という印象。
車軸の折れた車輪が手前に散らばっているのだが、どれも綺麗に上向きになった画鋲みたいな状態で。
さっきとは状況が明らかに違う。
「メリアン……馬車 って、こんなにもしょっちゅう襲撃されるものですか?」
「いや、半年に二度でも多い方だ。さっきの連中、金持ちの商人がどうこう言っていただろう。そいつを狙って片っ端から襲撃して回ったってんなら筋は通るが……」
「でもそれなら、フォーリーへ向かってる定期便が通り過ぎた後で道を塞ぐってのも変ですよね?」
さっきのは横転したのを放置って感じだったけど、今度のはがっつりバリケード作りましたって感じ。
「ああ、そうなんだよ。考えられるとしたら、その商人の救出を邪魔する目的とかかな」
だとしたら、付近には見張りが残っている可能性は大きい。
「メリアン、また偵察しながら近づいてみますか?馬車 はここに置いたままで」
「それは慎重になった方がいい。さっきの襲撃場所とこの場所と、両方とも同じ犯人の仕業だとしたら敵の人数は少なくない」
「メリアン、こういうとき、いつもはどうしてる?」
俺とメリアンとの会話にルブルムが混ざってきた。
「普通は、危険に首を突っ込んで得することは何もない。最寄りの監理官が居る街や村まで引き返して報告すれば領兵が派遣される。特にここはフォーリーから首都キャンロルや隣の領都アイシスへと通じる主要な街道だ。もう少し行けばクスフォード領と王国領との領境だし砦だってある。そいつらとやり合う覚悟があるってんなら、単なる盗賊なんかじゃない。一つの軍隊って言っても言い過ぎじゃあない。だがそれならいくら裕福っつっても個人の商人レベルを相手にするのも妙だ……この辺にある村を一つまるごと襲うくらいの……」
なんだか物騒な話になってきた。
「ちなみに、普通じゃない方法ってのは……」
「押し通る」
うん。予想通りです。
でもメリアンがいくら強いとは言っても、相手の人数や武装の度合いも分からない。
それにこちらは戦闘の素人ばかり。
メリアンの足を引っ張るのが目に見えている。
かと言って、今から引き返すという選択肢も取りたくはない。
ラビツ一行との距離は開くし、何より今からだとフォーリーに戻っても深夜過ぎだろう。
それに、さっきのチェッシャーたちの乗っていた定期便を横転させた連中が――。
「既に挟まれている恐れもありますよね?」
「それは否定しない」
だとしたら突破するってのも手なのか?
「メリアン、砦とフォーリーなら砦の方が近いですよね?」
「圧倒的にな」
「知らせるのって、やっぱり直接行くしかないですよね……」
あの横転馬車を燃やしたら狼煙代わりになるかなと一瞬考えもしたが、あそこで盛大なキャンプファイヤーやったら、近くの森へ飛び火しかねない。
森やその近くでの火の扱いについては注意に注意を重ねろと、マクミラ師匠にさんざん叩き込まれたからなぁ。
「旦那がたぁ……ここで野営ってのだけはご勘弁願いますよ……」
なかなか結論が出ないことにシビレをきらしたのか、御者さんがボヤく。
「御者さん、ここらへんの道幅なら、馬車の向きを反対向きに戻すのって、すぐにできますか?」
「うーん……馬をいったん外すんなら……あっ、あそこに見える小道を使うなんてどぅですかい? 入ってって、広い場所がありゃぁそこで引き返すんでさぁ」
小道?
……確かにある。
街道から入り込む小道はここからでも見えるけど――横転馬車からやけに近い。
それが引っかかる。
そこを使わざるを得ないような状況が。
逆にその小道があったからこそ、あえてこの場所を封鎖したとも考えられる――だとしたら、今度こそ罠だよね?
「ね、あっちって山の方だよね? あの山々は、向こう側へ抜けられる道なんてないって聞くけれど」
ケティも話に混ざってくる。
「しかもドラゴン が出現するって噂もあるな」
メリアンがおどけて肩をすくめる。
街道から右、つまり東の方には「マンティコラの歯」と呼ばれる険しい山脈が連なっている。
マンティコラというのは、元の世界でマンティコアと呼んでいたあの魔獣とほぼ同じ存在っぽい。
猫種 の逆先祖返り――顔だけ人で、体は猫、というか獅子だけど。
ただしその尾の先には毒針があり、歯は三列に並んでいて、獣種を好んで喰らうという。
ラトウィヂ王国の東側をほぼ全て塞いでいるこの山脈は牙のように鋭い山々が幾重にも重なっている様子から、その危険性込みで「マンティコラの歯」と名付けられた、みたいなことをリテルは親から聞いている。
なぜかというとストウ村では、小さな子が夜遅くまで起きていると。マンティコラの歯山脈からマンティコラが飛んできて喰われてしまうぞ、などとしつけ用に用いられる魔獣としても馴染み深いからだ。
ドラコというのもドラゴンのことだし、地球で知名度の高いモンスター名が登場すると心なしか嬉しいのが不思議だ。
「ドラコ怖いです!」
マドハトがそう言うと、ケティもモソモソと「マンティコラも怖い」とか言い出す始末。
「そうだな。あの子らが本当にフォーリーへ向かったんなら、今頃、フォーリーの領兵どもが横転した定期便を回収しに向かって来ているかもしんないね。だとしたら、挟み撃ちになるのは、フォーリー側からあたしらを追っかけてくる連中さ」
メリアンがそう言い切ると、ケティやマドハトはちょっとホッとする。
「それなら、ここでもう方向転換しちゃう方がいいかもですね」
距離感からすると決してそんな楽観視はできないと思うのだが、俺たちを安心させようとして言っているのかもしれないのであえて賛同しておく。
「いいね、リテル。あたしも賛成だ……ってことで、御者さーん。あんたの腕なら小道なんて入らずに、ここでも切り返しできるって!」
メリアンが笑顔で御者さんの背中をパンと叩く。
「偵察はさっき同様、あたしとリテルとで行く。馬車 が反転し終わったらだけどな」
「道幅狭いところでの反転は面倒なんすがね……」
「まぁまぁ、そこをやっちゃうのが、あんたの腕のすごいところだろ?」
御者さんはまんざらでもない感じで、馬車 を反転させる。
確かに時間がかかっている印象。
それを興味深そうに見ているマドハトごしに、馬の動きのさらに向こう、森の方へ『魔力感知』を集中している俺の右手を、誰かがつかんだ。
ケティだった。
「リテルはさ……なんか、変わったよね」
「え?」
動揺を表に出さないようにしたものの――ケティはリテルと俺 との違いに気がついているってことか?
「昔はさ、いつもビンスンさんや私の後ろについてまわるばかりだったのに……いつの間にか一人で歩き出しちゃってるんだもんね。覚えている? 私たちにいっつも置いてくよーって言われて、必死においかけてきた頃のこと」
それはリテルの記憶の中にある。
リテルがまだ子どもだった頃、子どもだけのグループは、リテルの兄であるビンスン、ビンスンと同い年のエクシあんちゃん、それからケティの三人が輪の中心だった。
リテルの下はちょっと歳が離れていたから、幼い連中のお守りをしなくてよいときはリテルも含めた四人で遊ぶことになる――となると四人の中では一番下であるリテルは何につけてもびりっかすで……。
「それにしてもさ、メリアンと仲良くなるの早いよね。さっきのさ、チェッシャーちゃんだっけ? なんかすごい熱い視線でリテルのこと見つめてたし、どさくさまぎれに大好きとか言ってたような気がするんだけどさ……リテル、前はそんな感じじゃなかったよね? なんか、変わっちゃった気がして……ごめんね」
俺はリテルだよと、そう答えたいのに、言葉がとっさに出てこない。
「あんな綺麗な魔女さまのところで……アルブムちゃんも可愛いかったし、ルブルムさんだって美人さんだよね……私のリテルは……そんな、女性に慣れてなかったっていうか」
「な、慣れてなんか……ないよ……必死なだけ……だから」
その言葉はつかえずに出た。
俺 の本心だから。
「そ、そうだよね……ごめんね。なんか、リテルが、遠くなっちゃった気がして」
そう言うとケティは俺の頬にキスをして、荷台の後方へ移動する――のを目で追って、ルブルムがこっちをずっと見つめていたことに気付く。
感情の見えない表情だが、俺的にはなんか気まずい。
ルブルムへ何か声をかけた方がいいのか迷っていた俺の視界が、マドハトの頭で塞がれた。
「僕も! リテルさまの顔! なめたいです!」
ぴょんぴょんと飛び跳ねようとするマドハトの頭を、ぎゅっと押さえつける。
また面倒な感じに――おや、おとなしくなった?
「これ、落ち着くです!」
俺の手の下で、マドハトは自ら頭を動かし、撫でられている感を出す。
そういえばハッタも、頭撫でられるの好きだったっけ。
「おー! さすが熟練の御者さん! 見事な腕前だねぇ!」
「ま、まぁな。こんくれぇ簡単ですぜ」
馬車 の向きが変わったので降りようとすると、メリアンは後部の幌をしっかりと閉じた。
「御者さん、あんたも中に入っててくれ」
メリアンは馬車の前側の幌も閉じようとする。
「あっしもすか?」
「ああ。こっちが逃げる素振りを見せたら……弓を持っているやつが攻撃してくるかもしれない……念のためさ。射的の的にゃなりたかないだろ?」
「そ、そりゃそうでがすよ」
御者さんは御者席から降りて馬車の中へ。
「ケティ、あたしとリテルが出たら、ここもしっかり幌を閉じとくれ」
「わかった……けど、リテルとメリアンは大丈夫?」
「ああ。危険を感じたら、戻ってくるさ……あと、幌は目隠しにはなっても、矢を防ぐ盾にはならない。なにか異変を感じたら、すぐに馬車の床へ伏せてくれ……あとはえーと、マドハト」
「はいです!」
「歌は歌えるか?」
歌?
「歌えるです!」
「あたしらは降りたらすぐに森に潜み、森の中を通って偵察に向かう。でもこっちは気付いてませんよって相手を油断させるために歌うのさ。陽気なやつをいくつか頼むよ」
「はいです! じゃあ……晴ーれたー! 昼さーがりっ! 粉挽きのハグリーズがー! 向かうよはるばる魔女の森へー!」
これ、うちの村のことを歌っているのか?
「リテル、早く」
「はいっ」
馬車の外へ出ると、ケティが幌を閉じ際、俺に向かって手を振って――その横でルブルムは俺から目を反らした。
なんかいやだな、こんなタイミングでギクシャクするなんて。
「糸杉のー木陰ーにー! そこにっ! 隠れるはっ! 逢引のっ! あーいーてーっ!」
メリアンが俺の肩を軽く小突く。
「あ、ごめんなさい」
「いいさ。ケティもルブルムも、いい子だよね。迷うのも分かるさ」
その言葉は、やけに声のボリュームが控えめだった。
だから俺は変に反論はせず、メリアンの目をじっと見つめた。
「あたしがこの作業を終えるまで、チェッシャーの時みたく周囲への警戒を頼む」
小さな声で了承を告げると、メリアンはさっそくその「作業」とやらを開始する――え、何やってんの?
俺の表情を見たメリアンが周囲を指差す。
は、はいっ。そうですね。ちゃんと集中しよう。
マドハトの歌に惑わされることもなく、ケティとルブルムのこともいったん置いといて、俺は『魔力感知』の範囲を広げる。
チェッシャーの『死んだふり』みたいな魔法が使われている可能性も考慮して丁寧に、遠くまで。
例の改良型の『魔力感知』――『魔力探知機』を。
……居るな?
しかも森の中を近づいてきているような。
慌ててメリアンの目を見ると、指で何かを指示しているのは――俺が、馬車 の中へ戻れってこと?
でも馬車 がこんな状態じゃ逃げるの無理だろ――って、あー、そうか。
メリアンがさっき「押し通る」って言ってたアレは、そういうことなのか。
俺は弓を構えやすい姿勢のまま、馬車 の中へと駆け込んだ。
中へ入った途端、ケティがハンマーを振りかぶっていて。
「ま、待て! 俺だって!」
「リテル? 声もかけないで入ってくるから、てっきり」
ルブルムは『魔力感知』で俺だとわかるはずだからと――ケティが普通の人だというのが思考から漏れてた。
いけないな。こんなんじゃリテルの大事なケティを、守れないぞ。
馬車 がガタンと揺れ、動き始めるのを感じる。
「来るよ! 床に伏せてっ! 御者はあたしがやるから!」
外のメリアンの言葉を皆に伝え、馬車 の床へと伏せる。
木の匂いが近い。
「哀れハグリーズぅ 立っているのに立てなくてぇ ドッロドローのつーるつる!」
「マドハト、歌はもういい!」
外を移動してくる寿命の渦 へと注意を払う。
二人――いや四人。
偽装の渦 ではなく、寿命の渦 そのままで。
手前の二人――森の中を近づいてくるのは猿種 に鼠種 。緊張と敵意とが寿命の渦 に出ている。
もう二人は横転馬車 の辺り――というかその裏側辺りかな、羊種 と牛種 か。
動いてない方の二人の寿命の渦 が近付く感じから、こっちの馬車 がけっこうスピード出しているのが分かる。
床に貼り付いているので、振動がダイレクトに響く。
舌を噛まないように歯を食いしばったままだから会話も不可能だ。
「ど、どっちにんグッ」
ほら、御者さんが舌噛んだ――というか、さすが御者さんだ。
幌で四方を閉じていても、どっちに向かっているかわかるんだな。
メリアンがさっき手早くやっていた作業というのは、馬車のくびきに、馬を前後反対に取り付けること。
つまり今、俺たちは、横転した馬車 に向かって、こちらの馬車 のケツを突進させているってわけ。
「舌噛むぞ! 歯ぁ食いしばれっ!」
メリアンの叫びに、心の中でもう食いしばっていると答えたとき、強い衝撃を感じた。
「リテルは御者席から見える範囲を弓で威嚇!」
メリアンが幌の隙間から飛び込んできたかと思うと、数歩で後部――現在は横転馬車 へぶつけた前側へと移動し、幌の隙間から飛び出してゆく。
翻った幌の間にちらりと見えたの横転馬車は街道に対してだいぶ斜めになっていて、あの衝撃でけっこう押せたんだなと。
メリアンはそこへ飛び乗り、両手で小剣を抜いた。
体格の立派なメリアンが手にしているから小さく感じるが、ルブルムの持っている小剣と比べたらもはや長剣と言っても良さそうな長さに、さらに厚みもある重厚な剣。
「声をかけずに入る者は叩け!」
ケティとルブルムがすぐに起き上がり、メリアンが飛び出た衝突側の幌が閉じられる。
「マドハト、俺が出たらここを閉じろ」
俺は御者席側の幌を抜け、弓を構える。
「ど……どうしてぶつかるたぁ思うたら、そういうことかい!」
御者さんまで一緒に出てきた。
「御者さん、危ないから中に戻って!」
「でも旦那ぁ、これじゃ逃げられないでしょうが!」
御者さんは、馬の前後を直そうとしている。
こうなったら援護するしかないか。
敵が近くなったので、線を回転させる『魔力探知機』から範囲円を索敵する『魔力感知』へと戻しつつ、現実の視界と重ねながら矢をつがえた。
● 主な登場者
・有主 利照 /リテル
猿種 、十五歳。リテルの体と記憶、利照 の自意識と記憶とを持つ。魔術師見習い。
ラビツ一行をルブルム、マドハトと共に追いかけている。ゴブリン用呪詛と『虫の牙』の呪詛と二つの呪詛に感染している。
・ケティ
リテルの幼馴染の女子。猿種 、十六歳。黒い瞳に黒髪、肌は日焼けで薄い褐色の美人。胸も大きい。
リテルとは両想い。熱を出したリテルを一晩中看病してくれていた。フォーリーから護衛として合流した。
・ラビツ
久々に南の山を越えてストウ村を訪れた傭兵四人組の一人。ケティの唇を奪った。
フォーリーではやはり娼館街を訪れていたっぽい。
・マドハト
ゴブリン魔法『取り替え子』の被害者。ゴド村の住人で、今は犬種 の体を取り戻している。
リテルに恩を感じついてきている。元の世界で飼っていたコーギーのハッタに似ている。変な歌を知っている。
・ルブルム
魔女様の弟子である赤髪の少女。整った顔立ちのクールビューティー。華奢な猿種 。
槍を使った戦闘も得意で、知的好奇心も旺盛。ケティがリテルへキスをしたのを見てから微妙によそよそしい。
・アルブム
魔女様の弟子である白髪に銀の瞳の少女。鼠種 の兎亜種。
外見はリテルよりも二、三歳若い。知的好奇心が旺盛。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである猿種 。
ルブルムとアルブムをホムンクルスとして生み出し、リテルの魔法の師匠となった。『解呪の呪詛』を作成中。
・ディナ
カエルレウムの弟子。ルブルムの先輩にあたる。重度で極度の男嫌い。壮絶な過去がある。
アールヴを母に持ち、猿種 を父に持つ。精霊と契約している。トシテルをようやく信用してくれた。
・ウェス
ディナに仕えており、御者の他、幅広く仕事をこなす。肌は浅黒く、ショートカットのお姉さん。蝙蝠種 。
魔法を使えないときのためにと麻痺毒の入った金属製の筒をくれた。
・『虫の牙』所持者
キカイー白爵 の館に居た警備兵と思われる人物。
『虫の牙』と呼ばれる呪詛の傷を与える異世界の魔法の武器を所持し、ディナに呪詛の傷を付けた。
・メリアン
ディナ先輩が手配した護衛。リテルたちを鍛える依頼も同時に受けている。
ものすごい筋肉と角と副乳とを持つ牛種 の半返りの女傭兵。
・御者
ディナが管理する娼婦街の元締め、ロズの用意してくれた馬車 の御者。ちょっと訛っている。
・チェッシャー
乗っていた定期便が野盗に襲われ、街道脇へ逃げのびた女の子。猫種 の半返り。動作がいちいちあざと可愛い。
命を助けてくれたリテルへ本気のキスのお礼をお見舞いした。姉がアイシスで娼婦をしている。
・襲撃者たち
森の中を近づいてきたのは猿種 と鼠種 。
横転馬車 の裏側辺りに待機しているのが羊種 と牛種 。
■ はみ出しコラム【ゴブリン歌】
ホルトゥスのゴブリンは歌が好きである。
彼らは人生の大半を楽しいこと――とにかく誰かをからかうこと、からかった相手の無様な姿を歌にすること、その歌を仲間内で共有すること、その歌に合わせて踊ること、あとは繁殖――もちろん異種族とではなくゴブリン同士での繁殖に費やす。
このからかう相手として最も割合が多いのが獣種である。
その理由は、感情豊かで、ゴブリンを見下しているがゆえに、その格下のゴブリンにからかわれたときの反応が、同じゴブリン同士よりも格段に面白いからである。
ゴブリンは仲間同士ではゴブリン語にて会話する。
しかし、獣種の言葉はよく覚えている。
獣種をからかうとき、獣種の言葉でバカにする方が反応が面白いためだ。
ゴブリンの笑いのツボは、獣種の幼児に近い。
転んだり、落としたり、滑ったり、失敗したり、驚くところを見たり、あとは下ネタ。
例えば、地面に落ちている家畜の糞を避けようとして、別の糞に気づかずにそっちを踏み、あまつさえ糞で滑って転んで糞が顔にびたっと付こうものなら大爆笑である。
そんなシーン見たさに、演出を行うこともある。
というかそのための悪戯である。
上記の例の場合では、避けようとしてどけた足の先に突然、糞をそっと置く、など。
そして思い通りの大爆笑シーンを目撃できたら、それを歌にして仲間内で大騒ぎする。
もちろん獣種の耳にも入ることもある。
そのときに、獣種がその歌を理解して、本人ならば激怒したり、他人ならばその被害者をさらにからかったり、それを見てゴブリンたちはさらに笑うのである。
ゴブリンは、自分たちが大爆笑するための努力を惜しまず、そのための魔法さえある。
というより、『取り替え子』以外の魔法は、ほぼ誰かをからかうために使用・発達してきたと言っても過言ではない。
本文中において、哀れなハグリーズがつるつる滑っていた下りも、ゴブリン魔法に寄るものである。
以前、【ハグリーズの前科】コラムにて、ハグリーズが若い未亡人と不倫していた件を取り上げたが、マドハトが今回歌っていた歌は、森の中で密会していたハグリーズがズボンを下ろしていざことに及ぼうとしたとき、地面がつるつるになり「立っているのに立てない」という状況を笑った歌である。
ケティの声で目を覚ます――俺、寝ていたのか?
いつの間に――飛び起きて周囲を確認する。
マドハトとルブルムは後方を警戒していて、メリアンは前方を――街道の先の方で
え?
馬車ってそんなコロコロ街道に横転しているもの?
それとも俺は時間を巻き戻す能力でも――いや、そうじゃない。
街道の両側はいつの間にかほぼ森になっているし、
そう、置かれている、という印象。
車軸の折れた車輪が手前に散らばっているのだが、どれも綺麗に上向きになった画鋲みたいな状態で。
さっきとは状況が明らかに違う。
「メリアン……
「いや、半年に二度でも多い方だ。さっきの連中、金持ちの商人がどうこう言っていただろう。そいつを狙って片っ端から襲撃して回ったってんなら筋は通るが……」
「でもそれなら、フォーリーへ向かってる定期便が通り過ぎた後で道を塞ぐってのも変ですよね?」
さっきのは横転したのを放置って感じだったけど、今度のはがっつりバリケード作りましたって感じ。
「ああ、そうなんだよ。考えられるとしたら、その商人の救出を邪魔する目的とかかな」
だとしたら、付近には見張りが残っている可能性は大きい。
「メリアン、また偵察しながら近づいてみますか?
「それは慎重になった方がいい。さっきの襲撃場所とこの場所と、両方とも同じ犯人の仕業だとしたら敵の人数は少なくない」
「メリアン、こういうとき、いつもはどうしてる?」
俺とメリアンとの会話にルブルムが混ざってきた。
「普通は、危険に首を突っ込んで得することは何もない。最寄りの監理官が居る街や村まで引き返して報告すれば領兵が派遣される。特にここはフォーリーから首都キャンロルや隣の領都アイシスへと通じる主要な街道だ。もう少し行けばクスフォード領と王国領との領境だし砦だってある。そいつらとやり合う覚悟があるってんなら、単なる盗賊なんかじゃない。一つの軍隊って言っても言い過ぎじゃあない。だがそれならいくら裕福っつっても個人の商人レベルを相手にするのも妙だ……この辺にある村を一つまるごと襲うくらいの……」
なんだか物騒な話になってきた。
「ちなみに、普通じゃない方法ってのは……」
「押し通る」
うん。予想通りです。
でもメリアンがいくら強いとは言っても、相手の人数や武装の度合いも分からない。
それにこちらは戦闘の素人ばかり。
メリアンの足を引っ張るのが目に見えている。
かと言って、今から引き返すという選択肢も取りたくはない。
ラビツ一行との距離は開くし、何より今からだとフォーリーに戻っても深夜過ぎだろう。
それに、さっきのチェッシャーたちの乗っていた定期便を横転させた連中が――。
「既に挟まれている恐れもありますよね?」
「それは否定しない」
だとしたら突破するってのも手なのか?
「メリアン、砦とフォーリーなら砦の方が近いですよね?」
「圧倒的にな」
「知らせるのって、やっぱり直接行くしかないですよね……」
あの横転馬車を燃やしたら狼煙代わりになるかなと一瞬考えもしたが、あそこで盛大なキャンプファイヤーやったら、近くの森へ飛び火しかねない。
森やその近くでの火の扱いについては注意に注意を重ねろと、マクミラ師匠にさんざん叩き込まれたからなぁ。
「旦那がたぁ……ここで野営ってのだけはご勘弁願いますよ……」
なかなか結論が出ないことにシビレをきらしたのか、御者さんがボヤく。
「御者さん、ここらへんの道幅なら、馬車の向きを反対向きに戻すのって、すぐにできますか?」
「うーん……馬をいったん外すんなら……あっ、あそこに見える小道を使うなんてどぅですかい? 入ってって、広い場所がありゃぁそこで引き返すんでさぁ」
小道?
……確かにある。
街道から入り込む小道はここからでも見えるけど――横転馬車からやけに近い。
それが引っかかる。
そこを使わざるを得ないような状況が。
逆にその小道があったからこそ、あえてこの場所を封鎖したとも考えられる――だとしたら、今度こそ罠だよね?
「ね、あっちって山の方だよね? あの山々は、向こう側へ抜けられる道なんてないって聞くけれど」
ケティも話に混ざってくる。
「しかも
メリアンがおどけて肩をすくめる。
街道から右、つまり東の方には「マンティコラの歯」と呼ばれる険しい山脈が連なっている。
マンティコラというのは、元の世界でマンティコアと呼んでいたあの魔獣とほぼ同じ存在っぽい。
ただしその尾の先には毒針があり、歯は三列に並んでいて、獣種を好んで喰らうという。
ラトウィヂ王国の東側をほぼ全て塞いでいるこの山脈は牙のように鋭い山々が幾重にも重なっている様子から、その危険性込みで「マンティコラの歯」と名付けられた、みたいなことをリテルは親から聞いている。
なぜかというとストウ村では、小さな子が夜遅くまで起きていると。マンティコラの歯山脈からマンティコラが飛んできて喰われてしまうぞ、などとしつけ用に用いられる魔獣としても馴染み深いからだ。
ドラコというのもドラゴンのことだし、地球で知名度の高いモンスター名が登場すると心なしか嬉しいのが不思議だ。
「ドラコ怖いです!」
マドハトがそう言うと、ケティもモソモソと「マンティコラも怖い」とか言い出す始末。
「そうだな。あの子らが本当にフォーリーへ向かったんなら、今頃、フォーリーの領兵どもが横転した定期便を回収しに向かって来ているかもしんないね。だとしたら、挟み撃ちになるのは、フォーリー側からあたしらを追っかけてくる連中さ」
メリアンがそう言い切ると、ケティやマドハトはちょっとホッとする。
「それなら、ここでもう方向転換しちゃう方がいいかもですね」
距離感からすると決してそんな楽観視はできないと思うのだが、俺たちを安心させようとして言っているのかもしれないのであえて賛同しておく。
「いいね、リテル。あたしも賛成だ……ってことで、御者さーん。あんたの腕なら小道なんて入らずに、ここでも切り返しできるって!」
メリアンが笑顔で御者さんの背中をパンと叩く。
「偵察はさっき同様、あたしとリテルとで行く。
「道幅狭いところでの反転は面倒なんすがね……」
「まぁまぁ、そこをやっちゃうのが、あんたの腕のすごいところだろ?」
御者さんはまんざらでもない感じで、
確かに時間がかかっている印象。
それを興味深そうに見ているマドハトごしに、馬の動きのさらに向こう、森の方へ『魔力感知』を集中している俺の右手を、誰かがつかんだ。
ケティだった。
「リテルはさ……なんか、変わったよね」
「え?」
動揺を表に出さないようにしたものの――ケティはリテルと
「昔はさ、いつもビンスンさんや私の後ろについてまわるばかりだったのに……いつの間にか一人で歩き出しちゃってるんだもんね。覚えている? 私たちにいっつも置いてくよーって言われて、必死においかけてきた頃のこと」
それはリテルの記憶の中にある。
リテルがまだ子どもだった頃、子どもだけのグループは、リテルの兄であるビンスン、ビンスンと同い年のエクシあんちゃん、それからケティの三人が輪の中心だった。
リテルの下はちょっと歳が離れていたから、幼い連中のお守りをしなくてよいときはリテルも含めた四人で遊ぶことになる――となると四人の中では一番下であるリテルは何につけてもびりっかすで……。
「それにしてもさ、メリアンと仲良くなるの早いよね。さっきのさ、チェッシャーちゃんだっけ? なんかすごい熱い視線でリテルのこと見つめてたし、どさくさまぎれに大好きとか言ってたような気がするんだけどさ……リテル、前はそんな感じじゃなかったよね? なんか、変わっちゃった気がして……ごめんね」
俺はリテルだよと、そう答えたいのに、言葉がとっさに出てこない。
「あんな綺麗な魔女さまのところで……アルブムちゃんも可愛いかったし、ルブルムさんだって美人さんだよね……私のリテルは……そんな、女性に慣れてなかったっていうか」
「な、慣れてなんか……ないよ……必死なだけ……だから」
その言葉はつかえずに出た。
「そ、そうだよね……ごめんね。なんか、リテルが、遠くなっちゃった気がして」
そう言うとケティは俺の頬にキスをして、荷台の後方へ移動する――のを目で追って、ルブルムがこっちをずっと見つめていたことに気付く。
感情の見えない表情だが、俺的にはなんか気まずい。
ルブルムへ何か声をかけた方がいいのか迷っていた俺の視界が、マドハトの頭で塞がれた。
「僕も! リテルさまの顔! なめたいです!」
ぴょんぴょんと飛び跳ねようとするマドハトの頭を、ぎゅっと押さえつける。
また面倒な感じに――おや、おとなしくなった?
「これ、落ち着くです!」
俺の手の下で、マドハトは自ら頭を動かし、撫でられている感を出す。
そういえばハッタも、頭撫でられるの好きだったっけ。
「おー! さすが熟練の御者さん! 見事な腕前だねぇ!」
「ま、まぁな。こんくれぇ簡単ですぜ」
「御者さん、あんたも中に入っててくれ」
メリアンは馬車の前側の幌も閉じようとする。
「あっしもすか?」
「ああ。こっちが逃げる素振りを見せたら……弓を持っているやつが攻撃してくるかもしれない……念のためさ。射的の的にゃなりたかないだろ?」
「そ、そりゃそうでがすよ」
御者さんは御者席から降りて馬車の中へ。
「ケティ、あたしとリテルが出たら、ここもしっかり幌を閉じとくれ」
「わかった……けど、リテルとメリアンは大丈夫?」
「ああ。危険を感じたら、戻ってくるさ……あと、幌は目隠しにはなっても、矢を防ぐ盾にはならない。なにか異変を感じたら、すぐに馬車の床へ伏せてくれ……あとはえーと、マドハト」
「はいです!」
「歌は歌えるか?」
歌?
「歌えるです!」
「あたしらは降りたらすぐに森に潜み、森の中を通って偵察に向かう。でもこっちは気付いてませんよって相手を油断させるために歌うのさ。陽気なやつをいくつか頼むよ」
「はいです! じゃあ……晴ーれたー! 昼さーがりっ! 粉挽きのハグリーズがー! 向かうよはるばる魔女の森へー!」
これ、うちの村のことを歌っているのか?
「リテル、早く」
「はいっ」
馬車の外へ出ると、ケティが幌を閉じ際、俺に向かって手を振って――その横でルブルムは俺から目を反らした。
なんかいやだな、こんなタイミングでギクシャクするなんて。
「糸杉のー木陰ーにー! そこにっ! 隠れるはっ! 逢引のっ! あーいーてーっ!」
メリアンが俺の肩を軽く小突く。
「あ、ごめんなさい」
「いいさ。ケティもルブルムも、いい子だよね。迷うのも分かるさ」
その言葉は、やけに声のボリュームが控えめだった。
だから俺は変に反論はせず、メリアンの目をじっと見つめた。
「あたしがこの作業を終えるまで、チェッシャーの時みたく周囲への警戒を頼む」
小さな声で了承を告げると、メリアンはさっそくその「作業」とやらを開始する――え、何やってんの?
俺の表情を見たメリアンが周囲を指差す。
は、はいっ。そうですね。ちゃんと集中しよう。
マドハトの歌に惑わされることもなく、ケティとルブルムのこともいったん置いといて、俺は『魔力感知』の範囲を広げる。
チェッシャーの『死んだふり』みたいな魔法が使われている可能性も考慮して丁寧に、遠くまで。
例の改良型の『魔力感知』――『魔力探知機』を。
……居るな?
しかも森の中を近づいてきているような。
慌ててメリアンの目を見ると、指で何かを指示しているのは――俺が、
でも
メリアンがさっき「押し通る」って言ってたアレは、そういうことなのか。
俺は弓を構えやすい姿勢のまま、
中へ入った途端、ケティがハンマーを振りかぶっていて。
「ま、待て! 俺だって!」
「リテル? 声もかけないで入ってくるから、てっきり」
ルブルムは『魔力感知』で俺だとわかるはずだからと――ケティが普通の人だというのが思考から漏れてた。
いけないな。こんなんじゃリテルの大事なケティを、守れないぞ。
「来るよ! 床に伏せてっ! 御者はあたしがやるから!」
外のメリアンの言葉を皆に伝え、
木の匂いが近い。
「哀れハグリーズぅ 立っているのに立てなくてぇ ドッロドローのつーるつる!」
「マドハト、歌はもういい!」
外を移動してくる
二人――いや四人。
手前の二人――森の中を近づいてくるのは
もう二人は横転
動いてない方の二人の
床に貼り付いているので、振動がダイレクトに響く。
舌を噛まないように歯を食いしばったままだから会話も不可能だ。
「ど、どっちにんグッ」
ほら、御者さんが舌噛んだ――というか、さすが御者さんだ。
幌で四方を閉じていても、どっちに向かっているかわかるんだな。
メリアンがさっき手早くやっていた作業というのは、馬車のくびきに、馬を前後反対に取り付けること。
つまり今、俺たちは、横転した
「舌噛むぞ! 歯ぁ食いしばれっ!」
メリアンの叫びに、心の中でもう食いしばっていると答えたとき、強い衝撃を感じた。
「リテルは御者席から見える範囲を弓で威嚇!」
メリアンが幌の隙間から飛び込んできたかと思うと、数歩で後部――現在は横転
翻った幌の間にちらりと見えたの横転馬車は街道に対してだいぶ斜めになっていて、あの衝撃でけっこう押せたんだなと。
メリアンはそこへ飛び乗り、両手で小剣を抜いた。
体格の立派なメリアンが手にしているから小さく感じるが、ルブルムの持っている小剣と比べたらもはや長剣と言っても良さそうな長さに、さらに厚みもある重厚な剣。
「声をかけずに入る者は叩け!」
ケティとルブルムがすぐに起き上がり、メリアンが飛び出た衝突側の幌が閉じられる。
「マドハト、俺が出たらここを閉じろ」
俺は御者席側の幌を抜け、弓を構える。
「ど……どうしてぶつかるたぁ思うたら、そういうことかい!」
御者さんまで一緒に出てきた。
「御者さん、危ないから中に戻って!」
「でも旦那ぁ、これじゃ逃げられないでしょうが!」
御者さんは、馬の前後を直そうとしている。
こうなったら援護するしかないか。
敵が近くなったので、線を回転させる『魔力探知機』から範囲円を索敵する『魔力感知』へと戻しつつ、現実の視界と重ねながら矢をつがえた。
● 主な登場者
・
ラビツ一行をルブルム、マドハトと共に追いかけている。ゴブリン用呪詛と『虫の牙』の呪詛と二つの呪詛に感染している。
・ケティ
リテルの幼馴染の女子。
リテルとは両想い。熱を出したリテルを一晩中看病してくれていた。フォーリーから護衛として合流した。
・ラビツ
久々に南の山を越えてストウ村を訪れた傭兵四人組の一人。ケティの唇を奪った。
フォーリーではやはり娼館街を訪れていたっぽい。
・マドハト
ゴブリン魔法『取り替え子』の被害者。ゴド村の住人で、今は
リテルに恩を感じついてきている。元の世界で飼っていたコーギーのハッタに似ている。変な歌を知っている。
・ルブルム
魔女様の弟子である赤髪の少女。整った顔立ちのクールビューティー。華奢な
槍を使った戦闘も得意で、知的好奇心も旺盛。ケティがリテルへキスをしたのを見てから微妙によそよそしい。
・アルブム
魔女様の弟子である白髪に銀の瞳の少女。
外見はリテルよりも二、三歳若い。知的好奇心が旺盛。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである
ルブルムとアルブムをホムンクルスとして生み出し、リテルの魔法の師匠となった。『解呪の呪詛』を作成中。
・ディナ
カエルレウムの弟子。ルブルムの先輩にあたる。重度で極度の男嫌い。壮絶な過去がある。
アールヴを母に持ち、
・ウェス
ディナに仕えており、御者の他、幅広く仕事をこなす。肌は浅黒く、ショートカットのお姉さん。
魔法を使えないときのためにと麻痺毒の入った金属製の筒をくれた。
・『虫の牙』所持者
キカイー
『虫の牙』と呼ばれる呪詛の傷を与える異世界の魔法の武器を所持し、ディナに呪詛の傷を付けた。
・メリアン
ディナ先輩が手配した護衛。リテルたちを鍛える依頼も同時に受けている。
ものすごい筋肉と角と副乳とを持つ
・御者
ディナが管理する娼婦街の元締め、ロズの用意してくれた
・チェッシャー
乗っていた定期便が野盗に襲われ、街道脇へ逃げのびた女の子。
命を助けてくれたリテルへ本気のキスのお礼をお見舞いした。姉がアイシスで娼婦をしている。
・襲撃者たち
森の中を近づいてきたのは
横転
■ はみ出しコラム【ゴブリン歌】
ホルトゥスのゴブリンは歌が好きである。
彼らは人生の大半を楽しいこと――とにかく誰かをからかうこと、からかった相手の無様な姿を歌にすること、その歌を仲間内で共有すること、その歌に合わせて踊ること、あとは繁殖――もちろん異種族とではなくゴブリン同士での繁殖に費やす。
このからかう相手として最も割合が多いのが獣種である。
その理由は、感情豊かで、ゴブリンを見下しているがゆえに、その格下のゴブリンにからかわれたときの反応が、同じゴブリン同士よりも格段に面白いからである。
ゴブリンは仲間同士ではゴブリン語にて会話する。
しかし、獣種の言葉はよく覚えている。
獣種をからかうとき、獣種の言葉でバカにする方が反応が面白いためだ。
ゴブリンの笑いのツボは、獣種の幼児に近い。
転んだり、落としたり、滑ったり、失敗したり、驚くところを見たり、あとは下ネタ。
例えば、地面に落ちている家畜の糞を避けようとして、別の糞に気づかずにそっちを踏み、あまつさえ糞で滑って転んで糞が顔にびたっと付こうものなら大爆笑である。
そんなシーン見たさに、演出を行うこともある。
というかそのための悪戯である。
上記の例の場合では、避けようとしてどけた足の先に突然、糞をそっと置く、など。
そして思い通りの大爆笑シーンを目撃できたら、それを歌にして仲間内で大騒ぎする。
もちろん獣種の耳にも入ることもある。
そのときに、獣種がその歌を理解して、本人ならば激怒したり、他人ならばその被害者をさらにからかったり、それを見てゴブリンたちはさらに笑うのである。
ゴブリンは、自分たちが大爆笑するための努力を惜しまず、そのための魔法さえある。
というより、『取り替え子』以外の魔法は、ほぼ誰かをからかうために使用・発達してきたと言っても過言ではない。
本文中において、哀れなハグリーズがつるつる滑っていた下りも、ゴブリン魔法に寄るものである。
以前、【ハグリーズの前科】コラムにて、ハグリーズが若い未亡人と不倫していた件を取り上げたが、マドハトが今回歌っていた歌は、森の中で密会していたハグリーズがズボンを下ろしていざことに及ぼうとしたとき、地面がつるつるになり「立っているのに立てない」という状況を笑った歌である。