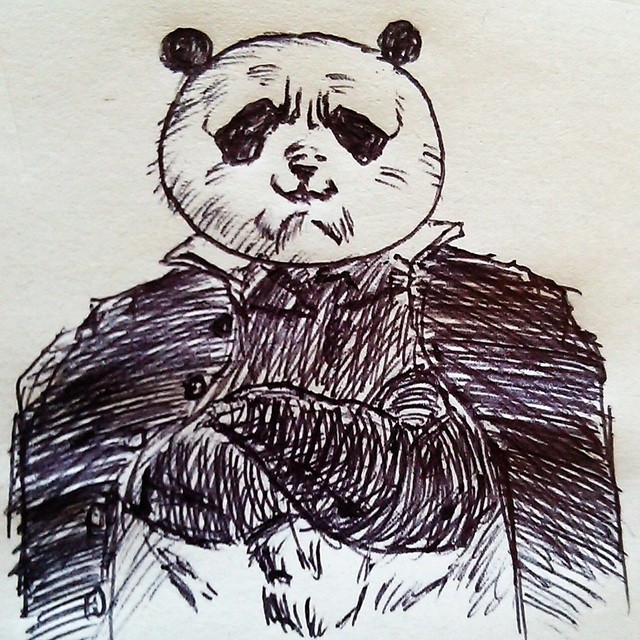#37 深夜の全裸勉強会
文字数 5,862文字
「ディナ先輩……もしかしてなのですが、この呪詛の傷、ディナ先輩の腕から脇腹へ移動したりしませんでした?」
傷のムカデの動きは皮膚の表面を移動するだけだと思っていたのだが、その皮膚同士が接触している場合、そこを渡ることができるような気がする。
腕から腹へ、腹からまた別の腕へ。
「それは考えたことなかったが……そう言われれば確かに」
傷のムカデが胴から腕へと移ろうとした瞬間、ディナ先輩は素早く肘を上げた――傷のムカデは弾かれたように胴体へと戻る。
「あっ、移らずに戻りましたっ」
「半分ほど移った状態だとどうなる?」
肘を体にぴったりとつけ、傷のムカデが移ろうとするのを待つ。
そして傷のムカデが移り始め、今度は半身ぐらいが移ったタイミングで、肘をパッと持ち上げた……移った先の方へ一瞬にして移動する。
「捕まえられないもんですかね……ディナ先輩、今度は移り初めて、四分の一くらいのとこで肘上げお願いします」
「呪詛をか? 面白いことを考える」
「呪詛っていうより、だんだんムカデに見えてきちゃっ……あ、また!」
ディナ先輩の胸から腕へ傷のムカデが移ろうとした瞬間、ディナ先輩がパッと肘を上げる。
すると傷のムカデはその先頭部分をディナ先輩の胸側へ戻そうとする。
「またくっつけて!」
ディナ先輩が再び脇を閉めると、傷のムカデは再び、腕の側へ移り始めた。
「ディナ先輩、試してみたいことができました。試してみてもよいですか?」
「試せるような魔法を思いついたつもりか? 呪詛は構成魔法の全てを把握しなければ解除できないのだぞ。カエルレウム様でさえも把握できない異界の魔法が使われているこの呪詛に」
「お願いします!」
魔法のイメージを固め、軽めの消費命 として一ディエスだけを集中する。
ディナ先輩は俺のことを信用してくれたのか、肘と脇とを再び閉じてくださった。
「失礼します! 『同じ皮膚』!」
ディナ先輩の肘と脇との隙間に俺の左手を差し込みながら、創ったばかりの魔法を唱えてみた。
触れている相手の皮膚を、自分の皮膚にかぶせる、そういう認識の魔法。
傷のムカデは相変わらずディナ先輩の皮膚の上をうろつきまわり、やがて俺の皮膚の上を通っ――反射的に放しそうになった左手を、右手で抑え込む。
そのくらい凄まじい激痛。
左手の甲へ、たくさんの釘を打ち込まれたような鋭い痛み。
その痛みが俺の腕を登ってくる。
俺の手の甲から、手首、そして、肘の方へ、と。
目でも、見える。
傷のムカデが、俺の手を、這い登るのが。
のこぎりで、引かれ、続けてる、みたい、芯まで響く、痛み。
奥歯が、壊れるかもって、くらい、歯を食いしばり、傷ムカデの、ほぼ全てが、移動しきった、とき、ディナ先輩から、手を、放した。
限界は、超えて、いる。
傷ムカデが、這うその場所、その、場所に、信じられない、痛みが、襲う。
我慢、できず、ベッドの、上で、のたうち、回った。
「トシテルっ! お前っ!」
なに、この激、痛。
ディナ先輩、ずっと、これ、耐えて、たの?
ベッド、から、体、落ちた、けど、腕の、痛さ、しか、感じねぇ。
フォーク、突き立て、られて、ぐちゃ、ぐちゃ、混ぜられ、てる、みたいな。
痛ってぇぇぇぇ、より、もっと、痛い、という、言葉、知って、たら、使い、たい。
痛みで、呼吸が、浅く、なる。
「トシテル!」
「じゅ、呪詛を、騙して、やり、ました」
笑顔を、浮かべた、つもり。
「おかしい。そんなに痛みは続かないはずだ……そうか、トシテル、お前、魔術特異症だったろう。呪詛が変異したのか」
マジ、か。
痛み、全然、慣れ、ない。
こーゆー、のって、慣れるって……ああ!
ほら、なん、だっけ、えっと。
消費命 、集中。
「『脳内モルヒネ』」
……忘れていた呼吸を、取り戻す。
痛みが、だいぶ治まった。
まだ洗濯バサミを付けられているくらいの痛さはあるけれど、さっきのに比べたら全然へっちゃら。
「トシテル、なんだ今のは……」
「俺の手を、ディナ先輩の手だと思わせてやったんです。触れた皮膚と、同じ皮膚に偽装する魔法にしてみました」
「二つ目のは何だ。痛みを奪ったのか? それとも封印か?」
「いえ、呪詛に何かしたんじゃなく、自分の方の痛みをごまかしました」
「どうやって?」
「生物がもともと持っている能力で、痛みに襲われたとき、脳内の物質が出て」
「脳内の物質?」
「あ、ええと」
ドーパミンとかエンドルフィンとかいう単語は聞いたことがあるけれど、どれがどれだったっけかな。
マンガとか小説とかだと、異世界転生の主人公はこういう知識をちゃんと覚えているよな。
俺は全然そんなんじゃない。
だいたい検索すれば簡単に調べられたから。
「チキュウでは、魔法がない分、物質的なものへの研究が進んでます。人間の内側の構造や機能がかなり解析されているんです。目では見えないくらい小さな機能の研究も進んでいて……だから、俺の使った『生命回復』は、一ディエス分の消費命 でも回復効果が大きいようです」
「なるほど。魔法を除いた思考で世界の真理 に近づくというのは面白いものだな。それで、脳の中の痛みを和らげる物質の存在を知っていたトシテルは、その物質の活用を思考したというわけか」
「完全に、ではないですが、これなら耐えられます」
不意にディナ先輩に抱きしめられた。
「トシテル、感謝する。この呪詛のせいで、獣種の魔法の使用は今まで最小限に抑えてきた。本当はもっと試したいこともたくさんあったのだが」
「い、いえ、光栄です、じゃなくて!」
慌ててディナ先輩から離れる。
「またディナ先輩の体に戻ってしまう恐れが」
「それはそれで構わぬ。トシテルのような未熟者がそれを抱えたままでルブルムを守れるかと考えると不安しかないからな。そうだ……少し待て」
いったん部屋の外へと出たディナ先輩が、しばらくして袋のようなものを持って戻ってきた。
「豚皮の袋だ。この表面に『同じ皮膚』とやらをかけてみろ」
そうか、俺に移せたということは、別の皮膚に閉じ込めることもできるかもしれないのか……と、鼻息荒く挑戦してみたが失敗。
生きていないとダメなのかな。
ディナ先輩へもう一度戻す実験も失敗。
というかそもそも俺の腕から胴や別の腕への移動すらしてくれない。
「魔術特異症で移動法則が制限されるよう変異したのかもしれない……ということは」
ディナ先輩はナイフを取り出し、俺の腕へ突然、斬りつけた。
『脳内モルヒネ』が効いているのか、痛みはほとんどない。ペンで線を描かれている、そんな変な感じ。
「見ろ、トシテル。お前へ移った『虫の牙』の傷は、途切れた皮膚を越えられなくなったようだぞ」
傷ムカデが左腕に移動しているうちに、俺の肘から下あたりに腕をぐるりと一周する傷がつけられた。
傷ムカデはそこから出ては来ない。
顔とか背中とか他の敏感なところを這いずり回られるよりはかなりマシだ。
「普段は布でも巻いておけ」
左手に呪詛の動く傷。それを隠す包帯。うわ、なんだこの中二病設定は……大きなため息がでかけた瞬間、思わずそれを飲み込んでしまう。
ルブルムの声で。
「ずるい! 私には見せないのに、ディナ先輩とは見せあっている!」
部屋の入り口に、いつの間にかルブルムが立っていた。
言われてみればディナ先輩は上半身裸のままだし、俺も検証の都合上、上半身は脱いでいた。
「い、いや、これはっ……そ、それに下は見せてないからっ」
「そうか。そちらの耐性もつけておく必要があるか」
ディナ先輩?
「だ、大丈夫です。この痛みでそういう気持ち飛びますから!」
「私は、トシテルの見てみたい。私も脱げばいいのか?」
ルブルム?
慌ててルブルムの手を止める。
「そうだな。慣れておいた方がいい。ルブルムも脱ぐといい」
ディ、ディナ先輩?
「トシテル、お前も脱げ」
これ、どういう状況?
「そ、それよりももっと今しかできないことを、調査! 調査を先に!」
「何の調査だ?」
ルブルムが食いついた!
「ほら、この、ムカデみたいな傷」
「トシテル、腕を怪我している」
魔法代償を集中しようとするルブルムを慌てて制する。
「この傷は、当分は治さなくていいんだ」
「そうだな。ルブルムにも話しておいた方が良いかもしれない。ルブルムは人の悪意に触れてなさすぎる。ここから北へ向かうなら、危険に対するある程度の心構えが必要になるだろうからな」
ディナ先輩は、さっきの話をもう一度、ルブルムへと話す。
俺に話した時よりも多少、生々しく。
その後、『虫の牙』の傷……というか俺が実験台になる研究は、三人で続けることになった……全裸で。
うん。全裸で。
股間に血液が集中しない呪詛のおかげでなんとかなったようなものの……おかげで、自分の中の超紳士スイッチを入れる感覚がちょっとわかった。
検証結果をまとめてみると、良いニュースと悪いニュースがあった。
まず悪い方。
この傷のムカデは、本来は魔法代償を消費した一瞬しか咬まなかったらしいが、俺の魔術特異症はその魔法の効果期間中、ずっと継続させるようにしてしまったっぽい。
効果時間が一瞬である魔法や、効果時間があっても他の人にかけた場合は、咬まれる激痛も一瞬だが、俺自身にかけた場合、効果時間が切れるまでずっと痛み続ける。
最初に『脳内モルヒネ』を使わないとしんどいことになる――けど、奇襲をかける場合なんかだと、相手に気付かれるのを避けるため、初手は我慢しなきゃ――という。
次に良い方。
俺の魔法効果が増大しているのだ。
呪詛が伝染するには、呪詛により被るだけの不利益を受け入れようと思えるだけの利益がないといけない。
例の「ひとつまみの祝福」ってやつだ。
この呪詛の場合、どのような仕組みかはわからないが、俺の使用する魔法効果が増大する方向に働いているようだ。
ただし魔法発動時、咬まれる激痛に負けて魔法代償を消費する前に手放しちゃうと、その勢いに引っ張られて追加消費されてしまう魔法代償もより大きくなるという。
「でも『虫の牙』という武器……戦闘中に相手を強化する呪詛をかけるとか、設計した人の思考はとんでもないですね」
「いるんだよ。強い者と戦いたい欲求にかられている戦闘狂の類いは」
戦闘狂……。
キカイーの屋敷に居た、強い警備兵。
もしもそいつを見つけたとして、今の俺では全く歯が立たない……可能性が高いんだろうな。
俺はもっと強くならないといけない。
「くしゅんっ」
可愛いくしゃみをしたのは、ルブルムだった。
● 主な登場者
・有主 利照 /リテル
猿種 、十五歳。リテルの体と記憶、利照 の自意識と記憶とを持つ。魔術師見習い。
ラビツ一行をルブルム、マドハトと共に追いかけている。ゴブリン用呪詛と『虫の牙』の呪詛と二つの呪詛に感染している。
・ケティ
リテルの幼馴染の女子。猿種 、十六歳。黒い瞳に黒髪、肌は日焼けで薄い褐色の美人。胸も大きい。
リテルとは両想い。熱を出したリテルを一晩中看病してくれていた。リテルが腰紐を失くしたのを目ざとく見つけた。
・ラビツ
久々に南の山を越えてストウ村を訪れた傭兵四人組の一人。ケティの唇を奪った。
フォーリーではやはり娼館街を訪れていたっぽい。
・マドハト
ゴブリン魔法『取り替え子』の被害者。ゴド村の住人で、とうとう犬種 の体を取り戻した。
リテルに恩を感じついてきている。元の世界で飼っていたコーギーのハッタに似ている。街中で魔法を使い捕まった。
・ルブルム
魔女様の弟子である赤髪の少女。整った顔立ちのクールビューティー。華奢な猿種 。
槍を使った戦闘も得意で、知的好奇心も旺盛。念願のリテルとの見せ合いっこがようやくできた。
・アルブム
魔女様の弟子である白髪に銀の瞳の少女。鼠種 の兎亜種。
外見はリテルよりも二、三歳若い。知的好奇心が旺盛。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである猿種 。
ルブルムとアルブムをホムンクルスとして生み出し、リテルの魔法の師匠となった。『解呪の呪詛』を作成中。
・ディナ
カエルレウムの弟子。ルブルムの先輩にあたる。重度で極度の男嫌い。壮絶な過去がある。
アールヴを母に持ち、猿種 を父に持つ。精霊と契約している。トシテルをようやく信用してくれるように。
・ウェス
ディナに仕えており、御者の他、幅広く仕事をこなす。肌は浅黒く、ショートカットのお姉さん。蝙蝠種 。
リテルに対して貧民街 での最低限の知識やマナーを教えてくれた。
・『虫の牙』所持者
キカイー白爵 の館に居た警備兵と思われる人物。
『虫の牙』と呼ばれる呪詛の傷を与える異世界の魔法の武器を所持し、ディナに呪詛の傷を付けた。
■ はみ出しコラム【入れ墨】
魔法が存在するホルトゥスにおいて、入れ墨は呪術的な意味合いでは使用されない。
また、魔法で消し込むことも可能であるため、通常の入れ墨は犯罪者の印としての使用もない。
入れ墨には、「皮膚に傷を付けて色を入れるもの」と「染料で人体を染めるもの」の二種類がある。
前者をスティグマタ、後者をティンクトゥーラと呼ぶ。
共に発祥はホルトゥスの南方地域である。
・スティグマタ
サボテン類の針を使用して墨を入れる。
発祥の地においては、成人した者が、家を現す記号なり模様なりを体の特定の部位に入れた。
その痛みに耐える通過儀礼としての意味合いも持つ。
このスティグマタがもとになり、実績紋というモノができるようになった。
※ 実績紋
【依頼斡旋屋】の項目でも触れたが、粉末状の魔石を用い、功績や犯罪歴等が記載される。
魔術師組合でないと内容判別ができないため、大きな街でしか確認に使用されない。
・ティンクトゥーラ
ヘナと呼ばれる植物をもとに作られた染料で身体を染める。
元々は、体を冷やす効果のあるヘナを、夏季の暑さ対策としてティンクトゥーラを施すようになった。
やがてそれがファッションとして用いられるようになり、スティグマタと異なり、時間が経てば消えるティンクトゥーラは、ホルトゥスでも広く用いられるようになった。
最初の流行は、都市部の貴族たちの間であったが、その後、公娼たちが淫猥なファッションとして用いるようになると、貴族たちはこれを用いなくなり、現在ではティンクトゥーラは娼婦の象徴として認識されている。
ただし、マニキュアや白髪染めとしてであれば、公娼でなくとも使用する。
傷のムカデの動きは皮膚の表面を移動するだけだと思っていたのだが、その皮膚同士が接触している場合、そこを渡ることができるような気がする。
腕から腹へ、腹からまた別の腕へ。
「それは考えたことなかったが……そう言われれば確かに」
傷のムカデが胴から腕へと移ろうとした瞬間、ディナ先輩は素早く肘を上げた――傷のムカデは弾かれたように胴体へと戻る。
「あっ、移らずに戻りましたっ」
「半分ほど移った状態だとどうなる?」
肘を体にぴったりとつけ、傷のムカデが移ろうとするのを待つ。
そして傷のムカデが移り始め、今度は半身ぐらいが移ったタイミングで、肘をパッと持ち上げた……移った先の方へ一瞬にして移動する。
「捕まえられないもんですかね……ディナ先輩、今度は移り初めて、四分の一くらいのとこで肘上げお願いします」
「呪詛をか? 面白いことを考える」
「呪詛っていうより、だんだんムカデに見えてきちゃっ……あ、また!」
ディナ先輩の胸から腕へ傷のムカデが移ろうとした瞬間、ディナ先輩がパッと肘を上げる。
すると傷のムカデはその先頭部分をディナ先輩の胸側へ戻そうとする。
「またくっつけて!」
ディナ先輩が再び脇を閉めると、傷のムカデは再び、腕の側へ移り始めた。
「ディナ先輩、試してみたいことができました。試してみてもよいですか?」
「試せるような魔法を思いついたつもりか? 呪詛は構成魔法の全てを把握しなければ解除できないのだぞ。カエルレウム様でさえも把握できない異界の魔法が使われているこの呪詛に」
「お願いします!」
魔法のイメージを固め、軽めの
ディナ先輩は俺のことを信用してくれたのか、肘と脇とを再び閉じてくださった。
「失礼します! 『同じ皮膚』!」
ディナ先輩の肘と脇との隙間に俺の左手を差し込みながら、創ったばかりの魔法を唱えてみた。
触れている相手の皮膚を、自分の皮膚にかぶせる、そういう認識の魔法。
傷のムカデは相変わらずディナ先輩の皮膚の上をうろつきまわり、やがて俺の皮膚の上を通っ――反射的に放しそうになった左手を、右手で抑え込む。
そのくらい凄まじい激痛。
左手の甲へ、たくさんの釘を打ち込まれたような鋭い痛み。
その痛みが俺の腕を登ってくる。
俺の手の甲から、手首、そして、肘の方へ、と。
目でも、見える。
傷のムカデが、俺の手を、這い登るのが。
のこぎりで、引かれ、続けてる、みたい、芯まで響く、痛み。
奥歯が、壊れるかもって、くらい、歯を食いしばり、傷ムカデの、ほぼ全てが、移動しきった、とき、ディナ先輩から、手を、放した。
限界は、超えて、いる。
傷ムカデが、這うその場所、その、場所に、信じられない、痛みが、襲う。
我慢、できず、ベッドの、上で、のたうち、回った。
「トシテルっ! お前っ!」
なに、この激、痛。
ディナ先輩、ずっと、これ、耐えて、たの?
ベッド、から、体、落ちた、けど、腕の、痛さ、しか、感じねぇ。
フォーク、突き立て、られて、ぐちゃ、ぐちゃ、混ぜられ、てる、みたいな。
痛ってぇぇぇぇ、より、もっと、痛い、という、言葉、知って、たら、使い、たい。
痛みで、呼吸が、浅く、なる。
「トシテル!」
「じゅ、呪詛を、騙して、やり、ました」
笑顔を、浮かべた、つもり。
「おかしい。そんなに痛みは続かないはずだ……そうか、トシテル、お前、魔術特異症だったろう。呪詛が変異したのか」
マジ、か。
痛み、全然、慣れ、ない。
こーゆー、のって、慣れるって……ああ!
ほら、なん、だっけ、えっと。
「『脳内モルヒネ』」
……忘れていた呼吸を、取り戻す。
痛みが、だいぶ治まった。
まだ洗濯バサミを付けられているくらいの痛さはあるけれど、さっきのに比べたら全然へっちゃら。
「トシテル、なんだ今のは……」
「俺の手を、ディナ先輩の手だと思わせてやったんです。触れた皮膚と、同じ皮膚に偽装する魔法にしてみました」
「二つ目のは何だ。痛みを奪ったのか? それとも封印か?」
「いえ、呪詛に何かしたんじゃなく、自分の方の痛みをごまかしました」
「どうやって?」
「生物がもともと持っている能力で、痛みに襲われたとき、脳内の物質が出て」
「脳内の物質?」
「あ、ええと」
ドーパミンとかエンドルフィンとかいう単語は聞いたことがあるけれど、どれがどれだったっけかな。
マンガとか小説とかだと、異世界転生の主人公はこういう知識をちゃんと覚えているよな。
俺は全然そんなんじゃない。
だいたい検索すれば簡単に調べられたから。
「チキュウでは、魔法がない分、物質的なものへの研究が進んでます。人間の内側の構造や機能がかなり解析されているんです。目では見えないくらい小さな機能の研究も進んでいて……だから、俺の使った『生命回復』は、一ディエス分の
「なるほど。魔法を除いた思考で
「完全に、ではないですが、これなら耐えられます」
不意にディナ先輩に抱きしめられた。
「トシテル、感謝する。この呪詛のせいで、獣種の魔法の使用は今まで最小限に抑えてきた。本当はもっと試したいこともたくさんあったのだが」
「い、いえ、光栄です、じゃなくて!」
慌ててディナ先輩から離れる。
「またディナ先輩の体に戻ってしまう恐れが」
「それはそれで構わぬ。トシテルのような未熟者がそれを抱えたままでルブルムを守れるかと考えると不安しかないからな。そうだ……少し待て」
いったん部屋の外へと出たディナ先輩が、しばらくして袋のようなものを持って戻ってきた。
「豚皮の袋だ。この表面に『同じ皮膚』とやらをかけてみろ」
そうか、俺に移せたということは、別の皮膚に閉じ込めることもできるかもしれないのか……と、鼻息荒く挑戦してみたが失敗。
生きていないとダメなのかな。
ディナ先輩へもう一度戻す実験も失敗。
というかそもそも俺の腕から胴や別の腕への移動すらしてくれない。
「魔術特異症で移動法則が制限されるよう変異したのかもしれない……ということは」
ディナ先輩はナイフを取り出し、俺の腕へ突然、斬りつけた。
『脳内モルヒネ』が効いているのか、痛みはほとんどない。ペンで線を描かれている、そんな変な感じ。
「見ろ、トシテル。お前へ移った『虫の牙』の傷は、途切れた皮膚を越えられなくなったようだぞ」
傷ムカデが左腕に移動しているうちに、俺の肘から下あたりに腕をぐるりと一周する傷がつけられた。
傷ムカデはそこから出ては来ない。
顔とか背中とか他の敏感なところを這いずり回られるよりはかなりマシだ。
「普段は布でも巻いておけ」
左手に呪詛の動く傷。それを隠す包帯。うわ、なんだこの中二病設定は……大きなため息がでかけた瞬間、思わずそれを飲み込んでしまう。
ルブルムの声で。
「ずるい! 私には見せないのに、ディナ先輩とは見せあっている!」
部屋の入り口に、いつの間にかルブルムが立っていた。
言われてみればディナ先輩は上半身裸のままだし、俺も検証の都合上、上半身は脱いでいた。
「い、いや、これはっ……そ、それに下は見せてないからっ」
「そうか。そちらの耐性もつけておく必要があるか」
ディナ先輩?
「だ、大丈夫です。この痛みでそういう気持ち飛びますから!」
「私は、トシテルの見てみたい。私も脱げばいいのか?」
ルブルム?
慌ててルブルムの手を止める。
「そうだな。慣れておいた方がいい。ルブルムも脱ぐといい」
ディ、ディナ先輩?
「トシテル、お前も脱げ」
これ、どういう状況?
「そ、それよりももっと今しかできないことを、調査! 調査を先に!」
「何の調査だ?」
ルブルムが食いついた!
「ほら、この、ムカデみたいな傷」
「トシテル、腕を怪我している」
魔法代償を集中しようとするルブルムを慌てて制する。
「この傷は、当分は治さなくていいんだ」
「そうだな。ルブルムにも話しておいた方が良いかもしれない。ルブルムは人の悪意に触れてなさすぎる。ここから北へ向かうなら、危険に対するある程度の心構えが必要になるだろうからな」
ディナ先輩は、さっきの話をもう一度、ルブルムへと話す。
俺に話した時よりも多少、生々しく。
その後、『虫の牙』の傷……というか俺が実験台になる研究は、三人で続けることになった……全裸で。
うん。全裸で。
股間に血液が集中しない呪詛のおかげでなんとかなったようなものの……おかげで、自分の中の超紳士スイッチを入れる感覚がちょっとわかった。
検証結果をまとめてみると、良いニュースと悪いニュースがあった。
まず悪い方。
この傷のムカデは、本来は魔法代償を消費した一瞬しか咬まなかったらしいが、俺の魔術特異症はその魔法の効果期間中、ずっと継続させるようにしてしまったっぽい。
効果時間が一瞬である魔法や、効果時間があっても他の人にかけた場合は、咬まれる激痛も一瞬だが、俺自身にかけた場合、効果時間が切れるまでずっと痛み続ける。
最初に『脳内モルヒネ』を使わないとしんどいことになる――けど、奇襲をかける場合なんかだと、相手に気付かれるのを避けるため、初手は我慢しなきゃ――という。
次に良い方。
俺の魔法効果が増大しているのだ。
呪詛が伝染するには、呪詛により被るだけの不利益を受け入れようと思えるだけの利益がないといけない。
例の「ひとつまみの祝福」ってやつだ。
この呪詛の場合、どのような仕組みかはわからないが、俺の使用する魔法効果が増大する方向に働いているようだ。
ただし魔法発動時、咬まれる激痛に負けて魔法代償を消費する前に手放しちゃうと、その勢いに引っ張られて追加消費されてしまう魔法代償もより大きくなるという。
「でも『虫の牙』という武器……戦闘中に相手を強化する呪詛をかけるとか、設計した人の思考はとんでもないですね」
「いるんだよ。強い者と戦いたい欲求にかられている戦闘狂の類いは」
戦闘狂……。
キカイーの屋敷に居た、強い警備兵。
もしもそいつを見つけたとして、今の俺では全く歯が立たない……可能性が高いんだろうな。
俺はもっと強くならないといけない。
「くしゅんっ」
可愛いくしゃみをしたのは、ルブルムだった。
● 主な登場者
・
ラビツ一行をルブルム、マドハトと共に追いかけている。ゴブリン用呪詛と『虫の牙』の呪詛と二つの呪詛に感染している。
・ケティ
リテルの幼馴染の女子。
リテルとは両想い。熱を出したリテルを一晩中看病してくれていた。リテルが腰紐を失くしたのを目ざとく見つけた。
・ラビツ
久々に南の山を越えてストウ村を訪れた傭兵四人組の一人。ケティの唇を奪った。
フォーリーではやはり娼館街を訪れていたっぽい。
・マドハト
ゴブリン魔法『取り替え子』の被害者。ゴド村の住人で、とうとう
リテルに恩を感じついてきている。元の世界で飼っていたコーギーのハッタに似ている。街中で魔法を使い捕まった。
・ルブルム
魔女様の弟子である赤髪の少女。整った顔立ちのクールビューティー。華奢な
槍を使った戦闘も得意で、知的好奇心も旺盛。念願のリテルとの見せ合いっこがようやくできた。
・アルブム
魔女様の弟子である白髪に銀の瞳の少女。
外見はリテルよりも二、三歳若い。知的好奇心が旺盛。
・カエルレウム
寄らずの森の魔女様。深い青のストレートロングの髪が膝くらいまである
ルブルムとアルブムをホムンクルスとして生み出し、リテルの魔法の師匠となった。『解呪の呪詛』を作成中。
・ディナ
カエルレウムの弟子。ルブルムの先輩にあたる。重度で極度の男嫌い。壮絶な過去がある。
アールヴを母に持ち、
・ウェス
ディナに仕えており、御者の他、幅広く仕事をこなす。肌は浅黒く、ショートカットのお姉さん。
リテルに対して
・『虫の牙』所持者
キカイー
『虫の牙』と呼ばれる呪詛の傷を与える異世界の魔法の武器を所持し、ディナに呪詛の傷を付けた。
■ はみ出しコラム【入れ墨】
魔法が存在するホルトゥスにおいて、入れ墨は呪術的な意味合いでは使用されない。
また、魔法で消し込むことも可能であるため、通常の入れ墨は犯罪者の印としての使用もない。
入れ墨には、「皮膚に傷を付けて色を入れるもの」と「染料で人体を染めるもの」の二種類がある。
前者をスティグマタ、後者をティンクトゥーラと呼ぶ。
共に発祥はホルトゥスの南方地域である。
・スティグマタ
サボテン類の針を使用して墨を入れる。
発祥の地においては、成人した者が、家を現す記号なり模様なりを体の特定の部位に入れた。
その痛みに耐える通過儀礼としての意味合いも持つ。
このスティグマタがもとになり、実績紋というモノができるようになった。
※ 実績紋
【依頼斡旋屋】の項目でも触れたが、粉末状の魔石を用い、功績や犯罪歴等が記載される。
魔術師組合でないと内容判別ができないため、大きな街でしか確認に使用されない。
・ティンクトゥーラ
ヘナと呼ばれる植物をもとに作られた染料で身体を染める。
元々は、体を冷やす効果のあるヘナを、夏季の暑さ対策としてティンクトゥーラを施すようになった。
やがてそれがファッションとして用いられるようになり、スティグマタと異なり、時間が経てば消えるティンクトゥーラは、ホルトゥスでも広く用いられるようになった。
最初の流行は、都市部の貴族たちの間であったが、その後、公娼たちが淫猥なファッションとして用いるようになると、貴族たちはこれを用いなくなり、現在ではティンクトゥーラは娼婦の象徴として認識されている。
ただし、マニキュアや白髪染めとしてであれば、公娼でなくとも使用する。