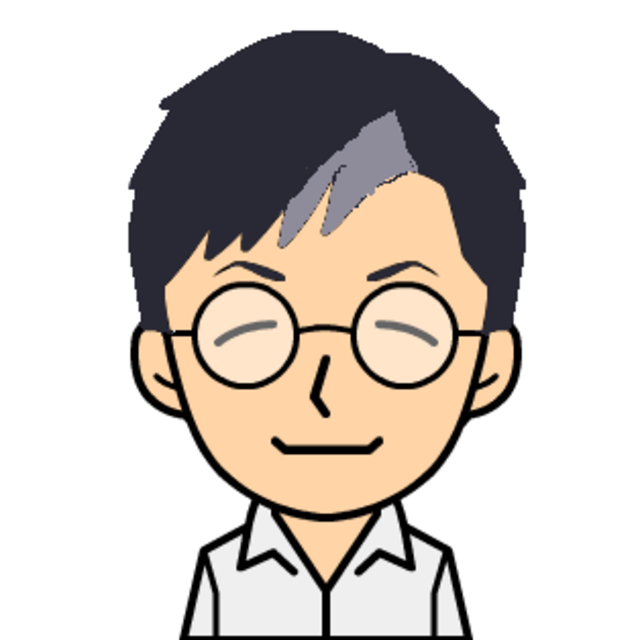第1話
文字数 2,329文字
荒野の真ん中のしけた街は、場合によっては地図にさえ載っていない事がある。
そしてこの街も、そんな場所の一つだった。
「病人さえ出なければ、迂回したい場所だな」
ドクターが言った言葉に、私はうなずいた。
「仕方が無いさ、ドクター」
「……あたしなら、大丈夫、よ」
私の腕の中の女が、細い声で言った。
「おまえさんは黙っていろ。行こう、ドクター」
この女は別に私の知り合いではない。半日ほど前にトレイルの途中で見つけた、馬を盗まれた馬車の中で動けなくなっていた人間だった。
もう一人の連れであるドクターは、昨日の宿で知り合った。この辺境に散らばっている家々を回る巡回医だという事で、この娘にとってはこれ以上の幸運はなかっただろう。
街といっても、埃っぽい道の両側に崩れ掛けたような家が並んでいるだけの代物だ。そのバルコニーには酒瓶を片手に昼間から飲んだくれている男達の姿もある。
要するに、捨てられる寸前の町という事だった。
「まともな宿があればいいのだが」
南京虫と病人を同居させるのは、ドクターのお気に入りではないらしい。
そして街で一軒だけ開いていた宿屋は、辛うじてドクターの気に触れない程度のものだった。
建物は古い。しかし迎え入れてくれた主人と少女が、ここを退廃した街の空気から守っているようにも見えた。
「とにかく、病人を寝かせてやりたいんだ」
ドクターの一言に、少女がてきぱきと動いていた。
私はといえば、病気の女を寝かしつけてしまえば、何かすることがあるわけでもない。
一階の酒場に下り、酒を飲む事にした。
ここにも人の姿はまばらだ。酒場の隅っこの方で、酒で人生を潰してしまったような風体の男が一人、テーブルに突っ伏しているだけだった。
「ずいぶん、荒れた街でしょう」
私が黙ってその男を眺めていると、主人がぼそっと言った。
「いつからだ」
「さあ……ウォルカターラとの戦争が始まった後ですよ。ところでお客さん、ウォルカターラの方ですね」
「そうだな。しかし、気にしなくていい」
ウォルカターラ系の人間など、この大陸にも腐るほどいる。私が宿帳に書いた名前も、ウォルカターラ系の典型的な名前だった。
「そうですか……ところで、あのお嬢さんは?」
「聞きたがりだな?」
「だいぶん、ご病気が悪いようですからね」
「マラリアだそうだ」
どこからか逃げ出して来て、マラリアで動けなくなった時に馬を盗まれて立ち往生したのだろう。女だけという事に腑に落ちない点があったが、詮索するのは今の私の仕事ではなかった。
「しばらく、ここに置いてやってくれるか」
「私どもは構いません」
「代金は俺が持とう」
金貨二枚もあれば、十日は泊まれる宿だった。薬代まで入れても、金貨五枚もあればしばらく過ごせるだろう。
私が無造作にカウンターに並べた金貨に主人は目を丸くしたが、うなずいて受け取った。
「あの方の身内の方で……?」
「いや。あれはここに来る途中で拾っただけだ」
「そうでしたか」
主人は何か考えているようだったが、私は何も聞く気はなかった。
──────────
「そういえば、君が彼女の分を支払ってくれたそうだな」
その日の晩になってから、ドクターが私にそう言った。
「たいした額ではない」
私にとってはどうでもいい金だった。
ドクターが私の顔をつくづく眺め、
「今まで聞かなかったが……君はどういう人間なんだ?」
「別に、何だっていいだろう」
話したい気分ではなかった。
「たかが金貨五枚だ。それ以上の事ではないさ」
「だが、それで彼女の命が買えたようなものだ」
「持ち直せばな」
「大丈夫さ。薬は与えてある。患者も十分体力があるし、あとはゆっくり休める場所が必要なだけだ。……最後の一つは君が与えてくれた」
「よしてくれ。俺は聖人君子という柄じゃない」
そこまで言った時、酒場のドアが軋んで開いた。
入って来た男は、帽子も脱がなかった。
その男の周りを固める、動く大岩のような男達は、服の下に銃を持っていた。
「久しぶりに客が入っているようじゃないか、ジェイク?」
ずかずかと歩いて来てカウンターに肘をつき、男は煙草の煙と一緒に言葉を吐き出した。
「なにかご注文ですか、モリソンさん」
主人は顔色一つ変えず、そう返した。
「ん?注文か、面白い事を言うじゃないか。そうだな、お前の娘って言うのはどうだ」
「あれは売り物ではありませんよ」
男達が馬鹿笑いする。
「なかなかいい根性をしているじゃないか?あまり突っ張るなよ、こっちには」
「おっしゃらなくても存じておりますよ。ウォルカターラの魔術師がついていらっしゃるというのでしょう」
「良く分かっているじゃないか。あの女、フェナーブの呪術師っていう話なんでな。検分させてもらうぜ」
「お断りします」
と、主人はためらわずに答えた。
「ほほう。これで頼んでも駄目か」
男が銃を抜き、主人の鼻先に突き付けた。
取り巻きが、それをにやにやしながら見ているのが、目障りだった。
銃を抜き、撃つ。男の手から銃が弾き飛ばされ、取り巻きが銃を抜いた。
酒場は私にとって、銃撃戦をする場所ではない。私は銃を使わず、魔力で取り巻きの銃を奪った。
一人の男が手首を折り、絶叫する。ぎょっとした顔をしたリーダー格の男がこちらを凝視する中、私は自分の銃を収めた。
「……魔術師か」
「なんだっていい。酒くらい、静かに飲みたいだけだ」
「……そうか。いずれ、この礼はさせてもらう。覚えておけ」
リーダー格の男が凄んでみせたが、私には鬱陶しいだけだった。
そしてこの街も、そんな場所の一つだった。
「病人さえ出なければ、迂回したい場所だな」
ドクターが言った言葉に、私はうなずいた。
「仕方が無いさ、ドクター」
「……あたしなら、大丈夫、よ」
私の腕の中の女が、細い声で言った。
「おまえさんは黙っていろ。行こう、ドクター」
この女は別に私の知り合いではない。半日ほど前にトレイルの途中で見つけた、馬を盗まれた馬車の中で動けなくなっていた人間だった。
もう一人の連れであるドクターは、昨日の宿で知り合った。この辺境に散らばっている家々を回る巡回医だという事で、この娘にとってはこれ以上の幸運はなかっただろう。
街といっても、埃っぽい道の両側に崩れ掛けたような家が並んでいるだけの代物だ。そのバルコニーには酒瓶を片手に昼間から飲んだくれている男達の姿もある。
要するに、捨てられる寸前の町という事だった。
「まともな宿があればいいのだが」
南京虫と病人を同居させるのは、ドクターのお気に入りではないらしい。
そして街で一軒だけ開いていた宿屋は、辛うじてドクターの気に触れない程度のものだった。
建物は古い。しかし迎え入れてくれた主人と少女が、ここを退廃した街の空気から守っているようにも見えた。
「とにかく、病人を寝かせてやりたいんだ」
ドクターの一言に、少女がてきぱきと動いていた。
私はといえば、病気の女を寝かしつけてしまえば、何かすることがあるわけでもない。
一階の酒場に下り、酒を飲む事にした。
ここにも人の姿はまばらだ。酒場の隅っこの方で、酒で人生を潰してしまったような風体の男が一人、テーブルに突っ伏しているだけだった。
「ずいぶん、荒れた街でしょう」
私が黙ってその男を眺めていると、主人がぼそっと言った。
「いつからだ」
「さあ……ウォルカターラとの戦争が始まった後ですよ。ところでお客さん、ウォルカターラの方ですね」
「そうだな。しかし、気にしなくていい」
ウォルカターラ系の人間など、この大陸にも腐るほどいる。私が宿帳に書いた名前も、ウォルカターラ系の典型的な名前だった。
「そうですか……ところで、あのお嬢さんは?」
「聞きたがりだな?」
「だいぶん、ご病気が悪いようですからね」
「マラリアだそうだ」
どこからか逃げ出して来て、マラリアで動けなくなった時に馬を盗まれて立ち往生したのだろう。女だけという事に腑に落ちない点があったが、詮索するのは今の私の仕事ではなかった。
「しばらく、ここに置いてやってくれるか」
「私どもは構いません」
「代金は俺が持とう」
金貨二枚もあれば、十日は泊まれる宿だった。薬代まで入れても、金貨五枚もあればしばらく過ごせるだろう。
私が無造作にカウンターに並べた金貨に主人は目を丸くしたが、うなずいて受け取った。
「あの方の身内の方で……?」
「いや。あれはここに来る途中で拾っただけだ」
「そうでしたか」
主人は何か考えているようだったが、私は何も聞く気はなかった。
──────────
「そういえば、君が彼女の分を支払ってくれたそうだな」
その日の晩になってから、ドクターが私にそう言った。
「たいした額ではない」
私にとってはどうでもいい金だった。
ドクターが私の顔をつくづく眺め、
「今まで聞かなかったが……君はどういう人間なんだ?」
「別に、何だっていいだろう」
話したい気分ではなかった。
「たかが金貨五枚だ。それ以上の事ではないさ」
「だが、それで彼女の命が買えたようなものだ」
「持ち直せばな」
「大丈夫さ。薬は与えてある。患者も十分体力があるし、あとはゆっくり休める場所が必要なだけだ。……最後の一つは君が与えてくれた」
「よしてくれ。俺は聖人君子という柄じゃない」
そこまで言った時、酒場のドアが軋んで開いた。
入って来た男は、帽子も脱がなかった。
その男の周りを固める、動く大岩のような男達は、服の下に銃を持っていた。
「久しぶりに客が入っているようじゃないか、ジェイク?」
ずかずかと歩いて来てカウンターに肘をつき、男は煙草の煙と一緒に言葉を吐き出した。
「なにかご注文ですか、モリソンさん」
主人は顔色一つ変えず、そう返した。
「ん?注文か、面白い事を言うじゃないか。そうだな、お前の娘って言うのはどうだ」
「あれは売り物ではありませんよ」
男達が馬鹿笑いする。
「なかなかいい根性をしているじゃないか?あまり突っ張るなよ、こっちには」
「おっしゃらなくても存じておりますよ。ウォルカターラの魔術師がついていらっしゃるというのでしょう」
「良く分かっているじゃないか。あの女、フェナーブの呪術師っていう話なんでな。検分させてもらうぜ」
「お断りします」
と、主人はためらわずに答えた。
「ほほう。これで頼んでも駄目か」
男が銃を抜き、主人の鼻先に突き付けた。
取り巻きが、それをにやにやしながら見ているのが、目障りだった。
銃を抜き、撃つ。男の手から銃が弾き飛ばされ、取り巻きが銃を抜いた。
酒場は私にとって、銃撃戦をする場所ではない。私は銃を使わず、魔力で取り巻きの銃を奪った。
一人の男が手首を折り、絶叫する。ぎょっとした顔をしたリーダー格の男がこちらを凝視する中、私は自分の銃を収めた。
「……魔術師か」
「なんだっていい。酒くらい、静かに飲みたいだけだ」
「……そうか。いずれ、この礼はさせてもらう。覚えておけ」
リーダー格の男が凄んでみせたが、私には鬱陶しいだけだった。