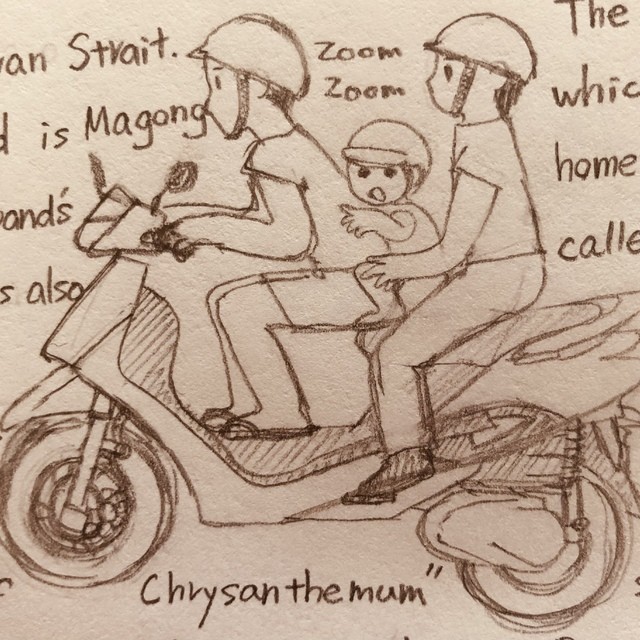花の香るあそこまで
文字数 4,107文字
いつ来たのだったろうか。
窓から見える外の様子は、暗く雨にけぶって定かではない。ときおり雲を映すのか、ひゅうひゅうと瞬くものは水面のようなので、この喫茶店は川か湖を見下ろす高台に建っているのだろう。頭かぶりを返せば、アンティーク調の店内は暖かく明るい。ちらほらいる他の客に混じって窓際の席に腰かけている私は、なぜここへ来たのか思い出せないでいた。
いつも通り夜勤からアパートに戻ったまでは覚えている。超過勤務のうえ先輩の愚痴と上司の癇癪を散々聞かされ、短い仮眠を取ることだけ考えてやっと部屋へ辿り着こうとした矢先、廊下で隣りに住むオクムラ君に鉢合わせしてしまった。陰気な前髪が適当に会釈する。私より若そうだが、ほとんど外に出てこず、仕事をしている様子もなく、よく薄い壁を伝ってコンピューター・ゲームの音がしてくる。きっと親が金持ちで放任なんだろう、と浅ましく思う。「こんにちは」とだけ返して部屋に滑り込んだ。ひきっぱなしの布団へ横になると、機械油と汗のにおいが悪い夢を引き寄せるようで、けれど眠気に逆らえない。こんな生活いつまで続くのだろうか。蒸発した父親の借金と、故郷の母親の薬代、町工場で働けるようになったはいいが、ノルマは厳しい。疲れて、焦るばかりで、何の希望も無い。
そんなどうにもならない不安で眠いのに寝付けず、また起き出してコンビニに行ったはずだが、その途中でこの喫茶店を見つけたのだったろうか。しかし天気は良かったはずだ。もうすぐアパート脇に立っている桃の木の蕾も開くだろうな、という陽気だった。まあいい、たまには喫茶店でゆっくりコーヒーでも飲むのも悪くないかもしれない。しかしおかしなことに、一人の店員も見つけることができなかった。他の客たちは皆、静かに手元の飲み物や軽食を摂っているようだった。
手持ち無沙汰でいるのも座り心地が悪い。水はセルフサービスらしいので、立ち上がってピッチャーの置いてあるコーナーまで向かおうとしたが、最後のピッチャーは目の前で持ち去られてしまった。むっとしてその男性のあとを目で追うと、彼のテーブルには既に幾つものピッチャーが空になっていた。男性は席に戻ると、グラスに水を注ぎ、猛然と飲み出した。
半分呆気に取られて見ていると、向かい合って座っていた連れらしい男性が、私の視線に気付いて苦笑した。
「許してやってくれないか。俺達『燃えちまった』もんだから、喉がかわくんだ」
その男性は対照的に、オリーブをツマミに舐めるようにグラスを呷あおっていたが、カーキ色のジャケットにも濡れて黒ずんだ染みが浮いていた。
諦めて踵を返し、自分の席に戻ろうとすると、橙色のライトを鈍く散らす、場違いのように美しいドレスの女性と目が合った。蜜色の肌にくっきりとした目鼻立ち、宝石類に彩られた豪奢なアクセサリーと、蛇のように幾重にも身体に巻きつく煌びやかなドレス。思わず見惚れて足を留めた私に、女性はにっこりと微笑んだ。
「じろじろとすみません。素敵なドレスですね」
「有り難うございます。故郷の伝統的なウェディング・ドレスなんです」
ウェディング・ドレスで喫茶店に来るものだろうか。心中傾げた小首が見えるわけもなかろうが、女性はまたうっそりと口角を上げた。
「逃げてきたんです。家の決めた結婚が嫌で」
テーブルの上の茶器に視線を戻す。金箔の施されたグラスから香気を漂わせる紅茶と、お茶受けのドライ・フルーツは杏あんずのようだった。
「一生婚家から出られないなど耐えられません」
二人で学校帰りよくお喋りをした杏あんずの木陰で、あの子は待っていてくれると言った。祝宴の夜陰に紛れて走った。あの子の手を取ることができた時、とても幸福だった。けれど家人と追っ手に捕まるのは、時間の問題だった。
「彼女の身分なら無下には扱われないでしょう。私は、最後に会えただけで報われました」
願わくば、私の故郷の女性たちが、これからもみんな安全に自由に生きることができますように。
「君、すまなかったな、気付かなくて。今新しい水を汲んでくる」
萎れる寸前の薔薇のように艶あでやかに微笑む女性に、私は何と言ったらいいか分らなかった。立ち尽くしていると、先程の男性が声を掛けてきたので、反射的に「有り難うございます」と振り向いてしまう。やはりカーキ色のジャケットを着た体格の良いその男性は、気さくに手を振ってくれたが、その色白の首から半顔には、火傷の跡が刻まれていた。
一体、この喫茶店は何なんだろう。私は女性に挨拶してその場を離れた。やっと席に戻ると、今度は見知らぬ老人がそこに座っていた。
「あれ、すみません。あなたの席だったんですか」
ぼさぼさとした白い頭髪と口髭に、くたびれたコートを羽織った老人は、決して洗練された印象ではなかったが、声音は穏やかだった。手元には銀のカップにワン・スクープのバニラアイス、シロップ漬けの真っ赤なチェリーがのせられている。
「構いません、私はまだ注文していませんので」
店は頻繁でもないが常に人の出入りがあり、テーブルはほぼ埋まっている。近くの丁度空いた席を見つけて移ろうとした私を、老人はまあまあと引き留めた。
「相席でもいいじゃないですか。若い人と話すのは久しぶりだ」
最近は路上に若い人たちも増えてきたけれどね、彼らは彼らでグループがあるから。はあ、と私は腰掛け直した。普段なら絶対に赤の他人と相席などしないが、真っ赤なチェリーがやけに鮮やかなのが気になった。老人は皺まで煤汚れてしまった指先で小さなスプーンを持ち、丁寧にアイスクリームを掬う。さくり、と雪をかくように小さく崩れたアイスクリームの表面が輝いて綺麗だ。
「アイスクリーム、お好きなんですか」
乾いて黒ずんだ唇をゆっくり動かす老人に、私は思わず尋ねた。銀のカップに盛られたバニラアイスと真っ赤なチェリー。何か思い出しかけた。老人はふふふ、と目尻の皺をたわめて笑った。
「……妻と初めてデートした時に一緒に食べたんです」
あの時は、どうやったら彼女が喜んでくれるのかということばかり考えていたのに、それから事業にのめり込んだ挙句失敗してね、苦労ばかりかけて別れてしまった。連絡を取ったのは一度きり、こんななりになってしまって焼香を上げることもできなかった。
「やっと会って謝ることができます」
チェリー、あげましょうか。長らく会っていませんが、息子があなたと同い年くらいです。昔一緒に喫茶店に行くと、よくねだられたものでした。老人が可笑そうに懐かしそうに言う。ナプキンを使ってつまみあげ、こちらに差し出してくれる。手に取ったシロップ漬けの真っ赤なチェリーは、つやつやと柔らかく光って何かに似ている気がした。そうだ、風船だ。初春の青空に放たれてしまった赤い風船。幼い頃、家族で一度だけ訪れた遊園地で、父親が買ってくれたものと同じの。
「ハネダさん!」
ドアを勢いよく開けて入ってきたのは、オクムラ君だった。髪を振り乱し、フリースの上着をはためかせてこちらへ駆けてくると、腕を掴まれた。
「帰りますよ、何してるんです」
「何してるって、君こそ失礼だな」
オクムラ君の剣幕に、私もかっとして声を上げると、老人が落ち着いて、と間に入ってくれる。
「どうしたの、この人」
オクムラ君に向かって私を指差し、老人は優しく尋ねた。それは私に対するオクムラ君がどうしたのか、という質問であるべきではなかろうか。私は憤懣 やる方ない。
「……階段から落ちて、意識不明なんです」
ぎょっとして、オクムラ君を振り返る。長い前髪の下、落ち窪んだ大きな目は、今にも泣き出しそうだった。
「俺もコンビニから帰るところで。ハネダさん、飛んでく風船に気を取られて、歩道橋の階段で足を踏み外したんです」
どんな間抜けなんです、俺、人生で初めて救急車呼んで病院まで付き添いしました。もう勘弁して下さい、帰りましょう。
「……君には関係無いだろう」
やはりこれは夢なのだろうか。私の言葉に、オクムラ君は大の大人のくせに、鼻を啜ってこちらを睨む。
「ありますよ。お隣りでしょ。それにハネダさんがいないと、俺、他に誰も話す相手いなくなっちゃう」
家族とか友人とか会社の関係者とか、そんなじゃなけりゃ心配しちゃいけないんです? ハネダさん、アパートの桃の木よく眺めてるでしょ。カレーや煮物のつくり置きしてるいい匂いがする時もあるし、意外と洋楽がんがん聞いてるし、そのくらい知ってれば充分じゃないですか。となりで生きてる、って知ってるんですよ。俺、会社で上手くやっていけなくて人と関わるのが辛くなってたんだけど、今年桃の花が咲いたら今度こそ、こっちから「花が咲きましたね」って言うつもりだったのに。オクムラ君がこんなに饒舌だとは知らなかった。一気に捲まくし立て、怒らせた肩を老人がポンポンと撫ぜる。
「帰れますよ、彼はまだ何も口にしていないから」
ドレスの女性が立ち上がり、こちらにやって来て言う。おっとそりゃ、これも返してもらわないと、と老人は私の手からチェリーを奪い取ってしまった。理解の許容を越えて固まっている私に、女性が優美に囁く。
「“こちら“のものを食べてしまったら、もう“あちら“には戻れません。けれど、貴方はまだでしょう」
「お前さんたちの国は戦争してるんじゃないんだろう、じゃあ、帰ったほうがいい」
ピッチャーが積み上げられた向こうのテーブルから、男性二人が顔を覗かせて付け加える。俺たちだって、誰かを生かすために戦っていたはずなんだがな、と火傷顔をくしゃりと歪めて笑った。
外に出ると、雨はもう止んでいた。先を歩くオクムラ君が、ついてきていることを確認するように振り向く。私は、淡い光を放つ喫茶店の窓際へ手を振った。彼らは、これから“あちら“へ行って、もう戻らない。あの喫茶店は、黄泉比良坂を下る途中の休憩所だったのだろう、多分。俺は葡萄も筍タケノコも持ってませんけどね、とオクムラ君が隣りに並んで言う。桃の花を一緒に見ることはできますよ。仰げば満天に花びらの舞うような星空だった。
窓から見える外の様子は、暗く雨にけぶって定かではない。ときおり雲を映すのか、ひゅうひゅうと瞬くものは水面のようなので、この喫茶店は川か湖を見下ろす高台に建っているのだろう。頭かぶりを返せば、アンティーク調の店内は暖かく明るい。ちらほらいる他の客に混じって窓際の席に腰かけている私は、なぜここへ来たのか思い出せないでいた。
いつも通り夜勤からアパートに戻ったまでは覚えている。超過勤務のうえ先輩の愚痴と上司の癇癪を散々聞かされ、短い仮眠を取ることだけ考えてやっと部屋へ辿り着こうとした矢先、廊下で隣りに住むオクムラ君に鉢合わせしてしまった。陰気な前髪が適当に会釈する。私より若そうだが、ほとんど外に出てこず、仕事をしている様子もなく、よく薄い壁を伝ってコンピューター・ゲームの音がしてくる。きっと親が金持ちで放任なんだろう、と浅ましく思う。「こんにちは」とだけ返して部屋に滑り込んだ。ひきっぱなしの布団へ横になると、機械油と汗のにおいが悪い夢を引き寄せるようで、けれど眠気に逆らえない。こんな生活いつまで続くのだろうか。蒸発した父親の借金と、故郷の母親の薬代、町工場で働けるようになったはいいが、ノルマは厳しい。疲れて、焦るばかりで、何の希望も無い。
そんなどうにもならない不安で眠いのに寝付けず、また起き出してコンビニに行ったはずだが、その途中でこの喫茶店を見つけたのだったろうか。しかし天気は良かったはずだ。もうすぐアパート脇に立っている桃の木の蕾も開くだろうな、という陽気だった。まあいい、たまには喫茶店でゆっくりコーヒーでも飲むのも悪くないかもしれない。しかしおかしなことに、一人の店員も見つけることができなかった。他の客たちは皆、静かに手元の飲み物や軽食を摂っているようだった。
手持ち無沙汰でいるのも座り心地が悪い。水はセルフサービスらしいので、立ち上がってピッチャーの置いてあるコーナーまで向かおうとしたが、最後のピッチャーは目の前で持ち去られてしまった。むっとしてその男性のあとを目で追うと、彼のテーブルには既に幾つものピッチャーが空になっていた。男性は席に戻ると、グラスに水を注ぎ、猛然と飲み出した。
半分呆気に取られて見ていると、向かい合って座っていた連れらしい男性が、私の視線に気付いて苦笑した。
「許してやってくれないか。俺達『燃えちまった』もんだから、喉がかわくんだ」
その男性は対照的に、オリーブをツマミに舐めるようにグラスを呷あおっていたが、カーキ色のジャケットにも濡れて黒ずんだ染みが浮いていた。
諦めて踵を返し、自分の席に戻ろうとすると、橙色のライトを鈍く散らす、場違いのように美しいドレスの女性と目が合った。蜜色の肌にくっきりとした目鼻立ち、宝石類に彩られた豪奢なアクセサリーと、蛇のように幾重にも身体に巻きつく煌びやかなドレス。思わず見惚れて足を留めた私に、女性はにっこりと微笑んだ。
「じろじろとすみません。素敵なドレスですね」
「有り難うございます。故郷の伝統的なウェディング・ドレスなんです」
ウェディング・ドレスで喫茶店に来るものだろうか。心中傾げた小首が見えるわけもなかろうが、女性はまたうっそりと口角を上げた。
「逃げてきたんです。家の決めた結婚が嫌で」
テーブルの上の茶器に視線を戻す。金箔の施されたグラスから香気を漂わせる紅茶と、お茶受けのドライ・フルーツは杏あんずのようだった。
「一生婚家から出られないなど耐えられません」
二人で学校帰りよくお喋りをした杏あんずの木陰で、あの子は待っていてくれると言った。祝宴の夜陰に紛れて走った。あの子の手を取ることができた時、とても幸福だった。けれど家人と追っ手に捕まるのは、時間の問題だった。
「彼女の身分なら無下には扱われないでしょう。私は、最後に会えただけで報われました」
願わくば、私の故郷の女性たちが、これからもみんな安全に自由に生きることができますように。
「君、すまなかったな、気付かなくて。今新しい水を汲んでくる」
萎れる寸前の薔薇のように艶あでやかに微笑む女性に、私は何と言ったらいいか分らなかった。立ち尽くしていると、先程の男性が声を掛けてきたので、反射的に「有り難うございます」と振り向いてしまう。やはりカーキ色のジャケットを着た体格の良いその男性は、気さくに手を振ってくれたが、その色白の首から半顔には、火傷の跡が刻まれていた。
一体、この喫茶店は何なんだろう。私は女性に挨拶してその場を離れた。やっと席に戻ると、今度は見知らぬ老人がそこに座っていた。
「あれ、すみません。あなたの席だったんですか」
ぼさぼさとした白い頭髪と口髭に、くたびれたコートを羽織った老人は、決して洗練された印象ではなかったが、声音は穏やかだった。手元には銀のカップにワン・スクープのバニラアイス、シロップ漬けの真っ赤なチェリーがのせられている。
「構いません、私はまだ注文していませんので」
店は頻繁でもないが常に人の出入りがあり、テーブルはほぼ埋まっている。近くの丁度空いた席を見つけて移ろうとした私を、老人はまあまあと引き留めた。
「相席でもいいじゃないですか。若い人と話すのは久しぶりだ」
最近は路上に若い人たちも増えてきたけれどね、彼らは彼らでグループがあるから。はあ、と私は腰掛け直した。普段なら絶対に赤の他人と相席などしないが、真っ赤なチェリーがやけに鮮やかなのが気になった。老人は皺まで煤汚れてしまった指先で小さなスプーンを持ち、丁寧にアイスクリームを掬う。さくり、と雪をかくように小さく崩れたアイスクリームの表面が輝いて綺麗だ。
「アイスクリーム、お好きなんですか」
乾いて黒ずんだ唇をゆっくり動かす老人に、私は思わず尋ねた。銀のカップに盛られたバニラアイスと真っ赤なチェリー。何か思い出しかけた。老人はふふふ、と目尻の皺をたわめて笑った。
「……妻と初めてデートした時に一緒に食べたんです」
あの時は、どうやったら彼女が喜んでくれるのかということばかり考えていたのに、それから事業にのめり込んだ挙句失敗してね、苦労ばかりかけて別れてしまった。連絡を取ったのは一度きり、こんななりになってしまって焼香を上げることもできなかった。
「やっと会って謝ることができます」
チェリー、あげましょうか。長らく会っていませんが、息子があなたと同い年くらいです。昔一緒に喫茶店に行くと、よくねだられたものでした。老人が可笑そうに懐かしそうに言う。ナプキンを使ってつまみあげ、こちらに差し出してくれる。手に取ったシロップ漬けの真っ赤なチェリーは、つやつやと柔らかく光って何かに似ている気がした。そうだ、風船だ。初春の青空に放たれてしまった赤い風船。幼い頃、家族で一度だけ訪れた遊園地で、父親が買ってくれたものと同じの。
「ハネダさん!」
ドアを勢いよく開けて入ってきたのは、オクムラ君だった。髪を振り乱し、フリースの上着をはためかせてこちらへ駆けてくると、腕を掴まれた。
「帰りますよ、何してるんです」
「何してるって、君こそ失礼だな」
オクムラ君の剣幕に、私もかっとして声を上げると、老人が落ち着いて、と間に入ってくれる。
「どうしたの、この人」
オクムラ君に向かって私を指差し、老人は優しく尋ねた。それは私に対するオクムラ君がどうしたのか、という質問であるべきではなかろうか。私は
「……階段から落ちて、意識不明なんです」
ぎょっとして、オクムラ君を振り返る。長い前髪の下、落ち窪んだ大きな目は、今にも泣き出しそうだった。
「俺もコンビニから帰るところで。ハネダさん、飛んでく風船に気を取られて、歩道橋の階段で足を踏み外したんです」
どんな間抜けなんです、俺、人生で初めて救急車呼んで病院まで付き添いしました。もう勘弁して下さい、帰りましょう。
「……君には関係無いだろう」
やはりこれは夢なのだろうか。私の言葉に、オクムラ君は大の大人のくせに、鼻を啜ってこちらを睨む。
「ありますよ。お隣りでしょ。それにハネダさんがいないと、俺、他に誰も話す相手いなくなっちゃう」
家族とか友人とか会社の関係者とか、そんなじゃなけりゃ心配しちゃいけないんです? ハネダさん、アパートの桃の木よく眺めてるでしょ。カレーや煮物のつくり置きしてるいい匂いがする時もあるし、意外と洋楽がんがん聞いてるし、そのくらい知ってれば充分じゃないですか。となりで生きてる、って知ってるんですよ。俺、会社で上手くやっていけなくて人と関わるのが辛くなってたんだけど、今年桃の花が咲いたら今度こそ、こっちから「花が咲きましたね」って言うつもりだったのに。オクムラ君がこんなに饒舌だとは知らなかった。一気に捲まくし立て、怒らせた肩を老人がポンポンと撫ぜる。
「帰れますよ、彼はまだ何も口にしていないから」
ドレスの女性が立ち上がり、こちらにやって来て言う。おっとそりゃ、これも返してもらわないと、と老人は私の手からチェリーを奪い取ってしまった。理解の許容を越えて固まっている私に、女性が優美に囁く。
「“こちら“のものを食べてしまったら、もう“あちら“には戻れません。けれど、貴方はまだでしょう」
「お前さんたちの国は戦争してるんじゃないんだろう、じゃあ、帰ったほうがいい」
ピッチャーが積み上げられた向こうのテーブルから、男性二人が顔を覗かせて付け加える。俺たちだって、誰かを生かすために戦っていたはずなんだがな、と火傷顔をくしゃりと歪めて笑った。
外に出ると、雨はもう止んでいた。先を歩くオクムラ君が、ついてきていることを確認するように振り向く。私は、淡い光を放つ喫茶店の窓際へ手を振った。彼らは、これから“あちら“へ行って、もう戻らない。あの喫茶店は、黄泉比良坂を下る途中の休憩所だったのだろう、多分。俺は葡萄も筍タケノコも持ってませんけどね、とオクムラ君が隣りに並んで言う。桃の花を一緒に見ることはできますよ。仰げば満天に花びらの舞うような星空だった。