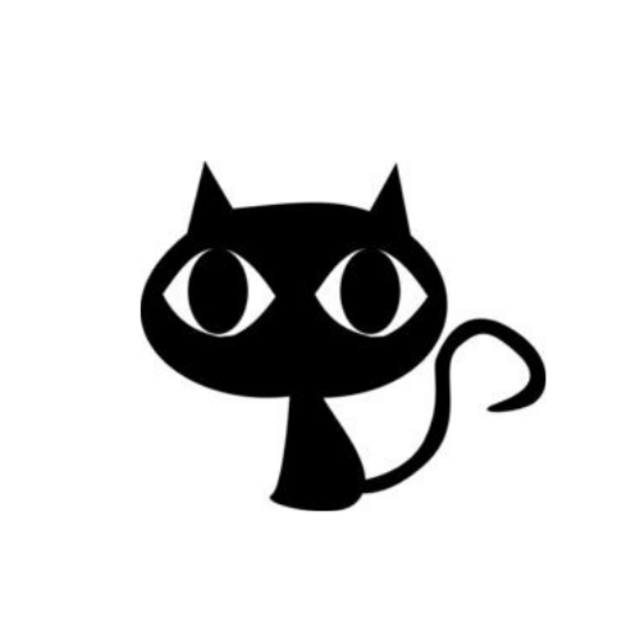最後に、復讐の章
文字数 9,845文字
ぱたり、ぱたり、小さな音がするたびに、微かな風が頰を過ぎる。ぱたり、ぱたり。ぱたり、ぱたり。規則的に音は続き、空気は小さく揺らぎ続ける。止まないそれが何だろうと思って見下ろせば、他でもない俺の手が手持ち無沙汰に封筒を左右に扇ぎ、その微かな風を生み出しているのだった。ぱたり、ぱたり。無意識に続くその動きをしばらく見つめてから、俺は再び視線を窓の外へと戻した。目を離したのは十秒ほどだったが、その窓に切り取られた風景は静止画のように、どこにも変わった箇所は認められない。
予定通りにウィークリーマンションを借り、元・妻の動きを刑事のように見張り始めてから、一週間が経っていた。手帳がなくなってしまった理由をどう考えているのかは分からないが、そこに書かれた予定通り、妻は仕事へ出かける日々を送っている。
彼女がアパートの部屋から出てくるのは、午前九時。最寄り駅から電車に乗って三十分、下車駅にはいつも白いワゴンが待っていて、彼女を含めた数人がその車に乗り込む。その送迎ワゴンで職場であるクリーニング工場まで行くのだ。シフト開始は十時で終わりは六時、ワゴンが再び駅に戻ってくるのは七時過ぎで、そのあとはすぐに家に帰るか、たまに駅前で夕飯の買い物をするくらいで、寄り道はほとんどしない。休日の曜日は決まっておらず、けれどそれは週に一度か二度だと、手帳の空白が教えてくれている。
真紀の命日である今日は、「村野・野洲・宮崎と会う?」とだけ書き込まれていて、仕事は休みらしかったが、記述とは裏腹に、彼女は今日も駅へ向かった。まさか村野に会うのか――俺は緊張したが、何のことはない、たまたまシフトが変更になっただけの様子で、その横顔にはいつもと同じ、ぼんやりとした疲れが浮かんでいた。その服装もいつも仕事へ行くときと同じ、質素なシャツとズボン姿で、うさぎの公園に着てきたワンピースのような、外出用の服装ではない。まさか俺が見張っていることを知っていて、油断させるためにそこまでしているのだとも思わなかったが、それでも俺はいつものように妻の後を尾行し、彼女が駅の改札口を出て、送迎ワゴンに乗り込むのを確認してから、この部屋にとって返した。
彼女が働いている間、その留守を知らずに村野が訪ねてくる可能性は十分にあった。また、それは楽観的な想像で、悪い想像をすれば、あいつはわざわざ彼女の留守を狙い、お礼参り の下見にやってくるということも考えられた。妻は村野といい関係を築いていると信じているようだが、犯罪者の考えることなど普通の人間には分からない。特に、妻のような善い人間には。
燃えるような夕日に、腕時計に視線を落とすと、針は五時過ぎを指していた。ワゴンが駅に戻ってくるのは七時過ぎだが、今日は村野に会うかもしれない特別な日だ。早めに出発したほうがいいかもしれない。
二人が友人のように再会を喜ぶ場面を思い浮かべ、俺は気分が悪くなった。今日は真紀の命日で、そんな日に――それもあの日と同じ赤い夕焼けが空を染める日に二人が会うなど、あってはならないことに思えた。しかし、同時にそうであったらいいと思う自分もいた。もし、村野が姿を現せば、あいつは真紀の命日に死ぬことになるのだから。
道の向こう側を、ダックスフンドを連れた中年女性が歩いていく。ということは、そろそろ部活を終えた中学生たちが自転車で通り過ぎていくはずだった。道は車で混み始め、その渋滞を尻目に、反射板を体中につけてウォーキングをする二人組が通り過ぎて行く。そうして、同じ時間に同じことが起こるその風景は、俺の目には奇妙に映った。まるで俺だけ時間が止まったように変わらない、別の世界に生きているようだった。いや、案外その感覚は正しいのかもしれない。あの日常に、俺はもう二度と戻れない。人殺しを企む俺のような人間は、もう二度と――。
ぱたり、ぱたり。意思とは裏腹に動いてしまう手を、俺は意識的に止めた。この部屋に俺が持ってきたものは少なかった。少しの着替えと、バスタオルと、髭剃り、石鹸、それからあいつを殺すための文化包丁。バッグ一つで済むような引っ越し荷物の中に、けれどこの封筒を入れてきたのはなぜだろう。村野から届いた、最後の手紙。刑務所の外から出された、桜の押印のない手紙を。
この手紙に何か記されているのか、封を開けない俺が知るはずもなかった。けれど、こんなものを持ってきたのは――そう、決心を鈍らせないためだった。二十五年間、待ち続けたこの日を、この機会を逃さないため。あいつへの憎しみを最大限に保ち続けるために持ってきたのだ。待ってろよ、真紀――カーテンの隙間から、赤く染まった空を見つめながら、俺は呟いた。待っててくれ、お父さんがいま、わるもん をやっつけてやるからな。
そのときだった。ポケットの携帯が震えた。かけてくる人間などいないはずだが。俺はちらと画面を見て――心臓が止まりそうになった。表示されているその番号は家 のものだった。真紀が使っていたものを捨てたくない一心で、契約を続けている自宅の電話番号。一体、誰が――俺は思わず立ち上がると、震える指先で通話ボタンを押した。
まさか、村野か? あいつが真紀の命日に、真紀を殺した場所へと戻ってきたのか――?
「あ、もしもし、お父さん ?」
しかし、聞こえてきたのは村野の声ではなく――それどころか男の声でもない――驚いたことに妻の声 だった。それも声こそ一週間前に聞いたものと変わりないが、その呼び方は、「お父さん」という呼び方は、遠い昔、真紀が生きていた頃の、俺たちが幸せな家族だった頃のもので、俺はまるで時間が巻き戻ってしまったかのような錯覚を起こした。
「お父さん 、聞こえてる?」
妻は再びその呼び名で俺を呼んだ。けれど、興奮して声を弾ませる彼女は、そう呼んでいることに気づいていない様子だった。
「あのね、いま、由紀からここに電話があったの。……あ、勝手に電話を取ってごめんなさいね。もちろん、ちゃんと『雨ヶ谷です』って名乗ったけど、すごく久しぶりだから緊張したわ。でも、大事な電話だったら困ると思って――」
「電話って……お前、家にいるのか?」
訳が分からず、俺は聞き返した。彼女は仕事に行ったんじゃなかったのか? それがどうして家に――しかもあんなに帰るのを拒否した我が家にいるのか。
「あ、そもそもそれを先に謝らないといけないわね」
妻ははっとしたように言った。
「ごめんなさい、勝手に家に入っちゃって。最初は外で待とうと思ったんだけど、昔、鍵を置いてあった場所を探したら、まだそこにあったから。ああいうのは変えとかないとだめよ、危ないから。でも、中は綺麗に片付いててびっくりしたわ。前は脱いだものも散らかしっぱなしだったのに。家具や何かもあのときと何も変わってないのね。……増えたのは、真紀の仏壇くらいかしら」
声が小さくなり、そこに少しの涙が滲んだ。
「あのブランコの写真、どこにあったの? 私、見たことないような気がするんだけど」
「あれは……」
答えようとする声が、痰が絡んだように掠 れた。この電話の相手は本当に妻なのか――俺はまだ信じられないような気持ちだった。一週間前、俺を軽蔑したような目で睨んでいた彼女は別人だったのか。それとも彼女はようやくあの女弁護士の洗脳から解けたのか。
何も分からないまま、俺は咳払いをして、言い直した。これが夢だろうと何だろうと、昔に戻ったような妻と話せる機会を失いたくなかった。
「あれは――家を片付けたときにカメラを見つけて、そのフィルムに残ってたんだ。あの日の前日、みんなでうさぎの公園に行った。それは覚えてるだろう?」
「もちろん」
妻は答えた。その声がくすりと笑った。
「こないだも、いきなり『うさぎの公園』だなんて言うから、初め、何のことか分からなかったのよ。それから少し考えて、よくあんな懐かしい呼び方を覚えてたなって。でもよくよく考えれば、自分が言い出したことだから覚えててもおかしくないかって思い直したけど」
「自分が言い出したって、俺が?」
身に覚えのない台詞に、俺は聞き返した。
「そう呼んでたのは子供だろう?」
「違うわよ。あれはあなたが言ったんだって」
思わずといったように、妻は吹き出した。
「『うさぎのいる公園があるから、行こう』って、あなたがそう言って誘ったのよ。だからわざわざ餌まで用意して行ったのに、うさぎなんてどこにもいなくって。それで由紀がずいぶん怒ってたの、覚えてない?」
「……そうだったか?」
まるで思い出せない俺に、妻はやはり楽しげだった。
「もう、どうして二人とも覚えてないのよ。由紀なんか『うさぎがいたような気がする』って言ってたし。『うさぎに餌をあげたらキューキュー鳴いて可愛かった』って。あんまりうさぎに会いたかったもんだから、きっと記憶を変えちゃったのね」
そういうことってあるでしょう――妻が言う。俺は戸惑いながらも頷いた。と、その拍子に、頭にある映像がひらめいた。それはこの二十五年、思い出すことのなかった――いや、俺一人では引き出すことのできない、記憶の奥底に仕舞い込まれていたものだった。
「いや――そうだ、いたよ、うさぎ」
その映像が蘇るままに、俺は口を開いた。
「あそこ、遊歩道があっただろ? そのずっと奥のところに、ふれあいコーナーみたいなやつがあったんだ。でも、滑り台やなんかとはかなり離れた場所にあったから、そのうちに行かなくなって……」
「本当に? でも、うさぎって鳴かないでしょう? うさぎの鳴き声なんて聞いたことある?」
妻は首を傾げるように言う。その瞬間、また別の映像がひらめいて、俺は思わず手を叩いた。
「違う、うさぎじゃない、あれはモルモットだ。モルモットがいたんだ。ほら、耳の短い、うさぎよりもでっかいやつ」
「モルモット?」
「いただろう?」
促すように尋ねると、ややあって、妻がゆっくりと頷く気配がした。
「ええ、確かにいたかもしれない。でもあれ、公園のモルモットだったかしら。何かあそこでお祭りでもあったときに、ミニ動物園みたいなのが来たんじゃなかった?」
「そうだったか?」
今度は俺が首を傾げる番だった。その気配を察したのか、勢い込んで妻が続ける。
「そうよ。だから、触るだけで、餌はあげないでくださいって書いてあったような」
「でも、由紀は餌をあげたって言ったんだろう?」
「そうだけど……じゃ、こっそり内緒であげたのかしら……」
電話の向こうで、再び、妻は考え込んだ。沈黙の中、窓の下をガヤガヤとうるさい中学生の集団が通り過ぎていった。ということは、もうじき道は車で混み始め、その渋滞を尻目に、体中に反射板をつけてウォーキングをする二人組が通り過ぎていくはずだった。大昔に巻き戻っていった時間が、ゆっくりと現在へと戻っていく。そんな感覚に、俺は時計を見上げた後、尋ねた。
「それで、由紀はどうして家に電話をかけてきたんだ?」
「そうだった」
思い出したように、妻は声を上げた。それから居住まいを正すように一呼吸置いて、こう言った。
「由紀ね、子供が生まれるんだって!」
不意打ちに、俺はよろめいた。
「子供……?」
それは眩しい光そのもののような言葉で、俺はそれを直視できずに、ただ口の中で繰り返す。
「子供、子供って?」
「お父さんったら」
さもおかしそうに、妻は笑った。それは俺の記憶に残っている通りの、幸せだった頃の彼女の笑い方だった。
「赤ちゃんよ。由紀の赤ちゃんが生まれるの! 相手とか時期とか、詳しいことはまだ聞いてないんだけど……あの子、お父さんの携帯の番号なんか知らないでしょう? だから、この家にかけたんだって。不思議よね、十桁の数字なんていまは覚えられる気がしないけど、昔覚えた電話番号って意外と忘れてないのよね。由紀もそう言って笑ってたわ。自分の携帯番号も忘れちゃうのにって……ねえ、聞いてる? あなた、お父さん じゃなくて、おじいちゃん になるのよ」
「おじいちゃん……」
――俺が?
たじろぐように、俺は窓ガラスに反射した自分の顔を見た。白髪の混じった太い眉。皺だらけの厳しい顔。しかし、その顔が今朝、鏡の中で見たものとは違い、どこか筋肉が緩んで見えるのは気のせいか。違う、そんなはずはない――動揺したまま振り返ると、そこには生活感のない、寒々しい景色が広がっていた。浴室のドアにかかったタオル、シンクに放り出された歯ブラシ、髭剃り――たった一つ、それだけ部屋の隅にきちんと置かれた黒いバッグ。俺はここで何をするつもりだったのか。頭が混乱し、それを振り払うように目を閉じて、開ける。すると、いままでの憎しみに満ちた生活がまるで嘘だったような、酷い白昼夢から目が覚め、我に返ったような、そんな奇妙な心地がした。
「私ね、あなたに謝りたくてここに来たの」
呆然とする俺に、電話の向こうから妻が言った。
「ここに来るまで、いろいろあった。それは長すぎて、全部をいま、この電話で話すことはできないけど、でも一番は、あなたに向きあってこなかったことを謝りたいの。ごめんなさい。いまさら遅いかもしれないけど、私、あなたと話したい。私の気持ちを押しつけたいわけじゃないし、誰に言われたわけじゃないけど、でも私たち、もう一度……」
俺の耳は妻の言葉を聞いてはいたが、頭は真っ白で何を言われているのか定かではなかった。ただ何かを失ってしまいそうな感覚だけが手のひらの熱を奪っていって――俺はごくりと息を飲んだ。携帯を持っていないほうの俺の手。俺の左手が空いている。そこには何かがあったはずなのに。次の瞬間、俺の目は床に落ちた封筒を捉えた。白い封筒。桜の押印のない、宛先だけが書かれた封筒。
それを手放しちゃだめだ――俺は封筒を拾い上げようとした。やめろ――それを別の声が止めた。何のためにいままで生きてきたのか考えろ――また別の声が言った。忘れない、真紀に俺はそう約束したはずだろう――と。
「あのとき家族はばらばらになった、って由紀は言ったわ」
俺の返事を待たず、涙声になって妻は続けた。
「その通りだと思う。でも、あの子、続けて何て言ったと思う? まだ間に合うって、まだ繋がってるんだって、あの子は言ったの。それを聞いて私、その通りだと思った。私たちは繋がってる、そうでしょう? だって、私たちはまだこうして話すことができるんだもの」
「――そうだな」
俺の声ではないような乾いた声が、俺の口からぽろりとこぼれた。同時に、いいのか――熱を失ったような声が、内側から俺に尋ねた。真紀との約束を破っていいのか、彼女の夢を見なくなってもいいのか、その他大勢の人々のように、彼女を忘れてしまっていいのか――。
真紀を殺したあいつを殺してやる――。それは長い間、俺を支えた目標だった。何物にも揺らぐことのない、固い固い決心だった。それをどうしてこんなにも簡単に手放してしまえるのか、俺自身にも分からなかった。けれど、確かなこととして、俺の手は床の封筒を拾い上げることができなかった。憎しみを取り戻すことができなかった。温かい光に触れた雪のように、凝り固まった憎しみは溶けていき、もう二度とそれを取り戻すことはできなくなってしまったような気がした。
俺は携帯を耳に当てたまま、床に座り込み、俺の一部ではなくなってしまったその封筒を見つめた。桜の押印のない封筒。住所と俺の名前だけが、村野の字で記された封筒――。
違和感を覚えたのは、そのときだった。この封筒はどこかおかしい。俺は床のそれを見つめた。なぜだろう、焦燥感が胸にこみ上げて――それはあの間に合わない夢 に似て、俺を急き立てた。早く、早く行かなければ、あのドアまで辿り着かなければ、あいつ がまたやってくる――。
何を考えてるんだ、あれは夢の話だろう。嫌な予感を振り払うように俺が頭を振るのと、電話の向こうで妻が不思議そうな声を上げたのは同時だった。
「あら。いま、玄関の方で音が……誰か来たのかしら」
「誰か?」
どきりとして俺は聞き返した。それはあの悪夢のように村野――であるはずがない。けれど、会社も辞め、友人もいなくなった、そんな俺の家に誰かが訪ねて来るはずがない。胸騒ぎに、けれど妻は呑気だった。
「宅配便とか頼んでるの? 見て来るわね。ちょっと待ってて」
「待て――」
自分でもわからないまま俺は言った。しかし時すでに遅く、俺の耳に届いたのは受話器をそのままにした妻の足音が、玄関のほうへ消えていく。
封筒に感じていた違和感の正体に気づいたのはそのときだった。いままで桜の押印がないことにばかり気を取られていた封筒。そこには、消印 が見当たらなかった。封筒に貼られた切手、そこに押されるはずの消印が、それが郵便局を経て、配達員の手によって届けられたという印がどこにも見当たらない。それは即ち、この手紙はその差出人によって直接、俺の家のポストに届けられたという証だった。差出人――つまり、村野正臣の手によって。
理解した瞬間、全身から血の気が引いた。
犯罪者は決して自分が悪いと思っていない。自分をそこへ追い込んだ誰か が悪いと思っている。自分に刑務所に入れた誰か が、自分から二十五年もの時間を奪った誰か が。この場合の誰か とは誰か。それは女弁護士とともに村野を助け、仮釈放のために動いた妻ではなかった――考えてみれば当然の展開に、俺は立ち尽くした。
それは妻ではなく、俺だった 。妻とともに村野を助けなかった俺こそが恨まれ、憎まれる対象だったのだ。真紀の命日にあいつを殺してやると、そう決意した俺のように、その俺を逆恨みしたあいつもまたそう決意していたのだ。真紀の命日、その真っ赤な夕方に、今度は俺の死体をあのリビングに横たわらせてやろう、と。
そのとき電話越しに、驚いたような妻の悲鳴が聞こえた。続けて、遠くで聞こえるはずのない声が、これも少し驚いたように言った。
「……あれ、なんで美希子さんがいるの?」
それは男の声だった。けれど、男にしては少し甲高い、少年のような声だった。声は少し震えたように続けた。
「やっぱり、美希子さんはそっちの味方だったの? 俺じゃなくて、俺の手紙を読まないようなやつの。離婚して会ってないって言ってたのに、本当はこそこそ隠れて会ってたってこと?」
話し声はだんだん近づいて来る。電話の方へ、一歩一歩、距離を縮めてくる。
「美希子!」
届くことがないと知りながら、俺は叫んだ。
「逃げろ、そいつはお前を――」
「いや、助けて! 助けて!」
大きくなった妻の声が叫んだ。その手で必死に受話器を掴んだのだろう、美希子――俺も必死に叫び返す。しかし、その次の瞬間だった。耳を塞ぎたくなるような悲鳴が響き渡った。続けて、どさりと何か重たいものが床に崩れ落ちる音。受話器の向こうには、あっけない終わりを知らせるような静けさが満ち、そこに俺の鼓動がうるさいほど響いた。それは毎日見る、あの悪夢とまったく同じ感覚だった。それがいつもと違うのは、悪夢なら覚めてしまえば終わるというのに、これは現実であるがゆえに、俺は終わらない続きと対峙し続けなければならないということだった。
その続きが――終わらない現実の俺の耳に、ごとり、受話器が持ち上げられた音がした。美希子――俺は思わず呼びかけようとし、けれど、すぐにそれが彼女ではないことに気づいた。荒い、獣のような呼吸音。こちらを窺う、憎悪の気配。
「――お前、村野だろう」
掠れた声で、俺は言った。それは問いだったが、しかし俺は答える間も与えず、問い詰めるように口早になった。
「お前、美希子に何をした? なぜ、こんなことをする? なぜ、どうして、真紀を、美希子を、俺の大切なものを奪うんだ――」
電話の向こうから、妻の気配は――その生命の気配は微塵も感じられなかった。けれど、それでも万が一を考え、俺は救急車を呼ぶべきだった。一刻も早くこの電話を切り、救急に連絡しなければ、助かるものも助からない。それなのに、そんな場面でさえ俺が口にするのはなぜ という問いだった。他人の命など虫けらほどの価値もないと思っているようなやつらから、納得のいく答えなど返ってこないというのに、失われてしまったものは、もう永遠に戻ってこないのだというのに、俺はまだなぜ と問いかけているのであった。
「……やっぱり読んでないんだな?」
するとそのとき、期待もしなかった声が聞こえた。その声。その話し方。やはり、村野だ。
「どうなんだ、やっぱり読んでないんだな?」
「何をだ」
俺は問い返した。そうしながら、よろけながら玄関へ向かった。やはり警察に知らせなければ――そうは思っても、この電話を切ることなどできなかった。駅まで行けば公衆電話がある。そこから警察を呼ぶしかない。
しかし、ドアへ向かう俺の足を、村野の言葉が止めた。
「手紙だ」
「手紙……?」
それがどういう意味か分からず、床の上に放り出されたままの封筒を、俺は振り返った。すると、いつのまにか滲んだ涙のせいで、一通きりであるはずのそれは何十通にも何百通にも――山のように重なって見えた。届くたび、焼き捨てていたその数を、俺は数えたことなどなかった。けれど、村野は数えていたのだろうか――そんな思いが頭をよぎった。
「やっぱり読んでないんだな」
電話の向こうで村野は呟いた。
「届いた手紙を、お前はどうしたんだ? 俺がどんな気持ちで書いたかも知らないで、読まずに破り捨てたのか?」
呟くような声は次第に大きくなった。その動揺が、混乱が、彼の言葉を乱していった。
「あんなに、あんなに俺が書いたのに、お前は何も、何一つ読んでないのか? ふ、ふざけるな! お前は、お前が、俺を無視しやがって!」
吠えるように、叫び続ける。
「これだって、お、お前の、全部お前のせいだからな! お前のせいだ! お前のせいで殺さなきゃなんなかったんだ! 俺はお前を殺したかったのに! お、俺を許さないお前を、美希子さんじゃなくて、お前だ! お前が許さないから、俺は二十五年も刑務所にいたんだ! その気持ちがお前に分かるかああああ!」
割れるような絶叫が響き渡った。それは妻の断末魔に――また、聞くことのなかった真紀の断末魔に、どこか似た響きがあった。電話の向こうで、村野は真っ赤な血に塗れていて、それは妻の体から流れ出したものであるはずだった。けれど、その絶叫を聞いていると、その赤はまるで彼の心臓から吹き出したものであるような気がした。
力が抜けていく体に鞭打って、俺は玄関を振り返った。俺の望みは、いまから全速力で家へ取って返し、あいつを殺すことだった。用意した包丁ではなく、俺のこの手で縊 り殺してやることだった。二度とあいつが俺の目の前に現れることのないように、もう誰もあいつに殺されることのないように。
「おい! 聞いてんのか! お前だ、お前が全部悪いんだ、お、俺じゃない、お前が全部悪いんだ!」
電話越しに、村野は叫び続けていた。けれど、いつまで経っても俺の足は動かなかった。あいつを殺すために立ち上がることさえしなかった。あなた、おじいちゃんになるのよ――頭に響くのは、妻の断末魔ではなく、そう報告した彼女の嬉しそうな声だった。母親になるという、お腹の大きくなった由紀が微笑む姿だった。そんな家族の想像に、憎しみは萎えてしまっていた。それはすっかり消えてしまったわけではなかったが、それでも憎む相手を殺したいと思い詰めるまでに、再び燃え盛ることはないのだった。
気力を失った俺は、ゆるゆると視線を床に落とした。一度手放した封筒を拾い上げ、見つめる。それから、二十五年間、一度もしたことのないこと――その封筒の封を切り、中の便箋を取り出した。三つ折りにされたそれを広げ、そこに記された文字を、読みにくい村野の文字を一語一語、確かめるように読み進めていく。
「俺にはもう何も残ってないんだ! お前たちが全部俺から奪ったんだ――」
それでもなお、村野は叫ぶのをやめなかった。その手紙の内容に、俺は嗚咽を堪えながら、そうして声が枯れるほどに叫び続ける村野を、初めてほんの少しだけ、本当にほんの少しだけ、哀れに思った。
予定通りにウィークリーマンションを借り、元・妻の動きを刑事のように見張り始めてから、一週間が経っていた。手帳がなくなってしまった理由をどう考えているのかは分からないが、そこに書かれた予定通り、妻は仕事へ出かける日々を送っている。
彼女がアパートの部屋から出てくるのは、午前九時。最寄り駅から電車に乗って三十分、下車駅にはいつも白いワゴンが待っていて、彼女を含めた数人がその車に乗り込む。その送迎ワゴンで職場であるクリーニング工場まで行くのだ。シフト開始は十時で終わりは六時、ワゴンが再び駅に戻ってくるのは七時過ぎで、そのあとはすぐに家に帰るか、たまに駅前で夕飯の買い物をするくらいで、寄り道はほとんどしない。休日の曜日は決まっておらず、けれどそれは週に一度か二度だと、手帳の空白が教えてくれている。
真紀の命日である今日は、「村野・野洲・宮崎と会う?」とだけ書き込まれていて、仕事は休みらしかったが、記述とは裏腹に、彼女は今日も駅へ向かった。まさか村野に会うのか――俺は緊張したが、何のことはない、たまたまシフトが変更になっただけの様子で、その横顔にはいつもと同じ、ぼんやりとした疲れが浮かんでいた。その服装もいつも仕事へ行くときと同じ、質素なシャツとズボン姿で、うさぎの公園に着てきたワンピースのような、外出用の服装ではない。まさか俺が見張っていることを知っていて、油断させるためにそこまでしているのだとも思わなかったが、それでも俺はいつものように妻の後を尾行し、彼女が駅の改札口を出て、送迎ワゴンに乗り込むのを確認してから、この部屋にとって返した。
彼女が働いている間、その留守を知らずに村野が訪ねてくる可能性は十分にあった。また、それは楽観的な想像で、悪い想像をすれば、あいつはわざわざ彼女の留守を狙い、
燃えるような夕日に、腕時計に視線を落とすと、針は五時過ぎを指していた。ワゴンが駅に戻ってくるのは七時過ぎだが、今日は村野に会うかもしれない特別な日だ。早めに出発したほうがいいかもしれない。
二人が友人のように再会を喜ぶ場面を思い浮かべ、俺は気分が悪くなった。今日は真紀の命日で、そんな日に――それもあの日と同じ赤い夕焼けが空を染める日に二人が会うなど、あってはならないことに思えた。しかし、同時にそうであったらいいと思う自分もいた。もし、村野が姿を現せば、あいつは真紀の命日に死ぬことになるのだから。
道の向こう側を、ダックスフンドを連れた中年女性が歩いていく。ということは、そろそろ部活を終えた中学生たちが自転車で通り過ぎていくはずだった。道は車で混み始め、その渋滞を尻目に、反射板を体中につけてウォーキングをする二人組が通り過ぎて行く。そうして、同じ時間に同じことが起こるその風景は、俺の目には奇妙に映った。まるで俺だけ時間が止まったように変わらない、別の世界に生きているようだった。いや、案外その感覚は正しいのかもしれない。あの日常に、俺はもう二度と戻れない。人殺しを企む俺のような人間は、もう二度と――。
ぱたり、ぱたり。意思とは裏腹に動いてしまう手を、俺は意識的に止めた。この部屋に俺が持ってきたものは少なかった。少しの着替えと、バスタオルと、髭剃り、石鹸、それからあいつを殺すための文化包丁。バッグ一つで済むような引っ越し荷物の中に、けれどこの封筒を入れてきたのはなぜだろう。村野から届いた、最後の手紙。刑務所の外から出された、桜の押印のない手紙を。
この手紙に何か記されているのか、封を開けない俺が知るはずもなかった。けれど、こんなものを持ってきたのは――そう、決心を鈍らせないためだった。二十五年間、待ち続けたこの日を、この機会を逃さないため。あいつへの憎しみを最大限に保ち続けるために持ってきたのだ。待ってろよ、真紀――カーテンの隙間から、赤く染まった空を見つめながら、俺は呟いた。待っててくれ、お父さんがいま、
そのときだった。ポケットの携帯が震えた。かけてくる人間などいないはずだが。俺はちらと画面を見て――心臓が止まりそうになった。表示されているその番号は
まさか、村野か? あいつが真紀の命日に、真紀を殺した場所へと戻ってきたのか――?
「あ、もしもし、
しかし、聞こえてきたのは村野の声ではなく――それどころか男の声でもない――驚いたことに
「
妻は再びその呼び名で俺を呼んだ。けれど、興奮して声を弾ませる彼女は、そう呼んでいることに気づいていない様子だった。
「あのね、いま、由紀からここに電話があったの。……あ、勝手に電話を取ってごめんなさいね。もちろん、ちゃんと『雨ヶ谷です』って名乗ったけど、すごく久しぶりだから緊張したわ。でも、大事な電話だったら困ると思って――」
「電話って……お前、家にいるのか?」
訳が分からず、俺は聞き返した。彼女は仕事に行ったんじゃなかったのか? それがどうして家に――しかもあんなに帰るのを拒否した我が家にいるのか。
「あ、そもそもそれを先に謝らないといけないわね」
妻ははっとしたように言った。
「ごめんなさい、勝手に家に入っちゃって。最初は外で待とうと思ったんだけど、昔、鍵を置いてあった場所を探したら、まだそこにあったから。ああいうのは変えとかないとだめよ、危ないから。でも、中は綺麗に片付いててびっくりしたわ。前は脱いだものも散らかしっぱなしだったのに。家具や何かもあのときと何も変わってないのね。……増えたのは、真紀の仏壇くらいかしら」
声が小さくなり、そこに少しの涙が滲んだ。
「あのブランコの写真、どこにあったの? 私、見たことないような気がするんだけど」
「あれは……」
答えようとする声が、痰が絡んだように
何も分からないまま、俺は咳払いをして、言い直した。これが夢だろうと何だろうと、昔に戻ったような妻と話せる機会を失いたくなかった。
「あれは――家を片付けたときにカメラを見つけて、そのフィルムに残ってたんだ。あの日の前日、みんなでうさぎの公園に行った。それは覚えてるだろう?」
「もちろん」
妻は答えた。その声がくすりと笑った。
「こないだも、いきなり『うさぎの公園』だなんて言うから、初め、何のことか分からなかったのよ。それから少し考えて、よくあんな懐かしい呼び方を覚えてたなって。でもよくよく考えれば、自分が言い出したことだから覚えててもおかしくないかって思い直したけど」
「自分が言い出したって、俺が?」
身に覚えのない台詞に、俺は聞き返した。
「そう呼んでたのは子供だろう?」
「違うわよ。あれはあなたが言ったんだって」
思わずといったように、妻は吹き出した。
「『うさぎのいる公園があるから、行こう』って、あなたがそう言って誘ったのよ。だからわざわざ餌まで用意して行ったのに、うさぎなんてどこにもいなくって。それで由紀がずいぶん怒ってたの、覚えてない?」
「……そうだったか?」
まるで思い出せない俺に、妻はやはり楽しげだった。
「もう、どうして二人とも覚えてないのよ。由紀なんか『うさぎがいたような気がする』って言ってたし。『うさぎに餌をあげたらキューキュー鳴いて可愛かった』って。あんまりうさぎに会いたかったもんだから、きっと記憶を変えちゃったのね」
そういうことってあるでしょう――妻が言う。俺は戸惑いながらも頷いた。と、その拍子に、頭にある映像がひらめいた。それはこの二十五年、思い出すことのなかった――いや、俺一人では引き出すことのできない、記憶の奥底に仕舞い込まれていたものだった。
「いや――そうだ、いたよ、うさぎ」
その映像が蘇るままに、俺は口を開いた。
「あそこ、遊歩道があっただろ? そのずっと奥のところに、ふれあいコーナーみたいなやつがあったんだ。でも、滑り台やなんかとはかなり離れた場所にあったから、そのうちに行かなくなって……」
「本当に? でも、うさぎって鳴かないでしょう? うさぎの鳴き声なんて聞いたことある?」
妻は首を傾げるように言う。その瞬間、また別の映像がひらめいて、俺は思わず手を叩いた。
「違う、うさぎじゃない、あれはモルモットだ。モルモットがいたんだ。ほら、耳の短い、うさぎよりもでっかいやつ」
「モルモット?」
「いただろう?」
促すように尋ねると、ややあって、妻がゆっくりと頷く気配がした。
「ええ、確かにいたかもしれない。でもあれ、公園のモルモットだったかしら。何かあそこでお祭りでもあったときに、ミニ動物園みたいなのが来たんじゃなかった?」
「そうだったか?」
今度は俺が首を傾げる番だった。その気配を察したのか、勢い込んで妻が続ける。
「そうよ。だから、触るだけで、餌はあげないでくださいって書いてあったような」
「でも、由紀は餌をあげたって言ったんだろう?」
「そうだけど……じゃ、こっそり内緒であげたのかしら……」
電話の向こうで、再び、妻は考え込んだ。沈黙の中、窓の下をガヤガヤとうるさい中学生の集団が通り過ぎていった。ということは、もうじき道は車で混み始め、その渋滞を尻目に、体中に反射板をつけてウォーキングをする二人組が通り過ぎていくはずだった。大昔に巻き戻っていった時間が、ゆっくりと現在へと戻っていく。そんな感覚に、俺は時計を見上げた後、尋ねた。
「それで、由紀はどうして家に電話をかけてきたんだ?」
「そうだった」
思い出したように、妻は声を上げた。それから居住まいを正すように一呼吸置いて、こう言った。
「由紀ね、子供が生まれるんだって!」
不意打ちに、俺はよろめいた。
「子供……?」
それは眩しい光そのもののような言葉で、俺はそれを直視できずに、ただ口の中で繰り返す。
「子供、子供って?」
「お父さんったら」
さもおかしそうに、妻は笑った。それは俺の記憶に残っている通りの、幸せだった頃の彼女の笑い方だった。
「赤ちゃんよ。由紀の赤ちゃんが生まれるの! 相手とか時期とか、詳しいことはまだ聞いてないんだけど……あの子、お父さんの携帯の番号なんか知らないでしょう? だから、この家にかけたんだって。不思議よね、十桁の数字なんていまは覚えられる気がしないけど、昔覚えた電話番号って意外と忘れてないのよね。由紀もそう言って笑ってたわ。自分の携帯番号も忘れちゃうのにって……ねえ、聞いてる? あなた、
「おじいちゃん……」
――俺が?
たじろぐように、俺は窓ガラスに反射した自分の顔を見た。白髪の混じった太い眉。皺だらけの厳しい顔。しかし、その顔が今朝、鏡の中で見たものとは違い、どこか筋肉が緩んで見えるのは気のせいか。違う、そんなはずはない――動揺したまま振り返ると、そこには生活感のない、寒々しい景色が広がっていた。浴室のドアにかかったタオル、シンクに放り出された歯ブラシ、髭剃り――たった一つ、それだけ部屋の隅にきちんと置かれた黒いバッグ。俺はここで何をするつもりだったのか。頭が混乱し、それを振り払うように目を閉じて、開ける。すると、いままでの憎しみに満ちた生活がまるで嘘だったような、酷い白昼夢から目が覚め、我に返ったような、そんな奇妙な心地がした。
「私ね、あなたに謝りたくてここに来たの」
呆然とする俺に、電話の向こうから妻が言った。
「ここに来るまで、いろいろあった。それは長すぎて、全部をいま、この電話で話すことはできないけど、でも一番は、あなたに向きあってこなかったことを謝りたいの。ごめんなさい。いまさら遅いかもしれないけど、私、あなたと話したい。私の気持ちを押しつけたいわけじゃないし、誰に言われたわけじゃないけど、でも私たち、もう一度……」
俺の耳は妻の言葉を聞いてはいたが、頭は真っ白で何を言われているのか定かではなかった。ただ何かを失ってしまいそうな感覚だけが手のひらの熱を奪っていって――俺はごくりと息を飲んだ。携帯を持っていないほうの俺の手。俺の左手が空いている。そこには何かがあったはずなのに。次の瞬間、俺の目は床に落ちた封筒を捉えた。白い封筒。桜の押印のない、宛先だけが書かれた封筒。
それを手放しちゃだめだ――俺は封筒を拾い上げようとした。やめろ――それを別の声が止めた。何のためにいままで生きてきたのか考えろ――また別の声が言った。忘れない、真紀に俺はそう約束したはずだろう――と。
「あのとき家族はばらばらになった、って由紀は言ったわ」
俺の返事を待たず、涙声になって妻は続けた。
「その通りだと思う。でも、あの子、続けて何て言ったと思う? まだ間に合うって、まだ繋がってるんだって、あの子は言ったの。それを聞いて私、その通りだと思った。私たちは繋がってる、そうでしょう? だって、私たちはまだこうして話すことができるんだもの」
「――そうだな」
俺の声ではないような乾いた声が、俺の口からぽろりとこぼれた。同時に、いいのか――熱を失ったような声が、内側から俺に尋ねた。真紀との約束を破っていいのか、彼女の夢を見なくなってもいいのか、その他大勢の人々のように、彼女を忘れてしまっていいのか――。
真紀を殺したあいつを殺してやる――。それは長い間、俺を支えた目標だった。何物にも揺らぐことのない、固い固い決心だった。それをどうしてこんなにも簡単に手放してしまえるのか、俺自身にも分からなかった。けれど、確かなこととして、俺の手は床の封筒を拾い上げることができなかった。憎しみを取り戻すことができなかった。温かい光に触れた雪のように、凝り固まった憎しみは溶けていき、もう二度とそれを取り戻すことはできなくなってしまったような気がした。
俺は携帯を耳に当てたまま、床に座り込み、俺の一部ではなくなってしまったその封筒を見つめた。桜の押印のない封筒。住所と俺の名前だけが、村野の字で記された封筒――。
違和感を覚えたのは、そのときだった。この封筒はどこかおかしい。俺は床のそれを見つめた。なぜだろう、焦燥感が胸にこみ上げて――それはあの
何を考えてるんだ、あれは夢の話だろう。嫌な予感を振り払うように俺が頭を振るのと、電話の向こうで妻が不思議そうな声を上げたのは同時だった。
「あら。いま、玄関の方で音が……誰か来たのかしら」
「誰か?」
どきりとして俺は聞き返した。それはあの悪夢のように村野――であるはずがない。けれど、会社も辞め、友人もいなくなった、そんな俺の家に誰かが訪ねて来るはずがない。胸騒ぎに、けれど妻は呑気だった。
「宅配便とか頼んでるの? 見て来るわね。ちょっと待ってて」
「待て――」
自分でもわからないまま俺は言った。しかし時すでに遅く、俺の耳に届いたのは受話器をそのままにした妻の足音が、玄関のほうへ消えていく。
封筒に感じていた違和感の正体に気づいたのはそのときだった。いままで桜の押印がないことにばかり気を取られていた封筒。そこには、
理解した瞬間、全身から血の気が引いた。
犯罪者は決して自分が悪いと思っていない。自分をそこへ追い込んだ
それは妻ではなく、
そのとき電話越しに、驚いたような妻の悲鳴が聞こえた。続けて、遠くで聞こえるはずのない声が、これも少し驚いたように言った。
「……あれ、なんで美希子さんがいるの?」
それは男の声だった。けれど、男にしては少し甲高い、少年のような声だった。声は少し震えたように続けた。
「やっぱり、美希子さんはそっちの味方だったの? 俺じゃなくて、俺の手紙を読まないようなやつの。離婚して会ってないって言ってたのに、本当はこそこそ隠れて会ってたってこと?」
話し声はだんだん近づいて来る。電話の方へ、一歩一歩、距離を縮めてくる。
「美希子!」
届くことがないと知りながら、俺は叫んだ。
「逃げろ、そいつはお前を――」
「いや、助けて! 助けて!」
大きくなった妻の声が叫んだ。その手で必死に受話器を掴んだのだろう、美希子――俺も必死に叫び返す。しかし、その次の瞬間だった。耳を塞ぎたくなるような悲鳴が響き渡った。続けて、どさりと何か重たいものが床に崩れ落ちる音。受話器の向こうには、あっけない終わりを知らせるような静けさが満ち、そこに俺の鼓動がうるさいほど響いた。それは毎日見る、あの悪夢とまったく同じ感覚だった。それがいつもと違うのは、悪夢なら覚めてしまえば終わるというのに、これは現実であるがゆえに、俺は終わらない続きと対峙し続けなければならないということだった。
その続きが――終わらない現実の俺の耳に、ごとり、受話器が持ち上げられた音がした。美希子――俺は思わず呼びかけようとし、けれど、すぐにそれが彼女ではないことに気づいた。荒い、獣のような呼吸音。こちらを窺う、憎悪の気配。
「――お前、村野だろう」
掠れた声で、俺は言った。それは問いだったが、しかし俺は答える間も与えず、問い詰めるように口早になった。
「お前、美希子に何をした? なぜ、こんなことをする? なぜ、どうして、真紀を、美希子を、俺の大切なものを奪うんだ――」
電話の向こうから、妻の気配は――その生命の気配は微塵も感じられなかった。けれど、それでも万が一を考え、俺は救急車を呼ぶべきだった。一刻も早くこの電話を切り、救急に連絡しなければ、助かるものも助からない。それなのに、そんな場面でさえ俺が口にするのは
「……やっぱり読んでないんだな?」
するとそのとき、期待もしなかった声が聞こえた。その声。その話し方。やはり、村野だ。
「どうなんだ、やっぱり読んでないんだな?」
「何をだ」
俺は問い返した。そうしながら、よろけながら玄関へ向かった。やはり警察に知らせなければ――そうは思っても、この電話を切ることなどできなかった。駅まで行けば公衆電話がある。そこから警察を呼ぶしかない。
しかし、ドアへ向かう俺の足を、村野の言葉が止めた。
「手紙だ」
「手紙……?」
それがどういう意味か分からず、床の上に放り出されたままの封筒を、俺は振り返った。すると、いつのまにか滲んだ涙のせいで、一通きりであるはずのそれは何十通にも何百通にも――山のように重なって見えた。届くたび、焼き捨てていたその数を、俺は数えたことなどなかった。けれど、村野は数えていたのだろうか――そんな思いが頭をよぎった。
「やっぱり読んでないんだな」
電話の向こうで村野は呟いた。
「届いた手紙を、お前はどうしたんだ? 俺がどんな気持ちで書いたかも知らないで、読まずに破り捨てたのか?」
呟くような声は次第に大きくなった。その動揺が、混乱が、彼の言葉を乱していった。
「あんなに、あんなに俺が書いたのに、お前は何も、何一つ読んでないのか? ふ、ふざけるな! お前は、お前が、俺を無視しやがって!」
吠えるように、叫び続ける。
「これだって、お、お前の、全部お前のせいだからな! お前のせいだ! お前のせいで殺さなきゃなんなかったんだ! 俺はお前を殺したかったのに! お、俺を許さないお前を、美希子さんじゃなくて、お前だ! お前が許さないから、俺は二十五年も刑務所にいたんだ! その気持ちがお前に分かるかああああ!」
割れるような絶叫が響き渡った。それは妻の断末魔に――また、聞くことのなかった真紀の断末魔に、どこか似た響きがあった。電話の向こうで、村野は真っ赤な血に塗れていて、それは妻の体から流れ出したものであるはずだった。けれど、その絶叫を聞いていると、その赤はまるで彼の心臓から吹き出したものであるような気がした。
力が抜けていく体に鞭打って、俺は玄関を振り返った。俺の望みは、いまから全速力で家へ取って返し、あいつを殺すことだった。用意した包丁ではなく、俺のこの手で
「おい! 聞いてんのか! お前だ、お前が全部悪いんだ、お、俺じゃない、お前が全部悪いんだ!」
電話越しに、村野は叫び続けていた。けれど、いつまで経っても俺の足は動かなかった。あいつを殺すために立ち上がることさえしなかった。あなた、おじいちゃんになるのよ――頭に響くのは、妻の断末魔ではなく、そう報告した彼女の嬉しそうな声だった。母親になるという、お腹の大きくなった由紀が微笑む姿だった。そんな家族の想像に、憎しみは萎えてしまっていた。それはすっかり消えてしまったわけではなかったが、それでも憎む相手を殺したいと思い詰めるまでに、再び燃え盛ることはないのだった。
気力を失った俺は、ゆるゆると視線を床に落とした。一度手放した封筒を拾い上げ、見つめる。それから、二十五年間、一度もしたことのないこと――その封筒の封を切り、中の便箋を取り出した。三つ折りにされたそれを広げ、そこに記された文字を、読みにくい村野の文字を一語一語、確かめるように読み進めていく。
「俺にはもう何も残ってないんだ! お前たちが全部俺から奪ったんだ――」
それでもなお、村野は叫ぶのをやめなかった。その手紙の内容に、俺は嗚咽を堪えながら、そうして声が枯れるほどに叫び続ける村野を、初めてほんの少しだけ、本当にほんの少しだけ、哀れに思った。