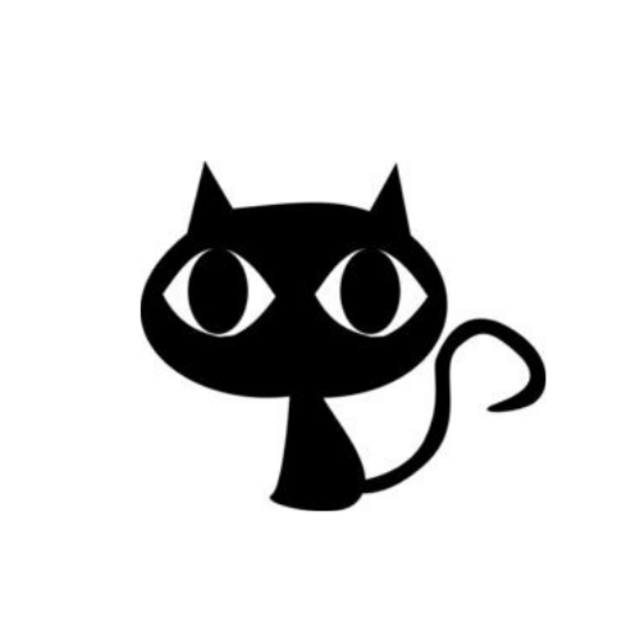再び、愛の章
文字数 20,355文字
「そろそろ時間になってしまいますが、最後にこれだけは言わせてください」
壇上の男性は、そう言うと広い会場を見渡した。その訴えかけるような眼差し。そのとき、彼の手のマイクが何度目かのハウリングを起こし、耳障りな高音が鼓膜をつんざいたが、思わず顔をしかめてしまったのは私一人で、他の誰もがそんなことを気にする様子は見せなかった。それほど会場は真剣な雰囲気に包まれていた。死刑囚が死刑執行を待つ拘置所、そこの元・刑務官だという、その男性の主張に聞き入っていた。
「これまでお話ししたように、殺人も、死刑も、その本質は同じだということを私は現場にいた人間として知っています。殺人は個人が個人を殺すことであり、死刑は国家が個人を殺すことです。だというのに、一方は重罪になり、一方はその重罪を贖 う手段として許されている。これは、本当におかしなことです。また、私は国家が個人を殺すと言いましたが、実際に『国家』という誰かがいるわけではありません。では、誰が死刑囚を殺すのかというと、それは私たちです。私たち刑務官が、この手で一人の人間の命を奪うことを国家に強制されるのです」
男性は聴衆に向かって手を広げ、それをぎゅっと握りしめた。その拳は震え、真っ赤に充血した目からは、涙がこぼれ落ちそうだった。
「私たちは『死にたくない』と叫び、暴れる死刑囚を数人がかりで無理やり押さえつけ、首に縄をかけ、執行ボタンを押します。これはドラマや映画などでよく知られていることですが、ボタンは三つあって、それを三人の人間が同時に押します。どのボタンが死刑囚の足元の床を開き、宙吊りにして殺したか、分からないようにするためです。ともあれ、そうして死刑囚は首吊り状態になります」
男性はそこで息を止めた。そして、まるでそこに死刑囚が見えるかのように、空中に手を伸ばした。
「太い縄から死刑囚がぶら下がり、苦しそうにもがいている。やめてくれ、と全身で叫んでいる。一人の人間の命が、目の前で消えていく。その最期を、彼が絶命するまでの数分間、私たちは直立不動で見つめます。所長以下、十数人の刑務官が何もせずに、ただ彼が死んでいくのを見つめるんです。これを異様と言わずに何と言いましょう。考えてもみてください。もし、これが日常生活の出来事だったら、死にゆく人をただじっと見ていることなんてしないですよね? 誰かが救急車を呼んだり、人工呼吸をしたり、必死で助けようとするはずです。それが人間の本能です。正しいあり方です。なのに、私たち刑務官にはそれができない。目の前で彼が死んでいくのを、ただじっと待ち続けることしかできないんです」
悲痛な訴えに、聴衆からため息が漏れた。隣に座った女性が洟 をすすり、手のハンカチで涙を拭うような仕草をしたので、私も慌ててそれに倣った。そうでなくても、仕事用の質素なシャツとズボンで座る私は、会場の中で少し浮いていた。せめて人と同じ仕草でもしなければ、完全に浮いてしまうだろうことは目に見えていた。
野洲も所属している「日本の死刑にNOを突きつける市民たちの会」主催のフォーラムに出席したのは、実に二十年振りのことだった。とはいっても、参加したのは一度きりで、それもまだ村野の無期懲役が確定する前のことだった。そのとき講演していたのは刑務官ではなく、現役弁護士だという人だったが、同じように死刑廃止をテーマに話をしていたことを覚えている。
『被害者遺族としての体験を、フォーラムで話してみみませんか』
そんな話があったのは、最高裁が終わった後のことだった。
『皆さん、美希子さんの話を聞きたがっています』
野洲はそう言って誘ったが、私はそれを断った。大勢の前で話すことは苦手だし、自分にそんな大役が務まるとも思えなかった。人前に出たくないのは、あの会見のせいもあった。初めこそ、テレビに映る自分に高揚感も覚えたが、何度も映像が流れるようになると話は別だった。自分の顔を見たくないばかりに、私はテレビをつけなくなり、一人暮らしのアパートへ引っ越すのを機にテレビそのものを捨ててしまった。
私は野洲の打診を断ったが、彼女はその後も諦めずに私を誘った。しかし、やはり私は断り続けた。そんなことが何度かあった。そのうちに野洲は私を誘わなくなったが、それでも講演会を知らせる会報は、私の元へ届き続けた。その中には興味のあるものもあったのだけれど、打診を断った手前、何となく行き辛いまま、今日まで過ごしてしまったのだ。
それがいまになって――それも突然、仕事を無断欠勤してまで、ここへ足を運んだのかというと、それは私自身にもよく分からないことだった。いや、今朝、アパートを出るまでは、仕事へ行こうとしていたのだ。本来は休日だったこの日に、無理やり仕事を入れてもらい、いつものように駅から工場までの、迎えのワゴンに乗り込んだのだ。けれど、信号待ちの車窓から見覚えのある景色が見えたとき、「すみません、降ろしてください!」――気がつくと、私はワゴンを飛び降り、この市営のフォーラムセンターへと続く並木道を歩いていた。いつか野洲と二人で歩いた道。その景色があまりに変わらないことに、ほんの少し、驚きを感じながら。
けやき通りという名の通り、頭上には欅 の濃い緑が茂っていたが、強い日差しに焼けたのか、道の両側に広がる芝生は枯れた色をしていた。いまはそこに誰もいないが、あとひと月もして涼しくなれば、あの木陰のベンチに座って読書をするのもいいかもしれないと、ぼんやりとそんなことを思いながらも、私の足は早まった。なぜ、突然、講演会へ来てしまったのか、その答えは陽炎の向こうに会場が見え始めたとき、ようやく分かったような気がした。
私はきっと、野洲に会いたいのだ。村野の仮釈放が決まったという連絡以降、彼女からの電話はなかった。いや、正確には、彼女は事務所の司法修士生である宮崎に電話させると言ったのだったが、その宮崎からもまだ何の連絡もなかった。それが私を不安にさせていた。
なぜなら、野洲の提案にあった日時――真紀の命日は、今日だった。9月6日。だからこそ、私は無意識に講演会があることを覚えていたのだろう。娘の命日に死刑廃止の講演を聞くというのは、野洲の言う「尊いこと」である気がした。少なくとも、いつものように仕事をしているよりは。
しかし――何度目かにそっと会場を見渡し、私は小さく息をついた。会場に野洲の姿はないようだった。ここへ来れば、きっと会えると思ったというのに。
「目の前の男を殺す、この死刑のボタン。私はこれまでに、これを三回、押しました」
そのとき痛みに耐えるような声が、マイクを通して大きく響き、私は慌てて彼に視線を戻した。その姿は悲しさを漂わせながらも、壇上で堂々として見えた。やはり、私には講演などできなかっただろう。後ろめたさに私は俯いた。人前で話すのは苦手だということ以上に、私にはその資格がない。野洲という光なしには愛の手触りを思い出せず、冷たさに迷ってしまう私は、きっと不安な言葉しか吐くことができない。聴衆を同じ不安に引き込むことしかできない。
それに比べて、壇上の元・刑務官の男性は自信に満ち溢れていた。自らは愛を知り、正しいことをしているのだという、確固たる響きがその声にはあった。
「もちろん、刑務官というのはそういう仕事 です」
その響きのままに、彼は言った。
「そういう仕事だ、それを分かって就職したんです。けれど、頭で理解するのと実際にやるのでは全然違う。私がこの仕事を辞めたのは五十歳のときでしたが、それまでに心を病んで辞めていった刑務官も少なくありませんでした。それくらい死刑というのは恐ろしいものなんです。人殺しが仕事の一部だなんて、とんでもない。死刑のある日本という国は、本当に異常です」
さざなみが起こるように聴衆が頷く。それを待って、彼は静かに続けた。
「繰り返しますが、欧米では死刑など、もはや前世紀の遺物なんです。けれど、日本ではどうでしょう。こうして志のある方々は集まりつつありますが、それでも廃止の議論さえなされていないのが現状です。人殺しは殺してもいいだなんて、そんな乱暴な理論はありません。彼らは間違いを犯してしまっただけなのです。だったら、その間違いを正せばいい。正す機会も与えず、殺すだなんて人間のやることじゃありません。もう一度言います。彼らも一人の尊い人間です。私や、あなたと変わらない人間なんです」
これで私の話を終わりたいと思います――男性が一礼すると、会場には割れんばかりの拍手が沸き起こった。前に進み出た誰かが男性に花束を手渡している。拍手が一層、大きくなる。私も懸命に手を叩きながら、一瞬だけ、本当にほんの一瞬だけ、そこにいるのが私だったらという想像をした。
もし、あのとき野洲の依頼を受け、こんなふうに大勢の人の前で正しさを訴えることができていたら、この拍手を受け取るのは私だった。そうなっていれば、私はその拍手を糧に、より正しさを信じることができていたかもしれない。こうして愛を探し、さまよわずに済んだかもしれない。そして何よりも、あの人の前で――あの懐かしい公園でも、堂々と振る舞うことができたかもしれない。
あいつをこの手で殺してやる――。
つい一週間前に聞いた台詞を、そのぞっとするような響きを私は思い返した。二十数年ぶりに会った元・夫の目は暗く、隠し切れない憎しみで溢れ返っていた。いや、隠し切れないのではなく、隠そうともしていなかったというほうが正しいかもしれない。その目を見た途端、私の小さな自信は吹き飛んだ。いまも闇の中をさまようこの人に、私なら光を見せてあげられるかもしれないという自信が。
笑われるかもしれないが、夫から電話があったあの日、だから私は、会って話をしようと切り出したのだ。野洲が私を救ってくれたように、私も夫を救うことができるかもしれない、そんな馬鹿みたいな考えが頭をよぎってしまったのだ。しかし、その結果はどうだ。私は野洲になれなかったばかりか、そのとき以上に愛を見失っている。彼の強い暗闇が、私の心までも黒く染めたのだ。
野洲にどうしても会いたくなったのは、そのせいもあるのかもしれなかった。更生した村野を殺すだなんて、村野と同じ人殺しの罪を犯そうとしているあの人に、私ができることなど何もなかったのだ。初めから何一つ――。
いや、一つだけあった――私は自嘲気味に思い直した。あのとき、私にできたたった一つのことは、すぐ警察に通報することだった。夫はかつての夫ではなくなってしまった。あの人は本当に村野を殺す気だった。一生を添い遂げようとしていた人の本気くらい、私にも分かる。だというのに、それなのにあのときの私はどうしたのだったか。辛うじて抱きしめていた愛が、村野を支援し続けた年月までもが揺らいでしまうような気がして、そこから逃げるように去ってしまったのだった。どうして私は正しさを信じきれないのか、愛というものを知りながら、その尊さをすぐに見失ってしまうのかと、自責の念に駆られながら。
壇上では閉会の挨拶が行われていた。その理事だという女性の話が終わると再び拍手が起き、会場にはざわめきが満ちた。人波が出口を目指してぞろぞろと進んでいく。しばらく待ってから出た方が良さそうだ。私は、無意識に手でカバンを探った。会場の時計は正午過ぎを指している。今更すぎるかもしれないが、職場に連絡をしなければと思ったのだ。説明できるような理由もないが、平謝りに謝らなくてはいけないだろう。
しかし、その手はすぐに止まった。肝心の連絡先を書いた手帳がない。そうだった、と私は顔をしかめた。あれはどこかで紛失してしまったのだ。いや、どこかではなく、あの「うさぎの公園」で。あの公園から帰ってすぐに無くなったことに気づいたのだし、帰りのバスや電車の中で手帳を広げた記憶もないから、きっとそうに違いない。
仕事のシフトは新しく書き写せばよかったが、連絡先が分からなくなってしまったのは不便だった。不便なだけではなく、その番号にいたずら電話でもされて迷惑がかかってもいけないし、誕生日などの情報も、いまどきは詐欺にも使われるのだと聞いたことがある。親切な人が拾ってどこかに届けてくれていたらいいのだけれどと、私はため息をついた。届いているとしたら、きっとあの洒落たレストランだろう。昔はあんな場所にレストランなどなかったから、わざわざ早起きをして、お弁当をつくって行ったものだ。
私は昔を懐かしく思い出した。それにしてもと、もう一つ、ため息をつくように思う。うさぎの公園、だなんて。あそこをそんなふうに呼んでいたこともあったっけ。
それは苦いのか甘いのか、懐かしい感情が胸に込み上げた。あそこは三ツ池公園といっただろうか。三つ池があるから三ツ池公園なのかと、そんなふうに納得したような記憶がある。けれど――「うさぎの公園」。遠い昔、確かに子供たちは、そんなふうに呼んでいた。けれど、それを夫から、ましてや長い年月の後、突然電話して来た元・夫の口から聞くことになろうとは、予想だにしていなかった。
それならどこかで会いましょう――いまでは無謀と思えるそんなを提案したとき、その懐かしい名前は夫の口から出たのだった。『それなら、明日、うさぎの公園で』。そう言って、電話は切れた。
私は混乱もあって、初め、それがどこを意味するのかまったく思い出すことができなかった。けれど、一度思い出してしまえば、その思い出はまるで開かれることを待ちわびていた物語のように、私の目の前に広がった。花の咲き乱れる遊歩道を、振り返りもせずに駆けて行く子供たちの後ろ姿が、お揃いのひまわり柄のワンピースの裾が軽やかに翻 る様が、『転ばないでよ』――声をかけ、寄り添うように並んだ私たちが、その後ろ姿を見失わないように、けれどゆっくりと歩いていく光景が――。
『お母さん、うさぎはどこ?』
と、唐突に、思い出の中の由紀が私を振り返り、尋ねた。手にはニンジンを入れたビニール袋。ああ、そうだった――私は滑り台のほうへ駆けていく真紀を目で追いながらも、さらに記憶を蘇らせる。そもそも、この公園を訪れたのは、夫が同僚から「遊園地みたいな公園がある」と聞いてきたのがきっかけだった。そして、喜ぶ子供たちに、夫はさらに付け足したのだ。「そこ、うさぎもいるらしいぞ」と。
けれど、聞いた場所が違ったのか、それとも初めからその同僚の勘違いだったのか、公園にうさぎはいなかった。幼い真紀は、それでも大きな滑り台やブランコで満足したが、由紀のほうはといえば、ニンジン入りのビニール袋を握りしめ、いつまでも拗 ねていた。機嫌を取ろうと、一緒に滑り台を滑ってやっても無駄だった。由紀にはそんな頑固なところがあった。うさぎがいないと分かったにも関わらず、「うさぎの公園」と呼び続けたのも由紀だったと思う。そして、それはいつのまにか、家族の間でしか通じない呼び名になった。
あの子はどうしているだろう。いまは連絡もくれなくなった娘を思い、私は息をついた。
中学を卒業すると、由紀は私の元を離れ、寮付きの高校へ行ってしまった。それも無理はないだろう。真紀がいなくなり、夫が出て行き、私たちの生活は以前とはまるきり変わってしまった。由紀はきっとそれが嫌だったのだ。また、決して口にはしないが、私が村野の更生を助けることも気に食わなかったのだろう。私が愛というものを、野洲ほどうまく説明できなかったのもその理由の一つだと思う。高校を卒業して就職した後は、帰省も年に一度あればいいほうで、やがては電話すらなくなってしまった。お腹を痛めて産んだ娘は、二人とも私の元を離れていってしまったのだ。
けれど、暗黙のうちに、私はそれを許した。
殺された妹がいるという過去は辛い。野洲に会う前の私のように、きっと由紀はその過去を忘れてしまいたいのだろう。関わりを絶ってしまいたいのだろう。そうしないと幸せになれない、そう思っているのだろう。その気持ちは痛いほどに理解できた。
『辛くなったらいつでも帰ってきてね』。家を出るとき、私はそんなメッセージを中に入れたお守り袋を持たせた。小さい頃、由紀のお気に入りだったアニメのリボンをつけて。こんな子供っぽいのはやめてと、そう言って由紀は嫌うかもしれなかったが、それは直接口では伝えられない、私にできる精一杯だった。
そのお守りの中のメッセージを、きっと由紀は読んだことだろう。だというのに頼ってこないということは、きっと幸せになって、自分のことは放っておいて欲しいという無言の要求なのだろう。寂しさはあったが、私は自分にそう言い聞かせた。由紀は立派に独り立ちしたのだから、それを悲しむことはない、と。
私は椅子から立ち上がった。長く座っていたせいで膝が固まっていた。それをほぐすように動かし、ゆっくりと伸ばす。そうしているうちに、思い出も、由紀の姿も、色あせた澱 となって心の底へ沈んでいき、私の意識は現実へと戻った。職場へ連絡しなければならないことを思い出し、手帳を取り戻すためにうさぎの公園まで行くべきかと、そんなことを思いながら歩き出したときだった。
「梶田さん」
後ろから呼び止められた。振り向き、見上げると、化粧っ気のない若い女性がいた。宮崎だ。どことなく感じの良くない、野洲の事務所の司法研修生――。
「お久しぶりです」
鴨居に頭をぶつけそうなほど背の高い宮崎は、そう言って軽く頭を下げた。挨拶もそこそこに、つっけんどんにも聞こえる口調で続ける。
「野洲先生から電話するようにって言われてたんですけど、タイミングが合わなくて……いま、ちょっといいですか」
「なんでしょう」
渋々私が聞き返すと、宮崎は人の少なくなった出口に目をやった。
「ここだとあれなんで、何か飲みながらでも」
「いいですけど……」
村野のことなら、単に日程を擦り合わせるだけの話ではないのか。にわかに私の胸は騒いだ。まさか、夫が村野を見つけてしまったのだろうか――最悪の想像が頭をよぎる。いや、そんなはずはない。そんなことが起きたとするなら、私の元へとやってくるのは宮崎ではなく、警察だ。だから、これはそういうことではないのだろう。
しかしこちらのことなど気にもかけず、早足で宮崎は歩き出した。ホールに併設されている喫茶店に行くのかと思いきや、それを通り過ぎ、日差しの照りつける外へ出た。一体どこへ行くのだろう。たまらず足を止めると、宮崎はこちらを振り返った。「すぐそこですから」と言うと、並木道をずんずんと進んで行く。その足は自販機の前まできて、ようやく立ち止まった。
「私が出しますけど、何がいいですか」
よろよろと私が追いつくのを待って、宮崎はちらりと枯れた芝生を見やった。私は半ば呆れながら、宮崎の目線の先を見た。あとひと月もすれば涼しいだろう、けれどいまは蒸し暑いだけの木陰のベンチ。
「今日は暑いし、喫茶店にでも入ったほうが……」
思わず私が口走ると、彼女は迷惑な提案だと言わんばかりに顔をしかめた。
「喫茶店の飲み物って、量が少ないのにバカみたいに高くて嫌なんですよね。それに私、クーラーの風って冷えちゃって苦手なんです」
「そう……」
そう言われれば強く言い返せない私は、促されてお茶のボタンを押した。ガコン、安っぽい音でペットボトルが落ちてくる。宮崎はそれを拾い上げて私に差し出すと、先にベンチに腰掛けた。バックから飲みかけの水を取り出し、一口、飲み込む。仕方なく、私もペットボトルに口をつける。早く済む話だといいけど――そう思いながら、隣の宮崎をちらと見ると、その口は一文字に結ばれ、眉は怒ったように顰 められていた。
こんな暑い中に連れ出され、その上ペットボトルのお茶をあてがわれ、怒り出したいのはこちらだとは思ったが、しばらく経っても彼女は無言で、その表情も変わらない。何か気に障ることでもしてしまっただろうかと、落ち着かない気分になり始めた頃だった。ようやく彼女は「村野さんのことなんですけど」と切り出した。
「梶田さんって、本当にあの人に会いたいんですか?」
質問もさながら、その怒ったような口調に私は驚き、思わず宮崎を見上げた。高い場所から私を見下ろす彼女の顔は、木漏れ日というには強すぎる夏の光が作り出した影のせいか、まるで宇宙人か何かのようだった。同じ言葉を話しているようで、まるで意思疎通のできない地球外生命体。その未知の生物が、よく意味の分からない質問を私に投げかけていた。あなたは本当に村野に会いたいのか、という。
「会いたいかって、どういう……」
むっとした私は、反射的に口を開いた。
こんなところまで連れて来てどんな話があるかと思えば、一体この人は何を言い出すのか。私は若い宮崎を睨むように見据えた。
彼女は確か、今年で二十五歳だと言っていた。つまり、彼女が生まれてからいままでの、気が遠くなるような年月をかけて、私は村野を支援してきたのだ。面会に行き、手紙を出し、彼を赦し、その更生を助けたのだ。野洲とともに尊い愛の光で以って、彼の仮釈放まで漕ぎつけたのだ。
その私に向かって、本当に会いたいかとは何事だ。彼女は自分の口にした言葉の意味が分かっているのだろうか。それとも――。
「いや、別に梶田さんがいいならいいんですけど。私はどうこう言う立場じゃないので」
怒りの気配を察知したのか、宮崎は目をそらし、肩をすくめた。
「じゃ、面会の日程と場所についてですけど――」
「ちょっと待って」
私はそれを制止した。
「本当に会いたいのかって、どういう意味でしょう? どうしてそんなこと聞くのか、教えてほしいんだけど……」
その若さゆえか、宮崎が人を尊敬することを知らない、失礼な人間だということは分かっていた。二十五年という年月の重みも、その苦難さえ想像がついていないのだろうとは思う。けれど――何かが私の胸に引っかかっていた。その分からない何か がなぜか気になり、どうしても聞かずにはいられなかったのだ。
「どういう意味って言われても」
真剣な問いに、宮崎は眉間に皺を寄せた。面倒くさそうに、あのつっけんどんな口調で言う。
「いや、本当に会いたいのかなって思っただけです。だから、梶田さんが別にいいんならいいんです。すいません」
とってつけたような謝罪を口にする。けれど、私はさらに尋ねた。
「私が本当は会いたくないと思ってるように見えたってこと? これまでの面会でも、嫌々会ってるふうに見えたとか?」
言葉を重ねるごとに、なぜか私は必死になっていく自分を感じた。本当ならあまり話したくないような相手に、何をそんなに必死になるのか分からない。それなのに、私はそんな自分を止められなかった。どうして――繰り返す私に、宮崎はますます困惑したようだった。
「だから、そう思っただけです。違うなら別に――」
「どうして?」
だから、もういいって言ってるじゃないですか――宮崎の顔にはそう書いてあるようだった。けれど、私はどうして、と繰り返した。
そう問いかけているうちに、ふとこれは宮崎へ向けた問いではないということに気がついた。それは、自分への問いだった。村野に本当に会いたいのかという、二十五年分の自信で肯定できるはずの問いに、どうして私は引っかかりを感じたのか。そこに些細ではあるが、何か致命的な、決して気づいてはいけないことに気づいてしまったような、そんな感覚に囚われたのだった。
それは一体何だろう――見えない風に目を凝らすように、私は感覚を研ぎ澄ませようとした。
「だって、自分の子供を殺した人じゃないですか。普通、会いたくないですよ」
そのとき、どうして、の答えを宮崎が口にした。胸に引っかかった何か が、その言葉にほんの僅か、風を感じた。けれどその微かな風は、それに、と宮崎が付け加えるように放った言葉の衝撃で吹き飛んだ。
「梶田さんってそんなタイプでもないから、野洲先生にうまく乗せられちゃったんだろうなって感じだし」
「……先生に、乗せられてる?」
何を言われているのか分からず、私は聞き返した。すると、宮崎は再び肩をすくめた。
「いや、まあ、分かりますけどね。あの人、カリスマ的だし。だから信者もいっぱいいるわけだし」
「カリスマ? 信者って?」
まったく心当たりのない言葉に、私は置いてけぼりを食ってぽかんとした。しかし、彼女はそんな私のほうも見ることもなく、吐き出すように続けた。
「ってか、私も元・信者ですから気持ちは分かりますけど。とは言っても私の場合、梶田さんみたいに巻き込まれたってわけじゃなくて、小さい頃からテレビで見て憧れてたから、進んで近づいたんですけどね。だから、修習生で採ってもらったときはすごい嬉しかったんですけど、やっぱ実態を知っちゃうとなんだかなって感じがすごくて。だって、どんな犯罪者でも無罪にするのが弁護士って、そんなのってないなっていうか。……ああ、私、これで結構、正義とか信じてる方なんで」
その唇がほんの少し歪んだのは、笑顔を作ったつもりなのだろうか。しかし、その笑みの理由も、言われた言葉も理解できなかった私は、かろうじて聞き取ることのできた部分を尋ねた。
「宮崎さん、その、元・信者って……」
「ああ、先生から聞いてないですか? 私、事務所辞めるんですよ」
あっさりと彼女は答えた。
「ついでに弁護士志望もやめて、犯罪心理学みたいな分野に進もうかなって。で、いつかワイドショーのコメンテーターになって、先生とバトルしようかなって……って、それは面白そうだなって思ってるだけですけど。それまであの人がテレビ出てるかも分かんないですし」
「あの人って、野洲先生のこと?」
訳が分からないまま、私は尋ねた。
「野洲先生が、今度テレビに出るっていう話?」
すると、宮崎の眉間に皺が寄った。このおばあちゃん、何も知らないのかしら――表情が露骨にそう言っている。
「テレビは私、全然見ないから……」
言い訳のようにつぶやきながら、私はそろりと胸に手を置いた。微かだが、そこにまだ風は感じられた。けれど、その先には何があるのか分からない。それは良いものか、悪いものか、少しでも私が欲しいと願っているものなのだろうか。
「テレビ見ないとか、そういう人もいるんですね」
宮崎は呆れ顔で言った。
「いや、あの人、一時期テレビに出まくってたじゃないですか。それこそ、梶田さんと会見した後からですよ。それで有名になって、法律番組とか、バラエティ番組とか出て……知りませんでした?」
野洲からそんな話を聞いたことはない。つい、恨み言のような台詞が口をついた。
「野洲さんも、教えてくれれば良かったのに」
「敢えて教えなかったんだと思いますけどね」
宮崎は吐き捨てるように続けた。
「梶田さんは大切な信者さんだから、タレント活動を知られたくなかったんじゃないですか? テレビにはテレビのキャラがあるし、やっぱ計算高くいかないと」
「計算?」
「そうですよ。言っときますけど、あの人が死刑廃止をテレビで訴えてるとこなんて見たことないですからね。そりゃ、経歴のテロップに『死刑廃止を訴えている』くらいは出ますけど、それもキャラ付けくらいな意味しかないですよ。死刑廃止とかいうと、すごそうだし、信者も増えるかもしれないし、自分もいいことしてるような気分になれるし、いいこと尽くしじゃないですか。実態は、人殺しを野に放ってるだけだとしても」
「それはちょっと言い過ぎでしょう」
胸をざわつきに気を取られながらも、私は言い返した。
「野洲先生がテレビでどう振る舞っているのかは知りませんけど、あの人の信念や情熱は本物です。だからこそ、村野さんも更生した。宮崎さんもそれは分かってるでしょう」
「ええ、分かってます」
宮崎は頷いた。何を考えているのか分からない、あの宇宙人のような漆黒の瞳で私を覗き込むように見る。
「じゃ、梶田さんは村野正臣が本当に更生したと思ってるんですね」
「それは、もちろん――」
反射的に私は答えて、それから黙り込んだ。胸をざわつかせる風は、いまや辺りの空気を巻き込むほどに大きくなっていた。どうして――再び、私は自分に問いかけた。そろり、柱の陰から何か恐ろしいものを覗くように、彼の顔を思い出す。刑務所の面会室にある、アクリル板越しに見た彼の顔。
面会室でのことをあまり思い出したくないのは、彼のせいではなく、中に入るだけで押し潰されてしまいそうな雰囲気のある刑務所という場所のせいだった。そこでの出来事はいつも地に足のつかない、夢の中の出来事のようで、アクリル板の向こうにいる彼もまた、夢の中の人物のようだった。それは良い夢なのか、悪夢なのか。けれど一つだけ確かなことは、それが変化を伴う夢だということだった。
初め、どこかだらしない印象だった彼は、徐々に真面目な顔つきに変わっていった。あれは五年ほど経った頃――いや、もう少し経った頃だろうか。その真面目な顔に、怯えたような表情が加わるようになった。彼は突然、人が変わったように自分の罪を恐れ出したのだ。『あなたはもう赦されているんですよ』と、優しく言葉をかける野洲をそっちのけで、彼は私に何度も謝った。すみません、すみません、すみません――血を吐くような謝罪を前に、私はどうしたらいいかも分からず、ただ漠然とした恐怖を感じていた。謝罪に恐怖を感じるなんて、おかしなことだろうか。いまから思えば、面会が憂鬱になったのはあの頃だけだった。
けれどその後――それも何年かかかったはずだが――彼は落ち着きを取り戻し、ようやく面会室にも安寧が戻ってきた。そして、最後に彼を見た夏の初め頃にはもう、その顔はとても落ち着いていた。年齢を重ねて少し細くなった頰に浮かんだ笑みは、悟りを開いた仏僧のようで、それは更生した証だと、私は嬉しく思っていた。野洲と共にそれを喜んでいた。
それなのに、村野正臣が本当に更生したと思ってるんですねという宮崎の問いに、どうして私は頷くことを躊躇 ったのか。それ以前に、更生を果たした村野に本当に会いたいのだと、言い切ることができないのか。
ぐるぐると思考が渦を描く。宮崎はそんな私の反応を嘲笑 っているようだった。いや、それは私の考えすぎだろうか。彼女の表情はこれまでと同じにそっけない。そのそっけない調子のまま、彼女は尋ねた。
「梶田さん。なぜ犯罪を犯す人間がこの世にいるか、知ってますか」
「それは……いろいろあると思うけど」
風に巻き込まれまいとする一心で、私は答えた。
「村野さんの場合は、虐待されたから――」
「じゃ、虐待されて育った人間が全員人殺しになりますか」
「それは違うけど――」
言いかけて、私はどこかでこんな問答をしたことを思い出す。――元・夫だ。あのうさぎの公園で、夫もいまの宮崎と同じ問いを口にしたのだった。
「ですよね。じゃ、それは理由にならないですね」
しかしあのときの夫とは違い、至極真面目に宮崎は言う。私もあのときのように言い返した。
「そうかもしれないけど、それは原因の一部というか、ほら、他にも色々あったわけでしょう。裏切られた経験とか、親がいない寂しさとか。そういう原因が集まって」
「じゃ、例えば、そういう『原因』が十個集まったら人殺しになるとか、そういうことですか?」
「そういうのじゃないけど」
「それなら、どういうことですか? もし、梶田さんが、村野さんとまったく同じ環境で育ったとしたら、梶田さんも殺人を犯していたってことですか?」
「そんなの知りませんよ!」
私はとうとう音を上げた。夫といい、宮崎といい、どうしてこんなに分からず屋なのだろう。普通の人なら感覚で理解してくれるだろう「愛」が、どうしてこの人たちからはこんなに遠いのだろう。夫も、宮崎も、宇宙人だ。人間の心が分からない、地球外生命体だ。
「じゃ、宮崎さんはご存知なんですか?」
その宇宙人に、私は渾身の嫌味を言った。しかし、それが嫌味とも分からないのか、宮崎は頷いた。おもむろに口を開く。
「実は、犯罪を犯す人間の脳には、欠陥があるんですよ」
「脳?」
意外な答えに、私は思わず眉を顰 めた。
「脳って……この、脳みそのこと?」
「そうです」
したり顔をするわけでもなく、むしろなぜそんなことも知らないのかといった様子で、宮崎は頷いた。
「これはテレビなんかでもやってる、れっきとした脳科学の話なんですけど……ある研究者が殺人犯たちの脳を調べたんですね。そしたら、彼らの脳にはすべて、その一部に損傷があるということが分かったんです。当たり前ですが、人間はその行動のすべてを脳で決定します。じゃ、その脳に損傷があるとどうなるか。その人は衝動的になりやすく、判断能力が低い人間になります。ということはつまり、犯罪を犯しやすくなるということです。いいですか、考えてみて下さい。例えば、梶田さんが誰かにムカついてたとして、その人を殺しますか? または、お金に困ってるからって、見ず知らずの人間を殺しますか? 普通は殺さないですよね? いや、殺さない というよりも、殺せない んです。そうでしょう? でも、世の中には殺してしまう人がいる――それが、犯罪者になる人間、つまり脳に損傷のある人間なんです。彼らはいわば、生まれながらの犯罪者なんです。ということは、どういうことかというと――」
宮崎は一気に言うと、私を見下ろした。それから、まるで判決を言い渡すように言った。
「犯罪者が更生するなんて、有り得ないってことです。犯罪を犯す脳がそのままなんだから、いくら反省とか、謝罪とか口で言ってたとしても、そんなものには意味なんてないんです。なぜ殺人を犯してしまうのか 、そんなのは彼ら自身にも分からないんですよ。だって、問題は脳なんですから。理由なんかないし、そんなこと聞いたって無駄なんです。さっきの講演で刑務官の人が『同じ人間だ』とか言ってましたけど、あんなの大嘘ですよ。私たちは同じ人間じゃないんです。まともな脳と、損傷した脳が考えることは全然違うんですから。だから、犯罪者なんか全員、精神病院にでもぶち込んじゃえばいいんです」
そう言い切ると、彼女はぎゅっと上下の唇を閉じた。脳みその損傷。初めて聞いた話に混乱しながら、私は彼女の短髪の下の皮膚、さらにその下の頭蓋骨に覆われた彼女の脳みそを想像した。それから、同じように村野の脳みそを想像しようとした。彼の脳みそは損傷しているのだろうか? だから彼は反省も、更生もできず、けれどそのまま仮釈放されて――。
「村野さんは、また誰かを殺すかもしれないってこと?」
恐ろしい考えが閃き、私はそれをそのまま口にした。
「真紀のような子が――また誰か子供が殺されるってこと?」
「その可能性はあるし、普通の人よりその可能性は高いかもしれないですよね」
あれだけ熱を込めて語っておきながら、宮崎は冷たく言った。
「可能性の話ですから、実際にそうなるかなんて誰にも分かんないですけど」
「でも、もしそうなら――」
急に背筋が寒くなり、私はごくりと唾を飲んだ。
「どうしたらいいの、私のせいで――」
さっきまで思い浮かべていた村野の笑顔が、急に恐ろしいものに思え、私は怯えた。あの悟りきった仏僧のような笑み。果たしてそれは心からのものだったのだろうか? そう言われてみれば、口では笑っているようでも、その目は笑っていなかったような気がする。励ましの言葉をかける私に、野洲に、彼は本心では何を思っていたのだろう? 俺を許すなんて馬鹿なやつらだと、せせら笑っていたのだろうか。
「……ほんと、梶田さんって自分がないんですね」
すると、呆れたように宮崎が言った。
「まあ、だから家族も捨てて、先生一筋になっちゃったんでしょうけど。にしても、詐欺とか大丈夫かって、心配になるレベルですよ」
「詐欺……?」
私はぼんやりと聞き返し――それから、違う、と首を振った。精一杯、宮崎を睨みつける。
「家族を捨てたってどういうこと? そんなこと、したつもりはないけど」
「いや、梶田さんが先生側に行ったから、旦那さんとも離婚したって聞きましたけど」
「誰が言ったの、そんなこと」
無性に怒りが湧き、私は言い返した。どんな言葉を使ってでも、宮崎を打ち負かさなければならない、そんな気がした。
「言っとくけど、夫は――元・夫はね、更生した村野さんに復讐しようだなんて思うような人よ。村野さんが送り続けてる謝罪の手紙も読まずに捨てるような人よ。死刑にだって賛成してるし、それに、それに――まだ血の跡が残ってる家に平気で住んでるような、とにかくひどい、気持ち悪い人なの。そんな人と一緒にいられると思う? だから私は離婚したのよ。あの人が、そんな人だとは思わなかったから。昔は優しかったのに、あの事件で人が変わってしまったから――」
夫は最低な人間だという証拠を、もっと宮崎に投げつけなければならないのに、そこで言葉を失った私は金魚のようにパクパクと口を動かした。野洲ならここで、「愛を知らない、可哀想な人ですね。でもだからこそ、私たちがそういう人から村野さんを守ってあげなければ」などと言い、慰めてくれるはずだった。けれど、宮崎は違った。彼女は呆れ顔のまま、言った。
「でもそれって、普通だと思うんですけど」
「普通?」
「ええ」
憮然と彼女は答えた。
「だって、娘さんを殺されたんでしょ。普通、そう思いますよ。復讐したいとか、手紙読みたくないとか、死刑賛成とか。ってか、血の跡が残ってるから気持ち悪いとか、そんなこと言う人のほうが怖いんですけど。他人の血ならともかく、娘さんの血だし。それを気持ち悪いとか、ちょっと……」
宮崎が、理解できないものを見るような目で――宇宙人でも見るような目で私を見る。その視線に私はたじろいだ。違う。宇宙人は私ではない。宮崎だ。なのにどうしてそんな目で見られなくてはならないのか。
「でも、あの人は本当に村野さんに危害を加えるつもりなのよ。間違いないの。だって、ついこの間、会って聞いたんだから」
「そうですか」
しかし、宮崎の反応は薄かった。まるで私が嘘をついているとでもいうように。
「嘘じゃないのよ」
「じゃ、尊い『愛』で何とかしてあげたらどうですか」
「愛?」
「それで村野さんは更生したんですよね。だったら、どうして旦那さんには教えてあげないんですか」
「それは……」
私は口ごもった。言いたいことは山ほどある気がしたが、そのどれを口にしたとしても、宮崎は納得してはくれない気がした。そんな私を軽蔑するように、宮崎は冷たい視線を投げた。
「村野さんが更生できたのが支援のおかげだとしたら、旦那さんが変われないのは一人だったせいなんじゃないですか」
一人。その言葉に一瞬どきりとするが、めげずに私は言い返した。
「夫を無視して、村野さんに向き合った私がおかしいって言いたいの?」
それは精一杯の攻撃だったが、宮崎は気もなさそうに肩をすくめただけだった。
「別に勝手だとは思いますけどね。でも人に頼るんじゃなくて、少しは自分で考えたらどうですか。このまま野洲先生の言いなり人形でも、私には関係ないですけど」
そう言って、腕時計をちらりと見ると立ち上がる。
「じゃ、そろそろ次の用事があるので。……村野さんに会いたいのかどうか、決まったら連絡ください。私の番号、ご存知ですよね」
「ちょっと待って」
反射的に私は引き止めた。意図したわけではないが、その声にはすがるような響きがあった。それを宮崎は嫌うように一瞥 すると、無言でこちらに背を向けた。飲みかけのペットボトルを手にした長身が、日差しの中へ消えていく。
反論したいことは山ほどあった。反論しなければならないことも。第一、私は野洲の言いなり人形ではないし、離婚も野洲のためではない。ましてや、由紀が出て行ったことには、野洲は全く関係ない。
――本当に?
そのとき、忘れかけていた風が微かに胸をざわつかせた。それは初め、村野に会いたいのかと聞かれたときに感じた風だった。
――本当に野洲は関係ないの?
風の運んできた問いに、先程と同様、私は答えることができなかった。なぜ答えることができないのか。もがいていると、日差しが急激に冷え、私は自分のアパートの一室にいるような錯覚を覚えた。一人で毛布にくるまっている、孤独な私。泥に半身を呑まれたように動くこともできず、叫ぶこともできず、ただ冷たさに溺れる私。
私はいつもこうなのだ。何かにすがるように手を伸ばし、思う。誰か、誰か私を助け出して。野洲の言葉が欲しい、いや、それが宮崎でも構わない、誰か私を助け出して。もがけばもがくほど沈んでいく私に、藁の一本でもいい、お願いだから投げ込んでほしい。
――少しは自分で考えたらどうですか。
そのとき、宮崎の軽蔑したような声が聞こえた。それは空耳だったが、まるで現実に聞こえたようだった。
――だからあなたは言いなり人形なんですよ。いつまでも誰かの言いなり人形。
「違う」
声に出して否定はしてみたものの、その中身は空っぽだった。それは言葉通りの意味ではなく、かといって逆の意味でも、また全然別の意味を表しているというわけでもなかった。そんなふうに私の言葉は空っぽだった。自分のあまりの頼りなさに、私は誰かを――もしくは何かを探して顔を上げた。けれど、真昼の並木道を行く人はおらず、その照り返しで白く乾いてしまったような景色は、まるで私以外の人間がすべて消えてしまったかのようだった。
――分かったわよ。
悔し紛れに、私は敗北を認めた。宮崎の言う通り、私は野洲の言いなりだったかもしれない。でも、それは野洲の言葉が正しいと思ったからだ。そして、いまも本当に野洲が正しいと信じているからだ。
――本当に?
陽炎のように、実体のない宮崎が冷たく尋ねた。
――じゃ、どうして会いたいかと聞かれて答えられなかったんですか?
それは――私は口ごもり、考えた。そして、考えた結果、渋々ながら、再び白旗を掲げることにした。
本当に会いたいのかと聞かれて答えられなかったのはきっと、そこに問われていたのが私の意志だったからだ。野洲を排除した、私の意志。けれど野洲の言葉なしには動けない、私は空っぽの人形だったから、答えることができなかった。野洲の言葉をそのまま飲み込み、野洲に手を引かれただけだったから。それが自分の頭で真剣に考えた結果ではなかったから。
では、私の意志はどこにあるのだろう――微かだった風がほんの少しだけ強く吹き、私に思考を呼び覚ました。けれど――分からない――考えもせず、私はすぐに首を振った。私がどうしたいのかなんて、私にはまるで分からない。そもそも娘が殺されてさえ「逃げ出したい」と願った私に、意志だなんて強靭なものがあるのだろうか。宮崎の言葉に従い、野洲から離れたとして、その先に何があるのだろうか。
宮崎と話さなければ。私はベンチから立ち上がった。いますぐ駅に行けば、彼女に追いつけるかもしれないし、そうでなければ公衆電話から彼女に電話しよう。そうして、私は一体どうしたらいいのか尋ねよう。跪 いてでも、答えをもらおう。そしてその答えの通りに、今度こそ、この冷たい泥から抜けだそう。
一歩、木陰から踏み出すと、いきなり立ち上がったせいか、めまいがした。ぐるりと地面が回り、私はベンチに倒れこんだ。無様な私に、耳の奥の誰かが諭 した。「少しは自分で考えろ」と、死んだ娘よりも若い彼女は、そう言ったのではなかったか? もし、いま彼女に頼るのなら、それは野洲を頼るのと何が違うのかと、静かな声で。
耳に囁くのは、風だった。私の中に意志を巻き起こそうと吹き始めた、微かな風。私はいつのまにか閉じていたまぶたを開け、目の前の景色に目を凝らした。そして、やっと理解した。そこには宮崎はおろか、野洲さえいないことに。それどころか、そこが灯りひとつない、二十五年前と同じ暗闇であったことに。
ああ、そうか――私は小さく息を吐いた。
野洲に出会い、愛を知った私は、その尊い光のおかげで暗闇から抜け出せたのだと信じていた。なぜなら、野洲に会うたび、その声を聞くたび、彼女の愛は私の心を照らしてくれたから。その温もりで冷たさから救い出してくれたから。
けれどその温もりは、私が一人になると、いつのまにか消えてしまった。それは、その温かい光を携えているのが彼女であったからだった。だから、彼女が去ってしまえば、光は、温もりは、再び失われることとなったのだった。その種火を野洲は分けてはくれなかったから、だから私は再び凍えなければならなかったのだった。
いや、彼女はその光を分けてくれようとしたかもしれない――ベンチに顔を伏せたまま、私はさらに考えた。そうだ、きっと愛に溢れる彼女のことだ、何度も何度も、私の胸に光を灯そうとしてくれたに違いない。問題は、私がその光を灯し続ける術を知らないということだった。だから、光はいつもすぐに消えてしまった。そのたびに、冷たさは私を覆った。けれど、私はそれに気づかなかった。私は温かく輝くそれを思い出そうと、懸命に目を閉じていたから。野洲の手に引かれ、とうの昔に暗闇から抜け出しているのだと信じ込んでいたから。
けれど、いま、目を開けてみれば、私はやはり暗闇にいるのだった。二十五年前とまったく同じ、真紀を失ったままの闇の中に。
――それが普通ですって。
洞穴に響く音のように、うつろな宮崎の声が聞こえた。
――殺した犯人が憎いだなんて、当たり前です。復讐したいという願いも、手紙を捨てることも、死刑に賛成することも。あなたがそう願わなかったのは、あなたが愛を知ったからではなく、誰かの愛に逃げ込んだだけ。悲しみから逃げて向き合わなかっただけ。だからあなたは救われない。どんなに尊いことをしても、どんなに愛の光を灯そうとも、暗闇から抜け出すことができない。
それは悲しげで、とても寂しそうな声だった。宮崎はこんなことを言っていただろうか。私はのろのろと顔を上げた。いや、彼女はそんなことは言っていなかった。それならこれは、私の心の声か。あの寒々しい面会室で、アクリル板越しに村野と言葉を交わしている私を、もう一人の私はそんなふうに見ていたのか。愛で温められて笑顔さえ浮かべる私を、暗闇から一人、寂しそうに。
――一人?
ふと違和感を覚え、私は胸の暗闇を探った。手を伸ばせばすぐ届く場所にあったその答えは、すぐに見つかった。思いのほか懐かしいその形を手に取り、撫でると、それは蛍のように淡く光った。
その瞬間、誰もいないはずの暗闇に、誰かの気配を感じた。夫だ――私はそれがすぐに分かった。それから少し遠くにもう一人――由紀だ、私はそれもすぐに分かった。この暗闇に、私は決して一人ではなかった。そこには同じようにさまよう夫が、由紀が、かつて家族という絆で繋がっていた二人がいた。私たちは同じ暗闇にいた。互いの存在を知らず、それぞれが孤独であると信じ切って。
ざわざわと風が頭上の梢 を揺らした。目の前のお茶のペットボトルにはびっしり水滴がついていて、その結露がベンチに丸く染みをつくっていた。私は顔を上げた。真昼の光に、私は目を細めた。こんな光を見たのは、久しぶりだとさえ思った。ゆっくりと立ち上がり、振り向くと、歩道の脇の案内板が駅までの道を示していた。ここから電車を乗り継ぎ、あの家へ――真紀が殺された家へ、いまも夫が住むあの家へ行くにはどれだけかかるだろうか。頭が勝手に計算を始め、それを止めようともせず、むしろ足を踏み出した自分に、私は少し驚いた。
うまくいけば、夕暮れまでには着くだろうか。足はいつになく軽く、その歩みは意識せずとも早くなった。腕時計の針は一時過ぎを指している。警備会社に転職した夫は、夕方に出勤して朝に帰宅するという生活をしているのだと聞いていた。だとすると、入れ違いになってしまう可能性はある。けれど、それでもいい。あの人に会いに行こう。しっかり前を向き、私は歩いた。暗闇をさまよい、憎しみでいっぱいになったあの人の手を握り、私もここにいるのだと知らせよう。一人ではないことを、確かめ合おう。
本来、それはあのとき――真紀が殺されたときに、私たちが最初にすべきことだった。けれど、なぜだろう。私たちはそうせずに、暗闇の中、てんでばらばらな方向へ足を向けてしまった。そうして再び出会うことができないまま、孤独にさまよっていた。けれど、いま、そう気づいたのなら会いに行けばいい。誰かの言葉ではなく、素直な自分の気持ちに従えばいい。
なぜか涙が溢れてきて、私はぎゅっと口を結んだ。あれほど欲しかった光が、いまは私の心から微かに滲み出ているような気がした。もし、野洲の言う「愛」で村野が救われたというのなら、あの人だって救われるべきだ。いや、先に救われなければならないのは、あの人のほうだ。小走りになるのを堪 えながら、私はそのとき、改めて気がついた。
今日は、真紀の命日だ。
壇上の男性は、そう言うと広い会場を見渡した。その訴えかけるような眼差し。そのとき、彼の手のマイクが何度目かのハウリングを起こし、耳障りな高音が鼓膜をつんざいたが、思わず顔をしかめてしまったのは私一人で、他の誰もがそんなことを気にする様子は見せなかった。それほど会場は真剣な雰囲気に包まれていた。死刑囚が死刑執行を待つ拘置所、そこの元・刑務官だという、その男性の主張に聞き入っていた。
「これまでお話ししたように、殺人も、死刑も、その本質は同じだということを私は現場にいた人間として知っています。殺人は個人が個人を殺すことであり、死刑は国家が個人を殺すことです。だというのに、一方は重罪になり、一方はその重罪を
男性は聴衆に向かって手を広げ、それをぎゅっと握りしめた。その拳は震え、真っ赤に充血した目からは、涙がこぼれ落ちそうだった。
「私たちは『死にたくない』と叫び、暴れる死刑囚を数人がかりで無理やり押さえつけ、首に縄をかけ、執行ボタンを押します。これはドラマや映画などでよく知られていることですが、ボタンは三つあって、それを三人の人間が同時に押します。どのボタンが死刑囚の足元の床を開き、宙吊りにして殺したか、分からないようにするためです。ともあれ、そうして死刑囚は首吊り状態になります」
男性はそこで息を止めた。そして、まるでそこに死刑囚が見えるかのように、空中に手を伸ばした。
「太い縄から死刑囚がぶら下がり、苦しそうにもがいている。やめてくれ、と全身で叫んでいる。一人の人間の命が、目の前で消えていく。その最期を、彼が絶命するまでの数分間、私たちは直立不動で見つめます。所長以下、十数人の刑務官が何もせずに、ただ彼が死んでいくのを見つめるんです。これを異様と言わずに何と言いましょう。考えてもみてください。もし、これが日常生活の出来事だったら、死にゆく人をただじっと見ていることなんてしないですよね? 誰かが救急車を呼んだり、人工呼吸をしたり、必死で助けようとするはずです。それが人間の本能です。正しいあり方です。なのに、私たち刑務官にはそれができない。目の前で彼が死んでいくのを、ただじっと待ち続けることしかできないんです」
悲痛な訴えに、聴衆からため息が漏れた。隣に座った女性が
野洲も所属している「日本の死刑にNOを突きつける市民たちの会」主催のフォーラムに出席したのは、実に二十年振りのことだった。とはいっても、参加したのは一度きりで、それもまだ村野の無期懲役が確定する前のことだった。そのとき講演していたのは刑務官ではなく、現役弁護士だという人だったが、同じように死刑廃止をテーマに話をしていたことを覚えている。
『被害者遺族としての体験を、フォーラムで話してみみませんか』
そんな話があったのは、最高裁が終わった後のことだった。
『皆さん、美希子さんの話を聞きたがっています』
野洲はそう言って誘ったが、私はそれを断った。大勢の前で話すことは苦手だし、自分にそんな大役が務まるとも思えなかった。人前に出たくないのは、あの会見のせいもあった。初めこそ、テレビに映る自分に高揚感も覚えたが、何度も映像が流れるようになると話は別だった。自分の顔を見たくないばかりに、私はテレビをつけなくなり、一人暮らしのアパートへ引っ越すのを機にテレビそのものを捨ててしまった。
私は野洲の打診を断ったが、彼女はその後も諦めずに私を誘った。しかし、やはり私は断り続けた。そんなことが何度かあった。そのうちに野洲は私を誘わなくなったが、それでも講演会を知らせる会報は、私の元へ届き続けた。その中には興味のあるものもあったのだけれど、打診を断った手前、何となく行き辛いまま、今日まで過ごしてしまったのだ。
それがいまになって――それも突然、仕事を無断欠勤してまで、ここへ足を運んだのかというと、それは私自身にもよく分からないことだった。いや、今朝、アパートを出るまでは、仕事へ行こうとしていたのだ。本来は休日だったこの日に、無理やり仕事を入れてもらい、いつものように駅から工場までの、迎えのワゴンに乗り込んだのだ。けれど、信号待ちの車窓から見覚えのある景色が見えたとき、「すみません、降ろしてください!」――気がつくと、私はワゴンを飛び降り、この市営のフォーラムセンターへと続く並木道を歩いていた。いつか野洲と二人で歩いた道。その景色があまりに変わらないことに、ほんの少し、驚きを感じながら。
けやき通りという名の通り、頭上には
私はきっと、野洲に会いたいのだ。村野の仮釈放が決まったという連絡以降、彼女からの電話はなかった。いや、正確には、彼女は事務所の司法修士生である宮崎に電話させると言ったのだったが、その宮崎からもまだ何の連絡もなかった。それが私を不安にさせていた。
なぜなら、野洲の提案にあった日時――真紀の命日は、今日だった。9月6日。だからこそ、私は無意識に講演会があることを覚えていたのだろう。娘の命日に死刑廃止の講演を聞くというのは、野洲の言う「尊いこと」である気がした。少なくとも、いつものように仕事をしているよりは。
しかし――何度目かにそっと会場を見渡し、私は小さく息をついた。会場に野洲の姿はないようだった。ここへ来れば、きっと会えると思ったというのに。
「目の前の男を殺す、この死刑のボタン。私はこれまでに、これを三回、押しました」
そのとき痛みに耐えるような声が、マイクを通して大きく響き、私は慌てて彼に視線を戻した。その姿は悲しさを漂わせながらも、壇上で堂々として見えた。やはり、私には講演などできなかっただろう。後ろめたさに私は俯いた。人前で話すのは苦手だということ以上に、私にはその資格がない。野洲という光なしには愛の手触りを思い出せず、冷たさに迷ってしまう私は、きっと不安な言葉しか吐くことができない。聴衆を同じ不安に引き込むことしかできない。
それに比べて、壇上の元・刑務官の男性は自信に満ち溢れていた。自らは愛を知り、正しいことをしているのだという、確固たる響きがその声にはあった。
「もちろん、刑務官というのは
その響きのままに、彼は言った。
「そういう仕事だ、それを分かって就職したんです。けれど、頭で理解するのと実際にやるのでは全然違う。私がこの仕事を辞めたのは五十歳のときでしたが、それまでに心を病んで辞めていった刑務官も少なくありませんでした。それくらい死刑というのは恐ろしいものなんです。人殺しが仕事の一部だなんて、とんでもない。死刑のある日本という国は、本当に異常です」
さざなみが起こるように聴衆が頷く。それを待って、彼は静かに続けた。
「繰り返しますが、欧米では死刑など、もはや前世紀の遺物なんです。けれど、日本ではどうでしょう。こうして志のある方々は集まりつつありますが、それでも廃止の議論さえなされていないのが現状です。人殺しは殺してもいいだなんて、そんな乱暴な理論はありません。彼らは間違いを犯してしまっただけなのです。だったら、その間違いを正せばいい。正す機会も与えず、殺すだなんて人間のやることじゃありません。もう一度言います。彼らも一人の尊い人間です。私や、あなたと変わらない人間なんです」
これで私の話を終わりたいと思います――男性が一礼すると、会場には割れんばかりの拍手が沸き起こった。前に進み出た誰かが男性に花束を手渡している。拍手が一層、大きくなる。私も懸命に手を叩きながら、一瞬だけ、本当にほんの一瞬だけ、そこにいるのが私だったらという想像をした。
もし、あのとき野洲の依頼を受け、こんなふうに大勢の人の前で正しさを訴えることができていたら、この拍手を受け取るのは私だった。そうなっていれば、私はその拍手を糧に、より正しさを信じることができていたかもしれない。こうして愛を探し、さまよわずに済んだかもしれない。そして何よりも、あの人の前で――あの懐かしい公園でも、堂々と振る舞うことができたかもしれない。
あいつをこの手で殺してやる――。
つい一週間前に聞いた台詞を、そのぞっとするような響きを私は思い返した。二十数年ぶりに会った元・夫の目は暗く、隠し切れない憎しみで溢れ返っていた。いや、隠し切れないのではなく、隠そうともしていなかったというほうが正しいかもしれない。その目を見た途端、私の小さな自信は吹き飛んだ。いまも闇の中をさまようこの人に、私なら光を見せてあげられるかもしれないという自信が。
笑われるかもしれないが、夫から電話があったあの日、だから私は、会って話をしようと切り出したのだ。野洲が私を救ってくれたように、私も夫を救うことができるかもしれない、そんな馬鹿みたいな考えが頭をよぎってしまったのだ。しかし、その結果はどうだ。私は野洲になれなかったばかりか、そのとき以上に愛を見失っている。彼の強い暗闇が、私の心までも黒く染めたのだ。
野洲にどうしても会いたくなったのは、そのせいもあるのかもしれなかった。更生した村野を殺すだなんて、村野と同じ人殺しの罪を犯そうとしているあの人に、私ができることなど何もなかったのだ。初めから何一つ――。
いや、一つだけあった――私は自嘲気味に思い直した。あのとき、私にできたたった一つのことは、すぐ警察に通報することだった。夫はかつての夫ではなくなってしまった。あの人は本当に村野を殺す気だった。一生を添い遂げようとしていた人の本気くらい、私にも分かる。だというのに、それなのにあのときの私はどうしたのだったか。辛うじて抱きしめていた愛が、村野を支援し続けた年月までもが揺らいでしまうような気がして、そこから逃げるように去ってしまったのだった。どうして私は正しさを信じきれないのか、愛というものを知りながら、その尊さをすぐに見失ってしまうのかと、自責の念に駆られながら。
壇上では閉会の挨拶が行われていた。その理事だという女性の話が終わると再び拍手が起き、会場にはざわめきが満ちた。人波が出口を目指してぞろぞろと進んでいく。しばらく待ってから出た方が良さそうだ。私は、無意識に手でカバンを探った。会場の時計は正午過ぎを指している。今更すぎるかもしれないが、職場に連絡をしなければと思ったのだ。説明できるような理由もないが、平謝りに謝らなくてはいけないだろう。
しかし、その手はすぐに止まった。肝心の連絡先を書いた手帳がない。そうだった、と私は顔をしかめた。あれはどこかで紛失してしまったのだ。いや、どこかではなく、あの「うさぎの公園」で。あの公園から帰ってすぐに無くなったことに気づいたのだし、帰りのバスや電車の中で手帳を広げた記憶もないから、きっとそうに違いない。
仕事のシフトは新しく書き写せばよかったが、連絡先が分からなくなってしまったのは不便だった。不便なだけではなく、その番号にいたずら電話でもされて迷惑がかかってもいけないし、誕生日などの情報も、いまどきは詐欺にも使われるのだと聞いたことがある。親切な人が拾ってどこかに届けてくれていたらいいのだけれどと、私はため息をついた。届いているとしたら、きっとあの洒落たレストランだろう。昔はあんな場所にレストランなどなかったから、わざわざ早起きをして、お弁当をつくって行ったものだ。
私は昔を懐かしく思い出した。それにしてもと、もう一つ、ため息をつくように思う。うさぎの公園、だなんて。あそこをそんなふうに呼んでいたこともあったっけ。
それは苦いのか甘いのか、懐かしい感情が胸に込み上げた。あそこは三ツ池公園といっただろうか。三つ池があるから三ツ池公園なのかと、そんなふうに納得したような記憶がある。けれど――「うさぎの公園」。遠い昔、確かに子供たちは、そんなふうに呼んでいた。けれど、それを夫から、ましてや長い年月の後、突然電話して来た元・夫の口から聞くことになろうとは、予想だにしていなかった。
それならどこかで会いましょう――いまでは無謀と思えるそんなを提案したとき、その懐かしい名前は夫の口から出たのだった。『それなら、明日、うさぎの公園で』。そう言って、電話は切れた。
私は混乱もあって、初め、それがどこを意味するのかまったく思い出すことができなかった。けれど、一度思い出してしまえば、その思い出はまるで開かれることを待ちわびていた物語のように、私の目の前に広がった。花の咲き乱れる遊歩道を、振り返りもせずに駆けて行く子供たちの後ろ姿が、お揃いのひまわり柄のワンピースの裾が軽やかに
『お母さん、うさぎはどこ?』
と、唐突に、思い出の中の由紀が私を振り返り、尋ねた。手にはニンジンを入れたビニール袋。ああ、そうだった――私は滑り台のほうへ駆けていく真紀を目で追いながらも、さらに記憶を蘇らせる。そもそも、この公園を訪れたのは、夫が同僚から「遊園地みたいな公園がある」と聞いてきたのがきっかけだった。そして、喜ぶ子供たちに、夫はさらに付け足したのだ。「そこ、うさぎもいるらしいぞ」と。
けれど、聞いた場所が違ったのか、それとも初めからその同僚の勘違いだったのか、公園にうさぎはいなかった。幼い真紀は、それでも大きな滑り台やブランコで満足したが、由紀のほうはといえば、ニンジン入りのビニール袋を握りしめ、いつまでも
あの子はどうしているだろう。いまは連絡もくれなくなった娘を思い、私は息をついた。
中学を卒業すると、由紀は私の元を離れ、寮付きの高校へ行ってしまった。それも無理はないだろう。真紀がいなくなり、夫が出て行き、私たちの生活は以前とはまるきり変わってしまった。由紀はきっとそれが嫌だったのだ。また、決して口にはしないが、私が村野の更生を助けることも気に食わなかったのだろう。私が愛というものを、野洲ほどうまく説明できなかったのもその理由の一つだと思う。高校を卒業して就職した後は、帰省も年に一度あればいいほうで、やがては電話すらなくなってしまった。お腹を痛めて産んだ娘は、二人とも私の元を離れていってしまったのだ。
けれど、暗黙のうちに、私はそれを許した。
殺された妹がいるという過去は辛い。野洲に会う前の私のように、きっと由紀はその過去を忘れてしまいたいのだろう。関わりを絶ってしまいたいのだろう。そうしないと幸せになれない、そう思っているのだろう。その気持ちは痛いほどに理解できた。
『辛くなったらいつでも帰ってきてね』。家を出るとき、私はそんなメッセージを中に入れたお守り袋を持たせた。小さい頃、由紀のお気に入りだったアニメのリボンをつけて。こんな子供っぽいのはやめてと、そう言って由紀は嫌うかもしれなかったが、それは直接口では伝えられない、私にできる精一杯だった。
そのお守りの中のメッセージを、きっと由紀は読んだことだろう。だというのに頼ってこないということは、きっと幸せになって、自分のことは放っておいて欲しいという無言の要求なのだろう。寂しさはあったが、私は自分にそう言い聞かせた。由紀は立派に独り立ちしたのだから、それを悲しむことはない、と。
私は椅子から立ち上がった。長く座っていたせいで膝が固まっていた。それをほぐすように動かし、ゆっくりと伸ばす。そうしているうちに、思い出も、由紀の姿も、色あせた
「梶田さん」
後ろから呼び止められた。振り向き、見上げると、化粧っ気のない若い女性がいた。宮崎だ。どことなく感じの良くない、野洲の事務所の司法研修生――。
「お久しぶりです」
鴨居に頭をぶつけそうなほど背の高い宮崎は、そう言って軽く頭を下げた。挨拶もそこそこに、つっけんどんにも聞こえる口調で続ける。
「野洲先生から電話するようにって言われてたんですけど、タイミングが合わなくて……いま、ちょっといいですか」
「なんでしょう」
渋々私が聞き返すと、宮崎は人の少なくなった出口に目をやった。
「ここだとあれなんで、何か飲みながらでも」
「いいですけど……」
村野のことなら、単に日程を擦り合わせるだけの話ではないのか。にわかに私の胸は騒いだ。まさか、夫が村野を見つけてしまったのだろうか――最悪の想像が頭をよぎる。いや、そんなはずはない。そんなことが起きたとするなら、私の元へとやってくるのは宮崎ではなく、警察だ。だから、これはそういうことではないのだろう。
しかしこちらのことなど気にもかけず、早足で宮崎は歩き出した。ホールに併設されている喫茶店に行くのかと思いきや、それを通り過ぎ、日差しの照りつける外へ出た。一体どこへ行くのだろう。たまらず足を止めると、宮崎はこちらを振り返った。「すぐそこですから」と言うと、並木道をずんずんと進んで行く。その足は自販機の前まできて、ようやく立ち止まった。
「私が出しますけど、何がいいですか」
よろよろと私が追いつくのを待って、宮崎はちらりと枯れた芝生を見やった。私は半ば呆れながら、宮崎の目線の先を見た。あとひと月もすれば涼しいだろう、けれどいまは蒸し暑いだけの木陰のベンチ。
「今日は暑いし、喫茶店にでも入ったほうが……」
思わず私が口走ると、彼女は迷惑な提案だと言わんばかりに顔をしかめた。
「喫茶店の飲み物って、量が少ないのにバカみたいに高くて嫌なんですよね。それに私、クーラーの風って冷えちゃって苦手なんです」
「そう……」
そう言われれば強く言い返せない私は、促されてお茶のボタンを押した。ガコン、安っぽい音でペットボトルが落ちてくる。宮崎はそれを拾い上げて私に差し出すと、先にベンチに腰掛けた。バックから飲みかけの水を取り出し、一口、飲み込む。仕方なく、私もペットボトルに口をつける。早く済む話だといいけど――そう思いながら、隣の宮崎をちらと見ると、その口は一文字に結ばれ、眉は怒ったように
こんな暑い中に連れ出され、その上ペットボトルのお茶をあてがわれ、怒り出したいのはこちらだとは思ったが、しばらく経っても彼女は無言で、その表情も変わらない。何か気に障ることでもしてしまっただろうかと、落ち着かない気分になり始めた頃だった。ようやく彼女は「村野さんのことなんですけど」と切り出した。
「梶田さんって、本当にあの人に会いたいんですか?」
質問もさながら、その怒ったような口調に私は驚き、思わず宮崎を見上げた。高い場所から私を見下ろす彼女の顔は、木漏れ日というには強すぎる夏の光が作り出した影のせいか、まるで宇宙人か何かのようだった。同じ言葉を話しているようで、まるで意思疎通のできない地球外生命体。その未知の生物が、よく意味の分からない質問を私に投げかけていた。あなたは本当に村野に会いたいのか、という。
「会いたいかって、どういう……」
むっとした私は、反射的に口を開いた。
こんなところまで連れて来てどんな話があるかと思えば、一体この人は何を言い出すのか。私は若い宮崎を睨むように見据えた。
彼女は確か、今年で二十五歳だと言っていた。つまり、彼女が生まれてからいままでの、気が遠くなるような年月をかけて、私は村野を支援してきたのだ。面会に行き、手紙を出し、彼を赦し、その更生を助けたのだ。野洲とともに尊い愛の光で以って、彼の仮釈放まで漕ぎつけたのだ。
その私に向かって、本当に会いたいかとは何事だ。彼女は自分の口にした言葉の意味が分かっているのだろうか。それとも――。
「いや、別に梶田さんがいいならいいんですけど。私はどうこう言う立場じゃないので」
怒りの気配を察知したのか、宮崎は目をそらし、肩をすくめた。
「じゃ、面会の日程と場所についてですけど――」
「ちょっと待って」
私はそれを制止した。
「本当に会いたいのかって、どういう意味でしょう? どうしてそんなこと聞くのか、教えてほしいんだけど……」
その若さゆえか、宮崎が人を尊敬することを知らない、失礼な人間だということは分かっていた。二十五年という年月の重みも、その苦難さえ想像がついていないのだろうとは思う。けれど――何かが私の胸に引っかかっていた。その分からない
「どういう意味って言われても」
真剣な問いに、宮崎は眉間に皺を寄せた。面倒くさそうに、あのつっけんどんな口調で言う。
「いや、本当に会いたいのかなって思っただけです。だから、梶田さんが別にいいんならいいんです。すいません」
とってつけたような謝罪を口にする。けれど、私はさらに尋ねた。
「私が本当は会いたくないと思ってるように見えたってこと? これまでの面会でも、嫌々会ってるふうに見えたとか?」
言葉を重ねるごとに、なぜか私は必死になっていく自分を感じた。本当ならあまり話したくないような相手に、何をそんなに必死になるのか分からない。それなのに、私はそんな自分を止められなかった。どうして――繰り返す私に、宮崎はますます困惑したようだった。
「だから、そう思っただけです。違うなら別に――」
「どうして?」
だから、もういいって言ってるじゃないですか――宮崎の顔にはそう書いてあるようだった。けれど、私はどうして、と繰り返した。
そう問いかけているうちに、ふとこれは宮崎へ向けた問いではないということに気がついた。それは、自分への問いだった。村野に本当に会いたいのかという、二十五年分の自信で肯定できるはずの問いに、どうして私は引っかかりを感じたのか。そこに些細ではあるが、何か致命的な、決して気づいてはいけないことに気づいてしまったような、そんな感覚に囚われたのだった。
それは一体何だろう――見えない風に目を凝らすように、私は感覚を研ぎ澄ませようとした。
「だって、自分の子供を殺した人じゃないですか。普通、会いたくないですよ」
そのとき、どうして、の答えを宮崎が口にした。胸に引っかかった
「梶田さんってそんなタイプでもないから、野洲先生にうまく乗せられちゃったんだろうなって感じだし」
「……先生に、乗せられてる?」
何を言われているのか分からず、私は聞き返した。すると、宮崎は再び肩をすくめた。
「いや、まあ、分かりますけどね。あの人、カリスマ的だし。だから信者もいっぱいいるわけだし」
「カリスマ? 信者って?」
まったく心当たりのない言葉に、私は置いてけぼりを食ってぽかんとした。しかし、彼女はそんな私のほうも見ることもなく、吐き出すように続けた。
「ってか、私も元・信者ですから気持ちは分かりますけど。とは言っても私の場合、梶田さんみたいに巻き込まれたってわけじゃなくて、小さい頃からテレビで見て憧れてたから、進んで近づいたんですけどね。だから、修習生で採ってもらったときはすごい嬉しかったんですけど、やっぱ実態を知っちゃうとなんだかなって感じがすごくて。だって、どんな犯罪者でも無罪にするのが弁護士って、そんなのってないなっていうか。……ああ、私、これで結構、正義とか信じてる方なんで」
その唇がほんの少し歪んだのは、笑顔を作ったつもりなのだろうか。しかし、その笑みの理由も、言われた言葉も理解できなかった私は、かろうじて聞き取ることのできた部分を尋ねた。
「宮崎さん、その、元・信者って……」
「ああ、先生から聞いてないですか? 私、事務所辞めるんですよ」
あっさりと彼女は答えた。
「ついでに弁護士志望もやめて、犯罪心理学みたいな分野に進もうかなって。で、いつかワイドショーのコメンテーターになって、先生とバトルしようかなって……って、それは面白そうだなって思ってるだけですけど。それまであの人がテレビ出てるかも分かんないですし」
「あの人って、野洲先生のこと?」
訳が分からないまま、私は尋ねた。
「野洲先生が、今度テレビに出るっていう話?」
すると、宮崎の眉間に皺が寄った。このおばあちゃん、何も知らないのかしら――表情が露骨にそう言っている。
「テレビは私、全然見ないから……」
言い訳のようにつぶやきながら、私はそろりと胸に手を置いた。微かだが、そこにまだ風は感じられた。けれど、その先には何があるのか分からない。それは良いものか、悪いものか、少しでも私が欲しいと願っているものなのだろうか。
「テレビ見ないとか、そういう人もいるんですね」
宮崎は呆れ顔で言った。
「いや、あの人、一時期テレビに出まくってたじゃないですか。それこそ、梶田さんと会見した後からですよ。それで有名になって、法律番組とか、バラエティ番組とか出て……知りませんでした?」
野洲からそんな話を聞いたことはない。つい、恨み言のような台詞が口をついた。
「野洲さんも、教えてくれれば良かったのに」
「敢えて教えなかったんだと思いますけどね」
宮崎は吐き捨てるように続けた。
「梶田さんは大切な信者さんだから、タレント活動を知られたくなかったんじゃないですか? テレビにはテレビのキャラがあるし、やっぱ計算高くいかないと」
「計算?」
「そうですよ。言っときますけど、あの人が死刑廃止をテレビで訴えてるとこなんて見たことないですからね。そりゃ、経歴のテロップに『死刑廃止を訴えている』くらいは出ますけど、それもキャラ付けくらいな意味しかないですよ。死刑廃止とかいうと、すごそうだし、信者も増えるかもしれないし、自分もいいことしてるような気分になれるし、いいこと尽くしじゃないですか。実態は、人殺しを野に放ってるだけだとしても」
「それはちょっと言い過ぎでしょう」
胸をざわつきに気を取られながらも、私は言い返した。
「野洲先生がテレビでどう振る舞っているのかは知りませんけど、あの人の信念や情熱は本物です。だからこそ、村野さんも更生した。宮崎さんもそれは分かってるでしょう」
「ええ、分かってます」
宮崎は頷いた。何を考えているのか分からない、あの宇宙人のような漆黒の瞳で私を覗き込むように見る。
「じゃ、梶田さんは村野正臣が本当に更生したと思ってるんですね」
「それは、もちろん――」
反射的に私は答えて、それから黙り込んだ。胸をざわつかせる風は、いまや辺りの空気を巻き込むほどに大きくなっていた。どうして――再び、私は自分に問いかけた。そろり、柱の陰から何か恐ろしいものを覗くように、彼の顔を思い出す。刑務所の面会室にある、アクリル板越しに見た彼の顔。
面会室でのことをあまり思い出したくないのは、彼のせいではなく、中に入るだけで押し潰されてしまいそうな雰囲気のある刑務所という場所のせいだった。そこでの出来事はいつも地に足のつかない、夢の中の出来事のようで、アクリル板の向こうにいる彼もまた、夢の中の人物のようだった。それは良い夢なのか、悪夢なのか。けれど一つだけ確かなことは、それが変化を伴う夢だということだった。
初め、どこかだらしない印象だった彼は、徐々に真面目な顔つきに変わっていった。あれは五年ほど経った頃――いや、もう少し経った頃だろうか。その真面目な顔に、怯えたような表情が加わるようになった。彼は突然、人が変わったように自分の罪を恐れ出したのだ。『あなたはもう赦されているんですよ』と、優しく言葉をかける野洲をそっちのけで、彼は私に何度も謝った。すみません、すみません、すみません――血を吐くような謝罪を前に、私はどうしたらいいかも分からず、ただ漠然とした恐怖を感じていた。謝罪に恐怖を感じるなんて、おかしなことだろうか。いまから思えば、面会が憂鬱になったのはあの頃だけだった。
けれどその後――それも何年かかかったはずだが――彼は落ち着きを取り戻し、ようやく面会室にも安寧が戻ってきた。そして、最後に彼を見た夏の初め頃にはもう、その顔はとても落ち着いていた。年齢を重ねて少し細くなった頰に浮かんだ笑みは、悟りを開いた仏僧のようで、それは更生した証だと、私は嬉しく思っていた。野洲と共にそれを喜んでいた。
それなのに、村野正臣が本当に更生したと思ってるんですねという宮崎の問いに、どうして私は頷くことを
ぐるぐると思考が渦を描く。宮崎はそんな私の反応を
「梶田さん。なぜ犯罪を犯す人間がこの世にいるか、知ってますか」
「それは……いろいろあると思うけど」
風に巻き込まれまいとする一心で、私は答えた。
「村野さんの場合は、虐待されたから――」
「じゃ、虐待されて育った人間が全員人殺しになりますか」
「それは違うけど――」
言いかけて、私はどこかでこんな問答をしたことを思い出す。――元・夫だ。あのうさぎの公園で、夫もいまの宮崎と同じ問いを口にしたのだった。
「ですよね。じゃ、それは理由にならないですね」
しかしあのときの夫とは違い、至極真面目に宮崎は言う。私もあのときのように言い返した。
「そうかもしれないけど、それは原因の一部というか、ほら、他にも色々あったわけでしょう。裏切られた経験とか、親がいない寂しさとか。そういう原因が集まって」
「じゃ、例えば、そういう『原因』が十個集まったら人殺しになるとか、そういうことですか?」
「そういうのじゃないけど」
「それなら、どういうことですか? もし、梶田さんが、村野さんとまったく同じ環境で育ったとしたら、梶田さんも殺人を犯していたってことですか?」
「そんなの知りませんよ!」
私はとうとう音を上げた。夫といい、宮崎といい、どうしてこんなに分からず屋なのだろう。普通の人なら感覚で理解してくれるだろう「愛」が、どうしてこの人たちからはこんなに遠いのだろう。夫も、宮崎も、宇宙人だ。人間の心が分からない、地球外生命体だ。
「じゃ、宮崎さんはご存知なんですか?」
その宇宙人に、私は渾身の嫌味を言った。しかし、それが嫌味とも分からないのか、宮崎は頷いた。おもむろに口を開く。
「実は、犯罪を犯す人間の脳には、欠陥があるんですよ」
「脳?」
意外な答えに、私は思わず眉を
「脳って……この、脳みそのこと?」
「そうです」
したり顔をするわけでもなく、むしろなぜそんなことも知らないのかといった様子で、宮崎は頷いた。
「これはテレビなんかでもやってる、れっきとした脳科学の話なんですけど……ある研究者が殺人犯たちの脳を調べたんですね。そしたら、彼らの脳にはすべて、その一部に損傷があるということが分かったんです。当たり前ですが、人間はその行動のすべてを脳で決定します。じゃ、その脳に損傷があるとどうなるか。その人は衝動的になりやすく、判断能力が低い人間になります。ということはつまり、犯罪を犯しやすくなるということです。いいですか、考えてみて下さい。例えば、梶田さんが誰かにムカついてたとして、その人を殺しますか? または、お金に困ってるからって、見ず知らずの人間を殺しますか? 普通は殺さないですよね? いや、
宮崎は一気に言うと、私を見下ろした。それから、まるで判決を言い渡すように言った。
「犯罪者が更生するなんて、有り得ないってことです。犯罪を犯す脳がそのままなんだから、いくら反省とか、謝罪とか口で言ってたとしても、そんなものには意味なんてないんです。
そう言い切ると、彼女はぎゅっと上下の唇を閉じた。脳みその損傷。初めて聞いた話に混乱しながら、私は彼女の短髪の下の皮膚、さらにその下の頭蓋骨に覆われた彼女の脳みそを想像した。それから、同じように村野の脳みそを想像しようとした。彼の脳みそは損傷しているのだろうか? だから彼は反省も、更生もできず、けれどそのまま仮釈放されて――。
「村野さんは、また誰かを殺すかもしれないってこと?」
恐ろしい考えが閃き、私はそれをそのまま口にした。
「真紀のような子が――また誰か子供が殺されるってこと?」
「その可能性はあるし、普通の人よりその可能性は高いかもしれないですよね」
あれだけ熱を込めて語っておきながら、宮崎は冷たく言った。
「可能性の話ですから、実際にそうなるかなんて誰にも分かんないですけど」
「でも、もしそうなら――」
急に背筋が寒くなり、私はごくりと唾を飲んだ。
「どうしたらいいの、私のせいで――」
さっきまで思い浮かべていた村野の笑顔が、急に恐ろしいものに思え、私は怯えた。あの悟りきった仏僧のような笑み。果たしてそれは心からのものだったのだろうか? そう言われてみれば、口では笑っているようでも、その目は笑っていなかったような気がする。励ましの言葉をかける私に、野洲に、彼は本心では何を思っていたのだろう? 俺を許すなんて馬鹿なやつらだと、せせら笑っていたのだろうか。
「……ほんと、梶田さんって自分がないんですね」
すると、呆れたように宮崎が言った。
「まあ、だから家族も捨てて、先生一筋になっちゃったんでしょうけど。にしても、詐欺とか大丈夫かって、心配になるレベルですよ」
「詐欺……?」
私はぼんやりと聞き返し――それから、違う、と首を振った。精一杯、宮崎を睨みつける。
「家族を捨てたってどういうこと? そんなこと、したつもりはないけど」
「いや、梶田さんが先生側に行ったから、旦那さんとも離婚したって聞きましたけど」
「誰が言ったの、そんなこと」
無性に怒りが湧き、私は言い返した。どんな言葉を使ってでも、宮崎を打ち負かさなければならない、そんな気がした。
「言っとくけど、夫は――元・夫はね、更生した村野さんに復讐しようだなんて思うような人よ。村野さんが送り続けてる謝罪の手紙も読まずに捨てるような人よ。死刑にだって賛成してるし、それに、それに――まだ血の跡が残ってる家に平気で住んでるような、とにかくひどい、気持ち悪い人なの。そんな人と一緒にいられると思う? だから私は離婚したのよ。あの人が、そんな人だとは思わなかったから。昔は優しかったのに、あの事件で人が変わってしまったから――」
夫は最低な人間だという証拠を、もっと宮崎に投げつけなければならないのに、そこで言葉を失った私は金魚のようにパクパクと口を動かした。野洲ならここで、「愛を知らない、可哀想な人ですね。でもだからこそ、私たちがそういう人から村野さんを守ってあげなければ」などと言い、慰めてくれるはずだった。けれど、宮崎は違った。彼女は呆れ顔のまま、言った。
「でもそれって、普通だと思うんですけど」
「普通?」
「ええ」
憮然と彼女は答えた。
「だって、娘さんを殺されたんでしょ。普通、そう思いますよ。復讐したいとか、手紙読みたくないとか、死刑賛成とか。ってか、血の跡が残ってるから気持ち悪いとか、そんなこと言う人のほうが怖いんですけど。他人の血ならともかく、娘さんの血だし。それを気持ち悪いとか、ちょっと……」
宮崎が、理解できないものを見るような目で――宇宙人でも見るような目で私を見る。その視線に私はたじろいだ。違う。宇宙人は私ではない。宮崎だ。なのにどうしてそんな目で見られなくてはならないのか。
「でも、あの人は本当に村野さんに危害を加えるつもりなのよ。間違いないの。だって、ついこの間、会って聞いたんだから」
「そうですか」
しかし、宮崎の反応は薄かった。まるで私が嘘をついているとでもいうように。
「嘘じゃないのよ」
「じゃ、尊い『愛』で何とかしてあげたらどうですか」
「愛?」
「それで村野さんは更生したんですよね。だったら、どうして旦那さんには教えてあげないんですか」
「それは……」
私は口ごもった。言いたいことは山ほどある気がしたが、そのどれを口にしたとしても、宮崎は納得してはくれない気がした。そんな私を軽蔑するように、宮崎は冷たい視線を投げた。
「村野さんが更生できたのが支援のおかげだとしたら、旦那さんが変われないのは一人だったせいなんじゃないですか」
一人。その言葉に一瞬どきりとするが、めげずに私は言い返した。
「夫を無視して、村野さんに向き合った私がおかしいって言いたいの?」
それは精一杯の攻撃だったが、宮崎は気もなさそうに肩をすくめただけだった。
「別に勝手だとは思いますけどね。でも人に頼るんじゃなくて、少しは自分で考えたらどうですか。このまま野洲先生の言いなり人形でも、私には関係ないですけど」
そう言って、腕時計をちらりと見ると立ち上がる。
「じゃ、そろそろ次の用事があるので。……村野さんに会いたいのかどうか、決まったら連絡ください。私の番号、ご存知ですよね」
「ちょっと待って」
反射的に私は引き止めた。意図したわけではないが、その声にはすがるような響きがあった。それを宮崎は嫌うように
反論したいことは山ほどあった。反論しなければならないことも。第一、私は野洲の言いなり人形ではないし、離婚も野洲のためではない。ましてや、由紀が出て行ったことには、野洲は全く関係ない。
――本当に?
そのとき、忘れかけていた風が微かに胸をざわつかせた。それは初め、村野に会いたいのかと聞かれたときに感じた風だった。
――本当に野洲は関係ないの?
風の運んできた問いに、先程と同様、私は答えることができなかった。なぜ答えることができないのか。もがいていると、日差しが急激に冷え、私は自分のアパートの一室にいるような錯覚を覚えた。一人で毛布にくるまっている、孤独な私。泥に半身を呑まれたように動くこともできず、叫ぶこともできず、ただ冷たさに溺れる私。
私はいつもこうなのだ。何かにすがるように手を伸ばし、思う。誰か、誰か私を助け出して。野洲の言葉が欲しい、いや、それが宮崎でも構わない、誰か私を助け出して。もがけばもがくほど沈んでいく私に、藁の一本でもいい、お願いだから投げ込んでほしい。
――少しは自分で考えたらどうですか。
そのとき、宮崎の軽蔑したような声が聞こえた。それは空耳だったが、まるで現実に聞こえたようだった。
――だからあなたは言いなり人形なんですよ。いつまでも誰かの言いなり人形。
「違う」
声に出して否定はしてみたものの、その中身は空っぽだった。それは言葉通りの意味ではなく、かといって逆の意味でも、また全然別の意味を表しているというわけでもなかった。そんなふうに私の言葉は空っぽだった。自分のあまりの頼りなさに、私は誰かを――もしくは何かを探して顔を上げた。けれど、真昼の並木道を行く人はおらず、その照り返しで白く乾いてしまったような景色は、まるで私以外の人間がすべて消えてしまったかのようだった。
――分かったわよ。
悔し紛れに、私は敗北を認めた。宮崎の言う通り、私は野洲の言いなりだったかもしれない。でも、それは野洲の言葉が正しいと思ったからだ。そして、いまも本当に野洲が正しいと信じているからだ。
――本当に?
陽炎のように、実体のない宮崎が冷たく尋ねた。
――じゃ、どうして会いたいかと聞かれて答えられなかったんですか?
それは――私は口ごもり、考えた。そして、考えた結果、渋々ながら、再び白旗を掲げることにした。
本当に会いたいのかと聞かれて答えられなかったのはきっと、そこに問われていたのが私の意志だったからだ。野洲を排除した、私の意志。けれど野洲の言葉なしには動けない、私は空っぽの人形だったから、答えることができなかった。野洲の言葉をそのまま飲み込み、野洲に手を引かれただけだったから。それが自分の頭で真剣に考えた結果ではなかったから。
では、私の意志はどこにあるのだろう――微かだった風がほんの少しだけ強く吹き、私に思考を呼び覚ました。けれど――分からない――考えもせず、私はすぐに首を振った。私がどうしたいのかなんて、私にはまるで分からない。そもそも娘が殺されてさえ「逃げ出したい」と願った私に、意志だなんて強靭なものがあるのだろうか。宮崎の言葉に従い、野洲から離れたとして、その先に何があるのだろうか。
宮崎と話さなければ。私はベンチから立ち上がった。いますぐ駅に行けば、彼女に追いつけるかもしれないし、そうでなければ公衆電話から彼女に電話しよう。そうして、私は一体どうしたらいいのか尋ねよう。
一歩、木陰から踏み出すと、いきなり立ち上がったせいか、めまいがした。ぐるりと地面が回り、私はベンチに倒れこんだ。無様な私に、耳の奥の誰かが
耳に囁くのは、風だった。私の中に意志を巻き起こそうと吹き始めた、微かな風。私はいつのまにか閉じていたまぶたを開け、目の前の景色に目を凝らした。そして、やっと理解した。そこには宮崎はおろか、野洲さえいないことに。それどころか、そこが灯りひとつない、二十五年前と同じ暗闇であったことに。
ああ、そうか――私は小さく息を吐いた。
野洲に出会い、愛を知った私は、その尊い光のおかげで暗闇から抜け出せたのだと信じていた。なぜなら、野洲に会うたび、その声を聞くたび、彼女の愛は私の心を照らしてくれたから。その温もりで冷たさから救い出してくれたから。
けれどその温もりは、私が一人になると、いつのまにか消えてしまった。それは、その温かい光を携えているのが彼女であったからだった。だから、彼女が去ってしまえば、光は、温もりは、再び失われることとなったのだった。その種火を野洲は分けてはくれなかったから、だから私は再び凍えなければならなかったのだった。
いや、彼女はその光を分けてくれようとしたかもしれない――ベンチに顔を伏せたまま、私はさらに考えた。そうだ、きっと愛に溢れる彼女のことだ、何度も何度も、私の胸に光を灯そうとしてくれたに違いない。問題は、私がその光を灯し続ける術を知らないということだった。だから、光はいつもすぐに消えてしまった。そのたびに、冷たさは私を覆った。けれど、私はそれに気づかなかった。私は温かく輝くそれを思い出そうと、懸命に目を閉じていたから。野洲の手に引かれ、とうの昔に暗闇から抜け出しているのだと信じ込んでいたから。
けれど、いま、目を開けてみれば、私はやはり暗闇にいるのだった。二十五年前とまったく同じ、真紀を失ったままの闇の中に。
――それが普通ですって。
洞穴に響く音のように、うつろな宮崎の声が聞こえた。
――殺した犯人が憎いだなんて、当たり前です。復讐したいという願いも、手紙を捨てることも、死刑に賛成することも。あなたがそう願わなかったのは、あなたが愛を知ったからではなく、誰かの愛に逃げ込んだだけ。悲しみから逃げて向き合わなかっただけ。だからあなたは救われない。どんなに尊いことをしても、どんなに愛の光を灯そうとも、暗闇から抜け出すことができない。
それは悲しげで、とても寂しそうな声だった。宮崎はこんなことを言っていただろうか。私はのろのろと顔を上げた。いや、彼女はそんなことは言っていなかった。それならこれは、私の心の声か。あの寒々しい面会室で、アクリル板越しに村野と言葉を交わしている私を、もう一人の私はそんなふうに見ていたのか。愛で温められて笑顔さえ浮かべる私を、暗闇から一人、寂しそうに。
――一人?
ふと違和感を覚え、私は胸の暗闇を探った。手を伸ばせばすぐ届く場所にあったその答えは、すぐに見つかった。思いのほか懐かしいその形を手に取り、撫でると、それは蛍のように淡く光った。
その瞬間、誰もいないはずの暗闇に、誰かの気配を感じた。夫だ――私はそれがすぐに分かった。それから少し遠くにもう一人――由紀だ、私はそれもすぐに分かった。この暗闇に、私は決して一人ではなかった。そこには同じようにさまよう夫が、由紀が、かつて家族という絆で繋がっていた二人がいた。私たちは同じ暗闇にいた。互いの存在を知らず、それぞれが孤独であると信じ切って。
ざわざわと風が頭上の
うまくいけば、夕暮れまでには着くだろうか。足はいつになく軽く、その歩みは意識せずとも早くなった。腕時計の針は一時過ぎを指している。警備会社に転職した夫は、夕方に出勤して朝に帰宅するという生活をしているのだと聞いていた。だとすると、入れ違いになってしまう可能性はある。けれど、それでもいい。あの人に会いに行こう。しっかり前を向き、私は歩いた。暗闇をさまよい、憎しみでいっぱいになったあの人の手を握り、私もここにいるのだと知らせよう。一人ではないことを、確かめ合おう。
本来、それはあのとき――真紀が殺されたときに、私たちが最初にすべきことだった。けれど、なぜだろう。私たちはそうせずに、暗闇の中、てんでばらばらな方向へ足を向けてしまった。そうして再び出会うことができないまま、孤独にさまよっていた。けれど、いま、そう気づいたのなら会いに行けばいい。誰かの言葉ではなく、素直な自分の気持ちに従えばいい。
なぜか涙が溢れてきて、私はぎゅっと口を結んだ。あれほど欲しかった光が、いまは私の心から微かに滲み出ているような気がした。もし、野洲の言う「愛」で村野が救われたというのなら、あの人だって救われるべきだ。いや、先に救われなければならないのは、あの人のほうだ。小走りになるのを
今日は、真紀の命日だ。