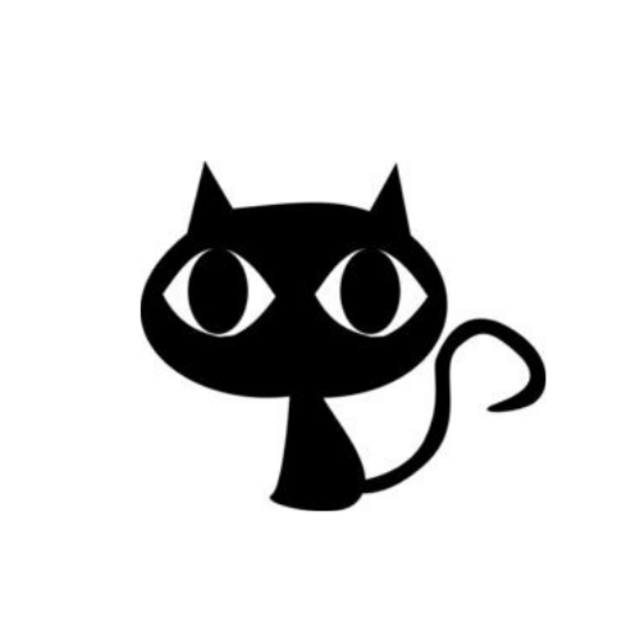再び、断絶の章
文字数 22,000文字
休日の今日、うさぎの公園は普段よりもたくさんの親子連れで賑わっていた。暑いとはいっても夏休みが終わり、秋に入ったという安心感からだろうか。池沿いの散策路を歩く人も多い。
「おれ、最初は滑り台!」
「じゃ、早く行ったほうの勝ちね! よーい、どん!」
「あ、ずるすんなって!」
「ずるしてないでーす!」
そのとき、きゃあきゃあと騒がしい声を立て、子供たちが目の前を駆けていった。小学生くらいの男の子と、女の子。きっと兄妹なのだろう、少し離れた後方からベビーカーを押す母親が「転ばないでよ」と声をかける。けれど、そんな注意は耳に入らないのか、兄妹は我先にと転がるようにして坂を下っていく。
その小道の脇に建つ、小さな東屋 に身を隠すように座った私は、その無邪気な姿から目を逸らし、俯いた。すると、まだ膨らみも定かではない下腹部が自然と目に入った。
いまはまだ親指の先ほどだという、小さな小さな命が息づく場所。いつかはあの子たちのように公園を駆け回り、もっと先の未来には、それを見守る親になるはずの小さな命。そうして命は巡り、人は大きな幸せを築き上げていく――込み上げてくるものを必死に飲み込みながら、私は思った。子供を産み、育てるということはきっと、その大きな幸せの一部になるということなのだろう。そう、きっと普通 の人々にとっては。異分子である、私以外のみんな にとっては。
みんな にとって当たり前のことを、私が信じることができないのは――それはやはり真紀のせいだった。大人になることもできず、子供のまま殺された真紀のせいだった。いや、そればかりではない。それは真紀が殺されたせいで家族がばらばらになったせいでもあったし、またそのせいで私が普通 から弾き出されたせいでもあった。
足元のコンクリートの染みに視線を落とし、私はさらに考える。それはあれから二十五年も経ったというのに、私の父が復讐を忘れず、自ら殺人犯になろうとしているせいだった。母がそれを止めないせいだった。それだけでも十分なのに、最後のとどめを刺すように起こった事件のせいだった。あの日、私が両親の話を盗み聞きしてしまった直後、ラパンで起こった事件の――。
私の視界はみるみる滲み、コンクリートには丸い染みが一つ増えた。この小さな東屋は、かつて伊藤が私を慰めてくれた場所だった。過去に足を取られ、何もかもうまく行かないと泣く私にココアを差し出し、そのすべてを聞いてくれた場所だった。『でも、死んだのは妹で、君じゃないじゃん』と、あのとき伊藤はそう言ってくれたのだった。『俺なんかあれだよ、高校のとき、交通事故で腕がポッキリいったんだから。しかも利き手』と自慢げに。
そうして伊藤は、私が二度と戻れないと思っていた日和見菌たちの世界へ、簡単に招き入れてくれたのだった。だから私は彼といることができたのだった。自分こそ特別だと信じて疑わない彼の隣にいれば、私は普通 でいられたから。実際、彼は特別 で、私は普通 だった。けれど、結局はその彼の特別さが今回の事件を引き起こしてしまったに違いない。
あの日、ラパンの休憩室で、両親の会話を盗み聞きしてしまった私は泣いていた。二十五年経ったいまも、家族はばらばらのままだということを目の当たりにして、悲しむことしかできなかったのだ。手嶋が――あのお節介なアニメオタクが現れたのはそのときだった。泣いている私を見るなり、彼はいつものあのお節介癖で、『どうしたの、店長と何かあった?』と尋ねてきた。
『来ないで、放っておいて』。私はそう言って拒否したが、彼は立ち去るどころか、真面目な顔をして私の向かいに座った。そして、『シャルルの呪文の意味って知ってる?』と、突然、何の関係もないことを話し出した。『有名かもしれないけど、あれって英語なんだよ。オル・フォル・ギュネス(all for goodness)、すべては善いことのためになされるべきだっていう意味なんだって』と。
『あっちへ行ってって言ってるでしょ』、あのとき私はそう叫ぶべきだった。彼のためにも、そうするべきだった。けれどそうしなかったのは、そのときの私はあまりに悲しく、そうする気力もなかったからだ。聞いているふりさえしない私に、手嶋が話し続けたからだ。けれど、その一番の理由は、迷惑なはずのその話を聞いているうちに、なぜか不思議な気分に陥ったからだった。ずっとずっと遠い昔、聞きそびれた懐かしい物語の続きを、いまになって聞いているかのような――。
伊藤がドアを開けたのはそのときだった。私と向かい合わせに座った手嶋との距離は、決して近くはなかった。けれど、彼はそこに自分の入ることのできない親密な空気を感じ取ったのだろう。そして、怒りに我を忘れた。
『てめえ、俺の女に何しやがる!』
伊藤はそんなようなことを言って殴りかかった。口喧嘩さえしたこともなさそうな手嶋は、驚くほど簡単に床に倒れ――頭から血を流して動かなくなった。
『きゅ、救急車を呼ばないと』
ようやく私が呟いたのと、ことの重大さに気づいた伊藤が休憩室から飛び出していったのは、ほぼ同時だった。『殺してしまったと思って逃げた』と、アパートに戻ったところを逮捕された伊藤は、警察の取り調べにそう供述したらしい。よほど打ち所が悪かったのだろう、手嶋は意識不明の状態だった。その夕方、伊藤の名前は過失傷害の容疑者としてニュースに流れた。その肩書きが「元・会社員」となっていたのは、事件を知ったラパン本部が、すぐさま彼の首を切ったからだろう。私は警察で彼を待ったが、彼は身元引き受け人に母親を指名した。帰ったほうがいいと警官に勧められ、私は二人のアパートへ戻った。しばらくぼんやりしたあと、彼の身の周りのものをバッグに詰めようと思い立ったが、母親と実家に帰るのならそれも必要ないだろうと、再びぼんやりと座り込んだ。
時計の針は真夜中過ぎを指していた。私は明日のために少しでも眠って、手嶋の見舞いに行かなくてはならない。すでに新しい店長がいるラパンに出勤して事情を説明しなければならない。そうしながら何とかして伊藤と連絡を取り、これから私たちはどうなるのか、尋ねなければならない。そして、その返答次第では、この一人には広すぎるアパートは引っ越さなくてはならないし、新しい仕事を見つけなくてはならないし、何よりもこのお腹に宿った命をどうするのか、決めなくてはならない。産んで一人で育てるのか、それとも――。
そこまで考えて、私は八つ当たりをするように握りこぶしを床に叩きつけた。この命をどうするか決めなくてはならない? 嘘だ。そんなことは初めから決まっている。いや、決められてしまっている。妹が殺され、家族が離散し、私の父が人殺しを企てているその上で、伊藤もまた人殺しになろうとしている。そんな状況で産むなどという選択肢を選べるはずがない――。
事件の翌日、私は結局、手嶋の見舞いに行かなかった。ラパンにも出勤しなかった。そうして何もかも放棄して、この東屋で座っていた。考えても仕方のないことばかりを、ぐるぐると考え続けていた。あれから一週間、それが私のしているすべてだった。日に日にお腹の中で大きくなる命の存在に怯えながら。
また一つ、新しい染みがコンクリートに吸い込まれていき、私は鼻を啜りあげた。子供の声が賑やかに響き渡る公園で、過去から現在に戻った私は下腹をなぞり、今度は未来の想像をした。堕胎のために産婦人科へ行く自分を。バイトで貯めた全財産を財布に詰め込み、待合室の隅で順番を待つ自分を。
夫婦なのだろうか、嬉しそうにささやきを交す男女をぼんやりと見ていると、梶田さん、せかせかした看護婦が私を呼び、汚いクリーム色のカーテンを開ける。そこには男の医者がいる。どうされました、気の無いふうに尋ねる。堕ろしたいんです、私は言う。けれど、その声はあまりに小さいため、医者の耳には届かない。赤ちゃんを堕ろしたいんです、聞き返された私は勇気を振り絞って、もう一度言う。育てられる自信がないので、と今度は言い訳を付け加えることも忘れずに。
すると、私は白いベッドに寝かされていて、その私を手術着を着た医者が覗き込んでいる。手術は無事終わりましたよ、医者が言う。このまましばらく安静にしていてくださいね、と言って去っていく。白い部屋に、私は一人取り残される。赤ちゃんはいなくなってしまった、私は考える。私の赤ちゃんは死んでしまったのだ、と。
いつもならば、想像はここで終わりだった。そして、私の思考は再び最初に戻る。公園の子供たちを眺め、どうして私の赤ちゃんにはあんな未来がないのだろうと考え、過去の記憶を辿りだす――。
しかし、何日も同じ場所に座り、同じ想像をし続けたせいだろうか。そのときふと、私の思考は道を逸れた。不快な痛みを感じたように、私は小さく顔をしかめた。赤ちゃんは死んでしまった ? いや、それは違うだろう。赤ちゃんは殺された 、それが正しい言い方だ。
――けれど、それは誰 によって?
すると、胸に新しく、ささやかな疑問が生まれた。それは母親の私? それとも父親である伊藤だろうか? いや、それが誰が殺したか という問いならば、医者や手伝いの看護師だと答えるのが正確かもしれない。けれど、彼らを人殺しと呼ぶのは、あまりにも乱暴だろう。
私はしばらく思考を巡らせた末、もしこれがお父さんだったら、と思った。もし、ここに父がいたら。真紀のために村野正臣を殺すと言い切った父がいたなら、あの人は殺された赤ちゃんのため、誰に復讐してやると言うだろうか。誰の心臓にナイフを突き立てることを選ぶのだろうか。
ぼんやりと考えているうちに、あの無機質な法廷の風景が私の目の前に広がった。二十五年前、何度も通った裁判所。あのときの光景のままに、検察官と弁護人が左右に分かれ、傍聴席は大勢の傍聴人で埋まっている。その後ろには、騒ぎがあったときのための廷吏が二名、休めの姿勢で立っている。二十五年前と何か違いがあるとすれば、それは裁判長席と被告人席で、裁判長席に座った父は木槌の代わりにギラギラ光る包丁を手にしていて、被告人席のあるべき場所にはその包丁を突き刺すときに暴れないようにか、拘束具のついた木台が据えられている。そして、その木台の前には四人の人間が横一列に並んでいた。四人とはもちろん、私と伊藤、それから顔も知らない医者と看護師だ。どうやらこの中から罪を負うべき一人を選び出そうということらしい。
『静粛に』
そのとき裁判長席の父が、木槌代わりの包丁を振りかざし、口を開いた。
『さて、ここに集った全員が知っての通り、この度、一つの小さな命が奪われた。梶田由紀のお腹に宿っていた赤ん坊だ。赤ん坊と言えど、命は命。その命は、奪った者の命によって償われなければならない。そこで、本法廷は彼を――いや、まだ彼か彼女かさえ分からなかったその赤ん坊を殺したのは誰 なのか、ひいては誰が死罪に値するのか、議論を行いたいと思う。ぜひとも忌憚なき意見をお願いしたい』
すると早速、厳しい顔をした検察官が立ち上がり、口を開いた。
『赤ん坊殺しの犯人は、その母親であると言っていいでしょう。ついては、死罪に値するのは梶田由紀に違いありません』
私を指差し、断言する。
『なぜなら、母親である彼女の同意なしに堕胎は行われない。赤ん坊を殺す決断をしたのは、彼女です。その決断が赤ん坊を殺したのですから』
そうだそうだ――傍聴席から声が上がった。その大勢でありながら足並みの揃った声に思わず振り返り、よく見ると、そこに詰めかけていたのは個を持った人間ではなく、大勢がくっついて一つの塊になったような日和見菌たちだった。彼らは当事者と部外者を隔てる安全な仕切りの向こう側から、私たち四人の中から一体誰が選ばれるのか、心から楽しそうに見守っているのであった。
『いえ、死罪がふさわしいのは梶田由紀ではなく、父親の伊藤雅人でしょう』
傍聴席に気を取られていると、そのとき別の検察官が立ち上がった。
『梶田由紀は、何も一人で赤ん坊を作ったわけではない。そこには父親――伊藤雅人の存在があるわけです。けれど、彼は暴力事件を起こした。手嶋という男を殴って、過失傷害で逮捕されたのです。それだけではない、 梶田由紀は彼に何度も殴られています。そんな人間が父親として相応しいか? 答えは否です。もし、無事に生まれたとしても、その暴力は結局赤ん坊を殺すかもしれない。梶田由紀は、伊藤雅人のせいで、泣く泣く赤ん坊を諦めざるを得なかったのです』
力強い説明に、傍聴席から、なるほどという声が漏れる。
『異議あり!』
しかし、そのざわめきを断ち切るかのように、また別の検察官が大声を上げた。彼はこれまでの発言がまったく理解できないとでもいうように、肩をすくめて法廷を見回した。一つ咳払いをしてから、口を開く。
『みなさん、これが赤ん坊殺しの裁判だということを忘れてはいませんか? ならば、殺したのは誰か。そう考えれば、罪を負うべき人物は明白です』
彼は医者を指差した。
『そう、他でもない彼の手こそが、幼い命を摘んだのです。つまり、彼こそが死罪にふさわしいのではないでしょうか』
裁判長席の父が、鋭い眼光で医者を見る。その視線に満足したように、検察官は付け足した。
『また、ここに私は看護師の罪も追求しましょう。なにせ、彼女は医者が赤ん坊を殺す手伝いをしたのですからね』
『そんな馬鹿な話はない!』
すると、たまりかねたように弁護人が声を上げた。
『堕胎は法律で認められていて、医者や看護師はその法律で守られている! 頼まれて堕胎する医者を人殺し呼ばわりするなんて、そんなことがあってたまるか!』
『それに付け加えるなら、そもそも生まれていない赤ん坊は法律上、人間とはみなされません。人権も何もない。だから中絶が可能なのです』
隣の弁護人が冷静に頷く。しかし、裁判長席の父は納得するどころか、カッと眼を見開き、その弁護人を憎悪の目つきで睨みつけた。
『ということは、その法律に赤ん坊を殺しの罪があるということか』
父が舐めるようにそこにいる全員を見回す。その低い声は、地響きのように法廷を揺るがした。
『いいか、もう一度周知しておく。本法廷は赤ん坊殺しを裁く場である 。もし、その法律がなければ、赤ん坊は殺されなかったというのならば、罪はその法律が償うべきだ。本法廷の権限をもって法律に死を与え、二度とそんな悪法が世に蔓延 ることのないようにしなければならない』
『いや、しかし――』
弁護人たちは何か言いかけたが、父の手に光る包丁を見て、それを諦めたようだった。被告席を争う四人の列に「法律」が加わり、私たちは五人になった。それを見て、ふと別の検察官が口を開いた。
『しかし法律にも罪を認めるということになると、社会制度にも罪を認めざるを得ないのではないでしょうか? 例えば、福祉のことですが……』
検察官は考え込むように続けた。
『例えば、梶田由紀が暴力的な夫に頼らず、シングルマザーとして赤ん坊を出産したとして、それでも生活が十分に保障されるような制度があったなら、赤ん坊は殺されずに済んだかもしれません。そう考えると、私たちは現在の福祉制度に死を与え、より手厚い福祉を生み出すべきでは――』
『それにつきまして、傍聴席のみなさんの意見を代弁しますと』
検察官の話を遮って、また別の検察官が大きな声を出した。ちら、と傍聴席の日和見菌たちを見やる。つられてそちらに目をやると、いままで身を乗り出して目を輝かせていた彼らは、気まずそうにあらぬほうを向いていた。
検察官は歯切れ悪く続けた。
『えー、社会福祉というものは、本当に最後の最後の手段であって、自己解決できる可能性のある人間が、簡単に利用するというのは甘えでしかないでしょう。ここにいるみなさんもそれぞれの事情を抱えていらっしゃいますが、努力していまの生活を築き上げ、血税を払う側へ回っているわけです。ですから、梶田由紀に関しましても、まずは福祉を頼らず、自分で努力してみることが大切であって……もしそれでも立ち行かないというのならば、次善の策として身近な人が支えるべきじゃないでしょうかというのが、私もでありますが、みなさんの意見であると思いますが――この場合、それは母親の梶田美希子です』
検察官が誰かを紹介するように右手を差し出す。すると、その隣にはいつのまにか年老いた母の姿があった。彼に促され、母も死罪候補の列に加わる。その姿を目で追いながら、検察官は続けた。
『もし、彼女が娘を突き放さず、その出産や育児を手助けできる関係であったなら、梶田由紀は赤ん坊を産むことができたでしょう。ということは、そういう環境をつくらなかった母親にも、赤ん坊殺しの責任があるに違いありません』
『梶田美希子に責任があるというのなら――』
すると、思わずといったように検察官の一人が立ち上がった。小さく息を吸い、覚悟を決めるようにして、一段高い場所にいる裁判長を――父を見上げる。
『彼女よりも大きな罪を持つ人間を、私はここに糾弾しましょう。それは、あなたです――雨ヶ谷洋介裁判長』
突然の糾弾に、父はぴくりと眉を上げた。無言のまま、先を促す。検察官は続けた。
『ここにおります裁判長――いえ、梶田由紀の実父・雨ヶ谷洋介は、二十五年前、由紀の妹であるもう一人の娘、真紀を殺害された恨みを晴らすため、なんと仮釈放された加害者を殺害する計画を企てています。いいですか、この男は人殺しを――殺人を企てているのです。先ほど、伊藤雅人の過失傷害の話が出ましたが、どちらの罪が重いのかは明白でしょう。伊藤が暴行犯なら、雨ヶ谷洋介は完全なる殺人犯です。赤ん坊はその孫となるのです。生まれてくる子供に「殺人犯の孫」という足枷をつけたくない、そんな梶田由紀の思いは理解できます』
『しかし、伊藤雅人はすでに罪を犯しましたが、雨ヶ谷洋介の犯行はまだ行われていません。そう考えると――』
弁護人の指摘に、検察官は首を振る。
『いいえ、彼は必ずやり遂げます。ですから、これは既成事実と同等であると言っていいかと』
『検察官の意見を認める。雨ヶ谷洋介は直ちに被告の列に加わるように』
厳かな声に裁判長席を見上げると、そこにはいつのまにか別の裁判長が現れていて、居場所を失った父はその命令通り、しかし不服そうに段を降り、私たちのほうへと歩いてきた。
『……しかし、そうすると、また新たな被告が増えるということにはなりませんかね』
その歩みを待つ間、考え込むように検察官が呟いた。
『村野正臣ですよ。そもそも彼が雨ヶ谷真紀を殺さなければ、雨ヶ谷洋介も殺人を考えることはなかったはずです。また、それだけじゃない。彼は妻の梶田美希子とも離婚せず、そうなると梶田由紀は至極普通の家庭で育ったことが想像されます。そうすると、ですよ? 彼女は就職した会社できちんと働くことができ、そうなれば伊藤雅人のような暴力男と付き合うこともなく――』
『いや、それは単に男の趣味が悪いだけでしょ』
弁護人の皮肉に、どっと傍聴席が湧いた。一度は法廷から目を逸らした日和見菌たちが体を揺すり、笑っている。殺人事件に同情した次の瞬間には、パンダの赤ちゃんが可愛いと歓声を上げ、芸能人の結婚に一喜一憂する彼らにとっては、この法廷すら他人事であり、対岸の火事なのだ。その楽しげな様子に、違う――私は無性に苛立ちを覚えて叫んだ。
『違う! 私たちは悪くない!』
『被告人は静粛に』
裁判長が木槌を鳴らした。騒ぐと罪が増えますよ、弁護人が目顔で合図してくる。けれど、私は止まらなかった。二十五年分の怒りが体中を駆け巡り、その怒りは日和見菌たちに向けた奔流 となって、私の口から飛び出した。
『赤ちゃんが殺されたのは私たちのせい? 違う、私の赤ちゃんが殺されたのは、あなたたちのせいだ。あなたたちが私を異物扱いして、仲間外れにしたせいだ。あの子が妹を殺された子だと、可哀想な子だと、こそこそ噂したからだ。そしてこれからも同じことを――いいえ、もっとひどいことを生まれてくる赤ちゃんにもするだろうと、簡単に想像がつくからだ。殺人犯の孫、暴行犯の子と囁 かれながらの人生がどんなに辛いか、あなたたちに分かるか。あなたたちがこの子を受け入れてくれないから、この子は死ななくちゃならないんだ!』
声が割れるほど滅茶苦茶に叫ぶと、法廷はしんと静まり返った。私の思いは彼らに届いたのだろうか、そう思ってしてしまうほどに。けれど、やはりそれは錯覚であったらしい。
『おや。ということは、またまた被告人が増えたということですかねえ。とはいえ、不特定多数の人たちに罪を――ましてや死罪を突きつけることなど、まったくもって不可能なことですが』
馬鹿馬鹿しいと言わんばかりに、肩をすくめて裁判長は笑った。すると、その仕草にほっとした日和見菌たちも同じように声を立てて笑った。明るく楽しげな雰囲気が法廷に満ち、私の怒りは急速にしぼんだ。
裁判長の指摘は現実的だった。もし、私の糾弾が正しく、彼らに罪があったのだとしても、彼の言う通り、その罪は不特定多数の人々によってほとんど透明なまでに薄まり、それを全員に償わせることなど不可能だった。
そう考えて、私はふと息を止めた。赤ん坊殺しの罪。その命を命で償うために集められた、私たち被告人の列。この列に並んだ誰か の罪が死罪に相当するのだと、法廷は言う。
けれど――私は考えを巡らせた。彼らは私たちの罪状を読み上げた。しかし、そのどれもが決め手に欠けるものだった。だからこそ、被告人の列は次第に長くなり、しまいには不特定多数の人間まで巻き込んだのだ。
つまり、私たち一人一人が抱える罪は、どれ一つとして完全ではなかった。それは例えるなら、被告人全員がそれぞれ同じパズルのピースを持っているようなもので、けれど、赤ん坊殺しの絵を完成させるためには、その全てのピースを――私や伊藤、医者、看護師、父に母、村野正臣、さらに言うならば法律に社会福祉制度、誰であるかさえ分からない日和見菌たち、そしてもしかしたら二十五年前に殺されてしまった真紀さえ持っているかもしれないピースを一つ残らずかき集める必要があった。そうしなければ、パズルは――赤ん坊殺しの罪は完成しないのだ。命を命で償うというほどの完全な罪は、誰か一人の罪では成立しないのだ。
しかし、だというのに、その罪は誰か によって償われなければならないと法廷は言う。この赤ん坊殺しという大罪は 、誰か一人の 命によって 償われなければならない 。それが 死罪と いうものだから 。
『さて、そろそろ結論を出さなければ』
再び静まった法廷を、裁判長が感情のない目でぐるりと見渡した。被告人たちの長い列を端から端までゆっくりと眺める。そして、おもむろに問うた。
『さあ、この中で一体、誰 が死罪にふさわしいだろうか?』
いつのまにか、彼は父の持っていたはずの包丁を手にしていた。私たちの中の誰かに、ぎらぎらと光るその刃は振り上げられる。振り下ろされる。誰かの心臓に突き刺さり、彼に裁きの死を与える。
「いやあああああ!」
次の瞬間、断末魔のような声が響き、私ははっと我に返った。気がつくと私がいるのは法廷ではなく、うさぎの公園の東屋だった。
「ほら、次はお友達の番でしょう」
癇癪 を起こして泣く子供を、その母親が慰めている。どうやら子供たちが、二つしかないブランコの取り合いをしているらしい。私はこめかみを流れ落ちる汗を拭い、小さく息をついた。震える指で心臓のあたりを探る。まさか振り下ろされた包丁が刺さっていやしないかと思ったのだが、早い鼓動が伝わってくるだけで、そこには血の一滴も流れていなかった。ほっとした私は、深呼吸を繰り返した。しかし、早鐘を打つような鼓動は泣きやまない子供と同様、なかなか収まることがなかった。
――私の赤ちゃんを殺すのは、誰 か。
しばらくして、ようやく気持ちを落ち着けると、私はそっと下腹に手を当てた。赤ん坊殺しの裁判。あれはただの妄想だ。現実じゃない。このお腹に宿った命を生かすも殺すも、実際には私の決断次第だ。それは私の罪であり、それを人のせいにするなんて、そんなことをしてはいけない。
私は自分にそう言い聞かせた。しかし、一度生まれてしまった疑問は、すぐに胸を去ってはくれなかった。
この子を殺すのは、私の決断だ。ならば、罪があるのはその決断をした私だろう。けれど――私は慎重に問いかけた。その決断は、本当に私だけのものなのだろうか? 他の誰も関わることのない、純粋な私個人の考えなのだろうか。
いや、それは絶対に違う――自分の問いを、私は自分で否定した。なぜなら、私はこの子を殺したいだなんて思ってはいなかった。そうではなく、暴行事件を起こした伊藤がこの子の父親だから、殺人を犯そうとしている私の父がこの子の祖父だから、私ではなく妹を殺した犯人を愛するのがこの子の祖母だから、そして何より妹を殺された私は特別 だから、日和見菌たちの世界で生きることが難しいから、だから私はこの子を殺したほうがいいかもしれない と思っているだけだった。
それは私の決断であり、同時に私の決断ではなかった。なぜなら、私は数ある選択肢の中からそれを選んだわけではなかった。元々はたくさんあったかもしれない選択肢は何か に奪われ、私が選ぼうとするときにはもう、いくらも選べるものなど残っていなかったのだ。ただ一つ、殺す という選択が、一番ましだと思えるほどに。
東屋の中には、重だるい熱を含んだ空気が充満していた。張り詰めた息を吐き、私は一度目を閉じた。そんなことは考えても仕方がないと言い聞かせた。第一、私は赤ちゃんをどうするか、まだ決めていない。よしんば殺すという決断を下したとしても、あんな裁判が開かれることは絶対にない。堕胎は法律で許可されている。医者も看護師も私も伊藤も、死刑どころか、そもそも罪に問われることがないのだ――殺人という罪を犯した村野正臣と違って。
村野正臣。ふとこぼれ落ちてきたようなその名前に、私はどきりとした。けれど、すぐにそれも当然だと思い直した。裁判に法廷、死刑という罪――それらはすべて村野のせいで私の人生にもたらされたものだった。彼さえいなければ、私はそんなものなど知らずにいられたのだ。日和見菌たちと一緒になって笑っていられたのだ。あの検察官が言ったように、伊藤と付き合うこともなかったかもしれない。
ならば――奥歯を噛み締め、私は思った。やはり、罪に問われるべきは彼ではないか。すべては彼が――村野正臣が真紀を殺したことから始まったのだ。彼が私たち家族をばらばらに壊したことで、それから先の未来は狂った。私の赤ちゃんまで殺さなければならない状況に追い込まれたのは、そのせいだ。だから、赤ん坊殺しで死罪に問われるべきは彼だ。彼が諸悪の根源だ。シャルルにおける悪の大王ジャークだ。彼が生きている限り、不幸は止まらない。ということは、その諸悪の根源を倒してしまえば、世界には平和が訪れるということだ。だから、あのとき私たちは村野正臣を死刑にするべきだったのだ。
興奮に、血が激流のように体中を駆け巡り、ぎゅっと攣 るような痛みが下腹に走った。私は思わずそこを押さえたまま、うずくまった。そうしながら、私はその痛みは赤ちゃんからの抗議だろうと思った。なぜなら、私がこう言ったのはついさっきのことだった――命を命で償うというほどの完全な罪は、誰か一人の罪では成立し得ないのだ、と。
目には目を、そう言って命で命を償わせるためには、その人間だけにすべての罪が集約しているという証が必要なのではないのか――痛みは、改めてそう訴えているようであった。
そして、その問いはその先にある考えたくもない問題までもを、真っ直ぐ私に問いかけた。
果たして 、村野正臣の罪は完全なのか ?
それは私たちが望むほどに――例えば死刑がふさわしいと詰 られ、父の手によって行われる復讐が許容されるほどに完璧なのだろうか。私の赤ちゃんが殺されるのと同じように、村野の罪にも大勢の人が関わり、その人々の分だけ、数多 の事情が隠されてはいないだろうか。
「……そんなこと、考えたくない」
信じていたものを根底から覆してしまいそうな大きな力に怯え、私はわざと声に出してそう言った。
「私が考える必要もないし、いまさら何も考えたくない」
一語一語区切るように、はっきりと私は言った。他に誰もいないこの東屋で、独り言に異議を唱える人など誰もいなかった。にも関わらず、反論を聞くまいとするように、私は両手で耳を塞いだ。そして「全部、村野正臣のせいだ」と呟いた。何度も何度も、念仏を唱えるように呟いた。けれど、私の意識とは別の何かは、その先を考えることをやめなかった。
伊藤が暴行事件を起こし、母は頼れず、父は殺人犯になろうとしていて、だから私は赤ちゃんを殺すことを決断する。そこには殺してくれる医者や看護師がいて、それを許可する法律があって、逆に私と赤ちゃんが生きていくのに十分な支援はないから。人の目は冷たく、私たちは異物として肩身狭く暮らしていくしかないだろうと思うから。
けれど――本当に考えたくもないことだけれど、同じような事情が村野正臣にもあったとしたら。彼に殺人を犯すという選択肢しか残さなかった何か がそこにあったなら。事実として、真紀に直接手をかけたのは彼だ。けれど、彼をそこに導いた何か を私たちは見落としてはいないだろうか。いや、見落とすどころか初めから目を背け、その背後にあるものの想像すらしようとしていないのではないだろうか?
もうやめて、聞きたくない――目を閉じ、子供のように叫ぶ私を押しのけ、思考は続いた。
例えば、伊藤が暴力を振るう理由――いや、振るってしまう 理由を、私は知っていた。伊藤自身も知っていた。それは、もう覚えてもいないような些細なことが原因で、ひどく殴られた夜のことだった。ようやく怒りが収まった彼は泣き出した。それ自体はいつものことだった。ごめん――私を散々殴った後、彼はそう言って涙を流すのだ。けれど、その夜はいつもと違った。
『俺、前はこんなんじゃなかったんだよ』
頭を抱えるようにして、伊藤は言った。
『前はこんなことなかったんだ。人を殴ったことなんかなかった。ホントなんだ。それなのに、あれからダメなんだ。自分が抑えられなくて、頭が真っ白になって、気がついたらこうやって……』
彼は子供のように泣き崩れた。そうしながらも、さっき私を殴った手で、私を撫でた。その触れ方はとても優しく、前っていつのことなの――掠れた声で私は聞き返した。
『あの事故の前だよ。利き腕ポッキリいく前。あの事故で俺の脳みそがイカれちまったんだ。それまではこんなことなかったんだ。それなのにこんなことになって、俺は家族からだって見放されて……』
伊藤はさらに泣いた。初めての告白に驚きながらも、痛む身体を起こし、私は彼に寄り添った。
交通事故の後遺症で人が変わったようになってしまった――そんな人の話を、いつだか私はテレビで見たことがあった。『あなたの脳が犯罪を犯す』――それはある種オカルトのような、にわかには信じられない話ばかりが詰め込まれた番組だった。犯罪者の脳には異常があり、だから犯罪者は罪悪感もなく犯罪を犯し続けるのだとか、人間の一生はあらかじめ遺伝子によって決められていて、それ以外の人生は歩めないのだとか。
その中の話の一つに、交通事故で脳に障害が生まれ、怒りが制御できなくなった人のものがあった。以前は穏やかだったその人が、事故をきっかけに怒りっぽくなり、最後には家族全員を惨殺してしまうという、それはそんな衝撃的なストーリーだった。
もし、伊藤の言うことが本当なら。そしてあのテレビ番組の話が本当だったなら。彼が暴力を振るってしまうのは仕方がないことに思えた。だって、普通 の人は暴力を振るわない。だったら、暴力を振るう特別 な人には理由がある。妹を殺された私が特別 になったように、その交通事故が彼を特別 にしてしまったという考えは、とても納得がいくものだったのだ。
それから少し考え――もしもそれが本当でなかったとしても、例えば伊藤が嘘をついていたとしても、それは同じことだと私は思った。どうにせよ、彼は普通 ではない。だとしたら、その普通 から彼を弾き出した何か がそこにはあるのだ。彼と同じ、特別 を持つ私には、それが自然と理解できた。
もしかしたら、村野正臣も伊藤と同じではないか。いままで自分のいる場所とはまったく別の場所に位置づけていた「殺人犯」の彼に、私は小さく歩み寄った。
法廷で明かされることのなかった彼の事情を、私たちは知ることができなかった。けれど、彼にもまた特別 になった理由があるのではないか。私の意志とは裏腹に、思考はどんどんと先へ進み続けた。
例えば、それは村野を虐待した母親。彼女が村野を特別 にしたのではないか。もしくは、虐待死したという彼の妹。その妹が死ななければ、村野は殺人犯にならなかったのかもしれない。また、話に決して出てこない村野の父親はどこにいるのだろう。もしかしたら、彼の母親は父親の不在に苦しみ、村野を虐待したのかもしれない。だとしたら、村野の殺人は父親のせいとも言えるはずだ。
それから、彼が少年のときに補導されていたという話。そのとき、関わった警察や周りの人々が適切な指導ができていれば、彼は真紀を殺さなかったかもしれない。あのテレビで見た、脳みその話だってそうだ。もしかしたら、村野の脳にはもともと障害があったのかもしれない。伊藤のように、彼もまた交通事故に遭ったことがあるのかもしれない。その場合、罪はその障害を発見できなかった誰かに、また彼を撥 ねたかもしれない誰かにもあるとは言えないか――。
赤ちゃんが殺される理由として、私が最後には不特定多数の日和見菌たちを責めたように、村野が殺人を犯した理由も、突き詰めていけば遠い他人に行き当たった。彼を中心として、円状に広がった罪は、その遠い他人の場所まで来れば――円の一番外側まで辿り着いた頃には、限りなく透明に見えた。けれど、それは透明に見えるだけで、まったく何の罪もないわけではないようにも思えた。
例えば、私はそこに殺される直前に真紀を見たという、近所のおばさんの姿を見た。男がついていくのを見たという、カメラ屋のおじさんを見た。そして、私たちの姿を見た――パートのために私たちを鍵っ子にした母を、それを許可した父を、あの日に限って一緒に下校しなかった私を、危険に気づくことのできなかった真紀本人の姿さえ見た。もちろん、それらの行動は真紀を直接殺すことはなかったし、後悔しても仕方のない、偶然の行動ではある。けれど、真紀が殺されたという結果から振り返れば、私たちは村野の殺人にほんの僅か、加担したことになってしまうのだった。
そこに責任があるとは言えないような、ましてや罪とも言えないような、そんな取るに足らない行動の積み重ね。誰に所属しているとも言えない、けれど殺人という罪を構成する、私たちはパズルのピースを手にしていた。それはもちろん私たちだけではない。村野の両親やその周りの人々、社会や法律や彼の脳みそ、そして村野自身もまた、その数に差こそあれど、同じパズルのピースを持っていた。
もちろん、そのピースを一番多く持っている村野は、何らかの罰を与えられてしかるべきだろう。けれど罪というものは、そのすべてのピースが持ち寄られて完成を見るものだった。とすれば、彼の持つピースだけで罪が完成しない以上、その刑罰が彼という人間を根本的に成立させているもの――その命を奪うのは間違っているのではないだろうか。殺人という罪に参加した、たくさんの人々の代表として、村野が死ぬことは正しいことなのだろうか。それは一般に生贄と呼ばれるものなのではないだろうか。その罪を誰か のものとして終わらせてしまうための、みんな が一貫して、この罪は自分には関係のない他人事なのだ 、と切り捨ててしまうための。
私は固く閉じたまぶたを開け、耳を塞いでいた手をのろのろと膝へ戻した。意思とは裏腹にたどり着いたその結論を、私はとても正しいと思った。けれど同時に、そんな考えはとても間違っているとも感じ、どうして私がこんなことを考えなければならないのかという強い怒りを感じた。
妹が殺され、お腹の赤ちゃんまでも殺されようとしている私は正真正銘の被害者で、そこに疑いが挟まれる余地などあってはならなかった。被害者は怒りのままに加害者を憎むことができるはずで、だというのに、その加害者にも実は被害者の一面があるかもしれないだなんて、そんな訳の分からない擁護は耳に入れたくもないものだった。
けれど、一方で私がこんなことを考え続けるのは、伊藤のせいもあるのだろう。手嶋が死んでしまえば、伊藤は殺人犯になってしまう。伊藤が暴力を振るうのは、大昔に起きた交通事故のせいかもしれないのに、それなのに車のドライバーが罪に問われることは絶対にない。あるいは、その暴力を知っていながら放置した彼の家族や、私のせいであるかもしれないのに、私たちの罪もまた、決して問われることがない。それどころか、私たちが暴力を受けていたことが知れれば、その罪は彼の「前科」として加算されてしまうことだろう。そうして膨れ上がったその罪を、伊藤はたった一人で負うことになるのだ。
この世には、生きている人の分だけ事情がある。目に見えるものから、見えないもの、容易く想像できるものから、想像すら難しいものまで――。私たちは関わる人のすべてを知ることはできない。そういう意味で言えば、私も誰かにとっての日和見菌だった。限りなく透明な罪の中で、円の一番外側で、知らん顔で生き続けるたくさんの日和見菌のうちの、私はその中の一人に違いないのだった。
私はそんな自分を嫌悪した。あのぬるま湯のような日和見菌たちの世界へ戻りたいと、ずっとそう願っていたはずだというのに、いまの私はその逆だった。例えその罪の一番外側であったとしても、私は誰かの罪に属していたくはないし、そこにいることを良しとすることができなかった。私は人と関わっていたかった。けれど、そうすることで誰かの罪に属すことになってしまうのは嫌だった。
しかし、それならどうすればいいのだろう――私はうなだれた。どうしたら、私は罪なく生きることができるのだろう。それとも、そもそもそんな風に生きるだなんて、無理な話なのだろうか。
子供はまだ泣き続けていた。泣き止まない子供を見かねて、別の子がブランコを降り、その子に譲った。しかし、その子はまだ泣き止まなかった。まるでここで折れたら負けだとでもいうように、傷ついた私にはこれほど泣き喚く権利があるのだというように。だから、泣き続ける彼女には見えていないようだった。そこにブランコを譲ってくれた子がいることを、傍らで母親が慰めてくれていることを。それとも、すべて分かった上で、彼女は意地になって泣き続けているのだろうか。
真紀にも意地っ張りなところがあったな――その泣き声を聞くうちに、私はふと思い出した。たった六歳で死んでしまった、私の妹。いま振り返れば、私の人生の中で、彼女と過ごした時間はあまりにも少なかった。生きていたら、どんな大人に成長したのか、私との仲はどうだったのか、意地っ張りな性格は直ったのか――古びて文字も薄くなってしまった記憶のページをめくるように、私は過去に思いを馳せた。シャルル役を争ったこと、家の中でローラースケートをして怒られたこと、二人で一緒に下校したこと、私の嫌いなピーマンと真紀が嫌いだったトマトを内緒でこっそり交換したこと、うさぎの公園で遊んだこと、そしてあの日の喧嘩のこと――。
――シャルルの呪文の意味って知ってる?
そのとき、なぜだろう、不意に手嶋の言葉が蘇った。
――有名かもしれないけど、あれって英語なんだよ。オル・フォル・ギュネス(all for goodness)、すべては善いことのためになされるべきだっていう意味なんだって。
あのときもそうだったように、なんだか不思議な気持ちが込み上げた。日々のお節介に迷惑しているというのに、その手嶋が「善いこと」などと言い出したからだろうか? いや、違う。引っかかったのは手嶋のことじゃなくて、もっと誰か別の――。
――あのジュモンの意味、知ってる?
そのときだった。脳裏に鮮やかな色が弾けるように、幼い声が蘇った。
――あれ、エイゴなんだって。お姉ちゃん、知らなかったでしょ。
得意げなその声は、真紀の声だった。あのとき――真紀が殺される直前、一緒に帰り道を歩いていたときの声。そうだ、それが私たちの喧嘩の原因だった――私は思わず胸に手を当てた。あの日の放課後に一体何があったのか、記憶がみるみる蘇った。
あの日、いつもの待ち合わせ場所の校門。そこに駆け寄ってきた真紀は、友達にシャルルの呪文の意味を教えてもらったと、得意げに話してきたのだった。
『え、どういう意味なの?』
勢い込んで聞いた私に、
『教えてほしい?』
真紀はにんまりと笑った。いまでこそ想像がつくが、姉の私が知らないことを知っているということが、真紀はよほど嬉しかったのだと思う。教えてよと言う私に、真紀はいつまでももったいぶって、ちっとも教えてくれなかった。
『ねえ、いいから早く教えてよ』
『えー、どうしよっかなあ』
『いいから早く』
『うーん、あと地球が百周まわったらね』
『バカなこと言ってないで、早く教えて』
『あ、やっぱあと百億周!』
『もう、真紀!』
教えてよ、教えない――問答は次第に激しくなった。そうするうちに、あのブランコの子のように、真紀も意固地になったのだと思う。もうお姉ちゃんには教えてあげないと言い出した。泣いて頼んだって、絶対に教えてあげないと言い張った。
大人になったいまなら、そんな真紀をなだめすかし、うまく聞き出すことができるだろう。喧嘩などせずにいられただろう。けれど、あのとき私は子供だった。真紀のお姉さんではあったけれど、まだ小学生のお姉さんだった。だから、私は言ったのだ。『じゃあ、バイバイ』と。意地悪な顔で、『真紀のことなんか、もう知らないから』と。
姉の私にそう言われた真紀は、むっと口をへの字に曲げた。けれど、それも一瞬だった。
『バイバイ』
そう言うと、真紀はあっかんべーをして駆けていった。
『もう一生、お姉ちゃんには教えてあげないからね』
と、そんな捨て台詞を残して。
その言葉が現実となるだなんて、誰が予想しただろう。けれど、それは現実になった。私と別れた後、真紀は村野に殺されてしまった。だから、シャルルの呪文の意味は本当に分からないままになってしまった。真紀とともに葬り去られてしまった。
いや、そんなことはどうでもよかったのだ。私は頭を振った。善いことをしろだか、善いことのためにだか知らないけれど、そんなのは本当にどうでもいいことだった。そんなことは一生知らなくてもいいから、私は真紀が死んでほしくなんてなかった。喧嘩ばかりの姉妹だったとしても、それでも生きていてほしかった。
「……真紀、どうして死んじゃったの」
呟くと、私の目から涙がこぼれた。それはもしかしたら、真紀のためだけに私が流した、初めての涙かもしれなかった。
うさぎの公園に、私の嗚咽が小さく響いた。あたりの静けさに気がつけば、遊んでいた親子連れはひと組、またひと組と、元来た道を引き返していた。泣き疲れた顔を上げると、真上にあった太陽は傾き、東屋には赤い夕日が差し込み始めていた。
そういえばあの後も、手嶋は何か言ってたっけ――しばらくして涙が落ち着いたとき、私はぼんやりと思い出した。すべては善いことのためになされるべきだという、あの呪文の意味を解説した後、手嶋は続けて何かを言っていた。アニメの世界が何だとか、そこが好きなんだとか何とか――。
――お節介って思われてるかもしれないけど、だから僕はこうやって梶田さんとも話そうと思ってるんだよ。
ああ、そうだ――私は思い出した。あっちへ行けと拒絶されてもお節介を焼く理由を、彼は泣き続ける私に話したのだった。
――いつも店長に言われるけど、アニメって確かにクソだよね。
彼は自虐するようにそう言った。
――努力して、努力して頑張れば、すべてはうまくいく。仲間に裏切られても、その仲間を信じて、最後にはその気持ちで悪に打ち勝つ。でも現実はそうじゃない。理不尽なことなんかいっぱいある。努力なんか報われないし、頑張っても自分の力じゃどうにもならないことなんか当たり前だし。でも、それなのにアニメは勧善懲悪の単純な世界を描き続ける。人を馬鹿にしてんのかって、実は僕も思ってたんだ。でも、繰り返し見るうちに……こうも思うようになった。そういう世界って羨ましいなって。梶田さんはそう思わない?
手嶋はこちらを窺うように見た。私はそれを知りながら顔を上げようともしなかった。しかし、彼は優しく続けた。
――もしかしたら、そう思わない人もいるのかもしれないけど……僕はそう思ったんだよ。現実もこんな世界だったらいいのになって。それからさらに見るうちに、今度はこう思うようになった。アニメをつくる人たちも、そう思いながらつくったんじゃないかって。現実もそういう世界であるべきだと思ったからこそ、アニメの中に善い世界を、いいもん が活躍できる理想の世界をつくりあげたんじゃないかって。
手嶋の言葉に、私はそのとき顔を上げた。いいもん――その子供じみた表現は、耳に妙に懐かしかった。私が興味を持ったことが嬉しかったのか、手嶋も笑顔になった。ただでさえ小太りの丸い顔が、月のようにまんまるになった。優しい口調には、ほんの少し、熱がこもった。
――僕、思うんだよ。すべては善いことのためになされるべき だってシャルルが唱える呪文のように、現実の世界も善が報われる世界であるべきだって。善いものが善いまま、善い人が善いままでいられる世界であるべきだって。もし、そこにジャークのような悪があったとしても、それを善が上回る世界であるべきだって。そういう世界を目指して、僕たちは生きていくべきなんだって、僕はそのとき思ったんだ。だから僕は偽善者と言われようが、お節介だと言われようが、自分が善いと思うことはしようと思ってる。悪いことと知りながら知らんぷりするんじゃなく、世界を少しでも善いほうへ変えていきたいと思うから、だから僕は――。
私が手嶋の言葉に耳を傾け出したそのとき、伊藤の怒声が休憩室に響いた。私はそのあとのことを繰り返し思い出そうとして――止めた。代わりに、病院のベッドの上で眠っているはずの手嶋のことを考えた。意識不明で、いつ死んでしまうかもわからない彼のことを思った。
手嶋はバカだ――最初に浮かんだのはそんな言葉だった。確かにアニメの主人公なら、目の前で泣いている人に知らんぷりなんてしない。その人を慰め、最後には一緒に笑っているだろう。それがアニメの描く理想だ。「善いこと」だ。けれど、現実はどうだ。手嶋の「善行」は、その彼を病院送りにしただけだった。それで世界が善いほうへ変わった? そんなはずないだろう。伊藤は警察に捕まり、私はここで堕胎をしようと思いつめているのだ。それが手嶋の言う「善い世界」か? どう考えたって、そんなはずはない。
それなら、あのとき手嶋はどうすればよかったのか。私はそうも考えた。けれど、そんなことは分かりきっていた。彼は、あのとき私に声を掛けるべきではなかった。私にお節介など焼かなければ、いま、彼は意識不明になどなっていないのだから。
――シャルルのように、世界を善い方向へ変えていきたいと思ってるから。
しかし、一度思い出してしまった手嶋の声は、耳の奥から離れなかった。世の中の人間には、その人間の数だけ事情があると、私はついさっき、そう考えたばかりだった。手嶋は善いことをしたいと願った。けれど、それは他人の事情――伊藤の事情と噛み合わなかった。手嶋は、事故に遭った伊藤の事情を知らなかったから。その結果だって、まるで予測のつかないものだったから。手嶋は自分が善いと思った行動しただけだった。
それでも、こんな結果を知ってさえ、手嶋は満足していると言うだろうか。答えのない疑問に、私は唇を噛んだ。彼は自分の行動に後悔はないのか。善と信じたお節介のせいで伊藤に殴られ、病院送りになったけれど、それでも、あれがそのときの最善の選択だったと言うのだろうか。あのまんまるな笑顔を見せて。
刻々と赤みを増していく空を、私は見上げた。今日は真紀の命日で、真紀は二十五年前のいま頃、村野に殺されてしまったのだった。過去を思い、私は身じろぎをした。すると、何かが膝の上から滑り落ちたような気配がして――私は屈み込んで、それを拾い上げた。母のお守りが揺れる、古いポーチ。そこに縫いつけられたシャルルのリボン、その中央のプラスチックの宝石がきらきらと夕日を反射した。この宝石が虹色に光って、シャルルは変身するんだっけ――私はその偽物の石をじっと見つめた。
子供の頃に買ってもらった食玩についてきた、小さなリボン。このお守りをもらったとき、私はもう高校生で、シャルルの好きな子供なんかじゃなかったのに、母はどうしてこんなものを縫いつけようと思ったんだろう。そっと撫でるように触れていると、脇のほつれかけていた糸がプツリと切れた。たった一つの母との繋がりが切れてしまったような気がして、私の胸には悲しみが込み上げた。現実はやはり、アニメのようにはいかなかった。ばらばらになった家族は元に戻ることもなく、私たちは決して幸せな結末を迎えることはないのだ。
私は、切れた糸くずを指先で抜き取った。すると、合わせ目から中の護符がはみ出しているのが見えた。私は元に戻そうとしたが、その紙に罫線があることに気づき、首をかしげた。少しためらってから、それを中から引っ張り出す。すると、やはりそれはただの紙切れ――それもルーズリーフの切れ端のようだった。これはまさか――私は息を飲んだ。しばらくそれを見つめた後、小さく丁寧に畳まれたそれをゆっくりと開く。
そこに記されていたのは、母の字だった。会えなかった時間も、苦しい感情も、何もかもを溶かしてしまうような、優しい母の字。私は驚きを感じながらも、その文字を目で辿った。その言葉を、何度も何度も読み返した。
『辛くなったら、いつでも帰ってきていいからね。どんなに離れ離れになったとしても、お父さんもお母さんも、いつも由紀のことを思っているから』
紙に視線を往復させるうちに、私の胸は熱くなった。言葉にならない思いが、思い出が次々と込み上げ、それらは一つとなって私に幸せの意味を教えた。そのためにすべきことを教えた。その一歩を踏み出すための力を与えた。
あの頃、夢見たいいもん に、シャルルになろう――心にぽつりと点のような光が生まれ、それはじわじわと次第に大きく広がっていった。人にはそれぞれ事情があって、そのすべてを想像することなんて誰にもできない。私は私の思う善いことしかできないかもしれない。でも、想像のつかない結果を恐れて立ち止まるよりは、思い切って歩き出そう。悪から顔を背けるのではなく、善いことをしよう。それがきっといつか、誰かを救うかもしれないと胸に信じて。
そう決意すると、私はカバンの中から携帯を取り出した。もう何年も思い出すことさえしなかったというのに、指は懐かしい電話番号を正確に押していった。母はまだ仕事から帰っていないだろうか。父も家にはいないだろうか。でも、それでもいい。断たれてしまったものを、また繋ぎなおそうという意志のために、私は通話ボタンを押した。呼び出し音を優しく聞いた。
お父さん、お母さん――言うべき言葉は知っていた。私、お腹に赤ちゃんがいるんだよ。お父さんたちにとっては、孫になるんだよ。真紀のことは悲しかったけれど、でも私たち、もう一度会えないかな。家族に戻れないかな。きっとそれが善いことだと思うから。善い未来へ繋がることだと思うから――。
優しい音は続いていた。その音が唐突に止む。そして――はい、雨ヶ谷です、懐かしい声が私に応えた。
「おれ、最初は滑り台!」
「じゃ、早く行ったほうの勝ちね! よーい、どん!」
「あ、ずるすんなって!」
「ずるしてないでーす!」
そのとき、きゃあきゃあと騒がしい声を立て、子供たちが目の前を駆けていった。小学生くらいの男の子と、女の子。きっと兄妹なのだろう、少し離れた後方からベビーカーを押す母親が「転ばないでよ」と声をかける。けれど、そんな注意は耳に入らないのか、兄妹は我先にと転がるようにして坂を下っていく。
その小道の脇に建つ、小さな
いまはまだ親指の先ほどだという、小さな小さな命が息づく場所。いつかはあの子たちのように公園を駆け回り、もっと先の未来には、それを見守る親になるはずの小さな命。そうして命は巡り、人は大きな幸せを築き上げていく――込み上げてくるものを必死に飲み込みながら、私は思った。子供を産み、育てるということはきっと、その大きな幸せの一部になるということなのだろう。そう、きっと
足元のコンクリートの染みに視線を落とし、私はさらに考える。それはあれから二十五年も経ったというのに、私の父が復讐を忘れず、自ら殺人犯になろうとしているせいだった。母がそれを止めないせいだった。それだけでも十分なのに、最後のとどめを刺すように起こった事件のせいだった。あの日、私が両親の話を盗み聞きしてしまった直後、ラパンで起こった事件の――。
私の視界はみるみる滲み、コンクリートには丸い染みが一つ増えた。この小さな東屋は、かつて伊藤が私を慰めてくれた場所だった。過去に足を取られ、何もかもうまく行かないと泣く私にココアを差し出し、そのすべてを聞いてくれた場所だった。『でも、死んだのは妹で、君じゃないじゃん』と、あのとき伊藤はそう言ってくれたのだった。『俺なんかあれだよ、高校のとき、交通事故で腕がポッキリいったんだから。しかも利き手』と自慢げに。
そうして伊藤は、私が二度と戻れないと思っていた日和見菌たちの世界へ、簡単に招き入れてくれたのだった。だから私は彼といることができたのだった。自分こそ特別だと信じて疑わない彼の隣にいれば、私は
あの日、ラパンの休憩室で、両親の会話を盗み聞きしてしまった私は泣いていた。二十五年経ったいまも、家族はばらばらのままだということを目の当たりにして、悲しむことしかできなかったのだ。手嶋が――あのお節介なアニメオタクが現れたのはそのときだった。泣いている私を見るなり、彼はいつものあのお節介癖で、『どうしたの、店長と何かあった?』と尋ねてきた。
『来ないで、放っておいて』。私はそう言って拒否したが、彼は立ち去るどころか、真面目な顔をして私の向かいに座った。そして、『シャルルの呪文の意味って知ってる?』と、突然、何の関係もないことを話し出した。『有名かもしれないけど、あれって英語なんだよ。オル・フォル・ギュネス(all for goodness)、すべては善いことのためになされるべきだっていう意味なんだって』と。
『あっちへ行ってって言ってるでしょ』、あのとき私はそう叫ぶべきだった。彼のためにも、そうするべきだった。けれどそうしなかったのは、そのときの私はあまりに悲しく、そうする気力もなかったからだ。聞いているふりさえしない私に、手嶋が話し続けたからだ。けれど、その一番の理由は、迷惑なはずのその話を聞いているうちに、なぜか不思議な気分に陥ったからだった。ずっとずっと遠い昔、聞きそびれた懐かしい物語の続きを、いまになって聞いているかのような――。
伊藤がドアを開けたのはそのときだった。私と向かい合わせに座った手嶋との距離は、決して近くはなかった。けれど、彼はそこに自分の入ることのできない親密な空気を感じ取ったのだろう。そして、怒りに我を忘れた。
『てめえ、俺の女に何しやがる!』
伊藤はそんなようなことを言って殴りかかった。口喧嘩さえしたこともなさそうな手嶋は、驚くほど簡単に床に倒れ――頭から血を流して動かなくなった。
『きゅ、救急車を呼ばないと』
ようやく私が呟いたのと、ことの重大さに気づいた伊藤が休憩室から飛び出していったのは、ほぼ同時だった。『殺してしまったと思って逃げた』と、アパートに戻ったところを逮捕された伊藤は、警察の取り調べにそう供述したらしい。よほど打ち所が悪かったのだろう、手嶋は意識不明の状態だった。その夕方、伊藤の名前は過失傷害の容疑者としてニュースに流れた。その肩書きが「元・会社員」となっていたのは、事件を知ったラパン本部が、すぐさま彼の首を切ったからだろう。私は警察で彼を待ったが、彼は身元引き受け人に母親を指名した。帰ったほうがいいと警官に勧められ、私は二人のアパートへ戻った。しばらくぼんやりしたあと、彼の身の周りのものをバッグに詰めようと思い立ったが、母親と実家に帰るのならそれも必要ないだろうと、再びぼんやりと座り込んだ。
時計の針は真夜中過ぎを指していた。私は明日のために少しでも眠って、手嶋の見舞いに行かなくてはならない。すでに新しい店長がいるラパンに出勤して事情を説明しなければならない。そうしながら何とかして伊藤と連絡を取り、これから私たちはどうなるのか、尋ねなければならない。そして、その返答次第では、この一人には広すぎるアパートは引っ越さなくてはならないし、新しい仕事を見つけなくてはならないし、何よりもこのお腹に宿った命をどうするのか、決めなくてはならない。産んで一人で育てるのか、それとも――。
そこまで考えて、私は八つ当たりをするように握りこぶしを床に叩きつけた。この命をどうするか決めなくてはならない? 嘘だ。そんなことは初めから決まっている。いや、決められてしまっている。妹が殺され、家族が離散し、私の父が人殺しを企てているその上で、伊藤もまた人殺しになろうとしている。そんな状況で産むなどという選択肢を選べるはずがない――。
事件の翌日、私は結局、手嶋の見舞いに行かなかった。ラパンにも出勤しなかった。そうして何もかも放棄して、この東屋で座っていた。考えても仕方のないことばかりを、ぐるぐると考え続けていた。あれから一週間、それが私のしているすべてだった。日に日にお腹の中で大きくなる命の存在に怯えながら。
また一つ、新しい染みがコンクリートに吸い込まれていき、私は鼻を啜りあげた。子供の声が賑やかに響き渡る公園で、過去から現在に戻った私は下腹をなぞり、今度は未来の想像をした。堕胎のために産婦人科へ行く自分を。バイトで貯めた全財産を財布に詰め込み、待合室の隅で順番を待つ自分を。
夫婦なのだろうか、嬉しそうにささやきを交す男女をぼんやりと見ていると、梶田さん、せかせかした看護婦が私を呼び、汚いクリーム色のカーテンを開ける。そこには男の医者がいる。どうされました、気の無いふうに尋ねる。堕ろしたいんです、私は言う。けれど、その声はあまりに小さいため、医者の耳には届かない。赤ちゃんを堕ろしたいんです、聞き返された私は勇気を振り絞って、もう一度言う。育てられる自信がないので、と今度は言い訳を付け加えることも忘れずに。
すると、私は白いベッドに寝かされていて、その私を手術着を着た医者が覗き込んでいる。手術は無事終わりましたよ、医者が言う。このまましばらく安静にしていてくださいね、と言って去っていく。白い部屋に、私は一人取り残される。赤ちゃんはいなくなってしまった、私は考える。私の赤ちゃんは死んでしまったのだ、と。
いつもならば、想像はここで終わりだった。そして、私の思考は再び最初に戻る。公園の子供たちを眺め、どうして私の赤ちゃんにはあんな未来がないのだろうと考え、過去の記憶を辿りだす――。
しかし、何日も同じ場所に座り、同じ想像をし続けたせいだろうか。そのときふと、私の思考は道を逸れた。不快な痛みを感じたように、私は小さく顔をしかめた。赤ちゃんは
――けれど、それは
すると、胸に新しく、ささやかな疑問が生まれた。それは母親の私? それとも父親である伊藤だろうか? いや、それが
私はしばらく思考を巡らせた末、もしこれがお父さんだったら、と思った。もし、ここに父がいたら。真紀のために村野正臣を殺すと言い切った父がいたなら、あの人は殺された赤ちゃんのため、誰に復讐してやると言うだろうか。誰の心臓にナイフを突き立てることを選ぶのだろうか。
ぼんやりと考えているうちに、あの無機質な法廷の風景が私の目の前に広がった。二十五年前、何度も通った裁判所。あのときの光景のままに、検察官と弁護人が左右に分かれ、傍聴席は大勢の傍聴人で埋まっている。その後ろには、騒ぎがあったときのための廷吏が二名、休めの姿勢で立っている。二十五年前と何か違いがあるとすれば、それは裁判長席と被告人席で、裁判長席に座った父は木槌の代わりにギラギラ光る包丁を手にしていて、被告人席のあるべき場所にはその包丁を突き刺すときに暴れないようにか、拘束具のついた木台が据えられている。そして、その木台の前には四人の人間が横一列に並んでいた。四人とはもちろん、私と伊藤、それから顔も知らない医者と看護師だ。どうやらこの中から罪を負うべき一人を選び出そうということらしい。
『静粛に』
そのとき裁判長席の父が、木槌代わりの包丁を振りかざし、口を開いた。
『さて、ここに集った全員が知っての通り、この度、一つの小さな命が奪われた。梶田由紀のお腹に宿っていた赤ん坊だ。赤ん坊と言えど、命は命。その命は、奪った者の命によって償われなければならない。そこで、本法廷は彼を――いや、まだ彼か彼女かさえ分からなかったその赤ん坊を殺したのは
すると早速、厳しい顔をした検察官が立ち上がり、口を開いた。
『赤ん坊殺しの犯人は、その母親であると言っていいでしょう。ついては、死罪に値するのは梶田由紀に違いありません』
私を指差し、断言する。
『なぜなら、母親である彼女の同意なしに堕胎は行われない。赤ん坊を殺す決断をしたのは、彼女です。その決断が赤ん坊を殺したのですから』
そうだそうだ――傍聴席から声が上がった。その大勢でありながら足並みの揃った声に思わず振り返り、よく見ると、そこに詰めかけていたのは個を持った人間ではなく、大勢がくっついて一つの塊になったような日和見菌たちだった。彼らは当事者と部外者を隔てる安全な仕切りの向こう側から、私たち四人の中から一体誰が選ばれるのか、心から楽しそうに見守っているのであった。
『いえ、死罪がふさわしいのは梶田由紀ではなく、父親の伊藤雅人でしょう』
傍聴席に気を取られていると、そのとき別の検察官が立ち上がった。
『梶田由紀は、何も一人で赤ん坊を作ったわけではない。そこには父親――伊藤雅人の存在があるわけです。けれど、彼は暴力事件を起こした。手嶋という男を殴って、過失傷害で逮捕されたのです。それだけではない、 梶田由紀は彼に何度も殴られています。そんな人間が父親として相応しいか? 答えは否です。もし、無事に生まれたとしても、その暴力は結局赤ん坊を殺すかもしれない。梶田由紀は、伊藤雅人のせいで、泣く泣く赤ん坊を諦めざるを得なかったのです』
力強い説明に、傍聴席から、なるほどという声が漏れる。
『異議あり!』
しかし、そのざわめきを断ち切るかのように、また別の検察官が大声を上げた。彼はこれまでの発言がまったく理解できないとでもいうように、肩をすくめて法廷を見回した。一つ咳払いをしてから、口を開く。
『みなさん、これが赤ん坊殺しの裁判だということを忘れてはいませんか? ならば、殺したのは誰か。そう考えれば、罪を負うべき人物は明白です』
彼は医者を指差した。
『そう、他でもない彼の手こそが、幼い命を摘んだのです。つまり、彼こそが死罪にふさわしいのではないでしょうか』
裁判長席の父が、鋭い眼光で医者を見る。その視線に満足したように、検察官は付け足した。
『また、ここに私は看護師の罪も追求しましょう。なにせ、彼女は医者が赤ん坊を殺す手伝いをしたのですからね』
『そんな馬鹿な話はない!』
すると、たまりかねたように弁護人が声を上げた。
『堕胎は法律で認められていて、医者や看護師はその法律で守られている! 頼まれて堕胎する医者を人殺し呼ばわりするなんて、そんなことがあってたまるか!』
『それに付け加えるなら、そもそも生まれていない赤ん坊は法律上、人間とはみなされません。人権も何もない。だから中絶が可能なのです』
隣の弁護人が冷静に頷く。しかし、裁判長席の父は納得するどころか、カッと眼を見開き、その弁護人を憎悪の目つきで睨みつけた。
『ということは、その法律に赤ん坊を殺しの罪があるということか』
父が舐めるようにそこにいる全員を見回す。その低い声は、地響きのように法廷を揺るがした。
『いいか、もう一度周知しておく。
『いや、しかし――』
弁護人たちは何か言いかけたが、父の手に光る包丁を見て、それを諦めたようだった。被告席を争う四人の列に「法律」が加わり、私たちは五人になった。それを見て、ふと別の検察官が口を開いた。
『しかし法律にも罪を認めるということになると、社会制度にも罪を認めざるを得ないのではないでしょうか? 例えば、福祉のことですが……』
検察官は考え込むように続けた。
『例えば、梶田由紀が暴力的な夫に頼らず、シングルマザーとして赤ん坊を出産したとして、それでも生活が十分に保障されるような制度があったなら、赤ん坊は殺されずに済んだかもしれません。そう考えると、私たちは現在の福祉制度に死を与え、より手厚い福祉を生み出すべきでは――』
『それにつきまして、傍聴席のみなさんの意見を代弁しますと』
検察官の話を遮って、また別の検察官が大きな声を出した。ちら、と傍聴席の日和見菌たちを見やる。つられてそちらに目をやると、いままで身を乗り出して目を輝かせていた彼らは、気まずそうにあらぬほうを向いていた。
検察官は歯切れ悪く続けた。
『えー、社会福祉というものは、本当に最後の最後の手段であって、自己解決できる可能性のある人間が、簡単に利用するというのは甘えでしかないでしょう。ここにいるみなさんもそれぞれの事情を抱えていらっしゃいますが、努力していまの生活を築き上げ、血税を払う側へ回っているわけです。ですから、梶田由紀に関しましても、まずは福祉を頼らず、自分で努力してみることが大切であって……もしそれでも立ち行かないというのならば、次善の策として身近な人が支えるべきじゃないでしょうかというのが、私もでありますが、みなさんの意見であると思いますが――この場合、それは母親の梶田美希子です』
検察官が誰かを紹介するように右手を差し出す。すると、その隣にはいつのまにか年老いた母の姿があった。彼に促され、母も死罪候補の列に加わる。その姿を目で追いながら、検察官は続けた。
『もし、彼女が娘を突き放さず、その出産や育児を手助けできる関係であったなら、梶田由紀は赤ん坊を産むことができたでしょう。ということは、そういう環境をつくらなかった母親にも、赤ん坊殺しの責任があるに違いありません』
『梶田美希子に責任があるというのなら――』
すると、思わずといったように検察官の一人が立ち上がった。小さく息を吸い、覚悟を決めるようにして、一段高い場所にいる裁判長を――父を見上げる。
『彼女よりも大きな罪を持つ人間を、私はここに糾弾しましょう。それは、あなたです――雨ヶ谷洋介裁判長』
突然の糾弾に、父はぴくりと眉を上げた。無言のまま、先を促す。検察官は続けた。
『ここにおります裁判長――いえ、梶田由紀の実父・雨ヶ谷洋介は、二十五年前、由紀の妹であるもう一人の娘、真紀を殺害された恨みを晴らすため、なんと仮釈放された加害者を殺害する計画を企てています。いいですか、この男は人殺しを――殺人を企てているのです。先ほど、伊藤雅人の過失傷害の話が出ましたが、どちらの罪が重いのかは明白でしょう。伊藤が暴行犯なら、雨ヶ谷洋介は完全なる殺人犯です。赤ん坊はその孫となるのです。生まれてくる子供に「殺人犯の孫」という足枷をつけたくない、そんな梶田由紀の思いは理解できます』
『しかし、伊藤雅人はすでに罪を犯しましたが、雨ヶ谷洋介の犯行はまだ行われていません。そう考えると――』
弁護人の指摘に、検察官は首を振る。
『いいえ、彼は必ずやり遂げます。ですから、これは既成事実と同等であると言っていいかと』
『検察官の意見を認める。雨ヶ谷洋介は直ちに被告の列に加わるように』
厳かな声に裁判長席を見上げると、そこにはいつのまにか別の裁判長が現れていて、居場所を失った父はその命令通り、しかし不服そうに段を降り、私たちのほうへと歩いてきた。
『……しかし、そうすると、また新たな被告が増えるということにはなりませんかね』
その歩みを待つ間、考え込むように検察官が呟いた。
『村野正臣ですよ。そもそも彼が雨ヶ谷真紀を殺さなければ、雨ヶ谷洋介も殺人を考えることはなかったはずです。また、それだけじゃない。彼は妻の梶田美希子とも離婚せず、そうなると梶田由紀は至極普通の家庭で育ったことが想像されます。そうすると、ですよ? 彼女は就職した会社できちんと働くことができ、そうなれば伊藤雅人のような暴力男と付き合うこともなく――』
『いや、それは単に男の趣味が悪いだけでしょ』
弁護人の皮肉に、どっと傍聴席が湧いた。一度は法廷から目を逸らした日和見菌たちが体を揺すり、笑っている。殺人事件に同情した次の瞬間には、パンダの赤ちゃんが可愛いと歓声を上げ、芸能人の結婚に一喜一憂する彼らにとっては、この法廷すら他人事であり、対岸の火事なのだ。その楽しげな様子に、違う――私は無性に苛立ちを覚えて叫んだ。
『違う! 私たちは悪くない!』
『被告人は静粛に』
裁判長が木槌を鳴らした。騒ぐと罪が増えますよ、弁護人が目顔で合図してくる。けれど、私は止まらなかった。二十五年分の怒りが体中を駆け巡り、その怒りは日和見菌たちに向けた
『赤ちゃんが殺されたのは私たちのせい? 違う、私の赤ちゃんが殺されたのは、あなたたちのせいだ。あなたたちが私を異物扱いして、仲間外れにしたせいだ。あの子が妹を殺された子だと、可哀想な子だと、こそこそ噂したからだ。そしてこれからも同じことを――いいえ、もっとひどいことを生まれてくる赤ちゃんにもするだろうと、簡単に想像がつくからだ。殺人犯の孫、暴行犯の子と
声が割れるほど滅茶苦茶に叫ぶと、法廷はしんと静まり返った。私の思いは彼らに届いたのだろうか、そう思ってしてしまうほどに。けれど、やはりそれは錯覚であったらしい。
『おや。ということは、またまた被告人が増えたということですかねえ。とはいえ、不特定多数の人たちに罪を――ましてや死罪を突きつけることなど、まったくもって不可能なことですが』
馬鹿馬鹿しいと言わんばかりに、肩をすくめて裁判長は笑った。すると、その仕草にほっとした日和見菌たちも同じように声を立てて笑った。明るく楽しげな雰囲気が法廷に満ち、私の怒りは急速にしぼんだ。
裁判長の指摘は現実的だった。もし、私の糾弾が正しく、彼らに罪があったのだとしても、彼の言う通り、その罪は不特定多数の人々によってほとんど透明なまでに薄まり、それを全員に償わせることなど不可能だった。
そう考えて、私はふと息を止めた。赤ん坊殺しの罪。その命を命で償うために集められた、私たち被告人の列。この列に並んだ
けれど――私は考えを巡らせた。彼らは私たちの罪状を読み上げた。しかし、そのどれもが決め手に欠けるものだった。だからこそ、被告人の列は次第に長くなり、しまいには不特定多数の人間まで巻き込んだのだ。
つまり、私たち一人一人が抱える罪は、どれ一つとして完全ではなかった。それは例えるなら、被告人全員がそれぞれ同じパズルのピースを持っているようなもので、けれど、赤ん坊殺しの絵を完成させるためには、その全てのピースを――私や伊藤、医者、看護師、父に母、村野正臣、さらに言うならば法律に社会福祉制度、誰であるかさえ分からない日和見菌たち、そしてもしかしたら二十五年前に殺されてしまった真紀さえ持っているかもしれないピースを一つ残らずかき集める必要があった。そうしなければ、パズルは――赤ん坊殺しの罪は完成しないのだ。命を命で償うというほどの完全な罪は、誰か一人の罪では成立しないのだ。
しかし、だというのに、その罪は
『さて、そろそろ結論を出さなければ』
再び静まった法廷を、裁判長が感情のない目でぐるりと見渡した。被告人たちの長い列を端から端までゆっくりと眺める。そして、おもむろに問うた。
『さあ、この中で一体、
いつのまにか、彼は父の持っていたはずの包丁を手にしていた。私たちの中の誰かに、ぎらぎらと光るその刃は振り上げられる。振り下ろされる。誰かの心臓に突き刺さり、彼に裁きの死を与える。
「いやあああああ!」
次の瞬間、断末魔のような声が響き、私ははっと我に返った。気がつくと私がいるのは法廷ではなく、うさぎの公園の東屋だった。
「ほら、次はお友達の番でしょう」
――私の赤ちゃんを殺すのは、
しばらくして、ようやく気持ちを落ち着けると、私はそっと下腹に手を当てた。赤ん坊殺しの裁判。あれはただの妄想だ。現実じゃない。このお腹に宿った命を生かすも殺すも、実際には私の決断次第だ。それは私の罪であり、それを人のせいにするなんて、そんなことをしてはいけない。
私は自分にそう言い聞かせた。しかし、一度生まれてしまった疑問は、すぐに胸を去ってはくれなかった。
この子を殺すのは、私の決断だ。ならば、罪があるのはその決断をした私だろう。けれど――私は慎重に問いかけた。その決断は、本当に私だけのものなのだろうか? 他の誰も関わることのない、純粋な私個人の考えなのだろうか。
いや、それは絶対に違う――自分の問いを、私は自分で否定した。なぜなら、私はこの子を殺したいだなんて思ってはいなかった。そうではなく、暴行事件を起こした伊藤がこの子の父親だから、殺人を犯そうとしている私の父がこの子の祖父だから、私ではなく妹を殺した犯人を愛するのがこの子の祖母だから、そして何より妹を殺された私は
それは私の決断であり、同時に私の決断ではなかった。なぜなら、私は数ある選択肢の中からそれを選んだわけではなかった。元々はたくさんあったかもしれない選択肢は
東屋の中には、重だるい熱を含んだ空気が充満していた。張り詰めた息を吐き、私は一度目を閉じた。そんなことは考えても仕方がないと言い聞かせた。第一、私は赤ちゃんをどうするか、まだ決めていない。よしんば殺すという決断を下したとしても、あんな裁判が開かれることは絶対にない。堕胎は法律で許可されている。医者も看護師も私も伊藤も、死刑どころか、そもそも罪に問われることがないのだ――殺人という罪を犯した村野正臣と違って。
村野正臣。ふとこぼれ落ちてきたようなその名前に、私はどきりとした。けれど、すぐにそれも当然だと思い直した。裁判に法廷、死刑という罪――それらはすべて村野のせいで私の人生にもたらされたものだった。彼さえいなければ、私はそんなものなど知らずにいられたのだ。日和見菌たちと一緒になって笑っていられたのだ。あの検察官が言ったように、伊藤と付き合うこともなかったかもしれない。
ならば――奥歯を噛み締め、私は思った。やはり、罪に問われるべきは彼ではないか。すべては彼が――村野正臣が真紀を殺したことから始まったのだ。彼が私たち家族をばらばらに壊したことで、それから先の未来は狂った。私の赤ちゃんまで殺さなければならない状況に追い込まれたのは、そのせいだ。だから、赤ん坊殺しで死罪に問われるべきは彼だ。彼が諸悪の根源だ。シャルルにおける悪の大王ジャークだ。彼が生きている限り、不幸は止まらない。ということは、その諸悪の根源を倒してしまえば、世界には平和が訪れるということだ。だから、あのとき私たちは村野正臣を死刑にするべきだったのだ。
興奮に、血が激流のように体中を駆け巡り、ぎゅっと
目には目を、そう言って命で命を償わせるためには、その人間だけにすべての罪が集約しているという証が必要なのではないのか――痛みは、改めてそう訴えているようであった。
そして、その問いはその先にある考えたくもない問題までもを、真っ直ぐ私に問いかけた。
それは私たちが望むほどに――例えば死刑がふさわしいと
「……そんなこと、考えたくない」
信じていたものを根底から覆してしまいそうな大きな力に怯え、私はわざと声に出してそう言った。
「私が考える必要もないし、いまさら何も考えたくない」
一語一語区切るように、はっきりと私は言った。他に誰もいないこの東屋で、独り言に異議を唱える人など誰もいなかった。にも関わらず、反論を聞くまいとするように、私は両手で耳を塞いだ。そして「全部、村野正臣のせいだ」と呟いた。何度も何度も、念仏を唱えるように呟いた。けれど、私の意識とは別の何かは、その先を考えることをやめなかった。
伊藤が暴行事件を起こし、母は頼れず、父は殺人犯になろうとしていて、だから私は赤ちゃんを殺すことを決断する。そこには殺してくれる医者や看護師がいて、それを許可する法律があって、逆に私と赤ちゃんが生きていくのに十分な支援はないから。人の目は冷たく、私たちは異物として肩身狭く暮らしていくしかないだろうと思うから。
けれど――本当に考えたくもないことだけれど、同じような事情が村野正臣にもあったとしたら。彼に殺人を犯すという選択肢しか残さなかった
もうやめて、聞きたくない――目を閉じ、子供のように叫ぶ私を押しのけ、思考は続いた。
例えば、伊藤が暴力を振るう理由――いや、
『俺、前はこんなんじゃなかったんだよ』
頭を抱えるようにして、伊藤は言った。
『前はこんなことなかったんだ。人を殴ったことなんかなかった。ホントなんだ。それなのに、あれからダメなんだ。自分が抑えられなくて、頭が真っ白になって、気がついたらこうやって……』
彼は子供のように泣き崩れた。そうしながらも、さっき私を殴った手で、私を撫でた。その触れ方はとても優しく、前っていつのことなの――掠れた声で私は聞き返した。
『あの事故の前だよ。利き腕ポッキリいく前。あの事故で俺の脳みそがイカれちまったんだ。それまではこんなことなかったんだ。それなのにこんなことになって、俺は家族からだって見放されて……』
伊藤はさらに泣いた。初めての告白に驚きながらも、痛む身体を起こし、私は彼に寄り添った。
交通事故の後遺症で人が変わったようになってしまった――そんな人の話を、いつだか私はテレビで見たことがあった。『あなたの脳が犯罪を犯す』――それはある種オカルトのような、にわかには信じられない話ばかりが詰め込まれた番組だった。犯罪者の脳には異常があり、だから犯罪者は罪悪感もなく犯罪を犯し続けるのだとか、人間の一生はあらかじめ遺伝子によって決められていて、それ以外の人生は歩めないのだとか。
その中の話の一つに、交通事故で脳に障害が生まれ、怒りが制御できなくなった人のものがあった。以前は穏やかだったその人が、事故をきっかけに怒りっぽくなり、最後には家族全員を惨殺してしまうという、それはそんな衝撃的なストーリーだった。
もし、伊藤の言うことが本当なら。そしてあのテレビ番組の話が本当だったなら。彼が暴力を振るってしまうのは仕方がないことに思えた。だって、
それから少し考え――もしもそれが本当でなかったとしても、例えば伊藤が嘘をついていたとしても、それは同じことだと私は思った。どうにせよ、彼は
もしかしたら、村野正臣も伊藤と同じではないか。いままで自分のいる場所とはまったく別の場所に位置づけていた「殺人犯」の彼に、私は小さく歩み寄った。
法廷で明かされることのなかった彼の事情を、私たちは知ることができなかった。けれど、彼にもまた
例えば、それは村野を虐待した母親。彼女が村野を
それから、彼が少年のときに補導されていたという話。そのとき、関わった警察や周りの人々が適切な指導ができていれば、彼は真紀を殺さなかったかもしれない。あのテレビで見た、脳みその話だってそうだ。もしかしたら、村野の脳にはもともと障害があったのかもしれない。伊藤のように、彼もまた交通事故に遭ったことがあるのかもしれない。その場合、罪はその障害を発見できなかった誰かに、また彼を
赤ちゃんが殺される理由として、私が最後には不特定多数の日和見菌たちを責めたように、村野が殺人を犯した理由も、突き詰めていけば遠い他人に行き当たった。彼を中心として、円状に広がった罪は、その遠い他人の場所まで来れば――円の一番外側まで辿り着いた頃には、限りなく透明に見えた。けれど、それは透明に見えるだけで、まったく何の罪もないわけではないようにも思えた。
例えば、私はそこに殺される直前に真紀を見たという、近所のおばさんの姿を見た。男がついていくのを見たという、カメラ屋のおじさんを見た。そして、私たちの姿を見た――パートのために私たちを鍵っ子にした母を、それを許可した父を、あの日に限って一緒に下校しなかった私を、危険に気づくことのできなかった真紀本人の姿さえ見た。もちろん、それらの行動は真紀を直接殺すことはなかったし、後悔しても仕方のない、偶然の行動ではある。けれど、真紀が殺されたという結果から振り返れば、私たちは村野の殺人にほんの僅か、加担したことになってしまうのだった。
そこに責任があるとは言えないような、ましてや罪とも言えないような、そんな取るに足らない行動の積み重ね。誰に所属しているとも言えない、けれど殺人という罪を構成する、私たちはパズルのピースを手にしていた。それはもちろん私たちだけではない。村野の両親やその周りの人々、社会や法律や彼の脳みそ、そして村野自身もまた、その数に差こそあれど、同じパズルのピースを持っていた。
もちろん、そのピースを一番多く持っている村野は、何らかの罰を与えられてしかるべきだろう。けれど罪というものは、そのすべてのピースが持ち寄られて完成を見るものだった。とすれば、彼の持つピースだけで罪が完成しない以上、その刑罰が彼という人間を根本的に成立させているもの――その命を奪うのは間違っているのではないだろうか。殺人という罪に参加した、たくさんの人々の代表として、村野が死ぬことは正しいことなのだろうか。それは一般に生贄と呼ばれるものなのではないだろうか。その罪を
私は固く閉じたまぶたを開け、耳を塞いでいた手をのろのろと膝へ戻した。意思とは裏腹にたどり着いたその結論を、私はとても正しいと思った。けれど同時に、そんな考えはとても間違っているとも感じ、どうして私がこんなことを考えなければならないのかという強い怒りを感じた。
妹が殺され、お腹の赤ちゃんまでも殺されようとしている私は正真正銘の被害者で、そこに疑いが挟まれる余地などあってはならなかった。被害者は怒りのままに加害者を憎むことができるはずで、だというのに、その加害者にも実は被害者の一面があるかもしれないだなんて、そんな訳の分からない擁護は耳に入れたくもないものだった。
けれど、一方で私がこんなことを考え続けるのは、伊藤のせいもあるのだろう。手嶋が死んでしまえば、伊藤は殺人犯になってしまう。伊藤が暴力を振るうのは、大昔に起きた交通事故のせいかもしれないのに、それなのに車のドライバーが罪に問われることは絶対にない。あるいは、その暴力を知っていながら放置した彼の家族や、私のせいであるかもしれないのに、私たちの罪もまた、決して問われることがない。それどころか、私たちが暴力を受けていたことが知れれば、その罪は彼の「前科」として加算されてしまうことだろう。そうして膨れ上がったその罪を、伊藤はたった一人で負うことになるのだ。
この世には、生きている人の分だけ事情がある。目に見えるものから、見えないもの、容易く想像できるものから、想像すら難しいものまで――。私たちは関わる人のすべてを知ることはできない。そういう意味で言えば、私も誰かにとっての日和見菌だった。限りなく透明な罪の中で、円の一番外側で、知らん顔で生き続けるたくさんの日和見菌のうちの、私はその中の一人に違いないのだった。
私はそんな自分を嫌悪した。あのぬるま湯のような日和見菌たちの世界へ戻りたいと、ずっとそう願っていたはずだというのに、いまの私はその逆だった。例えその罪の一番外側であったとしても、私は誰かの罪に属していたくはないし、そこにいることを良しとすることができなかった。私は人と関わっていたかった。けれど、そうすることで誰かの罪に属すことになってしまうのは嫌だった。
しかし、それならどうすればいいのだろう――私はうなだれた。どうしたら、私は罪なく生きることができるのだろう。それとも、そもそもそんな風に生きるだなんて、無理な話なのだろうか。
子供はまだ泣き続けていた。泣き止まない子供を見かねて、別の子がブランコを降り、その子に譲った。しかし、その子はまだ泣き止まなかった。まるでここで折れたら負けだとでもいうように、傷ついた私にはこれほど泣き喚く権利があるのだというように。だから、泣き続ける彼女には見えていないようだった。そこにブランコを譲ってくれた子がいることを、傍らで母親が慰めてくれていることを。それとも、すべて分かった上で、彼女は意地になって泣き続けているのだろうか。
真紀にも意地っ張りなところがあったな――その泣き声を聞くうちに、私はふと思い出した。たった六歳で死んでしまった、私の妹。いま振り返れば、私の人生の中で、彼女と過ごした時間はあまりにも少なかった。生きていたら、どんな大人に成長したのか、私との仲はどうだったのか、意地っ張りな性格は直ったのか――古びて文字も薄くなってしまった記憶のページをめくるように、私は過去に思いを馳せた。シャルル役を争ったこと、家の中でローラースケートをして怒られたこと、二人で一緒に下校したこと、私の嫌いなピーマンと真紀が嫌いだったトマトを内緒でこっそり交換したこと、うさぎの公園で遊んだこと、そしてあの日の喧嘩のこと――。
――シャルルの呪文の意味って知ってる?
そのとき、なぜだろう、不意に手嶋の言葉が蘇った。
――有名かもしれないけど、あれって英語なんだよ。オル・フォル・ギュネス(all for goodness)、すべては善いことのためになされるべきだっていう意味なんだって。
あのときもそうだったように、なんだか不思議な気持ちが込み上げた。日々のお節介に迷惑しているというのに、その手嶋が「善いこと」などと言い出したからだろうか? いや、違う。引っかかったのは手嶋のことじゃなくて、もっと誰か別の――。
――あのジュモンの意味、知ってる?
そのときだった。脳裏に鮮やかな色が弾けるように、幼い声が蘇った。
――あれ、エイゴなんだって。お姉ちゃん、知らなかったでしょ。
得意げなその声は、真紀の声だった。あのとき――真紀が殺される直前、一緒に帰り道を歩いていたときの声。そうだ、それが私たちの喧嘩の原因だった――私は思わず胸に手を当てた。あの日の放課後に一体何があったのか、記憶がみるみる蘇った。
あの日、いつもの待ち合わせ場所の校門。そこに駆け寄ってきた真紀は、友達にシャルルの呪文の意味を教えてもらったと、得意げに話してきたのだった。
『え、どういう意味なの?』
勢い込んで聞いた私に、
『教えてほしい?』
真紀はにんまりと笑った。いまでこそ想像がつくが、姉の私が知らないことを知っているということが、真紀はよほど嬉しかったのだと思う。教えてよと言う私に、真紀はいつまでももったいぶって、ちっとも教えてくれなかった。
『ねえ、いいから早く教えてよ』
『えー、どうしよっかなあ』
『いいから早く』
『うーん、あと地球が百周まわったらね』
『バカなこと言ってないで、早く教えて』
『あ、やっぱあと百億周!』
『もう、真紀!』
教えてよ、教えない――問答は次第に激しくなった。そうするうちに、あのブランコの子のように、真紀も意固地になったのだと思う。もうお姉ちゃんには教えてあげないと言い出した。泣いて頼んだって、絶対に教えてあげないと言い張った。
大人になったいまなら、そんな真紀をなだめすかし、うまく聞き出すことができるだろう。喧嘩などせずにいられただろう。けれど、あのとき私は子供だった。真紀のお姉さんではあったけれど、まだ小学生のお姉さんだった。だから、私は言ったのだ。『じゃあ、バイバイ』と。意地悪な顔で、『真紀のことなんか、もう知らないから』と。
姉の私にそう言われた真紀は、むっと口をへの字に曲げた。けれど、それも一瞬だった。
『バイバイ』
そう言うと、真紀はあっかんべーをして駆けていった。
『もう一生、お姉ちゃんには教えてあげないからね』
と、そんな捨て台詞を残して。
その言葉が現実となるだなんて、誰が予想しただろう。けれど、それは現実になった。私と別れた後、真紀は村野に殺されてしまった。だから、シャルルの呪文の意味は本当に分からないままになってしまった。真紀とともに葬り去られてしまった。
いや、そんなことはどうでもよかったのだ。私は頭を振った。善いことをしろだか、善いことのためにだか知らないけれど、そんなのは本当にどうでもいいことだった。そんなことは一生知らなくてもいいから、私は真紀が死んでほしくなんてなかった。喧嘩ばかりの姉妹だったとしても、それでも生きていてほしかった。
「……真紀、どうして死んじゃったの」
呟くと、私の目から涙がこぼれた。それはもしかしたら、真紀のためだけに私が流した、初めての涙かもしれなかった。
うさぎの公園に、私の嗚咽が小さく響いた。あたりの静けさに気がつけば、遊んでいた親子連れはひと組、またひと組と、元来た道を引き返していた。泣き疲れた顔を上げると、真上にあった太陽は傾き、東屋には赤い夕日が差し込み始めていた。
そういえばあの後も、手嶋は何か言ってたっけ――しばらくして涙が落ち着いたとき、私はぼんやりと思い出した。すべては善いことのためになされるべきだという、あの呪文の意味を解説した後、手嶋は続けて何かを言っていた。アニメの世界が何だとか、そこが好きなんだとか何とか――。
――お節介って思われてるかもしれないけど、だから僕はこうやって梶田さんとも話そうと思ってるんだよ。
ああ、そうだ――私は思い出した。あっちへ行けと拒絶されてもお節介を焼く理由を、彼は泣き続ける私に話したのだった。
――いつも店長に言われるけど、アニメって確かにクソだよね。
彼は自虐するようにそう言った。
――努力して、努力して頑張れば、すべてはうまくいく。仲間に裏切られても、その仲間を信じて、最後にはその気持ちで悪に打ち勝つ。でも現実はそうじゃない。理不尽なことなんかいっぱいある。努力なんか報われないし、頑張っても自分の力じゃどうにもならないことなんか当たり前だし。でも、それなのにアニメは勧善懲悪の単純な世界を描き続ける。人を馬鹿にしてんのかって、実は僕も思ってたんだ。でも、繰り返し見るうちに……こうも思うようになった。そういう世界って羨ましいなって。梶田さんはそう思わない?
手嶋はこちらを窺うように見た。私はそれを知りながら顔を上げようともしなかった。しかし、彼は優しく続けた。
――もしかしたら、そう思わない人もいるのかもしれないけど……僕はそう思ったんだよ。現実もこんな世界だったらいいのになって。それからさらに見るうちに、今度はこう思うようになった。アニメをつくる人たちも、そう思いながらつくったんじゃないかって。現実もそういう世界であるべきだと思ったからこそ、アニメの中に善い世界を、
手嶋の言葉に、私はそのとき顔を上げた。いいもん――その子供じみた表現は、耳に妙に懐かしかった。私が興味を持ったことが嬉しかったのか、手嶋も笑顔になった。ただでさえ小太りの丸い顔が、月のようにまんまるになった。優しい口調には、ほんの少し、熱がこもった。
――僕、思うんだよ。
私が手嶋の言葉に耳を傾け出したそのとき、伊藤の怒声が休憩室に響いた。私はそのあとのことを繰り返し思い出そうとして――止めた。代わりに、病院のベッドの上で眠っているはずの手嶋のことを考えた。意識不明で、いつ死んでしまうかもわからない彼のことを思った。
手嶋はバカだ――最初に浮かんだのはそんな言葉だった。確かにアニメの主人公なら、目の前で泣いている人に知らんぷりなんてしない。その人を慰め、最後には一緒に笑っているだろう。それがアニメの描く理想だ。「善いこと」だ。けれど、現実はどうだ。手嶋の「善行」は、その彼を病院送りにしただけだった。それで世界が善いほうへ変わった? そんなはずないだろう。伊藤は警察に捕まり、私はここで堕胎をしようと思いつめているのだ。それが手嶋の言う「善い世界」か? どう考えたって、そんなはずはない。
それなら、あのとき手嶋はどうすればよかったのか。私はそうも考えた。けれど、そんなことは分かりきっていた。彼は、あのとき私に声を掛けるべきではなかった。私にお節介など焼かなければ、いま、彼は意識不明になどなっていないのだから。
――シャルルのように、世界を善い方向へ変えていきたいと思ってるから。
しかし、一度思い出してしまった手嶋の声は、耳の奥から離れなかった。世の中の人間には、その人間の数だけ事情があると、私はついさっき、そう考えたばかりだった。手嶋は善いことをしたいと願った。けれど、それは他人の事情――伊藤の事情と噛み合わなかった。手嶋は、事故に遭った伊藤の事情を知らなかったから。その結果だって、まるで予測のつかないものだったから。手嶋は自分が善いと思った行動しただけだった。
それでも、こんな結果を知ってさえ、手嶋は満足していると言うだろうか。答えのない疑問に、私は唇を噛んだ。彼は自分の行動に後悔はないのか。善と信じたお節介のせいで伊藤に殴られ、病院送りになったけれど、それでも、あれがそのときの最善の選択だったと言うのだろうか。あのまんまるな笑顔を見せて。
刻々と赤みを増していく空を、私は見上げた。今日は真紀の命日で、真紀は二十五年前のいま頃、村野に殺されてしまったのだった。過去を思い、私は身じろぎをした。すると、何かが膝の上から滑り落ちたような気配がして――私は屈み込んで、それを拾い上げた。母のお守りが揺れる、古いポーチ。そこに縫いつけられたシャルルのリボン、その中央のプラスチックの宝石がきらきらと夕日を反射した。この宝石が虹色に光って、シャルルは変身するんだっけ――私はその偽物の石をじっと見つめた。
子供の頃に買ってもらった食玩についてきた、小さなリボン。このお守りをもらったとき、私はもう高校生で、シャルルの好きな子供なんかじゃなかったのに、母はどうしてこんなものを縫いつけようと思ったんだろう。そっと撫でるように触れていると、脇のほつれかけていた糸がプツリと切れた。たった一つの母との繋がりが切れてしまったような気がして、私の胸には悲しみが込み上げた。現実はやはり、アニメのようにはいかなかった。ばらばらになった家族は元に戻ることもなく、私たちは決して幸せな結末を迎えることはないのだ。
私は、切れた糸くずを指先で抜き取った。すると、合わせ目から中の護符がはみ出しているのが見えた。私は元に戻そうとしたが、その紙に罫線があることに気づき、首をかしげた。少しためらってから、それを中から引っ張り出す。すると、やはりそれはただの紙切れ――それもルーズリーフの切れ端のようだった。これはまさか――私は息を飲んだ。しばらくそれを見つめた後、小さく丁寧に畳まれたそれをゆっくりと開く。
そこに記されていたのは、母の字だった。会えなかった時間も、苦しい感情も、何もかもを溶かしてしまうような、優しい母の字。私は驚きを感じながらも、その文字を目で辿った。その言葉を、何度も何度も読み返した。
『辛くなったら、いつでも帰ってきていいからね。どんなに離れ離れになったとしても、お父さんもお母さんも、いつも由紀のことを思っているから』
紙に視線を往復させるうちに、私の胸は熱くなった。言葉にならない思いが、思い出が次々と込み上げ、それらは一つとなって私に幸せの意味を教えた。そのためにすべきことを教えた。その一歩を踏み出すための力を与えた。
あの頃、夢見た
そう決意すると、私はカバンの中から携帯を取り出した。もう何年も思い出すことさえしなかったというのに、指は懐かしい電話番号を正確に押していった。母はまだ仕事から帰っていないだろうか。父も家にはいないだろうか。でも、それでもいい。断たれてしまったものを、また繋ぎなおそうという意志のために、私は通話ボタンを押した。呼び出し音を優しく聞いた。
お父さん、お母さん――言うべき言葉は知っていた。私、お腹に赤ちゃんがいるんだよ。お父さんたちにとっては、孫になるんだよ。真紀のことは悲しかったけれど、でも私たち、もう一度会えないかな。家族に戻れないかな。きっとそれが善いことだと思うから。善い未来へ繋がることだと思うから――。
優しい音は続いていた。その音が唐突に止む。そして――はい、雨ヶ谷です、懐かしい声が私に応えた。