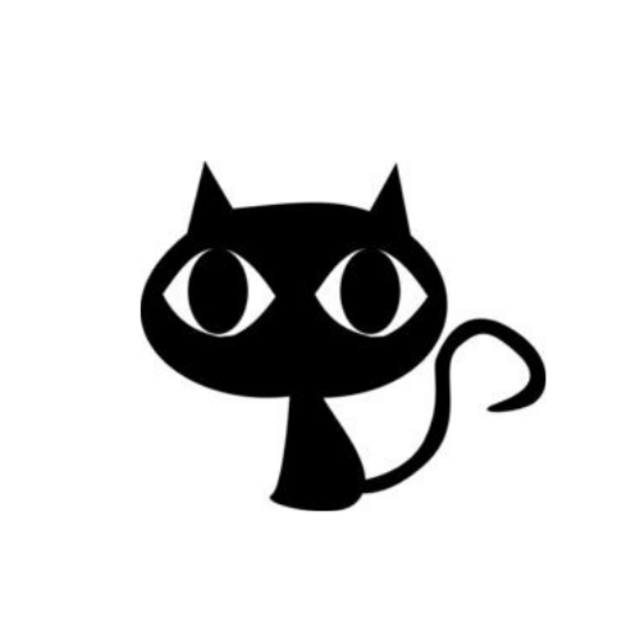断絶の章
文字数 19,132文字
19XX年、妹の真紀が殺された。
その事件をきっかけに、私たち家族はばらばらになった。
だから、これは断絶の物語である。
「いらっしゃいませ」の声は、危うく悲鳴に変わるところだった。続く「二名様でよろしいですか」という台詞は、まるで新人バイトのようにたどたどしかった。そればかりではなく「それではお好きな席へどうぞ」――そう言い終わるなり、私はその二人組の前から逃げ出すようにして厨房へ戻った。
三ツ池森林公園内に建つ、この「カフェレストラン・ラパン」でバイトを始めて一年ちょっと。ろくに案内もせずにお客の前から逃げるように立ち去るだなんて、社会経験のない学生バイトならともかく、三十路を過ぎた女の態度としては常識外れなものだった。けれど、それがあまりに突然の出来事だったせいで、私の体は考えるよりも先に反応してしまったのだ。こんなリアクションをしたら逆に怪しまれてしまうじゃないか――そんな思いすら浮かぶ余裕もないほどに。
その証拠に、私の心臓は胸から飛び出してしまうんじゃないかと思うほどに暴れていて、塞がったはずの傷からは新しい血が滲み始めていた。ほんの一瞬、頭をよぎったのはあの約束 のことだったけれど、そんな期待は確かめる前に忘れたほうが身のためだろう――私はすぐに思い直した。同時に皮肉な笑いを浮かべようとしたが、果たしてそれが成功しているのか、確かめることはできなかった。
日常というものは何の前触れもなく崩壊するものだということを、そして崩壊したときのその絶望を、私はこの数年、忘れていたらしい。ありがたいことだ。幸せなことだ。だけど、その幸せをいまこの瞬間は詰 りたい気分だ。
「どうしたんだ? 顔、真っ青だぞ」
逃げ込んだ先の厨房で、店長の伊藤が眉を顰 めた。寸胴鍋からよそっているのは「季節野菜の欧風カリー」。ラパンの一番人気メニューだが、ほとんど客のいない今日のような平日は、十皿出れば御の字というようなものである。
「どっか具合でも悪いのか?」
一向に減らない鍋の中身に苛立ったように尋ねる。どうやら機嫌が悪いようだ。私は精一杯の笑顔をつくって首を振った。しかしその実、暴れ続ける心臓のせいで目の前はぼやけ、胃はぎゅっと絞られたように痛かった。気のせいか、胃だけではなく、下腹部にも鈍痛があるようだ。こんなことじゃだめなのに――泣き出しそうになりながら、私はその場に座り込んだ。最近どうも情緒不安定気味だったところに、さらに不意打ちを食らったせいで、頭がどうかなりそうだ。
「ちょっと、手嶋さん。これ、六番テーブル」
そんな私を見て、伊藤は眉を顰めたまま、もう一人のバイトを手招きした。
「あ、はい」
無駄に大きな返事のあと、小太りの男が急ぎ足でやってくる。バイトのくせにほとんど常勤の私と同じく、週六でシフトを入れているアニメオタクの四十男だ。以前は普通の会社に勤めていたらしいが、何の事情か、こんなところでバイトをしているのだから、アニメオタクであるばかりでなく、使えない人材なのだろう。
厨房へ入った手嶋は、うずくまった私を見て驚いたような顔をしたが、伊藤が一つ舌打ちをすると、慌てたようにカレーをトレイに乗せ、客の元へと運んでいった。
「ったく、キモすぎんだよ、アニオタはさあ……」
伊藤はその背中に毒づいて――思い出したように私の方を振り向いた。
「由紀」
思わずびくりとしてしまうような低い声で私の名前を呼ぶ。
店では店長とバイトという関係ながら、実は私たちは同じアパートの部屋で同棲している恋人であり、それも私にしては珍しく、一年という長い付き合いの彼氏だった。その彼氏の機嫌が極限に悪い。まずい――私は立ち上がりかけたが、時はすでに遅いようだった。
「あのさあ」
伊藤は仁王立ちになって私を見下ろした。
「そうやって座り込んで、何? 具合悪いアピール? そういうの店でやるの、やめてくんない? そういうのって公私混同でしょ」
パシッと頭を叩かれる。ここが店だということは意識しているのだろう、恋人同士のじゃれ合いだと言われればそれ以上は反論できないくらいの軽い叩き方だ。これが家の中だったら、髪を掴まれて引き摺り回されても文句は言えない。普段は優しい人だが、彼はそれ以上にひどい気分屋でもあり、その怒りのスイッチはよく分からない場所にあるのだった。そして、今日は不運にもそのスイッチを押してしまったらしい。
「ご、ごめんなさい」
込み上げる吐き気を必死に耐え、私は笑顔をつくって立ち上がった。ふらつく足に力を込める。無意識にお腹のあたりに当てた手を、今度は意識的にかばうように守る。
「ちょっと貧血気味だっただけだから」
顔色を伺いながら言い訳をするが、どうやらこれも彼の気に入るところではなかったらしい。伊藤の目はますますつり上がった。
「貧血? そんなの、自己管理がなってないだけの言い訳だろ」
「あ、うん、でも……」
「言い訳はいいから。大体、貧血くらいでギャーギャー言うのっておかしくない? 俺が今日、朝早かったって知ってるだろ。せっかく作ったカレーもこのままじゃ廃棄だし」
鍋に入った大量のカレーを睨みつける。機嫌の悪い理由はそれか――私は顔には出さずに納得した。彼が本部に呼び出され、食材の廃棄が多いことをどやされたと言って怒っていたのは、確か先週のことだった。ラパンは各地に店舗を展開しているが、この「三ツ池森林公園店」は、そのチェーン店の中でも売り上げが少ないことに以前から目をつけられていたというのだ。
そんなことを言われても、隣の少し大きいばかりの公園に来る、休日の家族連れが主な客層なのだから、売り上げを伸ばせと言われても無理がある――私もそう思ったのだが、本部からすればそれも「店長の努力が足りない」せいらしく、このままでは本社での出世の道も危ういという。
もちろん、それは彼の仕事の問題で、バイトの身分である私に当たられても仕方がないことなのだが、それでも仕事に問題を抱えていれば不機嫌になってしまうのは仕方のないことだろう。
「ごめん。雅人さんのほうが大変だってことは知ってるよ」
家では「まあくん」と呼んでいるのだが、そんな呼び方をしたら今度は本気で殴られそうだったのでやめておいた。
「私もちょっとふらっとしただけだから、大丈夫だから。ほら、もう治ったし」
ぎこちないながらも、もう一度笑顔を作ると、彼は嘘を見抜こうとでもいうようにじっと私の目を見つめた。それからやはり苛立ったように問い詰める。
「本当だろうな」
「もちろん」
私はほかの地雷を踏まないように、慎重に付け足した。
「だから、全然大したことないんだって。ちゃんと朝食べなかったからお腹が空いちゃった、くらいな感じなの、本当に」
「え、お前、腹が空いてんの?」
すると、彼の表情が一気に変わった。マイナスに振り切っていた針が、今度はプラスに振り切ったような明るい表情でカレー鍋を振り返る。
「じゃ、昼飯にこれ食っちまえよ。先に休憩とっていいから。その代わり、大盛り二人前な」
楽しげに言いながら、うどん用のどんぶりになみなみカレーを注いでいく。お腹が空いたというのは例え話で、その上、いくら大盛りのカレーを私が食べたところで、廃棄の量はそれほど変わらないと思うのだが、いいことを思いついたと言わんばかりに嬉しそうな顔をする彼に、私も思わず顔をほころばせた。怒らせると怖い彼だが、こんなふうに無邪気で可愛い一面もある。そして、私は彼のそんなところに幾度となく救われているのだ。
「俺のおごりだからな。ちゃんと全部食えよ」
まかないは、どのメニューも一律五百円のルールだが、その分を給料から引かないでいてやるという意味だろう。
「うん、ありがとう――ございます」
戻ってきた手嶋が心配そうにこちらを見ていることに気づいて、私は何となく語尾を正した。手嶋は、伊藤が私を殴っていることに薄々気がついているようだった。それも、それがいわゆるDVだと認識している節があった。そのアザ、どうしたの――何気なくそう聞いてくることもあったし、以前など「女性のための避難シェルター」なる団体への連絡先がバッグに入っていたこともあった。あれも私が知らないうちに手嶋が忍ばせたに違いない。
他人のことなど放っておいてくれればいいのに、どうしてお節介を焼くのだろう――私は意識的に手嶋を避けるようになった。そうでなくとも、伊藤は嫉妬深い。二人きりで話をしているところを見られた日には、よほど酷いお仕置きが待っているに違いない。
私は手嶋から目を逸らすと、何気ないふりを装って、騒動の元々の原因――店内に先ほどの二人組を探した。初老の男性と、同じ年頃の女性。はたから見れば、同じように年を重ねた夫婦にしか見えない二人。私の視線は彼らを捉え――その二人の選んだ席を見て、静まりかけた私の心臓は再び跳ね上がった。
彼らはクーラの効いた店内ではなく、ガラス扉の先にあるテラス席に座っていた。八月も終わりとはいえ、まだ日差しは十分に厳しく、頭上のパラソルが作り出す程度の日陰では暑さはまったくしのげない。にも関わらずテラス席を、しかもその一番端の席を選んだのは、何か他人に聞かれたくない話でもするせいか。それとも――。
その理由を探ろうとすると、胸の一番奥がぎゅっと痛んだ。そろそろあの日 がやってくる。今年で二十五年目になる、あの日 が。探るまでもない、だから、彼らはここを訪れたのだ。古い傷がびりびりと音を立てて裂けていくのを自覚しながら、私は思った。
でも、それならどうして二人だけで訪れるのだろう――それが次の問いだった。どうして彼らは私を誘ってはくれなかったのか。いや、それとも私が知らないだけで、彼らはたびたび会っていたのか。去年も、一昨年も、その前からずっと内緒で会っていたのか。そして私は、今日、たまたま目撃しなければ、何も知らないままでいたということなのか。
「ほら、早く食ってこいよ」
急かす伊藤の声で、私ははっと我に返った。そのまま急いで裏の休憩室へと向かう。足は血を失ったようにふらつくというのに、なみなみとカレーの入ったどんぶりを持つ手は強張っている。ドアの前で立ち止まり、震える右手を伸ばすと、いつもは気にも留めない、金色をしたドアノブが、この部屋に入る覚悟はあるのかと問いかけているように思えた。
本当のことを言えば、そんな覚悟などまったくなかった。こんな機会が訪れるなんて想像したこともなかったし、彼らも私がいると知っていれば、このレストランへ立ち寄ることもなかっただろう。だから、これは私が望んだことでも、反対に望まれたことでもない。けれど、私にはその権利があるはずだ。
心を決めると、私はノブをゆっくりと回し、ドアを開いた。むわっとした熱気がアメーバのように体にまとわりつく。一呼吸置いて小さな机の上にカレーを乗せると、私はクーラーをつけ、ロッカーから小さなポーチを取り出した。チャックの金具に揺れるお守りを握りしめる。そうしてから目を閉じて、壁の向こうへ耳を澄ました。
もし、彼らが他人に聞かれたくない話をするのなら、あのテラス席の端を選んだのは大きな間違いだった。なぜなら、二人が座ったテラス席のすぐ脇の仕切りは、この休憩室の壁を兼ねており、ラブホテルのものよりお粗末で薄っぺらいこの壁は、どんな内緒話も筒抜けにしてしまうのだ。
それを発見したのは、手嶋が来る前のバイト仲間だった噂好きのおばさんだった。不思議とあの席に座る客には秘密が多く、彼女はその内緒話を聞きたいがために「トイレへ行く」という名目で仕事をサボり、ささいな夫婦喧嘩や不倫カップルの会話を楽しんでいたらしい。しかし、そんなおばさんも半年前、「トイレ休憩」の多さに気づいた伊藤にクビを言い渡されてしまった。
その盗み聞きを、今度は自分がすることになるとは――私はしばらく耳を澄ましていたが、彼らはメニューでも見ているのか、その声が聞こえてくることはなかった。私はなぜかほっと胸を撫で下ろした。このまま何も聞こえなければ、それはそれでいいような気もする――軋む音を気にしながら、パイプ椅子に腰を下ろす。すると、鏡の中の女と目が合った。休憩後、仕事へ戻る前の身だしなみチェックのために設置された大きな姿見。その奥から、その女は私を見つめ返しているのだった。
彼女は、私が思い浮かべる「私」とはかけ離れた姿をしたおばさん だった。三十六歳という年相応に肌はたるみ、ほうれい線は深くなり、注意すれば目尻の皺さえ見て取れる、アラフォー女。一体、私はいつのまにそれほどの年月を生きたのだろうか? いまも私が「私」として思い浮かべるのは、あのひまわりのワンピースを着て駆け回る、無邪気な女の子の姿だというのに、鏡の中のおばさんにはその頃の面影など一つも残っていなかった。本当に一つも、そのかけらさえ残っていない。
だから、あの人たちは私に気づかなかったのだろうか――泣き出しそうになる女を見ながら、私はそんなことを考えた。すると、気づかないなんてそんなことが許されるはずがない――女は顔を歪めて訴えた。そうかもしれない――私は女に同情するように頷き返した。親が娘を忘れるなんて、そんなことが許されるはずがない――。
私は鏡から目を逸らすと、薄い壁をじっと睨んだ。
親と、娘。そう、あのテラス席の二人組は紛れもない、私の両親だった。ある事件をきっかけに、いまはばらばらになってしまったけれど、それ以前まで、私たちはどこにでもいるような、幸せな家族だったのだ。
涙の気配にまぶたを閉じると、クーラーの稼動音の向こうから、子どもたちがはしゃぐ声が聞こえた。その声はさほど遠くはない――ラパンのある三ツ池森林公園から響いてくるものだった。私はその無邪気な声に強い郷愁を覚え、唇を噛み締めた。
このラパンなんてレストランが影も形もなかった頃、私はこの公園で遊んだことがある。いや、私たち は遊んだことがあると言ったほうが正しいだろう。いまもその長い長いローラー滑り台があることで有名なこの公園は、私たちが家族だったその昔に訪れた――うさぎの公園、と呼んでいた場所だった。
三ツ池森林公園はその名の通り、敷地に三つの池がある公園だったが、そればかりではなくゴーカート乗り場や、三十分百円の変形自転車乗り場、それにたくさんの遊具が置かれたアスレチック広場まである、とても広い公園だった。中でも人気なのは長いローラー滑り台で、全長は約百六十メートル。昔は日本一長いローラー滑り台がある公園として有名だったらしい。
あの頃、私たちはここを「うさぎの公園」と呼んではいたけれど、いま、この公園にうさぎはいない。けれど、私たちが幼い頃にはいたのだろう。わざわざ家から持って行ったニンジンを、うさぎにあげた記憶があるし、抱き上げるとキューキュー鳴いて可愛かったことも覚えている。
それからほかに覚えていることといえば、お気に入りの公園ではあったけれど、家から遠く、それほど頻繁に連れて行ってはもらえなかったということ。それから、子供だった私はその長いローラー滑り台が大好きで、何度もあの長い階段を登っては滑り降りてを繰り返していたことだった。おばさん となったいまでは、遠くから見ているだけで疲れてしまうようなそれを、繰り返し繰り返し登っては降りて――。
そういえば、あのときの母は幾つだったんだろう――脳裏をそんな思いがよぎった。子供の私に付き合って、何度も階段を登ってくれた母。その母に押され、勢いよく私が滑り出すと、景色の先には父がいて――そう、その手にはコンパクトカメラが構えられていた。そしてその父の傍に、もう一人――蘇らせたくない記憶を、それでも渋々蘇らせるように、私はその小さな影に目を向けた。真紀――それは私の妹だ。
握り締めた手を開き、私はポーチについたお守りを見つめた。それは昔、私が家を出て、寮付きの高校へ入ったときに、母がくれた手作りのお守りだった。長い間、カバンに入れっぱなしにしていたため、紐はよれ、口が開きかけていたが、表についたリボンはしっかり縫われていて、取れるような気配もない。その中央にピンクの宝石を模したプラスチックがついている、色あせた虹色のリボンは、私の大切な思い出の品だった。
――それ、「シャルル」のリボンでしょ?
手嶋の声が耳元でしたような気がして、私は思わず顔を上げた。いままで、存在さえ指摘されることのなかったこのリボンの素性を、手嶋に言い当てられたのは、ついこの間のことだった。その驚きがまだ胸に残っていたのだろう。アニメオタクだとは聞いていたが、まさかこんな古い――しかも少女向けのアニメまで知っているとは思わなかったのだ。
美少女仮面シャルル――それは、私たち姉妹が大好きだったアニメで、「シャルル」はその主人公の名前だった。普段はただの中学生、けれど一度 悪が現れると、彼女は美少女仮面シャルルに変身する。呪文を唱えながら、キラキラ光る魔法の虹を滑り降り、悪の大王ジャークと戦うのだ。
実は、私たちがうさぎの公園を気に入っていた理由はそこにあった。あの長いローラー滑り台はシャルルの虹に似て、変身ごっこをするのにおあつらえ向きの場所だったのだ。いまは思い出すことのできないその呪文を大声で叫びながら、滑り台を先に滑っていく真紀を、私は思い出した。お姉さんだった私は、真紀のように叫びたいと思いながらも、恥ずかしくてそれができなかった。だから、私は八つ当たりのようにそのストレスを妹へ向けた。
『真紀は呪文、言わないでよね! 由紀がシャルルなんだから!』
しかし、そんなことを言われて引き下がる真紀ではない。私たちはそうしていつも喧嘩した。真紀は四歳も離れた妹だったから、勝つのはたいてい私だった。そうなると、真紀は拗ねてブランコの方へ走って行き、私はシャルルの座を手中に納めるのだが、身勝手なもので、そうなると途端につまらなくなって、滑り台をやめてしまうのだった。
――オル・フォル・ギュネス。
忘れていた呪文がふと蘇り、私はぎょっと体を強張らせた。オル・フォル・ギュネス、確かにそんな呪文だった。いま繰り返すと、ラテン語か何かのようだ。となると、何か意味がある言葉なのだろうか――ぼんやりと考えていると、胸のどこかに引っかかりを感じた。そんなはずもないのに、私はこの呪文の意味を知っているような、誰かから聞いたような、そんな気がして考え込んだ。けれど、結局そこからは何も思い出せないまま、私の心は再び過去へと戻っていった。
あの頃――子供だった私はシャルルになりたいと思っていた。もちろん本気ではなかったと思うが、なれるものならなりたいという、憧れの存在だった。食玩についてきたこの小さなリボンで変身し、悪と戦い、人々を守る、そんな正義の味方になりたいと、私はあの頃思っていたのだ。大人になり、世の中を知ったいまでは、馬鹿みたいな話だけれど――私は口を歪めて少し笑った。
実際の世の中には、シャルルのような絶対的正義 も、ジャークのような絶対的悪 も存在しない。それなのに、アニメというものはその二つの立場しか存在しないような、単純な世界を描く。いつでも正義が勝ち、悪が負け、それだけならまだしも、負けた悪が改心して、善い人になることすらある。まったく人を馬鹿にしているとしか思えないような話だ。それが分からない小さな子供は仕方ないにしろ、それを好んで見るような――手嶋のような人間がいることが理解できない。
このアニオタが――手嶋がミスをするたび、伊藤はそう言って舌打ちしたが、それも仕方のないことだろう。このリボンを一目見て、シャルルだと目を輝かせるなんて、大人になりきれていない子供だという証明にほかならない。前の会社をどんな理由でクビになったのかは知らないが、善が報われ、悪が滅ぼされると、本気で思っているような幼い精神をしているからこそ、四十にもなるのにバイトなどしていられるのだ。
「季節の欧風カリーとラパン特製サンドイッチです。ご注文の品は以上でよろしいですか」
そのとき、ちょうど壁の向こうから聞こえた手嶋の声に、私はどきりとして耳を澄ませた。しかし、彼らは頷いただけだったのか、「それではごゆっくりどうぞ」という手嶋の妙に優しげな声が、再び聞こえただけだった。あとには誰もいないかのような沈黙が残った。遠いはずの子供たちの声が、やけに大きく耳に響き、私はそこに広がっているはずの光景に思いを馳 せた。
昔、私の母がそうしたように、母親たちは子供に付き合って、あの長い階段を登っているのだろう。父親たちは滑り台の終わりで、コンパクトカメラ――ではなく、いまはスマホを構えているのだろう。ばらばらに断絶した、かつて家族だった人間たちがここにいることに気づくこともなく、彼らは日常の幸せに浸っているに違いない。
話すより先に食べることにしたのだろう、壁の向こうからはスプーンが皿に当たる小さな音が聞こえた。家族とは何だったんだろう――その静かな物音に集中していると、胸の奥からじわじわと苦いものが染み出した。
家族が家族でなくなったのは、いまから二十五年前、私が小学五年生のときだった。その日、私が家に帰ると、玄関の前には人だかりができていた。どうしたのだろう、私は立ちすくんだ。すると、人々の間から、取り乱した様子の母が飛び出してきた。かと思うと、私の肩を強く掴んでこう言った。
『どうして真紀と一緒じゃなかったの!』
その声は別人のように低く、目は恐ろしく血走っていて、驚いた私は思わず後ずさった。どうしたの――尋ねる前に、警察官が母を私から引き離した。私は婦人警官に連れられてパトカーに乗り、そこで真紀が殺されたことを知った。それは私とシャルルの座を争っていたライバルが永遠にいなくなったという知らせであり、同時に、それが私にとっての「雨ヶ谷真紀ちゃん殺害事件」の始まりだった。
事件の始まり、などと言うと、何だか奇妙に聞こえるかもしれない。けれど、私の人生にとってあの事件は確かな始まり だった。殺された妹にとっては終わり となったものが、これからも生きていく私にとっては始まりとなったのだ。
地味で平凡だった私の生活は一転、人々の好奇の的となり、私はどこへ行っても私のことを知っている 人ばかりに出会った。事件を報道したマスコミは、当時小学生だった私の映像にはモザイクをかけたが、一方で死んだ真紀のフルネームや通っていた小学校、住んでいる町、家族構成などを全国ネットで報道した。そこまでされてしまっては、私の顔のモザイクなど、端 からないも同然だった。
私が「真紀ちゃん」の姉の雨ヶ谷由紀だということは、町の人だけではなく、当時、ニュースを見た日本中の人々の知る事実だった。それは決して大げさな言い方ではない。私は一歩外を歩けば「ほら、あの子」と指をさされて井戸端会議のネタを提供し、「可哀想にねえ」という慰めや同情の声を一身に受けた。学校に行けば、先生やクラスメイトは私を遠巻きにし、ひそひそと噂話を始めた。中には、私が有名になったことが気に入らないらしく、すれ違いざまに睨んでくる女子もいた。反対に優しい顔をして近づいてきて、何とか噂以上の事件の話を聞き出そうとする子たちもいた。
また、実際に会う人ばかりではない。家の電話にはニュースで事件を知ったという、会ったこともない親戚や、保育園時代の友人だと名乗る子、驚いたことにまったく関係のない他人からさえ、コールがひっきりなしにかかってきていた。「雨ヶ谷」という苗字は珍しく、彼らはその苗字を頼りに電話帳を辿ってきたのだった。
それでも、その内容が同情や励ましなら、まだ良かった。中には、「小学一年生に一人で留守番をさせるなんて」という非難の電話や、「神様を信じないからです」というわけの分からない電話もあって、私たちを疲弊させた。
責められるべきなのは、私たちではなかった。真紀を殺した犯人の村野正臣という男だった。だというのに、村野は拘置所だかどこかの檻の中で静かな時間を過ごし、私たち家族は騒がしい渦の中に飲み込まれていた。何と不公平なことだろうと、いまでも私はそう思う。祖父母の家に避難してさえ、私たちは夜、ゆっくり眠ることもできなかった。なぜなら、私たちの行く先々に金魚の糞のようについてきたマスコミは、夜になっても家へ強烈なライトを浴びせ続けたからである。
それでも真紀が死んでしまって――殺されてしまって、私は多分悲しんだんだろうと思う。きっと涙を流したんだと思う。けれど、いま振り返る記憶の中に、そんな光景は一つもなかった。覚えているのは、私を見るみんな の目だった。そしてみんな という枠から外れてしまった私 という存在だった。昨日とは何一つ変わっていないというのに、真紀の死によって特別 へと押し上げられてしまった私自身のことだった。
いや、特別になったのは真紀も同じだった。良くも悪くも、妹は普通の女の子だった。その死こそが彼女を特別にしたものの、生きていれば日本中の人々が知るニュースなどとは縁のない、平凡な人生を送っていたはずの人間だった。
けれど実際には彼女は死に、その名前は有名になった。そして望みもしないのに、私はそのおこぼれに預かってしまった。死んでしまった真紀はそんなことを気にすることもできないだろうけれど、生きている私にとって、それはみんな から仲間外れにされることと同じだった。
私はかつて、無害な日和見 菌だった。シャルルのような善玉菌でもなく、ジャークのような悪玉菌でもない、その他大勢の日和見菌。世の中のほとんどの人間は、この日和見菌だろう。例えば、お昼のワイドショーで見た殺人事件に「かわいそうだね」と同情し、それと同じ調子で、赤ちゃんパンダが遊ぶ映像に「可愛い」と歓声を上げ、芸能人の結婚に一喜一憂するような。私たちはいつでも遠くから物事を見て、その物事に対して好きなことを言ったり、また言わなかったりすることができた。それは部外者の自由 だった。何も考えずにいられる自由が、そこにはふんだんに溢れていた。
けれど、真紀は殺され――事件は私を当事者にしてしまった。あの子が妹を殺された子だよ――抜け殻のような私を指差すみんな のように、私自身がその噂に加われたならどんなによかったことだろう。けれど、どうあがいても私は私を噂する立場になれなかった。私は外側 へと弾き出されてしまった。そうして外から見てみれば、世界はあまりに完璧に編み上げられていて、私のような異分子が再び入り込める隙間はまったく見えないのだった。
それでも私は元の場所に戻りたくて、もう一度仲間に入れて欲しくて、うろうろとその周りをさまよった。けれど日和見菌たちは、決して手を差し伸べてはくれなかった。私という当事者に触れてしまえば、その誰かは特別 に伝染してしまう。遠くから見ていたいだけの彼らが、自分の身を危険に晒 すことなど考えもしないのは当然だった。
もちろん、彼らの中には特別な私を羨 む者もいたが、それはぬるま湯に浸かりながら、同時に特別でもありたいと願っているだけで、外側へ行きたいと本気で思っているわけではなかった。だからこそ、なのだろうか。彼らの視線には、常に敵意が満ちていた。私が暗い顔をしていれば、「いつまでも悲劇のヒロインぶって」と嘲 り、私が少しでも笑えば「妹が死んだのにもう笑えるなんて」と非難した。
どうすればいいのか分からなくなった一人ぼっちの私は、耳を塞ぎ、俯いて道を歩くようになった。それは家に帰ってさえ同じだった。父や母の前でも、私はどういう顔をしたらいいのか分からなかった。私たちは家族で、同じ当事者だった。けれど、それは決して同じ立場であるという意味ではなかった。
なぜなら、私が失ったのは妹 で、娘 ではなかった。もっと言えば、父母の立場も両親 と一括りにはできるものではなかったはずだ。真紀はどちらにとっても娘 でありながら、その関わり方や関わった時間は同じではない。ましてや、母に至っては、真紀は自分のお腹を痛めて産んだ子供だったのだ。
誰が一番悲しんでいたか、その深さを比べる気はない。けれど、私と両親のそれを比べれば、私の悲しみは明らかに小さかったのではないかと思う。そうでなければ、真紀の死に涙を流したかどうか思い出せないなんてことはないだろうから。
あの日、私が真紀と帰らなかったことを、母は二度と責めることはなかった。けれど、代わりに口数もめっきり減って家事も滞 ることが多くなった。自ずとそれは父の役目となり、その下手くそな家事を私も黙ってフォローした。料理上手な母が、昔、よく作ってくれたクリームスパゲッティが無性に食べたくなることがあったが、真紀も好きだったそれを作ってくれなど、口が裂けても言えなかった。そればかりではない。またうさぎの公園へ行こうね――真紀が殺される前日、家族で交わした約束 が守られていないことも、これからも永遠に守られることがないことにも知らんぷりをして生きていかなければならないということくらい、私にだって分かっていた。そうすれば、せめて「真紀だけがいない」生活が守られると、そんな淡い期待を持っていたのだろう。
そんな生活が四年続いた。私は中学二年生になっていた。けれど結局、その果てに待っていたのは断絶だった。長い間、呆けたように黙りこくっていた母は、突然記者会見を開き、村野の死刑を取りやめてほしいと訴えた。そして、寝耳に水のその会見に怒った父は、荷物をまとめて元の家へと帰ってしまった。由紀はどうする――アパートを出る直前、こちらに背を向けた父の低い問いが忘れられない。
あのとき、私の頭は「真紀が殺された家には帰りたくない」という思いでいっぱいで、黙って俯くことしかできなかった。そうしている間に父は行ってしまった。まるで少女のように頰を紅潮させた母が帰ってきたのはその後だった。彼女は部屋に入るなりテレビをつけ、画面の中の自分を食い入るように見つめた。そして私を振り向いた。
父についていかなかったことを後悔したのはそのときだった。分かるわね、由紀――妙に優しい声で母は言ったのだ。被害者遺族である私たちこそが、村野さん を愛してあげなくちゃいけないのよ、と。
その顔には、久しく見ることのなかった微笑みが浮かんでおり、私の背筋をぞっとさせた。母の心はあまりの悲しみに壊れてしまったか、そうでなければ変な宗教に入ってしまったのではないかと思われた。
私は絶望した。私は「妹が殺された私」という存在として、ただでさえ普通ではなくなってしまったというのに、母は「愛」とやらに目覚め、愛想を尽かした父は出て行ってしまった。いや、後になって思えば、その父も十分に壊れておかしくなっていたのだ。そうでなければ、血の染みが残る殺害現場に戻って暮らせるはずがない。例え、それが父にとっては愛しい娘の血だったとしても、気味が悪いことには変わりない。普通の人間ならば、そう思うはずだ。
そして、私はもう一度「普通の人間」に、あの自由で何も考えずにいられる日和見菌たちの世界へ戻りたかった。ならばするべきことは一つだった。おかしくなってしまった両親や、私の顔を知る人たちの元から離れ、すべてをリセットすることだ。
私は必死で勉強に励み、誰も私のことを知らない他県の全寮制高校への進学を決めた。その頃には両親の離婚が成立していたため、私は母の旧姓を使い、梶田由紀として新しい生活を始めた。離婚のとき、父はその預貯金をそっくり私のために残してくれていたため、お金の心配がないのはありがたかった。そうして私は再び普通 を始めた。
私の望みは、ニュースで流れる殺人事件にさも同情しているような声をあげ、パンダの赤ちゃんが生まれたというニュースに歓声を上げ、芸能人の結婚に喜んだり悲しんだりすることだった。けれど、特別でいた時間が長すぎたせいだろうか、私はもう元に戻れなくなってしまった自分に気がついた。どのニュースにも当事者がいることを、私は知ってしまった。だから私はニュースよりも、その当事者のことを思い、日和見菌たちのように振る舞うことができなくなっていたのだった。そう実感したときから、私のすべてはだめになった。
高校を卒業し、就職した会社は、たった半年で辞めることになった。その会社は社員同士の仲がとても良かったのだが、私はその輪に入れなかったからだ。すぐに見つけた別の会社も、同じような理由で辞めてしまった。そして次に見つけた会社も、その次に見つけた会社も――。
若いうちはそれでも選り好みさえしなければ、転職先は見つかったが、三十を過ぎる頃になるとバイトしか見つからなくなった。それはプライベートも同じだった。恋人と呼べる人はできるのだが、過去を語るような段階に入ると、別れを切り出さずにはいられなくなる。
黙りこくる私に、たいていの人が腹を立て、あるいは呆れ、去っていった。けれど、やはり私は俯き、耳を塞ぐことしかできなかった。いつでも私の足元は過去から染み出した泥で緩んでいた。今度こそ前を向いて行こうと思うのに、うまく歩けないのはそのせいだった。過去は変えることはできない。逃げることもできない。それならいっそ、何もかも終わりにしてしまいたい――。
人は死を考えたとき、最後に懐かしい場所を訪れたくなるのだろうか。私にとって、それはこの公園――うさぎの公園であったようだった。
おかしな話だが、うさぎの公園が「うさぎの公園」という名前でないことに気づいたのは、そのときだった。「三ツ池森林公園」という、その聞いた覚えもない、無感情な名前に、私は凍りついたように立ち尽くした。そんなことがあるはずもないが、真紀を失ったことで、うさぎの公園の魔法が解け、三ツ池森林公園という見知らぬものに変わってしまったのかもしれないと思った。またうさぎの公園へ行こうね――だからあの約束 は守られなかったのだと思った。
家族はなく、約束もなく、仕事も、未来さえも見えない、そんな私の横を、かつての私たちのような親子連れが通り抜けた。手を繋いだその後ろ姿を、私は背中で見つめていた。
あの日始まった 事件は終わることなく続いている。世間的に言えば、妹を殺した犯人は捕まり、裁判にかけられ、相応の刑に服し、そうして終わりを迎えた。けれど、ばらばらになってしまった私たち家族が元通りになるときは二度とやってはこないのだ。
悲しくなった私は、そこにうずくまり、泣き出した。このまま死んでしまえたらどんなにいいかと思っていた。そんなときに、声をかけてくれたのが彼――伊藤だった。伊藤はラパン特製のココアを差し出し――それもこのカレーのように、作りすぎて余っていたのかもしれないと思って私の口元は少し緩んだ――話を聞いてくれた。そして意外な反応をした。それから私は彼と付き合っている。
「……変わらないな」
そのとき、壁の向こうから声が聞こえた。父の声だ。その懐かしい声に私は思わず口を押さえた。
「あなたは痩せたわ」
母の声が続けて聞こえた。しかし、その声はどこか緊張しているようだった。予想とは裏腹に、二人は長い間会っていなかったのだろうか――ちらりとではあるが、先ほど久しぶりに見た二人の顔を思い浮かべる。
電話すらかけなくなった母の顔を見たのは八年ぶり、父に至っては判決のとき以来になるはずだから、二十年ぶりにもなるだろうか。聖母めいた微笑を浮かべる母は変わったように見えなかったが、父は母の言うようにずいぶんと痩せたようだった。それだけでなく雰囲気も変わっていた。隠しても隠し切れない怒りは、まるで檻の中からこちらを睨む猛獣のようだった。まさか病気だろうかと、私は不安になった。母も同じ不安を口にしたが、父はその疑いをきっぱりと否定した。
「別に病気じゃない。毎朝、走っているせいだ」
「走ってる? また柔道でも始めたの――」
母は質問の途中で、言葉を飲み込んだ。私もつられて息を飲んだ。不安になるような、長い沈黙。その後、父の低い声が聞こえた。
「あいつはどこだ。お前は知ってるんだろう」
――あいつ ?
一拍おいて、心臓を直接殴られたような衝撃が走った。吐き捨てるようなその言い方、憎々しげなその調子。それを聞けば、あいつ が誰かなんてことは明らかだ。村野正臣。真紀を、妹を殺した男。けれど、その村野は裁判で無期懲役となり、いまは刑務所にいるはずだ。
反射的に考えた直後、二十五年という月日がずしりと重たくのしかかった。二十五年。あれからそれほどの年月が経ったのだ。それが刑として長いのか短いのかは分からないが、少なくともまだ私はあの事件の中にいて、その月日が立ち直るには不十分なものであることは知っている。しかし、一方でそれが仮釈放されるのに十分な年月であったとしたら? 膨れ上がる疑惑を決定づけるように父が続けた。
「一昨日、桜の押印のない手紙が届いた。あいつは仮釈放された。そうなんだろう?」
「……手紙にそう書いてあったっていうこと?」
探るように母は尋ねた。すると、馬鹿な質問はするなとでもいうように、父は鼻を鳴らした。
こんなことをする人だっただろうか――私はたじろぎ、思い出したように下腹に手を当てた。もしかしたら、それはあの大きな熊のような体型のせいでそう見えていたのかもしれないが、私の知っている父はとても温厚で、かつ勇気のある人だった。その昔、職場でいじめられていた母を助けたのが馴れ初めだと、母本人から聞いたこともある。そんな人だからこそ、父は真紀が死んだ後も、母に代わって家事をし、学校の面談にも来てくれたのではなかったか。それがどうしたことだろう。
「あいつからの手紙なんか読むわけがない」
以前からは考えられない、荒っぽい口調で父は言った。
「どうせ仮釈放のための実績づくりだ。そんなもの、俺が読んでどうなる」
「どうなるって……そんな。村野さんはずっと返事を待ってたのに」
対して母のほうは、私が家を出たときと、さして変わっていないようだった。父は再び鼻を鳴らした。
「返事? 馬鹿も休み休み言え。何で俺がそんなもんを書いて、あいつを赦してやらなきゃならないんだ?」
「いえ、赦してやるとかやらないとかじゃなくて……」
「いや、そういうことだ。あいつからの手紙を開けた時点で、俺の負けだ」
「勝ち負けの問題じゃないでしょう」
「じゃ、どういう問題だ?」
「どういうって……そもそも謝罪の手紙だと分かっていて読みもしないだなんて、人間としてどうなんですか」
「なら、お前はあいつがやったことが人間としてどうだと思ってるんだ?」
母は言葉に詰まった。しかし、それでも振り絞るような声で言い返した。
「村野さんはちゃんと罪を償って、更生しました。私はずっとそれを助けたんです。手紙を書いて、面会に行って」
「あのクズにさん 付けするな」
恫喝するような声で、父。母は怯えたように黙ったが、勇気を振り絞るように言い返した。
「村野さんはクズじゃありません。刑務所の人もそれを認めたから、仮釈放されたんです。手紙も読まないあなたは知らないでしょうけど」
「クズが更生するもんか」
すると、父は笑うような声を出した。けれど、その顔が笑ってなどいないだろうことは、壁越しにもよく分かった。彼は続けた。
「いいか。普通の人間は人を殺さない。どんなに金に困っても、嫌な目に遭っても、口で『殺す』とは言ってはみても、それを実行するやつなんかいない。それなのに、偶然見かけただけの子供の後をつけていって殺す? そんなやつはクズ以外の何物でもない。本性からして狂ったクズなんだ。そんなやつが反省なんかするわけがない。そうだろ? 俺たちとは人間が違うんだから」
「誰だって間違いを犯すことはあるわ。私だって――」
「間違いで人を殺したことがあるのか?」
「そうじゃない。でも、村野さんは虐待とか、これまでいろいろ苦しい思いをされてきて」
「虐待された人間は、全員人殺しになるのか?」
「だから、そうじゃないってば! そのほかにもいろんな要因が重なって」
「真紀が死んだ妹に似てた、とか?」
「そうよ。だから彼は」
「妹に似た真紀を殺した。なぜだ? 理屈が分からないのは俺だけか?」
「もうやめて! 村野さんの気持ちは、あなたみたいに愛されて育った人には分からないのよ!」
母はとうとう小さく悲鳴をあげた。テーブルの上で飛び跳ねたらしいスプーンの金属音が、その悲鳴に重なった。
「私たちには分からないものがそこにあるのよ! だから村野さんは間違いを犯した! でもその罪はちゃんと償われて、もう彼は更生したの! あなたが何と言おうが、彼はもう赦されたのよ!」
呼吸音まで聞こえるような、長い沈黙が後に続いた。あの日、最高裁のさなかに父がアパートを出て行ってから、これがほとんど初めて持たれた話し合いの場なのだということに、私はその雰囲気から気づかされた。両親の会話は、それほど過去に囚われていた。死んだ真紀のことで頭はいっぱいで、そこにもう一人の娘がいたことを――そしてその娘はまだ生きているのだということを、思い出す余裕もないようだった。
「……あいつはどこにいる。仮釈放された後の行き先はどこだ」
一気に熱を失ったような、冷え切った声で、父が再び尋ねた。憎しみを隠そうともしない父。トレーニングで体を絞り、執拗に村野の居場所を聞く父。彼が何を望んでいるのか、何をしようとしているのか、冷たい水が染み込むようにじわりじわりと、私は少しずつ理解していた。聞きたくもないその質問を母が投げた。
「どうして聞くの? 普通の人間は人を殺さない。そうするのは狂った人だけなんでしょう?」
その声はすがるような響きを含んではいたが真剣で、決して皮肉を含んだものではなかった。問いに、父はすぐには答えなかった。けれど、その無言の間こそが、彼が心からそれ を望んでいることの証に思えた。村野への復讐。それも嫌がらせの類ではなく、死をもって遂げられる報復。
ああ、そうだったのか――私は心に大きな穴が空くのを感じた。二十五年もの間、父はそれだけを考えて生きてきたのだ。生きている私ではなく、死んだ真紀のことだけを考えて。
「どうして」
長い沈黙の後、ぽつり、つぶやくように母が言った。
「昔は、そんな人じゃなかった。あなたはもっと――善い人だった」
「善い人?」
冷めた父の声が繰り返した。
「子どもみたいなことを言うな。俺は何も変わらない」
「いいえ、あなたは善い人だった。だから、あのときだって私を助けてくれたんじゃない」
「何の話だ?」
「覚えてないの?」
「さあ。いまの俺には何もない。あいつが奪っていったからだ。だから、俺はあいつを許さない。あいつをこの手で殺して――」
不意に父は言葉を切った。母の前で決意を口にしてしまったことを、悔やむように黙りこくった。それは邪魔されることを嫌がってのことか、それとも――。
けれど、そんなことはどうでもよかった。私は押しつぶされそうになっていた。父は村野を殺すつもりなのだ――それが予感ではなく、確信に変わってしまったという衝撃で。
その衝撃の波がゆっくりと引いていくと、今度は目から、次から次へと涙の粒が湧き出した。喉の奥から嗚咽が漏れ、それはどんなに歯を食いしばっても止められるものではなかった。会話に耳を澄ますこともできず、私は机に突っ伏すようにして泣きじゃくった。
私は父が殺人を犯そうとしていることが悲しかったわけではなかった。もし、父が復讐を遂げ、私のお父さん に戻ってくれるのならば、ばらばらになった家族が元に戻るというのなら、殺人の一つや二つ、犯してくれたって構わなかった。けれど、そんな望みは決して叶わないということを、私はそれをよく分かっていたのだ。
村野を殺した父は、復讐を遂げた父 になるだけで、お父さん には戻らない。復讐が真紀のためなら、その罪も真紀のためであり、私という存在が入り込む余地はどこにもないのだ。それは母も同じだった。真紀のために村野を赦した彼女もまた、今度は真紀のために殺人を犯した父を赦すという道を選ぶだろう。お母さん には戻ってくれない。すべては死んでしまった真紀のため。どこにもいない真紀のために、両親の世界は回り続けるのだ。
ぎゅっと下腹に痛みが走り、私はそこを強く押さえた。もし、ここで倒れたら――馬鹿な考えが頭をよぎる。私が倒れ、騒ぎになったら、両親は私がここにいることに気づいてくれるだろうか。私の存在を思い出し、名前を呼んでくれるだろうか。
咄嗟に壁を破り、姿を現したいような衝動に駆られ、私は椅子から立ち上がった。次の瞬間、ひどいめまいに座り込む。この頃続いている、ひどい貧血。その原因は分かっている。私は抱きしめるように下腹を押さえた。
私のここには赤ちゃんがいる。まだ胎動も感じられない、小さな存在が私のお腹で育っているのだ。
もし、私が妊娠していることを知ったなら――三十路も半ばを過ぎた娘のお腹に赤ん坊がいることを知ったなら、父はその子のために殺人犯になることをやめてくれるだろうか。母は村野にではなく、この子に愛を教えてくれるだろうか。私たちは家族に戻れるだろうか。
そのどれも、儚い望みだということは知っていた。けれど、どうしてもその望みを手放せず、私はさらに泣きじゃくった。壁の向こうに聞こえるくらい、声を上げて泣き続けた。
「梶田さん、店長が食べたら戻れって言ってますけど」
休憩室のドアを開けた手嶋が驚いた顔で立ちすくむ。それでも私はだだをこねる子どものように、大声を上げて泣き続けた。
その事件をきっかけに、私たち家族はばらばらになった。
だから、これは断絶の物語である。
「いらっしゃいませ」の声は、危うく悲鳴に変わるところだった。続く「二名様でよろしいですか」という台詞は、まるで新人バイトのようにたどたどしかった。そればかりではなく「それではお好きな席へどうぞ」――そう言い終わるなり、私はその二人組の前から逃げ出すようにして厨房へ戻った。
三ツ池森林公園内に建つ、この「カフェレストラン・ラパン」でバイトを始めて一年ちょっと。ろくに案内もせずにお客の前から逃げるように立ち去るだなんて、社会経験のない学生バイトならともかく、三十路を過ぎた女の態度としては常識外れなものだった。けれど、それがあまりに突然の出来事だったせいで、私の体は考えるよりも先に反応してしまったのだ。こんなリアクションをしたら逆に怪しまれてしまうじゃないか――そんな思いすら浮かぶ余裕もないほどに。
その証拠に、私の心臓は胸から飛び出してしまうんじゃないかと思うほどに暴れていて、塞がったはずの傷からは新しい血が滲み始めていた。ほんの一瞬、頭をよぎったのは
日常というものは何の前触れもなく崩壊するものだということを、そして崩壊したときのその絶望を、私はこの数年、忘れていたらしい。ありがたいことだ。幸せなことだ。だけど、その幸せをいまこの瞬間は
「どうしたんだ? 顔、真っ青だぞ」
逃げ込んだ先の厨房で、店長の伊藤が眉を
「どっか具合でも悪いのか?」
一向に減らない鍋の中身に苛立ったように尋ねる。どうやら機嫌が悪いようだ。私は精一杯の笑顔をつくって首を振った。しかしその実、暴れ続ける心臓のせいで目の前はぼやけ、胃はぎゅっと絞られたように痛かった。気のせいか、胃だけではなく、下腹部にも鈍痛があるようだ。こんなことじゃだめなのに――泣き出しそうになりながら、私はその場に座り込んだ。最近どうも情緒不安定気味だったところに、さらに不意打ちを食らったせいで、頭がどうかなりそうだ。
「ちょっと、手嶋さん。これ、六番テーブル」
そんな私を見て、伊藤は眉を顰めたまま、もう一人のバイトを手招きした。
「あ、はい」
無駄に大きな返事のあと、小太りの男が急ぎ足でやってくる。バイトのくせにほとんど常勤の私と同じく、週六でシフトを入れているアニメオタクの四十男だ。以前は普通の会社に勤めていたらしいが、何の事情か、こんなところでバイトをしているのだから、アニメオタクであるばかりでなく、使えない人材なのだろう。
厨房へ入った手嶋は、うずくまった私を見て驚いたような顔をしたが、伊藤が一つ舌打ちをすると、慌てたようにカレーをトレイに乗せ、客の元へと運んでいった。
「ったく、キモすぎんだよ、アニオタはさあ……」
伊藤はその背中に毒づいて――思い出したように私の方を振り向いた。
「由紀」
思わずびくりとしてしまうような低い声で私の名前を呼ぶ。
店では店長とバイトという関係ながら、実は私たちは同じアパートの部屋で同棲している恋人であり、それも私にしては珍しく、一年という長い付き合いの彼氏だった。その彼氏の機嫌が極限に悪い。まずい――私は立ち上がりかけたが、時はすでに遅いようだった。
「あのさあ」
伊藤は仁王立ちになって私を見下ろした。
「そうやって座り込んで、何? 具合悪いアピール? そういうの店でやるの、やめてくんない? そういうのって公私混同でしょ」
パシッと頭を叩かれる。ここが店だということは意識しているのだろう、恋人同士のじゃれ合いだと言われればそれ以上は反論できないくらいの軽い叩き方だ。これが家の中だったら、髪を掴まれて引き摺り回されても文句は言えない。普段は優しい人だが、彼はそれ以上にひどい気分屋でもあり、その怒りのスイッチはよく分からない場所にあるのだった。そして、今日は不運にもそのスイッチを押してしまったらしい。
「ご、ごめんなさい」
込み上げる吐き気を必死に耐え、私は笑顔をつくって立ち上がった。ふらつく足に力を込める。無意識にお腹のあたりに当てた手を、今度は意識的にかばうように守る。
「ちょっと貧血気味だっただけだから」
顔色を伺いながら言い訳をするが、どうやらこれも彼の気に入るところではなかったらしい。伊藤の目はますますつり上がった。
「貧血? そんなの、自己管理がなってないだけの言い訳だろ」
「あ、うん、でも……」
「言い訳はいいから。大体、貧血くらいでギャーギャー言うのっておかしくない? 俺が今日、朝早かったって知ってるだろ。せっかく作ったカレーもこのままじゃ廃棄だし」
鍋に入った大量のカレーを睨みつける。機嫌の悪い理由はそれか――私は顔には出さずに納得した。彼が本部に呼び出され、食材の廃棄が多いことをどやされたと言って怒っていたのは、確か先週のことだった。ラパンは各地に店舗を展開しているが、この「三ツ池森林公園店」は、そのチェーン店の中でも売り上げが少ないことに以前から目をつけられていたというのだ。
そんなことを言われても、隣の少し大きいばかりの公園に来る、休日の家族連れが主な客層なのだから、売り上げを伸ばせと言われても無理がある――私もそう思ったのだが、本部からすればそれも「店長の努力が足りない」せいらしく、このままでは本社での出世の道も危ういという。
もちろん、それは彼の仕事の問題で、バイトの身分である私に当たられても仕方がないことなのだが、それでも仕事に問題を抱えていれば不機嫌になってしまうのは仕方のないことだろう。
「ごめん。雅人さんのほうが大変だってことは知ってるよ」
家では「まあくん」と呼んでいるのだが、そんな呼び方をしたら今度は本気で殴られそうだったのでやめておいた。
「私もちょっとふらっとしただけだから、大丈夫だから。ほら、もう治ったし」
ぎこちないながらも、もう一度笑顔を作ると、彼は嘘を見抜こうとでもいうようにじっと私の目を見つめた。それからやはり苛立ったように問い詰める。
「本当だろうな」
「もちろん」
私はほかの地雷を踏まないように、慎重に付け足した。
「だから、全然大したことないんだって。ちゃんと朝食べなかったからお腹が空いちゃった、くらいな感じなの、本当に」
「え、お前、腹が空いてんの?」
すると、彼の表情が一気に変わった。マイナスに振り切っていた針が、今度はプラスに振り切ったような明るい表情でカレー鍋を振り返る。
「じゃ、昼飯にこれ食っちまえよ。先に休憩とっていいから。その代わり、大盛り二人前な」
楽しげに言いながら、うどん用のどんぶりになみなみカレーを注いでいく。お腹が空いたというのは例え話で、その上、いくら大盛りのカレーを私が食べたところで、廃棄の量はそれほど変わらないと思うのだが、いいことを思いついたと言わんばかりに嬉しそうな顔をする彼に、私も思わず顔をほころばせた。怒らせると怖い彼だが、こんなふうに無邪気で可愛い一面もある。そして、私は彼のそんなところに幾度となく救われているのだ。
「俺のおごりだからな。ちゃんと全部食えよ」
まかないは、どのメニューも一律五百円のルールだが、その分を給料から引かないでいてやるという意味だろう。
「うん、ありがとう――ございます」
戻ってきた手嶋が心配そうにこちらを見ていることに気づいて、私は何となく語尾を正した。手嶋は、伊藤が私を殴っていることに薄々気がついているようだった。それも、それがいわゆるDVだと認識している節があった。そのアザ、どうしたの――何気なくそう聞いてくることもあったし、以前など「女性のための避難シェルター」なる団体への連絡先がバッグに入っていたこともあった。あれも私が知らないうちに手嶋が忍ばせたに違いない。
他人のことなど放っておいてくれればいいのに、どうしてお節介を焼くのだろう――私は意識的に手嶋を避けるようになった。そうでなくとも、伊藤は嫉妬深い。二人きりで話をしているところを見られた日には、よほど酷いお仕置きが待っているに違いない。
私は手嶋から目を逸らすと、何気ないふりを装って、騒動の元々の原因――店内に先ほどの二人組を探した。初老の男性と、同じ年頃の女性。はたから見れば、同じように年を重ねた夫婦にしか見えない二人。私の視線は彼らを捉え――その二人の選んだ席を見て、静まりかけた私の心臓は再び跳ね上がった。
彼らはクーラの効いた店内ではなく、ガラス扉の先にあるテラス席に座っていた。八月も終わりとはいえ、まだ日差しは十分に厳しく、頭上のパラソルが作り出す程度の日陰では暑さはまったくしのげない。にも関わらずテラス席を、しかもその一番端の席を選んだのは、何か他人に聞かれたくない話でもするせいか。それとも――。
その理由を探ろうとすると、胸の一番奥がぎゅっと痛んだ。そろそろ
でも、それならどうして二人だけで訪れるのだろう――それが次の問いだった。どうして彼らは私を誘ってはくれなかったのか。いや、それとも私が知らないだけで、彼らはたびたび会っていたのか。去年も、一昨年も、その前からずっと内緒で会っていたのか。そして私は、今日、たまたま目撃しなければ、何も知らないままでいたということなのか。
「ほら、早く食ってこいよ」
急かす伊藤の声で、私ははっと我に返った。そのまま急いで裏の休憩室へと向かう。足は血を失ったようにふらつくというのに、なみなみとカレーの入ったどんぶりを持つ手は強張っている。ドアの前で立ち止まり、震える右手を伸ばすと、いつもは気にも留めない、金色をしたドアノブが、この部屋に入る覚悟はあるのかと問いかけているように思えた。
本当のことを言えば、そんな覚悟などまったくなかった。こんな機会が訪れるなんて想像したこともなかったし、彼らも私がいると知っていれば、このレストランへ立ち寄ることもなかっただろう。だから、これは私が望んだことでも、反対に望まれたことでもない。けれど、私にはその権利があるはずだ。
心を決めると、私はノブをゆっくりと回し、ドアを開いた。むわっとした熱気がアメーバのように体にまとわりつく。一呼吸置いて小さな机の上にカレーを乗せると、私はクーラーをつけ、ロッカーから小さなポーチを取り出した。チャックの金具に揺れるお守りを握りしめる。そうしてから目を閉じて、壁の向こうへ耳を澄ました。
もし、彼らが他人に聞かれたくない話をするのなら、あのテラス席の端を選んだのは大きな間違いだった。なぜなら、二人が座ったテラス席のすぐ脇の仕切りは、この休憩室の壁を兼ねており、ラブホテルのものよりお粗末で薄っぺらいこの壁は、どんな内緒話も筒抜けにしてしまうのだ。
それを発見したのは、手嶋が来る前のバイト仲間だった噂好きのおばさんだった。不思議とあの席に座る客には秘密が多く、彼女はその内緒話を聞きたいがために「トイレへ行く」という名目で仕事をサボり、ささいな夫婦喧嘩や不倫カップルの会話を楽しんでいたらしい。しかし、そんなおばさんも半年前、「トイレ休憩」の多さに気づいた伊藤にクビを言い渡されてしまった。
その盗み聞きを、今度は自分がすることになるとは――私はしばらく耳を澄ましていたが、彼らはメニューでも見ているのか、その声が聞こえてくることはなかった。私はなぜかほっと胸を撫で下ろした。このまま何も聞こえなければ、それはそれでいいような気もする――軋む音を気にしながら、パイプ椅子に腰を下ろす。すると、鏡の中の女と目が合った。休憩後、仕事へ戻る前の身だしなみチェックのために設置された大きな姿見。その奥から、その女は私を見つめ返しているのだった。
彼女は、私が思い浮かべる「私」とはかけ離れた姿をした
だから、あの人たちは私に気づかなかったのだろうか――泣き出しそうになる女を見ながら、私はそんなことを考えた。すると、気づかないなんてそんなことが許されるはずがない――女は顔を歪めて訴えた。そうかもしれない――私は女に同情するように頷き返した。親が娘を忘れるなんて、そんなことが許されるはずがない――。
私は鏡から目を逸らすと、薄い壁をじっと睨んだ。
親と、娘。そう、あのテラス席の二人組は紛れもない、私の両親だった。ある事件をきっかけに、いまはばらばらになってしまったけれど、それ以前まで、私たちはどこにでもいるような、幸せな家族だったのだ。
涙の気配にまぶたを閉じると、クーラーの稼動音の向こうから、子どもたちがはしゃぐ声が聞こえた。その声はさほど遠くはない――ラパンのある三ツ池森林公園から響いてくるものだった。私はその無邪気な声に強い郷愁を覚え、唇を噛み締めた。
このラパンなんてレストランが影も形もなかった頃、私はこの公園で遊んだことがある。いや、
三ツ池森林公園はその名の通り、敷地に三つの池がある公園だったが、そればかりではなくゴーカート乗り場や、三十分百円の変形自転車乗り場、それにたくさんの遊具が置かれたアスレチック広場まである、とても広い公園だった。中でも人気なのは長いローラー滑り台で、全長は約百六十メートル。昔は日本一長いローラー滑り台がある公園として有名だったらしい。
あの頃、私たちはここを「うさぎの公園」と呼んではいたけれど、いま、この公園にうさぎはいない。けれど、私たちが幼い頃にはいたのだろう。わざわざ家から持って行ったニンジンを、うさぎにあげた記憶があるし、抱き上げるとキューキュー鳴いて可愛かったことも覚えている。
それからほかに覚えていることといえば、お気に入りの公園ではあったけれど、家から遠く、それほど頻繁に連れて行ってはもらえなかったということ。それから、子供だった私はその長いローラー滑り台が大好きで、何度もあの長い階段を登っては滑り降りてを繰り返していたことだった。
そういえば、あのときの母は幾つだったんだろう――脳裏をそんな思いがよぎった。子供の私に付き合って、何度も階段を登ってくれた母。その母に押され、勢いよく私が滑り出すと、景色の先には父がいて――そう、その手にはコンパクトカメラが構えられていた。そしてその父の傍に、もう一人――蘇らせたくない記憶を、それでも渋々蘇らせるように、私はその小さな影に目を向けた。真紀――それは私の妹だ。
握り締めた手を開き、私はポーチについたお守りを見つめた。それは昔、私が家を出て、寮付きの高校へ入ったときに、母がくれた手作りのお守りだった。長い間、カバンに入れっぱなしにしていたため、紐はよれ、口が開きかけていたが、表についたリボンはしっかり縫われていて、取れるような気配もない。その中央にピンクの宝石を模したプラスチックがついている、色あせた虹色のリボンは、私の大切な思い出の品だった。
――それ、「シャルル」のリボンでしょ?
手嶋の声が耳元でしたような気がして、私は思わず顔を上げた。いままで、存在さえ指摘されることのなかったこのリボンの素性を、手嶋に言い当てられたのは、ついこの間のことだった。その驚きがまだ胸に残っていたのだろう。アニメオタクだとは聞いていたが、まさかこんな古い――しかも少女向けのアニメまで知っているとは思わなかったのだ。
美少女仮面シャルル――それは、私たち姉妹が大好きだったアニメで、「シャルル」はその主人公の名前だった。普段はただの中学生、けれど
実は、私たちがうさぎの公園を気に入っていた理由はそこにあった。あの長いローラー滑り台はシャルルの虹に似て、変身ごっこをするのにおあつらえ向きの場所だったのだ。いまは思い出すことのできないその呪文を大声で叫びながら、滑り台を先に滑っていく真紀を、私は思い出した。お姉さんだった私は、真紀のように叫びたいと思いながらも、恥ずかしくてそれができなかった。だから、私は八つ当たりのようにそのストレスを妹へ向けた。
『真紀は呪文、言わないでよね! 由紀がシャルルなんだから!』
しかし、そんなことを言われて引き下がる真紀ではない。私たちはそうしていつも喧嘩した。真紀は四歳も離れた妹だったから、勝つのはたいてい私だった。そうなると、真紀は拗ねてブランコの方へ走って行き、私はシャルルの座を手中に納めるのだが、身勝手なもので、そうなると途端につまらなくなって、滑り台をやめてしまうのだった。
――オル・フォル・ギュネス。
忘れていた呪文がふと蘇り、私はぎょっと体を強張らせた。オル・フォル・ギュネス、確かにそんな呪文だった。いま繰り返すと、ラテン語か何かのようだ。となると、何か意味がある言葉なのだろうか――ぼんやりと考えていると、胸のどこかに引っかかりを感じた。そんなはずもないのに、私はこの呪文の意味を知っているような、誰かから聞いたような、そんな気がして考え込んだ。けれど、結局そこからは何も思い出せないまま、私の心は再び過去へと戻っていった。
あの頃――子供だった私はシャルルになりたいと思っていた。もちろん本気ではなかったと思うが、なれるものならなりたいという、憧れの存在だった。食玩についてきたこの小さなリボンで変身し、悪と戦い、人々を守る、そんな正義の味方になりたいと、私はあの頃思っていたのだ。大人になり、世の中を知ったいまでは、馬鹿みたいな話だけれど――私は口を歪めて少し笑った。
実際の世の中には、シャルルのような
このアニオタが――手嶋がミスをするたび、伊藤はそう言って舌打ちしたが、それも仕方のないことだろう。このリボンを一目見て、シャルルだと目を輝かせるなんて、大人になりきれていない子供だという証明にほかならない。前の会社をどんな理由でクビになったのかは知らないが、善が報われ、悪が滅ぼされると、本気で思っているような幼い精神をしているからこそ、四十にもなるのにバイトなどしていられるのだ。
「季節の欧風カリーとラパン特製サンドイッチです。ご注文の品は以上でよろしいですか」
そのとき、ちょうど壁の向こうから聞こえた手嶋の声に、私はどきりとして耳を澄ませた。しかし、彼らは頷いただけだったのか、「それではごゆっくりどうぞ」という手嶋の妙に優しげな声が、再び聞こえただけだった。あとには誰もいないかのような沈黙が残った。遠いはずの子供たちの声が、やけに大きく耳に響き、私はそこに広がっているはずの光景に思いを
昔、私の母がそうしたように、母親たちは子供に付き合って、あの長い階段を登っているのだろう。父親たちは滑り台の終わりで、コンパクトカメラ――ではなく、いまはスマホを構えているのだろう。ばらばらに断絶した、かつて家族だった人間たちがここにいることに気づくこともなく、彼らは日常の幸せに浸っているに違いない。
話すより先に食べることにしたのだろう、壁の向こうからはスプーンが皿に当たる小さな音が聞こえた。家族とは何だったんだろう――その静かな物音に集中していると、胸の奥からじわじわと苦いものが染み出した。
家族が家族でなくなったのは、いまから二十五年前、私が小学五年生のときだった。その日、私が家に帰ると、玄関の前には人だかりができていた。どうしたのだろう、私は立ちすくんだ。すると、人々の間から、取り乱した様子の母が飛び出してきた。かと思うと、私の肩を強く掴んでこう言った。
『どうして真紀と一緒じゃなかったの!』
その声は別人のように低く、目は恐ろしく血走っていて、驚いた私は思わず後ずさった。どうしたの――尋ねる前に、警察官が母を私から引き離した。私は婦人警官に連れられてパトカーに乗り、そこで真紀が殺されたことを知った。それは私とシャルルの座を争っていたライバルが永遠にいなくなったという知らせであり、同時に、それが私にとっての「雨ヶ谷真紀ちゃん殺害事件」の始まりだった。
事件の始まり、などと言うと、何だか奇妙に聞こえるかもしれない。けれど、私の人生にとってあの事件は確かな
地味で平凡だった私の生活は一転、人々の好奇の的となり、私はどこへ行っても私のことを
私が「真紀ちゃん」の姉の雨ヶ谷由紀だということは、町の人だけではなく、当時、ニュースを見た日本中の人々の知る事実だった。それは決して大げさな言い方ではない。私は一歩外を歩けば「ほら、あの子」と指をさされて井戸端会議のネタを提供し、「可哀想にねえ」という慰めや同情の声を一身に受けた。学校に行けば、先生やクラスメイトは私を遠巻きにし、ひそひそと噂話を始めた。中には、私が有名になったことが気に入らないらしく、すれ違いざまに睨んでくる女子もいた。反対に優しい顔をして近づいてきて、何とか噂以上の事件の話を聞き出そうとする子たちもいた。
また、実際に会う人ばかりではない。家の電話にはニュースで事件を知ったという、会ったこともない親戚や、保育園時代の友人だと名乗る子、驚いたことにまったく関係のない他人からさえ、コールがひっきりなしにかかってきていた。「雨ヶ谷」という苗字は珍しく、彼らはその苗字を頼りに電話帳を辿ってきたのだった。
それでも、その内容が同情や励ましなら、まだ良かった。中には、「小学一年生に一人で留守番をさせるなんて」という非難の電話や、「神様を信じないからです」というわけの分からない電話もあって、私たちを疲弊させた。
責められるべきなのは、私たちではなかった。真紀を殺した犯人の村野正臣という男だった。だというのに、村野は拘置所だかどこかの檻の中で静かな時間を過ごし、私たち家族は騒がしい渦の中に飲み込まれていた。何と不公平なことだろうと、いまでも私はそう思う。祖父母の家に避難してさえ、私たちは夜、ゆっくり眠ることもできなかった。なぜなら、私たちの行く先々に金魚の糞のようについてきたマスコミは、夜になっても家へ強烈なライトを浴びせ続けたからである。
それでも真紀が死んでしまって――殺されてしまって、私は多分悲しんだんだろうと思う。きっと涙を流したんだと思う。けれど、いま振り返る記憶の中に、そんな光景は一つもなかった。覚えているのは、私を見る
いや、特別になったのは真紀も同じだった。良くも悪くも、妹は普通の女の子だった。その死こそが彼女を特別にしたものの、生きていれば日本中の人々が知るニュースなどとは縁のない、平凡な人生を送っていたはずの人間だった。
けれど実際には彼女は死に、その名前は有名になった。そして望みもしないのに、私はそのおこぼれに預かってしまった。死んでしまった真紀はそんなことを気にすることもできないだろうけれど、生きている私にとって、それは
私はかつて、無害な
けれど、真紀は殺され――事件は私を当事者にしてしまった。あの子が妹を殺された子だよ――抜け殻のような私を指差す
それでも私は元の場所に戻りたくて、もう一度仲間に入れて欲しくて、うろうろとその周りをさまよった。けれど日和見菌たちは、決して手を差し伸べてはくれなかった。私という当事者に触れてしまえば、その誰かは
もちろん、彼らの中には特別な私を
どうすればいいのか分からなくなった一人ぼっちの私は、耳を塞ぎ、俯いて道を歩くようになった。それは家に帰ってさえ同じだった。父や母の前でも、私はどういう顔をしたらいいのか分からなかった。私たちは家族で、同じ当事者だった。けれど、それは決して同じ立場であるという意味ではなかった。
なぜなら、私が失ったのは
誰が一番悲しんでいたか、その深さを比べる気はない。けれど、私と両親のそれを比べれば、私の悲しみは明らかに小さかったのではないかと思う。そうでなければ、真紀の死に涙を流したかどうか思い出せないなんてことはないだろうから。
あの日、私が真紀と帰らなかったことを、母は二度と責めることはなかった。けれど、代わりに口数もめっきり減って家事も
そんな生活が四年続いた。私は中学二年生になっていた。けれど結局、その果てに待っていたのは断絶だった。長い間、呆けたように黙りこくっていた母は、突然記者会見を開き、村野の死刑を取りやめてほしいと訴えた。そして、寝耳に水のその会見に怒った父は、荷物をまとめて元の家へと帰ってしまった。由紀はどうする――アパートを出る直前、こちらに背を向けた父の低い問いが忘れられない。
あのとき、私の頭は「真紀が殺された家には帰りたくない」という思いでいっぱいで、黙って俯くことしかできなかった。そうしている間に父は行ってしまった。まるで少女のように頰を紅潮させた母が帰ってきたのはその後だった。彼女は部屋に入るなりテレビをつけ、画面の中の自分を食い入るように見つめた。そして私を振り向いた。
父についていかなかったことを後悔したのはそのときだった。分かるわね、由紀――妙に優しい声で母は言ったのだ。被害者遺族である私たちこそが、村野
その顔には、久しく見ることのなかった微笑みが浮かんでおり、私の背筋をぞっとさせた。母の心はあまりの悲しみに壊れてしまったか、そうでなければ変な宗教に入ってしまったのではないかと思われた。
私は絶望した。私は「妹が殺された私」という存在として、ただでさえ普通ではなくなってしまったというのに、母は「愛」とやらに目覚め、愛想を尽かした父は出て行ってしまった。いや、後になって思えば、その父も十分に壊れておかしくなっていたのだ。そうでなければ、血の染みが残る殺害現場に戻って暮らせるはずがない。例え、それが父にとっては愛しい娘の血だったとしても、気味が悪いことには変わりない。普通の人間ならば、そう思うはずだ。
そして、私はもう一度「普通の人間」に、あの自由で何も考えずにいられる日和見菌たちの世界へ戻りたかった。ならばするべきことは一つだった。おかしくなってしまった両親や、私の顔を知る人たちの元から離れ、すべてをリセットすることだ。
私は必死で勉強に励み、誰も私のことを知らない他県の全寮制高校への進学を決めた。その頃には両親の離婚が成立していたため、私は母の旧姓を使い、梶田由紀として新しい生活を始めた。離婚のとき、父はその預貯金をそっくり私のために残してくれていたため、お金の心配がないのはありがたかった。そうして私は再び
私の望みは、ニュースで流れる殺人事件にさも同情しているような声をあげ、パンダの赤ちゃんが生まれたというニュースに歓声を上げ、芸能人の結婚に喜んだり悲しんだりすることだった。けれど、特別でいた時間が長すぎたせいだろうか、私はもう元に戻れなくなってしまった自分に気がついた。どのニュースにも当事者がいることを、私は知ってしまった。だから私はニュースよりも、その当事者のことを思い、日和見菌たちのように振る舞うことができなくなっていたのだった。そう実感したときから、私のすべてはだめになった。
高校を卒業し、就職した会社は、たった半年で辞めることになった。その会社は社員同士の仲がとても良かったのだが、私はその輪に入れなかったからだ。すぐに見つけた別の会社も、同じような理由で辞めてしまった。そして次に見つけた会社も、その次に見つけた会社も――。
若いうちはそれでも選り好みさえしなければ、転職先は見つかったが、三十を過ぎる頃になるとバイトしか見つからなくなった。それはプライベートも同じだった。恋人と呼べる人はできるのだが、過去を語るような段階に入ると、別れを切り出さずにはいられなくなる。
黙りこくる私に、たいていの人が腹を立て、あるいは呆れ、去っていった。けれど、やはり私は俯き、耳を塞ぐことしかできなかった。いつでも私の足元は過去から染み出した泥で緩んでいた。今度こそ前を向いて行こうと思うのに、うまく歩けないのはそのせいだった。過去は変えることはできない。逃げることもできない。それならいっそ、何もかも終わりにしてしまいたい――。
人は死を考えたとき、最後に懐かしい場所を訪れたくなるのだろうか。私にとって、それはこの公園――うさぎの公園であったようだった。
おかしな話だが、うさぎの公園が「うさぎの公園」という名前でないことに気づいたのは、そのときだった。「三ツ池森林公園」という、その聞いた覚えもない、無感情な名前に、私は凍りついたように立ち尽くした。そんなことがあるはずもないが、真紀を失ったことで、うさぎの公園の魔法が解け、三ツ池森林公園という見知らぬものに変わってしまったのかもしれないと思った。またうさぎの公園へ行こうね――だから
家族はなく、約束もなく、仕事も、未来さえも見えない、そんな私の横を、かつての私たちのような親子連れが通り抜けた。手を繋いだその後ろ姿を、私は背中で見つめていた。
あの日
悲しくなった私は、そこにうずくまり、泣き出した。このまま死んでしまえたらどんなにいいかと思っていた。そんなときに、声をかけてくれたのが彼――伊藤だった。伊藤はラパン特製のココアを差し出し――それもこのカレーのように、作りすぎて余っていたのかもしれないと思って私の口元は少し緩んだ――話を聞いてくれた。そして意外な反応をした。それから私は彼と付き合っている。
「……変わらないな」
そのとき、壁の向こうから声が聞こえた。父の声だ。その懐かしい声に私は思わず口を押さえた。
「あなたは痩せたわ」
母の声が続けて聞こえた。しかし、その声はどこか緊張しているようだった。予想とは裏腹に、二人は長い間会っていなかったのだろうか――ちらりとではあるが、先ほど久しぶりに見た二人の顔を思い浮かべる。
電話すらかけなくなった母の顔を見たのは八年ぶり、父に至っては判決のとき以来になるはずだから、二十年ぶりにもなるだろうか。聖母めいた微笑を浮かべる母は変わったように見えなかったが、父は母の言うようにずいぶんと痩せたようだった。それだけでなく雰囲気も変わっていた。隠しても隠し切れない怒りは、まるで檻の中からこちらを睨む猛獣のようだった。まさか病気だろうかと、私は不安になった。母も同じ不安を口にしたが、父はその疑いをきっぱりと否定した。
「別に病気じゃない。毎朝、走っているせいだ」
「走ってる? また柔道でも始めたの――」
母は質問の途中で、言葉を飲み込んだ。私もつられて息を飲んだ。不安になるような、長い沈黙。その後、父の低い声が聞こえた。
「あいつはどこだ。お前は知ってるんだろう」
――
一拍おいて、心臓を直接殴られたような衝撃が走った。吐き捨てるようなその言い方、憎々しげなその調子。それを聞けば、
反射的に考えた直後、二十五年という月日がずしりと重たくのしかかった。二十五年。あれからそれほどの年月が経ったのだ。それが刑として長いのか短いのかは分からないが、少なくともまだ私はあの事件の中にいて、その月日が立ち直るには不十分なものであることは知っている。しかし、一方でそれが仮釈放されるのに十分な年月であったとしたら? 膨れ上がる疑惑を決定づけるように父が続けた。
「一昨日、桜の押印のない手紙が届いた。あいつは仮釈放された。そうなんだろう?」
「……手紙にそう書いてあったっていうこと?」
探るように母は尋ねた。すると、馬鹿な質問はするなとでもいうように、父は鼻を鳴らした。
こんなことをする人だっただろうか――私はたじろぎ、思い出したように下腹に手を当てた。もしかしたら、それはあの大きな熊のような体型のせいでそう見えていたのかもしれないが、私の知っている父はとても温厚で、かつ勇気のある人だった。その昔、職場でいじめられていた母を助けたのが馴れ初めだと、母本人から聞いたこともある。そんな人だからこそ、父は真紀が死んだ後も、母に代わって家事をし、学校の面談にも来てくれたのではなかったか。それがどうしたことだろう。
「あいつからの手紙なんか読むわけがない」
以前からは考えられない、荒っぽい口調で父は言った。
「どうせ仮釈放のための実績づくりだ。そんなもの、俺が読んでどうなる」
「どうなるって……そんな。村野さんはずっと返事を待ってたのに」
対して母のほうは、私が家を出たときと、さして変わっていないようだった。父は再び鼻を鳴らした。
「返事? 馬鹿も休み休み言え。何で俺がそんなもんを書いて、あいつを赦してやらなきゃならないんだ?」
「いえ、赦してやるとかやらないとかじゃなくて……」
「いや、そういうことだ。あいつからの手紙を開けた時点で、俺の負けだ」
「勝ち負けの問題じゃないでしょう」
「じゃ、どういう問題だ?」
「どういうって……そもそも謝罪の手紙だと分かっていて読みもしないだなんて、人間としてどうなんですか」
「なら、お前はあいつがやったことが人間としてどうだと思ってるんだ?」
母は言葉に詰まった。しかし、それでも振り絞るような声で言い返した。
「村野さんはちゃんと罪を償って、更生しました。私はずっとそれを助けたんです。手紙を書いて、面会に行って」
「あのクズに
恫喝するような声で、父。母は怯えたように黙ったが、勇気を振り絞るように言い返した。
「村野さんはクズじゃありません。刑務所の人もそれを認めたから、仮釈放されたんです。手紙も読まないあなたは知らないでしょうけど」
「クズが更生するもんか」
すると、父は笑うような声を出した。けれど、その顔が笑ってなどいないだろうことは、壁越しにもよく分かった。彼は続けた。
「いいか。普通の人間は人を殺さない。どんなに金に困っても、嫌な目に遭っても、口で『殺す』とは言ってはみても、それを実行するやつなんかいない。それなのに、偶然見かけただけの子供の後をつけていって殺す? そんなやつはクズ以外の何物でもない。本性からして狂ったクズなんだ。そんなやつが反省なんかするわけがない。そうだろ? 俺たちとは人間が違うんだから」
「誰だって間違いを犯すことはあるわ。私だって――」
「間違いで人を殺したことがあるのか?」
「そうじゃない。でも、村野さんは虐待とか、これまでいろいろ苦しい思いをされてきて」
「虐待された人間は、全員人殺しになるのか?」
「だから、そうじゃないってば! そのほかにもいろんな要因が重なって」
「真紀が死んだ妹に似てた、とか?」
「そうよ。だから彼は」
「妹に似た真紀を殺した。なぜだ? 理屈が分からないのは俺だけか?」
「もうやめて! 村野さんの気持ちは、あなたみたいに愛されて育った人には分からないのよ!」
母はとうとう小さく悲鳴をあげた。テーブルの上で飛び跳ねたらしいスプーンの金属音が、その悲鳴に重なった。
「私たちには分からないものがそこにあるのよ! だから村野さんは間違いを犯した! でもその罪はちゃんと償われて、もう彼は更生したの! あなたが何と言おうが、彼はもう赦されたのよ!」
呼吸音まで聞こえるような、長い沈黙が後に続いた。あの日、最高裁のさなかに父がアパートを出て行ってから、これがほとんど初めて持たれた話し合いの場なのだということに、私はその雰囲気から気づかされた。両親の会話は、それほど過去に囚われていた。死んだ真紀のことで頭はいっぱいで、そこにもう一人の娘がいたことを――そしてその娘はまだ生きているのだということを、思い出す余裕もないようだった。
「……あいつはどこにいる。仮釈放された後の行き先はどこだ」
一気に熱を失ったような、冷え切った声で、父が再び尋ねた。憎しみを隠そうともしない父。トレーニングで体を絞り、執拗に村野の居場所を聞く父。彼が何を望んでいるのか、何をしようとしているのか、冷たい水が染み込むようにじわりじわりと、私は少しずつ理解していた。聞きたくもないその質問を母が投げた。
「どうして聞くの? 普通の人間は人を殺さない。そうするのは狂った人だけなんでしょう?」
その声はすがるような響きを含んではいたが真剣で、決して皮肉を含んだものではなかった。問いに、父はすぐには答えなかった。けれど、その無言の間こそが、彼が心から
ああ、そうだったのか――私は心に大きな穴が空くのを感じた。二十五年もの間、父はそれだけを考えて生きてきたのだ。生きている私ではなく、死んだ真紀のことだけを考えて。
「どうして」
長い沈黙の後、ぽつり、つぶやくように母が言った。
「昔は、そんな人じゃなかった。あなたはもっと――善い人だった」
「善い人?」
冷めた父の声が繰り返した。
「子どもみたいなことを言うな。俺は何も変わらない」
「いいえ、あなたは善い人だった。だから、あのときだって私を助けてくれたんじゃない」
「何の話だ?」
「覚えてないの?」
「さあ。いまの俺には何もない。あいつが奪っていったからだ。だから、俺はあいつを許さない。あいつをこの手で殺して――」
不意に父は言葉を切った。母の前で決意を口にしてしまったことを、悔やむように黙りこくった。それは邪魔されることを嫌がってのことか、それとも――。
けれど、そんなことはどうでもよかった。私は押しつぶされそうになっていた。父は村野を殺すつもりなのだ――それが予感ではなく、確信に変わってしまったという衝撃で。
その衝撃の波がゆっくりと引いていくと、今度は目から、次から次へと涙の粒が湧き出した。喉の奥から嗚咽が漏れ、それはどんなに歯を食いしばっても止められるものではなかった。会話に耳を澄ますこともできず、私は机に突っ伏すようにして泣きじゃくった。
私は父が殺人を犯そうとしていることが悲しかったわけではなかった。もし、父が復讐を遂げ、私の
村野を殺した父は、
ぎゅっと下腹に痛みが走り、私はそこを強く押さえた。もし、ここで倒れたら――馬鹿な考えが頭をよぎる。私が倒れ、騒ぎになったら、両親は私がここにいることに気づいてくれるだろうか。私の存在を思い出し、名前を呼んでくれるだろうか。
咄嗟に壁を破り、姿を現したいような衝動に駆られ、私は椅子から立ち上がった。次の瞬間、ひどいめまいに座り込む。この頃続いている、ひどい貧血。その原因は分かっている。私は抱きしめるように下腹を押さえた。
私のここには赤ちゃんがいる。まだ胎動も感じられない、小さな存在が私のお腹で育っているのだ。
もし、私が妊娠していることを知ったなら――三十路も半ばを過ぎた娘のお腹に赤ん坊がいることを知ったなら、父はその子のために殺人犯になることをやめてくれるだろうか。母は村野にではなく、この子に愛を教えてくれるだろうか。私たちは家族に戻れるだろうか。
そのどれも、儚い望みだということは知っていた。けれど、どうしてもその望みを手放せず、私はさらに泣きじゃくった。壁の向こうに聞こえるくらい、声を上げて泣き続けた。
「梶田さん、店長が食べたら戻れって言ってますけど」
休憩室のドアを開けた手嶋が驚いた顔で立ちすくむ。それでも私はだだをこねる子どものように、大声を上げて泣き続けた。