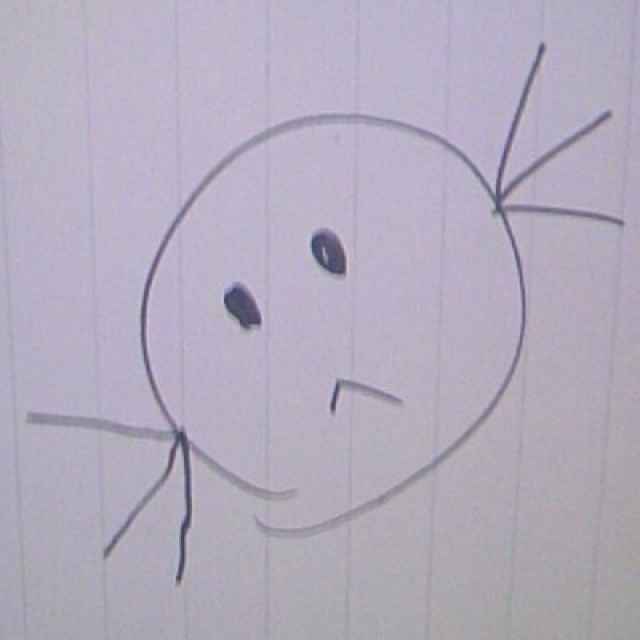4.
文字数 13,585文字
「はあ、はあ……やっぱりそうか」
部屋のドアは、昨夜クローブにぶち破られたはずだったのに何事もなかったかのように元通りになっていた。何度か開閉したが、使用に問題もないみたいだ。
「今朝、部屋を出た時の違和感の正体はこれだったんだな」
「つーか、普通はすぐ気付くでしょうが……」
キェーンは呆れ顔でこちらを見ている。
「これを直すのに、何か道具を使ったのか?」
「いいえ。素手でちゃちゃっとやっただけよ」
首を横に振って答えたキェーンは、足をバタつかせる。ああ、そういやキェーンを抱えっぱなしだったな。
キェーンを解放すると、俺はさっきの首輪の件も含めて今一度キェーンの力について考えてみることにした。
「こういう物をいじくるのが得意」とキェーンは言った。
魔導ロック式の首輪に、魔法により強化されたドア――
この二つの共通点は、マジックアイテムということだ。
何らかの魔法の力が付与されていたり、使用者の魔力に反応して特別な動作を起こしたりする道具の総称をマジックアイテムというわけだが、どうやらキェーンの言う「こういう物」とはマジックアイテムのことではないだろうか。
ちなみに、先程の実験場で、キェーンが押しても引いてもびくともしなかったブロックはマジックアイテムでなかった。
「よし、ちょっといくつか試させろ!」
思い立った俺は机からいくつかのマジックアイテムを取り出した。
発光効果のある魔法石を使用した筒状のハンディライト、強化魔法の施された燃えにくく刃物でも切れにくいロープ、使用者の意思に反応して柄が伸縮するホウキの三点。これらは実家を出る時に両親が半ば強引に持たせたマジックアイテム達の一部だ。
「これ全部、好きにいじっていいぞ。気に入った物があったらお前にやる」
「え、本当に? どれどれ……」
突然の俺の申し出にキェーンは驚いた様子を見せたが、すぐにマジックアイテム達に飛び付いた。そして、無邪気にそれらで遊び始めた。
ハンディライトを付けたり消したり、ホウキを部屋いっぱいに伸ばしたと思ったらすぐに縮めたり、どちらも使い方を教えたわけでもないのにもう使いこなしてやがる。
「キェーン、そのロープはどういう物かわかるか?」
「これ? これは魔法の力で普通より丈夫にしてあるんでしょ。材料となる繊維に魔法の影響を受けやすいよう薬草の汁を染み込ませてあるわね」
こいつ……本当に手に取っただけでわかったのかよ。
その後も、ハンディライトを分解してすぐにまた元通りの形に組み直したり、強化魔法が施されているはずのロープを力も入れずにぷつりと断ち切ったりと、俺の取り出したマジックアイテムを思う存分いじくり倒した。しかも、全て素手でだ。
うーん。やっぱりこいつの能力って、マジックアイテムを好き勝手扱うことができるって能力なんだろうか……
「――ちくしょう、なんだよそれ」
生き生きとした顔でマジックアイテムを手にしているキェーンを見ていると、胸の辺りがモヤモヤしてきた。
――こんな光景は、見ていて腹が立つ――
「あれ? あんたどこ行くのよ?」
「昼飯だよ……ついてきたけりゃ好きにしろ」
食堂が開く時間まではまだ少しあるが、今はとにかくこの場にいたくなかった。
くそっ、もうこんなことでウジウジするのは嫌だったのに。
いや、このゴーレム科にいるうちは、俺はずっと――
キェーンは俺に少し遅れて食堂に到着し、その姿を見つけてタンケルが駆け寄ってきた。もちろん、その背後にはクローブの姿もある。
「ダーリン、私が席を確保しておこう。中庭が見下ろせる二階のテラス席がいいかな?」
「ああ、頼むよ」
クローブはそう言うとテーブルの方に向かっていき、その姿を見ていたキェーンは俺の顔を一瞥してからクローブの後を追っていったのだった。
大盛りのパスタとサラダを食堂のおばちゃんから受け取り、俺とタンケルはクローブが確保していたテーブルに着席した。
食堂はゴーレム科以外の生徒から教員、果ては学校の警備員も分け隔てなく利用するので多くの座席が必要なため、三階建ての建物になっている。
「タンケル。お前、図書館で何調べてたんだ?」
パスタを食べながら俺はタンケルにそんなことを聞いてみた。
「ちょっと引っかかることがあってな。なあ、クローブ。少しの間席を外してくれると有りがたいんだけど……」
「うむ。男同士の話を邪魔するのは野暮というものだ。お嬢ちゃん、君も一緒に来るんだ」
「あ、ちょっと――」
クローブはあっさりと了承し、キェーンを片手でつまみ上げるとなんとテラスから飛び降りて中庭に着地した。そして、呆気に取られた俺達に笑顔で手を振るのだった。
「お前のゴーレムってなんというか豪快だよな……その、見た目通りというか……
それで、引っかかることってなんだ?」
「ああ、クローブのことさ」
「なんだよ。もう彼女の能力はわかったんじゃねえの?」
もうクローブの能力はあの怪力だと判明したはずだろうが。
「まあ聞いてくれ。さっきまで調べてたのは、あいつの見た目や性格に関することだよ」
そう言うとタンケルは鞄から古ぼけた本を取り出した。
「『ゴーレムの性格と容姿への生成者の心理反映説』……?」
こりゃまたずいぶんと難しそうな本だ。
「さて、本題に入る前に言っておきたいんだが……俺は美少女が好きでしょうがないということは知ってるよな?」
いきなり何言ってんだこいつ。そりゃあ知ってはいるが――お前の将来が不安になるくらい。
「それは知っている。で、美少女ゴーレムを大量に生成して、ハーレムを作るのがお前の夢なんだろ? 初生成でクローブができたおかげで夢に近付いたみたいじゃん」
俺がそう言うと、タンケルは身を乗り出して反論してきた。
「違うんだ! クローブは違う! 確かにあいつの見た目は美女だ。だがな、俺の好みである美少女ではない! 色々と――デカ過ぎるんだよ!」
「わかったから落ち着け! まあ、少なくともあれは少女って感じじゃないな。大人の色香漂う豊満な美女って感じで……」
「そうなんだっ!」
今度はバンっと大きな音を立ててテーブルを叩き、タンケルは唸った。
「ああいう年上のナイスバディはむしろ苦手なんだよ! 俺を子供扱いしているようで、そこら辺も気に食わん! あと、あけっぴろげに愛を語るのも正直好かない! 俺の好みは小じんまりとしているというか、見た目も中身も幼いというか、性格は慎ましやかというか――」
「落ち着けって! 周りの目を気にしろお前は!」
どんどん語調が強くなっていくタンケルを制す。こいつ、自分の趣味嗜好の話になると途端に熱くなるな。
「つまり、俺は自分の好みと正反対のゴーレムが生まれてきてしまったことに納得がいかなかったんだ。それで、図書館でその原因を解明できそうな文献を探して――たまたま見つけたのがこれ!」
やっと本題に戻ってくれたみたいだ。タンケルは『ゴーレムの性格と容姿における心理反映説』をパラパラとめくり出した。
「この本はゴーレム専門の魔法研究家の論文をまとめたものなんだけどな。簡単に言うと、俺達のした生成方法によって生まれたゴーレムの見た目や芽生える性格には、生成主の心理が影響しているって説について書かれてあるんだよ。あっ、心理っつーのは本人でも把握できてない深層心理を含むみたいだ」
――生成者の心理?
「じゃあ、タンケルはその説を知ってクローブみたいなゴーレムが生まれてきたことに納得できたっていうことなのか?」
「うん。全て受け入れられたってわけじゃないけどな。でも、この本に載っている実例を見たら色々と納得できる部分も多くてさ。例えば、小さい頃に猫に食いつかれて以来猫が苦手な奴がゴーレムを生成したら猫型ゴーレムが生まれてきたとか、天使に憧れを持ってるちょっと夢見がちな女の子がゴーレムを生成したら人型に羽根の生えたゴーレムが生まれたとかな」
「そんな……俺達がやった方法はどんなゴーレムが生まれてくるのかコントロールできないんじゃ……」
そうだ。手順さえきちんと踏めば成功率が非常に高くなる代わりに、どんなゴーレムが生まれてくるか操作、予測できないというのが、俺達が初生成で行った方法なわけだが……
「うーん。俺だってこの本を読んで全部内容を理解できたわけじゃないけど、コントロールできないからこそ生成者の心理が変に反映されちゃうんじゃねえの? 気になるならターロも読んでみろよ。あと、読み終わったらついでに図書館に返しといてくれ」
タンケルはそう言って俺に本を渡すと、立ち上がって中庭の方に目をやった。
「まあさ、ちょっと頭に引っかかってたことを晴らすヒントを見つけたから、俺としてはよかったよ」
「知ったところでクローブがお前好みの小じんまりした美少女になるわけでもないだろ」
「ははは。たしかにそうかもな。でも、何も知らないで過ごすよりは実りがあることなんじゃねえかな? ま、根拠はねえけど!」
タンケルはそう言うと笑顔を見せた。こいつ、ただの美少女好きかと思いきや前向きで探究心が強い。そこら辺が、時々すごく眩しく感じる……
「おーい。クローブ! そろそろ部屋に戻るぞ!」
中庭に向かってタンケルが叫ぶと、次の瞬間にはテラス席にクローブが着地していた。
中庭から二階のテラスまで易々と跳躍してしまうクローブの脚力は、腕力同様やはり人間離れしている。
「お、少年。お嬢ちゃんはまだ下にいるぞ。組み合ってじゃれているうちにバテてしまったようだから、少年が迎えに行ってやれ」
「あ、ああ……」
クローブに言われて中庭の方を見ると、キェーンが芝生の上で転がっていた。タンケルから渡された本の内容が気になっていた俺は、キェーンの姿を見て複雑な気持ちになってしまっていた。
心理反映説――俺のケースも当てはまっている予感がしてならない。
「ふう……」
部屋に戻った後、タンケルから借りた本も気になったが、俺はまずレポートの作成に取りかかる。とりあえずキェーンの能力がどういうものかわかったので、さっさとレポートをやってしまって残り二日をダラダラと過ごそうと思ったわけだ。
その間キェーンは俺が与えたマジックアイテムをいじっていたわけだが、さすがにマンネリ気味になってきたのか不満を口に出すようになった。
「もうこれ触るのも飽きたんだけどー!」
伸縮自在のホウキを伸ばし、柄の先で俺の頭を小突いてきやがった。
「うるさい! だったらあそこの窓でもいじってろ! この寮全体がマジックアイテムみたいなもんなんだから、どうにかできるだろ?」
「ああ、そういやそうだったわね」
この寮は魔法で強化されており耐久性が上がっているわけだが、これにより寮全体がマジックアイテム化しているといえるのだ。魔法による強化を受けた物体というものは大小関係なくマジックアイテムなのだと、以前父親から聞いたことがある。
実際キェーンは壊れたドアを直してしまったようだし、あの窓もいじくれば何らかの反応をするだろう。実は、俺の部屋の窓はメンテナンスを怠ったのか元から雑に作ってしまったのかは知らないが、立て付けが悪いのだ。
キェーンの暇潰しのついでにそれが直れば一石二鳥である。
「よし。これでしばらくはおとなしくなるか」
さっそくキェーンは窓をペタペタと触りだし、そちらに夢中になってしまった。
ふむ。こうやってキェーンを上手く利用すれば色々と役に立つのかも知れない……いや、それでもあいつがああやってマジックアイテムを好き勝手いじれることなんて……
しばらく机に向かい続け、気が付くと終礼の鐘が鳴る時間になっていた。
「おいキェーン、いったん教室に行くぞ。終礼の時間だ」
「わかったわ」
そう言うとキェーンは我先にと教室に向かって行った。ゴーレムのくせに生成者を置いていくとは……
やれやれと思いながらキェーンがいじっていた窓を試しに開閉してみると、
「――おっ」
窓は実にスムーズな動きを見せた。立て付けの悪さはキェーンによって完璧に直されていたのだった。
終礼後、タンケルと話してみるとこいつもすでにレポートの作成に入っているようだった。
「なーんだ。ターロももうレポート書けてるのかよ」
「ああ、たぶんタンケルと同じくらい進んでると思う」
「キェーンちゃんの能力ってどんなもんなの?」
タンケルは俺でなくキェーンに直接聞いた。
「ふっふっふっ。聞いて驚かないことね! アタシはなんと――マジックアイテムを自由自在に扱うことができるのよ!」
キェーンは椅子の上に立ち上がり堂々と言った。
「へえ。すごいじゃないか!」
「えっへへ。まあねえ」
「よっ! 手先が器用な美少女ゴーレムなんて、色々期待しちゃうぜ!」
「言葉の意味はわからないけど褒められてるのはわかるわ! もっと言って!」
タンケルにおだてられ照れた様子を見せるキェーン。二人共ノリノリだ。
「ダーリン! 早く部屋に帰ってレポートの続きをやろうじゃないか! さっさと終わらせて私とダラダライチャイチャと過ごすんだ!」
その光景が気に食わなかったのか、クローブがタンケルの背後から覆いかぶさった。
「うわあ――やめろっ! 離れろぉ!」
「あんたらさっきからうるさいのよ!」
バンっと何かを叩く音と大声がした。発生源は俺の後ろの席に座るユリィだった。
「ここにはまだ作業中のクラスメイトがいるんだから、少しは配慮しなさいよね!」
ユリィにそう言われて教室を見回すと、本を片手にゴーレムと睨めっこしていたり、友人同士でノートを見せ合っている生徒が何人もいた。
「あんたらみたいにさっさとゴーレムの能力が判明した人ばっかじゃないんだから……」
ユリィはそう言うとガシガシと頭を掻きながら本に向かった。その隣では彼女のゴーレムが何やらオタオタとしている。
黄土色の大きな球体に、同じく黄土色をした人間と同じ形の腕が生えているという奇妙な見た目をしたゴーレムは、言葉は発していないようだが生成者であるユリィがイライラしていることが心配な様子だ。
ああ、イライラの原因ってやっぱり――
「なに? ユリィはまだゴーレムの能力わかってないの?」
げっ、タンケルの奴あっさりそんなことを言ってしまった。
「ああそうよ! 悪かったわね。まだわかってなくて!」
ユリィは顔を真っ赤にしてこちらを睨みつける。不用意な発言をしたタンケルだけでなく、俺に対しても怒りを露わにしているみたいだ。
それは仕方ないかもしれないな。なにせ、授業に対していつもやる気を見せていない俺が順調にレポートを進めていて、いつも真面目な自分が行き詰まっているなら気分が良くないのは当たり前だろう。
とはいえ、それで不機嫌になられても俺だって困るけど。
「ダーリン。もう少し級友を気遣う発言をした方がいいんじゃないか?」
クローブはタンケルをそう諭す。さらに続けて、
「すまないなお嬢ちゃん。ダーリンは思ったことをすぐに口に出してしまう素直な性格なんだ。しかし、そこが魅力でもあるわけで……ともかく今回は勘弁してやってくれないだろうか」
「――わかったわよ。なんか、あんたらといると調子狂うわね……」
ユリィは少し顔を引きつらせてから本を閉じ、席から立ち上がった。いつもはガンガン言ってくるユリィも、クローブを相手にするといつも通りとはいかないみたいだ。
しかしユリィの浮かない顔というのもなにか見ていて……
「そうだユリィ。ユージン先輩に相談してみたらどうだ? あの人、俺達にゴーレムで困ったことがあったら何時でも相談に来いって言ってたぜ」
どこかいたたまれなくなった俺は、そんな言葉を投げかけて見た。
すると、立ち去ろうとしたユリィの動きが止まる。そして、再びこちらを向く。
「その手があったわあっ!」
この時ユリィが見せた表情と発した声は、さっきまでとは全然違っていたのだった。
「んん――でも、いざ相談に行くとなると恥ずかしいわ……けど、これを機会にさらに先輩と仲を深めるチャンスかも知れないし――あっ! 相談に乗ってもらったお礼も今から考えておかないと! 頑張れユリィ!」
教室で自問自答し始めたユリィ。そのテンションは異様に高い。
「あんたもたまには冴えてるじゃない! そういえば、ユージン先輩っていつもはどこにいるっけ?」
「あの人、基本的に自由人だからなあ。よくゴーレム科の格納庫にいるって聞くけど……」
格納庫とは教室や寮に入りきれない大きなゴーレム等を保管しておくゴーレム科の施設だ。そこの地下には国から預かった軍用ゴーレムが大量に保管されているとか、神を宿した禁断のゴーレムが眠っているとか眉唾物の噂が絶えない場所でもある。
「おっしゃあ! 行くわよ、パクチ!」
ユリィはさっきまでとは打って変わって上機嫌で教室を出て行った。あと、どうやら彼女のゴーレムの名前はパクチというようだ。
「やれやれ……」
「ユージンってあのでっかいゴーレムの?」
「ああ、そうだよ」
自室に戻る準備を始めた俺に、キェーンが少し不機嫌そうな顔で聞いてきた。
「なんか気に入らないのよね。あの男……」
「そんなこと言うな。あの人はむちゃくちゃ優秀で頼りになる先輩だぜ? あの通り、ユリィもばっちり惚れちゃってるし、非の打ちどころがない人だ」
横からタンケルが口を挟んできた。
「そうなんだよなあ。こう言っちゃなんだけど、ゴーレム科にいるのが不思議なくらいだもん。あの先輩ならクエスト 科にも楽勝で転科できたと思うんだけどなあ」
まったくだ。こんな不人気学科にいるより、エリート学科の俗称を持つクエスト科で専門研究に打ち込む方がよっぽど似合ってると思うんだが。
「人にはそれぞれ事情があるんだよダーリン。ところで、クエスト科とはなんだ?」
「この学校にいくつかある学科の中でも限られた優秀な生徒しか入れないとこさ。自分の興味関心がある分野をとことん研究する学科で、卒業が他の科の生徒より遅れることもあるくらいだ」
クローブに聞かれてタンケルが答える。そう、クエスト科はそんな優秀な生徒しか入ることができない俺達には無縁の学科だ。転科試験を受ければ他学科の生徒も入れるそうだが、先輩なら楽勝で通れただろうに。
さて、他人のことはこれくらいにして俺は部屋に戻ることにしよう。タンケルから借りた本を読んでみないといけないし。
「じゃあな。とりあえず俺は部屋に戻るわ」
「おう。夕食の時にまた会おうぜ」
「ダーリン。夜くらい学食から持ち帰って部屋でゆっくり食べようじゃないか! 二人でまったりと! そしてイチャイチャと!」
「お前はゴーレムだから飯はいらないだろ!」
「じゃあ、私があーんってやって食べさせてあげよう! 食べ終わったお口も拭いてやるぞ! もちろん食後のデザートはわた――」
「だあああっ! 俺の口を拭く前にお前は自分の口を塞げ!」
タンケルとクローブって実はすごく似た者同士なんじゃないか……
そんな二人を見つつ、俺は教室をあとにする。その後をキェーンは無言で追いかけて来た。
あいつ等に比べ、俺達は全然似ていないなあと思うのだった。
部屋に戻ると俺は机に向かい、『ゴーレムの性格と容姿における心理反映説』を読み始める。専門用語の連発や文章自体が難しいこともあって読み進めるのに苦労をしたが、読むほどに俺のケースもこの本に書いてある説に当てはまっているように思えてならなかった。
ゴーレムの容姿や芽生える性格に加え、ゴーレムが持つ能力もその生成者の心理に影響を受けたものになることがあると、この本には書かれていた。
さらには、生成者の人生における挫折、傷心の経験などにより生じた負の部分も反映されてしまうケースも見られるという。
「まいったなあ……まんまじゃねえか」
キェーンの能力、俺の人生の間で生まれた負の部分――もろに影響し合っている。
俺の実家はマジックアイテム店を営んでいる。自宅兼店舗はマジックアイテム店が多く立ち並ぶ街の一角にあり、お役所や軍からの受注、市民のための日用品販売までガンガンこなす評判の店なのだ。
親父は代々その店を受け継いできた腕利きの職人で、当たり前のように俺に後を継がせようとしていた。
だが俺は、幼い時に経験したある事件がきっかけで別の道に進みたいと常日頃から思っていたのだった。だから、親父が直接マジックアイテムに関することを教えようとしてきても俺はそれを避けて来たのだ。
今でもよく思うが、親の決めた道を進めさせられるということへの反発心もあったかもしれない。
魔法に関する基礎知識と極初歩的な実技を学ぶ初等魔法学校を出たら、マジックアイテム職人ではなくそちらの道に進みたいと両親に言おうとしたのだが、それを言い出すことは叶わなかった。
親父が掲示して来たのはエクスペリオン高等魔法学校のマジックアイテム科。マジックアイテムに関することを学ぶこの学科への進学以外は認めないと俺が言い出す前に言われてしまったのだった。
親父の頑なな態度に、俺は仕方なく夢見ていた道を諦めて親の決めた道を進んでしまおうと決めたのだった。
さらに、結婚前は役所の事務員をしていた心配性の母親は、マジックアイテム科一本の受験では心細いから一応の保険としてゴーレム科を併願で受験しておけと進言し親父もこれを了承した。
そして――マジックアイテム科、ゴーレム科の入学試験を連日受けた結果は、第一志望のマジックアイテム科は不合格。ゴーレム科は合格というものだった。
この結果を受け、親父は俺を進学させずに自分の店か知り合いの工場で修業させることを考えたが、母親との相談の末にゴーレム科への進学を選択してもよいと俺に言って来た。
――この辺のことは思い出したくもない。
あれだけ避けていたマジックアイテム店を継ぐこと。
それの下準備と言われて受けさせられたマジックアイテム科への入学試験が不合格。
小さな頃からの夢を捨て、不本意ながら現実の道を進もうと決めた後での不合格通知は、俺みたいなちっぽけな人間にとっては、あまりにも強烈な一撃だった。
選択を迫られた俺は、エクスペリオン高等魔法学校ゴーレム科への進学を決めた。
もう、マジックアイテムを扱う道のことなんて考えたくもないと思ったからである。
ゴーレム科にこうやって今いるわけだが、もちろん前向きな気持ちでいたいわけでなく――うん、ここは逃げ道でしかないのだ。
そんな逃げ道でやる気が出るわけないし、そう思いながら過ごしている自分が嫌でしょうがないという気持ちもあり――
「で、そんな俺の前に現れたのがこいつってわけか……」
「あん? なんか言った?」
「なんでもねえよ……」
俺の生み出したゴーレム――キェーン――はマジックアイテムを自由自在に操るという能力を見せつけ、ちっぽけな俺のどうしようもない心の傷を刺激しやがった。
そして、思ったことをすぐ口に出し、気に入らないとすぐ意志表明する性格についても考えさせられてしまう。いつまでも、ウジウジしている生成者の俺に比べて、このゴーレムときたら……
そんなキェーンは今も俺のベッドに堂々と陣取り、手の中でマジックアイテムを遊ばせている。
「あっ! そういや、昼間の賭けであんたに勝ったからこのベッドはアタシの物よね!」
「――げっ、忘れてた……」
そういや、そんな賭けに乗ってしまったんだった!
「ここで『そんなの取り消しだ!』とか言ったら、最高に格好悪いわよ?」
「う、うぐぐ!」
悔しい。反論しようとしても、言葉が出てこない。
「わかったよ! 男に二言はない! 第一、生成者がゴーレムに舐められてたまるかよ」
ちっぽけだ。最悪だ。あまりに格好が悪いぞ俺って……
歯ぎしりしながらも俺は毛布を引っ張り出して、それにくるまって床に寝転んだ。
そうして、何もかも頭から排除するために眠りに入る。そういえば、夕食のこともこの時はすっかり忘れていた。
翌朝。猛烈な空腹を大盛りの朝食セットで満たし俺は教室に向かう。
昨夜のこともあり目覚めはいまいちだったが、教室に入るといきなりその何もかもが吹っ飛ぶような事態に遭遇した。
「な、な、な……」
「え? うそ? なにこれ?」
驚きのあまり声も出ない俺の横で、同行していたキェーンも目を皿のようにしていた。
「おはようさんです! 本日は快晴で、朝から気分がいいですな!」
手を上げ、軽快な口調で挨拶をしてきたそいつは、教室にある俺の席に座っていた。
「ああ、そうですよね。やっぱり驚きますよね! あはは、しょうがないことですよ。
おっ、そちらはゴーレムの……えーと、名前はキェーンでしたっけ? おはようキェーンたん!」
そいつの表情は実に明るい笑顔。しかし、どこかで見た笑顔でもあった。
――ていうか、俺の顔をしている!
「何者だてめえ!」
「おお。実に的確なお言葉ですね。何者かと言われましたが――ボクとあなたはもう何回かお会いしているのですよ」
「え? もう会ってる?」
俺と同じ顔をした奴から返ってきた答えは、ますます俺を混乱させた。
よく見ると、背や体格も俺と全く同じみたいだ。
違うのは服装で、全身がタイル模様みたいな艶のある服で包まれている。そのせいで余計不気味に感じるわけだが。
「あーはっはっはっ! ターロったら本当にわかりやすい反応ね」
大笑いしながら俺に向かって言ってきたのはユリィ。その近くでは、タンケルとクローブもニヤニヤと笑っている。
「ユ、ユリィの仕業か? なんなんだよこれは!」
俺がそう怒鳴ると、自信満々にユリィは答えた。
「これぞ、私のゴーレム――パクチの能力なのよ!」
「はい。そうなんですねこれが。ボクはこちらにいらっしゃるユリィ・ドルフーレン様によって生成されたゴーレム、パクチと申します。ユリィ様がおっしゃったように、今ボクはボク自身の能力によってターロさんに姿を変えているわけなんですね」
俺の姿をしたそれは、どうやらユリィのゴーレムのようだった。
「能力によって姿を変える?」
「そう! 昨日、ターロに言われた通りユージン先輩を見つけて相談したんだけど、見事に私のゴーレムの能力はこれだって導いてくれたの! その間二人っきりで!」
「まあ、人間に限って言えば二人でしたがねえ。できればボクのことも忘れないで頂きたいです。あと、ユージンさんのゴーレムのペッパード六式殿もいましたし」
「わかってるわ――よっ!」
横から口を挟んできたパクチの頭を笑いながらユリィが叩いた。
「あ! お前、よくも俺の頭を……」
「何言ってんのよ。これは私のゴーレムの頭ですけど?」
俺は抗議したが、ユリィは見せつけるようにしてまたパクチの頭を叩いた。
これは……叩かれているのは彼女のゴーレム、パクチではあるのだが……
「目の前で自分が叩かれているみたいで気分悪いんだよ! だいたい、なんだよその服は! 全身ぴっちりな上にテカテカ光ってて、俺だったらそんな格好絶対にしたくねえ!」
そうだ。パクチの着ている服は体型にピッタリとフィットした感じの異様な服。
いや――服というか光沢を放った怪しげな素材が全身に張り付いているというか……
「先輩がくれた物にケチ付ける気? これはユージン先輩がくれた魔導素材を使ったスーツよ。どんな体型にもフィットする魔法のスーツで、これがないとパクチが誰かに変身したらその人の裸が――あっ!」
説明している途中でユリィが急に言葉を詰まらせた。
そして、顔がどんどん赤くなっていく。
「ほほう。その様子だと、もう誰かの裸を見てしまったみたいだな」
ニヤリと笑ってそう突っ込んだのはクローブ。
それを聞いてユリィはますます顔を赤くした。
「とにかく、先輩のくれた物を悪く言うんじゃないの!
パクチ! 戻りなさい!」
ユリィは慌てて指をパチンと鳴らし、パクチに指示を出した。
「はいはい!」
鈍い光を放ちながらパクチの体がぐにゃぐにゃと歪む。
これもちょっと……俺の姿がむちゃくちゃになっていくみたいで見ていて辛い……
しばらくするとパクチの見た目は昨日見たのと同じ球体になっていた。
全身は黄土色ではなくあの奇妙な服と同じ色や模様だ。所々に切れ込みがあり、人間に変身するとこの切れ込みから頭や手が出るわけか。
そして、あれだけ饒舌だったのに元の姿になると一転おとなしくなってしまった。なるほど。変身中しか言葉を発せられないわけだな。
「おーい、先生が来たぞ!」
そうこうしているうちに担任が来た。
今日は簡単な連絡だけで、本日も自分のゴーレムの能力を張り切って探しましょうとだけ言って朝礼は終わってしまった。
俺もタンケルもユリィもだいたい自分のゴーレムの能力についてはわかってきたため、午前中はレポート作成に徹した。いかに創意工夫したかの脚色も忘れず、昼前にはあらかた書き終えてしまった。
本日の昼食も学食のテラス席。俺とタンケルでの昼食になるかと思いきや、クローブが席取りをしている所にユリィがちゃっかりと入ってきてしまった。
こうして、三人と三体のゴーレムでのいつもより騒がしい昼食となった。
「私のパクチは、変身しないと喋れないみたいなの」
「ふうむ。生成者との信頼を深める上でそれはちょっとどうだろうな。まあ、私ならダーリンとは言葉に頼らない、より素晴らしく本能的というか官能的な方法をとれるわけだが――」
「やめろっ!」
すっかりお馴染みになってしまった、クローブがタンケルに絡み付く光景。毎度のことながら目のやり場に困ってしまう。
「ゴーレムとの信頼関係ねえ……」
揚げた鶏肉を口に運びながら、俺は自分のゴーレムに目をやる。キェーンはパクチが身にまとっている服をひっぱって遊んでいるようだ。
ああ、そういえばパクチのこれもマジックアイテムに分類されるんだろうな。
「ねえ、あんたはどうなのよターロ」
「なんだ?」
キェーンを見ていた俺に、ユリィが話しかけてきた。
「あんたはゴーレムと上手くやってるの?」
「……」
俺は答えられない。関係は最悪だとしか言えないからだ。
「能力がわかるだけじゃダメなのよ? ゴーレムは生成者と上手く連携を取ってこそ真価を発揮するって習ったでしょ」
ユリィはペラペラとまくし立てる。
「まあな……」
「もしかして、あんな可愛いゴーレムができちゃって戸惑ってるわけ? あんたなら有り得そうねえ……」
ふざけるなと言いたい。
確かにキェーンの見た目はちょっと浮世離れした美少女だ。
しかし、こいつは俺の魔力と血の混じったゴーレムである。異性として見るというのは少々戸惑う……
例えれば――それは家族、それも妹辺りというか――いや! 家族、それも妹ならそれはまた愛おしい存在であるはずだ! いや、俺には実際妹はいないが……
ともかく、俺はキェーンにそれに近い感情などこれっぽっちも抱いていない。
第一、家族と違ってまだこいつとは数日しか生活を共にしていないわけだし、おまけにこいつは俺の心にある嫌な気持ちを刺激する最悪の存在なのだ。
「キェーンちゃんはこいつのことどう思うの?」
ユリィの奴、俺が答えないからってキェーンに振りやがった。
キェーンはパクチの服を引っ張るのをやめ、こっちを向いた。
「うーん。簡単に言えば、パッとしない奴って感じかな。それで、最初にアタシの生成者だってわかった時はこんな奴の所に生まれちゃって嫌だなあって思った」
「おお! 言うねえ!」
キェーンは続ける。
「で、どんな奴か観察を続けてたけど、どっか心に引っかかりを感じながら過ごしてるのかなあって何となく思えてきたの。でも、それを心にしまってるみたいな?
何か不満があるなら、行動に移せばいいのになあとアタシは思うわ」
――そこまでわかっているのか。とそれを聞いていた俺は呆れてしまっていた。そして、次の瞬間、俺は周囲の反応などお構いなしに、ブチ切れていた。
「心だって? ふざけんじゃねえよ! てめえは人間じゃなくてゴーレムだろ!
それなのに心とか笑わせんな!
ゴーレムはしょせんゴーレムで、心なんかあるわけないんだよ!
――ああ、俺は不満を抱えまくってるよ! それも、山ほどな。
その不満の中で現在第一位に光り輝いているのは、てめえみたいな反抗的なゴーレムが生まれちまって、一緒の部屋で生活しなきゃならないなんて状況についてだ!
ああ、最悪だよ。本当に最悪だ!」
「な……」
「おいターロ、落ち着けって!」
俺は椅子が倒れるくらいの勢いで立ち上がっていた。タンケルに袖を掴まれるが、振り払い全速力で学食を後にした。
そして、自分の部屋に戻り、鍵を閉めてベッドに倒れ込む。
ああ、もう本当に、正真正銘に最悪だ。
部屋のドアは、昨夜クローブにぶち破られたはずだったのに何事もなかったかのように元通りになっていた。何度か開閉したが、使用に問題もないみたいだ。
「今朝、部屋を出た時の違和感の正体はこれだったんだな」
「つーか、普通はすぐ気付くでしょうが……」
キェーンは呆れ顔でこちらを見ている。
「これを直すのに、何か道具を使ったのか?」
「いいえ。素手でちゃちゃっとやっただけよ」
首を横に振って答えたキェーンは、足をバタつかせる。ああ、そういやキェーンを抱えっぱなしだったな。
キェーンを解放すると、俺はさっきの首輪の件も含めて今一度キェーンの力について考えてみることにした。
「こういう物をいじくるのが得意」とキェーンは言った。
魔導ロック式の首輪に、魔法により強化されたドア――
この二つの共通点は、マジックアイテムということだ。
何らかの魔法の力が付与されていたり、使用者の魔力に反応して特別な動作を起こしたりする道具の総称をマジックアイテムというわけだが、どうやらキェーンの言う「こういう物」とはマジックアイテムのことではないだろうか。
ちなみに、先程の実験場で、キェーンが押しても引いてもびくともしなかったブロックはマジックアイテムでなかった。
「よし、ちょっといくつか試させろ!」
思い立った俺は机からいくつかのマジックアイテムを取り出した。
発光効果のある魔法石を使用した筒状のハンディライト、強化魔法の施された燃えにくく刃物でも切れにくいロープ、使用者の意思に反応して柄が伸縮するホウキの三点。これらは実家を出る時に両親が半ば強引に持たせたマジックアイテム達の一部だ。
「これ全部、好きにいじっていいぞ。気に入った物があったらお前にやる」
「え、本当に? どれどれ……」
突然の俺の申し出にキェーンは驚いた様子を見せたが、すぐにマジックアイテム達に飛び付いた。そして、無邪気にそれらで遊び始めた。
ハンディライトを付けたり消したり、ホウキを部屋いっぱいに伸ばしたと思ったらすぐに縮めたり、どちらも使い方を教えたわけでもないのにもう使いこなしてやがる。
「キェーン、そのロープはどういう物かわかるか?」
「これ? これは魔法の力で普通より丈夫にしてあるんでしょ。材料となる繊維に魔法の影響を受けやすいよう薬草の汁を染み込ませてあるわね」
こいつ……本当に手に取っただけでわかったのかよ。
その後も、ハンディライトを分解してすぐにまた元通りの形に組み直したり、強化魔法が施されているはずのロープを力も入れずにぷつりと断ち切ったりと、俺の取り出したマジックアイテムを思う存分いじくり倒した。しかも、全て素手でだ。
うーん。やっぱりこいつの能力って、マジックアイテムを好き勝手扱うことができるって能力なんだろうか……
「――ちくしょう、なんだよそれ」
生き生きとした顔でマジックアイテムを手にしているキェーンを見ていると、胸の辺りがモヤモヤしてきた。
――こんな光景は、見ていて腹が立つ――
「あれ? あんたどこ行くのよ?」
「昼飯だよ……ついてきたけりゃ好きにしろ」
食堂が開く時間まではまだ少しあるが、今はとにかくこの場にいたくなかった。
くそっ、もうこんなことでウジウジするのは嫌だったのに。
いや、このゴーレム科にいるうちは、俺はずっと――
キェーンは俺に少し遅れて食堂に到着し、その姿を見つけてタンケルが駆け寄ってきた。もちろん、その背後にはクローブの姿もある。
「ダーリン、私が席を確保しておこう。中庭が見下ろせる二階のテラス席がいいかな?」
「ああ、頼むよ」
クローブはそう言うとテーブルの方に向かっていき、その姿を見ていたキェーンは俺の顔を一瞥してからクローブの後を追っていったのだった。
大盛りのパスタとサラダを食堂のおばちゃんから受け取り、俺とタンケルはクローブが確保していたテーブルに着席した。
食堂はゴーレム科以外の生徒から教員、果ては学校の警備員も分け隔てなく利用するので多くの座席が必要なため、三階建ての建物になっている。
「タンケル。お前、図書館で何調べてたんだ?」
パスタを食べながら俺はタンケルにそんなことを聞いてみた。
「ちょっと引っかかることがあってな。なあ、クローブ。少しの間席を外してくれると有りがたいんだけど……」
「うむ。男同士の話を邪魔するのは野暮というものだ。お嬢ちゃん、君も一緒に来るんだ」
「あ、ちょっと――」
クローブはあっさりと了承し、キェーンを片手でつまみ上げるとなんとテラスから飛び降りて中庭に着地した。そして、呆気に取られた俺達に笑顔で手を振るのだった。
「お前のゴーレムってなんというか豪快だよな……その、見た目通りというか……
それで、引っかかることってなんだ?」
「ああ、クローブのことさ」
「なんだよ。もう彼女の能力はわかったんじゃねえの?」
もうクローブの能力はあの怪力だと判明したはずだろうが。
「まあ聞いてくれ。さっきまで調べてたのは、あいつの見た目や性格に関することだよ」
そう言うとタンケルは鞄から古ぼけた本を取り出した。
「『ゴーレムの性格と容姿への生成者の心理反映説』……?」
こりゃまたずいぶんと難しそうな本だ。
「さて、本題に入る前に言っておきたいんだが……俺は美少女が好きでしょうがないということは知ってるよな?」
いきなり何言ってんだこいつ。そりゃあ知ってはいるが――お前の将来が不安になるくらい。
「それは知っている。で、美少女ゴーレムを大量に生成して、ハーレムを作るのがお前の夢なんだろ? 初生成でクローブができたおかげで夢に近付いたみたいじゃん」
俺がそう言うと、タンケルは身を乗り出して反論してきた。
「違うんだ! クローブは違う! 確かにあいつの見た目は美女だ。だがな、俺の好みである美少女ではない! 色々と――デカ過ぎるんだよ!」
「わかったから落ち着け! まあ、少なくともあれは少女って感じじゃないな。大人の色香漂う豊満な美女って感じで……」
「そうなんだっ!」
今度はバンっと大きな音を立ててテーブルを叩き、タンケルは唸った。
「ああいう年上のナイスバディはむしろ苦手なんだよ! 俺を子供扱いしているようで、そこら辺も気に食わん! あと、あけっぴろげに愛を語るのも正直好かない! 俺の好みは小じんまりとしているというか、見た目も中身も幼いというか、性格は慎ましやかというか――」
「落ち着けって! 周りの目を気にしろお前は!」
どんどん語調が強くなっていくタンケルを制す。こいつ、自分の趣味嗜好の話になると途端に熱くなるな。
「つまり、俺は自分の好みと正反対のゴーレムが生まれてきてしまったことに納得がいかなかったんだ。それで、図書館でその原因を解明できそうな文献を探して――たまたま見つけたのがこれ!」
やっと本題に戻ってくれたみたいだ。タンケルは『ゴーレムの性格と容姿における心理反映説』をパラパラとめくり出した。
「この本はゴーレム専門の魔法研究家の論文をまとめたものなんだけどな。簡単に言うと、俺達のした生成方法によって生まれたゴーレムの見た目や芽生える性格には、生成主の心理が影響しているって説について書かれてあるんだよ。あっ、心理っつーのは本人でも把握できてない深層心理を含むみたいだ」
――生成者の心理?
「じゃあ、タンケルはその説を知ってクローブみたいなゴーレムが生まれてきたことに納得できたっていうことなのか?」
「うん。全て受け入れられたってわけじゃないけどな。でも、この本に載っている実例を見たら色々と納得できる部分も多くてさ。例えば、小さい頃に猫に食いつかれて以来猫が苦手な奴がゴーレムを生成したら猫型ゴーレムが生まれてきたとか、天使に憧れを持ってるちょっと夢見がちな女の子がゴーレムを生成したら人型に羽根の生えたゴーレムが生まれたとかな」
「そんな……俺達がやった方法はどんなゴーレムが生まれてくるのかコントロールできないんじゃ……」
そうだ。手順さえきちんと踏めば成功率が非常に高くなる代わりに、どんなゴーレムが生まれてくるか操作、予測できないというのが、俺達が初生成で行った方法なわけだが……
「うーん。俺だってこの本を読んで全部内容を理解できたわけじゃないけど、コントロールできないからこそ生成者の心理が変に反映されちゃうんじゃねえの? 気になるならターロも読んでみろよ。あと、読み終わったらついでに図書館に返しといてくれ」
タンケルはそう言って俺に本を渡すと、立ち上がって中庭の方に目をやった。
「まあさ、ちょっと頭に引っかかってたことを晴らすヒントを見つけたから、俺としてはよかったよ」
「知ったところでクローブがお前好みの小じんまりした美少女になるわけでもないだろ」
「ははは。たしかにそうかもな。でも、何も知らないで過ごすよりは実りがあることなんじゃねえかな? ま、根拠はねえけど!」
タンケルはそう言うと笑顔を見せた。こいつ、ただの美少女好きかと思いきや前向きで探究心が強い。そこら辺が、時々すごく眩しく感じる……
「おーい。クローブ! そろそろ部屋に戻るぞ!」
中庭に向かってタンケルが叫ぶと、次の瞬間にはテラス席にクローブが着地していた。
中庭から二階のテラスまで易々と跳躍してしまうクローブの脚力は、腕力同様やはり人間離れしている。
「お、少年。お嬢ちゃんはまだ下にいるぞ。組み合ってじゃれているうちにバテてしまったようだから、少年が迎えに行ってやれ」
「あ、ああ……」
クローブに言われて中庭の方を見ると、キェーンが芝生の上で転がっていた。タンケルから渡された本の内容が気になっていた俺は、キェーンの姿を見て複雑な気持ちになってしまっていた。
心理反映説――俺のケースも当てはまっている予感がしてならない。
「ふう……」
部屋に戻った後、タンケルから借りた本も気になったが、俺はまずレポートの作成に取りかかる。とりあえずキェーンの能力がどういうものかわかったので、さっさとレポートをやってしまって残り二日をダラダラと過ごそうと思ったわけだ。
その間キェーンは俺が与えたマジックアイテムをいじっていたわけだが、さすがにマンネリ気味になってきたのか不満を口に出すようになった。
「もうこれ触るのも飽きたんだけどー!」
伸縮自在のホウキを伸ばし、柄の先で俺の頭を小突いてきやがった。
「うるさい! だったらあそこの窓でもいじってろ! この寮全体がマジックアイテムみたいなもんなんだから、どうにかできるだろ?」
「ああ、そういやそうだったわね」
この寮は魔法で強化されており耐久性が上がっているわけだが、これにより寮全体がマジックアイテム化しているといえるのだ。魔法による強化を受けた物体というものは大小関係なくマジックアイテムなのだと、以前父親から聞いたことがある。
実際キェーンは壊れたドアを直してしまったようだし、あの窓もいじくれば何らかの反応をするだろう。実は、俺の部屋の窓はメンテナンスを怠ったのか元から雑に作ってしまったのかは知らないが、立て付けが悪いのだ。
キェーンの暇潰しのついでにそれが直れば一石二鳥である。
「よし。これでしばらくはおとなしくなるか」
さっそくキェーンは窓をペタペタと触りだし、そちらに夢中になってしまった。
ふむ。こうやってキェーンを上手く利用すれば色々と役に立つのかも知れない……いや、それでもあいつがああやってマジックアイテムを好き勝手いじれることなんて……
しばらく机に向かい続け、気が付くと終礼の鐘が鳴る時間になっていた。
「おいキェーン、いったん教室に行くぞ。終礼の時間だ」
「わかったわ」
そう言うとキェーンは我先にと教室に向かって行った。ゴーレムのくせに生成者を置いていくとは……
やれやれと思いながらキェーンがいじっていた窓を試しに開閉してみると、
「――おっ」
窓は実にスムーズな動きを見せた。立て付けの悪さはキェーンによって完璧に直されていたのだった。
終礼後、タンケルと話してみるとこいつもすでにレポートの作成に入っているようだった。
「なーんだ。ターロももうレポート書けてるのかよ」
「ああ、たぶんタンケルと同じくらい進んでると思う」
「キェーンちゃんの能力ってどんなもんなの?」
タンケルは俺でなくキェーンに直接聞いた。
「ふっふっふっ。聞いて驚かないことね! アタシはなんと――マジックアイテムを自由自在に扱うことができるのよ!」
キェーンは椅子の上に立ち上がり堂々と言った。
「へえ。すごいじゃないか!」
「えっへへ。まあねえ」
「よっ! 手先が器用な美少女ゴーレムなんて、色々期待しちゃうぜ!」
「言葉の意味はわからないけど褒められてるのはわかるわ! もっと言って!」
タンケルにおだてられ照れた様子を見せるキェーン。二人共ノリノリだ。
「ダーリン! 早く部屋に帰ってレポートの続きをやろうじゃないか! さっさと終わらせて私とダラダライチャイチャと過ごすんだ!」
その光景が気に食わなかったのか、クローブがタンケルの背後から覆いかぶさった。
「うわあ――やめろっ! 離れろぉ!」
「あんたらさっきからうるさいのよ!」
バンっと何かを叩く音と大声がした。発生源は俺の後ろの席に座るユリィだった。
「ここにはまだ作業中のクラスメイトがいるんだから、少しは配慮しなさいよね!」
ユリィにそう言われて教室を見回すと、本を片手にゴーレムと睨めっこしていたり、友人同士でノートを見せ合っている生徒が何人もいた。
「あんたらみたいにさっさとゴーレムの能力が判明した人ばっかじゃないんだから……」
ユリィはそう言うとガシガシと頭を掻きながら本に向かった。その隣では彼女のゴーレムが何やらオタオタとしている。
黄土色の大きな球体に、同じく黄土色をした人間と同じ形の腕が生えているという奇妙な見た目をしたゴーレムは、言葉は発していないようだが生成者であるユリィがイライラしていることが心配な様子だ。
ああ、イライラの原因ってやっぱり――
「なに? ユリィはまだゴーレムの能力わかってないの?」
げっ、タンケルの奴あっさりそんなことを言ってしまった。
「ああそうよ! 悪かったわね。まだわかってなくて!」
ユリィは顔を真っ赤にしてこちらを睨みつける。不用意な発言をしたタンケルだけでなく、俺に対しても怒りを露わにしているみたいだ。
それは仕方ないかもしれないな。なにせ、授業に対していつもやる気を見せていない俺が順調にレポートを進めていて、いつも真面目な自分が行き詰まっているなら気分が良くないのは当たり前だろう。
とはいえ、それで不機嫌になられても俺だって困るけど。
「ダーリン。もう少し級友を気遣う発言をした方がいいんじゃないか?」
クローブはタンケルをそう諭す。さらに続けて、
「すまないなお嬢ちゃん。ダーリンは思ったことをすぐに口に出してしまう素直な性格なんだ。しかし、そこが魅力でもあるわけで……ともかく今回は勘弁してやってくれないだろうか」
「――わかったわよ。なんか、あんたらといると調子狂うわね……」
ユリィは少し顔を引きつらせてから本を閉じ、席から立ち上がった。いつもはガンガン言ってくるユリィも、クローブを相手にするといつも通りとはいかないみたいだ。
しかしユリィの浮かない顔というのもなにか見ていて……
「そうだユリィ。ユージン先輩に相談してみたらどうだ? あの人、俺達にゴーレムで困ったことがあったら何時でも相談に来いって言ってたぜ」
どこかいたたまれなくなった俺は、そんな言葉を投げかけて見た。
すると、立ち去ろうとしたユリィの動きが止まる。そして、再びこちらを向く。
「その手があったわあっ!」
この時ユリィが見せた表情と発した声は、さっきまでとは全然違っていたのだった。
「んん――でも、いざ相談に行くとなると恥ずかしいわ……けど、これを機会にさらに先輩と仲を深めるチャンスかも知れないし――あっ! 相談に乗ってもらったお礼も今から考えておかないと! 頑張れユリィ!」
教室で自問自答し始めたユリィ。そのテンションは異様に高い。
「あんたもたまには冴えてるじゃない! そういえば、ユージン先輩っていつもはどこにいるっけ?」
「あの人、基本的に自由人だからなあ。よくゴーレム科の格納庫にいるって聞くけど……」
格納庫とは教室や寮に入りきれない大きなゴーレム等を保管しておくゴーレム科の施設だ。そこの地下には国から預かった軍用ゴーレムが大量に保管されているとか、神を宿した禁断のゴーレムが眠っているとか眉唾物の噂が絶えない場所でもある。
「おっしゃあ! 行くわよ、パクチ!」
ユリィはさっきまでとは打って変わって上機嫌で教室を出て行った。あと、どうやら彼女のゴーレムの名前はパクチというようだ。
「やれやれ……」
「ユージンってあのでっかいゴーレムの?」
「ああ、そうだよ」
自室に戻る準備を始めた俺に、キェーンが少し不機嫌そうな顔で聞いてきた。
「なんか気に入らないのよね。あの男……」
「そんなこと言うな。あの人はむちゃくちゃ優秀で頼りになる先輩だぜ? あの通り、ユリィもばっちり惚れちゃってるし、非の打ちどころがない人だ」
横からタンケルが口を挟んできた。
「そうなんだよなあ。こう言っちゃなんだけど、ゴーレム科にいるのが不思議なくらいだもん。あの先輩なら
まったくだ。こんな不人気学科にいるより、エリート学科の俗称を持つクエスト科で専門研究に打ち込む方がよっぽど似合ってると思うんだが。
「人にはそれぞれ事情があるんだよダーリン。ところで、クエスト科とはなんだ?」
「この学校にいくつかある学科の中でも限られた優秀な生徒しか入れないとこさ。自分の興味関心がある分野をとことん研究する学科で、卒業が他の科の生徒より遅れることもあるくらいだ」
クローブに聞かれてタンケルが答える。そう、クエスト科はそんな優秀な生徒しか入ることができない俺達には無縁の学科だ。転科試験を受ければ他学科の生徒も入れるそうだが、先輩なら楽勝で通れただろうに。
さて、他人のことはこれくらいにして俺は部屋に戻ることにしよう。タンケルから借りた本を読んでみないといけないし。
「じゃあな。とりあえず俺は部屋に戻るわ」
「おう。夕食の時にまた会おうぜ」
「ダーリン。夜くらい学食から持ち帰って部屋でゆっくり食べようじゃないか! 二人でまったりと! そしてイチャイチャと!」
「お前はゴーレムだから飯はいらないだろ!」
「じゃあ、私があーんってやって食べさせてあげよう! 食べ終わったお口も拭いてやるぞ! もちろん食後のデザートはわた――」
「だあああっ! 俺の口を拭く前にお前は自分の口を塞げ!」
タンケルとクローブって実はすごく似た者同士なんじゃないか……
そんな二人を見つつ、俺は教室をあとにする。その後をキェーンは無言で追いかけて来た。
あいつ等に比べ、俺達は全然似ていないなあと思うのだった。
部屋に戻ると俺は机に向かい、『ゴーレムの性格と容姿における心理反映説』を読み始める。専門用語の連発や文章自体が難しいこともあって読み進めるのに苦労をしたが、読むほどに俺のケースもこの本に書いてある説に当てはまっているように思えてならなかった。
ゴーレムの容姿や芽生える性格に加え、ゴーレムが持つ能力もその生成者の心理に影響を受けたものになることがあると、この本には書かれていた。
さらには、生成者の人生における挫折、傷心の経験などにより生じた負の部分も反映されてしまうケースも見られるという。
「まいったなあ……まんまじゃねえか」
キェーンの能力、俺の人生の間で生まれた負の部分――もろに影響し合っている。
俺の実家はマジックアイテム店を営んでいる。自宅兼店舗はマジックアイテム店が多く立ち並ぶ街の一角にあり、お役所や軍からの受注、市民のための日用品販売までガンガンこなす評判の店なのだ。
親父は代々その店を受け継いできた腕利きの職人で、当たり前のように俺に後を継がせようとしていた。
だが俺は、幼い時に経験したある事件がきっかけで別の道に進みたいと常日頃から思っていたのだった。だから、親父が直接マジックアイテムに関することを教えようとしてきても俺はそれを避けて来たのだ。
今でもよく思うが、親の決めた道を進めさせられるということへの反発心もあったかもしれない。
魔法に関する基礎知識と極初歩的な実技を学ぶ初等魔法学校を出たら、マジックアイテム職人ではなくそちらの道に進みたいと両親に言おうとしたのだが、それを言い出すことは叶わなかった。
親父が掲示して来たのはエクスペリオン高等魔法学校のマジックアイテム科。マジックアイテムに関することを学ぶこの学科への進学以外は認めないと俺が言い出す前に言われてしまったのだった。
親父の頑なな態度に、俺は仕方なく夢見ていた道を諦めて親の決めた道を進んでしまおうと決めたのだった。
さらに、結婚前は役所の事務員をしていた心配性の母親は、マジックアイテム科一本の受験では心細いから一応の保険としてゴーレム科を併願で受験しておけと進言し親父もこれを了承した。
そして――マジックアイテム科、ゴーレム科の入学試験を連日受けた結果は、第一志望のマジックアイテム科は不合格。ゴーレム科は合格というものだった。
この結果を受け、親父は俺を進学させずに自分の店か知り合いの工場で修業させることを考えたが、母親との相談の末にゴーレム科への進学を選択してもよいと俺に言って来た。
――この辺のことは思い出したくもない。
あれだけ避けていたマジックアイテム店を継ぐこと。
それの下準備と言われて受けさせられたマジックアイテム科への入学試験が不合格。
小さな頃からの夢を捨て、不本意ながら現実の道を進もうと決めた後での不合格通知は、俺みたいなちっぽけな人間にとっては、あまりにも強烈な一撃だった。
選択を迫られた俺は、エクスペリオン高等魔法学校ゴーレム科への進学を決めた。
もう、マジックアイテムを扱う道のことなんて考えたくもないと思ったからである。
ゴーレム科にこうやって今いるわけだが、もちろん前向きな気持ちでいたいわけでなく――うん、ここは逃げ道でしかないのだ。
そんな逃げ道でやる気が出るわけないし、そう思いながら過ごしている自分が嫌でしょうがないという気持ちもあり――
「で、そんな俺の前に現れたのがこいつってわけか……」
「あん? なんか言った?」
「なんでもねえよ……」
俺の生み出したゴーレム――キェーン――はマジックアイテムを自由自在に操るという能力を見せつけ、ちっぽけな俺のどうしようもない心の傷を刺激しやがった。
そして、思ったことをすぐ口に出し、気に入らないとすぐ意志表明する性格についても考えさせられてしまう。いつまでも、ウジウジしている生成者の俺に比べて、このゴーレムときたら……
そんなキェーンは今も俺のベッドに堂々と陣取り、手の中でマジックアイテムを遊ばせている。
「あっ! そういや、昼間の賭けであんたに勝ったからこのベッドはアタシの物よね!」
「――げっ、忘れてた……」
そういや、そんな賭けに乗ってしまったんだった!
「ここで『そんなの取り消しだ!』とか言ったら、最高に格好悪いわよ?」
「う、うぐぐ!」
悔しい。反論しようとしても、言葉が出てこない。
「わかったよ! 男に二言はない! 第一、生成者がゴーレムに舐められてたまるかよ」
ちっぽけだ。最悪だ。あまりに格好が悪いぞ俺って……
歯ぎしりしながらも俺は毛布を引っ張り出して、それにくるまって床に寝転んだ。
そうして、何もかも頭から排除するために眠りに入る。そういえば、夕食のこともこの時はすっかり忘れていた。
翌朝。猛烈な空腹を大盛りの朝食セットで満たし俺は教室に向かう。
昨夜のこともあり目覚めはいまいちだったが、教室に入るといきなりその何もかもが吹っ飛ぶような事態に遭遇した。
「な、な、な……」
「え? うそ? なにこれ?」
驚きのあまり声も出ない俺の横で、同行していたキェーンも目を皿のようにしていた。
「おはようさんです! 本日は快晴で、朝から気分がいいですな!」
手を上げ、軽快な口調で挨拶をしてきたそいつは、教室にある俺の席に座っていた。
「ああ、そうですよね。やっぱり驚きますよね! あはは、しょうがないことですよ。
おっ、そちらはゴーレムの……えーと、名前はキェーンでしたっけ? おはようキェーンたん!」
そいつの表情は実に明るい笑顔。しかし、どこかで見た笑顔でもあった。
――ていうか、俺の顔をしている!
「何者だてめえ!」
「おお。実に的確なお言葉ですね。何者かと言われましたが――ボクとあなたはもう何回かお会いしているのですよ」
「え? もう会ってる?」
俺と同じ顔をした奴から返ってきた答えは、ますます俺を混乱させた。
よく見ると、背や体格も俺と全く同じみたいだ。
違うのは服装で、全身がタイル模様みたいな艶のある服で包まれている。そのせいで余計不気味に感じるわけだが。
「あーはっはっはっ! ターロったら本当にわかりやすい反応ね」
大笑いしながら俺に向かって言ってきたのはユリィ。その近くでは、タンケルとクローブもニヤニヤと笑っている。
「ユ、ユリィの仕業か? なんなんだよこれは!」
俺がそう怒鳴ると、自信満々にユリィは答えた。
「これぞ、私のゴーレム――パクチの能力なのよ!」
「はい。そうなんですねこれが。ボクはこちらにいらっしゃるユリィ・ドルフーレン様によって生成されたゴーレム、パクチと申します。ユリィ様がおっしゃったように、今ボクはボク自身の能力によってターロさんに姿を変えているわけなんですね」
俺の姿をしたそれは、どうやらユリィのゴーレムのようだった。
「能力によって姿を変える?」
「そう! 昨日、ターロに言われた通りユージン先輩を見つけて相談したんだけど、見事に私のゴーレムの能力はこれだって導いてくれたの! その間二人っきりで!」
「まあ、人間に限って言えば二人でしたがねえ。できればボクのことも忘れないで頂きたいです。あと、ユージンさんのゴーレムのペッパード六式殿もいましたし」
「わかってるわ――よっ!」
横から口を挟んできたパクチの頭を笑いながらユリィが叩いた。
「あ! お前、よくも俺の頭を……」
「何言ってんのよ。これは私のゴーレムの頭ですけど?」
俺は抗議したが、ユリィは見せつけるようにしてまたパクチの頭を叩いた。
これは……叩かれているのは彼女のゴーレム、パクチではあるのだが……
「目の前で自分が叩かれているみたいで気分悪いんだよ! だいたい、なんだよその服は! 全身ぴっちりな上にテカテカ光ってて、俺だったらそんな格好絶対にしたくねえ!」
そうだ。パクチの着ている服は体型にピッタリとフィットした感じの異様な服。
いや――服というか光沢を放った怪しげな素材が全身に張り付いているというか……
「先輩がくれた物にケチ付ける気? これはユージン先輩がくれた魔導素材を使ったスーツよ。どんな体型にもフィットする魔法のスーツで、これがないとパクチが誰かに変身したらその人の裸が――あっ!」
説明している途中でユリィが急に言葉を詰まらせた。
そして、顔がどんどん赤くなっていく。
「ほほう。その様子だと、もう誰かの裸を見てしまったみたいだな」
ニヤリと笑ってそう突っ込んだのはクローブ。
それを聞いてユリィはますます顔を赤くした。
「とにかく、先輩のくれた物を悪く言うんじゃないの!
パクチ! 戻りなさい!」
ユリィは慌てて指をパチンと鳴らし、パクチに指示を出した。
「はいはい!」
鈍い光を放ちながらパクチの体がぐにゃぐにゃと歪む。
これもちょっと……俺の姿がむちゃくちゃになっていくみたいで見ていて辛い……
しばらくするとパクチの見た目は昨日見たのと同じ球体になっていた。
全身は黄土色ではなくあの奇妙な服と同じ色や模様だ。所々に切れ込みがあり、人間に変身するとこの切れ込みから頭や手が出るわけか。
そして、あれだけ饒舌だったのに元の姿になると一転おとなしくなってしまった。なるほど。変身中しか言葉を発せられないわけだな。
「おーい、先生が来たぞ!」
そうこうしているうちに担任が来た。
今日は簡単な連絡だけで、本日も自分のゴーレムの能力を張り切って探しましょうとだけ言って朝礼は終わってしまった。
俺もタンケルもユリィもだいたい自分のゴーレムの能力についてはわかってきたため、午前中はレポート作成に徹した。いかに創意工夫したかの脚色も忘れず、昼前にはあらかた書き終えてしまった。
本日の昼食も学食のテラス席。俺とタンケルでの昼食になるかと思いきや、クローブが席取りをしている所にユリィがちゃっかりと入ってきてしまった。
こうして、三人と三体のゴーレムでのいつもより騒がしい昼食となった。
「私のパクチは、変身しないと喋れないみたいなの」
「ふうむ。生成者との信頼を深める上でそれはちょっとどうだろうな。まあ、私ならダーリンとは言葉に頼らない、より素晴らしく本能的というか官能的な方法をとれるわけだが――」
「やめろっ!」
すっかりお馴染みになってしまった、クローブがタンケルに絡み付く光景。毎度のことながら目のやり場に困ってしまう。
「ゴーレムとの信頼関係ねえ……」
揚げた鶏肉を口に運びながら、俺は自分のゴーレムに目をやる。キェーンはパクチが身にまとっている服をひっぱって遊んでいるようだ。
ああ、そういえばパクチのこれもマジックアイテムに分類されるんだろうな。
「ねえ、あんたはどうなのよターロ」
「なんだ?」
キェーンを見ていた俺に、ユリィが話しかけてきた。
「あんたはゴーレムと上手くやってるの?」
「……」
俺は答えられない。関係は最悪だとしか言えないからだ。
「能力がわかるだけじゃダメなのよ? ゴーレムは生成者と上手く連携を取ってこそ真価を発揮するって習ったでしょ」
ユリィはペラペラとまくし立てる。
「まあな……」
「もしかして、あんな可愛いゴーレムができちゃって戸惑ってるわけ? あんたなら有り得そうねえ……」
ふざけるなと言いたい。
確かにキェーンの見た目はちょっと浮世離れした美少女だ。
しかし、こいつは俺の魔力と血の混じったゴーレムである。異性として見るというのは少々戸惑う……
例えれば――それは家族、それも妹辺りというか――いや! 家族、それも妹ならそれはまた愛おしい存在であるはずだ! いや、俺には実際妹はいないが……
ともかく、俺はキェーンにそれに近い感情などこれっぽっちも抱いていない。
第一、家族と違ってまだこいつとは数日しか生活を共にしていないわけだし、おまけにこいつは俺の心にある嫌な気持ちを刺激する最悪の存在なのだ。
「キェーンちゃんはこいつのことどう思うの?」
ユリィの奴、俺が答えないからってキェーンに振りやがった。
キェーンはパクチの服を引っ張るのをやめ、こっちを向いた。
「うーん。簡単に言えば、パッとしない奴って感じかな。それで、最初にアタシの生成者だってわかった時はこんな奴の所に生まれちゃって嫌だなあって思った」
「おお! 言うねえ!」
キェーンは続ける。
「で、どんな奴か観察を続けてたけど、どっか心に引っかかりを感じながら過ごしてるのかなあって何となく思えてきたの。でも、それを心にしまってるみたいな?
何か不満があるなら、行動に移せばいいのになあとアタシは思うわ」
――そこまでわかっているのか。とそれを聞いていた俺は呆れてしまっていた。そして、次の瞬間、俺は周囲の反応などお構いなしに、ブチ切れていた。
「心だって? ふざけんじゃねえよ! てめえは人間じゃなくてゴーレムだろ!
それなのに心とか笑わせんな!
ゴーレムはしょせんゴーレムで、心なんかあるわけないんだよ!
――ああ、俺は不満を抱えまくってるよ! それも、山ほどな。
その不満の中で現在第一位に光り輝いているのは、てめえみたいな反抗的なゴーレムが生まれちまって、一緒の部屋で生活しなきゃならないなんて状況についてだ!
ああ、最悪だよ。本当に最悪だ!」
「な……」
「おいターロ、落ち着けって!」
俺は椅子が倒れるくらいの勢いで立ち上がっていた。タンケルに袖を掴まれるが、振り払い全速力で学食を後にした。
そして、自分の部屋に戻り、鍵を閉めてベッドに倒れ込む。
ああ、もう本当に、正真正銘に最悪だ。