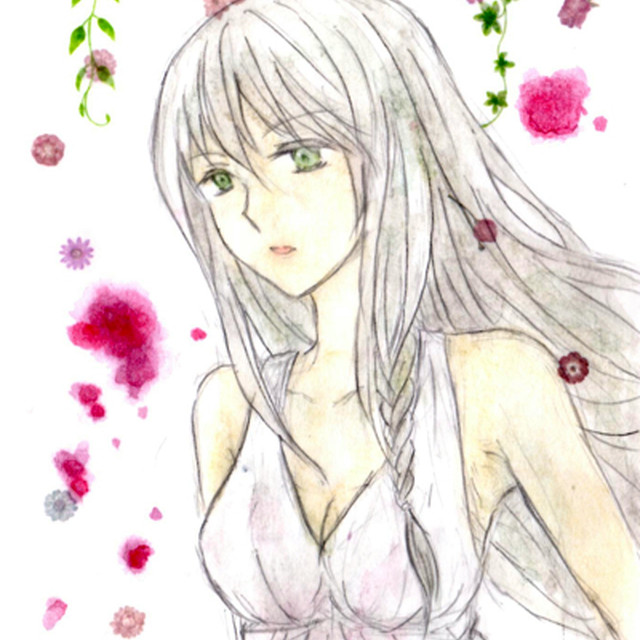第16話 砂の城が崩れるように
文字数 2,180文字
何度も繰り返される時間。
終わりを迎えては、またその不幸が起こる前の平穏だった時に戻されるという歪み。
これは、何度目だっただろう。
「ちがう。今日はおれの誕生日じゃない。今はまだ春でもないし、おれはこの城の使用人なんかでもない。これはなんだ? おれは……あんたは一体誰だ?」
言って、ルフスは正面に立つ男をまっすぐに見据える。
黒い髪と吊った目の、ルフスもよく知るその姿。少なくとも彼は、見た目だけでいえばティランだ。
ただ纏う空気がほんの少し違っているようにも感じる。
リゲルのあの夜のように何者かがティランの体に乗り移っているのか、それとも彼の見た目を借りただけの中身はまったく別人なのか。或いはティランもルフスと同じなのだろうか。何せ今の今まで、ルフス自身も己の意思とは関係なしに動いて話して、なんの疑問を抱くこともなく、この知らない誰かの日常の中に溶け込んでいた。
判然としないことはいくつもあるが、一つだけ、わかっていることがある。
目の前の男に悪意は感じられない。
「あんたは、ティランの姿をしているけど、おれの知っているティランとはちょっとちがう。違うんだけど、でも、まったく違うのかと言われたらそうでもない。なあ、また別の誰かがティランの中にいるのか? やめろよそういうの、言いたいことあるなら言えばいい、でもちゃんと姿見せて言え」
微笑む男の輪郭が一瞬ぶれて見えた気がして、ルフスは目をこする。
すると男は我に返ったようになって、
「ルフス?」
と呟く。
「ティランか?」
「他に誰に見えるっていうんや」
「うん。他の誰でもないティランだな」
叩かれた憎まれ口に間違いなく彼であることを確認して、安堵する。
ティランは部屋の中を見渡して言う。
「これは、あの城か?」
「たぶん」
今二人がいる部屋。それはルフスが二階で見つけた唯一家具が残された部屋と全く同じだった。
家具や床が埃を被っていないことを除いては。
バルコニーに出てみる。
庭は最初にこの城を訪れた際と同じように荒れているが、一部だけ手入れがされているようだった。おかしいのは葉が緑色で、枝には花の蕾がついていて、春の気配がすることだけだ。
本来なら秋の終わりで、冬が訪れようとしている時期だったはずだ。
「これあれかな? この間グルナさんが言ってた別の層」
「ああ、多構造世界ってやつの」
「そうそう、同じ場所だけどそうじゃないみたいな」
「てことはあれか? 何者かがおれらをこの空間に閉じ込めてて、そいつをどうにかせんと元の場所に戻れんってことか?」
「そうなるのかなあ。あ、でもさ、ちょっと違うのが、なんかこの間と違って悪いかんじはしないんだ」
確証はない。ただの勘みたいなものだ。
ティランが眉根を寄せる。
「おれにはようわからんのやけど、そもそもひとをこんなわけわからん場所に軟禁して、そのうえ好き勝手動かしておいて悪いかんじもなにもなくねぇか?」
「そりゃそうなんだけど」
「ところでな、さっきのあの懐中時計」
「あ、うん。おれも思った」
ルフスは腰紐に結わえた革袋から、預かりもののそれを出す。
ティランは手に取ると蓋を開き、目を瞠る。
「動いとる。ルフス、ひょっとして竜頭巻いたか?」
「え、いやおれはなんも触ってないけど、なに? リューズ?」
「これや、ここのネジみたいなやつ。これを定期的に巻かんと時計は動かんはずなんや」
「へぇー。あ、もしかしてあのお爺さんとか?」
「かもしれんけど……でも、この城と関係があることは間違いねぇやろ」
ルフスの掌に時計を落として、ティランはバルコニーから室内に戻る。何か思い当たることでもあるのか、廊下を過ぎて、一階に降り、食堂の隣の小さな寝室にやってくる。隅に寄せられた書き物机を物色し、二段目の引き出しから立派な装丁の書物のようなものを取り出した。
「なにそれ?」
「日記、あの使用人の男が書いてたやろ」
ぱらぱらとページを捲るのを肩口から覗き込み、ルフスは大きく頷く。
言われてみれば二階にある寝室よりもずっと狭いし、家具類も質素だ。
「そっか。ここあの人の部屋か」
「ああ、あった。主人が死んだ日、日記はそこで終わっとるみたいや」
「あの後、あの人どうしたんだろうな……」
主人を失い、悔やみ、自責の念に苛まれていたあの青年。
主人の死後について、日記には何も記されていない。
この広い城にたった一人残されて。大切な友人を失って。どんな思いで余生を過ごしたのだろうか。
ルフスの呟きに、最後のページに視線を落としたまま、ティランは言う。
「ここからはおれの勝手な想像でしかないけど、あの使用人は旅に出たんやないか? だっておまえが預かったその時計って、あいつのもんやろ?」
「あ」
故郷に戻る途中、あの街道で力尽きたのではないか。
老人の言葉が頭によみがえる。
「でもなんで」
「主人が見たがっていた景色を見るために、やないかな……」
天空の鏡。
氷を纏い宝石のようにキラキラ輝いて見える空気中の埃。砂地の上に自然にできた壮大な模様。
本に記された、本の中でしか知らない絶景。
ルフスは握りしめていた懐中時計を見つめる。
「そしてこの城に戻る途中力尽きて、あの場所で息絶えた。無念だったろうな。本当なら城に戻って、主の墓前で、見てきた景色を話して聞かせたかったんやないか……」
終わりを迎えては、またその不幸が起こる前の平穏だった時に戻されるという歪み。
これは、何度目だっただろう。
「ちがう。今日はおれの誕生日じゃない。今はまだ春でもないし、おれはこの城の使用人なんかでもない。これはなんだ? おれは……あんたは一体誰だ?」
言って、ルフスは正面に立つ男をまっすぐに見据える。
黒い髪と吊った目の、ルフスもよく知るその姿。少なくとも彼は、見た目だけでいえばティランだ。
ただ纏う空気がほんの少し違っているようにも感じる。
リゲルのあの夜のように何者かがティランの体に乗り移っているのか、それとも彼の見た目を借りただけの中身はまったく別人なのか。或いはティランもルフスと同じなのだろうか。何せ今の今まで、ルフス自身も己の意思とは関係なしに動いて話して、なんの疑問を抱くこともなく、この知らない誰かの日常の中に溶け込んでいた。
判然としないことはいくつもあるが、一つだけ、わかっていることがある。
目の前の男に悪意は感じられない。
「あんたは、ティランの姿をしているけど、おれの知っているティランとはちょっとちがう。違うんだけど、でも、まったく違うのかと言われたらそうでもない。なあ、また別の誰かがティランの中にいるのか? やめろよそういうの、言いたいことあるなら言えばいい、でもちゃんと姿見せて言え」
微笑む男の輪郭が一瞬ぶれて見えた気がして、ルフスは目をこする。
すると男は我に返ったようになって、
「ルフス?」
と呟く。
「ティランか?」
「他に誰に見えるっていうんや」
「うん。他の誰でもないティランだな」
叩かれた憎まれ口に間違いなく彼であることを確認して、安堵する。
ティランは部屋の中を見渡して言う。
「これは、あの城か?」
「たぶん」
今二人がいる部屋。それはルフスが二階で見つけた唯一家具が残された部屋と全く同じだった。
家具や床が埃を被っていないことを除いては。
バルコニーに出てみる。
庭は最初にこの城を訪れた際と同じように荒れているが、一部だけ手入れがされているようだった。おかしいのは葉が緑色で、枝には花の蕾がついていて、春の気配がすることだけだ。
本来なら秋の終わりで、冬が訪れようとしている時期だったはずだ。
「これあれかな? この間グルナさんが言ってた別の層」
「ああ、多構造世界ってやつの」
「そうそう、同じ場所だけどそうじゃないみたいな」
「てことはあれか? 何者かがおれらをこの空間に閉じ込めてて、そいつをどうにかせんと元の場所に戻れんってことか?」
「そうなるのかなあ。あ、でもさ、ちょっと違うのが、なんかこの間と違って悪いかんじはしないんだ」
確証はない。ただの勘みたいなものだ。
ティランが眉根を寄せる。
「おれにはようわからんのやけど、そもそもひとをこんなわけわからん場所に軟禁して、そのうえ好き勝手動かしておいて悪いかんじもなにもなくねぇか?」
「そりゃそうなんだけど」
「ところでな、さっきのあの懐中時計」
「あ、うん。おれも思った」
ルフスは腰紐に結わえた革袋から、預かりもののそれを出す。
ティランは手に取ると蓋を開き、目を瞠る。
「動いとる。ルフス、ひょっとして竜頭巻いたか?」
「え、いやおれはなんも触ってないけど、なに? リューズ?」
「これや、ここのネジみたいなやつ。これを定期的に巻かんと時計は動かんはずなんや」
「へぇー。あ、もしかしてあのお爺さんとか?」
「かもしれんけど……でも、この城と関係があることは間違いねぇやろ」
ルフスの掌に時計を落として、ティランはバルコニーから室内に戻る。何か思い当たることでもあるのか、廊下を過ぎて、一階に降り、食堂の隣の小さな寝室にやってくる。隅に寄せられた書き物机を物色し、二段目の引き出しから立派な装丁の書物のようなものを取り出した。
「なにそれ?」
「日記、あの使用人の男が書いてたやろ」
ぱらぱらとページを捲るのを肩口から覗き込み、ルフスは大きく頷く。
言われてみれば二階にある寝室よりもずっと狭いし、家具類も質素だ。
「そっか。ここあの人の部屋か」
「ああ、あった。主人が死んだ日、日記はそこで終わっとるみたいや」
「あの後、あの人どうしたんだろうな……」
主人を失い、悔やみ、自責の念に苛まれていたあの青年。
主人の死後について、日記には何も記されていない。
この広い城にたった一人残されて。大切な友人を失って。どんな思いで余生を過ごしたのだろうか。
ルフスの呟きに、最後のページに視線を落としたまま、ティランは言う。
「ここからはおれの勝手な想像でしかないけど、あの使用人は旅に出たんやないか? だっておまえが預かったその時計って、あいつのもんやろ?」
「あ」
故郷に戻る途中、あの街道で力尽きたのではないか。
老人の言葉が頭によみがえる。
「でもなんで」
「主人が見たがっていた景色を見るために、やないかな……」
天空の鏡。
氷を纏い宝石のようにキラキラ輝いて見える空気中の埃。砂地の上に自然にできた壮大な模様。
本に記された、本の中でしか知らない絶景。
ルフスは握りしめていた懐中時計を見つめる。
「そしてこの城に戻る途中力尽きて、あの場所で息絶えた。無念だったろうな。本当なら城に戻って、主の墓前で、見てきた景色を話して聞かせたかったんやないか……」