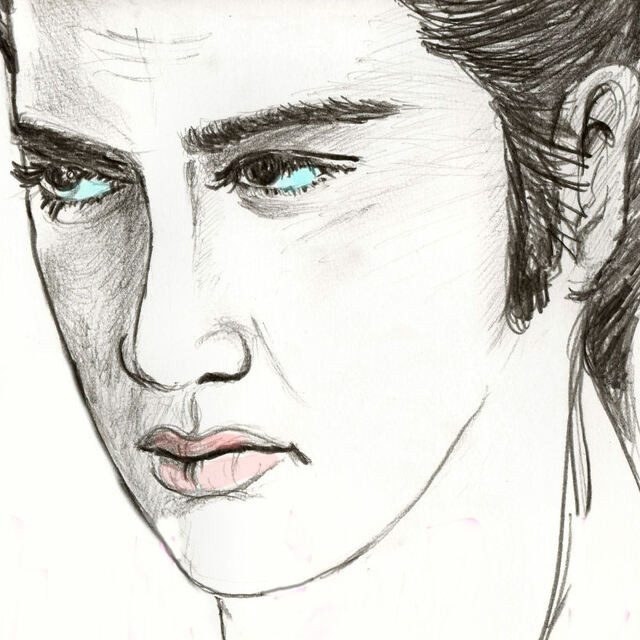第14話 パッション
文字数 1,377文字
老川由紀夫の舞台演劇「生きる」は本格的な稽古に入っていた。慎吾は今までとは見違えるように稽古に没頭していた。
老川が自分を主役に抜擢するなどとは、今までには考えられなかった。このチャンスを逃せば、もう自分の幸運は二度とやって来ない。
それは慎吾でなくても、誰でもがそう思っていた。マスコミもこれを少し報道しただけだったが、それでももう既に話題になっている。
今までの慎吾なら、少し有頂天になってマスコミのインタビューなどを受けていただろう。しかし今回の彼は一切そういうことを拒否していた。
「すみません、今は老川先生の稽古を受けている最中なので、インタビューを受けている余裕がはありません、失礼します」
今までの彼の少し横柄な態度からは、想像もつかないような低姿勢に、記者は彼の本気度を見たような気がした。
慎吾は同じ舞台俳優と一緒に厳しい稽古を受けていた、老川は主役だろうが、端役だろうが一切の妥協を許さなかった。もし慎吾が途中で挫折でもしようものならば、すぐにとって代わるような役者は何人もいる。
慎吾はそれをよく知っていた。おそらく今までの彼の生涯の中で、これほど神経を集中したことはないだろう。
慎吾は初めて老川の演技の指導を受けた、しかしこれほど厳しいとは予想していなかった。稽古を始めて三十分も経たないうちに彼の体中から汗が吹き出していた。額から出た汗が彼の目に流れて痛かった。
「慎吾、まだまだ体が硬い、そんなに緊張してどうするんだ、もっと堂々とした演技をしろ! お前が主役なんだからな」
舞台上の慎吾に向かって客席の一番前で陣取っている老川は台本を手で丸めて持ち大声を張り上げていた。時々納得がいかないと、そばにいる助手に向かって二言三言いう。
それを聞いた助手の青柳は、老川のアドバイスを直接指導しに舞台に上がってきた。
「慎吾君、老川さんが言っていることはそういう演技じゃないんだよ、演技は頭の中で考えていてはダメだ、体で体当たりする覚悟でやるんだ、いいか、見てろ」
青柳は、慎吾の相手役で達也役の逢崎健太の胸元をつかみながら、声を押し殺すようにし、睨み付ける演技指導をしていた。彼はその他にも慎吾に細かい指導をした。
「こうやって演技とはただ言葉だけで表現するんじゃないんだ、眼の配り、 息の付け方、指の先にも神経を集中させてそれを表現するんだ、分かったかい」
「はい、ありがとうございます」
慎吾が新川美子と面会したのは、「生きる」の出演者達が一堂に会した時だった。老川は皆を目の前にして言った。
「そういうわけで、皆さんも知ってると思いますが、ここにいる新川美子さんが一般公募で採用された人です。慎吾君が演じる(憲二)の恋人の(雪子)役になりました、皆さん仲良くやって下さい」
「よろしくお願いします、新川美子です」
「よろしく、慎吾です、新川さん」
その時、慎吾はこの新川美子を見たのだが、彼女を見ているとどこか懐かしいような、親しみを感じるのである。それは好きとか嫌いとか言う感情ではなく、何か大きく人を包み込むような優しさと包容力をこの美子から感じるのである。そして思った。
「この人となら、良い演技が出来そうだ」と……。
一方の美子は、慎吾に微笑みながら軽く会釈をしただけだった。
しかし、その眼はじっと慎吾を見つめていた。
老川が自分を主役に抜擢するなどとは、今までには考えられなかった。このチャンスを逃せば、もう自分の幸運は二度とやって来ない。
それは慎吾でなくても、誰でもがそう思っていた。マスコミもこれを少し報道しただけだったが、それでももう既に話題になっている。
今までの慎吾なら、少し有頂天になってマスコミのインタビューなどを受けていただろう。しかし今回の彼は一切そういうことを拒否していた。
「すみません、今は老川先生の稽古を受けている最中なので、インタビューを受けている余裕がはありません、失礼します」
今までの彼の少し横柄な態度からは、想像もつかないような低姿勢に、記者は彼の本気度を見たような気がした。
慎吾は同じ舞台俳優と一緒に厳しい稽古を受けていた、老川は主役だろうが、端役だろうが一切の妥協を許さなかった。もし慎吾が途中で挫折でもしようものならば、すぐにとって代わるような役者は何人もいる。
慎吾はそれをよく知っていた。おそらく今までの彼の生涯の中で、これほど神経を集中したことはないだろう。
慎吾は初めて老川の演技の指導を受けた、しかしこれほど厳しいとは予想していなかった。稽古を始めて三十分も経たないうちに彼の体中から汗が吹き出していた。額から出た汗が彼の目に流れて痛かった。
「慎吾、まだまだ体が硬い、そんなに緊張してどうするんだ、もっと堂々とした演技をしろ! お前が主役なんだからな」
舞台上の慎吾に向かって客席の一番前で陣取っている老川は台本を手で丸めて持ち大声を張り上げていた。時々納得がいかないと、そばにいる助手に向かって二言三言いう。
それを聞いた助手の青柳は、老川のアドバイスを直接指導しに舞台に上がってきた。
「慎吾君、老川さんが言っていることはそういう演技じゃないんだよ、演技は頭の中で考えていてはダメだ、体で体当たりする覚悟でやるんだ、いいか、見てろ」
青柳は、慎吾の相手役で達也役の逢崎健太の胸元をつかみながら、声を押し殺すようにし、睨み付ける演技指導をしていた。彼はその他にも慎吾に細かい指導をした。
「こうやって演技とはただ言葉だけで表現するんじゃないんだ、眼の配り、 息の付け方、指の先にも神経を集中させてそれを表現するんだ、分かったかい」
「はい、ありがとうございます」
慎吾が新川美子と面会したのは、「生きる」の出演者達が一堂に会した時だった。老川は皆を目の前にして言った。
「そういうわけで、皆さんも知ってると思いますが、ここにいる新川美子さんが一般公募で採用された人です。慎吾君が演じる(憲二)の恋人の(雪子)役になりました、皆さん仲良くやって下さい」
「よろしくお願いします、新川美子です」
「よろしく、慎吾です、新川さん」
その時、慎吾はこの新川美子を見たのだが、彼女を見ているとどこか懐かしいような、親しみを感じるのである。それは好きとか嫌いとか言う感情ではなく、何か大きく人を包み込むような優しさと包容力をこの美子から感じるのである。そして思った。
「この人となら、良い演技が出来そうだ」と……。
一方の美子は、慎吾に微笑みながら軽く会釈をしただけだった。
しかし、その眼はじっと慎吾を見つめていた。