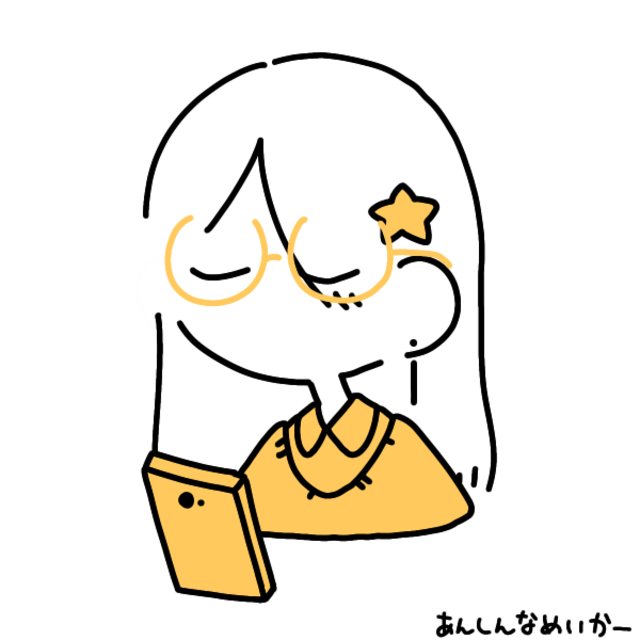1
文字数 3,908文字
あの日、日曜日なのに父は遊んでくれなくて、有馬を遊びに誘いに行ったけれど、妹と留守番をしなければいけないと断られた。
退屈だった聡介は、あてもなく自転車であちこちを走った。
川沿いの道には桜並木があり、もう少ししたら花見をする人で賑わうだろう。
だが今はまだ蕾かりで今日は風も冷たく、人気もない。誰もいない道を走るのは気分がよかった。
調子に乗ってずいぶん遠くまできてしまったらしい。いつの間にか町の外れまできてしまった。ほとんどきたことがない場所だ。
行く手には廃工場が見えた。持ち主が夜逃げしたとかで、取り壊されることもなくそのまま放置されていた。
ちょっとした冒険心だった。大人は近づくなと言うけれど、こんな身近なところで危ないことなんて、起きるはずがない。そう思っていた。
聡介はそろそろと様子を窺いながら、人気のない廃工場に入っていく。いい天気なのに中は暗く、オイルや何か得体の知れないにおいがした。
最初は怖かったが、薄気味悪い空気にも徐々に慣れた。こんなところに一人で乗り込む自分の度胸に気分がよくなって、聡介は動くのをやめた機械を覗き込んだり、そっと触れたりした。
その、まだ錆びついていない機械に、人影が映ったのをよく覚えている。突然背後から殴られ、聡介の記憶はそこで途切れていた。
聡介を襲ったのは、廃工場をアジトにしていた窃盗グループだった。聡介を探しにきた父が、血を流して倒れている息子を見て逆上し、犯人たちを殴殺した。
そのことを聡介が知ったのは、ずいぶんあとのことだった。
思い出すと、じくりと腹の奥が熱い。変身はとうに解いてしまっているのに、戦闘中と同じような血がざわつく感じがする。
ヒトミはそんな聡介を見据え、怒りをぶつけるような声で言う。
「殺された奴は悪党だった。当然の報いだ」
「窃盗では死刑にはならない」
「でも聡介を殺そうとした。無力な子どもを」
「……未遂だ」
「それは聡介のお父さんが助けにきたからだろう! どうして子どもを救った親が裁かれなければいけないんだ! 聡介は憎くないのか、犯人が。父親を裁いた奴らが」
言葉が胸に突き刺さる。水の中みたいに息が苦しかった。
蘇りそうになる恐怖をねじ伏せ、冷静さを保とうと聡介は抑揚のない声で応える。
「理由はどうあれ、父が三人の命を奪ったのは事実だ」
「違う! お父さんは、聡介を助けたんだ」
ヒトミが必死に言い募るけれど、聡介は首を横に降った。
聡介の傷はそれほど深くなかったが、精神的なショックが大きかった。何ヶ月かの入院のあと自宅に戻っても、聡介は一人では家を出られなかった。学校にも行かなかった。恐怖にじっと耐えるだけで精一杯だった。母はいつも何かに怯えているか、泣いているかのどちらかだった。そんな日々を続けてはいけないと思ったのか、母は住み慣れたこの町を捨てる決意をした。
忘れたかった。恐ろしい事件も、罪を犯した父のことも。
聡介が中学生になる頃、母は再婚した。妹ができ、家は少し賑やかになった。母も聡介と二人暮らしの頃よりは格段に明るくなり、笑顔を取り戻していった。
聡介にもようやく、平穏な日々が戻ってきた。それを壊さないように、静かに、危ないことや無茶はしないように、母にこれ以上心配をかけないように。気をつけて、息をひそめて、過ごしてきた。
聡介が社会人になった年に、父は服役を終えたことを祖父にだけ告げ、そのまま行方知れずになった。
祖父は聡介に喫茶ブレイクを託し、郷里へと帰った。その二つの場所に、いつか父が帰ってくるのでないかと考えたらしい。
聡介は父を待つために、母の反対を押し切ってこの町へ帰り喫茶ブレイクを継いだ。これまで、ただごく普通の、ありきたりな生活を必死で守って生きてきた聡介には、大きな決断だった。
何のために待つのかは自分でもわからない。会って何を話していいのかも見当がつかない。上手く思い出すことすらできない、父との思い出も。
それでも、会わなければいけない気がした。自分のために罪を犯した父に。
「お前の父親は間違っていない」
ヒトミの言葉に胸を抉られる。鼓動が速くなった。苦しくて聡介は胸元のシャツをぐしゃっと掴む。爪が食い込むくらい、拳を握り締めた。
「いい加減にしてくれ!」
思わず怒鳴った。声が震えて、喉が酷く乾いていた。ヒトミの表情が悲しげに歪む。だけど、抑えきれなかった。この人に怒りをぶつけても仕方がない。わかっているけれど、止められなかった。
「何をどう調べたのか知らないが、こっちの世界にはこっちの世界の事情があるんだ」
ルールというのはときに理不尽に機能する。完璧なジャッジなど存在しない。それでも、社会を形成する上でルールはなくてはならないものだ。
「どんな理由があるにせよ、罪は罪だ」
そう信じなければ、生きてこられなかった。父は犯罪者だ。だから、自分の家族はバラバラになってしまったのだ。
父が正しかったなどと思えば、世の中の全てを憎んでしまいそうだった。
目的はどうあれ、父の行ったことは〝悪〟だ。そう思って呑み込んだ。
そうやって、聡介は自分の中で折り合いをつけてきたのだ。今さらそれを壊されたら、これからどう心を保っていけばいいのかわからなくなる。
ヒトミは唇を嚙み、聡介を睨む。射貫くような視線だった。
「我が子のためになりふりかまわないのは、罪なのか。わたしは……わたしだって、迷わず殺す。誰だろうが、何人だろうが、息子の命を脅かす者は、許さない。それがたとえ―――」
「口ではなんとでも言える」
言ったあと、しまったと思った。だが、遅い。
表情の消えたヒトミの顔は蒼白だった。澄んだ瞳に見つめられているのが辛くて、聡介は顔を背ける。
ヒトミは何か言おうとしたのか口を開き、だけど何も言わずに踵を返し走り出した。
「ヒトミさん!」
有馬が声をかけたが、ヒトミは足を止めなかった。どんどん遠ざかっていく。
「聡ちゃん、追いかけなくていいの」
「……すぐ帰ってくるだろう。他に行くところないって言ってたし」
有馬からも目を逸らし、聡介は俯く。今は見たくなかった。幼なじみの顔も、走り去る女の後ろ姿も、雨上がりの空も。ただ、自分の立つ地面を凝視するしかなかった。
有馬がそっと肩に触れてくるまで、聡介は立ち尽くしていた。
ヒトミは夜になっても帰ってこなかった。
さすがに心配になって有馬としばらく町中を探したが、ヒトミの姿は見当たらなかった。
彼女はこの世界の人間ではない。ファミレスやネットカフェで一晩やり過ごすなんて方法を思いつくだろうか。生活費を差し引いて僅かながら給料も出してはいるが、現金をちゃんと持っていたかどうかも怪しい。しかも、白ビキニにマントといういかれた格好だ。
あんな格好でお金もろくに持たず、どうしているだろう。捜索を諦めて店に戻ると、もう零時近かった。
今夜は泊まっていくと言った有馬は、勝手に風呂に入り、冷蔵庫から発泡酒を出して飲みながらカップ麺を作り始めた。
「聡ちゃんも食べるでしょ」
「あ、ああ……」
「聡ちゃん、大丈夫?」
「何がだよ。ヒトミさんも大人なんだし、一晩くらい適当にどこかで時間潰してるだろ」
そう言った声が引き攣った。本当は心配で仕方がない。それを顔に出したくなくて、だけどどうして顔に出したくないのかわからない。聡介も冷蔵庫から発泡酒を出して一口飲む。いつもよりも苦く感じた。
「僕は聡ちゃんを心配してるんだよ。思い出したくないこと、思い出しちゃったでしょ」
「ああ……実のところ、あまりよく覚えていないんだ。ほら、大きなショックを受けると記憶が一部抜け落ちるとか、ドラマとかでよくあるだろ。ああいう感じ」
本当のことなのに嘘をついたようなばつの悪さがまといつく。タイマーが鳴ってカップ麺を啜ってみたけれど、味があまりよくわからなかった。
無言でカップ麺をかき込み長い息をついた有馬は、言葉を探すようにしばらく黙り込んだあと、聡介を見た。
「聡ちゃんは強いな。あんな目に遭ったのに、それでも死んでもいい命なんてないって言えるなんて」
困ったような、泣きそうな顔で有馬が言う。つられて、聡介の顔も歪んだ。
「違う……違うんだ、有馬」
聡介は声を詰まらせ、有馬から目を逸らした。
逆だよ、弱いからそう思わなければやりきれない。それだけだ。
父は人殺しだ。だから裁かれた。たとえ息子を助けるためだったとしても、相手が悪人であったとしても、命まで奪ってはいけなかった。
父は罪を犯したのだ。
そう思っていなければ、犯人への憎しみでどうにかなりそうだった。ぶつけるところのない憎しみが胸の中でくすぶって、自分を内側から焼いてしまいそうだった。
有馬は何か話したそうに空になった缶を両手で包みじっと見つめていたが、やがて諦めたように長い息をつき、顔を上げた。
たぶん、聞きたいことも言いたいことも山ほどあるだろう。だけど有馬は言葉を呑み込む。聡介を傷つけないために。
こんなとき、有馬との間に隔たりを感じてしまう。だけどこの隔たりは彼の優しさなのだ。だから聡介も言葉を失ってしまう。
しばしの沈黙のあと、先に口を開いたのは有馬だった。
「ヒトミさんはきっと大丈夫だよ。あの人は賢いから」
「そうだな……」
それによく見える目を持っている。最善の方法でやり過ごしているに違いない。
退屈だった聡介は、あてもなく自転車であちこちを走った。
川沿いの道には桜並木があり、もう少ししたら花見をする人で賑わうだろう。
だが今はまだ蕾かりで今日は風も冷たく、人気もない。誰もいない道を走るのは気分がよかった。
調子に乗ってずいぶん遠くまできてしまったらしい。いつの間にか町の外れまできてしまった。ほとんどきたことがない場所だ。
行く手には廃工場が見えた。持ち主が夜逃げしたとかで、取り壊されることもなくそのまま放置されていた。
ちょっとした冒険心だった。大人は近づくなと言うけれど、こんな身近なところで危ないことなんて、起きるはずがない。そう思っていた。
聡介はそろそろと様子を窺いながら、人気のない廃工場に入っていく。いい天気なのに中は暗く、オイルや何か得体の知れないにおいがした。
最初は怖かったが、薄気味悪い空気にも徐々に慣れた。こんなところに一人で乗り込む自分の度胸に気分がよくなって、聡介は動くのをやめた機械を覗き込んだり、そっと触れたりした。
その、まだ錆びついていない機械に、人影が映ったのをよく覚えている。突然背後から殴られ、聡介の記憶はそこで途切れていた。
聡介を襲ったのは、廃工場をアジトにしていた窃盗グループだった。聡介を探しにきた父が、血を流して倒れている息子を見て逆上し、犯人たちを殴殺した。
そのことを聡介が知ったのは、ずいぶんあとのことだった。
思い出すと、じくりと腹の奥が熱い。変身はとうに解いてしまっているのに、戦闘中と同じような血がざわつく感じがする。
ヒトミはそんな聡介を見据え、怒りをぶつけるような声で言う。
「殺された奴は悪党だった。当然の報いだ」
「窃盗では死刑にはならない」
「でも聡介を殺そうとした。無力な子どもを」
「……未遂だ」
「それは聡介のお父さんが助けにきたからだろう! どうして子どもを救った親が裁かれなければいけないんだ! 聡介は憎くないのか、犯人が。父親を裁いた奴らが」
言葉が胸に突き刺さる。水の中みたいに息が苦しかった。
蘇りそうになる恐怖をねじ伏せ、冷静さを保とうと聡介は抑揚のない声で応える。
「理由はどうあれ、父が三人の命を奪ったのは事実だ」
「違う! お父さんは、聡介を助けたんだ」
ヒトミが必死に言い募るけれど、聡介は首を横に降った。
聡介の傷はそれほど深くなかったが、精神的なショックが大きかった。何ヶ月かの入院のあと自宅に戻っても、聡介は一人では家を出られなかった。学校にも行かなかった。恐怖にじっと耐えるだけで精一杯だった。母はいつも何かに怯えているか、泣いているかのどちらかだった。そんな日々を続けてはいけないと思ったのか、母は住み慣れたこの町を捨てる決意をした。
忘れたかった。恐ろしい事件も、罪を犯した父のことも。
聡介が中学生になる頃、母は再婚した。妹ができ、家は少し賑やかになった。母も聡介と二人暮らしの頃よりは格段に明るくなり、笑顔を取り戻していった。
聡介にもようやく、平穏な日々が戻ってきた。それを壊さないように、静かに、危ないことや無茶はしないように、母にこれ以上心配をかけないように。気をつけて、息をひそめて、過ごしてきた。
聡介が社会人になった年に、父は服役を終えたことを祖父にだけ告げ、そのまま行方知れずになった。
祖父は聡介に喫茶ブレイクを託し、郷里へと帰った。その二つの場所に、いつか父が帰ってくるのでないかと考えたらしい。
聡介は父を待つために、母の反対を押し切ってこの町へ帰り喫茶ブレイクを継いだ。これまで、ただごく普通の、ありきたりな生活を必死で守って生きてきた聡介には、大きな決断だった。
何のために待つのかは自分でもわからない。会って何を話していいのかも見当がつかない。上手く思い出すことすらできない、父との思い出も。
それでも、会わなければいけない気がした。自分のために罪を犯した父に。
「お前の父親は間違っていない」
ヒトミの言葉に胸を抉られる。鼓動が速くなった。苦しくて聡介は胸元のシャツをぐしゃっと掴む。爪が食い込むくらい、拳を握り締めた。
「いい加減にしてくれ!」
思わず怒鳴った。声が震えて、喉が酷く乾いていた。ヒトミの表情が悲しげに歪む。だけど、抑えきれなかった。この人に怒りをぶつけても仕方がない。わかっているけれど、止められなかった。
「何をどう調べたのか知らないが、こっちの世界にはこっちの世界の事情があるんだ」
ルールというのはときに理不尽に機能する。完璧なジャッジなど存在しない。それでも、社会を形成する上でルールはなくてはならないものだ。
「どんな理由があるにせよ、罪は罪だ」
そう信じなければ、生きてこられなかった。父は犯罪者だ。だから、自分の家族はバラバラになってしまったのだ。
父が正しかったなどと思えば、世の中の全てを憎んでしまいそうだった。
目的はどうあれ、父の行ったことは〝悪〟だ。そう思って呑み込んだ。
そうやって、聡介は自分の中で折り合いをつけてきたのだ。今さらそれを壊されたら、これからどう心を保っていけばいいのかわからなくなる。
ヒトミは唇を嚙み、聡介を睨む。射貫くような視線だった。
「我が子のためになりふりかまわないのは、罪なのか。わたしは……わたしだって、迷わず殺す。誰だろうが、何人だろうが、息子の命を脅かす者は、許さない。それがたとえ―――」
「口ではなんとでも言える」
言ったあと、しまったと思った。だが、遅い。
表情の消えたヒトミの顔は蒼白だった。澄んだ瞳に見つめられているのが辛くて、聡介は顔を背ける。
ヒトミは何か言おうとしたのか口を開き、だけど何も言わずに踵を返し走り出した。
「ヒトミさん!」
有馬が声をかけたが、ヒトミは足を止めなかった。どんどん遠ざかっていく。
「聡ちゃん、追いかけなくていいの」
「……すぐ帰ってくるだろう。他に行くところないって言ってたし」
有馬からも目を逸らし、聡介は俯く。今は見たくなかった。幼なじみの顔も、走り去る女の後ろ姿も、雨上がりの空も。ただ、自分の立つ地面を凝視するしかなかった。
有馬がそっと肩に触れてくるまで、聡介は立ち尽くしていた。
ヒトミは夜になっても帰ってこなかった。
さすがに心配になって有馬としばらく町中を探したが、ヒトミの姿は見当たらなかった。
彼女はこの世界の人間ではない。ファミレスやネットカフェで一晩やり過ごすなんて方法を思いつくだろうか。生活費を差し引いて僅かながら給料も出してはいるが、現金をちゃんと持っていたかどうかも怪しい。しかも、白ビキニにマントといういかれた格好だ。
あんな格好でお金もろくに持たず、どうしているだろう。捜索を諦めて店に戻ると、もう零時近かった。
今夜は泊まっていくと言った有馬は、勝手に風呂に入り、冷蔵庫から発泡酒を出して飲みながらカップ麺を作り始めた。
「聡ちゃんも食べるでしょ」
「あ、ああ……」
「聡ちゃん、大丈夫?」
「何がだよ。ヒトミさんも大人なんだし、一晩くらい適当にどこかで時間潰してるだろ」
そう言った声が引き攣った。本当は心配で仕方がない。それを顔に出したくなくて、だけどどうして顔に出したくないのかわからない。聡介も冷蔵庫から発泡酒を出して一口飲む。いつもよりも苦く感じた。
「僕は聡ちゃんを心配してるんだよ。思い出したくないこと、思い出しちゃったでしょ」
「ああ……実のところ、あまりよく覚えていないんだ。ほら、大きなショックを受けると記憶が一部抜け落ちるとか、ドラマとかでよくあるだろ。ああいう感じ」
本当のことなのに嘘をついたようなばつの悪さがまといつく。タイマーが鳴ってカップ麺を啜ってみたけれど、味があまりよくわからなかった。
無言でカップ麺をかき込み長い息をついた有馬は、言葉を探すようにしばらく黙り込んだあと、聡介を見た。
「聡ちゃんは強いな。あんな目に遭ったのに、それでも死んでもいい命なんてないって言えるなんて」
困ったような、泣きそうな顔で有馬が言う。つられて、聡介の顔も歪んだ。
「違う……違うんだ、有馬」
聡介は声を詰まらせ、有馬から目を逸らした。
逆だよ、弱いからそう思わなければやりきれない。それだけだ。
父は人殺しだ。だから裁かれた。たとえ息子を助けるためだったとしても、相手が悪人であったとしても、命まで奪ってはいけなかった。
父は罪を犯したのだ。
そう思っていなければ、犯人への憎しみでどうにかなりそうだった。ぶつけるところのない憎しみが胸の中でくすぶって、自分を内側から焼いてしまいそうだった。
有馬は何か話したそうに空になった缶を両手で包みじっと見つめていたが、やがて諦めたように長い息をつき、顔を上げた。
たぶん、聞きたいことも言いたいことも山ほどあるだろう。だけど有馬は言葉を呑み込む。聡介を傷つけないために。
こんなとき、有馬との間に隔たりを感じてしまう。だけどこの隔たりは彼の優しさなのだ。だから聡介も言葉を失ってしまう。
しばしの沈黙のあと、先に口を開いたのは有馬だった。
「ヒトミさんはきっと大丈夫だよ。あの人は賢いから」
「そうだな……」
それによく見える目を持っている。最善の方法でやり過ごしているに違いない。