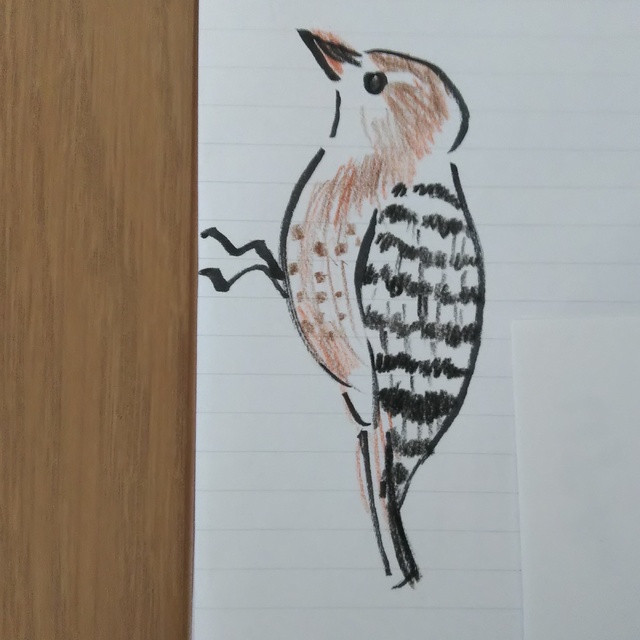王都にてDAY.02 ①『野良』
文字数 5,163文字
文字通り、一晩中語り明かした私達が目を覚ましたのは、昼過ぎだった。
私達は簡単に食事を済ませて、部屋を出た。男が"あの村"で暮らし、私が"この部屋"で暮らす為の準備を整える買い物をする為だ。
「手短に済ませるぞ。明朝には出発しないと、村に着くのが遅れてしまう」
私が村を出てから既に3日が過ぎていた。男の到着を考えると、5日間も村に医者が不在ということになってしまう。一応、大人達に怪我をした時の簡単な処置の方法や、診療所の薬の置き場は伝えて来たが……それでも心配は尽きなかった。
「向こうに着いても、お前が直ぐに動けるとは思えないからな」
「大丈夫ですよ。君からの手紙で依頼された薬品や医療道具を行商人に持たせていたのは、僕なんですから」
確かに、診療所に必要なものは、毎回手紙で男に依頼していた。医者としての経験も長いこの男なら、物の在りかさえわかれば問題はないだろう。ただ、私が心配しているのは"そこ"ではなかった。
「お前の体力の事を言っている。馬宿からは道が悪いからな、徒歩でしか村には辿り着けない」
この15年間で山歩きに慣れた私ですら、王都 までの道のりは骨の折れるものだった。お世辞にも体格がいいとは言えないこの男が、村に着いて直ぐに使い物になるとは思えなかった。
「山歩きを甘くみるな。本に囲まれた生活とは比べ物にならないぞ」
「わかってますよ。君の方こそ、僕の本をあまりいじらないようにしてくださいよ。どれも貴重な本ばかりなんですから」
「……お前、不安ではないのか?」
あまりにも動じていない男に、私は聞いた。
「これからお前は、王都 とは全く違った暮らしの場所に行くのだぞ」
「それは、昨晩散々聞かされたじゃないですか。朝はシユ河に水を汲みに行くことから始まるんでしょう?」
「……そうだが」
「水を汲み、火を起こし、煮沸し清潔な水を確保する。そこから一日が始まる。僕達の曾祖父の時代に時空旅行をするようなものじゃないですか。子どもの頃読んだ本に、そんな物語がありましたね」
「……」
"無血"と呼ばれた私も大概だと思ったが、やはりそんな女と今まで付き合ってくる事が出来たこの男もまた変わり者だと言うことを、改めて実感した。
「君は村人達から先生 と呼ばれていたんですよね?他にも、月 や太陽 など、今では使われていない言葉が、あの村には残っていたと」
「……ああ」
思わず、娘達の顔が浮かんだ。
「それは古代イーナ語の名残だと思うんです。イーナ語というのは、ジョド文明圏で使われていた言葉なのですが、不思議なのは、ジョド文明の発祥は海を越えた隣の大陸のはずーー」
「歴史の話はいい。結論を言え」
「言葉の違いは文化の違い。文化の違いは常識の違いでもあります。王都 の常識が通じない場所なんて、異国も同然。興味深いじゃないですか」
「……」
平気な顔でそう言う男に、私は昨日の言葉を思い出した。この男は、"そういう男"だった。
「患者が居ない時は、子ども達に勉強を教える。僕の医者としての王都 での暮らしとの大きな違いはそれくらいのものでは?」
「……もういい。お前の場合、語るよりも実際に体験した方が早いようだ」
半ば呆れながらつい口にしたその言葉に、私は15年前を思い出した。あの時も、私に似たような言葉を残していった者がいた。そんな事を思い出しながら、私は男の隣を歩いた。
一通り買い物を終えた私達は、男の希望で薬屋に寄ることになった。
「まぁ先生!」
随分古びた小さな建物だった。
私達が扉を開けようとした時、丁度中から扉が開いて、小さな布袋を手にした女が出てきた。
「先日はありがとうございました!お陰で娘も元気になりました!」
「ああ、それは良かったですね」
どうやら、男の患者の母親のようだった。この店に薬を買いに来ていたらしい。
「くれぐれも無理はせずに。薬は必ず飲み切って下さい。再発の恐れがありますから」
「はい!いつもいつも、本当にありがとうございます!」
深々と頭を下げながらそう言うと、女は去っていった。
「……"野良の医者"をしているというのは、本当だったのだな」
「ええ。組織に属さないのは自由でいいものですよ。ああ、君も似たようなものでしたね」
「お前が勤めていた診療院を辞めて、どこにも属さずにやっていくと知った時、父はえらく憤慨していたぞ」
「"先生"には、お世話になりましたからね。恩を仇で返したようなものです」
医者である私の父は、その傍らで長いこと医学院の院長も勤めていた。在院中の私にとっては、人としては父であり、医者としては師でもあった。
医学院卒業後、この男は父の推薦で父と同じ王室直属の診療院に勤めていたのだが、僅か半年で辞めた。丁度、私があの村へ派遣される直前の事だった。
男からの手紙で、その後は野良の医者として暮らしていた事は知っていたが……診療院を辞めた理由までは知らなかった。
「恐らく父は、いずれお前を自分の右腕にしたかったのだろう。当時、医学院を首席で卒業したお前が、どうして"そんな愚行に走った"のかと、随分ぼやいていた」
「はは。愚行、ですか」
男は苦笑いを浮かべると、眼鏡を外して太陽にかざした。
「その理由は、この先にありますよ」
そう言って、男は改めて眼鏡をかけ直すと、薬屋のドアを開いた。
「よう、遅かったな」
私達が扉を潜ると、薄暗い店の奥には随分年老いた男が座っていた。
「大先生 。明日の朝、"あの村"へ発ちます。頼んでおいた薬をいただきに来まーー」
「老師 、か?」
男の言葉を遮るように、私の口からはその名が溢れた。
「ハッハー。その名で呼ばれるのは随分久しい。10年振りか?いい面 になったな、小娘」
年老いた男はシワだらけの顔をさらに崩して笑った。その独特な笑い方は、間違いなく私の知る男だった。
「10年ではない。15年だ」
「年寄りにしてみれば、どっちもさほど変わらん」
忘れもしない15年前。私があの村に派遣された時に、先代の医者として村に常駐していたのが、村の人々から老師 と呼ばれていたこの男だった。
只でさえ村への派遣に不満があった上に、王都とは全く違う慣れない暮らしに混乱する私に、満足な引き継ぎをすることなく王都へ帰って行った薄情者。当時の私は、老師 に恨みしか抱いていなかった。
「習うより、慣れろ。解らんことは、自分で聞いて覚えろ」
そう言い残して、年寄りとは思えない軽快な足取りで去っていったあの後ろ姿を、今でもはっきり覚えている。
「まだ生きていたのか」
「……大先生 に失礼ですよ」
思わず本音が溢れた私を、男が肘で小突いた。私が村で出会った15年前ですら"いい歳"だったのだ。きっと、今の医学でも生きているのが不思議な位の歳のはずだ。
「ハッハー。相変わらず口の悪い小娘だ。若い頃のお前の"親父"によく似とる」
「親父?父を知っているのか?」
「……君、まさか大先生 の事を知らないんですか?」
「いや、あの村に私の前に常駐していた医者だという事は知っている」
「それだけじゃなくてーー」
「あとは助平な爺 だという事くらいか」
村の女達からも、腕はいいが手が早い男だったと……老師 の卑猥な所業は数えきれない程聞かされていた。それにも関わらず、村に老師 を悪く言う者はほとんど居なかったのが不思議だった。私は何度か尻を触られて、殴った覚えがあったけれど。
「す、助平だなんて……口を慎んで下さい。君は大先生 の事を何もわかっちゃいない」
「事実は事実だ」
珍しく取り乱している男に、私は強い口調で言った。
「私はこの助平爺が嫌いだ」
「ちょっー…」
「ハッハー!構わんさ。小娘の言う通り事実は事実。ワシはこの小娘に何も教えちゃいないからな」
「ならば尚の事。大先生 の偉業を伝えなければなりません」
私は男に促されるままに、老師 に背を向けた。
「いいですか、大先生 は我が国の医学の礎を築いた方です。僕達が学んだ医学院の創設者にして初代院長。君のお父上の師でもあります。本名を聞けば、きっと君もわかるはずです」
「そうだったのか」
男は小声だったが、私は声を落とす事はしなかった。
「……もっと驚く所では?」
「十分驚いている。ただの助平爺ではなかったのだとな」
「だから口を慎んでとーー」
「いやいや、今でも現役の助平爺だ。まだまだ小娘には変わらんが、少しは色気が出たか?尻を触らせてみろ」
「更に爺になっていても殴るぞ、私は」
「……」
急いで振り返り、拳を掲げた私の横で、男は青ざめた顔のまま立ち尽くしていた。言葉を発する気も失せたようだ。
「ワシを大先生 などと呼ぶのは、この男くらいだ。隠居した今では、この"裏"薬屋として余生を生きとる爺に過ぎん」
「裏?悪さでもしているのか?」
「違法行為をしているわけではありません。大先生 は他の診療所よりも格安で薬を販売しているだけです」
私が眉を潜めると、男が補足した。
「今はどの診療所からでも薬が出されますが、高額な診察代金を払えず、そもそも医者にかかる事が出来ない者も、この王都では少なくありません。そういう人々にとって、薬を安く売ってくれるこの店は欠かせないんです。まぁ、診療所 に勤める医者達は良い顔をしませんが」
「だから"裏"、というわけか。よく薬が手に入るな」
「一重に、大先生 の広い人脈があってこそです」
私が言うと、男は一人で深く頷いた。
「君は知らないかもしれませんが、王都 の貧富の格差は、"あの頃"より大きくなっています。医者にかかれない子どもも大勢います。さっきの女性の子どものように」
言葉には出さなかったが、確かにあの母親の身なりはお世辞にも整ったものとは言えなかった。私がこの街に感じた"壁"の理由のひとつがわかったような気がした。
「あのまま診療院に勤めていたら、自分の意志で彼等を診る事が出来なくなってしまいます。昨日君は言っていましたよね?"無益な血が流れる暴挙を、医者の自分は見過ごせない"と」
「……ああ」
「僕にとっては、自分が組織に属する事が暴挙になるんです。僕は、自分が診たいと思った人なら、誰でも平等に診る事が出来る医者でありたい」
「……」
男は、昨日とはまた違った顔を私に見せた。昨日が人としての顔だとするなら、今日は医者としての顔だった。
「ただ、僕が"野良"である以上、診察や簡単な治療はできても、薬を出してあげる事は出来ません。もちろん、毛嫌いされている僕が診療所に頼んでも薬を出してはくれません。王都の中でこの薬屋だけが、僕からの処方も受けてくれるんです。僕が医者として自分の信念を貫きながらこの街で暮らせているのは、大先生 が居るからです。僕は大先生 から、医者としての生き方を教えてもらいました」
「……」
どうやら、男にとって老師 は、言葉の通り"師"のようだった。私にとっては、あの村の人々がそうであったように。
「患者が医者を選ぶのはいい。医者にも馬鹿と天才が居るからな。だが、医者が患者を選ぶようになったら医学は終わりだ」
老師 が医者らしい事を言っているのを、私は初めて聞いた。
「近隣の国々に比べて頭ひとつ医学が進んだ位で国の誇りと呼び、高く祭り上げ、貧しい者の手には届かぬものになりつつあるのが、この国の現状だ。現王側 を持つお前の親父の苦労もわかるが……ワシが作りたかったのは、こんな尻の穴の小さい国じゃない」
老師 は小指で鼻をほじってはいたが、その言葉に偽りは無いのだろう。妙に説得力があった。
「もしもお前が親父と話すんなら、"もっと尻の穴を広げろ"と伝えておけ」
「……断る。自分で言え」
言葉の選び方は最低だが、その真意には感心するものがあったのは事実。そう、医者としての私が言っていた。
「では大先生 、少しの間王都を離れます。その間、患者達を宜しくお願いします」
「おう。あの村では習うより慣れろだ。解らんことは、自分で聞いて覚えろ」
老師 は、私に言ったのと同じ様な言葉を男に送ると、薬が入っているだろう大きな布袋を男に渡した。
「小娘、お前がそいつの代わりに王都に残るんだろう?」
「そのつもりだ」
「たまに面を出せ」
「なぜだ?」
「寂しいだろうからな。尻を撫でてやる」
「面も出さんし、尻も撫でさせん。用が済んだらさっさと行くぞ」
私は男の腕を掴んで、強引に引いて薬屋を出た。
少しでも、老師 を見直した医者としての自分を……人としての自分が諫めていた。
つづく。
私達は簡単に食事を済ませて、部屋を出た。男が"あの村"で暮らし、私が"この部屋"で暮らす為の準備を整える買い物をする為だ。
「手短に済ませるぞ。明朝には出発しないと、村に着くのが遅れてしまう」
私が村を出てから既に3日が過ぎていた。男の到着を考えると、5日間も村に医者が不在ということになってしまう。一応、大人達に怪我をした時の簡単な処置の方法や、診療所の薬の置き場は伝えて来たが……それでも心配は尽きなかった。
「向こうに着いても、お前が直ぐに動けるとは思えないからな」
「大丈夫ですよ。君からの手紙で依頼された薬品や医療道具を行商人に持たせていたのは、僕なんですから」
確かに、診療所に必要なものは、毎回手紙で男に依頼していた。医者としての経験も長いこの男なら、物の在りかさえわかれば問題はないだろう。ただ、私が心配しているのは"そこ"ではなかった。
「お前の体力の事を言っている。馬宿からは道が悪いからな、徒歩でしか村には辿り着けない」
この15年間で山歩きに慣れた私ですら、
「山歩きを甘くみるな。本に囲まれた生活とは比べ物にならないぞ」
「わかってますよ。君の方こそ、僕の本をあまりいじらないようにしてくださいよ。どれも貴重な本ばかりなんですから」
「……お前、不安ではないのか?」
あまりにも動じていない男に、私は聞いた。
「これからお前は、
「それは、昨晩散々聞かされたじゃないですか。朝はシユ河に水を汲みに行くことから始まるんでしょう?」
「……そうだが」
「水を汲み、火を起こし、煮沸し清潔な水を確保する。そこから一日が始まる。僕達の曾祖父の時代に時空旅行をするようなものじゃないですか。子どもの頃読んだ本に、そんな物語がありましたね」
「……」
"無血"と呼ばれた私も大概だと思ったが、やはりそんな女と今まで付き合ってくる事が出来たこの男もまた変わり者だと言うことを、改めて実感した。
「君は村人達から
「……ああ」
思わず、娘達の顔が浮かんだ。
「それは古代イーナ語の名残だと思うんです。イーナ語というのは、ジョド文明圏で使われていた言葉なのですが、不思議なのは、ジョド文明の発祥は海を越えた隣の大陸のはずーー」
「歴史の話はいい。結論を言え」
「言葉の違いは文化の違い。文化の違いは常識の違いでもあります。
「……」
平気な顔でそう言う男に、私は昨日の言葉を思い出した。この男は、"そういう男"だった。
「患者が居ない時は、子ども達に勉強を教える。僕の医者としての
「……もういい。お前の場合、語るよりも実際に体験した方が早いようだ」
半ば呆れながらつい口にしたその言葉に、私は15年前を思い出した。あの時も、私に似たような言葉を残していった者がいた。そんな事を思い出しながら、私は男の隣を歩いた。
一通り買い物を終えた私達は、男の希望で薬屋に寄ることになった。
「まぁ先生!」
随分古びた小さな建物だった。
私達が扉を開けようとした時、丁度中から扉が開いて、小さな布袋を手にした女が出てきた。
「先日はありがとうございました!お陰で娘も元気になりました!」
「ああ、それは良かったですね」
どうやら、男の患者の母親のようだった。この店に薬を買いに来ていたらしい。
「くれぐれも無理はせずに。薬は必ず飲み切って下さい。再発の恐れがありますから」
「はい!いつもいつも、本当にありがとうございます!」
深々と頭を下げながらそう言うと、女は去っていった。
「……"野良の医者"をしているというのは、本当だったのだな」
「ええ。組織に属さないのは自由でいいものですよ。ああ、君も似たようなものでしたね」
「お前が勤めていた診療院を辞めて、どこにも属さずにやっていくと知った時、父はえらく憤慨していたぞ」
「"先生"には、お世話になりましたからね。恩を仇で返したようなものです」
医者である私の父は、その傍らで長いこと医学院の院長も勤めていた。在院中の私にとっては、人としては父であり、医者としては師でもあった。
医学院卒業後、この男は父の推薦で父と同じ王室直属の診療院に勤めていたのだが、僅か半年で辞めた。丁度、私があの村へ派遣される直前の事だった。
男からの手紙で、その後は野良の医者として暮らしていた事は知っていたが……診療院を辞めた理由までは知らなかった。
「恐らく父は、いずれお前を自分の右腕にしたかったのだろう。当時、医学院を首席で卒業したお前が、どうして"そんな愚行に走った"のかと、随分ぼやいていた」
「はは。愚行、ですか」
男は苦笑いを浮かべると、眼鏡を外して太陽にかざした。
「その理由は、この先にありますよ」
そう言って、男は改めて眼鏡をかけ直すと、薬屋のドアを開いた。
「よう、遅かったな」
私達が扉を潜ると、薄暗い店の奥には随分年老いた男が座っていた。
「
「
男の言葉を遮るように、私の口からはその名が溢れた。
「ハッハー。その名で呼ばれるのは随分久しい。10年振りか?いい
年老いた男はシワだらけの顔をさらに崩して笑った。その独特な笑い方は、間違いなく私の知る男だった。
「10年ではない。15年だ」
「年寄りにしてみれば、どっちもさほど変わらん」
忘れもしない15年前。私があの村に派遣された時に、先代の医者として村に常駐していたのが、村の人々から
只でさえ村への派遣に不満があった上に、王都とは全く違う慣れない暮らしに混乱する私に、満足な引き継ぎをすることなく王都へ帰って行った薄情者。当時の私は、
「習うより、慣れろ。解らんことは、自分で聞いて覚えろ」
そう言い残して、年寄りとは思えない軽快な足取りで去っていったあの後ろ姿を、今でもはっきり覚えている。
「まだ生きていたのか」
「……
思わず本音が溢れた私を、男が肘で小突いた。私が村で出会った15年前ですら"いい歳"だったのだ。きっと、今の医学でも生きているのが不思議な位の歳のはずだ。
「ハッハー。相変わらず口の悪い小娘だ。若い頃のお前の"親父"によく似とる」
「親父?父を知っているのか?」
「……君、まさか
「いや、あの村に私の前に常駐していた医者だという事は知っている」
「それだけじゃなくてーー」
「あとは助平な
村の女達からも、腕はいいが手が早い男だったと……
「す、助平だなんて……口を慎んで下さい。君は
「事実は事実だ」
珍しく取り乱している男に、私は強い口調で言った。
「私はこの助平爺が嫌いだ」
「ちょっー…」
「ハッハー!構わんさ。小娘の言う通り事実は事実。ワシはこの小娘に何も教えちゃいないからな」
「ならば尚の事。
私は男に促されるままに、
「いいですか、
「そうだったのか」
男は小声だったが、私は声を落とす事はしなかった。
「……もっと驚く所では?」
「十分驚いている。ただの助平爺ではなかったのだとな」
「だから口を慎んでとーー」
「いやいや、今でも現役の助平爺だ。まだまだ小娘には変わらんが、少しは色気が出たか?尻を触らせてみろ」
「更に爺になっていても殴るぞ、私は」
「……」
急いで振り返り、拳を掲げた私の横で、男は青ざめた顔のまま立ち尽くしていた。言葉を発する気も失せたようだ。
「ワシを
「裏?悪さでもしているのか?」
「違法行為をしているわけではありません。
私が眉を潜めると、男が補足した。
「今はどの診療所からでも薬が出されますが、高額な診察代金を払えず、そもそも医者にかかる事が出来ない者も、この王都では少なくありません。そういう人々にとって、薬を安く売ってくれるこの店は欠かせないんです。まぁ、
「だから"裏"、というわけか。よく薬が手に入るな」
「一重に、
私が言うと、男は一人で深く頷いた。
「君は知らないかもしれませんが、
言葉には出さなかったが、確かにあの母親の身なりはお世辞にも整ったものとは言えなかった。私がこの街に感じた"壁"の理由のひとつがわかったような気がした。
「あのまま診療院に勤めていたら、自分の意志で彼等を診る事が出来なくなってしまいます。昨日君は言っていましたよね?"無益な血が流れる暴挙を、医者の自分は見過ごせない"と」
「……ああ」
「僕にとっては、自分が組織に属する事が暴挙になるんです。僕は、自分が診たいと思った人なら、誰でも平等に診る事が出来る医者でありたい」
「……」
男は、昨日とはまた違った顔を私に見せた。昨日が人としての顔だとするなら、今日は医者としての顔だった。
「ただ、僕が"野良"である以上、診察や簡単な治療はできても、薬を出してあげる事は出来ません。もちろん、毛嫌いされている僕が診療所に頼んでも薬を出してはくれません。王都の中でこの薬屋だけが、僕からの処方も受けてくれるんです。僕が医者として自分の信念を貫きながらこの街で暮らせているのは、
「……」
どうやら、男にとって
「患者が医者を選ぶのはいい。医者にも馬鹿と天才が居るからな。だが、医者が患者を選ぶようになったら医学は終わりだ」
「近隣の国々に比べて頭ひとつ医学が進んだ位で国の誇りと呼び、高く祭り上げ、貧しい者の手には届かぬものになりつつあるのが、この国の現状だ。
「もしもお前が親父と話すんなら、"もっと尻の穴を広げろ"と伝えておけ」
「……断る。自分で言え」
言葉の選び方は最低だが、その真意には感心するものがあったのは事実。そう、医者としての私が言っていた。
「では
「おう。あの村では習うより慣れろだ。解らんことは、自分で聞いて覚えろ」
「小娘、お前がそいつの代わりに王都に残るんだろう?」
「そのつもりだ」
「たまに面を出せ」
「なぜだ?」
「寂しいだろうからな。尻を撫でてやる」
「面も出さんし、尻も撫でさせん。用が済んだらさっさと行くぞ」
私は男の腕を掴んで、強引に引いて薬屋を出た。
少しでも、
つづく。