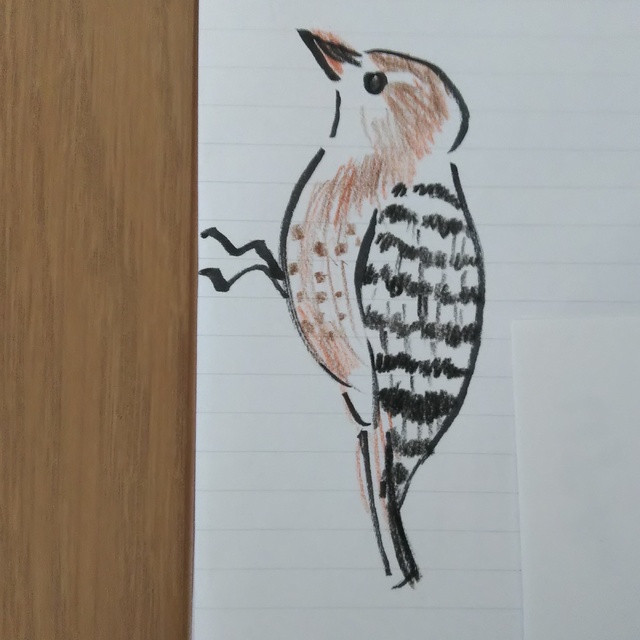王都にてDAY.03 『出発』
文字数 4,872文字
独りで眠らない夜を過ごしたのは、何年振りだったろう。
目が覚めた私は、カーテンの隙間から差し始めた朝日を呆然と眺めながらそんな事を考えていた。
思い出したのは……10年程前の村での記憶。
娘達がまだ小さかった頃に、夜に勉強小屋に子ども達を集めて怪談話をした事があった。
すっかり怯えてしまった泣き虫娘の一人が、夜道を歩いて家に帰る事も出来なくなり……結局、私の診療所に泊まることになった。
最初は別々で寝ていたのに、いつの間にか私の寝床に潜り込んで来ていた。仕方なく、私達は手を繋いで一緒に眠った。
朝になり隣に身を縮めながら眠っている娘の寝顔を見た時、とても不思議で……幸せな気持ちになった。子どものいない私にも、母性というものがある事を知った出来事だった。
「……」
もちろん、あの時とは全く違った状況。全く違った感情。それでもどこか似たような幸福感を抱きながら、私は寝付いた時よりも少しだけ広くなっていた寝床を抜け出した。
「やあ。丁度珈琲を淹れてたんですよ」
私の顔を見るなり、いつもと変わらない調子で男が言った。
「飲みます?」
「……他に言うことは無いのか?」
「ああ、もちろん砂糖はつけますよ」
「変わらないんだな、お前は」
「たった一晩ですからね」
そう言うと、男は慣れた手付きで私の分も珈琲を淹れ始めた。
「……」
その横顔を私は黙って見ていた。
男が言うように、見た目からは何も変わった印象は受けなかった。
15年振りに再会し、男はその日のうちに「君は変わった」と私に言ってくれた。反対に、私は男に「お前は変わらない」と言った。けれど、本当は違っていた。
言い合いになった時にムッとした顔で反論してくる姿こそ、あの頃から変わってはいなかった。けれど、子ども の前で見せる笑顔や、患者の前で見せる医者としての顔、そして何より自分の本音を口にした時の真剣な顔。この男もまた、この王都 で過ごした15年で随分変わっていた。
再会した直後に"それ"に気づいた男と、2日もかかってしまった私。思えば、それだけ男が昔から私の事を見てくれていた証であり、私が男の事を見ていなかった証拠でもあった。
「医学院で初めて会った日からずっと、君の事が好きでした」
男はそう言ってくれた。"無血"だった頃の私でさえ、好きだったと。けれど、その思いを伝えてくれたのは、15年経ってからだった。
きっと、あの頃の私の目に自分が映っていない事を男はわかっていたからだろう。もしもあの頃に告白されていたとしても、私は間違いなく首を縦には振らなかった。
「くだらない話をするな。馬鹿にしているのか?」そう言い放っていただろう自分が目に浮かんだ。もしもこの男が本当に15年私を想い、待っていてくれたのだとしたら……
私と初めて共にした一夜は、特別な時間じゃなかったのか?
そう思っている私が居る反面、あまりにもいつもと変わらない様子を見せつけられると、自分だけが考え過ぎているかも知れないと思ってしまう私も居た。いくら言葉を並べられても、私はこの男の15年を知らないからだ。
そう考えると悔しい気持ちにもなった。もちろん、そんな事を男の前で言うつもりはなかったし、聞くつもりもなかった。
「どうぞ」
「……あ、ああ」
そんな風な疑問や不満を考えているうちに、いつの間にか珈琲は淹れられていた。私は男から湯気が立つ珈琲を受け取ると一口すすった。
「ッ?!」
その直後、声にならない声と共に肩をすくめた。
「どうかしまいましたか?」
私の様子に、男が隣で首を傾げた。
「……いや、何でもない。少し熱かっただけだ」
「淹れたてですから。気をつけてください」
「……ああ」
本当は、そうじゃない。
男が淹れてくれた珈琲には、砂糖が入っていなかった。口の中に広がった強い苦味に、私は顔をしかめたのだった。
珈琲に砂糖が入っていなかっただけ。
些細な事かもしれないが、私にはそれが意外だった。
「珈琲は寝起きではなく朝食後に飲むのが望ましいらしいんです。本来なら直さなければならないのでしょうが……僕の場合は習慣になってしまっているので。朝一でコレを飲まないと、なかなか、目が覚めないんです」
しかもその事に、男は全く気付いていなかった。
これまで男が珈琲を淹れてくれたことは何度もあったが、苦いものが苦手な私の珈琲に砂糖を入れ忘れる事など一度もなかった。
「朝日を浴びる事も、目を覚ますにはいいらしいですよ。異国の医学書で読んだ事があります。興味があれば探して読んでみてください。昨日も言いましたけど、医学書だけはちゃんと棚に戻しておいて下さいね」
「……」
そう言えば、いつもより饒舌なような気がした。平常心を装ってはいるが、この男も少なからず"普段とは違った精神状態 "である事は間違いなさそうだった。
そう思うと、何だか安心出来た。
「ふっ」
「どうしたんです?」
私が笑うと、男は不思議そうに珈琲をすすった。
「いや、なんでもない。"そういう事"にしておくよ、首席殿」
「……何か、隠してますね」
男が不満げな顔をしながら私の尻に伸ばしてきたその手を、私は遠慮なくつねりあげた。
まだ朝が早いという事もあり、馬車の乗り合い所には馬と御者以外には私達しかいなかった。
「道中は道が悪い。くれぐれも気をつけて行くのだぞ。途中、風が強く吹く谷を通る。マントは持ったか?それから、路銀は多目に持っていた方がいい。野盗に出くわさないとも限らないからな」
「まるで心配性の母親のような物の言い方ですね」
私が言うと、男はパンパンに膨らんだ鞄を叩きながら笑った。その中身のほとんどが私が無理やり持たせたものだった。
「心配でしかない。お前はあの村までの道のりをわかっていない」
これから王都を発ち、男があの村へ到着するのは2日後。しかもそれは旅路が"順調に"進んだ場合だった。
「大丈夫ですよ。大先生 からも道中の事は聞いていましたから」
「老師 の言う事はいい加減だ。あまり鵜呑みには――まあいい」
言いかけて、私は言葉を切った。昨日の出来事を思い出したからだ。
「すまないが、これを私の娘達に渡してくれ」
私は自分の鞄から、二本の櫛を取り出し、男に差し出した。
「お土産、ですか?」
それは昨日、街で買い物をした時に買っていた物だった。"月"と"太陽"がそれぞれに彫り込まれた櫛。露店で見た瞬間に即決して買ったものだった。
「そんなところだ。他の子ども達の分はないからな、こっそり渡してやってくれ。太陽の模様は髪の短い元気な方。月の模様は髪の長い大人しい方だ」
「ええと、パルティマとシュシーマ、でしたっけ?」
「
「ああそうか、太陽と月。イーナ語でしたね。わかりました。ちゃんと渡しておきますよ」
男は髪飾りと手紙を受けとると、鞄ではなく懐にしまった。
「他に、何か心配事はありますか?」
「全てが心配だ。村に着いたら必ず手紙を送ってくれ」
それでも、その手紙が私の手元に届くのはずいぶん先になってしまうのだが……。
「お前は、心配ではないのか?」
「その話は一昨日に済んでます。強いて言うのであれば――」
そう言うと、男は私の手を取った。
「君と離れる事が心配です」
たった1日で私への態度が別人のように変わったこの男に、私は改めて朝の想いを取り消した。
「私は王都に居るんだぞ?何を心配する事がある?」
「……まぁ、いろいろと」
男が気まずそうに言い渋る様子から、私の勘がその理由を察した。
「なるほど。三席殿の事か」
「……」
男は黙っていたが、実に分かりやすい反応だった。
「確かに、奴は私を妻に娶 るつもりらしいからな。小男とは言え男だ。力ずくで来られたら太刀打ち出来ないかも――」
「それは心配していません」
ところが、男はバッサリ言い切った。
「君の拳が、そんなに弱いとは思っていません」
「おい、暴力は無意味だと言ったのはお前だぞ?」
「自分の身を守るための抵抗は暴力ではありません。もしもの時は、存分に暴れて下さい」
「ものは言いよう、か。ズルい答えだ。人を暴れん坊のように言うな」
私は握られた手を振り払った。
「ならば何が心配だと言うんだ?」
「もしも君の縁談が本当にお父上に仕組まれていたものだとして、君が縁談を受ける事でお父上が壁の建設中止に口を出すという条件を出したとしたら。そう考えると不安ではあります」
私は男が言わんとしている事がわかった。
「私が、娘たちの為に自分の身を犠牲にするのではないか、ということか」
「……」
私がそう推測すると、男は黙って頷いた。
「"私達"をみくびるな」
私は男を睨んだ。
「もしも私が望まぬ結婚と引き換えに壁の撤回を勝ち取ったとしても、あの娘達が喜ばない事は十分わかっている」
自分を過大評価するわけではなく、私が娘達を大切に思っているのと同じだけ、娘達も私を大切に思ってくれている。私にはそれがわかっていたし、そう思われている自信があった。それは自惚れではなく、信頼だと思う。
「私は自分の力で壁の建設を止め、自分の足であの村に帰る。それ以外の選択肢はない」
「そう、ですね。すみません」
そう言うと、男は頭を下げた。
「どうやら僕は君を……いや、"君達"の繋がりを甘く見ていたようです」
「全くだ。15年だぞ?たった一晩で越えられると思ったのか?」
「……正直、自信はありません。君が僕とあの村を天秤にかけた時、君に選んでもらう自信が僕にはありません」
「……冗談だ。馬鹿正直に捉えるな」
明らかに寂しそうな顔をした男の頭に手を伸ばし、何度か撫でてやった。
変わったのはこの男だけじゃない。自分から自然に"そう"出来るようになっていた私もまた、たった一晩で随分変わったようだった。
無血から人間に変わるのには何年もかかったのに、学友から恋仲へ変わるのにはたった一晩しかかからなかった。つくづく、人の気持ちほど不完全で不安定なものはないと実感した。
「私にとってあの村も娘達も特別だ。だが、お前も……まぁ特別だ。そもそも向けている感情が違うんだ。優劣なんてつける必要はないだろう」
「そう言ってもらえると、有難いですね」
私達はどちらからともなく身を寄せると、互いを抱きしめた。
私にとってはやはり抱擁は分岐点。今回は、この男との別れの決断の場だった。
「村の若い娘達に手を出すんじゃないぞ」
「わかっています。君に殴られるのも、殴らせるのも嫌ですからね」
「ふふ、その時は、"右手"を使ってやるさ」
「……それは責任重大ですね」
「そこの熱いお二人さん、そろそろ出発するぜ」
御者にからかうように言われ、私達は慌てて身を離した。
いつの間にか、馬車には何人かの客が乗り込み、出発の時を待っているようだった。
「では、行ってきます」
「ああ」
私は男が差し出した手をもう一度握り返した。
「くれぐれも、無茶をしないで下さいね」
「わかっている。お前もな」
握った手を離さなければならないのに、私には自分からそうする事が出来なかった。
つい数日前に別れた娘達と過ごした時間の方が圧倒的に長いにも関わらず、たった2日しか一緒にいなかったこの男との別れが、その時以上に辛いと思っている私がいた。
――この手を、離したくない。一人になりたくない
そう思ってしまう自分の心を無理やり律し、私は手を離した。
誰かと別れるという事が、こんなに辛いとは思わなかった。
「……」
男は、いつものように少し困ったような笑みを最後に浮かべると、何も言わずに馬車の荷台に乗り込んだ。
私も少しづつ遠くなっていくその姿を黙って見送った。
村の人達から見送られた私にとって、誰かを見送るというの事が初めての経験だった。
私があの村を発つ時の娘達も、こんな気持ちだったのだろうか?
そんな事を考えているうちに、いつの間にか馬車は見えなくなった。
「……ょし!」
私は両手で自分の頬を叩くと、挫けそうになった心に気合を入れた。
私は私のやるべき事をこの王都 でやろう。改めてそう決意した。
――笑顔で"みんな"の元へ帰る為に
見上げた空には、登り始めた太陽が輝いていた。
つづく。
目が覚めた私は、カーテンの隙間から差し始めた朝日を呆然と眺めながらそんな事を考えていた。
思い出したのは……10年程前の村での記憶。
娘達がまだ小さかった頃に、夜に勉強小屋に子ども達を集めて怪談話をした事があった。
すっかり怯えてしまった泣き虫娘の一人が、夜道を歩いて家に帰る事も出来なくなり……結局、私の診療所に泊まることになった。
最初は別々で寝ていたのに、いつの間にか私の寝床に潜り込んで来ていた。仕方なく、私達は手を繋いで一緒に眠った。
朝になり隣に身を縮めながら眠っている娘の寝顔を見た時、とても不思議で……幸せな気持ちになった。子どものいない私にも、母性というものがある事を知った出来事だった。
「……」
もちろん、あの時とは全く違った状況。全く違った感情。それでもどこか似たような幸福感を抱きながら、私は寝付いた時よりも少しだけ広くなっていた寝床を抜け出した。
「やあ。丁度珈琲を淹れてたんですよ」
私の顔を見るなり、いつもと変わらない調子で男が言った。
「飲みます?」
「……他に言うことは無いのか?」
「ああ、もちろん砂糖はつけますよ」
「変わらないんだな、お前は」
「たった一晩ですからね」
そう言うと、男は慣れた手付きで私の分も珈琲を淹れ始めた。
「……」
その横顔を私は黙って見ていた。
男が言うように、見た目からは何も変わった印象は受けなかった。
15年振りに再会し、男はその日のうちに「君は変わった」と私に言ってくれた。反対に、私は男に「お前は変わらない」と言った。けれど、本当は違っていた。
言い合いになった時にムッとした顔で反論してくる姿こそ、あの頃から変わってはいなかった。けれど、
再会した直後に"それ"に気づいた男と、2日もかかってしまった私。思えば、それだけ男が昔から私の事を見てくれていた証であり、私が男の事を見ていなかった証拠でもあった。
「医学院で初めて会った日からずっと、君の事が好きでした」
男はそう言ってくれた。"無血"だった頃の私でさえ、好きだったと。けれど、その思いを伝えてくれたのは、15年経ってからだった。
きっと、あの頃の私の目に自分が映っていない事を男はわかっていたからだろう。もしもあの頃に告白されていたとしても、私は間違いなく首を縦には振らなかった。
「くだらない話をするな。馬鹿にしているのか?」そう言い放っていただろう自分が目に浮かんだ。もしもこの男が本当に15年私を想い、待っていてくれたのだとしたら……
私と初めて共にした一夜は、特別な時間じゃなかったのか?
そう思っている私が居る反面、あまりにもいつもと変わらない様子を見せつけられると、自分だけが考え過ぎているかも知れないと思ってしまう私も居た。いくら言葉を並べられても、私はこの男の15年を知らないからだ。
そう考えると悔しい気持ちにもなった。もちろん、そんな事を男の前で言うつもりはなかったし、聞くつもりもなかった。
「どうぞ」
「……あ、ああ」
そんな風な疑問や不満を考えているうちに、いつの間にか珈琲は淹れられていた。私は男から湯気が立つ珈琲を受け取ると一口すすった。
「ッ?!」
その直後、声にならない声と共に肩をすくめた。
「どうかしまいましたか?」
私の様子に、男が隣で首を傾げた。
「……いや、何でもない。少し熱かっただけだ」
「淹れたてですから。気をつけてください」
「……ああ」
本当は、そうじゃない。
男が淹れてくれた珈琲には、砂糖が入っていなかった。口の中に広がった強い苦味に、私は顔をしかめたのだった。
珈琲に砂糖が入っていなかっただけ。
些細な事かもしれないが、私にはそれが意外だった。
「珈琲は寝起きではなく朝食後に飲むのが望ましいらしいんです。本来なら直さなければならないのでしょうが……僕の場合は習慣になってしまっているので。朝一でコレを飲まないと、なかなか、目が覚めないんです」
しかもその事に、男は全く気付いていなかった。
これまで男が珈琲を淹れてくれたことは何度もあったが、苦いものが苦手な私の珈琲に砂糖を入れ忘れる事など一度もなかった。
「朝日を浴びる事も、目を覚ますにはいいらしいですよ。異国の医学書で読んだ事があります。興味があれば探して読んでみてください。昨日も言いましたけど、医学書だけはちゃんと棚に戻しておいて下さいね」
「……」
そう言えば、いつもより饒舌なような気がした。平常心を装ってはいるが、この男も少なからず"普段とは違った
そう思うと、何だか安心出来た。
「ふっ」
「どうしたんです?」
私が笑うと、男は不思議そうに珈琲をすすった。
「いや、なんでもない。"そういう事"にしておくよ、首席殿」
「……何か、隠してますね」
男が不満げな顔をしながら私の尻に伸ばしてきたその手を、私は遠慮なくつねりあげた。
まだ朝が早いという事もあり、馬車の乗り合い所には馬と御者以外には私達しかいなかった。
「道中は道が悪い。くれぐれも気をつけて行くのだぞ。途中、風が強く吹く谷を通る。マントは持ったか?それから、路銀は多目に持っていた方がいい。野盗に出くわさないとも限らないからな」
「まるで心配性の母親のような物の言い方ですね」
私が言うと、男はパンパンに膨らんだ鞄を叩きながら笑った。その中身のほとんどが私が無理やり持たせたものだった。
「心配でしかない。お前はあの村までの道のりをわかっていない」
これから王都を発ち、男があの村へ到着するのは2日後。しかもそれは旅路が"順調に"進んだ場合だった。
「大丈夫ですよ。
「
言いかけて、私は言葉を切った。昨日の出来事を思い出したからだ。
「すまないが、これを私の娘達に渡してくれ」
私は自分の鞄から、二本の櫛を取り出し、男に差し出した。
「お土産、ですか?」
それは昨日、街で買い物をした時に買っていた物だった。"月"と"太陽"がそれぞれに彫り込まれた櫛。露店で見た瞬間に即決して買ったものだった。
「そんなところだ。他の子ども達の分はないからな、こっそり渡してやってくれ。太陽の模様は髪の短い元気な方。月の模様は髪の長い大人しい方だ」
「ええと、パルティマとシュシーマ、でしたっけ?」
「
パシーマ
とシュルティナ
だ。それから、この手紙も一緒に渡してくれ」「ああそうか、太陽と月。イーナ語でしたね。わかりました。ちゃんと渡しておきますよ」
男は髪飾りと手紙を受けとると、鞄ではなく懐にしまった。
「他に、何か心配事はありますか?」
「全てが心配だ。村に着いたら必ず手紙を送ってくれ」
それでも、その手紙が私の手元に届くのはずいぶん先になってしまうのだが……。
「お前は、心配ではないのか?」
「その話は一昨日に済んでます。強いて言うのであれば――」
そう言うと、男は私の手を取った。
「君と離れる事が心配です」
たった1日で私への態度が別人のように変わったこの男に、私は改めて朝の想いを取り消した。
「私は王都に居るんだぞ?何を心配する事がある?」
「……まぁ、いろいろと」
男が気まずそうに言い渋る様子から、私の勘がその理由を察した。
「なるほど。三席殿の事か」
「……」
男は黙っていたが、実に分かりやすい反応だった。
「確かに、奴は私を妻に
「それは心配していません」
ところが、男はバッサリ言い切った。
「君の拳が、そんなに弱いとは思っていません」
「おい、暴力は無意味だと言ったのはお前だぞ?」
「自分の身を守るための抵抗は暴力ではありません。もしもの時は、存分に暴れて下さい」
「ものは言いよう、か。ズルい答えだ。人を暴れん坊のように言うな」
私は握られた手を振り払った。
「ならば何が心配だと言うんだ?」
「もしも君の縁談が本当にお父上に仕組まれていたものだとして、君が縁談を受ける事でお父上が壁の建設中止に口を出すという条件を出したとしたら。そう考えると不安ではあります」
私は男が言わんとしている事がわかった。
「私が、娘たちの為に自分の身を犠牲にするのではないか、ということか」
「……」
私がそう推測すると、男は黙って頷いた。
「"私達"をみくびるな」
私は男を睨んだ。
「もしも私が望まぬ結婚と引き換えに壁の撤回を勝ち取ったとしても、あの娘達が喜ばない事は十分わかっている」
自分を過大評価するわけではなく、私が娘達を大切に思っているのと同じだけ、娘達も私を大切に思ってくれている。私にはそれがわかっていたし、そう思われている自信があった。それは自惚れではなく、信頼だと思う。
「私は自分の力で壁の建設を止め、自分の足であの村に帰る。それ以外の選択肢はない」
「そう、ですね。すみません」
そう言うと、男は頭を下げた。
「どうやら僕は君を……いや、"君達"の繋がりを甘く見ていたようです」
「全くだ。15年だぞ?たった一晩で越えられると思ったのか?」
「……正直、自信はありません。君が僕とあの村を天秤にかけた時、君に選んでもらう自信が僕にはありません」
「……冗談だ。馬鹿正直に捉えるな」
明らかに寂しそうな顔をした男の頭に手を伸ばし、何度か撫でてやった。
変わったのはこの男だけじゃない。自分から自然に"そう"出来るようになっていた私もまた、たった一晩で随分変わったようだった。
無血から人間に変わるのには何年もかかったのに、学友から恋仲へ変わるのにはたった一晩しかかからなかった。つくづく、人の気持ちほど不完全で不安定なものはないと実感した。
「私にとってあの村も娘達も特別だ。だが、お前も……まぁ特別だ。そもそも向けている感情が違うんだ。優劣なんてつける必要はないだろう」
「そう言ってもらえると、有難いですね」
私達はどちらからともなく身を寄せると、互いを抱きしめた。
私にとってはやはり抱擁は分岐点。今回は、この男との別れの決断の場だった。
「村の若い娘達に手を出すんじゃないぞ」
「わかっています。君に殴られるのも、殴らせるのも嫌ですからね」
「ふふ、その時は、"右手"を使ってやるさ」
「……それは責任重大ですね」
「そこの熱いお二人さん、そろそろ出発するぜ」
御者にからかうように言われ、私達は慌てて身を離した。
いつの間にか、馬車には何人かの客が乗り込み、出発の時を待っているようだった。
「では、行ってきます」
「ああ」
私は男が差し出した手をもう一度握り返した。
「くれぐれも、無茶をしないで下さいね」
「わかっている。お前もな」
握った手を離さなければならないのに、私には自分からそうする事が出来なかった。
つい数日前に別れた娘達と過ごした時間の方が圧倒的に長いにも関わらず、たった2日しか一緒にいなかったこの男との別れが、その時以上に辛いと思っている私がいた。
――この手を、離したくない。一人になりたくない
そう思ってしまう自分の心を無理やり律し、私は手を離した。
誰かと別れるという事が、こんなに辛いとは思わなかった。
「……」
男は、いつものように少し困ったような笑みを最後に浮かべると、何も言わずに馬車の荷台に乗り込んだ。
私も少しづつ遠くなっていくその姿を黙って見送った。
村の人達から見送られた私にとって、誰かを見送るというの事が初めての経験だった。
私があの村を発つ時の娘達も、こんな気持ちだったのだろうか?
そんな事を考えているうちに、いつの間にか馬車は見えなくなった。
「……ょし!」
私は両手で自分の頬を叩くと、挫けそうになった心に気合を入れた。
私は私のやるべき事をこの
――笑顔で"みんな"の元へ帰る為に
見上げた空には、登り始めた太陽が輝いていた。
つづく。