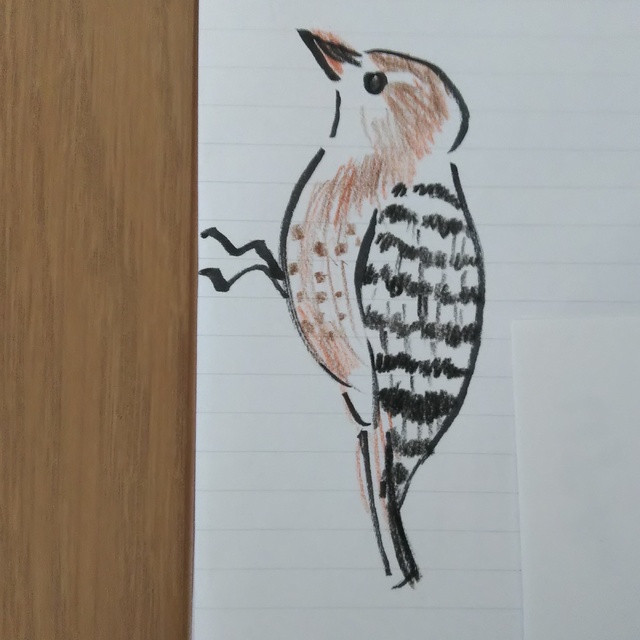王都にてDAY.01『無血』
文字数 4,936文字
「やあ。丁度先日、珍しい珈琲が手に入ったんですよ」
キシむ音をたてながらドアが開くと、"あの頃"とほとんど変わっていない眼鏡の男が顔を出した。
「飲みます?」
「……」
久し振りの再会。にも関わらず男はまるで昨日も会っていた人間を相手にするように私に言った。
「他に言うことは無いのか?」
「ああ、もちろん砂糖はつけますよ」
「……変わらないな、お前」
「たった15年ですからね」
「……もういい。少し休ませてもらうぞ」
私は男の許可を待つ事無く、部屋に入った。
「本の虫も相変わらずのようだな。むしろ悪化しているようだ」
部屋中に、昔以上に大量に積み上げられた本の山を見上げながら私が言うと、男は「食べる場所と寝る場所はあるのでご心配無く」と、やはりあの頃と同じ様な事を言った。
「本はあらゆる知識の宝庫です。特に異国の本は味わい深い。文化の違いというものが、ここまで価値観を変えるものかと毎回感心させられーー」
「その話は聞き飽きている。それより、味わい深い珈琲を煎れてくれるんじゃなかったのか?」
「ああ、そうでしたね。苦いのが苦手な君には、味わい深いかは分かりませんが」
「余計なお世話だ」
私は本の山をどかして椅子を発掘した。
ようやく腰を落ち着ける事が出来た事に、思わず息が漏れた。見上げた天井は……あの頃のままだった。
訳あって私は、15年前この男と一緒にこの部屋に住んでいた時期があった。お互いに若かったが、恋仲になることはなかった。あの頃の私達は……いや"私"は、自分しか見えていなかったから。
「まさか、まだここに住んでいるとはな」
「これだけの本を動かすのは、流石に手間も暇もかかりますからね。そんなことに時間を裂く位なら、僕が動かない方がいいじゃないですか」
「お前らしい理由だな。そんな考え方じゃあ、いつまで経っても家庭は持てないぞ」
「ご心配無く。僕の人生は探求心を満たす事に捧げているので」
「……心配はしていない。呆れているだけだ」
これも、あの頃と同じやり取りだった。
「懐かしいですか?」
くすんだ窓から、王都 の様子を眺めていた私に、男が珈琲が淹れられたカップを差し出した。
「……どうかな」
父の命令で、王都から追い出されるように医者として"あの村"に派遣されて15年。久し振りの故郷の景色にも関わらず、懐かしいという感情はあまり湧かなかった。この部屋に入った時になって、ようやくそんな感情を抱けていたが……もちろん、男には黙っていた。
「前よりも一層、壁が増えたようだ」
「建物の事、ですか」
「"どっちも"だ」
私が村に居る間、王都の情報 を知る術は、手紙だけだった。手紙と言っても、王都から随分離れたあの村に行商人が来るのは月に一度だけ。私の手元に届いた頃には、ひと月も前の出来事になっている事がざらだった。
「"壁"の件は、どうなっている?」
「現王の考えまではわかりませんが、側近達は壁の建設に前向きのようです。最近は行商人達が"足代"として法外な値段を吹っ掛けてくるとぼやいてました」
「……壁と関税を設ける一番の理由は、それか」
「恐らく。向こうが足代を上乗せしてくるなら、こちらは"通行料"で元を取ろうという魂胆なのでしょう」
「……まるで子どもの喧嘩だな」
村に残してきた子ども達の無邪気な顔が浮かんだ私は、思わず笑みを浮かべた。
「あの村で、何があったんですか?」
「どういう意味だ?」
「雰囲気が、随分変わったようです」
「そうか?」
「ええ。昔の君は、そんな風に微笑む事なんてありませんでしたから」
「……そう、か」
確かに、15年前の私は相当な無愛想かつ、負けず嫌いかつ、頑固者だった気がする。
それこそ、当時女は誰も居なかった王都の医学院に入学した位に。
「あの頃の君は、"病気"と"男"に対して剥き出しの敵意を隠す事もしませんでしたし、何よりも"合理的"である事に強いこだわりがあった。いかに合理的に治療を施すか、いかに合理的に診るか。患者やその家族の感情は二の次」
「……」
自分の過去を無いものには出来ない事はわかっていた。それでも……やはり聞いていて気持ちの良いものではなかった。
「当時の君の考え方なら、壁を造って人を管理する事は、むしろ歓迎すると思うのですが?」
「お前は、どう思う?」
「質問に質問で返さないで下さい。聞いているのは僕です」
「その前に聞いたのは私だ」
あの頃のように私が言い返すと、男もまた少しムッとしたような顔をした。その態度に、毎晩のように議論を交わしていた昔 を思い出した。
「……まぁ、医者としては賛成出来る部分はありますね。人の流れを制限することで疫病の蔓延を食い止める事に繋がるでしょうし、区画すれば患者の人数も把握しやすくなるでしょう。まさに、昔の君が思い描いていたーー」
「だから私の事はいいと言っている。お前の考えを聞いているんだ」
「言ったじゃないですか。医者としては賛成出来る部分はあるって」
「では、"何"としては反対なのだ?」
「"人"として、でしょうね」
男はこれまでにない真剣な眼差しと口調を私に向けた。まるで……私が"そこ"を一番知りたいと分かっていたように。
「柵で囲って動きを制限すれば、確かに管理は楽でしょう。ですが、我々は家畜じゃありません。自由を奪われた人間は、本当の意味で生きている事になるのでしょうか?僕には甚だ疑問です。それにーー」
男は珈琲を飲み干すとーー
「高い関税を嫌って行商が滞ったら、異国の本や珈琲が手に入らなくなります。それだけは絶対に避けたいですしね」
そう言って笑ってみせた。
「……結局は私欲の為、か」
「欲があってこその人間です。いけませんか?」
「……いや」
そう言われて頭に浮かんだのは、二人の少女の顔だった。
「私欲の為と言うのなら、私も一緒だからな」
決して大袈裟ではなく私は、その二人の少女を悲しませたくないが為に、国に喧嘩を売りに来たのだから。
「……王都 に戻る為に、あの村を出たのが2日前の朝。徒歩で馬宿に着いたのが昼過ぎ。そこから引馬で半日かけて隣町へ。更に隣町から馬宿を2ヵ所通って丸1日。そして、ようやく王都 に着いた。"2日間"と言葉にするのは簡単だが、決して楽な道のりではない。そんな長旅をしてきた私に、お前は開口一番何と言った?珍しい珈琲が手に入っただと?」
「……お気に召しませんでしたか」
私が睨むと、男はわざとらしく眼鏡を外して、服の裾でレンズを拭いた。気まずい時のその癖も、変わっていなかった。
「それが、王都 に住む人間の姿だ。便利な暮らしに胡座 をかき、外の世界に目を向けようとしない」
それは、私自信が身をもってわかったことでもあった。
「全ての行商人が馬を持っているわけではない。昼夜休まず歩いて来る者もいるだろうし、道中、獣や野盗に襲われないとも限らない」
この話は、今日乗ってきた馬車の御者に聞いた話だった。
「行商 の者が、王都 に来る為にどれだけの労力を使い、危険を犯しているのか王都の者は知ろうともしない。法外とする足代も、彼らにとっては当然の報酬だ。それに気付いていないから、壁を作って高額な税を取るなんて考えに至るのだ」
「では、どうしろと?」
「行商 の者をむしろ歓迎してやればいい。そうだな……品物を一律3割増で買い取るか、王都での食費と宿泊費を国が半分負担してやればいい」
「そんな事をしたら、益々負担が増えるだけじゃないですか」
「最初はそれで構わない。商人が増え、安定した流通の基盤が出来れば、それを辿るように人の流れも増えていく。人が流れるようになれば、物が流れ、物が流れれば、金が流れる。利益は後から必ずついてくる」
「しかし、そのやり方では一時的にこちらの負担が跳ね上がるのも事実です。どうやってそれを補うのですか?」
「それには……私に考えがある」
それが今回の私の切り札と言ってもいい。私は父と国を説得する為に、私が持っている手札 を切るつもりだった。
「大切なのは壁を築く事ではなく、流れを作る事だ。その後は流れを太く確かなものにする為に街道 を整備する事で、更に人も物も金も流れるだろう」
「言ってることはわかりますが、全て君の推測です。机上論の域を出ませんね」
男はどこか呆れたように言った。
「机上ではない。私は自分の目で見て、耳で聞いて、足で歩いて考えたのだ。どの町でも壁の建築に賛成する者などいなかった。強行すれば反乱も起きかねない。無益な血が流れる暴挙を、医者である私がを見て見ぬふりをしろというのか?」
その言い方にカチンときた私は、もう一度男を睨みつけた。
「人は血だ。王都と町と村を繋ぐ道は血管だ。血管が廃れ血の流れが滞り完全に止まったら、その先は腐れ落ちる。国も同じだ」
「……」
男もまた、私から目を逸らさなかった。
「目を向けるべきなのは、目先の利益不利益じゃない。もっと遠く、広い視野で見なければならない。この国の未来を、本気で考えるのならばな」
壁のないあの村で、見渡す限り広がる田畑の中で、私はそれを学んだ。種を撒くのは未来の為だと、彼等は笑って汗を流していた。
「……そういう君は、本気でお父上に意見する気なんですか?」
「もちろんだ。その為に私は戻ってきたのだからな」
私が言い切ると、男は小さなため息をついた。
「……本当に変わりましたね」
「そうか?」
「随分、人間らしくなりました」
「ふふ。お前から見ても、昔の私は相当だったようだな」
周りから、切っても血が流れない"無血の女"と称されていただけある。
「では、今度は私がお前の質問に答えよう。あの村で、私の身に何が起こったのか……過去に無血と呼ばれた私が、血の通った人間になった理由を知りたいのだったな」
「……ええ。非常に興味がありますね」
「ただ、この話は長くなる。夜にでも話そう」
「夜?また部屋 に来るんですか?」
「何を言っている。私が王都に滞在する間、この部屋を使わせてもらうぞ」
「えぇ?!実家 には戻らないんですか?」
男は、初めて戸惑いの声をあげた。
「長旅で疲れているんだ。あんな堅苦しい所で寛げるものか。食べる場所と寝る場所はあるんだろう?」
「そうですが……食事はどうするんですか?」
「私が作ろう」
「作れるんですか?!」
「15年単身者だったのだぞ。侮るな」
とは言うものの、男が驚くのも無理はない。15年前の私は、いわゆる"家事"と呼ばれるものは一切出来なかったのだから。
「それに、お前には"私の代わり"を頼んでいるんだ。しっかり引き継いでおきたいからな」
そう。私の代わりにあの村に常駐する医者として私が選んだのが、この男だった。
周りから敬遠されていた私の唯一の理解者(?)であり、友人(?)であり、手紙を通じて繋がっていた人間。
そして何より、今のこの男の考えが今の私と違わない事が、代わりを頼んだ一番の理由だった。
「お前が不在の間の部屋の使い方を教えてもらうぞ。私も今夜一晩で、お前にあの村での暮らし方を叩き込んでおこう」
「……僕の読書 時間はどうなるんですか」
「本からでは学べない事も世の中には山程ある。光栄に思うんだな。この私を一夜、独り占め出来るのだから」
私が微笑むと、男は心なしか顔を赤くして、先程拭いたばかりの眼鏡をもう一度拭きだした。
夜。
湯浴みを終えた私は、くすんだ窓を開けて夜空を眺めていた。いや……夜空に輝く月を眺めながら、二人 の顔を思い出していた。
「寂しくなったら空を見るといい」
偉そうに、そう言い残してきたくせに……離れてたった2日でこの様 だ。先に寂しくなったのは、私の方だった。
「月も、村とは変わって見えますか?」
いつの間に部屋に戻ってきたのか、男が濡れた髪を拭きながら言った。
「……そうだな」
きっと娘達も、同じ月を見上げている。そう思うと、余計に寂しさが増した。
「きっと、私が変わったからだろうな。人が恋しいなんて……これまで、思う事はなかったからな」
私は指で目を擦ると、眼鏡を外した男を見た。その顔は、どこか寂しそうだった。
「心配するな。男じゃない」
「……僕は何も言ってません」
私が笑うと、男は顔を背けた。
「さて、どこから話そうか」
私は、もう一度月を見上げながら、15年前に思いを馳せた。目を閉じると、村に吹く夜風の匂いがした。
つづく。
キシむ音をたてながらドアが開くと、"あの頃"とほとんど変わっていない眼鏡の男が顔を出した。
「飲みます?」
「……」
久し振りの再会。にも関わらず男はまるで昨日も会っていた人間を相手にするように私に言った。
「他に言うことは無いのか?」
「ああ、もちろん砂糖はつけますよ」
「……変わらないな、お前」
「たった15年ですからね」
「……もういい。少し休ませてもらうぞ」
私は男の許可を待つ事無く、部屋に入った。
「本の虫も相変わらずのようだな。むしろ悪化しているようだ」
部屋中に、昔以上に大量に積み上げられた本の山を見上げながら私が言うと、男は「食べる場所と寝る場所はあるのでご心配無く」と、やはりあの頃と同じ様な事を言った。
「本はあらゆる知識の宝庫です。特に異国の本は味わい深い。文化の違いというものが、ここまで価値観を変えるものかと毎回感心させられーー」
「その話は聞き飽きている。それより、味わい深い珈琲を煎れてくれるんじゃなかったのか?」
「ああ、そうでしたね。苦いのが苦手な君には、味わい深いかは分かりませんが」
「余計なお世話だ」
私は本の山をどかして椅子を発掘した。
ようやく腰を落ち着ける事が出来た事に、思わず息が漏れた。見上げた天井は……あの頃のままだった。
訳あって私は、15年前この男と一緒にこの部屋に住んでいた時期があった。お互いに若かったが、恋仲になることはなかった。あの頃の私達は……いや"私"は、自分しか見えていなかったから。
「まさか、まだここに住んでいるとはな」
「これだけの本を動かすのは、流石に手間も暇もかかりますからね。そんなことに時間を裂く位なら、僕が動かない方がいいじゃないですか」
「お前らしい理由だな。そんな考え方じゃあ、いつまで経っても家庭は持てないぞ」
「ご心配無く。僕の人生は探求心を満たす事に捧げているので」
「……心配はしていない。呆れているだけだ」
これも、あの頃と同じやり取りだった。
「懐かしいですか?」
くすんだ窓から、
「……どうかな」
父の命令で、王都から追い出されるように医者として"あの村"に派遣されて15年。久し振りの故郷の景色にも関わらず、懐かしいという感情はあまり湧かなかった。この部屋に入った時になって、ようやくそんな感情を抱けていたが……もちろん、男には黙っていた。
「前よりも一層、壁が増えたようだ」
「建物の事、ですか」
「"どっちも"だ」
私が村に居る間、王都の
「"壁"の件は、どうなっている?」
「現王の考えまではわかりませんが、側近達は壁の建設に前向きのようです。最近は行商人達が"足代"として法外な値段を吹っ掛けてくるとぼやいてました」
「……壁と関税を設ける一番の理由は、それか」
「恐らく。向こうが足代を上乗せしてくるなら、こちらは"通行料"で元を取ろうという魂胆なのでしょう」
「……まるで子どもの喧嘩だな」
村に残してきた子ども達の無邪気な顔が浮かんだ私は、思わず笑みを浮かべた。
「あの村で、何があったんですか?」
「どういう意味だ?」
「雰囲気が、随分変わったようです」
「そうか?」
「ええ。昔の君は、そんな風に微笑む事なんてありませんでしたから」
「……そう、か」
確かに、15年前の私は相当な無愛想かつ、負けず嫌いかつ、頑固者だった気がする。
それこそ、当時女は誰も居なかった王都の医学院に入学した位に。
「あの頃の君は、"病気"と"男"に対して剥き出しの敵意を隠す事もしませんでしたし、何よりも"合理的"である事に強いこだわりがあった。いかに合理的に治療を施すか、いかに合理的に診るか。患者やその家族の感情は二の次」
「……」
自分の過去を無いものには出来ない事はわかっていた。それでも……やはり聞いていて気持ちの良いものではなかった。
「当時の君の考え方なら、壁を造って人を管理する事は、むしろ歓迎すると思うのですが?」
「お前は、どう思う?」
「質問に質問で返さないで下さい。聞いているのは僕です」
「その前に聞いたのは私だ」
あの頃のように私が言い返すと、男もまた少しムッとしたような顔をした。その態度に、毎晩のように議論を交わしていた
「……まぁ、医者としては賛成出来る部分はありますね。人の流れを制限することで疫病の蔓延を食い止める事に繋がるでしょうし、区画すれば患者の人数も把握しやすくなるでしょう。まさに、昔の君が思い描いていたーー」
「だから私の事はいいと言っている。お前の考えを聞いているんだ」
「言ったじゃないですか。医者としては賛成出来る部分はあるって」
「では、"何"としては反対なのだ?」
「"人"として、でしょうね」
男はこれまでにない真剣な眼差しと口調を私に向けた。まるで……私が"そこ"を一番知りたいと分かっていたように。
「柵で囲って動きを制限すれば、確かに管理は楽でしょう。ですが、我々は家畜じゃありません。自由を奪われた人間は、本当の意味で生きている事になるのでしょうか?僕には甚だ疑問です。それにーー」
男は珈琲を飲み干すとーー
「高い関税を嫌って行商が滞ったら、異国の本や珈琲が手に入らなくなります。それだけは絶対に避けたいですしね」
そう言って笑ってみせた。
「……結局は私欲の為、か」
「欲があってこその人間です。いけませんか?」
「……いや」
そう言われて頭に浮かんだのは、二人の少女の顔だった。
「私欲の為と言うのなら、私も一緒だからな」
決して大袈裟ではなく私は、その二人の少女を悲しませたくないが為に、国に喧嘩を売りに来たのだから。
「……
「……お気に召しませんでしたか」
私が睨むと、男はわざとらしく眼鏡を外して、服の裾でレンズを拭いた。気まずい時のその癖も、変わっていなかった。
「それが、
それは、私自信が身をもってわかったことでもあった。
「全ての行商人が馬を持っているわけではない。昼夜休まず歩いて来る者もいるだろうし、道中、獣や野盗に襲われないとも限らない」
この話は、今日乗ってきた馬車の御者に聞いた話だった。
「
「では、どうしろと?」
「
「そんな事をしたら、益々負担が増えるだけじゃないですか」
「最初はそれで構わない。商人が増え、安定した流通の基盤が出来れば、それを辿るように人の流れも増えていく。人が流れるようになれば、物が流れ、物が流れれば、金が流れる。利益は後から必ずついてくる」
「しかし、そのやり方では一時的にこちらの負担が跳ね上がるのも事実です。どうやってそれを補うのですか?」
「それには……私に考えがある」
それが今回の私の切り札と言ってもいい。私は父と国を説得する為に、私が持っている
「大切なのは壁を築く事ではなく、流れを作る事だ。その後は流れを太く確かなものにする為に
「言ってることはわかりますが、全て君の推測です。机上論の域を出ませんね」
男はどこか呆れたように言った。
「机上ではない。私は自分の目で見て、耳で聞いて、足で歩いて考えたのだ。どの町でも壁の建築に賛成する者などいなかった。強行すれば反乱も起きかねない。無益な血が流れる暴挙を、医者である私がを見て見ぬふりをしろというのか?」
その言い方にカチンときた私は、もう一度男を睨みつけた。
「人は血だ。王都と町と村を繋ぐ道は血管だ。血管が廃れ血の流れが滞り完全に止まったら、その先は腐れ落ちる。国も同じだ」
「……」
男もまた、私から目を逸らさなかった。
「目を向けるべきなのは、目先の利益不利益じゃない。もっと遠く、広い視野で見なければならない。この国の未来を、本気で考えるのならばな」
壁のないあの村で、見渡す限り広がる田畑の中で、私はそれを学んだ。種を撒くのは未来の為だと、彼等は笑って汗を流していた。
「……そういう君は、本気でお父上に意見する気なんですか?」
「もちろんだ。その為に私は戻ってきたのだからな」
私が言い切ると、男は小さなため息をついた。
「……本当に変わりましたね」
「そうか?」
「随分、人間らしくなりました」
「ふふ。お前から見ても、昔の私は相当だったようだな」
周りから、切っても血が流れない"無血の女"と称されていただけある。
「では、今度は私がお前の質問に答えよう。あの村で、私の身に何が起こったのか……過去に無血と呼ばれた私が、血の通った人間になった理由を知りたいのだったな」
「……ええ。非常に興味がありますね」
「ただ、この話は長くなる。夜にでも話そう」
「夜?また
「何を言っている。私が王都に滞在する間、この部屋を使わせてもらうぞ」
「えぇ?!
男は、初めて戸惑いの声をあげた。
「長旅で疲れているんだ。あんな堅苦しい所で寛げるものか。食べる場所と寝る場所はあるんだろう?」
「そうですが……食事はどうするんですか?」
「私が作ろう」
「作れるんですか?!」
「15年単身者だったのだぞ。侮るな」
とは言うものの、男が驚くのも無理はない。15年前の私は、いわゆる"家事"と呼ばれるものは一切出来なかったのだから。
「それに、お前には"私の代わり"を頼んでいるんだ。しっかり引き継いでおきたいからな」
そう。私の代わりにあの村に常駐する医者として私が選んだのが、この男だった。
周りから敬遠されていた私の唯一の理解者(?)であり、友人(?)であり、手紙を通じて繋がっていた人間。
そして何より、今のこの男の考えが今の私と違わない事が、代わりを頼んだ一番の理由だった。
「お前が不在の間の部屋の使い方を教えてもらうぞ。私も今夜一晩で、お前にあの村での暮らし方を叩き込んでおこう」
「……僕の
「本からでは学べない事も世の中には山程ある。光栄に思うんだな。この私を一夜、独り占め出来るのだから」
私が微笑むと、男は心なしか顔を赤くして、先程拭いたばかりの眼鏡をもう一度拭きだした。
夜。
湯浴みを終えた私は、くすんだ窓を開けて夜空を眺めていた。いや……夜空に輝く月を眺めながら、
「寂しくなったら空を見るといい」
偉そうに、そう言い残してきたくせに……離れてたった2日でこの
「月も、村とは変わって見えますか?」
いつの間に部屋に戻ってきたのか、男が濡れた髪を拭きながら言った。
「……そうだな」
きっと娘達も、同じ月を見上げている。そう思うと、余計に寂しさが増した。
「きっと、私が変わったからだろうな。人が恋しいなんて……これまで、思う事はなかったからな」
私は指で目を擦ると、眼鏡を外した男を見た。その顔は、どこか寂しそうだった。
「心配するな。男じゃない」
「……僕は何も言ってません」
私が笑うと、男は顔を背けた。
「さて、どこから話そうか」
私は、もう一度月を見上げながら、15年前に思いを馳せた。目を閉じると、村に吹く夜風の匂いがした。
つづく。