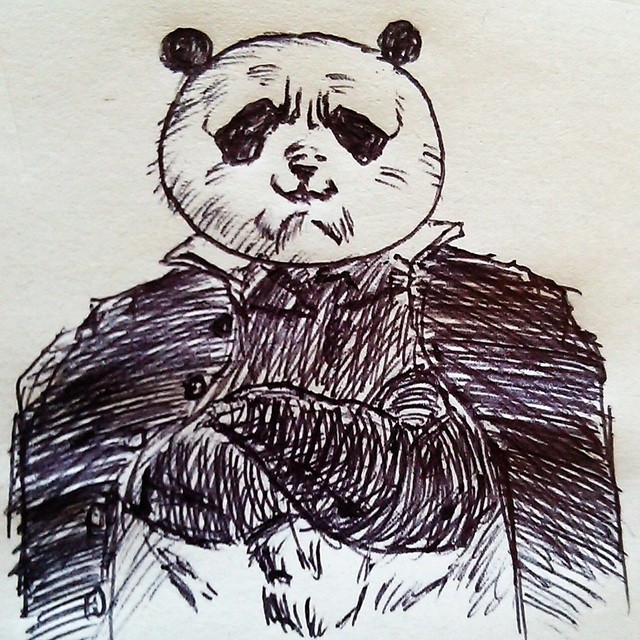白と黒
文字数 7,435文字
階下から漂うドミグラスソースの香りに誘われ、僕は部屋を出てリビングへと降りてゆく。
対面式のキッチンでは思った通り母が煮込みハンバーグを作っていた。
父の大好物であるこの料理が作られる時は大抵、母が父にお願いごとをしたいとき。
今回はなんだろうな――あれ?
自分の目がおかしくなったのだろうか。
空中にいくつか線のようなものが見えるのだけれど。
視界を斜めに走る半透明の線のようなもの――目、傷ついてんのかな。まいったな。
今日は土曜だし、もうこんな時間だし、どこの病院でも診察時間終わっているよね。
とりあえずスマホで症状について何か出てこないか検索していると、父がリビングに現れた。
それと同時に、視界になんとなく見えていたあの線の数が一気に増える。今度はさっきの斜めとは直角に交わる斜め――格子模様?
ナナメに傾けたテニスラケットを顔の前に置かれた感じ。
「お、今夜は俺の大好物か」
僕の視界が大変なことになっているというのに、父は鼻をひくつかせながらリビングに充満する肉とソースの香りとを楽しんでいる。
のんきなもんだよ――あれ?
おかしいな。
視界の左下端、今度は小さな黒い影みたいなもので霞んでいる。
マジか――どんよりと嫌な気分。
これ目の病気か怪我か、どちらにせよきっと良くないモノだよね?
目を閉じて、五つ数えて目を開ける。
視界には、父と母の満面の笑み。テニスラケットみたいなアレは相変わらず見えたまま。
「だって週末でしょ。今週も一週間お疲れさまっ」
なんだなんだ?
今度は右上端に小さな白い靄みたいなのが現れた。
さっきの影と大きさが似ている。
「いやいや、いつもママがうちのことをやってくれているからさ。いつも感謝しているよ」
父の言葉の後、白い靄からそう遠くない場所に黒い影が一つ増える。
「ありがとう。でも、あなたの忙しさに比べたら……」
母の言葉の後、白い靄も一つ増える。
「でね、だから今夜は特別に和牛なのよ」
白い靄。
「和牛? 高かったんじゃないのか?」
黒い影。
「それがね、安かったの! 特売でねっ!」
白い靄。
「あなたが頑張ってくれているから、普段から私、ちゃんとチラシをチェックしているのよ」
また白い靄。
どうやら、父の言葉の後は黒い影が視界に増え、母の言葉の後は白い靄が増えて――これってさ、二人の会話がまるで囲碁を打っているかのように見えているってこと?
「でね、話は変わって明日なんだけれど、どうしても行きたい場所があって、車を出してもらえたら嬉しいんだけれどなぁ……って」
白い靄。
本当に囲碁だったら母さんはちょっと打ちすぎだ。
打てる場所がなくてパスせざるを得ない時以外は連続で打てないってのに。
「明日? ……明日かぁ」
黒い影。
注意して見ると、黒と白の置かれている場所はさっきの半透明の線が交わった部分。
囲碁感は強いがルールがなぁ……。
「あら……もしかして何か使う予定でも? 予定があるなら仕方ないけれど、ねぇ?」
白い靄がまた連続で増える。
勝敗判定が囲碁なら、今のはかなり重要な場所に置いたし、ここから黒の挽回は相当厳しいだろうな――じゃなくて。
これはもしかして、目じゃなく脳の問題か?
今日の昼間、じいちゃんと囲碁をさんざん打っていたからなぁ。
「いや実は……取引先の部長さんにだね、釣りに誘われていてね……まあ、天気次第なんだけれどね」
黒い影。
父さん、食らい付く。
「明日? あなたなんでいつもそういう大事なこと、いつも突然言うの?」
白。
「ほら、天気次第だし……」
黒。
「お弁当とかの準備だってあるんだから。もっと前から言っておいてよ。いつも言ってるでしょ?」
白。白。
「いや、声かけられたのは昨日の夕方でね」
黒。
「昨日? その時点で連絡くれてもいいじゃない」
白。
「釣りってことは隣でその部長さんにお弁当見られちゃうわけでしょ? ありあわせで済ませるわけにはいかないんだからっ。いつもお弁当、どうやって作ってるか知ってますか? 栄養とか季節とか予算とか考えて、工夫して、毎日のご飯とも被らないようにしているし……目の前にあるお弁当にどれだけの手間と愛情が詰まっているか、あなたは考えた事なんてないんだわ……」
白。白。白。白。白。
父さんは目を泳がせながら沈黙している。
「もう、そういえばこないだもだったわよ?」
白。
母の勢いと物量に対し、父は完全に弱気な打ち筋。
大勢が決した。
『あいつの囲碁は粘りがない。なにかあるとすぐに逃げ出すんだ』
じいちゃんの言葉を思い出した。
じいちゃんは囲碁が滅茶苦茶強い。
若い頃、デキ婚のせいで固定給の仕事を始めなかったら今頃はプロ棋士になっていたかもしれない、とかいつも言っているくらい。
僕はそのじいちゃんに囲碁を教えてもらった。
じいちゃんが住んでいるのは隣の駅だけど、徒歩+電車よりは自転車の方が早いくらいのご近所。
だから小さい頃からしょっちゅう遊びに行っていた。
じいちゃんのとこは居心地がいい。
また家がいいんだ――って言うといつも「子供っぽくない感想だ」って笑われるけど。
でも本当に。
映画の撮影に使えそうな古い家。
壁や廊下に触れているだけで落ち着くというか。
本当は冬でも裸足で居たいくらい。
それから中庭。
家がロの字になっている内側に、小さな池と梅の木とがある。
皆でよく縁側に座って中庭を眺めてた。
僕、碁盤、じいちゃん、ばあちゃん、お茶菓子。
じいちゃんはあんまりこっちを見てないのに絶望的に強くて。
子ども相手に手を一切抜かないんだよね。
父が囲碁を辞めたのも、あの大人げない勝ち方のせいじゃないかなって思うくらい。
まあ、それでも僕は諦めずに打ち続けて、ようやくたまにはじいちゃんに勝てるくらいになったけどさ――手加減してもらっている疑惑がなくはないけど。
そんな、じいちゃんの家の居心地が変わってしまったのは去年のこと。
ばあちゃんが亡くなったから。
じいちゃんの落ち込みようったらなかった。
空気が抜けてるんじゃないかってくらい、毎日少しずつしぼんで小さくなってゆく。
それだけじゃない。あの家の居心地だってまるで変わってしまった。
ばあちゃん、古民家の精なんじゃないかって思ったほど。
とにかく何もかもが心配で、今は学校帰りに毎日通っている。
じいちゃんが、碁を打っている時だけはしゃんとすることに気付いたから。
僕が碁石を置いた途端、大人げないヤル気のあるじいちゃんが戻って来る。
「ちょ、ちょっと待って母さん」
あまりにも白の増えるペースが早すぎて、じいちゃんのこと考えているうちに、視界が真っ白になっていたから、思わず声を出して
しまった――けれど、何を待ってなのか自分でもよく分からない。
ただ僕の一言のあと、白い靄がいくつか黒い影へと変わった。
その場所は、思い返してみれば、最初の方に本来なら父が次打つかなって思ったときに母が連続して打った場所。
ここだけじゃない、ここも、ここも、母が連続で打ったけど本来ならば……と、意識を集中しただけで、白と黒の異常な差が直されてゆく。
ああ、これならズルなしの囲碁の勝負みたいな盤面だなと思えた時、母が叫んだ。
「ズルい! 二人がかりで説得なんて!」
二人がかり?
ちょっと待ってって言っただけだけど――そうやって思い返すと、盤面のズル白を正しい黒に直した時、僕の口から何か言葉が出ていたような気がする。
何て言ったかまでは思い出せないのだけど。
「ごめんごめん。本当にごめん」
父が母の手を握りしめている。
「ごめんよ。この埋め合わせは必ずするから。ね、ね」
なんか落ち着いてるというか、ちょっと子どもの目の前でイチャついているというか。
食事前だけど気分はご馳走さまです。見てらんない。
「ちょっとじいちゃんのとこ行って来る」
「え、ハンバーグは?」
「父さんの明日のお弁当のメインにでもしなよ」
僕がそう言った途端、白も黒も碁盤みたいな線も全部消えた。なんだったんだ。
まだ手を握り合っている両親を後目 に玄関へと走る。
「行ってきます!」
じいちゃんがあの家に一人きりになってから、僕がじいちゃんの家に行くことは、何においても優先していいことの一つになっている。
こうやって様子を見に行くとさえ言えば大抵の用事からは逃れられる免罪符として――こういうとこ、父に似たのかな。
いや、今はそんなこと言っている場合じゃなく――囲碁に似ているなって思ってからはずっとじいちゃんのことが頭の片隅にひっかかっていたんだ。
急いで自転車に飛び乗ると猛烈にペダルをこぐ。
既に陽が暮れた道、点々と連なる街灯が白い石に見える。
その白を次々と背後に飛ばしながら、じいちゃんの家まで走り続けた。
そしてたどり着いたじいちゃんの家。
自転車を止めようとして、家の前に大きな黒い車が停まっているの気づく。
門も半開き。
何か異様な気配を感じた僕はダッシュで玄関へと急ぐ。
玄関の戸の鍵も開いている。
「じいちゃん!」
大声でじいちゃんを呼びながら、ガラス戸をガラガラと開ける。
そして慌てて飛び込んだ玄関で黒い靴につまずきそうになる。
お客さん? こんな時間に?
急いで靴を脱ぎ、家の中へ駆け上がった。
「じいちゃん!」
とりあえず居間を覗いてみる――と、そこには渋い顔をしたじいちゃんと、スーツを着た大人たちが数人。
そして、また視界に例の碁盤模様が現れる。
対局は既に始まっていて、ぎょっとするほど黒が優勢――でもこれ、母の時と同じ。
明らかに黒が連続で打っているヤツだ。
「お邪魔しております」
一番先頭に座っている大人が僕に挨拶をして、すぐさまじいちゃんに向き直り目の前に並べた資料を指差しながら何か言っている。
ああ、こいつらが黒か。
とりあえず、今の黒はナシだろ。
あとはここも、ここも――じいちゃんの白をもとに、このへんは連続打ちされたんじゃないだろうか、と考え得る盤面のおかしなところを直しまくる。
僕の口から何か言葉が出ているみたいだけど、今は音のない世界に居るみたいに何も聞こえない。
直しているうちに、他の部分も勝手に白くなり始めた。
白と黒の数が同じくらいに直ると、そこはさすがじいちゃん。
しびれるような一手を打ち続け、対局はあっという間に白の圧勝に終わった。
「もう、二度と来るな」
じいちゃんの一言が聞こえるようになったとき、視界から碁盤は消え、他の声も音も戻ってきた。
スーツの大人たちは一礼をするとスゴスゴと帰ってゆく。
そいつらが玄関を出た後、じいちゃんはどこから取り出したのか塩をまく。
「もう、二度と来るな!」
じいちゃん、二回言った。
よっぽど腹を立てているのか。
そして車が去ってゆく音を確認したあと、僕に向かって小さな声でこう言った。
「助かった。ありがとな」
玄関にしっかりと立っているじいちゃんは、囲碁を打っている時のカッコイイじいちゃんだった。
「まあね」
「飯食ったか?」
「あ、まだだ」
「出前取るから、食べていけ」
じいちゃんはあの大人たちのことを何も言わなかったけれど、あいつらが置いていった紙をじいちゃんがくしゃくしゃに丸めてゴミ箱に投げ捨て――たのをこっそり拾ってチラリと見たら『あなたも夢のマンションオーナーに!』みたいなことが書かれていた。
なるほど。ここを潰してマンションにしようって計画か。
その紙を改めて丸め直すとゴミ箱の中へ投げ捨てた。
この家を壊すとか、絶対に許せない。
こんなにいい場所を――と柱に触れると、家の雰囲気が、ばあちゃんが生きていた頃みたいに戻った気がした。
そして気付いた。
床近くにしゃがみ込んだとき、廊下の端にうっすらと埃が溜まっていたことに――洗面所にバケツと雑巾、あったよな。
固く絞った雑巾で廊下を拭いてゆく。
端まで丁寧に。
途中からはじいちゃんも参加する。
「そうだな。俺たちの好きなこの家を、しっかり守らなきゃな」
じいちゃんはそう言いながら、ずっと僕に背中を向けて掃除していた。
うなぎが届くまで二人であちこちを綺麗にした。
おかげで家の中が少し明るくなった。
そのことをじいちゃんに伝えると、じいちゃんは少し赤い目で笑った。
「どんなもんにも命が宿ってる。大事にしたらした分だけ、ちゃんと返ってくんだよ」
なんだかわからないけど、僕まで泣きそうになった。
「さ、うなぎ食うぞ」
「やった!」
ハンバーグがうなぎに化けたと、喜んでいたら、じいちゃんが居間から出ていってしまう。
「あれ? じいちゃん、どこ行くの?」
「最近はこっちで食べてるんだ」
じいちゃんは仏壇の部屋へと移動する。
ばあちゃんの遺影が飾ってある。
じいちゃんは自分のお重から一口分を小皿に取り分けると、ばあちゃんへとお供えする。
僕も自分のお重から同じことをしようとしたら、「馬鹿。お前は食え。これは俺だけの特権だ」とちょっと照れた。
そうだよね。
じいちゃんも食べる前からご馳走様だった。
その夜はじいちゃんのところに泊まって行くことにした。
もちろん風呂の後は何回か手合わせしてもらう。
相変わらず手を抜かないじいちゃんは凄まじく強い。
というか、家の中ちょっと綺麗になったらさらに強くなってないか?
「お前、強くなったなぁ」
いやいや、じいちゃん。
一勝も出来てないのに、その言葉には全く実感がまるでわかないよ。
電気を消し、布団に入ってからも、頭の中でさっきまでの戦いを振り返る。
あそこをミスった。あそこは気付かなかった。あそこも――ほら、やっぱり。
僕はまだまだだ。
「いや、強くなっているぞ」
思わず、布団を剥いで飛び起きた。
男の声だけどじいちゃんじゃないし、そもそもじいちゃんは別の部屋だし。
しかも枕元で僕を見下ろしていたのは二人も居たから。
「だ、だだ、だ」
誰だ、と言いたいのに、口の中までビックリしてちゃんとした言葉が出てこない。
一瞬、夕方のスーツの連中かとも思ったけど二人とも着物だし、そもそも二人の体がほんのり淡い光に包まれているんだよね。
「ごめんなさいね。驚かせてしまったみたい」
今度は優しい声。
女の人かな――不思議と気持ちが落ち着く声。
状況に冷静に向き合えるようになってきた。
雨戸を閉めているから辺りは真っ暗のまま。
ということは、この人たち、幽霊?
ご先祖様?
「だ、誰ですか?」
そう問いながら、この光景に既視感を覚えていた。
正確には光景というよりも、本来見えるはずのないものが見えている、というこの感覚自体に。
「改めてご挨拶申し上げる。我はチゲン」
黒い着物の男の人。
「私はチハク」
白い着物を着た――性別は不詳だけど、とにかく綺麗な人。
「今回のご尽力、まこと感謝にたえない」
「本当に、ありがとうございました」
二人が頭を下げるから、僕も布団の上に正座して頭を下げ返す。
「い、いえ」
今回のって――もしかして昼間のスーツ追い返し事件のことかな?
もしかしてこの人たち、座敷童子――いや、座敷大人?
それに二人の雰囲気、着物とはいってもあんまり和っぽくなくて、なんか大陸っぽさを感じる。
「我らはこちらの家には先祖代々ずいぶんと世話になっている。その恩返しがしたくてそなたの力を借りたのだ」
先祖代々っていうことは、やっぱり人じゃない存在?
じいちゃんの家は古いし、一度くらいはこういうのが出てきてもいいんじゃないかとは思っていた。
「あの、写メ撮ってもよかったりしますか?」
じいちゃんに見せなきゃって気持ちが先走ってついそんなことを聞いてしまった。
失礼かな。というかやっぱり映らないものなのかな。
するとチハクさんがくすくすと笑った。
「親子ですね。やっぱり似るものですね。あなたのお父さんも私の写真が欲しいなんておっしゃいましたよ」
「いや、じいちゃんは父じゃなく祖父ですよ」
「久一郎さんと久輔さんの区別はついておりますよ。久輔さんも、小さな頃はよく遊んでくれましてね」
久一郎というのはじいちゃんの名前で、久輔ってのは父さんの名前。
なんかやっぱり「いい妖怪」みたいな――いや、もはや神様?
「そして貴方にも……」
僕も?
「これからもよろしく頼む。それとな。先ほどの者達、目先の利益を追うあまりよろしくない大工と徒党を組んでおる。また来ることもあると思うゆえ、くれぐれも注意なされい」
えっと――ああ、さっきのスーツの人たち、やっぱり悪者だったんだ。
と思いながら瞬きを何度かしたらもう、彼らの姿は消えていた。
写真はともかく聞きたいこと、もっとあったんだけどな。
真っ暗に戻った部屋で、目を開けたり閉じたりしているうちに、いつの間にか寝てしまったらしく、眩しさに目を覚ましたら朝だった。
じいちゃんが雨戸を開けていた。
「おう、起きたか」
僕は布団をたたみ、顔を洗ってからじいちゃんの居る縁側まで急いだ。
「ねぇ、じいちゃん。チゲンさんとかチハクさんって知っている?」
じいちゃんは眉間にしわを寄せ、遠くを見る。
「聞いたことあるような……ないような……」
結局、じいちゃんはそれが誰かっていうことを思い出せず、朝食を食べてから碁を打ち、三連敗してからなんとか一勝をもぎ取り僕は帰宅した。
帰ってからネットで検索すると『囲碁の精』というやつが出てきた。
チゲンさんは知玄さん、チハクさんは知白さん。
それぞれが碁石の黒と白とに宿る精のようなものらしい。
釣りから帰ってきた父にその話をすると、少し頬を赤らめ「母さんに内緒だぞ」と前置きした上で、チハクさんが初恋の人だったとこっそり教えてくれた。
囲碁を辞めたのは、チハクさんが女性ではなかったと知ってしまったかららしい。
どうやって知ったのかまでは教えてもらえなかった。
いつも後手後手にまわる父がその時はどうやって先手を打ったのか、そしてどんな確かめ方をして失敗したのか、とっても興味があったのに。
人の会話が囲碁の対局に見えることはそれっきりなかったし、あのスーツの連中も強引な方法を取ろうとして逮捕されたニュースも見た。
だからあれっきり、知玄さんにも知白さんにも会えてないんだけど――しばらくの間は白い石を持つ時についつい照れて困った。父のせいだ。
<終>
囲碁の精
対面式のキッチンでは思った通り母が煮込みハンバーグを作っていた。
父の大好物であるこの料理が作られる時は大抵、母が父にお願いごとをしたいとき。
今回はなんだろうな――あれ?
自分の目がおかしくなったのだろうか。
空中にいくつか線のようなものが見えるのだけれど。
視界を斜めに走る半透明の線のようなもの――目、傷ついてんのかな。まいったな。
今日は土曜だし、もうこんな時間だし、どこの病院でも診察時間終わっているよね。
とりあえずスマホで症状について何か出てこないか検索していると、父がリビングに現れた。
それと同時に、視界になんとなく見えていたあの線の数が一気に増える。今度はさっきの斜めとは直角に交わる斜め――格子模様?
ナナメに傾けたテニスラケットを顔の前に置かれた感じ。
「お、今夜は俺の大好物か」
僕の視界が大変なことになっているというのに、父は鼻をひくつかせながらリビングに充満する肉とソースの香りとを楽しんでいる。
のんきなもんだよ――あれ?
おかしいな。
視界の左下端、今度は小さな黒い影みたいなもので霞んでいる。
マジか――どんよりと嫌な気分。
これ目の病気か怪我か、どちらにせよきっと良くないモノだよね?
目を閉じて、五つ数えて目を開ける。
視界には、父と母の満面の笑み。テニスラケットみたいなアレは相変わらず見えたまま。
「だって週末でしょ。今週も一週間お疲れさまっ」
なんだなんだ?
今度は右上端に小さな白い靄みたいなのが現れた。
さっきの影と大きさが似ている。
「いやいや、いつもママがうちのことをやってくれているからさ。いつも感謝しているよ」
父の言葉の後、白い靄からそう遠くない場所に黒い影が一つ増える。
「ありがとう。でも、あなたの忙しさに比べたら……」
母の言葉の後、白い靄も一つ増える。
「でね、だから今夜は特別に和牛なのよ」
白い靄。
「和牛? 高かったんじゃないのか?」
黒い影。
「それがね、安かったの! 特売でねっ!」
白い靄。
「あなたが頑張ってくれているから、普段から私、ちゃんとチラシをチェックしているのよ」
また白い靄。
どうやら、父の言葉の後は黒い影が視界に増え、母の言葉の後は白い靄が増えて――これってさ、二人の会話がまるで囲碁を打っているかのように見えているってこと?
「でね、話は変わって明日なんだけれど、どうしても行きたい場所があって、車を出してもらえたら嬉しいんだけれどなぁ……って」
白い靄。
本当に囲碁だったら母さんはちょっと打ちすぎだ。
打てる場所がなくてパスせざるを得ない時以外は連続で打てないってのに。
「明日? ……明日かぁ」
黒い影。
注意して見ると、黒と白の置かれている場所はさっきの半透明の線が交わった部分。
囲碁感は強いがルールがなぁ……。
「あら……もしかして何か使う予定でも? 予定があるなら仕方ないけれど、ねぇ?」
白い靄がまた連続で増える。
勝敗判定が囲碁なら、今のはかなり重要な場所に置いたし、ここから黒の挽回は相当厳しいだろうな――じゃなくて。
これはもしかして、目じゃなく脳の問題か?
今日の昼間、じいちゃんと囲碁をさんざん打っていたからなぁ。
「いや実は……取引先の部長さんにだね、釣りに誘われていてね……まあ、天気次第なんだけれどね」
黒い影。
父さん、食らい付く。
「明日? あなたなんでいつもそういう大事なこと、いつも突然言うの?」
白。
「ほら、天気次第だし……」
黒。
「お弁当とかの準備だってあるんだから。もっと前から言っておいてよ。いつも言ってるでしょ?」
白。白。
「いや、声かけられたのは昨日の夕方でね」
黒。
「昨日? その時点で連絡くれてもいいじゃない」
白。
「釣りってことは隣でその部長さんにお弁当見られちゃうわけでしょ? ありあわせで済ませるわけにはいかないんだからっ。いつもお弁当、どうやって作ってるか知ってますか? 栄養とか季節とか予算とか考えて、工夫して、毎日のご飯とも被らないようにしているし……目の前にあるお弁当にどれだけの手間と愛情が詰まっているか、あなたは考えた事なんてないんだわ……」
白。白。白。白。白。
父さんは目を泳がせながら沈黙している。
「もう、そういえばこないだもだったわよ?」
白。
母の勢いと物量に対し、父は完全に弱気な打ち筋。
大勢が決した。
『あいつの囲碁は粘りがない。なにかあるとすぐに逃げ出すんだ』
じいちゃんの言葉を思い出した。
じいちゃんは囲碁が滅茶苦茶強い。
若い頃、デキ婚のせいで固定給の仕事を始めなかったら今頃はプロ棋士になっていたかもしれない、とかいつも言っているくらい。
僕はそのじいちゃんに囲碁を教えてもらった。
じいちゃんが住んでいるのは隣の駅だけど、徒歩+電車よりは自転車の方が早いくらいのご近所。
だから小さい頃からしょっちゅう遊びに行っていた。
じいちゃんのとこは居心地がいい。
また家がいいんだ――って言うといつも「子供っぽくない感想だ」って笑われるけど。
でも本当に。
映画の撮影に使えそうな古い家。
壁や廊下に触れているだけで落ち着くというか。
本当は冬でも裸足で居たいくらい。
それから中庭。
家がロの字になっている内側に、小さな池と梅の木とがある。
皆でよく縁側に座って中庭を眺めてた。
僕、碁盤、じいちゃん、ばあちゃん、お茶菓子。
じいちゃんはあんまりこっちを見てないのに絶望的に強くて。
子ども相手に手を一切抜かないんだよね。
父が囲碁を辞めたのも、あの大人げない勝ち方のせいじゃないかなって思うくらい。
まあ、それでも僕は諦めずに打ち続けて、ようやくたまにはじいちゃんに勝てるくらいになったけどさ――手加減してもらっている疑惑がなくはないけど。
そんな、じいちゃんの家の居心地が変わってしまったのは去年のこと。
ばあちゃんが亡くなったから。
じいちゃんの落ち込みようったらなかった。
空気が抜けてるんじゃないかってくらい、毎日少しずつしぼんで小さくなってゆく。
それだけじゃない。あの家の居心地だってまるで変わってしまった。
ばあちゃん、古民家の精なんじゃないかって思ったほど。
とにかく何もかもが心配で、今は学校帰りに毎日通っている。
じいちゃんが、碁を打っている時だけはしゃんとすることに気付いたから。
僕が碁石を置いた途端、大人げないヤル気のあるじいちゃんが戻って来る。
「ちょ、ちょっと待って母さん」
あまりにも白の増えるペースが早すぎて、じいちゃんのこと考えているうちに、視界が真っ白になっていたから、思わず声を出して
しまった――けれど、何を待ってなのか自分でもよく分からない。
ただ僕の一言のあと、白い靄がいくつか黒い影へと変わった。
その場所は、思い返してみれば、最初の方に本来なら父が次打つかなって思ったときに母が連続して打った場所。
ここだけじゃない、ここも、ここも、母が連続で打ったけど本来ならば……と、意識を集中しただけで、白と黒の異常な差が直されてゆく。
ああ、これならズルなしの囲碁の勝負みたいな盤面だなと思えた時、母が叫んだ。
「ズルい! 二人がかりで説得なんて!」
二人がかり?
ちょっと待ってって言っただけだけど――そうやって思い返すと、盤面のズル白を正しい黒に直した時、僕の口から何か言葉が出ていたような気がする。
何て言ったかまでは思い出せないのだけど。
「ごめんごめん。本当にごめん」
父が母の手を握りしめている。
「ごめんよ。この埋め合わせは必ずするから。ね、ね」
なんか落ち着いてるというか、ちょっと子どもの目の前でイチャついているというか。
食事前だけど気分はご馳走さまです。見てらんない。
「ちょっとじいちゃんのとこ行って来る」
「え、ハンバーグは?」
「父さんの明日のお弁当のメインにでもしなよ」
僕がそう言った途端、白も黒も碁盤みたいな線も全部消えた。なんだったんだ。
まだ手を握り合っている両親を
「行ってきます!」
じいちゃんがあの家に一人きりになってから、僕がじいちゃんの家に行くことは、何においても優先していいことの一つになっている。
こうやって様子を見に行くとさえ言えば大抵の用事からは逃れられる免罪符として――こういうとこ、父に似たのかな。
いや、今はそんなこと言っている場合じゃなく――囲碁に似ているなって思ってからはずっとじいちゃんのことが頭の片隅にひっかかっていたんだ。
急いで自転車に飛び乗ると猛烈にペダルをこぐ。
既に陽が暮れた道、点々と連なる街灯が白い石に見える。
その白を次々と背後に飛ばしながら、じいちゃんの家まで走り続けた。
そしてたどり着いたじいちゃんの家。
自転車を止めようとして、家の前に大きな黒い車が停まっているの気づく。
門も半開き。
何か異様な気配を感じた僕はダッシュで玄関へと急ぐ。
玄関の戸の鍵も開いている。
「じいちゃん!」
大声でじいちゃんを呼びながら、ガラス戸をガラガラと開ける。
そして慌てて飛び込んだ玄関で黒い靴につまずきそうになる。
お客さん? こんな時間に?
急いで靴を脱ぎ、家の中へ駆け上がった。
「じいちゃん!」
とりあえず居間を覗いてみる――と、そこには渋い顔をしたじいちゃんと、スーツを着た大人たちが数人。
そして、また視界に例の碁盤模様が現れる。
対局は既に始まっていて、ぎょっとするほど黒が優勢――でもこれ、母の時と同じ。
明らかに黒が連続で打っているヤツだ。
「お邪魔しております」
一番先頭に座っている大人が僕に挨拶をして、すぐさまじいちゃんに向き直り目の前に並べた資料を指差しながら何か言っている。
ああ、こいつらが黒か。
とりあえず、今の黒はナシだろ。
あとはここも、ここも――じいちゃんの白をもとに、このへんは連続打ちされたんじゃないだろうか、と考え得る盤面のおかしなところを直しまくる。
僕の口から何か言葉が出ているみたいだけど、今は音のない世界に居るみたいに何も聞こえない。
直しているうちに、他の部分も勝手に白くなり始めた。
白と黒の数が同じくらいに直ると、そこはさすがじいちゃん。
しびれるような一手を打ち続け、対局はあっという間に白の圧勝に終わった。
「もう、二度と来るな」
じいちゃんの一言が聞こえるようになったとき、視界から碁盤は消え、他の声も音も戻ってきた。
スーツの大人たちは一礼をするとスゴスゴと帰ってゆく。
そいつらが玄関を出た後、じいちゃんはどこから取り出したのか塩をまく。
「もう、二度と来るな!」
じいちゃん、二回言った。
よっぽど腹を立てているのか。
そして車が去ってゆく音を確認したあと、僕に向かって小さな声でこう言った。
「助かった。ありがとな」
玄関にしっかりと立っているじいちゃんは、囲碁を打っている時のカッコイイじいちゃんだった。
「まあね」
「飯食ったか?」
「あ、まだだ」
「出前取るから、食べていけ」
じいちゃんはあの大人たちのことを何も言わなかったけれど、あいつらが置いていった紙をじいちゃんがくしゃくしゃに丸めてゴミ箱に投げ捨て――たのをこっそり拾ってチラリと見たら『あなたも夢のマンションオーナーに!』みたいなことが書かれていた。
なるほど。ここを潰してマンションにしようって計画か。
その紙を改めて丸め直すとゴミ箱の中へ投げ捨てた。
この家を壊すとか、絶対に許せない。
こんなにいい場所を――と柱に触れると、家の雰囲気が、ばあちゃんが生きていた頃みたいに戻った気がした。
そして気付いた。
床近くにしゃがみ込んだとき、廊下の端にうっすらと埃が溜まっていたことに――洗面所にバケツと雑巾、あったよな。
固く絞った雑巾で廊下を拭いてゆく。
端まで丁寧に。
途中からはじいちゃんも参加する。
「そうだな。俺たちの好きなこの家を、しっかり守らなきゃな」
じいちゃんはそう言いながら、ずっと僕に背中を向けて掃除していた。
うなぎが届くまで二人であちこちを綺麗にした。
おかげで家の中が少し明るくなった。
そのことをじいちゃんに伝えると、じいちゃんは少し赤い目で笑った。
「どんなもんにも命が宿ってる。大事にしたらした分だけ、ちゃんと返ってくんだよ」
なんだかわからないけど、僕まで泣きそうになった。
「さ、うなぎ食うぞ」
「やった!」
ハンバーグがうなぎに化けたと、喜んでいたら、じいちゃんが居間から出ていってしまう。
「あれ? じいちゃん、どこ行くの?」
「最近はこっちで食べてるんだ」
じいちゃんは仏壇の部屋へと移動する。
ばあちゃんの遺影が飾ってある。
じいちゃんは自分のお重から一口分を小皿に取り分けると、ばあちゃんへとお供えする。
僕も自分のお重から同じことをしようとしたら、「馬鹿。お前は食え。これは俺だけの特権だ」とちょっと照れた。
そうだよね。
じいちゃんも食べる前からご馳走様だった。
その夜はじいちゃんのところに泊まって行くことにした。
もちろん風呂の後は何回か手合わせしてもらう。
相変わらず手を抜かないじいちゃんは凄まじく強い。
というか、家の中ちょっと綺麗になったらさらに強くなってないか?
「お前、強くなったなぁ」
いやいや、じいちゃん。
一勝も出来てないのに、その言葉には全く実感がまるでわかないよ。
電気を消し、布団に入ってからも、頭の中でさっきまでの戦いを振り返る。
あそこをミスった。あそこは気付かなかった。あそこも――ほら、やっぱり。
僕はまだまだだ。
「いや、強くなっているぞ」
思わず、布団を剥いで飛び起きた。
男の声だけどじいちゃんじゃないし、そもそもじいちゃんは別の部屋だし。
しかも枕元で僕を見下ろしていたのは二人も居たから。
「だ、だだ、だ」
誰だ、と言いたいのに、口の中までビックリしてちゃんとした言葉が出てこない。
一瞬、夕方のスーツの連中かとも思ったけど二人とも着物だし、そもそも二人の体がほんのり淡い光に包まれているんだよね。
「ごめんなさいね。驚かせてしまったみたい」
今度は優しい声。
女の人かな――不思議と気持ちが落ち着く声。
状況に冷静に向き合えるようになってきた。
雨戸を閉めているから辺りは真っ暗のまま。
ということは、この人たち、幽霊?
ご先祖様?
「だ、誰ですか?」
そう問いながら、この光景に既視感を覚えていた。
正確には光景というよりも、本来見えるはずのないものが見えている、というこの感覚自体に。
「改めてご挨拶申し上げる。我はチゲン」
黒い着物の男の人。
「私はチハク」
白い着物を着た――性別は不詳だけど、とにかく綺麗な人。
「今回のご尽力、まこと感謝にたえない」
「本当に、ありがとうございました」
二人が頭を下げるから、僕も布団の上に正座して頭を下げ返す。
「い、いえ」
今回のって――もしかして昼間のスーツ追い返し事件のことかな?
もしかしてこの人たち、座敷童子――いや、座敷大人?
それに二人の雰囲気、着物とはいってもあんまり和っぽくなくて、なんか大陸っぽさを感じる。
「我らはこちらの家には先祖代々ずいぶんと世話になっている。その恩返しがしたくてそなたの力を借りたのだ」
先祖代々っていうことは、やっぱり人じゃない存在?
じいちゃんの家は古いし、一度くらいはこういうのが出てきてもいいんじゃないかとは思っていた。
「あの、写メ撮ってもよかったりしますか?」
じいちゃんに見せなきゃって気持ちが先走ってついそんなことを聞いてしまった。
失礼かな。というかやっぱり映らないものなのかな。
するとチハクさんがくすくすと笑った。
「親子ですね。やっぱり似るものですね。あなたのお父さんも私の写真が欲しいなんておっしゃいましたよ」
「いや、じいちゃんは父じゃなく祖父ですよ」
「久一郎さんと久輔さんの区別はついておりますよ。久輔さんも、小さな頃はよく遊んでくれましてね」
久一郎というのはじいちゃんの名前で、久輔ってのは父さんの名前。
なんかやっぱり「いい妖怪」みたいな――いや、もはや神様?
「そして貴方にも……」
僕も?
「これからもよろしく頼む。それとな。先ほどの者達、目先の利益を追うあまりよろしくない大工と徒党を組んでおる。また来ることもあると思うゆえ、くれぐれも注意なされい」
えっと――ああ、さっきのスーツの人たち、やっぱり悪者だったんだ。
と思いながら瞬きを何度かしたらもう、彼らの姿は消えていた。
写真はともかく聞きたいこと、もっとあったんだけどな。
真っ暗に戻った部屋で、目を開けたり閉じたりしているうちに、いつの間にか寝てしまったらしく、眩しさに目を覚ましたら朝だった。
じいちゃんが雨戸を開けていた。
「おう、起きたか」
僕は布団をたたみ、顔を洗ってからじいちゃんの居る縁側まで急いだ。
「ねぇ、じいちゃん。チゲンさんとかチハクさんって知っている?」
じいちゃんは眉間にしわを寄せ、遠くを見る。
「聞いたことあるような……ないような……」
結局、じいちゃんはそれが誰かっていうことを思い出せず、朝食を食べてから碁を打ち、三連敗してからなんとか一勝をもぎ取り僕は帰宅した。
帰ってからネットで検索すると『囲碁の精』というやつが出てきた。
チゲンさんは知玄さん、チハクさんは知白さん。
それぞれが碁石の黒と白とに宿る精のようなものらしい。
釣りから帰ってきた父にその話をすると、少し頬を赤らめ「母さんに内緒だぞ」と前置きした上で、チハクさんが初恋の人だったとこっそり教えてくれた。
囲碁を辞めたのは、チハクさんが女性ではなかったと知ってしまったかららしい。
どうやって知ったのかまでは教えてもらえなかった。
いつも後手後手にまわる父がその時はどうやって先手を打ったのか、そしてどんな確かめ方をして失敗したのか、とっても興味があったのに。
人の会話が囲碁の対局に見えることはそれっきりなかったし、あのスーツの連中も強引な方法を取ろうとして逮捕されたニュースも見た。
だからあれっきり、知玄さんにも知白さんにも会えてないんだけど――しばらくの間は白い石を持つ時についつい照れて困った。父のせいだ。
<終>
囲碁の精