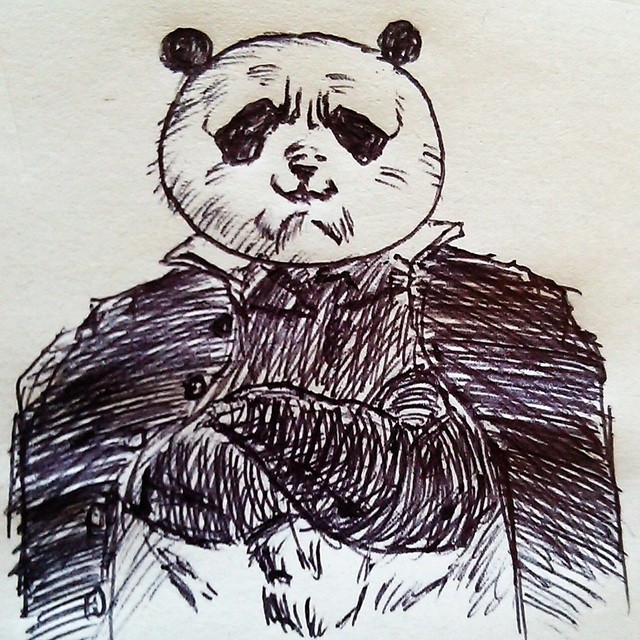猫屋敷
文字数 4,765文字
「あの……黒い子を……」
僕がそう言うとナァコは静かに頷いた。その顔が、あまりにも辛そうだったから、僕はナァコの手を握る。
「怒ってないの?」
「……」
怒ってはない。でも複雑な気持ちだったから、伝える言葉を考えるのに、集中したくて、目を閉じた。
唇に気配を感じる……これは、キス、かな。ああ、目を閉じなければ、良かった、かな。
僕が突然、旅に出た理由は、久々に間に合った終電で眠ってしまったから。
起こされた終着駅は隣の県。駅前にタクシーは来ていたが、ここから自宅までのタクシー代を考えると早々にその選択肢は消えた。自腹じゃ生活が苦しくなるのは確実だし、会社は絶対に出してくれないだろう。そもそもそんな金出してくれるとこなら連夜のサビ徹なんかさせられないだろうし。
とりあえず駅からは追い出されてしまったので、しんどい体を前へ前へと動かし続ける。
大きな通りに出て、遠くに見えた灯りにつられて虫のように無心で近づく。
ありがたいことにコンビニ。
とりあえず何か食べたい。今日は、いや昨日は、昼から何も食べていない。
おにぎりを幾つか買って駐車場の車止めに腰掛けて腹に詰め込む。気持ち的にはアルコールの一つでも入れたい気分だったが、そんなの飲んだら絶対にここで寝てしまう自信がある。
栄養ドリンクは米にはまったく合わないが、自分のヒットポイントが赤からオレンジになった気分がして、ようやくため息が出る。
空を見上げ、欠けた月を眺め、それから駐車場に停まっているトラックを見つめる――ああ、懐かしいな。あれ、うちの地元でよく見たトラックだ。こんな所でも見るなんて。
実家を思い出すとため息が出る。真ん中だけできが悪くて居心地の良くなかった実家。しんどくて飛び出したけれど、改めて考えると今の生活の方がずっとずっとしんどいな。
ああ、僕の人生ってなんなんだ――普段は考えないようにしていた想いがあふれるのを今夜は止められない。
「兄ちゃん、どうしたんだい?」
突然、板前みたいな顔のキリッとしたおじさんに話しかけられた。
「え、えーと、あのトラック、地元でよく見たなって」
「あー……じゃあ、ホームシックか?」
ホームシック? そうなのかな……もう随分と帰っていない、あんな実家でも、今よりマシって思えるからにはそうなのかな。
「兄ちゃん、乗ってくかい?」
この道を、実家方面だと自宅や会社とは反対方向だけど――会社と反対方向、という単語が、僕を強く突き動かして、首を大きく縦に振っていた。
トラックに乗せてもらってからは、おじさんはやたらと身の上話を聞いてきた。
どうやら僕はトラックを見ながら泣いていたらしく、挙動も変だったから自殺でもするのかと心配になったらしい。
仕事の愚痴も聞いてくれて、そんなところはさっさと辞めて新しい仕事を探したほうがいいとも言われた。忙しさで明日が見えない状況にいると、仕事を辞めるということさえ考えらなくなっちゃうから、仮病でもいいからいったん休めと。もしも体調悪くても仕事を休ませてもらえないのだとしたら、それは労働じゃなく奴隷だと。
僕は何度も肯きながら、気がついたら寝てしまっていた。
「この辺で良いんだっけ?」
おじさんが起こしてくれたのは、実家のある市内。おそらくおじさんの目的地からわざわざ遠回りして寄ってくれたんだと思う。ここまで来れば、徒歩でも数時間で実家まで付けるし、僕は何度もお礼を言って、トラックから降ろしてもらった。
早朝の車通りのそう多くない幹線道路。
少し肌寒い。
草臥れたスーツのボタンをちゃんと留め、青看板を確認してから歩き始め……その声にすぐに気がついた。
道路脇の草むらからニィニィとか細い猫っぽい鳴き声。
声を追っていくと、側溝の中で真っ黒い仔猫が震えていた。とりあえず抱き上げてハンカチで体を拭いて、スーツの上着を脱いでくるむ。自身が助けてもらったばかりだからかな、心に少しだけできたゆとりが助ける側に僕を回らせたんだと思う。
とはいえ、これで助けたと思うのはまだ早い。今はまだ拾っただけ、という状態。お腹も空かせていそうだし。
小さな黒猫を抱えたまま道路を歩き続け、コンビニを探す。
この辺は本当に店もない。もしあったとしても、時間的にはまだ開店していない恐れもある。実家に着くほうが早いかもな、なんて考えていると、見たことのある建物。
高い塀に囲まれた、和風二階建ての大きな建物。敷地も広く、パッと見は旅館のようにも見えるけど、ここは秘密の保養所なんだよね。
気持ちが急激に、あの頃へと戻る。
中二の夏、悪友たちと肝試しに行った『猫屋敷』に。
僕らの地元から『猫屋敷』までは自転車で一時間くらいの距離だった。
昼は猫だらけ、夜になると時折大きな化け物が出るという噂は僕らの地元にまで届いていて、『猫屋敷』での肝試しというのは当時の僕ら世代の男子にとっては一種の通過儀礼のようなものだった。
とはいえ地元から往復二時間もの距離を考えると夜に出られるチャンスというのは限られていて、俺と悪友三人は夏祭りまで冒険を待たねばならなかった。
満を持して迎えた夏祭りの夜、興奮と緊張とでカラカラになった口の中にカナブンが飛んで入ってきたのは今や良い思い出だ。
それ以外には特にトラブルもなく、僕らは『猫屋敷』へと到着する。
高い塀に一つしかない立派な門からそう遠くない場所に自転車を停め、懐中電灯をしっかり握りしめて近づいてゆく。
『□□社 保養所』
会社名はかすれていて読めないが、どこの会社かというのは僕らにはどうでもよくて、懐中電灯を落とさないよう気をつけながら、アルミ製の立派な門を乗り越えて敷地内へ忍び込む。
敷地内は木立や茂みが多く、建物からは一応死角になっていると思われるルートを進む。
何度かは猫に遭遇し、その度に肝を冷やし、もういい加減猫しかいないんじゃないかと肩の力も抜けきった頃、悪友の一人が突然声をあげた。
「あっ、あれっ!」
そいつが指している建物の屋上には、人間くらいの大きな影が動いていた。
その影は僕たちの声にこちらを向き、そこから地面まで一気に跳んだ。その跳躍が、着地が、あまりにも綺麗だったので、僕はため息をついたのを覚えている。
気がついたら周囲から悪友三人は居なくなっていた。
「何しに来たの?」
女の子の声。その子はまっすぐ僕の方へ向かってくる。
でも暗いのにけっこう目が慣れていた僕は、わずかな月明かりに照らされたその子の美少女っぷりに見惚れていた。ここの会社の関係者の人だろうか。
「すみません……肝試しです」
不法侵入という言葉は知っていたが、子供の遊びとちょっと叱られるだけで済むかもしれない――そんな打算でそう伝えた。
だが女の子は眉をしかめた。
「肝試し?」
「い、いえ、怖いってより、綺麗でした!」
何をトチ狂ってそんなことを言ってしまったのか。今思い出しても恥ずかしい。
でも、女の子はそんな僕を見て笑った。
「変なヒト」
その後、なぜか僕は女の子――ナァコと一緒に保養所の屋上へと登った。夏祭りの終わりに上がる花火、それが観たいらしくって。 しかも僕は初対面のナァコを肩車までした。カッコいいとこ見せたくて、言ってみたら本当に採用されちゃって。
女の子を肩車。思春期男子にとっては、それだけでかなりどでかいインパクトで。その時点でナァコは僕の好きな子ナンバーワンになっていた。
「今日はありがと。ギリギリ見えたよ」
笑顔のナァコに、僕は照れまくっていた。
暗くて良かった。顔が真っ赤なのがバレないだろうから。
「約束して。今夜のこと誰にも言わないって。それからもう二度とここへ来ないって」
好きになったばかりの子にそんなこと言われたら、ものすごくショックだった。その反面、オオゴトにならずに済みそうなことにホッとしていた。
もしかしたらここはどこかの芸能事務所の保養所で、この子はアイドルか何かで、会社の名前がわからなくなっているのも、秘密にするのも、ここへ来ちゃいけないのも全部、この子のためなんだって。
そう思い込んで僕は『猫屋敷』から外へ出た。
途中、僕がついてきてないことに気づいた悪友三人が引き返してきたのと合流し、僕はびっくりして転んだだけで、猫を見間違えただけで、落っことした懐中電灯を探してて遅くなったと嘘をついた。
それっきり。
ナァコとの約束をずっと守って……状況して社会人になって日々の忙しさに追われ、今の今までそのことをずっと忘れていた。
門の前に立つ。
あの夏に乗り越えた門と少しも変わっていない。
そして敷地の中には何匹もの猫。
これだけ猫がいっぱい居るなら、この黒い仔猫も一緒に可愛がってもらえるかもしれない。
僕は門の隙間から、そっと仔猫を敷地の中へ放した。
黒い仔猫はヨロヨロと歩きながら、猫の群れへと近づいてゆく。敷地内の猫たちはだんだんと集まってきて、じっと仔猫を見つめている。
その様子を僕も見守っていたのだが、なぜか背筋に冷たいものが走った。
その直後、予想だにしないことが起きた。猫たちがわっと集まってきて、一斉に仔猫を叩き始めたのだ。
仔猫は叩かれるたびに力なく鳴きながらこっちへと転がってくる。
ただでさえ弱っているのに――僕は気がついたら門を乗り越え、仔猫の近くへと駆け寄っていた。
仔猫を抱きかかえ、急いで門へ向かって戻ろうとしたそのとき、門の前に少女が立っていることに気づいた。
忘れもしない、あの夏に大好きになった美少女、ナァコにそっくりだったその子は、とても残念そうな顔でこう言った。
「約束、破ったんだね」
その後、首筋に熱いものが走り、意識が一瞬遠のき、気がついたらどこかの屋内で、たくさんの猫に囲まれていた。
傍らにはナァコを始め、何人もの人が居た。
ナァコ以外は皆、着物で――まるで時代劇の撮影でもしているかのような服装。ちょんまげの人さえも居た。やっぱりどこかの芸能事務所だったのかな。
「ごめんね。頼んでみたけど二回目はダメだって」
「二回目?」
ああ、そうか。あの夏の夜が一回目だったのか。でも……なんで?
「私たちが生き延びるためにはね、ヒトに関わっちゃダメなの」
ヒト? 一般人ってこと?
「あとね、ここには化け猫しかいないの。普通の猫はいられないの」
「……化け、猫?」
「死に際のヒトの生き血を舐めた猫はね、化け猫になれるの。ナァコのこの姿も、本当はナァコのご主人の姿よ。強盗に殺された……ナツミの」
「ああ……ナァコ」
それで、猫っぽい名前だったのか。
「なぁに?」
呼んだつもりではなかったけど、返事をしてくれた。
その瞬間にひらめいたこと。僕はあの会社でゴミクズのように扱われていつか突然過労死していたかもしれないなって。どうせ無駄に死ぬくらいなら……。
「あの……黒い子を……」
僕がそう言うとナァコは静かに頷いた。その顔が、あまりにも辛そうだったから、僕はナァコの手を握る。
「怒ってないの?」
「……」
怒ってはない。でも複雑な気持ちだったから、伝える言葉を考えるのに、集中したくて、目を閉じた。
唇に気配を感じる……これは、キス、かな。ああ、目を閉じなければ、良かった、かな。
胸元にトンと、キスとは違う軽いものが置かれて目を開ける。
あの黒い仔猫。
「僕の血で、この子を仲間にしてあげて」
涙目のナァコの唇が血に濡れていて、でも、怖いってよりとても綺麗で。
「わかった」
カッコいいとこ見せたくて、言ってみたら、また本当に採用されちゃったなって……あ、僕の人生、無駄じゃなかったって。
僕は精一杯の笑顔を作って、黒い仔猫を撫でてから、ゆっくりと目を閉じた。
<終>
化け猫
僕がそう言うとナァコは静かに頷いた。その顔が、あまりにも辛そうだったから、僕はナァコの手を握る。
「怒ってないの?」
「……」
怒ってはない。でも複雑な気持ちだったから、伝える言葉を考えるのに、集中したくて、目を閉じた。
唇に気配を感じる……これは、キス、かな。ああ、目を閉じなければ、良かった、かな。
僕が突然、旅に出た理由は、久々に間に合った終電で眠ってしまったから。
起こされた終着駅は隣の県。駅前にタクシーは来ていたが、ここから自宅までのタクシー代を考えると早々にその選択肢は消えた。自腹じゃ生活が苦しくなるのは確実だし、会社は絶対に出してくれないだろう。そもそもそんな金出してくれるとこなら連夜のサビ徹なんかさせられないだろうし。
とりあえず駅からは追い出されてしまったので、しんどい体を前へ前へと動かし続ける。
大きな通りに出て、遠くに見えた灯りにつられて虫のように無心で近づく。
ありがたいことにコンビニ。
とりあえず何か食べたい。今日は、いや昨日は、昼から何も食べていない。
おにぎりを幾つか買って駐車場の車止めに腰掛けて腹に詰め込む。気持ち的にはアルコールの一つでも入れたい気分だったが、そんなの飲んだら絶対にここで寝てしまう自信がある。
栄養ドリンクは米にはまったく合わないが、自分のヒットポイントが赤からオレンジになった気分がして、ようやくため息が出る。
空を見上げ、欠けた月を眺め、それから駐車場に停まっているトラックを見つめる――ああ、懐かしいな。あれ、うちの地元でよく見たトラックだ。こんな所でも見るなんて。
実家を思い出すとため息が出る。真ん中だけできが悪くて居心地の良くなかった実家。しんどくて飛び出したけれど、改めて考えると今の生活の方がずっとずっとしんどいな。
ああ、僕の人生ってなんなんだ――普段は考えないようにしていた想いがあふれるのを今夜は止められない。
「兄ちゃん、どうしたんだい?」
突然、板前みたいな顔のキリッとしたおじさんに話しかけられた。
「え、えーと、あのトラック、地元でよく見たなって」
「あー……じゃあ、ホームシックか?」
ホームシック? そうなのかな……もう随分と帰っていない、あんな実家でも、今よりマシって思えるからにはそうなのかな。
「兄ちゃん、乗ってくかい?」
この道を、実家方面だと自宅や会社とは反対方向だけど――会社と反対方向、という単語が、僕を強く突き動かして、首を大きく縦に振っていた。
トラックに乗せてもらってからは、おじさんはやたらと身の上話を聞いてきた。
どうやら僕はトラックを見ながら泣いていたらしく、挙動も変だったから自殺でもするのかと心配になったらしい。
仕事の愚痴も聞いてくれて、そんなところはさっさと辞めて新しい仕事を探したほうがいいとも言われた。忙しさで明日が見えない状況にいると、仕事を辞めるということさえ考えらなくなっちゃうから、仮病でもいいからいったん休めと。もしも体調悪くても仕事を休ませてもらえないのだとしたら、それは労働じゃなく奴隷だと。
僕は何度も肯きながら、気がついたら寝てしまっていた。
「この辺で良いんだっけ?」
おじさんが起こしてくれたのは、実家のある市内。おそらくおじさんの目的地からわざわざ遠回りして寄ってくれたんだと思う。ここまで来れば、徒歩でも数時間で実家まで付けるし、僕は何度もお礼を言って、トラックから降ろしてもらった。
早朝の車通りのそう多くない幹線道路。
少し肌寒い。
草臥れたスーツのボタンをちゃんと留め、青看板を確認してから歩き始め……その声にすぐに気がついた。
道路脇の草むらからニィニィとか細い猫っぽい鳴き声。
声を追っていくと、側溝の中で真っ黒い仔猫が震えていた。とりあえず抱き上げてハンカチで体を拭いて、スーツの上着を脱いでくるむ。自身が助けてもらったばかりだからかな、心に少しだけできたゆとりが助ける側に僕を回らせたんだと思う。
とはいえ、これで助けたと思うのはまだ早い。今はまだ拾っただけ、という状態。お腹も空かせていそうだし。
小さな黒猫を抱えたまま道路を歩き続け、コンビニを探す。
この辺は本当に店もない。もしあったとしても、時間的にはまだ開店していない恐れもある。実家に着くほうが早いかもな、なんて考えていると、見たことのある建物。
高い塀に囲まれた、和風二階建ての大きな建物。敷地も広く、パッと見は旅館のようにも見えるけど、ここは秘密の保養所なんだよね。
気持ちが急激に、あの頃へと戻る。
中二の夏、悪友たちと肝試しに行った『猫屋敷』に。
僕らの地元から『猫屋敷』までは自転車で一時間くらいの距離だった。
昼は猫だらけ、夜になると時折大きな化け物が出るという噂は僕らの地元にまで届いていて、『猫屋敷』での肝試しというのは当時の僕ら世代の男子にとっては一種の通過儀礼のようなものだった。
とはいえ地元から往復二時間もの距離を考えると夜に出られるチャンスというのは限られていて、俺と悪友三人は夏祭りまで冒険を待たねばならなかった。
満を持して迎えた夏祭りの夜、興奮と緊張とでカラカラになった口の中にカナブンが飛んで入ってきたのは今や良い思い出だ。
それ以外には特にトラブルもなく、僕らは『猫屋敷』へと到着する。
高い塀に一つしかない立派な門からそう遠くない場所に自転車を停め、懐中電灯をしっかり握りしめて近づいてゆく。
『□□社 保養所』
会社名はかすれていて読めないが、どこの会社かというのは僕らにはどうでもよくて、懐中電灯を落とさないよう気をつけながら、アルミ製の立派な門を乗り越えて敷地内へ忍び込む。
敷地内は木立や茂みが多く、建物からは一応死角になっていると思われるルートを進む。
何度かは猫に遭遇し、その度に肝を冷やし、もういい加減猫しかいないんじゃないかと肩の力も抜けきった頃、悪友の一人が突然声をあげた。
「あっ、あれっ!」
そいつが指している建物の屋上には、人間くらいの大きな影が動いていた。
その影は僕たちの声にこちらを向き、そこから地面まで一気に跳んだ。その跳躍が、着地が、あまりにも綺麗だったので、僕はため息をついたのを覚えている。
気がついたら周囲から悪友三人は居なくなっていた。
「何しに来たの?」
女の子の声。その子はまっすぐ僕の方へ向かってくる。
でも暗いのにけっこう目が慣れていた僕は、わずかな月明かりに照らされたその子の美少女っぷりに見惚れていた。ここの会社の関係者の人だろうか。
「すみません……肝試しです」
不法侵入という言葉は知っていたが、子供の遊びとちょっと叱られるだけで済むかもしれない――そんな打算でそう伝えた。
だが女の子は眉をしかめた。
「肝試し?」
「い、いえ、怖いってより、綺麗でした!」
何をトチ狂ってそんなことを言ってしまったのか。今思い出しても恥ずかしい。
でも、女の子はそんな僕を見て笑った。
「変なヒト」
その後、なぜか僕は女の子――ナァコと一緒に保養所の屋上へと登った。夏祭りの終わりに上がる花火、それが観たいらしくって。 しかも僕は初対面のナァコを肩車までした。カッコいいとこ見せたくて、言ってみたら本当に採用されちゃって。
女の子を肩車。思春期男子にとっては、それだけでかなりどでかいインパクトで。その時点でナァコは僕の好きな子ナンバーワンになっていた。
「今日はありがと。ギリギリ見えたよ」
笑顔のナァコに、僕は照れまくっていた。
暗くて良かった。顔が真っ赤なのがバレないだろうから。
「約束して。今夜のこと誰にも言わないって。それからもう二度とここへ来ないって」
好きになったばかりの子にそんなこと言われたら、ものすごくショックだった。その反面、オオゴトにならずに済みそうなことにホッとしていた。
もしかしたらここはどこかの芸能事務所の保養所で、この子はアイドルか何かで、会社の名前がわからなくなっているのも、秘密にするのも、ここへ来ちゃいけないのも全部、この子のためなんだって。
そう思い込んで僕は『猫屋敷』から外へ出た。
途中、僕がついてきてないことに気づいた悪友三人が引き返してきたのと合流し、僕はびっくりして転んだだけで、猫を見間違えただけで、落っことした懐中電灯を探してて遅くなったと嘘をついた。
それっきり。
ナァコとの約束をずっと守って……状況して社会人になって日々の忙しさに追われ、今の今までそのことをずっと忘れていた。
門の前に立つ。
あの夏に乗り越えた門と少しも変わっていない。
そして敷地の中には何匹もの猫。
これだけ猫がいっぱい居るなら、この黒い仔猫も一緒に可愛がってもらえるかもしれない。
僕は門の隙間から、そっと仔猫を敷地の中へ放した。
黒い仔猫はヨロヨロと歩きながら、猫の群れへと近づいてゆく。敷地内の猫たちはだんだんと集まってきて、じっと仔猫を見つめている。
その様子を僕も見守っていたのだが、なぜか背筋に冷たいものが走った。
その直後、予想だにしないことが起きた。猫たちがわっと集まってきて、一斉に仔猫を叩き始めたのだ。
仔猫は叩かれるたびに力なく鳴きながらこっちへと転がってくる。
ただでさえ弱っているのに――僕は気がついたら門を乗り越え、仔猫の近くへと駆け寄っていた。
仔猫を抱きかかえ、急いで門へ向かって戻ろうとしたそのとき、門の前に少女が立っていることに気づいた。
忘れもしない、あの夏に大好きになった美少女、ナァコにそっくりだったその子は、とても残念そうな顔でこう言った。
「約束、破ったんだね」
その後、首筋に熱いものが走り、意識が一瞬遠のき、気がついたらどこかの屋内で、たくさんの猫に囲まれていた。
傍らにはナァコを始め、何人もの人が居た。
ナァコ以外は皆、着物で――まるで時代劇の撮影でもしているかのような服装。ちょんまげの人さえも居た。やっぱりどこかの芸能事務所だったのかな。
「ごめんね。頼んでみたけど二回目はダメだって」
「二回目?」
ああ、そうか。あの夏の夜が一回目だったのか。でも……なんで?
「私たちが生き延びるためにはね、ヒトに関わっちゃダメなの」
ヒト? 一般人ってこと?
「あとね、ここには化け猫しかいないの。普通の猫はいられないの」
「……化け、猫?」
「死に際のヒトの生き血を舐めた猫はね、化け猫になれるの。ナァコのこの姿も、本当はナァコのご主人の姿よ。強盗に殺された……ナツミの」
「ああ……ナァコ」
それで、猫っぽい名前だったのか。
「なぁに?」
呼んだつもりではなかったけど、返事をしてくれた。
その瞬間にひらめいたこと。僕はあの会社でゴミクズのように扱われていつか突然過労死していたかもしれないなって。どうせ無駄に死ぬくらいなら……。
「あの……黒い子を……」
僕がそう言うとナァコは静かに頷いた。その顔が、あまりにも辛そうだったから、僕はナァコの手を握る。
「怒ってないの?」
「……」
怒ってはない。でも複雑な気持ちだったから、伝える言葉を考えるのに、集中したくて、目を閉じた。
唇に気配を感じる……これは、キス、かな。ああ、目を閉じなければ、良かった、かな。
胸元にトンと、キスとは違う軽いものが置かれて目を開ける。
あの黒い仔猫。
「僕の血で、この子を仲間にしてあげて」
涙目のナァコの唇が血に濡れていて、でも、怖いってよりとても綺麗で。
「わかった」
カッコいいとこ見せたくて、言ってみたら、また本当に採用されちゃったなって……あ、僕の人生、無駄じゃなかったって。
僕は精一杯の笑顔を作って、黒い仔猫を撫でてから、ゆっくりと目を閉じた。
<終>
化け猫