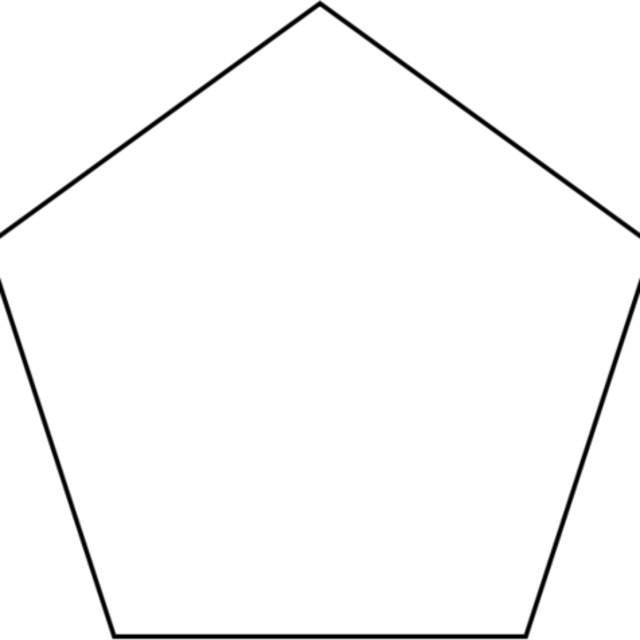妖刀事変
文字数 4,639文字
師は、かつて街で道場を開き、私に剣や、それ以外の様々なことを教えてくれた恩人である。今は加齢により師範を辞し、ここから数里ほど歩いた山中で、娘とともに暮らしている。彼の娘は、サエという。見た目はおしとやかで可憐な姿であるが、性格は苛烈であり、幼いころの私は毎日のように言い負かされ、服を涙で濡らしていた程である。
苛烈なのは性格だけではなく、剣の腕もだった。せめて、剣で勝てれば面目も立ったのだが、何分私は非力なもので、幾度挑んでも、勝てたのはただの一度、道場を私が辞す時だけであった。それも何度任されても挑み、剣の腕ではなく体力と気力で勝ち取った無様な勝利であったから、いつまでも、彼女には生きていて、唯一相手という印象が残っていた。
そういった印象もあって、妖刀に憑かれたと訊いても、私はいまいちぴんと来ていなかった。妖刀に憑かれたからと言って、あの娘が心を譲るわけがないと、どこかで思っていたのだろう。何があったのかを詳しく知るため、手紙を読み進める。
師、曰く、切欠は山中に迷い込んだ、旅商人を屋敷に招いたことだったという。随分、長い旅をしていたようで、服は擦り切れ、肌は痩せこけ、それは情けない姿をしていたそうな。師もサエも心根は優しい人たちであるから、数日の間、世話をしてやることにした。
やがて旅人は精気を取り戻し、屋敷を出ていったが、その際お礼として置かれていったのが、件の妖刀だったという。師は既に剣を置いた身。サエがそれを受け取ることとなった。その翌晩から、サエが狂い始めたのだと言う。
サエは手を入れた食物に手を付けなくなり、昼間、寝込むことが多くなった。病かとも思い薬も飲ませてみたが、一向に容態は良くならず。どうしたものかと師が頭を抱えていること数日。夜半に、けもののような鳴き声が聞こえて、師は目覚めた。冬の蓄えに失敗した獣が、食事を求め降りてきたのか。警戒しながら、師が声の方に向かうと、そこには手に持った刀で獣の首を狩り、血をすすり肉をはむ、サエの姿があった。
二日ほどの時をかけて私は体を清め、いくつか道具を持ち、家を出た。道中の食事と師匠への手土産に、日持ちの良い根菜の類や、毒抜きをし、塩漬けにした梅の実、蓄えていた干物も供に持つ。冬の寒さが身にしみた。しかし、師はこれよりも厳しい、心の寒さに震えているだろう。足取りは早かった。
途中、凍りついた山河を眼にした。覗き込むと、氷の下を泳ぐ、赤、黒、白、大小そろった魚が見えた。普段よりも、数が多い。原因は、すぐにわかった。山中に進むに連れ、彼らを狩る山犬や、熊の死体が散見されたのだ。寒さのせいか、血は殆ど流れておらず、腐臭もなかった。私は手を合わせ、師の屋敷へ急いだ。
戸をあけるなり、師は頭を下げて言った。痩せこけている。奥方に先立たれ、残された娘にも異変が訪れ、恐らくここ数日、ろくに食事も採っていないのだろう。挨拶もそこそこに、私は家から運んできた土産を手渡した。
「お受け取りください、御師様。冬の蓄えに、と思ったのですが、少々、気を入れて作りすぎてしまったものです。心労で、喉が狭くなっているのはわかります。しかし、今の姿を娘様が見られたら、大変驚きになるでしょう。これを食べて、少しでも精を取り戻して下さい。」
遮るものや、距離をある程度無視して、邪な力を見て取れる。それが、幼き頃から私に宿った、特殊な力だった。非力で剣の腕の立たぬ私が、こうして師に呼び寄せられたのも、この力が原因であろう。白くぼやけた息を弾ませ、中へ入る。不謹慎であるとは思うが、自らの力が師の役に立つと思うと、わずかに心に陽が射すのも、また隠せぬことだった。
しかし、そんな気分も、中の様子を見ると吹き飛んだ。サエは鎖によって、真中の最も太い柱につながれている。服は乱れ、ところどころに血の跡が見える。押さえつける際に、師が付けた傷かもしれない。足元には、彼女がちぎったのだろう、荒縄が散らばっていた。いくら彼女が強いとは言え、異常な力だ。夜毎暴れているのだろう、鎖に削られ、柱も細くなりつつある。
今は昼。大人しくなっていることを確認し、近づく。睨みつけては来るが、それ以上のことはされない。服をずらし、体の様子を見ていった。陽に当たっていないせいか、肌は透き通るように白い。その肌に、噛まれたような傷があるのが見えた。
師から旅人の身なりを聞き、私は屋敷を出た。道中に見た、獣の死体のもとへ戻る。どの獣にも、サエの体に残っていたものと同じ、噛まれたような跡があった。あの旅人が、付けたものだと思った。死体の作る道を、私は辿った。
男はよろめきながらも、刀を躰から抜き、私と向き合った。唇の隙間から、以上に伸びた犬歯が見える。サエと動物に残った噛み跡を、思い出した。影の付かぬ躰、そして心臓を突かれても死なぬ生命力。見当どおり、西洋で言う、吸血鬼と呼ばれる怪異だと、私は確信した。
おおよその、筋道は掴んでいた。恐らくこの男は吸血鬼となった自分を自覚し、自我を保つため、あの刀を手に入れた。しかし、それで防げるほど、魔の力は甘くはない。限界が来た彼は、人里を離れ山へ入った。いずれ躰が朽ちることを待って。彼の不幸は、入った山に同じく人里を離れた、我が師とその娘がいたことだ。
彼は抗おうとしたのだろう。だが、最後には本能に勝てず、娘に手を出してしまった。抵抗の様子がなかったことを見るに、寝静まった頃、血を頂いた。刀を召し上げたのは、せめてもの償いのつもりだったのかもしれない。今は聞くことも出来ないが、私はそうだと信じたかった。
剣の腕が断たぬ私でも、とどめを刺すのは容易だった。首を切り、その身を木陰から引きずり出す。朝になれば、陽の光が彼を天に誘うだろう。その前に、血と、幾つかの臓物を貰い受けた。吸血鬼の躰は、霊薬の材料になる。吸血鬼に噛まれてからさほど経っていないならば、治療薬を作ることも、不可能ではないはずだ。
師には言わなかったが、礼ならばしっかりと貰い受けている。私の腰には、来たときよりも一つ多く、刀が下げられていた。旅人が持ってきたという妖刀、正しくは魔除けの刀だ。私のこれからの仕事は、また一層楽になるだろう。
凍った川に立ち寄った。相変わらず、魚達は所狭しと、小さな川の中を泳ぎ回っている。とん、とんと表面を叩き、丸い穴を開けた。棒、糸、針を組み合わせた即席の釣り竿を、開いた穴へ向ける。これだけ数がいるのだ。師にあげた分の魚くらい、すぐに取れるだろう。