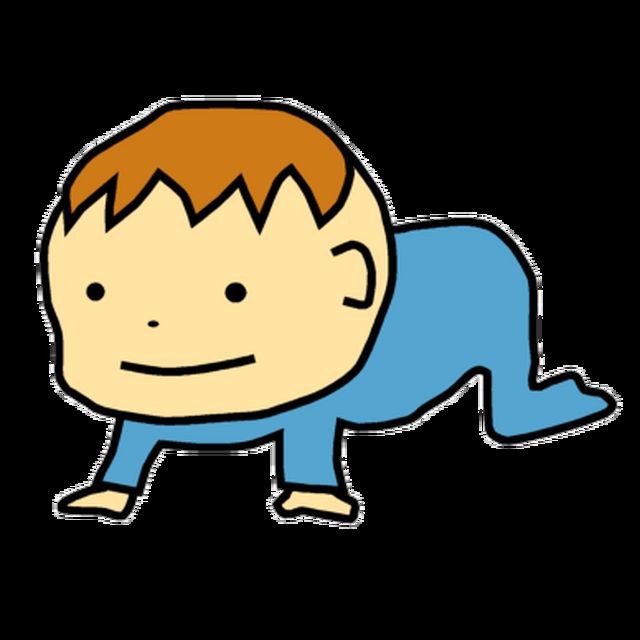第8話
文字数 2,776文字
三日後に現場に戻ってくると、僕らは目を疑った。彼女の予想した通り、そこには松の木が生えていた。が、それは驚いたことに子供の背丈ほどの高さに成長していた。一本立ちの幹の太さは、大人の男性の腕ほどもある。たまちゃんたちはその木を見て興奮気味に枝を揺らしたり、目を煌めかせて葉を眺めたり、ラッパを吹いたりしている。たいそう嬉しいらしい。池田さんも興奮気味に言う
「驚いたわ! 不思議ね! なんだか昔話みたいね。本来、死体の周りの植物は栄養が過剰になって枯れるらしいのだけど。」
実際、周りの雑草は萎れていた。その松の木だけが薄暗い森の中で、細い葉をピンと張り、威勢よく枝を伸ばしている。たまちゃんたちが何かに取り憑かれたように、めちゃくちゃなメロディーを奏でるので僕はいつものようにお面を外した。それを見て池田さんが問う。
「どうしたの?」
僕はたまちゃんたちの状況を説明した。
「じゃあたぶんこれはやっぱり目玉たちの仕業なのね。これからどうなるのか楽しみだわ。きっと何か意図があると思う」
ちなみにこの松の木を、鬼のお面を通して見ると、普通より目玉が多く見えた。その目玉たちも特に活発にキョロキョロしている。生命力に溢れている雰囲気がある。大小の目玉が重なり合い、ひしめいているのだ。
その日以降、僕らはたまにこの松の木を見に森へとやって来た。梅雨の雨で、松の木は狂ったように成長し、ひと月後には子供では幹に手が回せないほど立派になった。高さは小学校の校舎くらいだろう。
不思議なことにその松の木の周りは木々か傾き、松の木の樹冠にそって、ポッカリと光の空間ができていた。落葉広葉樹の森に、大きな松が一本だけで屹立する姿は、明らかな異常さを感じる。僕は松の細い葉を眺めてつぶやく。
「松の葉って明らかに光合成の効率が悪いよね。なんで今まで絶滅しなかったのかな」
池田さんは松の梢を見上げて言う。
「そのほうが寒冷地では有利なんですって。表面積を小さくした方が低い気温の影響を受けづらいから。象の耳が大きいのは温度を逃がすためでしょ。その反対ね」
松の幹の樹皮は象の皮膚のように粗く、もう何年もそこで生きているように、深い凹凸が刻まれていた。触ると湿った梅雨の空気を吸い込んでいて、しっとりとした弾力があった。
さて、梅雨の明けたある日、その日も僕らは森に来ていた。松はますます太く、高く成長している。僕らは松の木の根本で、どうでもいい話しをしていた。森中に響く、騒がしい蝉の鳴き声で、池田さんの声はよく聞こえなかった。
そんな中、たまちゃん達は何か相談をするように一箇所に身を寄せて、松の木の一点を見ていた。僕らが話している間、ずっとホバリングして同じ場所でそうしていた。あまり真剣に木を見ているので何かあるのかと思い、僕は彼らの見ている場所を観察してみた。しかし、そこには普通と変わらない、樹脈の刻まれた松の樹皮しかなかった。
僕は一応その周辺のいくつかの部分を観察したが、やはり何もなかった。それで僕はたまちゃんたちが何を見てるのか知るために、彼らに顔を寄せて彼らの見ている位置から見てみようとした。すると僕に場所をあけ渡すように、たまちゃんたちはその場所を横に移動した。僕は彼らのいた位置から樹皮を覗いた。そこには何かが白く光っているのが見えた。よく見るとその光の中には赤い四辺形が見える。建物の屋根に見えた。
「大松台小学校の屋根に似てるな」と思った次の瞬間、白い光は僕を包んだ。振り向くと、池田さんの顔が見えた気がした。気のせいかもしれない。よく分からなかった。とりあえずもう一度前方に視線を向けると、上の方に赤い屋根がある気がする。これも気のせいだったかもしれない。光の中で一瞬、一瞬が記憶に変わる度に他の一瞬に差し替えられていくような、奇妙な感覚に飲み込まれていった。すべてが気のせいだったみたいに。
その奇妙な感覚が終わると、僕はさっき見えた(気がした)建物の前にいた。僕はその建物の門の前に立っているらしい。周りには誰もいなかった。遠くから蝉の鳴き声と、子供たちが騒ぐ声がする。
門には「亀山小学校」と書いてあった。「大松台小学校」にとてもよく似ている。振り返ると見慣れた橋が見える。池田さんと猫たちに餌やりをしていた場所だ。
ぼーっと立ちつくしていると、たまちゃんたちが僕の前を通り過ぎた。彼らは僕を横目で見ながら進んでいった。ひとまず僕は彼らについていくことにした。たまちゃんたちは川沿いの道を川上に向かって飛んでいき、住宅街に入っていった。どうやら元の世界での僕の自宅に向かっているようだ。街の家並みは全く変わっていなかったし、家も同じ場所にあった。たまちゃんたちは家の前で振り返って僕を待っているので、玄関のドアに鍵を差し込み回してみた。ドアは案の定開いた。
たまちゃんたちは当然のように僕の部屋に入っていった。僕も続いて部屋に入ると、元の世界と全く同じ部屋だった。本棚の本も、写真立ての写真も、鏡に映る僕の姿も全て元の世界のそれだった。僕は一応机の引き出しなども開けて確認したが、変わったものはなかった。空になった竹籠は窓際に短い影を落としていた。
ふと気がつくと、たまちゃんたちはいなくなっていた。どこに行ったのかと家の中を探していると、彼らは玄関のドアの前にいた。僕がドアを開けてやると、外へ出ていった。首を(というか目を)捻って僕を確認しながら、ゆっくりと飛んでいく。来たときと同じように、また僕も彼らを追った。
彼らの向かった先は、元の世界の大松台小学校のあった場所だった。そこには小学校はなかったが、代わりに森があった。立看板には大松の森と書いてある。大松というのは、例の建校時に切り倒されたという松の木だろうか。
目玉達は看板を通り過ぎ、森の中に入っていった。森の入口付近は蛇行した登り坂になっている。一応杭のようなものにロープが渡され道が作られていた。その道をたまちゃんたちは飛んでいく。
だんだんと傾斜はなだらかになってきた。森のたいていの木は落葉広葉樹で、薄い葉が日光を透かしている。平坦な道を数十分進むと、道が太くなり、二股に別れている。そしてその中央に、他の広葉樹とは明らかに異質な、大きな大きな黒松が立っていた。その先は下り坂になっている。だからここは大松台小学校でいえば、一番奥、つまり裏門にあたる位置だろう。
たまちゃんたちはその松の枝に立ち、誇らしげに僕を見下ろした。そして人の腰回り程もある枝に腰掛け、ラッパを鳴らす。やはり3匹ともめちゃくちゃなリズムでラッパを吹き鳴らす。しかし僕は今日の演奏は聴いてやることにし、目を閉じて彼らの演奏に耳を傾けた。
僕が帰っても、たまちゃんたちはもう着いてこなかった。彼らはずっとあの森の松の太い枝に腰掛けている。
「驚いたわ! 不思議ね! なんだか昔話みたいね。本来、死体の周りの植物は栄養が過剰になって枯れるらしいのだけど。」
実際、周りの雑草は萎れていた。その松の木だけが薄暗い森の中で、細い葉をピンと張り、威勢よく枝を伸ばしている。たまちゃんたちが何かに取り憑かれたように、めちゃくちゃなメロディーを奏でるので僕はいつものようにお面を外した。それを見て池田さんが問う。
「どうしたの?」
僕はたまちゃんたちの状況を説明した。
「じゃあたぶんこれはやっぱり目玉たちの仕業なのね。これからどうなるのか楽しみだわ。きっと何か意図があると思う」
ちなみにこの松の木を、鬼のお面を通して見ると、普通より目玉が多く見えた。その目玉たちも特に活発にキョロキョロしている。生命力に溢れている雰囲気がある。大小の目玉が重なり合い、ひしめいているのだ。
その日以降、僕らはたまにこの松の木を見に森へとやって来た。梅雨の雨で、松の木は狂ったように成長し、ひと月後には子供では幹に手が回せないほど立派になった。高さは小学校の校舎くらいだろう。
不思議なことにその松の木の周りは木々か傾き、松の木の樹冠にそって、ポッカリと光の空間ができていた。落葉広葉樹の森に、大きな松が一本だけで屹立する姿は、明らかな異常さを感じる。僕は松の細い葉を眺めてつぶやく。
「松の葉って明らかに光合成の効率が悪いよね。なんで今まで絶滅しなかったのかな」
池田さんは松の梢を見上げて言う。
「そのほうが寒冷地では有利なんですって。表面積を小さくした方が低い気温の影響を受けづらいから。象の耳が大きいのは温度を逃がすためでしょ。その反対ね」
松の幹の樹皮は象の皮膚のように粗く、もう何年もそこで生きているように、深い凹凸が刻まれていた。触ると湿った梅雨の空気を吸い込んでいて、しっとりとした弾力があった。
さて、梅雨の明けたある日、その日も僕らは森に来ていた。松はますます太く、高く成長している。僕らは松の木の根本で、どうでもいい話しをしていた。森中に響く、騒がしい蝉の鳴き声で、池田さんの声はよく聞こえなかった。
そんな中、たまちゃん達は何か相談をするように一箇所に身を寄せて、松の木の一点を見ていた。僕らが話している間、ずっとホバリングして同じ場所でそうしていた。あまり真剣に木を見ているので何かあるのかと思い、僕は彼らの見ている場所を観察してみた。しかし、そこには普通と変わらない、樹脈の刻まれた松の樹皮しかなかった。
僕は一応その周辺のいくつかの部分を観察したが、やはり何もなかった。それで僕はたまちゃんたちが何を見てるのか知るために、彼らに顔を寄せて彼らの見ている位置から見てみようとした。すると僕に場所をあけ渡すように、たまちゃんたちはその場所を横に移動した。僕は彼らのいた位置から樹皮を覗いた。そこには何かが白く光っているのが見えた。よく見るとその光の中には赤い四辺形が見える。建物の屋根に見えた。
「大松台小学校の屋根に似てるな」と思った次の瞬間、白い光は僕を包んだ。振り向くと、池田さんの顔が見えた気がした。気のせいかもしれない。よく分からなかった。とりあえずもう一度前方に視線を向けると、上の方に赤い屋根がある気がする。これも気のせいだったかもしれない。光の中で一瞬、一瞬が記憶に変わる度に他の一瞬に差し替えられていくような、奇妙な感覚に飲み込まれていった。すべてが気のせいだったみたいに。
その奇妙な感覚が終わると、僕はさっき見えた(気がした)建物の前にいた。僕はその建物の門の前に立っているらしい。周りには誰もいなかった。遠くから蝉の鳴き声と、子供たちが騒ぐ声がする。
門には「亀山小学校」と書いてあった。「大松台小学校」にとてもよく似ている。振り返ると見慣れた橋が見える。池田さんと猫たちに餌やりをしていた場所だ。
ぼーっと立ちつくしていると、たまちゃんたちが僕の前を通り過ぎた。彼らは僕を横目で見ながら進んでいった。ひとまず僕は彼らについていくことにした。たまちゃんたちは川沿いの道を川上に向かって飛んでいき、住宅街に入っていった。どうやら元の世界での僕の自宅に向かっているようだ。街の家並みは全く変わっていなかったし、家も同じ場所にあった。たまちゃんたちは家の前で振り返って僕を待っているので、玄関のドアに鍵を差し込み回してみた。ドアは案の定開いた。
たまちゃんたちは当然のように僕の部屋に入っていった。僕も続いて部屋に入ると、元の世界と全く同じ部屋だった。本棚の本も、写真立ての写真も、鏡に映る僕の姿も全て元の世界のそれだった。僕は一応机の引き出しなども開けて確認したが、変わったものはなかった。空になった竹籠は窓際に短い影を落としていた。
ふと気がつくと、たまちゃんたちはいなくなっていた。どこに行ったのかと家の中を探していると、彼らは玄関のドアの前にいた。僕がドアを開けてやると、外へ出ていった。首を(というか目を)捻って僕を確認しながら、ゆっくりと飛んでいく。来たときと同じように、また僕も彼らを追った。
彼らの向かった先は、元の世界の大松台小学校のあった場所だった。そこには小学校はなかったが、代わりに森があった。立看板には大松の森と書いてある。大松というのは、例の建校時に切り倒されたという松の木だろうか。
目玉達は看板を通り過ぎ、森の中に入っていった。森の入口付近は蛇行した登り坂になっている。一応杭のようなものにロープが渡され道が作られていた。その道をたまちゃんたちは飛んでいく。
だんだんと傾斜はなだらかになってきた。森のたいていの木は落葉広葉樹で、薄い葉が日光を透かしている。平坦な道を数十分進むと、道が太くなり、二股に別れている。そしてその中央に、他の広葉樹とは明らかに異質な、大きな大きな黒松が立っていた。その先は下り坂になっている。だからここは大松台小学校でいえば、一番奥、つまり裏門にあたる位置だろう。
たまちゃんたちはその松の枝に立ち、誇らしげに僕を見下ろした。そして人の腰回り程もある枝に腰掛け、ラッパを鳴らす。やはり3匹ともめちゃくちゃなリズムでラッパを吹き鳴らす。しかし僕は今日の演奏は聴いてやることにし、目を閉じて彼らの演奏に耳を傾けた。
僕が帰っても、たまちゃんたちはもう着いてこなかった。彼らはずっとあの森の松の太い枝に腰掛けている。