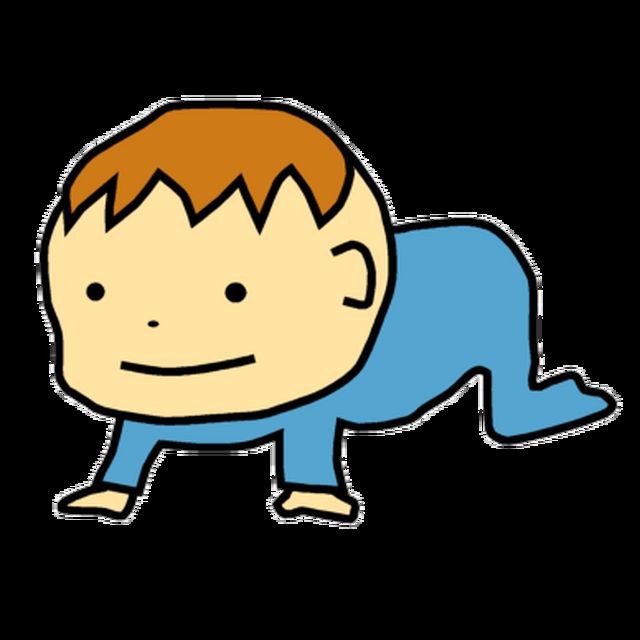第4話
文字数 2,892文字
尾行を始めてから、一週間程たったある日。その日の空はくすんだ白い雲に覆われ、点々と灰色に滲んでいた。
放課後池田さんはいつものように図書室へ行った。今日の彼女はいつもより落ち着きがないように見えた。いつもと変わらない表情だが、何度も脚を組み替えたり、時計を見たりしている。また、廊下側に体を向けて座っていた。彼女は小一時間図書室で本を読んでから学校を出た。いつもより少々早い。
やはりどこか様子がおかしい。ソワソワとした足取りで坂を下り、川沿いを進んでいく。
橋の下まで来ると「おーい」と今日は陽気に猫を呼んだ。その日もいつもと変わらず、三毛猫は橋の影からやってきた。僕はこの日もイチョウの幹に隠れていた。池田さんは普段と変わらず餌を与えた。
でもその後の行動が違った。餌やりを終えると猫を抱きかかえて、どこかへ向かった。
彼女は木の影に隠れる僕のすぐ前を通り過ぎた。何かを警戒するように小走りで。でも彼女が真っすぐ前をみて走っていったので見つからずにすんだ。僕も彼女を追いかけた。彼女は橋の先の亀山池の森に入っていった。
池田さんは少し肩を竦めるようにして、森の小道を小走りで抜けていく。10分ほど行ったところに池があり、その池の周りを反時計回りに進んでいく。ある程度進んだところで、何かを探すように彼女は周りを見回す。丁度いい場所を探しているように見える。
手頃な場所を見つけたのか、小道を外れて枯れ葉の堆積した踏み分け道に入った。それから細い道が二股に分かれたところの茂みの裏に回って、猫を抱いたまま身をかがめる。僕は、池の辺の大きな広葉樹に身を隠す。そこからは彼女の横顔が見える。
彼女は猫を地面に寝かせた。次に左手で猫を抑えて、右手で何かを振り上げた。手に握られたものが、梢から差す光に小さく閃いた。刃物か。そして振り上げた右手を、地面に勢いよく振り下ろした。鈍い衝撃音と猫の短い鳴き声が聞こえた。たまちゃんが興味深げに近づいて行き、池田さんの側でホバリングし、様子を観察している。
彼女はしゃがんだまま何度か刃物を振り下ろした。耳を済ましても彼女の声は聞こえない。聞こえるのは疎らなセミの鳴き声と、彼女の右腕が反復する度に聞こえる濁音だけだ。
そのあとも、ときどき辺りを注視しながら、数分間にわたって何か作業をしていた。そして立ち上がると、猫のいる地面を見下ろし微笑んだ。そして来た道を引き返していった。僕は森の入口に消えていく彼女を見送った。それから彼女の作業していた場所に来てみた。
彼女のいた位置には落ち葉が小さく盛られていた。その周辺には黒いシミが飛び散っていた。盛り上がった落ち葉を手でかき分けると、そこには無惨な猫の死体が横たわっていた。地面は血が染み込んでぬかるんでいる。
猫は首と胴体を切断されていた。胴のほうはお腹から胸まで不器用に何度も切り裂かれている。内臓はすべて取り出されていて猫の周りに転がっている。空っぽのお腹からは赤い皮膚や骨が見えた。
頭は叩き割られていた。そこから脳がはみ出て、何かで半分潰されている。そして瞼は閉じられ、開かれた口からは細く鋭い犬歯と、丁寧にしまわれた小さな舌が見える。
たまちゃんは地面に降りてきて、なぜかパタパタと手を振っている。僕はふと彼女が川辺りで猫を抱きかかえていた顔を思い出した。ここで猫を見下ろしていた表情と全く同じだった。どちらの彼女も微笑んでいたのだ。
何が楽しくてこんなことをするのか? スカスカなことと関係があるのか?
でも僕はこの調査が大きく進展していると実感していた。また、偶然にもこのような光景を見てしまったからには、僕には彼女を止める責任がある気がした。
明日池田さんと話してみよう。
翌日、彼女はいつも通りの様子で登校してきて、呑気な顔で授業を受けた。どことなく楽しそうにすら見えた。僕が言うのもなんだが鬼畜である。
その日も彼女は図書室へ行った。本を読みながら、ときどき宙を見つめていた。それから図書室を後にし、裏門をくぐり出た。
門の先の坂道を下る池田さんに、僕は後ろから声をかけた。
「い、池田さん。あの、今日は猫に餌をやらないのかな」
恥ずかしいことに、声が上ずってしまった。一方、彼女は僕に背を向けたまま首をかしげると、一瞬間を置いて振り返り、眉根を寄せ、瞳をギロリと僕に向けて言った。
「やらないけど。もしかして、ストーカーかな? 瀬津くんだっけ? 君、いい趣味を持ってるね」
間近で見る彼女はとても大きく見えた。おそらく僕より小さいのだろうけど。僕は視線を逸らした。
「まあ、似たようなものかな。はは… 昨日さあ…」
彼女は手のひらを僕に向けて言葉を制す。そして横目で僕を見やり、少し俯いて不機嫌そうに言う。
「昨日のことも見ていたの?」
僕は正直に答える。敵意がないことも添えて。
「う、うん。でも昨日のことは誰にも言わないからさ、安心して。ただ僕は… なんというか… どうしてあんなことをしたのか知りたいだけなんだ」
いざ彼女を前にしてみると言葉がうまく出てこない。彼女が問う。
「そんなこと聞いてどうするの」彼女は少し思案してから、それでも平然とした態度で続ける。「まあでも別に教えてあげてもいいよ。そうだな。簡単に言うと、あの子たちは死にたがってたのよ。わたしは、なんとなくそういうのが分かるの。きっと自分もそうだからね。だから殺してあげたの。悪い?」
そう言って前を向くと、彼女はまた来た道を歩きだした。僕も彼女の横について歩く。
はっきりしたことはまだ分からないが、どうやらスカスカの者たちは、みな死にたがっているらしい。僕は少し考えてから答える。
「それなら別に悪いとは思わない」
彼女は鼻で笑ってから言う。
「あなた意外と話が通じるね」
僕も苦笑する。
「そうかな。僕はね、実は鬼の子孫なんだ」
彼女は空を見上げて、小さな笑い声をあげた。
「ははは。それ面白い」
僕は少し、彼女の心の中に踏み込んでみる。
「じゃあさ、なぜ君は死なないんだい?」
「単純なことだね。わたしは自分が好きだから」
「そっか。変なこと聞いてごめんね」僕はつづけて本題を切り出す。「ところで僕たち友だちにならない?」
池田さんは目を細めて問う。
「なんで?」
僕は考えて来た言葉をどうにか伝える。
「うん。ちょっとまた失礼だけど、池田さんは友達もあまりいないみたいだし、いつも1人でいるから、変なこと考えちゃうんだと思う。だからさ、本ばかり読んでないで、他になにか楽しいことしようよ」
「うん。まあ、いいよ。あなたは、それなりに話が通じそうだし」
僕はお礼を言って、付け足す。
「僕もね、結構読書家なんだよ。だからさ、おもしろい本を教えてよ」
実際、僕は読書家だ。もちろん児童書ばかりだが、小学生なので当然だろう。彼女が読書家なのも知っている。趣味を共有すれば、距離も縮まるだろう。
趣味と言えば僕はこの頃、縄跳びに熱中していた。だから彼女を縄跳びに誘ってみた。
彼女は少し怪訝そうな顔をしたが、それでも頷いてくれた。それでこの後ふたり、公園で縄跳びをした。
このように、僕らは友達になった。
放課後池田さんはいつものように図書室へ行った。今日の彼女はいつもより落ち着きがないように見えた。いつもと変わらない表情だが、何度も脚を組み替えたり、時計を見たりしている。また、廊下側に体を向けて座っていた。彼女は小一時間図書室で本を読んでから学校を出た。いつもより少々早い。
やはりどこか様子がおかしい。ソワソワとした足取りで坂を下り、川沿いを進んでいく。
橋の下まで来ると「おーい」と今日は陽気に猫を呼んだ。その日もいつもと変わらず、三毛猫は橋の影からやってきた。僕はこの日もイチョウの幹に隠れていた。池田さんは普段と変わらず餌を与えた。
でもその後の行動が違った。餌やりを終えると猫を抱きかかえて、どこかへ向かった。
彼女は木の影に隠れる僕のすぐ前を通り過ぎた。何かを警戒するように小走りで。でも彼女が真っすぐ前をみて走っていったので見つからずにすんだ。僕も彼女を追いかけた。彼女は橋の先の亀山池の森に入っていった。
池田さんは少し肩を竦めるようにして、森の小道を小走りで抜けていく。10分ほど行ったところに池があり、その池の周りを反時計回りに進んでいく。ある程度進んだところで、何かを探すように彼女は周りを見回す。丁度いい場所を探しているように見える。
手頃な場所を見つけたのか、小道を外れて枯れ葉の堆積した踏み分け道に入った。それから細い道が二股に分かれたところの茂みの裏に回って、猫を抱いたまま身をかがめる。僕は、池の辺の大きな広葉樹に身を隠す。そこからは彼女の横顔が見える。
彼女は猫を地面に寝かせた。次に左手で猫を抑えて、右手で何かを振り上げた。手に握られたものが、梢から差す光に小さく閃いた。刃物か。そして振り上げた右手を、地面に勢いよく振り下ろした。鈍い衝撃音と猫の短い鳴き声が聞こえた。たまちゃんが興味深げに近づいて行き、池田さんの側でホバリングし、様子を観察している。
彼女はしゃがんだまま何度か刃物を振り下ろした。耳を済ましても彼女の声は聞こえない。聞こえるのは疎らなセミの鳴き声と、彼女の右腕が反復する度に聞こえる濁音だけだ。
そのあとも、ときどき辺りを注視しながら、数分間にわたって何か作業をしていた。そして立ち上がると、猫のいる地面を見下ろし微笑んだ。そして来た道を引き返していった。僕は森の入口に消えていく彼女を見送った。それから彼女の作業していた場所に来てみた。
彼女のいた位置には落ち葉が小さく盛られていた。その周辺には黒いシミが飛び散っていた。盛り上がった落ち葉を手でかき分けると、そこには無惨な猫の死体が横たわっていた。地面は血が染み込んでぬかるんでいる。
猫は首と胴体を切断されていた。胴のほうはお腹から胸まで不器用に何度も切り裂かれている。内臓はすべて取り出されていて猫の周りに転がっている。空っぽのお腹からは赤い皮膚や骨が見えた。
頭は叩き割られていた。そこから脳がはみ出て、何かで半分潰されている。そして瞼は閉じられ、開かれた口からは細く鋭い犬歯と、丁寧にしまわれた小さな舌が見える。
たまちゃんは地面に降りてきて、なぜかパタパタと手を振っている。僕はふと彼女が川辺りで猫を抱きかかえていた顔を思い出した。ここで猫を見下ろしていた表情と全く同じだった。どちらの彼女も微笑んでいたのだ。
何が楽しくてこんなことをするのか? スカスカなことと関係があるのか?
でも僕はこの調査が大きく進展していると実感していた。また、偶然にもこのような光景を見てしまったからには、僕には彼女を止める責任がある気がした。
明日池田さんと話してみよう。
翌日、彼女はいつも通りの様子で登校してきて、呑気な顔で授業を受けた。どことなく楽しそうにすら見えた。僕が言うのもなんだが鬼畜である。
その日も彼女は図書室へ行った。本を読みながら、ときどき宙を見つめていた。それから図書室を後にし、裏門をくぐり出た。
門の先の坂道を下る池田さんに、僕は後ろから声をかけた。
「い、池田さん。あの、今日は猫に餌をやらないのかな」
恥ずかしいことに、声が上ずってしまった。一方、彼女は僕に背を向けたまま首をかしげると、一瞬間を置いて振り返り、眉根を寄せ、瞳をギロリと僕に向けて言った。
「やらないけど。もしかして、ストーカーかな? 瀬津くんだっけ? 君、いい趣味を持ってるね」
間近で見る彼女はとても大きく見えた。おそらく僕より小さいのだろうけど。僕は視線を逸らした。
「まあ、似たようなものかな。はは… 昨日さあ…」
彼女は手のひらを僕に向けて言葉を制す。そして横目で僕を見やり、少し俯いて不機嫌そうに言う。
「昨日のことも見ていたの?」
僕は正直に答える。敵意がないことも添えて。
「う、うん。でも昨日のことは誰にも言わないからさ、安心して。ただ僕は… なんというか… どうしてあんなことをしたのか知りたいだけなんだ」
いざ彼女を前にしてみると言葉がうまく出てこない。彼女が問う。
「そんなこと聞いてどうするの」彼女は少し思案してから、それでも平然とした態度で続ける。「まあでも別に教えてあげてもいいよ。そうだな。簡単に言うと、あの子たちは死にたがってたのよ。わたしは、なんとなくそういうのが分かるの。きっと自分もそうだからね。だから殺してあげたの。悪い?」
そう言って前を向くと、彼女はまた来た道を歩きだした。僕も彼女の横について歩く。
はっきりしたことはまだ分からないが、どうやらスカスカの者たちは、みな死にたがっているらしい。僕は少し考えてから答える。
「それなら別に悪いとは思わない」
彼女は鼻で笑ってから言う。
「あなた意外と話が通じるね」
僕も苦笑する。
「そうかな。僕はね、実は鬼の子孫なんだ」
彼女は空を見上げて、小さな笑い声をあげた。
「ははは。それ面白い」
僕は少し、彼女の心の中に踏み込んでみる。
「じゃあさ、なぜ君は死なないんだい?」
「単純なことだね。わたしは自分が好きだから」
「そっか。変なこと聞いてごめんね」僕はつづけて本題を切り出す。「ところで僕たち友だちにならない?」
池田さんは目を細めて問う。
「なんで?」
僕は考えて来た言葉をどうにか伝える。
「うん。ちょっとまた失礼だけど、池田さんは友達もあまりいないみたいだし、いつも1人でいるから、変なこと考えちゃうんだと思う。だからさ、本ばかり読んでないで、他になにか楽しいことしようよ」
「うん。まあ、いいよ。あなたは、それなりに話が通じそうだし」
僕はお礼を言って、付け足す。
「僕もね、結構読書家なんだよ。だからさ、おもしろい本を教えてよ」
実際、僕は読書家だ。もちろん児童書ばかりだが、小学生なので当然だろう。彼女が読書家なのも知っている。趣味を共有すれば、距離も縮まるだろう。
趣味と言えば僕はこの頃、縄跳びに熱中していた。だから彼女を縄跳びに誘ってみた。
彼女は少し怪訝そうな顔をしたが、それでも頷いてくれた。それでこの後ふたり、公園で縄跳びをした。
このように、僕らは友達になった。