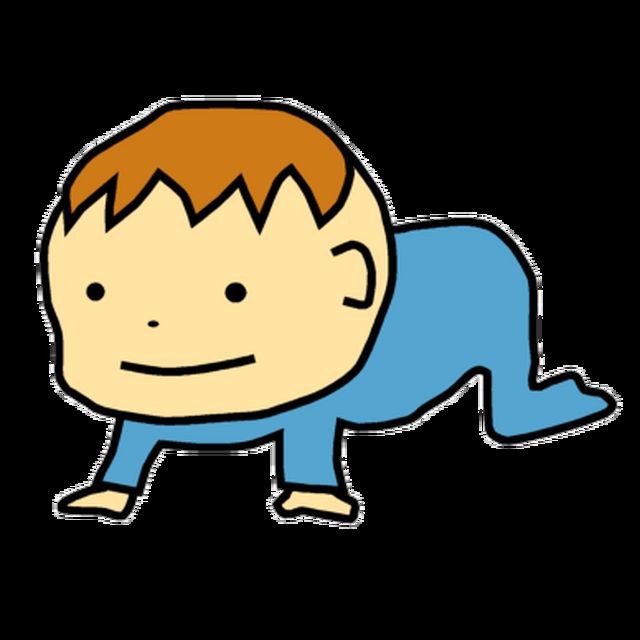第6話
文字数 2,342文字
この頃、池田さんが猫に餌を与えていた橋の下に、新しく猫の親子が住み始めた。彼女はその猫たちにも餌やりをしたいという。それで6月初旬のよく晴れた日、僕らは猫の餌を買いに、二人で商店街のスーパーマーケットにやって来た。
スーパーマーケットは商店街に入ってすぐの位置にある。入口の上部には大きく「スーパー越後屋」と書いてある。その隣にはにこやかな表情をしたパンダのキャラクターが描かれている。
入店すると彼女は、一直線に目的の缶詰の売り場へとむかった。かなり通い慣れているらしい。そこで池田さんは陳列棚を物色する。そのうちに彼女はカニ味噌の缶を手に取り言う。
「カニ味噌って何なのかな」
僕は答える。
「なんだろうね。たぶん内臓か脳だろうね」
「いくらかしら」
「趣味が悪いね。このサバ缶の方が美味しいし、安いよ」
「イワシ缶の方が安いわ。私はいつも猫にイワシ缶をやっていたのよ。小さいし与えやすいし」
「そういえば君はいつから猫に餌やりをしていたんだい」
「三年生のときだったから、2年くらい前ね。みんな死んでしまったけど」
小声で僕は問う。
「また次の猫たちも死んでしまうのかな」
彼女は「死なないと思う、なぜなら今度のは純粋な慈善活動だからだ」と言った。また街にネズミが出ないようにするためだとも言った。彼女は言う。
「猫に餌をやるのを悪く言う人がいるけど、そういう人は街がネズミだらけになるのを望んでいるのかしらね。わたしは猫のほうがマシだと思うけど」
賛否はあるにせよ、彼女が慈善活動を行うようになるとは、嬉しいかぎりだ。このまま真人間になってくれればいいのだが。
彼女は缶詰を持ってレジに並んだ。そこで今度は将来の夢について語ってくれた。
「わたし、本当に動物が好きなの。将来は獣医になりたいな。外科がいいかな」
「素敵な夢だね。なぜそんなに動物が好きなんだい?」
「なぜかしらね」彼女は斜め上を見る。そして首を傾げて言う。「動物が好きというより、ヒトが嫌いなのかもしれない」
「なるほど」
池田さんは何度か小さく頷いた。
会計をすませスーパーマーケットを出ると、彼女が算数のノートを買いたいと言うので僕らは文房具屋に向かった。文房具屋は商店街の反対側の端にある。
僕らが商店街の通りを歩いていると、横断幕の掲げられた交差点に、賑やかな人だかりが出来ていた。人だかりの先には、若者が白い水兵のような衣装を来て管楽器を運び、なにか演奏の準備をしていた。僕らもなんとなく人だかりに混じってそれを見物することにした。
演奏が始まると、大きなラッパやリズミカルな太鼓の音が通りに響いた。僕に着いて来たたまちゃんたちも興奮した様子で、上空を行ったり来たりしていた。そのうち羽ばたきながら手をラッパにし、音を真似だした。そして行列の上を誇らしげに飛行しながら、ラッパを吹き鳴らした。
僕と池田さんが、背伸びをして前方を見ていると、前の大人たちが譲ってくれて、いつの間にか最前列で演奏を聴いていた。
演奏しているのは、おそらく高校生だろう。金色の管楽器が日差しに眩しく反射している。長袖のセーラー服のような衣装で、汗をかきながら懸命に演奏している。
たぶん本当はそんなに上手ではないのだろうけど、そのときの僕にはとても心地よく、飛び抜けて素晴らしい演奏に聞こえた。
商店街の空を見上げると、たまちゃんたちも、いつになく上機嫌な様子で演奏しながら飛び回っていた。でも実のところ、彼らの演奏は相当にデタラメなものだ。ぼくはそっと首から鬼のお面の紐を外した。そうすると目玉とともに音も消えるのだ。
池田さんは曲が終わる度に拍手を送っていた。僕は池田さんに聞いてみる。
「音楽は好き?」
「音楽が嫌いな人って、なかなかいないと思う」
僕らは小一時間演奏を聴いてから、文房具屋で買い物をし、猫の親子のいる橋に向かった。
向かう途中、たまちゃんたちはまだ手をラッパにして、さっき聴いた音楽を奏でていた。彼らの演奏はデタラメだと言ったが、よく聞くと音程は正しい。しかしリズムがめちゃくちゃなのだ。彼らはどうやら時間概念というものが僕らと異なるらしい。頭がおかしくなりそうなので、やはりお面の紐を首から外しておいた。
池田さん曰く、猫の親子は橋の下のスペースの端っこの隙間にいるらしい。ちょうどよい窪みになっており、その前は雑草が生えてるから風も防げる。以前、三毛猫もいた場所だ。
腰を屈めてその場所をのぞくと、灰色と黒の縞猫と子猫が3匹いた。子猫のうち二匹は親と同じような模様で一匹は黒猫だ。僕らを見ると親猫は警戒して尻尾を上げ威嚇し、鳴いた。あまり人に慣れた猫ではないようだ。
池田さんは手慣れたもので、親猫の前に缶詰を置き、もう1つの缶詰のイワシをスプーンでほぐして子猫の前に置いた。僕はそれを少し離れた位置から見ていた。
子猫はじゃれ合いながらでて来て、缶詰をベロベロ舐めた。親猫もつま先歩きで尻込みしながら出てきて、イワシを食べた。その様子を僕らは並んで観察した。
「とりあえず、今日のところは近づかない方がいいわ。まだ警戒している。特に子連れのメスは凶暴だから」
食べ終えると猫たちは橋の影に戻っていった。池田さんが缶を回収して、その日は解散した。
それから毎日池田さんは猫の親子に餌やりをした。僕もたいていは付き添った。猫たちは徐々に僕らに慣れてきて、そのうち池田さんが呼ぶと出てくるようになった。子猫たちは大変健康だ。餌を持っていくと、親猫の尻尾をはたいたり、背中に飛びついたりしながらやってきて、ぺろりと缶詰を平らげてしまう。
僕らはたまに抱きかかえてウロウロしたり、松ぼっくりを投げたり、猫じゃらしで遊んでやったりした。池田さんが動物が好きというのはどうやら本当らしい。
スーパーマーケットは商店街に入ってすぐの位置にある。入口の上部には大きく「スーパー越後屋」と書いてある。その隣にはにこやかな表情をしたパンダのキャラクターが描かれている。
入店すると彼女は、一直線に目的の缶詰の売り場へとむかった。かなり通い慣れているらしい。そこで池田さんは陳列棚を物色する。そのうちに彼女はカニ味噌の缶を手に取り言う。
「カニ味噌って何なのかな」
僕は答える。
「なんだろうね。たぶん内臓か脳だろうね」
「いくらかしら」
「趣味が悪いね。このサバ缶の方が美味しいし、安いよ」
「イワシ缶の方が安いわ。私はいつも猫にイワシ缶をやっていたのよ。小さいし与えやすいし」
「そういえば君はいつから猫に餌やりをしていたんだい」
「三年生のときだったから、2年くらい前ね。みんな死んでしまったけど」
小声で僕は問う。
「また次の猫たちも死んでしまうのかな」
彼女は「死なないと思う、なぜなら今度のは純粋な慈善活動だからだ」と言った。また街にネズミが出ないようにするためだとも言った。彼女は言う。
「猫に餌をやるのを悪く言う人がいるけど、そういう人は街がネズミだらけになるのを望んでいるのかしらね。わたしは猫のほうがマシだと思うけど」
賛否はあるにせよ、彼女が慈善活動を行うようになるとは、嬉しいかぎりだ。このまま真人間になってくれればいいのだが。
彼女は缶詰を持ってレジに並んだ。そこで今度は将来の夢について語ってくれた。
「わたし、本当に動物が好きなの。将来は獣医になりたいな。外科がいいかな」
「素敵な夢だね。なぜそんなに動物が好きなんだい?」
「なぜかしらね」彼女は斜め上を見る。そして首を傾げて言う。「動物が好きというより、ヒトが嫌いなのかもしれない」
「なるほど」
池田さんは何度か小さく頷いた。
会計をすませスーパーマーケットを出ると、彼女が算数のノートを買いたいと言うので僕らは文房具屋に向かった。文房具屋は商店街の反対側の端にある。
僕らが商店街の通りを歩いていると、横断幕の掲げられた交差点に、賑やかな人だかりが出来ていた。人だかりの先には、若者が白い水兵のような衣装を来て管楽器を運び、なにか演奏の準備をしていた。僕らもなんとなく人だかりに混じってそれを見物することにした。
演奏が始まると、大きなラッパやリズミカルな太鼓の音が通りに響いた。僕に着いて来たたまちゃんたちも興奮した様子で、上空を行ったり来たりしていた。そのうち羽ばたきながら手をラッパにし、音を真似だした。そして行列の上を誇らしげに飛行しながら、ラッパを吹き鳴らした。
僕と池田さんが、背伸びをして前方を見ていると、前の大人たちが譲ってくれて、いつの間にか最前列で演奏を聴いていた。
演奏しているのは、おそらく高校生だろう。金色の管楽器が日差しに眩しく反射している。長袖のセーラー服のような衣装で、汗をかきながら懸命に演奏している。
たぶん本当はそんなに上手ではないのだろうけど、そのときの僕にはとても心地よく、飛び抜けて素晴らしい演奏に聞こえた。
商店街の空を見上げると、たまちゃんたちも、いつになく上機嫌な様子で演奏しながら飛び回っていた。でも実のところ、彼らの演奏は相当にデタラメなものだ。ぼくはそっと首から鬼のお面の紐を外した。そうすると目玉とともに音も消えるのだ。
池田さんは曲が終わる度に拍手を送っていた。僕は池田さんに聞いてみる。
「音楽は好き?」
「音楽が嫌いな人って、なかなかいないと思う」
僕らは小一時間演奏を聴いてから、文房具屋で買い物をし、猫の親子のいる橋に向かった。
向かう途中、たまちゃんたちはまだ手をラッパにして、さっき聴いた音楽を奏でていた。彼らの演奏はデタラメだと言ったが、よく聞くと音程は正しい。しかしリズムがめちゃくちゃなのだ。彼らはどうやら時間概念というものが僕らと異なるらしい。頭がおかしくなりそうなので、やはりお面の紐を首から外しておいた。
池田さん曰く、猫の親子は橋の下のスペースの端っこの隙間にいるらしい。ちょうどよい窪みになっており、その前は雑草が生えてるから風も防げる。以前、三毛猫もいた場所だ。
腰を屈めてその場所をのぞくと、灰色と黒の縞猫と子猫が3匹いた。子猫のうち二匹は親と同じような模様で一匹は黒猫だ。僕らを見ると親猫は警戒して尻尾を上げ威嚇し、鳴いた。あまり人に慣れた猫ではないようだ。
池田さんは手慣れたもので、親猫の前に缶詰を置き、もう1つの缶詰のイワシをスプーンでほぐして子猫の前に置いた。僕はそれを少し離れた位置から見ていた。
子猫はじゃれ合いながらでて来て、缶詰をベロベロ舐めた。親猫もつま先歩きで尻込みしながら出てきて、イワシを食べた。その様子を僕らは並んで観察した。
「とりあえず、今日のところは近づかない方がいいわ。まだ警戒している。特に子連れのメスは凶暴だから」
食べ終えると猫たちは橋の影に戻っていった。池田さんが缶を回収して、その日は解散した。
それから毎日池田さんは猫の親子に餌やりをした。僕もたいていは付き添った。猫たちは徐々に僕らに慣れてきて、そのうち池田さんが呼ぶと出てくるようになった。子猫たちは大変健康だ。餌を持っていくと、親猫の尻尾をはたいたり、背中に飛びついたりしながらやってきて、ぺろりと缶詰を平らげてしまう。
僕らはたまに抱きかかえてウロウロしたり、松ぼっくりを投げたり、猫じゃらしで遊んでやったりした。池田さんが動物が好きというのはどうやら本当らしい。