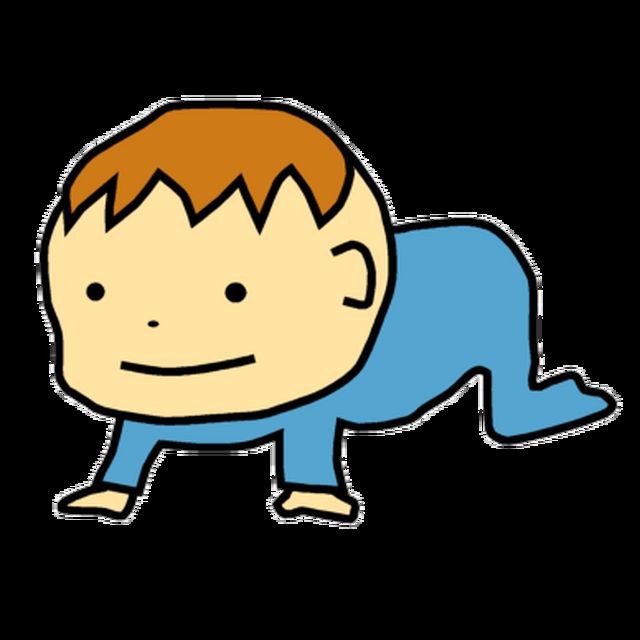第7話
文字数 2,981文字
ある放課後の学校の帰り道、池田さんが僕に訊いた。
「なぜわたしを尾行していたの」
僕は正直に答えた。またこの機会に、それにまつわる色々なことを全部話した。
おじいちゃんにもらった鬼のお面のこと。
この世界は実は目玉だらけだということ。
池田さんの体の目玉が人より薄いこと。
松ぼっくりが変な生き物に変わったこと。
「へえ、わたしだけがスカスカなの。なぜかしらね」
彼女は鬼のお面を貸してほしいと言った。
お面を渡し、彼女も顔にお面をつけてみたのだが「何も変わらない」とのことだった。
池田さんが首を振って言う。
「やっぱり鬼の子孫じゃないと、だめなのかもね」
ところで先日「三郎」が生まれた。三郎は目が3つ三角についている。そのうち「四郎」も生まれると期待していたのだが、三郎が生まれてからは、裏門の松ぼっくりは見当たらなくなってしまった。残念ながらとりあえずは三郎で最後らしいのだ。
三郎も基本的には生態はたまちゃんたちと同じで、餌を食べ、僕に着いて来るだけだ。しかし彼らはあの日以来たまに手をラッパにして演奏するようになった。もちろん三郎の演奏もめちゃくちゃだ。彼らの演奏は成長しない。
それと三郎が生まれて3匹になった彼らは、いろいろな植物を生み出せるようになった。
植物を生み出す工程は、以下のように進む。
まずたまちゃんが一つ目玉をつくる。両手に何か力を込めると目玉が生まれて来るのだ。たぶんこれは植物のコアになる部分なのだと思う。そして同じようにして三郎がその目玉を増やす。それから次郎が同じく手をかざして、色形を整えると出来上がる。
僕が鼻血を出した際にはごぼうを出してくれた。なぜごぼうなのかは分からないが、僕はそれを鼻に詰めた。
また、彼らは僕にマリーゴールドの花をくれたことがある。その日はよく晴れていた。マリーゴールドをうけとり、僕は嬉しくて、いろいろな方向から眺めていた。しかし何を思ったか、急に彼らはそのマリーゴールドを僕の口の中に押し込んだ。僕はあわてて吐き出した。それ以降、マリーゴールドをもらったことはない。他にもときどき、赤い藻や紫の実などをもらった。
さて、7月上旬のある日、僕らがいつものように猫の親子へ餌やりに行ったところ、とても悲劇的な出来事があった。
その日は晴れていたが、風の強い日だった。たまちゃんたちは上空で風に煽られ、飛行の下手な甲虫のように、フラフラと飛んでいた。
橋の下で池田さんがいつものように猫たちを呼ぶと3匹は普通に出てきたが、一匹の子猫だけ遅れて出てきた。三匹のうちの黒猫の子猫だ。どうやら後ろ脚を怪我してしまったらしい。両足をだらりと引きずり、前足だけで懸命に歩いてくる。事故にでもあったのだろうか、後ろ足は完全に砕けているように見えた。もしくは犬に噛まれたのかもしれない。ドキュメンタリーでライオン同士の縄張り争いによって、このように後ろ足を砕かれた雌ライオンのを見たことがある。殺さずに時間をかけて弄ばれるのだ。
池田さんはしゃがんで背筋を伸ばし、その子猫の歩く姿を大きな瞳でじっと見ていた。子猫が池田さんの前までたどり着くと、その子猫を抱えあげて言った。
「こりゃあ、だめかもなあ」
抱きあげられた子猫の腰から下は、まるっきり力が抜けていた。
それから、親猫と子猫たちにイワシの缶詰を与えた。怪我した子猫は他の子猫たちに押されて缶までたどり着けなかった。池田さんは言う。
「血も涙もないない奴らだな」
そう言って缶詰にむらがる猫たちを腕ではらって、怪我をした子猫に缶詰を食べさせた。子猫は食欲はあるようだった。
しかし数日後、事態はさらに悪化する。その日も、猫たちを呼ぶと怪我をした猫は遅れてやってきた。もう歩くのもやっとという感じでノロノロとやってきた。たぶんカラスか何かにいじめられたのだろう。顔が血だらけだ。目の下の被毛が剥がれて黒く固まり、その上にピンクの皮膚が見えている。
「あらら」池田さんが言った。そして彼女は怪我した猫に餌を与えたが、子猫はもう食べようとしなかった。少し考えてから池田さんが言う。
「殺してあげましょ。わたしたちにはそれしかできないし、たぶん生きてても何もいいことないわ。というかそのうち放っておいても死ぬわ。これから苦しんで死ぬよりは、殺してあげたほうがいいと思う」
僕は答える。
「うん。仕方がないよね。僕もそのほうがいいと思う。君がやってくるの?」
彼女は子猫を見つめながら、自分がすると答えた。池田さんの横顔にはなんとなく嫌悪感が滲んでいるように見えた。さすがの池田さんも、スカスカでない生き物を殺すのには抵抗があるのだろうか。
彼女は立ち上がると「道具を取ってくる」と言って、一度家に帰っていった。
僕はその子猫を抱きあげた。もう力が入らないのか、ハンガーに吊られたジーパンのように、鳴き声もあげずに、僕の腕に身を任せていた。なんとなく辺りを見渡すと、周辺にはペットボトルや割り箸が落ちていた。池田さんが帰ってくるまで、それらが妙に気になって、頭から離れなかった。
数十分後、彼女はリュックサックを背負って戻ってきた。彼女は亀山池の森に行くと言って、森へ歩き出した。僕は大股で歩く彼女の背中を、猫を抱えながら追った。木漏れ日の中、森の少し湿った腐葉土の上を足音もなく進んでいく。猫は大人しく僕の腕に抱かれている。
「もう少しだよ」
僕のTシャツは子猫の血で、ところどころ赤茶色のシミになっていた。
僕はふとつぶやいた。
「この猫は普段どこで何をしていたんだろう」
彼女がそれに答える。
「あの橋の下で兄弟とじゃれ合っていただけでしょうね」
そのうちに池の畔にたどり着いた。前に池田さんが猫を殺した側とは反対に進んでいき、ちょうどいい木陰の窪みを見つけると彼女は
「猫を貸して」
と手を差し出す。僕は子猫を渡して彼女の様子を見守る。たまちゃんたちも興味深げに頭上で静止している。
彼女は
「どうしようかな」
とつぶやき、少し思案した。そしておもむろに包丁を振り上げると子猫の首に何度か振り下ろした。軽いめった刺しだ。何度か刺して、それから首を引きちぎった。子猫にはもう抵抗する力は残っていなかったようだ。このように子猫は死んだ。
次に彼女はリュックサックからスコップを取り出し、穴を掘ってその穴に子猫を押し込んだ。そして立ち上がると、腕で額の汗を拭い、血に染まった子猫を、何か汚いものでも見るかのように見下ろした。そして同じように自分の手のひらを見つめた。
僕はそこにしゃがみこんで一部始終をただ口を閉ざし(開いていたかもしれない)、見ていた。そのとき、ふと見上げるとたまちゃんたちが三匹で何かこねくり回している。そしてその何かを穴に投入れた。それはガマの穂だった。次に彼らは松ぼっくりを作って投入れた。これらは池田さんにも見えるようで、たいそう驚いている。たまちゃんたちの仕業だというと、感心したようにうなずき、
「ガマの穂には止血作用があるそうよ。昔おばあちゃんが傷に塗ってくれた。彼らなりに心配してくれてるのかもね。松ぼっくりは何だろうね。今度また見に来ましょう。松の木が生えてるかも」
そして穴の上に掘った土をもどし、深くため息をついて、足で土を踏み固めた。そこに僕は落ち葉をかけておいた。その場所は何事もなかったかのように、森の風景に馴染んだ。
「なぜわたしを尾行していたの」
僕は正直に答えた。またこの機会に、それにまつわる色々なことを全部話した。
おじいちゃんにもらった鬼のお面のこと。
この世界は実は目玉だらけだということ。
池田さんの体の目玉が人より薄いこと。
松ぼっくりが変な生き物に変わったこと。
「へえ、わたしだけがスカスカなの。なぜかしらね」
彼女は鬼のお面を貸してほしいと言った。
お面を渡し、彼女も顔にお面をつけてみたのだが「何も変わらない」とのことだった。
池田さんが首を振って言う。
「やっぱり鬼の子孫じゃないと、だめなのかもね」
ところで先日「三郎」が生まれた。三郎は目が3つ三角についている。そのうち「四郎」も生まれると期待していたのだが、三郎が生まれてからは、裏門の松ぼっくりは見当たらなくなってしまった。残念ながらとりあえずは三郎で最後らしいのだ。
三郎も基本的には生態はたまちゃんたちと同じで、餌を食べ、僕に着いて来るだけだ。しかし彼らはあの日以来たまに手をラッパにして演奏するようになった。もちろん三郎の演奏もめちゃくちゃだ。彼らの演奏は成長しない。
それと三郎が生まれて3匹になった彼らは、いろいろな植物を生み出せるようになった。
植物を生み出す工程は、以下のように進む。
まずたまちゃんが一つ目玉をつくる。両手に何か力を込めると目玉が生まれて来るのだ。たぶんこれは植物のコアになる部分なのだと思う。そして同じようにして三郎がその目玉を増やす。それから次郎が同じく手をかざして、色形を整えると出来上がる。
僕が鼻血を出した際にはごぼうを出してくれた。なぜごぼうなのかは分からないが、僕はそれを鼻に詰めた。
また、彼らは僕にマリーゴールドの花をくれたことがある。その日はよく晴れていた。マリーゴールドをうけとり、僕は嬉しくて、いろいろな方向から眺めていた。しかし何を思ったか、急に彼らはそのマリーゴールドを僕の口の中に押し込んだ。僕はあわてて吐き出した。それ以降、マリーゴールドをもらったことはない。他にもときどき、赤い藻や紫の実などをもらった。
さて、7月上旬のある日、僕らがいつものように猫の親子へ餌やりに行ったところ、とても悲劇的な出来事があった。
その日は晴れていたが、風の強い日だった。たまちゃんたちは上空で風に煽られ、飛行の下手な甲虫のように、フラフラと飛んでいた。
橋の下で池田さんがいつものように猫たちを呼ぶと3匹は普通に出てきたが、一匹の子猫だけ遅れて出てきた。三匹のうちの黒猫の子猫だ。どうやら後ろ脚を怪我してしまったらしい。両足をだらりと引きずり、前足だけで懸命に歩いてくる。事故にでもあったのだろうか、後ろ足は完全に砕けているように見えた。もしくは犬に噛まれたのかもしれない。ドキュメンタリーでライオン同士の縄張り争いによって、このように後ろ足を砕かれた雌ライオンのを見たことがある。殺さずに時間をかけて弄ばれるのだ。
池田さんはしゃがんで背筋を伸ばし、その子猫の歩く姿を大きな瞳でじっと見ていた。子猫が池田さんの前までたどり着くと、その子猫を抱えあげて言った。
「こりゃあ、だめかもなあ」
抱きあげられた子猫の腰から下は、まるっきり力が抜けていた。
それから、親猫と子猫たちにイワシの缶詰を与えた。怪我した子猫は他の子猫たちに押されて缶までたどり着けなかった。池田さんは言う。
「血も涙もないない奴らだな」
そう言って缶詰にむらがる猫たちを腕ではらって、怪我をした子猫に缶詰を食べさせた。子猫は食欲はあるようだった。
しかし数日後、事態はさらに悪化する。その日も、猫たちを呼ぶと怪我をした猫は遅れてやってきた。もう歩くのもやっとという感じでノロノロとやってきた。たぶんカラスか何かにいじめられたのだろう。顔が血だらけだ。目の下の被毛が剥がれて黒く固まり、その上にピンクの皮膚が見えている。
「あらら」池田さんが言った。そして彼女は怪我した猫に餌を与えたが、子猫はもう食べようとしなかった。少し考えてから池田さんが言う。
「殺してあげましょ。わたしたちにはそれしかできないし、たぶん生きてても何もいいことないわ。というかそのうち放っておいても死ぬわ。これから苦しんで死ぬよりは、殺してあげたほうがいいと思う」
僕は答える。
「うん。仕方がないよね。僕もそのほうがいいと思う。君がやってくるの?」
彼女は子猫を見つめながら、自分がすると答えた。池田さんの横顔にはなんとなく嫌悪感が滲んでいるように見えた。さすがの池田さんも、スカスカでない生き物を殺すのには抵抗があるのだろうか。
彼女は立ち上がると「道具を取ってくる」と言って、一度家に帰っていった。
僕はその子猫を抱きあげた。もう力が入らないのか、ハンガーに吊られたジーパンのように、鳴き声もあげずに、僕の腕に身を任せていた。なんとなく辺りを見渡すと、周辺にはペットボトルや割り箸が落ちていた。池田さんが帰ってくるまで、それらが妙に気になって、頭から離れなかった。
数十分後、彼女はリュックサックを背負って戻ってきた。彼女は亀山池の森に行くと言って、森へ歩き出した。僕は大股で歩く彼女の背中を、猫を抱えながら追った。木漏れ日の中、森の少し湿った腐葉土の上を足音もなく進んでいく。猫は大人しく僕の腕に抱かれている。
「もう少しだよ」
僕のTシャツは子猫の血で、ところどころ赤茶色のシミになっていた。
僕はふとつぶやいた。
「この猫は普段どこで何をしていたんだろう」
彼女がそれに答える。
「あの橋の下で兄弟とじゃれ合っていただけでしょうね」
そのうちに池の畔にたどり着いた。前に池田さんが猫を殺した側とは反対に進んでいき、ちょうどいい木陰の窪みを見つけると彼女は
「猫を貸して」
と手を差し出す。僕は子猫を渡して彼女の様子を見守る。たまちゃんたちも興味深げに頭上で静止している。
彼女は
「どうしようかな」
とつぶやき、少し思案した。そしておもむろに包丁を振り上げると子猫の首に何度か振り下ろした。軽いめった刺しだ。何度か刺して、それから首を引きちぎった。子猫にはもう抵抗する力は残っていなかったようだ。このように子猫は死んだ。
次に彼女はリュックサックからスコップを取り出し、穴を掘ってその穴に子猫を押し込んだ。そして立ち上がると、腕で額の汗を拭い、血に染まった子猫を、何か汚いものでも見るかのように見下ろした。そして同じように自分の手のひらを見つめた。
僕はそこにしゃがみこんで一部始終をただ口を閉ざし(開いていたかもしれない)、見ていた。そのとき、ふと見上げるとたまちゃんたちが三匹で何かこねくり回している。そしてその何かを穴に投入れた。それはガマの穂だった。次に彼らは松ぼっくりを作って投入れた。これらは池田さんにも見えるようで、たいそう驚いている。たまちゃんたちの仕業だというと、感心したようにうなずき、
「ガマの穂には止血作用があるそうよ。昔おばあちゃんが傷に塗ってくれた。彼らなりに心配してくれてるのかもね。松ぼっくりは何だろうね。今度また見に来ましょう。松の木が生えてるかも」
そして穴の上に掘った土をもどし、深くため息をついて、足で土を踏み固めた。そこに僕は落ち葉をかけておいた。その場所は何事もなかったかのように、森の風景に馴染んだ。