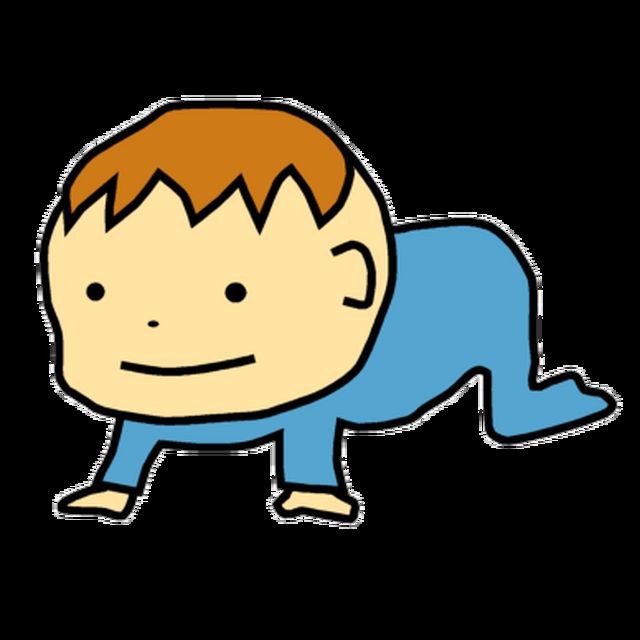第2話
文字数 2,953文字
ところで、僕は小学生(5年生)なので、もちろん小学校に通っている。僕の通う小学校は市立大松台小学校という。赤い屋根がトレードマークだ。この小学校には一つ、建設に関する胸に切ないエピソードがある。
それというのは、この大松台小学校が今建っている場所には、もともと山があって、その深く、一番奥に大きな大きな松の木が生えていたのだという。しかし小学校を建てるときに、その松の木もろとも山を切り拓いた。それでこの学校は、大松台小学校という名前を与えられたのだ。
これはとても悲しいエピソードですよね。もし僕が校長先生だったなら、学校の隅っこにでも、その松の木の子孫かなにかを植えてやりたいところだけど、残念ながらそういう物はどこにもない。松の木は跡形もなく消滅させられたのだ。ひどい話である。
僕はその高台にそびえる校舎を仰ぎ見て、消え去った大きな松の木について思いを馳せる。樹齢200年だか300年だか分からないけれど、この土地がまだ山だらけで、たぬきやブタがそこら辺を走り回っていたのも見ていたかもしれない。その頃はこの辺りの人々は、まだ畑を耕していたと思う。その間のあぜ道で天秤棒を担いだ野菜売りが、声を枯らしながらウロウロしていたのも、きっと見ていただろう。
この学校の屋根がなぜ赤いのか、先生に聞いたことがある。先生の答えは「将来老人ホームとして使われるから」というものだった。老人ホームの屋根は赤いものなのだろうか。
とにかくこの学校にはところどころに、将来老人ホームとして使われることを意識した設備がある。例えば校舎の所々にサンルームという区画がある。ここは天窓から明るい光が注がれる憩いの場だ。僕もいつかはそこで老眼鏡を掛けて新聞のパズルをやったりするのだろう。校庭では白いランニングシャツを着て集まり、毎朝ラジオ体操をしたり、ベレー帽を被ってゲートボールに興じたりするだろう。僕はこの小学校で学び、いつかこの小学校で死んでいくのだ。
話は変わるけれど、僕はある日、学校でとっても不思議な松ぼっくりを見つけた。
僕はいつも学校の裏門を通って登下校をする。その松ぼっくりは下校のとき学校の裏門に落ちていた。なにが不思議かと言うとまず、その周辺には松の木は一本も生えていないのだ。しかも学校は高台にあるため、どこかから転がってくることもない。初めに見たときは、少しは訝しんだが、烏が持ってきて、空から落としたのかもしれないし、特に気に止めなかった。
でも次の日に、松ぼっくりが2つになっていて、さすがに僕はおかしいと思った。ただ拾っていろいろな角度から見てみたが、特にこれといった特徴はなかった。
とりあえずその怪しい松ぼっくり2つは、持ち帰って、部屋に置いておいた。部屋の腰窓の縁に2つ並べて飾った。
一応、鬼のお面からも覗いてみたが、何の変哲もない普通の松ぼっくりだった。
驚いたことに翌日も一つ、松ぼっくりが同じ門の裏に転がっていた。僕はなにかの「予兆」を感じ、もちろんそれも持ち帰った。実際、次の日もその次の日も、毎日松ぼっくりは同じ場所に転がっていた。だんだんと窓枠がいっぱいになってしまったので、お母さんに竹籠をもらって同じ窓枠に置き、そこに松ぼっくりを集めるようになった。そして竹籠もいっぱいになってしまったある日の朝、僕はさらに不思議なものと出会う。
その朝起きて、竹籠を見ると松ぼっくりがなくなっているのだ。綺麗さっぱり一つ残らず消えていた。僕はなんとなく鬼のお面をしてもう一度竹籠を覗いてみた。するとなんとそこには手足の生えた目玉がいた。それは箱の真ん中に突っ立って、朝日の影から僕を見上げていた。大きな瞳で。
僕は恐る恐る、その目玉をすくい上げるように両手に乗せた。目玉はなんの動揺も見せず、僕の手に乗せられた。ぼくはその目玉をよく観察した。
体の構造は、胴体がなく、目玉から直接4本の手足が突き出ている。目玉自体の多きさはだいたいゴルフボールほどだ。目玉の方も瞬きもせず(瞬きする瞼もないが)じっと僕を観察しているようだった。それから目玉は上下左右に目玉を振って部屋を観察した。そして驚いたことに手足を引っ込め、見事なオオムラサキのような模様の羽を出し、飛び上がってホバリングした。 小さな目が次々に生まれ、それらが羽を形作った。そして僕の眼の前で静止すると、振り返って部屋を飛び回った。状況を確認するように、いろいろな場所を見て回っているようだ。ベッドの感触を確かめたり、机の上の宿題を眺めたり、壁に貼ってある僕の七五三の写真や、図工の授業で描いた絵を観察したりしている。一通り飛び回ると今度は羽を引っ込め、手足を出し、窓枠に腰掛けた。
そういえば僕はいつかテレビのアマゾンのドキュメンタリー番組で、ハチドリのホバリングは非常に疲れると紹介されているのを見たことがあった。窓枠に座っている目玉も、どことなく気だるそうに見える。だから目玉にご飯を与えようと考えた。目玉が何を食べるのかは全く分からなかったので、とりあえずペットの餌を与えることにした。目玉は小さいので、大さじ一杯くらいの極めて少量のドッグフードを、家の犬のステンレスの器に盛りつけた。そして目玉のいる窓枠に乗せてみた。しかし目玉はドッグフードを見下ろし、首を捻っているばかりで食べようとしてくれない。それで僕は
「どうぞ」
と言って器を目玉の方へ少し押し出してやった。すると目玉は僕の顔を確認するように一瞥し、ドッグフードを食べた。 なんと今度は口を発生させた。彼はまたもや小さな目玉をたくさん出してヒトの口を象った。その口へ小さな手を使い、ひと粒ずつ食べた。
食べ終わると、また僕を見上げた。やはりお腹が空いていたのだろう。器の裏を覗き込んだりしている。もっとほしいのだろうと思い、もう一杯与えた。それを食べ終わると、もう十分とばかりに座りこんだ。その顔(正確には目玉)は紙を切るハサミの目玉のようにどこか満足げだ。体の大きさと同じくらいの量のドッグフードを食べたのだが、一体この目玉のどこに消化器官があるのだろうか。
ちなみにこのドッグフードはヒューマングレードなので目玉に与えても問題ないだろう。彼の手や口はヒトのそれだし。
あと、この目玉には耳がないのに声が聞こえるようだ。
僕はいつまでもこの生物を「目玉」とか「彼」と呼ぶのもなんなので、「たまちゃん」と名付けた。そしてペットにし、かわいがった。暇さえあれば撫でてやり、夜は一緒の布団で寝た。ちなみに「たまちゃん」は瞼がないので目を閉じられず、寝ているのかどうか分からない。でも布団に入ると、横になって、動かないのでたぶん普通の生物と同じように夜は寝るのだ。
たまちゃんはどこにでもついてきた。トイレにも学校にもスイミングスクールにもついてきた。逆に言えばたまちゃんはついてくるだけだ。飼っていても何かのメリットがあるわけではない(その代わりにうんこもしない)。もちろん鬼のお面をしなければ見えないので、僕以外の誰にもたまちゃんは見えない。でも物質の無数の目玉には見えてる。というかむしろ注目の的といってもいいほどで、皆たまちゃんを優先的に目で追う。これは僕にとっても少し誇らしい体験なのだった。
それというのは、この大松台小学校が今建っている場所には、もともと山があって、その深く、一番奥に大きな大きな松の木が生えていたのだという。しかし小学校を建てるときに、その松の木もろとも山を切り拓いた。それでこの学校は、大松台小学校という名前を与えられたのだ。
これはとても悲しいエピソードですよね。もし僕が校長先生だったなら、学校の隅っこにでも、その松の木の子孫かなにかを植えてやりたいところだけど、残念ながらそういう物はどこにもない。松の木は跡形もなく消滅させられたのだ。ひどい話である。
僕はその高台にそびえる校舎を仰ぎ見て、消え去った大きな松の木について思いを馳せる。樹齢200年だか300年だか分からないけれど、この土地がまだ山だらけで、たぬきやブタがそこら辺を走り回っていたのも見ていたかもしれない。その頃はこの辺りの人々は、まだ畑を耕していたと思う。その間のあぜ道で天秤棒を担いだ野菜売りが、声を枯らしながらウロウロしていたのも、きっと見ていただろう。
この学校の屋根がなぜ赤いのか、先生に聞いたことがある。先生の答えは「将来老人ホームとして使われるから」というものだった。老人ホームの屋根は赤いものなのだろうか。
とにかくこの学校にはところどころに、将来老人ホームとして使われることを意識した設備がある。例えば校舎の所々にサンルームという区画がある。ここは天窓から明るい光が注がれる憩いの場だ。僕もいつかはそこで老眼鏡を掛けて新聞のパズルをやったりするのだろう。校庭では白いランニングシャツを着て集まり、毎朝ラジオ体操をしたり、ベレー帽を被ってゲートボールに興じたりするだろう。僕はこの小学校で学び、いつかこの小学校で死んでいくのだ。
話は変わるけれど、僕はある日、学校でとっても不思議な松ぼっくりを見つけた。
僕はいつも学校の裏門を通って登下校をする。その松ぼっくりは下校のとき学校の裏門に落ちていた。なにが不思議かと言うとまず、その周辺には松の木は一本も生えていないのだ。しかも学校は高台にあるため、どこかから転がってくることもない。初めに見たときは、少しは訝しんだが、烏が持ってきて、空から落としたのかもしれないし、特に気に止めなかった。
でも次の日に、松ぼっくりが2つになっていて、さすがに僕はおかしいと思った。ただ拾っていろいろな角度から見てみたが、特にこれといった特徴はなかった。
とりあえずその怪しい松ぼっくり2つは、持ち帰って、部屋に置いておいた。部屋の腰窓の縁に2つ並べて飾った。
一応、鬼のお面からも覗いてみたが、何の変哲もない普通の松ぼっくりだった。
驚いたことに翌日も一つ、松ぼっくりが同じ門の裏に転がっていた。僕はなにかの「予兆」を感じ、もちろんそれも持ち帰った。実際、次の日もその次の日も、毎日松ぼっくりは同じ場所に転がっていた。だんだんと窓枠がいっぱいになってしまったので、お母さんに竹籠をもらって同じ窓枠に置き、そこに松ぼっくりを集めるようになった。そして竹籠もいっぱいになってしまったある日の朝、僕はさらに不思議なものと出会う。
その朝起きて、竹籠を見ると松ぼっくりがなくなっているのだ。綺麗さっぱり一つ残らず消えていた。僕はなんとなく鬼のお面をしてもう一度竹籠を覗いてみた。するとなんとそこには手足の生えた目玉がいた。それは箱の真ん中に突っ立って、朝日の影から僕を見上げていた。大きな瞳で。
僕は恐る恐る、その目玉をすくい上げるように両手に乗せた。目玉はなんの動揺も見せず、僕の手に乗せられた。ぼくはその目玉をよく観察した。
体の構造は、胴体がなく、目玉から直接4本の手足が突き出ている。目玉自体の多きさはだいたいゴルフボールほどだ。目玉の方も瞬きもせず(瞬きする瞼もないが)じっと僕を観察しているようだった。それから目玉は上下左右に目玉を振って部屋を観察した。そして驚いたことに手足を引っ込め、見事なオオムラサキのような模様の羽を出し、飛び上がってホバリングした。 小さな目が次々に生まれ、それらが羽を形作った。そして僕の眼の前で静止すると、振り返って部屋を飛び回った。状況を確認するように、いろいろな場所を見て回っているようだ。ベッドの感触を確かめたり、机の上の宿題を眺めたり、壁に貼ってある僕の七五三の写真や、図工の授業で描いた絵を観察したりしている。一通り飛び回ると今度は羽を引っ込め、手足を出し、窓枠に腰掛けた。
そういえば僕はいつかテレビのアマゾンのドキュメンタリー番組で、ハチドリのホバリングは非常に疲れると紹介されているのを見たことがあった。窓枠に座っている目玉も、どことなく気だるそうに見える。だから目玉にご飯を与えようと考えた。目玉が何を食べるのかは全く分からなかったので、とりあえずペットの餌を与えることにした。目玉は小さいので、大さじ一杯くらいの極めて少量のドッグフードを、家の犬のステンレスの器に盛りつけた。そして目玉のいる窓枠に乗せてみた。しかし目玉はドッグフードを見下ろし、首を捻っているばかりで食べようとしてくれない。それで僕は
「どうぞ」
と言って器を目玉の方へ少し押し出してやった。すると目玉は僕の顔を確認するように一瞥し、ドッグフードを食べた。 なんと今度は口を発生させた。彼はまたもや小さな目玉をたくさん出してヒトの口を象った。その口へ小さな手を使い、ひと粒ずつ食べた。
食べ終わると、また僕を見上げた。やはりお腹が空いていたのだろう。器の裏を覗き込んだりしている。もっとほしいのだろうと思い、もう一杯与えた。それを食べ終わると、もう十分とばかりに座りこんだ。その顔(正確には目玉)は紙を切るハサミの目玉のようにどこか満足げだ。体の大きさと同じくらいの量のドッグフードを食べたのだが、一体この目玉のどこに消化器官があるのだろうか。
ちなみにこのドッグフードはヒューマングレードなので目玉に与えても問題ないだろう。彼の手や口はヒトのそれだし。
あと、この目玉には耳がないのに声が聞こえるようだ。
僕はいつまでもこの生物を「目玉」とか「彼」と呼ぶのもなんなので、「たまちゃん」と名付けた。そしてペットにし、かわいがった。暇さえあれば撫でてやり、夜は一緒の布団で寝た。ちなみに「たまちゃん」は瞼がないので目を閉じられず、寝ているのかどうか分からない。でも布団に入ると、横になって、動かないのでたぶん普通の生物と同じように夜は寝るのだ。
たまちゃんはどこにでもついてきた。トイレにも学校にもスイミングスクールにもついてきた。逆に言えばたまちゃんはついてくるだけだ。飼っていても何かのメリットがあるわけではない(その代わりにうんこもしない)。もちろん鬼のお面をしなければ見えないので、僕以外の誰にもたまちゃんは見えない。でも物質の無数の目玉には見えてる。というかむしろ注目の的といってもいいほどで、皆たまちゃんを優先的に目で追う。これは僕にとっても少し誇らしい体験なのだった。